 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(八) 象の前足
かくして、へたれ探偵であることをさらけ出してしまったわたしは、遺伝子工学の権威を詐称する男とともに、奥にある社長室の扉をノックしたのであった。
「いやあ、先生、お待ちしておりました」
社長室で待っていたのは、とても四十には見えない若々しいいでたちの人物であった。服装もさすがにヒッピーではないけれど、ポロシャツにジーンズと、実に飾らない感じである。
「わたしも若いころは、先生のご著書で勉強させていただいたものです」
「ああ、あれですか」
種山は、苦い顔になった。
「あれは、若いころのわたしの過ちでした」
「いえいえ、ご謙遜を。遺伝子工学の世界では先生の業績こそノーベル賞に値するものだったと皆が認識しておりますよ。すべての業績を放棄して先生が突然この業界を去られたのは、ほんとうに大きな痛手でした」
って、なにこれ? この会話?
「まさか先生」
あきれ果ててわたしは問うていた。
「うん。うちにいた権作ね、ああいう研究のきっかけになる仕事をね、わたしは若いころにやってたんだよ」
種山は頭を掻いた。
「すぐに自分のやっていることが孕んでいる危険性に気が付いて離れたんだけどね。ほら言ったでしょ、権作の権は権力の権だって。あの名前は、権力が、ああいう悲劇の生物を作り出したっていう意味なんですよ。権作を貸してくれた同僚は、その頃のぼくの教え子だった人なんだ」
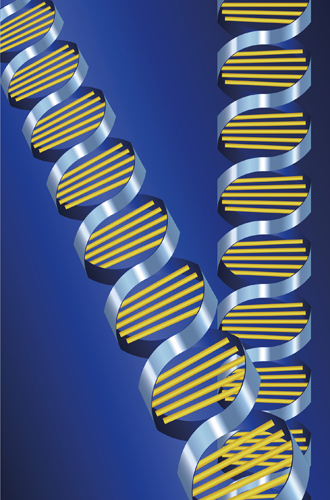
そういうことか。ようやく納得がいった。あの部屋のネズミたちのことを紹介する時、種山が妙に沈んだ雰囲気だった理由がよくわかったのだ。それにしても、さらなる疑問がわたしを待ち受けていた。でも、なんでヒッピーが遺伝子工学を?
「春山さんははあれですか、モンサントにお勤めでしたか?」
「ええ」
にこやかに応える春山幸雄の態度には、種山への尊敬の念が溢れていた。
「まあわたしは、途中から社外研究員になりましたけど」
「やはりそうでしたか」
種山がうんうんとうなずいた。
「つまり、プロスペクターですね」
「ええ、そうです」
ちょっと待ったあっ。わたしは種山の肩をつんつん突いた。
「あのこちらは」
わたしの存在が理解できないようであった。おかしいですね、秘書の方ではないのですかと、春山は問うているのであった。種山が遺伝子工学をやっていたことも知らず、プロスペクターがなんなのかも知らない秘書なんて、あるわけがない。そりゃそうだ。
「ああ、こちらは」
秘技、快刀乱麻!
「一条さやかと申します」
わたしは、すかさずねじ込んだ。
「女子大学の二年生で、種山先生の」
とそこまでいって自分で困ってしまった。わたしはいったいなんなのだ。種山龍宏のなんなのだ? いったいわたしと種山はどういう種類の因縁でつながっているのだろう。
「そうですね、同胞です、この人は」
「同胞、ですか?」
春山と、わたしが同時に聞き返していた。
「そうです。驚異を愛する同胞なんですよ」
なるほど。まあ座布団一枚というところである。いや、一枚は多いか、半分くらいかな。
「で、プロスペクターっていうのはですね」
やばい! 切り出し方で、すでにわたしには長講釈の予感がした。
「よろしければ、先生、わたしが説明いたしましょうか」
でも、春山がへりくだった口調で介入してくれた。お願いしますよ、春山さん、できるだけ簡潔にまとめてやってください。
「じゃあ、お願いします」
「プロスペクターっていうのは、遺伝子のハンターなんです」
遺伝子、ハンター? つながらなかった。だって遺伝子なんて眼に見えないのにどうやって、狩るんだろう。

「かなり以前から、世界中に企業のバックアップを受けた科学者たちが派遣されているんですよ。彼らは主として発展途上国へ行く。時には、少数民族の村や、未開とされる種族の村を訪れる。そこで、微生物、植物、動物などの遺伝子を採取し」
「人間のもですよね、春山君」
たしなめるように、種山が口をはさんだ。
「ごまかしちゃいけませんよ。大事なことなんですから」
「わかりました」
春山は素直に頭を下げた。
「そうなんです、人間の遺伝子も採取の対象になっているんです。たとえば、パプアニューギニアのハガハイ族というほとんど文明と接触のなかった部族がありました。そこに文明圏の病気に対する予防接種をするという口実で入り込んだ科学者たちは、彼らの遺伝子を極秘で採取しそれを本社に送ったのです。彼らには白血病などに対する免疫があることが明らかになり、ハガハイ族の遺伝子に対してその会社が特許を取ったのです」
「もちろんハガハイ族の人たちはそんなことは知らされていないんですけどね」
「そんな」
わたしにはにわかに信じがたい話だった。他人の遺伝子を勝手に奪ったうえ、それで特許を取っちゃうなんて、いったいどういう神経なんだか。
「ハガハイ族は、起こったことに無知だけど、文明国の場合は多少状況が変わってくる」
そうだよね、と種山は春山を見る。
「ええ、そうです。特許4438032号の話ですね」
「そうです、ムーア細胞のことです」
「なんですか、ムーア細胞って」
名前がついてるわけだから、なにやら新種の細胞みたいだけど。
「これは、ジョン・ムーアっていうアメリカ人男性の細胞なんです。彼は、脾臓癌を患って、カリフォルニア大学病院で手術を受けたんです。でも、その際摘出された彼の癌細胞を主治医が彼に無断で培養したんですよ。そして、特許を取得した。つまり〝発明者〟となったってことです。培養されたムーア細胞はその後、製薬会社に売却されて、数十億円にも上る価値をもつものとなったのです」
と春山が教えてくれた。
「癌細胞がですか?」
「そうなんです。そのことを知ったムーアは怒りました。だって自分には無断で自分の細胞が勝手に〝発明〟されたことになってたわけですからね。培養され、実験室で増やされて研究に使われ、しかも莫大な利益を生み出しているって知らされたわけですから」
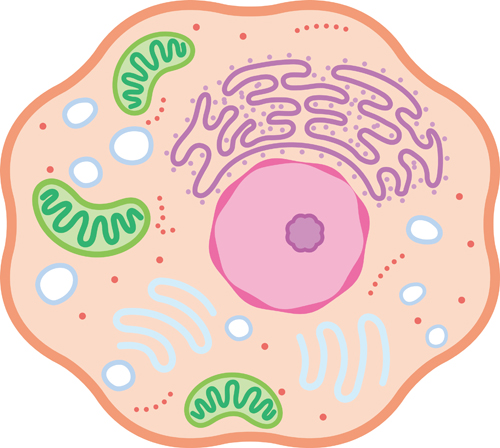
「まあ、癌細胞だから、いらないっていうか、いてほしくない細胞ではあったんでしょうけど」
「そりゃそうだけど、でも元はといえば自分の体の中にあったものでしょ」
「そうですね」
「でまあ、横領事件として裁判になったわけだけど」
「けど、ですか」
「そう、ジョン・ムーアは敗訴したんです」
「どうしてですか?」
「裁判所は、ムーアに、『あなたに、あなたの体の組織を所有する権利はない』と告げたのです。大学と企業とが、彼の身体部位を占有してそこから得たものを特許化することに問題はなかったとね」
「なんか、変ですね、それって」
うん、間違ってると思う。なんか変だ。
「でもそれがアメリカ的な発想というやつなんですよ。力と知識を持つものが、持たざる者を搾取することは悪ではないと彼らは考えているわけです」
どひゃーって感じだ。わたし、どえらいショックを受けました。結局、未開の地の人であれ、文明圏の人であれ、そういう人の身体より医学っていうか科学とかいった権威っていうか権力の方が優越しているっていう思考法なわけだよね、それって。
「そういうわけでしょ、春山君」
種山が話をもとに戻した。
「君がラーオ村に行ったのも、そういう目的だったわけでしょ」
「いやあ、ラーオ村か、参ったなあ」
春山は頭を掻いた。
「まさか、先生がそんな古い話を蒸し返されるとは思ってもみませんでした。なにかもっと利益につながるお話でもあるのかと思っていましたよ」
「残念ですか?」
「ええ、すこぶる残念です」
春山は堂々とそう答えた。
「その通りです。わたしは行く前からラーオ村のカレン族には特別な遺伝子があると踏んでいました。長い間近代文明と接触していなかったし、あの地域ではよくある風土病があの村には存在していないことを突き止めたからです」
「象皮病ですね」
「ええそうです」
な、な、なんと、お久しぶりです、西郷どん。しかし、ここでつながるとは。
「ご覧のとおり、わたしも二年ほどあの村に通ううちに、象皮病を患ってしまいました」
そう言って自虐的に笑った。
「ほら、覚えているかい?」
種山がわたしを振り返った。
「バボエ君、がに股だっただろ?」
「あっ」
思い出した。そうだったのだ。あの決して戻らぬナカマユキエを待ち続けている片言日本語の達人バボエ君は、奇妙な歩き方をしていた。ガニ股というか、カニ股というかそんな感じだった。
「そうでしたよね。そして、彼はそもそもあの村の出身者ではなかった」
「ああそういえば」
そんなことを言ってましたね。とわたしは思い出す。お母さんとしばらくお世話になってて、やがてカレンニー族だかなんかの父親が生還した。それで、十代の終わりに村を出た。確かそんな話だった。
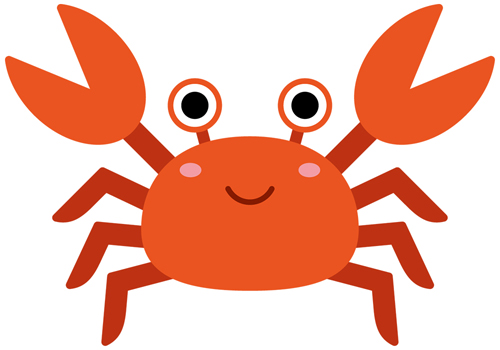
「そう、だから彼はバンクロフト糸状虫に抵抗できなかったわけです」
「そうか。被害者の和也氏も、あの村にいたから」
「うん」
なんとなく生返事で答える種山。
「でも、どうでした。あの村の人たちは誰もその病気にかかっていなかった。そうでしたよね」
そりゃわたしは女子だから、それほど彼らの股間に注意を向けるというようなことはなかったわけだけど、確かにわたしの記憶の映像のなかにがに股、あるいはカニ股で歩く村人の姿はなかった。
「つまり、免疫があったということですか」
「そうです、そういうことになるんです。ほら、学校で習ったことはないですか。マラリアの多い地域では、人々の赤血球が三日月型になるっていう話」
いえ、聞いたこともございません。とわたしは首を横に振る。ぶんぶん振る。
「赤血球が三日月型になることで、マラリア原虫が増殖できなくなるんです。代わりに貧血になりやすいんですけどね」
「すごいですね。人間の適応力って」
「そうなんですよ。表面は同じように見えても人間ってのは見かけよりずっと多様だし柔軟なんですよ。生活環境に応じてちゃんと遺伝子を作り替えてしまえるわけですからね。でも、逆にその特異性は搾取の対象になってしまうんですけど」
「で、あなたは」
今度はわたしが問う番である。
「あの村の人たちの遺伝子を売ったんですね。予防接種をしてあげるといいながら、こっそり血を抜いていたんですね」
「まあ、ギブ・アンド・テイクだとぼくは思ってるけどね」
春山はうそぶいた。
「彼らとは楽しくやってたし、ぼくも彼らもお互いにいやな感情は一切もっていなかったからね」
つまるところ、ラーオ村で採取した遺伝子から得た利益が、今の生活を用意してくれたようなものなのだと、春山は認めた。種山はポーカーフェイスだったが、わたしの眼光はかなり炯々していたと思う。心なしか春山が引いている感じだったからだ。
「なんとも思わないんですか。他人の遺伝子を盗んで、それで儲けてこんなビルに事務所を構えてる自分を」
「別に。ぼくは人生の半分以上をアメリカで過ごしたからね。そこで身に着けた価値観では、少なくともぼくがやっていることは罪ではない。むしろ勝利とか成功とか賞賛される類のものなんだよ」
「まあ、それはいいでしょう」
種山がまあまあという感じで割って入ってきた。
「ところで、あなたは橘さんをご存じですよね」
「橘?」
怪訝な顔をする春山。
「橘でわからなければ、和也さんです。あるいはカズ」
「ああ、カズですか。カズなら知ってます。ラーオ村では、ずいぶんと長い時間を一緒に過ごしましたからね」
つながった。とわたしは感動した。でも、なにもかも無駄なんだとがっかりした。カズとハル君の事件的なつながりはまず考えられないからだ。わたしの名推理ははかなくも霧となって立ち消えてしまったのだったから。
「ではご存じでしょうか。そのカズさんが亡くなったのは」
「亡くなった?」
驚きの表情。おや、少しは人間的な感情も持ち合わせているのね、この人。
「どういうことです? 病気ですか、事故ですか?」
「いえ、殺人です。殺されたのですよ」
種山は先週の日曜日の事件の詳細を語った。山荘。象の足跡。象の首。そして密室。
春山は眉をひそめてそれを聞いた。そして、ぶるぶると身を震わせた。
「そんな」
と喉を詰まらせた。
「あのカズが、いったい誰に? そして犯人は、どうしてそんなことをしたんでしょう」
いまにも泣き出しそうだった。やはり二人の間に友情はあったのだな、とわたしは少し感動した。
「その件に関してはですね」
種山の声には、相変わらず抑揚がなかった。
「むしろ、あなたにお聞きしたいとわたしは思っているのですよ」
「わたしにですか」
「ええ、そうですあなたにお聞きしたいのです」
何を言い出すのやらこのおじさんときたら。春山にいったいどんな推理ができるというのだろう。今状況を知ったばかりのこの男に。
「ご存じのはずですよ。あなたは犯人のことも。そして犯行の理由についても」
(第21回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







