 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(三)象の目(下編)
「なんだか、へんてこなことを言い出したんです。自分は、どうしてもある人物を見返してやらなくちゃならないんだってね。それが誰なのかは教えられない。でも、そいつが作った会社より利益をあげて鼻を明かしてやらないと腹の虫が治まらないんだと、いつになく烈しい口調で言い募るわけですよ」
「その相手について、心当たりは?」
「さあ、兄の交友関係についてはほとんど関心を持ってませんでしたからね。なにしろ、事業的なメリットがまったくないものですから。いずれにせよ、そんなヒッピー上がりの知人が始めたような会社がうまくいくとは思えませんでしたから、相手にしないつもりだったんです」
「取り合わないつもりだった?」
「ええ、そのつもりでした。だって、世界中ふらふらほっつき歩いてきただけで、ビジネスの現場についてなんの経験も知識もない人間だったんですよ、兄の和也は。わたしの性格からして、そんな危ない橋は渡れないじゃないですか」
「でも、結局は承諾した」
それはなぜ? と問いかけたかったのはわたしも同じ。右に同じ。
「もう長くないって聞かされたからでした」
「えっ」
どういうこと?
「旅先で仲良くなった女性がエイズだったっていうんですよ。それで、日本に戻ってから調べてみたら陽性だったと」
「それは」

さすがに、これにはわたしも参った。
「だから、自分はもう長くはないのだと兄は言いました。でも、このままでは死んでも死にきれない。冥途の土産に、一度その誰かさんを見返してやらなければ、気が済まないのだ。どうか、一度だけチャンスを与えてほしいってすがられたんです」
「で、折れたと」
「ええ、三年だけという条件付きでした。うまくいかなければ、途中でも交代してもらうという約束で。もちろん不安はあったし、実際その不安は的中しました。なにしろ、ずぶの素人ですからね、経営に関しても、社会人としても。
でまあ、このところ、実際わたしから打診はしていたんです。もう十分だ、変わってくれってね。あんな無謀な経営を続けてたら、会社がダメになってしまいますからね。
でも、兄のほうでは、もうちょっとだから、あとちょっとでなんとかするからと逃げ続けていた最中だったんです、そんなさ中に」
「事件が起こった、と?」
「ええ。まさか、こんなことになるなんて」
と喉を詰まらせ、
「もしかしたら、犯人はそのライバルの元友人ということになるのでしょうか?」
と種山とわたしの顔を交互に見た。
「うーん、その辺はなんともいえませんねえ」
問われた種山はもじゃもじゃの頭をさらにもじゃらせようと掻きむしった。
「いろいろと不確定な要素がまだ多いですし、第一その友人の正体がまるで見えないじゃないですか」
うなずく和也氏。いや、和也氏だったはずだが、いまは滋郎氏であった。双子ってやつはほんとうにややこしい。

「そうですね。旅先で出会った人だとは聞いたのですが、それ以上は頑として口を割りませんでしたからね」
「元ヒッピーで、会社を起こした人物というわけですね。しかも、その人の事業はそれなりの成功をみている」
おや、という顔つきになる滋郎氏。
「どうして、そう思われるのです?」
「さきほどおっしゃったじゃないですか滋郎さん。和也さんは、もう少しだといって社長職の交代を拒まれたと。ライバルはまだ倒れてなかったってことですよ。いや、むしろ順風満帆だったのかもしれない。それを見せつけられた和也さんとしては、まだまだやめるわけにはいかなかったのでしょう」
それで山ごもりをしたというわけか。事業からの撤退ではなく、どうすればこの失敗を回復し、さらには成功へと至る道が開けるのかというのが課題だったわけだ。でも、エイズでの寿命よりもずっと早い死を迎える結果になろうとは、確かに無念だったに違いない。
最終的に、和也転じて滋郎となった人物は、種山に感謝して帰っていった。
「ありがとうございました、先生」
そんな風に頭を下げさえした。
「正体を暴いていただいたおかげで、元の自分として会社に戻れますよ。兄が急死してしまって困ってたところなんです。だってわたしは兄を演じていたわけですし、ほんとうは弟だと名乗り出ても誰も信じてくれないかもしれないなんて、焦ってたところなんです。このままずっと兄として生きていかなきゃならないのかな、なんて」
それでもこの二年間は無駄ではなかったと、滋郎氏は語った。兄が見ていた世界を垣間見て、自分のこれからに生かすべき教訓を得たというのだ。
「それはありていにいうと『やさしさ』とか『調和』とかいったものです。こうして言葉にしてしまうとなんだかとても陳腐ですけど、わたしはそういうものの素晴らしさを、この二年間で体感することができたんです。だから、これからの経営に、それを活かしていけたらと思ってるんですよ」
それこそが、兄の無念に報いること、そして兄への弔いとなるはずだと滋郎氏は語った。語るうちに、ヒッピー的な雰囲気がすいーっと抜けていき、帰るころにはすっかり社長然とした気配に代わっていた。同じ服装のままなのに、精神性が変わるだけで人がこんなにも違って見えるのだというのは、また新たな驚きだった。ほんと、最後の方は滋郎さんの顔つきにヒッピールックがまったくそぐわなくなっていたわけよ。不思議な話だけどね。
でまあ、ここまで述懐してきたところで、
「ああしまったぁ」
とわたしは後悔するわけだ。だって、また驚かされてしまったわけだから、種山のやつに。悔しいけども、わたしは認めることにした。
「先生、素晴らしい推理でした。さすが、姉が見込んだだけのことはありますね」
「いえいえ」
せっかく褒めてあげたのに、種山ときたらひらひらと手のひらをふって否定した。
「推理なんかしてませんよ」
「ええっ、だって見破ったじゃないですか。兄弟が入れ替わっていたって事実を」
「ああ、それなら」
「なんですか」
「見ただけです」
「見たって、何を見たんですか」
「絵をです」
「タブロー? ってなんの」
「記憶のタブローですよ。記憶の地図の中に含まれる無数のタブローを呼び出して並べ替えていく。そうしたら、いくつかの組み合わせがおのずと答えを指し示してくれる、というわけです」
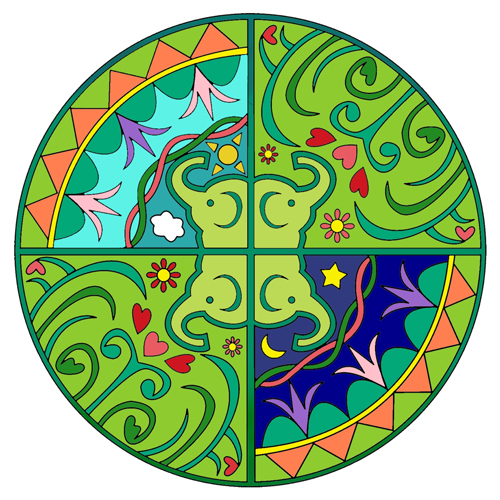
「?」
なんのこっちゃ。
「ほら、この間お話したじゃないですか」
「ってなんでしたっけ?」
「だから、結合術ですよ。この方法を用いれば、記憶の画像がシャッフルされる。そして、それまで無関係に見えていた画像同士が、ふとした瞬間に結び付いて意味を告げてくれるんです。わたしはただ見ているだけ。意識してなにかを考えるというわけではないのです。ただ虚心に見る。すべてを見て、あれこれ並べ替える。するとあら不思議、答えはおのずとあらわれてくる。だから、わたしはただ驚けばいいだけなのです」
なんだか狐につままれたような気分。推理ではなく並べ替えだなんていわれてもねえ。
「それよりだ」
なぞと、急ハンドル切るみたいにいきなり話題変更するもんだから、思わずその遠心力に体が傾いてしまうわたし。
「なんです?」
「すぐに出発しようじゃないか」
「出発? どこへ、です?」
唐突な提案に戸惑うペンギンと化すわたしであった。
「だから、探しに行くんですよ。唯一の手掛かりとなる人物を」
だから、ってなによ。そんな当然でしょって感じの接続詞やめてほしいんですけど。
「いったいどこへ行く気なんですか?」
「さあ、たぶん、タイだろうね」
タイってあなた、その、埼玉とか千葉って感じの平板な発音やめてくださいよ。まるで、タイが千葉の横にでもあるみたいな感じじゃないですか。京葉線ならぬ京泰線でもあるみたいな。
「インドじゃなくて?」
「確かにヒッピーにとって、インドは聖地だからってことで三回ほどチャレンジしたみたいだけど、いずれも三日とか、最長で一週間でギブアップしているんだ」
へえ、よく調べたもんですね。あやか姉さん。
「それに対してタイは、ずいぶん水があったようなんだ」
確かにインドとのギャップはすごかった。なんと、年に数カ月は長期滞在していたっていうんだから。
「多いときには、同じ年のうちに二回も三回も出かけて行っている。どうやら、相当お気に入りの場所があったようなんですよ」
「あるいはお気に入りの人物かもね、恋人とか」
さきほどのエイズの話が思い出される。
「まあ、そんなところかもしれませんね。とにかく、行ってみようじゃないですか」
「でも先生。明日は月曜日ですよ。授業とかあるんじゃないんですか?」
「いや」
返って来たのは、にべもない否定のお言葉。
「ぼくは特別招聘教員なんで、週に二コマしか授業はないんです。講義が一つと大学院のゼミがひとつ。それも金曜の午後だけなんです。だから、全然問題はない。さらにぼくの場合、研究のためとあらば、いつでも何回でも休講してかまわないという特権が保証されているんです」
ひええ、なんて閑な人なんだ。じゃあ、「授業のないときはたいていここにいます」とかいってたあのラブホに、週六日はいるってことじゃあ、あありませんかあ。でも、特別ショーヘーってどういう意味?
「でも、わたしは問題があります。だって特別ショーヘー学生とかじゃなくって、ただの学生なものですから」
ふふん、種山は笑った。せせら笑う感じだったような気がしたが、きっと気のせいだろう。わたしの内面の問題なのに違いない。
「なあに、授業の三つや四つ休んだところで、なんの問題もないでしょう。なにしろ、そもそも学問というものは人に頼ってするものではなく、自分でやるものなんですから」
へーんだ、特別ショーヘーだからってかっこいいことぬかしおって。こっちは単位とるのにひーひー言ってるっていうのにさあ。
「では、さっそく向かいましょうか」
「って、タイにですか」
「ええ、そのためにはまず飛行場です。さっそくタクシーを」
「ちょっと、待ってください」
着の身着のままって、そりゃないでしょ。一応わたしだってレディなんだし、それなりに着替えとかいろいろ準備が必要だし。第一パスポート持ってきてないし。それに、飛行機って、いきなり行って乗れるもんだっけ?

「そうですか、じゃあわたし一人で向かいます」
あっけなかった。実にあっけなかった。別にわたしが行かなくても全然かまわない、っていう感じ。なによそれ。わたしのこと、なんていうかちょっと右腕的っていうか、ワトソン君的っていうか、そんな感じに捉えてくれてたんじゃないわけ。ちょっと、っていうかかっ・なっ・りっ、悔しいんですけど。
「あー、ちょっと待って、ね、先生、こうしましょうよ」
俄然わたしもこの特ダネに興味がわいてきていたのだ。どうしても自分の目で、足で、事実を確かめに行かずにはいられなくなっていた。
「明日の朝いちばんに先生のお宅に伺います」
「といっても、今ぼくの住居はあのホテルですが」
おいおい、なんちゅうところに寝泊まりしてんだよ、この変人。
「わかりました。じゃあ明日の朝いちばんに、先生のラブホ、じゃなくってヴンダーカンマーへお邪魔します」
「出発が遅れるのは残念だけど、まあいいでしょう。ウィッチウイードの水やりとか、ネズミのゴンサクへの餌やりの手筈も整えとかなきゃならないですからね」
渋々ではあったがなんとか妥協させることができた。かくして、わたしたちは高円寺の駅前でさらりと別れたのであった。別れ際、勝手に先に行くなよ、ともう一度念をかけておいた。
(第10回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



