 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(四)象の耳(上編)
なんじゃこりゃ、ってなかんじの物体がホテルの入り口をふさいでいた。長い、そして黒い。いわゆるリムジィィィィンってやつだ。リムジンじゃない。このえばった感じはどうみてもリムジィィィィンだ。円山町にはいかにもそぐわない感じ。通りすがりのヤンキーが、引っかき傷とか付けて行きかねない状況だが、いや、それはない、断固ありえないとわたしは即座に理解した。黒服の男たちがいたからだ。
なんせコワモテ度が並じゃない。あなたもしかしてターミネーターに出てたでしょ、カリフォルニア州知事だったシュワルツェネガーでしょ? と声をかけたくなるようなムキムキ筋肉を黒いスーツの内側にぎゅうぎゅう押し込んだ感じの黒メガネが二人、リムジィィィィンの前と後ろに不動の姿勢で突っ立っていたのである。
くわばらくわばら。とにかく、触らぬ神に祟りなしという感じでわたしはそおっとリムジィィィィンの横をすり抜けた。けど、その際黒メガネがしっかりわたしをチェックしているのを感じた。こわっ、なに、これなによいったい、どういうことよ。
なんて思いながら、ホテルの入り口に近づいたとたん、
むわわわわああん、
強烈な匂いが鼻腔をついた。
一瞬あまりの強烈さにくらっとなるくらいの一撃だった。ご存知の通り、きつすぎる香水は、転じて悪臭と化すのである(嘘だと思うなら女子大の教室を訪れてみるといい)。
「くっさぁ。なによ、これ」
思わず毒づいてみてから、慌てた。黒メガネの二人が、険しい目で見ているではないか。黒メガネの奥の両の目が、怒りにばちっと見開かれ、戦闘のために鍛えられた腕や胸や腿の筋肉が、ぶくりぶくりと膨れ上がり始めている。いまにもスーツが、膨れ上がった筋肉でちぎれ飛ぶ、そんな妄想が膨れ上がった。
こわいっ、こわすぎるぅ。
とにかく、中へ避難だと飛びこもうとした途端、ガチャリと扉が開いた。そして、さらに濃度を増したむわわわわああんとともに、
「ああら、こんにちはあ」
とレイディが現れた。レディではなく、レイディである。リムジンでなくリムジィィィィンなのと同じ意味でレイディ。

年の頃はもしかしたらわたしとあんまり違わないのかもしれない。けど、身につけてるものの価格はトーシロの目にもケタが違った。金銭感覚的には、まさに別世界からやってきた稀人である。上から下までウン百万、いやウン千万円って感じ。いや下手したらそれ以上かも。札束を身にまとってあるいてるっていうより、レアメタルの塊って感じであった。とはいいつつも、無念にも艶やか、かつ綺麗。まさにスーパーモデルみたいな女であった。リムジィィィィンの主であることは、百七十パーセント間違いない感じ。で、そのレイディが、しずしずと、でもヒールの音をコツコツさせながら、扉の外に歩み出てきたのでありんす。いや、ありんした。
でも、ひとつだけ描写し忘れたものがある。あまりに信じ難いものだったために、わたしの目が、いや認知能力がそれを認知することを拒んだのだ。
それは、なあに?
あれは、なあに?
まさか、まさか、まさかねえ。いくらなんでも、首にあんなもの。ほんもののはずは、ってぎゃあ、動いた。動いたわ。巨大な長いものが。ぬらありのたありと鮮やかな黄緑色のぬめつくボディくゆらせながら、わたしを見た。
「おや、食ってやろうかお嬢さん」
「いいえ遠慮させていただきます」
みたいな会話が目線で交わされた感じ。
「こ、こ、こんちわ、っす」
衝撃のあまり返事が遅れ、なおかつ思わずため語になってしまったわたし。相当に動転していたのは間違いない。
「それ、なんですかね。その首飾りっていうか、その」
「ああ、この子?」
濛々たる香水のにおいを吹きあげながら、レイディは嫣然と微笑んだ。
「かわいいでしょ。エメラルドツリーボアっていうのよ。名前は翡翠ちゃん。そのまんまだけどね。頼もしい首飾りってわけよ。ちょっと肩が凝るけどね」
「お、お似合いですわ」
「でしょう?」
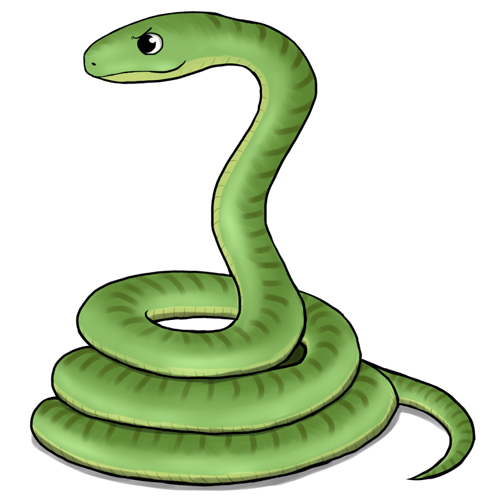
かろうじて絞り出したお追従を当然のものと受け止めての高笑い。さすがです、お嬢様。
体長三メートルに及ぼうかというヘビを肩の上でのたくらせながら、たおやかにわたしを見るレイディ。その一挙手一頭足ごとに、むわわわわあんって強烈な香水が空気をぞよめかせる。そして、おやっ、その後ろに垣間見えるは、あれはもじゃもじゃ頭ではありませんか。
「ああ、さやか君か。遅かったじゃないか」
「何言ってるんですか、先生。これでも、大急ぎでやってきたんですよ。最高時速は千二百二十五キロ超えですよ」
「おやおや、超音速ってわけかい」
「まあ、面白いお嬢ちゃんね。龍宏さんの新しいペットかしら」
ぺ、ペットぉ?
なんと、失礼なものいいであろうかこのいかにもな、でもペットの趣味があまりにぶっとんでるご令嬢殿ときたら。
「いやまあ、そんな感じかなあ」
っておいおい、否定しろよ種山ぁ。
「ご紹介いただけるかしら」
「いいですよ。未知子さん。こちらは、一条」
秘技、快刀乱麻! で種山の声をさえぎり、
「さやか、です」
わたしは戦国武将のごとき大音声で名乗りをあげた。いうまでもなかろうが、種山が口にしたかもしれないあやまった名前を打ち消すためであった。
「なあにぃ、いまの」
ちょっと驚きましたわ、おほほっほほって感じで未知子さんは微笑んだ。
「やっぱり面白い方ね。龍宏さんのチョイスはやっぱり抜群ね」
「でしょ」と、うれしそうに微笑む種山。なあににやけてんだ、もじゃのくせに。
「で、どちらのかたなの、さやかさんは」
「えーと、どちらって、・・・聖アフロディーテ女学院ですけど」
「あら」
おほほっほほほっ、ってなにその変な笑い方。
「ほんと面白いんだから、さやかさんったら。わたし、そんなこと聞いてなくってよ」
じゃあ、何が聞きたいんだよっ、てんだよっ。てやんでえっ。
「ちなみにわたしは宝島ですけど」
「ああ、スティーブンソン原作ですか」
小説だったんですかおたくは、へえ、そうですか。
「何言ってるんですか、あなた」
今度は、種山が驚く番だった。
「わかんないのか、未知子くんはあれですよ、ほらあの宝島財閥の」
「ええっ」
おのろくわたし。言葉の間違いではない。人は驚くを超えたとき、おのろくのである。
「宝島財閥といえば、あのグローバリゼーションを逆手にとって、発展途上国で悪魔のような所業を繰り返している悪の枢軸的な企業集団じゃないですか」
「あら、それはネガティブキャンペーンってやつよ。実際は、わたしたち『木を植えてます』し」
うわあっ、しれっとかまし返してきたよこの人、ポジティブキャンペーン。
「で、未知子さん、あなたは、その宝島財閥のいったいなんなんですか」
おほほっほほほっ。面白いことを聞く方ね、と種山を振り返る。
「ええ、そうなんですよ、未知子さん。実に面白い」
なぞとお追従笑いを浮かべる種山。おい、だらしねえぞ、しっかりしろよ。
「あのね、さやかさん。わたしは、宝島財閥総帥宝島独善のひとり娘です。なんていうか、龍宏さんともとてもお似合いのカップルなんて言われてるんですよ。あしからず」
あしからず、ってどういう意味。あたしがそれ聞いてなに、嫉妬とか、羨望とか、絶望とか、そんな感じの状態に陥るとか思ってるわけ。

「じゃあ、わたしはこれからスワヒリ語のレッスンを受けに参りますので、これにて失礼。さやかさん」
「は?」
なんで、スワヒリ語?
「龍宏さんをよろしくお願いしますよ。わたしの大切な人なんですからね」
えええっ! 冗談きついっすよ。大切な人だなんて。にしても、なんでスワヒリ語なんすかあ?
と問いかける間も与えず、二人のシュワルツェネガーが動いた。機敏な動きで未知子お嬢様をエスコートし、リムジィィィィンの後部座席に押し込んだ。バタム!
えっ、ちょっと待って!
いま、リムジィィィィンの扉が開いた時、なんか聞こえたよね。うがごおおおっとかなんとかかんとか。あれってMGM的なあれじゃない。咆哮、そう百獣の王の咆哮ってやつ、雄叫びってやつじゃないの。
でも、そんなわたしの疑問を置き去りにしたまま、リムジィィィィンは、ホテルの前から消え去った。どう考えても走りにくいはずのこの円山町の狭い道を、どうやって角を曲がるのかと他人事ながら心配になるような長さの、そうチンチン電車くらいの長さをもった黒塗リムジィィィィンは、静かに姿を消したのだ。
「先生、聞こえましたよね、今の」
「ん?」。間抜け面。
「だから、あれ、絶対獅子哮ですよね。ライオンさんの咆哮でしたよね」
「ああ、ジョンのことですか?」
「ジョン?」
「そうですよ、未知子君が飼ってるホワイトライオンの名前ですよ」
「ホワイトライオンって」
「絶滅危惧種です」
「ええっ」
なんで絶滅危惧種が、車に乗ってるわけ。
「彼女はね、動物愛護運動で世界的にその名を知られた人物でもあるんですよ」
「ほお」
どうやら種山の向こうには、わたしの想像を超えた世界が広がっていると感じられた。
「密輸入されて虐待されたり、放置されたりした動物を彼女は片っ端から引き取って保護しているんです。彼女の第四別邸がある逗子には、動物園もびっくりの希少動物たちが優雅に暮らしているんですよ。そして、彼女は魔女キルケのごとくその動物たちの中に君臨しているというわけなんです」
「なるほど、魔女ですね。まさに」
ということは、あの蛇もそういう由来で彼女の元にたどりついたということなのだろう。ちょっと見直したりもするわたしであった。
「ね、ほんとうにおもしろい人だろ」
リムジィィィィンが去って行った方向をじぃぃぃぃんと見つめながら微笑む種山。
「なあに、のろけちゃってるんですか、先生」
驚いたような顔でわたしを見つめる種山。
「なんでぼくが、のろけてるなどと」
「だって、なんか未知子さん、それっぽいことを」
「いや違うさ。あれは、からかっただけですよ、あなたを」
ふはふはと笑う、もじゃ。もうちょっとカッコイイ笑い方してほしいところだ。
「あのね、ぼくが面白いといったのは」
「動物のことでしょ。あれだな、きっとあのガードマンたちは車のなかでライオンと一緒にいるのが気まずくて外に立ってたんですね。わたしようやく理解しましたよ」
「いや、違うんです」
懸命に否定する種山。
「どういうことです、なにが違うんですか、先生」
「いいですか。ぼくが面白いといったのは、彼女の香水のことなんですよ」
「香水」
ああ、あのむわわわわんね。思い出した。鼻をくんくんしてみて、まだこのあたりの空気があの臭気による汚染から解放されていないことに気が付いた。けれどまあ、薄れてくれば、それなりにいい香りといえなくもなかった。
「ちょっと変わった匂いですね」
甘くって、でもちょっと粉っぽい感じ。
「まあ、ぼくにはよくはわかりませんけどね、こういう世界は」
「でしょうね」
「ところで、君だって当然知っているだろうけど」
いや、たぶん知りません、と胸のうちでつぶやくわたし。
「多くの香水には、動物の腸内分泌物が含まれていますよね」
鼻をひくつかせるわたしに、種山が語り始めた。
「腸内分泌物?」
「そうですよ、麝香しかり、龍涎香しかりです」
「ほんとですか」
そういえば、なんかそんな話聞いたことがあるような。
「でも、彼女がつけてたのは最高の逸品なんですよ。あれこそまさに、アートです」
「どういうことです」

いったい何をそこまで絶賛しようとしているのだろうか、このもじゃもじゃは。
「うん、あれは世界に八十本しかない、サープラス、つまり余剰品という意味の香水でね」
「ええ」
「イギリス人アーティスト、ジャーミー・ニコラスが」
「はい」
期待が高まる。
「なんと、あろうことか」
「ちょっと、もったいぶらないでくださいよ」
さてさて、どんな変わった動物の名前が出てくるのやら。
「自らの」
「自らのなんです」
「余剰品から作った香水なんですよ」
「余剰品って」
そんな!
「つまり、飯食ったら出る奴」
良い匂いと悪い匂いには、同じ芳香成分が含まれていることを逆手にとったアート作品としての香水なのだそうだ。なるほど、面白い人だとわたしも感心せざるをえなかった。確かにすごい。これこそが大物の風格ということなんだろうか。なんという勇敢な女性なのだろう。ちょっと尊敬入っちゃったりするのだった。それに、スワヒリ語まで学んでいらっしゃるようだし。
でも、驚きはそれで終わったわけではなかった。
わたしたちが乗ったタクシーは、羽田にも成田にも向かわなかったからだ。
代わりに、どんどん山奥に入り込んでいって、県境を越えた。そして、ついに海沿いに開けた、千葉県の広大な敷地にたどりついたのであった。
『不二見コンツェルン専用飛行場』との立て札。発着する数台のジェット機。ほかにも、まだ飛んでいないれっきとしたジェット機たちが待機している。
「なんですか、ここ」
私設の空港なんてものがありうるのだろうか? そう問いかけたいわたしをさしおいて、
「おはようございます、種山社外相談役殿」
髭面の皇太子。みたいな雰囲気の人がタクシーの扉の横に現れていた。
「相談役?」
どういうことと問うわたしに、
「まあそれは後で話すことにしようじゃないか。とりあえずは出発だ」
そう言ってタクシーを降りた。十円の単位まできっちりおつりを受け取る社外相談役の姿をわたしは見た。家政婦のように。
「用意はできてるの、吉村さん?」
〝もじゃ〟の問いに、恭しく応じる皇太子。なんか身分があべこべな感じ。
「もちろんでございます。もっと早くおっしゃっていただければ、A300の方もご用意できたのですが」
「いやいいよ、バカンスじゃないんだから。なにもフライング・パレスじゃなくったって。バンコクまで飛んでくれればそれでいいんだ」
「了解いたしました」
こちらへどうぞ、と案内されてついていくと、実にたまげたことに、そこには小型のジェット機が待機しているではないか。しかも、タラップの下では機長らしき人物と、副機長らしきイケメンの若者、そして数名の美しい客室乗務員たちがにこやかに待ち受けている。
「いったいどういうことでしょうか、先生」
わたしは問いかけようと試みるのであるが、
「では、出発いたしますので、ご搭乗ください」
イケメンの副機長に、にこやかに微笑みかけれられて手を取られてしまったりしたために、思わず舞いあがってしまったりしてしまったために、その機をいっしてしまったりしてしまったりしたのであった。

「えっ」
ずらりと三列縦隊で椅子が並ぶ庶民的な光景はそこにはなかった。
代わりに、そこに広がっていたのは巨大なラウンジ、のごとき部屋であった。ラグジュアリーな感じの、ソファとしか呼びようのない腰掛けが数脚設置されており、正面には巨大なスクリーン。他の客はと見回してみても、われわれ二人以外には見当たらないという始末である。
ジェット機貸切。人生ってやっぱり面白いね、お姉ちゃん。
そしていま。高度一万メートルでの安定飛行に移行して、客室乗務員が笑顔とともにシャンペンなど振舞ってくれたところである。さて種山先生、もう逃げられませんぞ。ここは空の密室。わたしの詰問から逃れるすべはもうないのです。ふっふっふっ。
というわけで、
「全体、これはどういう意味ですか」
「全体、というと?」
「すべてですよ。このすべて。きちんと説明をお願いいたします」
わたしは、眼光炯炯モードで澄まし顔の種山をねめつけた。普通の人間であれば、縮みあがる威力をもつメンチ切りである。なにしろ、わたしはかつて・・・、おっと、いけない、これは秘められた、いや封印された過去ってやつ。いまのわたしは花も恥じらう乙女な女子大生なんですもの。
「変だな、知ってると思ったけど。お姉さんには聞いてないんですか?」
「何をです?」
「何をっていうか、その全体? みたいなことを」
「いいえ、姉からは聞いておりませんが」
ほんと、なあんにもです。
(第11回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



