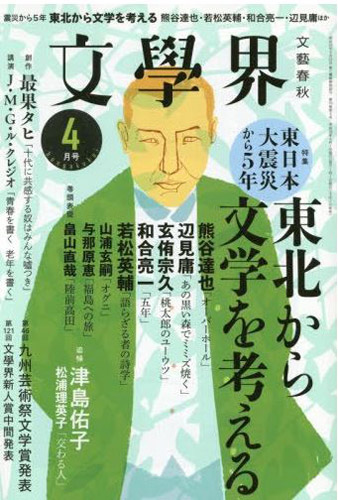
時代の変化はまず〝現象〟としてあらわれる。底の方から蠢く変化を感受してはいるが、その正体がはっきりわからぬまま表現されるのである。そのような表現が筍のようにポツポツと芽生え育ってゆくと、自ずから一つの精神的パラダイムが形成される。ただ時代の変化を〝感性〟として掴んだ者が、同時代を代表する作家になるとは限らない。それは確かに誰もが気づいているが、形にできなかった何かに最初に形を与えた記念すべき仕事である。ただ形(作品)になると、それはあっというまに一般化する。本当に優れた作家はその先の、変化の本質を表現しなければならない。
一九八〇年代から現在まで、文学、特に純文学の世界は衰退の一途を辿った。それは誰にも止められない、どうしようもない衰退だったと思う。大きな過渡期なのだ。この三十年ほどに起こったのは高度情報化社会の出現であり、インターネット革命だった。それは静かな革命だが、人々の仕事はもちろん、感受性をも決定的に変えた。その気になれば表情報も裏情報も簡単に入手できる時代に決定的な個の見解などあるはずがない。それは瞬時に相対化される。だから作家の仕事は〝どんな意見や思想を表現するか〟ではなく、〝同時代をどのように構造的に捉えるのか〟へと変化している。戦後文学まで続いた作家の特権的個の神話は、ほぼ完全に効力を失ったと言っていい。
下世話なことを言えば、今やもう「本を読まなければバカになる(知性は身につかない)」と大まじめで言う人はいないだろう。なるほど受験勉強では国語力が必須だが、文学を志す若者の感受性が変わってしまっている。子供たちはまずゲームやアニメで基本的感受性を養うのであり、その中のほんの少数が思春期になって、文学という古くて新しい表現に魅了される。ただ当たり前だが不況産業になった文学に、昔ほど多くの若者が魅了されるわけではない。その層は確実に薄くなっている。そのためたいていの文学少年少女は孤立している。また若い作家たちの大半が同時代のライトノベルに近い作品を好む。理由は決定的なことが書かれていないからだ。時代を規定するような核のような思想は存在せず、にもかからわず何かの中心を求めざるを得ない指向が時代全般のアトモスフィアになっている。
ではこれら生まれながらの情報化社会世代が育ってくるとどうなるのか。一九八〇年代から二〇〇〇年紀に一家を為した作家たちは、多かれ少なかれ戦後文学を規範としている。しかし全盛期の戦後文学の力強さを持たず、かといって二十一世紀的な感受性を反映しているわけでもない。新たな世代はこの時代の文学をスキップするだろう。八〇年代的作家たちは、半世紀も経てば文学史の中に埋没し、忘れ去られてしまう可能性があるということだ。もちろん現実には古い作家と新しい作家の中の、ほんの少数が二十一世紀的文学の基礎を作るだろう。しかし明治三十年代までの文語体作家が実質的に文学界から消え、四十年代以降の作家が近代文学を作ったように、八〇年代的作家はよほどの方向転換を果たさないと二十一世紀文学として生き残れないだろうと思う。
もちろん二十一世紀的感受性を持つ若い作家たちの前途が希望に満ちているとも言えない。娯楽はもちろん教育メディアも多様化した現代では、かつてのように文学書が売れることはほぼ期待できない。楽しみのために小説を読む読者は減り続けるだろうから、特に純文学系では読者が〝読まなければならない〟と動機付けされた作品しか支持されなくなるはずである。一般社会が勝ち組と負け組に分かれるように、純文学の世界でも大きな格差が生まれるだろう。また読者に読ませるための動機付けは、作家自身が読者を強く意識することからしか生まれない。文壇や詩壇と呼ばれる閉ざされた文学者たちのコロニーは、間違いなく質的に変化するということである。読者を意識できない作品は必然的に負け組になる。
かわいそうな人のためにしか芸術がないから、かわいそうな人がかわいそうぶっている世界が嫌いです。音楽に救われたって言っている子に永遠に勝てない。ただちょっとかっこよくて、いいかんじだなって思いましたよ、ぐらいじゃどうせ喜んでもらいない。ライブハウスで歌手にすがる右手より、私の存在は価値がないんです。価値がないファンなんですよ。私のための芸術なんて、欲していないからそんなものはない。生き残るために、この世界を生き残るために、って言えるほど私は苦しんでいないな。愛して。っていう感情が不要なのは私が両親に愛されているから? それとも性欲が少ないから? 女の子は性欲が人によって違うっていうのは本当だと思うけれど、他人が言っていたら純粋ぶっているな、と思う。
(最果タヒ「十代に共感する奴はみんな嘘つき」)
最果タヒ氏は新しい世代の才能をはっきり感じられる数少ない若手作家である。このくらい才能を感じられる作家の作品は久しぶりだ。詩人としてデビューしたが、彼女の場合、詩や小説というジャンルの違いはあまり意味がないだろう。作品が詩になっていない、小説になっていないという意味ではない。彼女の中の表現欲求が、時に詩になり小説になるということである。溢れ出るような表現だから成功作もあれば未熟な作品もある。ただ混ぜ物がない内面独白は非常に刺激的だ。作家は言葉数を増やせば増やすほど、それに足をすくわれるのが普通だ。だから抑制する。しかし最果氏の作品にはそれがない。呆れるような饒舌体だ。
純文学は一人称の内面独白小説が多いが、風景や物の描写など意外に混ぜ物が多い。しかし最果氏の内面独白は思考の流れが核になっている。それは基本的に否定の連続である。反語混じりだということだ。「音楽に救われた」「性欲が少ないから?」うんぬんは、はっきりとした否定だろうが、「私の存在は価値がないんです」「この世界を生き残るために」という記述は裏返しの希求である。しかしいくらやっても合うカードが見つからないトランプの神経衰弱のように、「私の存在価値」や「この世界を生き残るための答え」は見つからない。
主人公は問いを発する。発した途端にその答えが世の中にいくらでも、ほとんど無数に存在していることを思い出す。どの答えにも安住したくないと思う。やはりどれも間違った答えだと思う。だから矢継ぎ早に問いが発せられ続け、その答えが一つ一つ否定されてゆく。それを表現するには思春期の反抗期が一番ふさわしいというのが、「十代に共感する奴はみんな嘘つき」で、十七歳の女子高生を主人公にしたひとまずの理由だろう。
「それならお兄ちゃんだってビッチのこともう少し考えたら?」
「考えてるから結婚するんだろうが!」
うわ、という声が私から漏れたのだ。(中略)「あいつが、気に病んで俺が死ぬんじゃないかとずっと心配してくるから、結婚すんだよ。家族って死なないっていう約束みたいなところあるだろ? って、あー、もう、なんでこんなこと妹に話さなきゃいけないんだよ!」
「え、本当? お兄ちゃんがやけくそで結婚したがったんじゃなかったの?」
「そういうことにしているだけだって。俺はこんなさっさと結婚相手決めて良いのかなぐらいに思ってるよ、まだ卒業してねーんだぞ、わかるだろ、カズハ、俺がどんだけ留年してるか数えてみろよ」
(同)
主人公のカズハには七歳年上の兄・葉介がいて、長く付き合った彼女がいる。カズハは兄から彼女が浮気したと聞かされていた。それ以来カズハは彼女をビッチと呼んでいる。兄には三井という親友がいて、三井の彼女が自殺した。ビッチは三井が後追い自殺しないように、一度限りだがセックスしたのだった。その兄がビッチを連れて実家に戻ってくる。結婚するのだと言う。なぜか自殺しそうだという三井もいっしょだ。カズハは兄は三井が自殺しないように見張り、ビッチとはやけくそで結婚するのだと思っていた。しかし違っていた。
兄はふとしたはずみに、自分がビッチの浮気を気に病んで、彼女が「死ぬんじゃないかとずっと心配してくるから、結婚すんだよ」とカズハに告白する。自殺した者は弱いのかもしれない。自殺を心配された三井も弱いだろう。しかし庇護者であるはずの兄も弱いのだ。カズハは実家で初対面のビッチと兄について話していた。ビッチは兄は「強くて弱い」と言った。「ある一定のところまでは完全に耐えられるの。でもそれを超えると一瞬で粉々に砕ける」とある。誰もが強くて弱い。物語は円を描くように振り出しに戻る。
「唐坂さん」
呼ぶ声。初岡が私の制服のそでをつかんだまま、月を見ていた。
「なに?」
「あのさ、死なないでね」
兄にも、三井にも聞こえない小さな声。彼女は私の顔を見るのが嫌で、それだけで月を見ているのかもしれない。
「初岡さん、月おっきいよねー、でもスパームーンって名前はダサいよね」
「あー、日本語にすると超月だからね」
「日本語にするのやばい! おいしい中華屋さんみたい!」
そう笑って、それから、本当に小さく「大丈夫だよ」と伝えた。
(同)
カズハには初岡というクラスでも目立たない同級生がいて、彼女はいじめにあっているのではないかと思っていた。しかし兄や三井と来ていたファミレスで、初岡が大学生たちと食事をしているのを見る。初岡は大学生たちとバンドを組んでいた。ちゃんと学校以外の世界を持っているのだった。しかし初岡の手首にはたくさんの薄いリストカットの跡が見える。その初岡から、反抗期真っ盛りで生命力の塊のようなカズハは「死なないでね」と言われてしまう。ここでも物語は最初の入り口に戻る。
「十代に共感する奴はみんな嘘つき」というタイトルは、大人はわかってくれない的な思春期の少女の心理を描いた小説だということを、必ずしも意味しない。作者自身、カズハのように否定に否定を重ねる十代的反抗に、心から共感してはいない。そんなステレオタイプな反抗は、やはり嘘混じりだと考えているのだ。最果氏の作品には投げやりな全肯定と執拗で徹底した全否定が多い。しかしいずれにも属さない本当の答えといったものはまだ見えて来ない。勝負はこれからだろう。四十代、五十代になっても、ずっととりあえずの肯定と執拗な否定を繰り返してゆくわけにはいかない。ただ最果氏の作品は、同時代の感受性をしっかりと捉えている。優れた作家である。
大篠夏彦
■ 最果タヒさんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■






