
エズラ・パウンドの長篇詩『詩篇』の翻訳や、西脇順三郎研究で知られる英文学の碩学、新倉俊一先生が詩集をお出しになった。わずか二十三ページでホチキス中綴じの簡素な私家版だが、いかにも詩を愛する先生らしい装幀と内容だと思う。
パルティザンたちにではなく、救急車に運ばれて
知らない郊外へ収容され
視覚も触覚もなく、瞼は重くのしかかる
めまいと吐き気 それに腫れた足(オイディプス)
ここはどこ?
収容所/または地獄?
だれも互いに知らず、ただ仕切られた独房のなかで
呻いている
(中略)
数週間して病室を移され、やっと自分の意識を取り戻した
(『エズラ・パウンドを想いだす日』Ⅰ 冒頭)
新倉先生は今年の二月に体調を崩し、「救急車に運ばれて」入院された。退院後の療養中に『エズラ・パウンドを想いだす日』をおまとめになったようだ。詩集タイトルに明示されているように、この詩集で先生はエズラ・パウンドの詩法を援用されている。作者の意識の流れに沿って自在に詩行を紡いでゆく詩法である。この詩法は原理的には先生が私淑した西脇順三郎の方法と同じである。しかし詩の中に、同時代に対する厳しい批評を織り込んでゆくのがパウンド独自の特徴である。先生はこの詩法を我がものとされている。
『他人の空』以来ずっと 彼は
「石を食ったように頭をかかえている」空に憑かれていた
戦後社会に欠落している何かに
晩年の『アメリカ』でも
右翼のキリスト教原理主義によって
現代のアメリカもまた
「空に欺かれ」ていると嘆いている
一九三九年 パウンドがむなしくアメリカに
その回復を求めに来た「天」だ
(『エズラ・パウンドを想いだす日』Ⅱ 部分)
『エズラ・パウンドを想いだす日』は、先生の同時代詩人たちに対するレクイエムでもある。引用の詩で歌われているのは言うまでもなく飯島耕一氏である。先生と同じ昭和五年(一九三〇年)生まれの詩人で昨年お亡くなりになった。飯島氏は軍国少年で、終戦の年の昭和二十年(一九四五年)八月二十日に航空士官学校に入学する予定だった。処女詩集『他人の空』には、十五歳で死を覚悟した少年が抱いた深い空虚が表現されている。それは詩でしか表現できない空虚だった。
飯島氏はこの空虚を、戦後社会に対する批判的意識として育んでいった。飯島氏は大学教授で高名な詩人なら当然授与されるはずの国家からの表彰を一切拒んだ。それが少年の日に、自分の力を遙かに超えた巨大な力に翻弄された飯島氏が、自らに課した倫理だった。飯島氏はシュルレアリスムの先駆者で敬愛する瀧口修造が、戦前にわずか数篇だけ書いた翼賛詩に激しくこだわった。いささか意固地ともいえる潔癖が飯島氏にはあった。
飯島氏の戦後詩人としての姿勢は一貫していた。権力に対峙できる〝私〟を模索して『私有制にかんするエスキス』を書いた。「ことばを 私有せよ/非打算的に ことば/をつかうことをせよ/巨大な 監視者 に/は 理解 しがた い/ことばを 私有 せよ」という詩行は今も新鮮だ。新倉先生が飯島氏に、「一九三九年 パウンドがむなしくアメリカに/その回復を求めに来た「天」」を見出しておられるのは正しい。飯島氏は優れた現代詩の作家でもあった。

新倉先生の『エズラ・パウンドを想いだす日』には、最晩年の飯島氏と先生の交流が描かれている。飯島氏は先生の『ピサ詩篇』翻訳を激賞し、平成十六年(二〇〇四年)に最後になったご自分の詩集『アメリカ』との合同出版記念会を東京ステイション・ホテルで開いた。飯島氏のように無邪気で頑固で素直な詩人の言動には裏がない。晩年の飯島氏はパウンドの『詩篇』に強い興味を示していた。
飯島氏の詩集『さえずりきこう』収録の長篇詩『生死海』は、日本語で書かれた最も『詩篇』的な作品である。『生死海』で飯島氏は、社会批判的であるがゆえに、どうしても肥大化してしまう自我意識を無あるいは天の秩序の方へ溶解させようと試みている。悟りの境地に達しようとしているわけでは必ずしもない。ある理想的な秩序を求め続けることが、煉獄のような現実世界に生きる詩人の務めだという意識が飯島氏にはある。それはパウンドの『詩篇』での「天」の希求と同質のものである。
そういえば晩年の田村さんの詩集にも
『死語』という題名がある
彼こそ戦後詩壇の死語の大掃除者だ
一九七一年にニューヨークへ詩の朗読に招かれたとき
「だれか会いたい詩人がいるか」と聞かれ
グルニッジ・ヴィレッジに住む
オーデンの下宿を訪ねた
二人が片言の外国語でなにを語り合ったか知らない
でも詩は決して死語を使わないと一致した筈だ
(『エズラ・パウンドを想いだす日』Ⅳ 部分)
詩集『エズラ・パウンドを想いだす日』には、新倉先生と親交の深かったもう一人の詩人が登場する。田村隆一氏である。田村さんが聞いたら怒り出しそうだが、東京・大塚の老舗鳥料理店の御曹司として生まれた田村さんは生粋のボンボンだった。ただ田村さんの御曹司性は、素直でおとなしい貴公子詩人としては開花しなかった。田村さんは我が儘かつ傍若無人で人なつっこかった。しかしその孤独な精神は、なにものにも影響されない批評性を兼ね備えていた。ほとんど批判的な散文は書かなかったが、口を開けば詩人たちや詩壇への批判がとめどもなく溢れ出した。その批評は当然、極めて的確だった。
戦後詩と呼ばれる詩の潮流は、ある意味で田村さんの「おれは垂直的人間」(詩篇「言葉のない世界」)という一行に集約することができる。この「垂直的人間」は現実に焦土となった日本に――戦前の思想や価値基準が全面崩壊し、まだ新しい精神が見えてこない戦後精神の荒野にポツンと立っている。またその「垂直」性は天と地という両極(世界観)を有している。「垂直的人間」の精神は孤独な個のものだが、それ自体が一つの世界観を持っているのである。飯島氏の孤独な批評精神もまたそのような質のものであった。
オーデンがひそかに書いた「手紙」がぼくらの手もとにとどいたときは
ぼくらの国はすっかり灰になってしまっていて
政治的な「正しきものら」のメッセージに占領されてしまったのさ
三十年代のヨーロッパの「正しきものら」は深い沈黙のなかにあったのに
ぼくらの国の近代は
おびただしい「メッセージ」の変容の歴史 顔を変えて登場する
自己絶対化の「正しきものら」には事欠かない
(田村隆一 詩篇「新年の手紙」(その二)より)
田村さんは中桐雅夫氏の翻訳を通じてW・H・オーデンに強い関心を抱いていた。詩に表れる「オーデンがひそかに書いた「手紙」」は、オーデンの詩篇「一九三九年九月一日」のことである。この日、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まった。田村さんもオーデンも飯島氏も、常に研ぎすまされた批評精神を持って現実世界に対峙し、空疎な言葉を書き付けない姿勢を持っていた。新倉先生が「詩は決して死語を使わない」と表現した通りである。ただ田村さんは生粋の詩人だった。
新倉先生が詩篇で描いたように、田村さんは一九七一年にニューヨークでオーデンに会った。しかし直後に刊行された詩集『新年の手紙』あたりから、田村さんの詩はより自在な表現を求めて変わり始める。積極的に西脇順三郎の詩法を取り入れ始めたのである。瀧口修造に私淑していたこともあり、それまで犬猿の仲だった西脇氏と飯島氏が和解したのが一九六七年だから、最も戦後的な詩人である田村さんと飯島氏は、一九七〇年頃に期せずして西脇詩の詩法を援用し始めたのである。ただ西脇氏の詩法には問題があった。
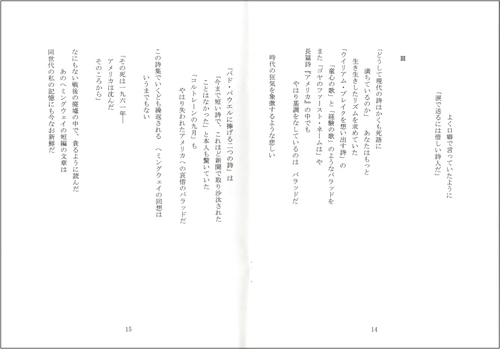
西脇氏の戦後の処女詩集である『旅人かへらず』は、ほとんど俳句と言っていい表現である。西脇詩の主題は東洋的無を表現することにあった。西脇氏はそれを「永遠の淋しさ」と表現した。氏には「肉体も草木もあたしには同じだわ」(詩篇「アン・ヴァロニカ」)という認識がある。そのため詩篇からは〝私〟という主語が消え、現実世界に食い込むような批判意識も表現されなかった。しかし西脇氏は日本語で初めて意識の流れの手法を使いこなし、現実から空想(観念)の世界に至るまで、自在に詩を紡ぐことができた詩人である。自由詩の歴史は短い。明治維新以降の詩の世界で、最晩年までレベルを落とさずに作品を量産できた詩人は西脇氏が最初なのである。たいていの詩人は晩年になると書けなくなる。
田村さんも飯島氏も、より自在に詩を書くためには西脇的詩法を我がものとする必要があることに気づいていた。しかし文明批評的詩人である二人には〝私〟という表現の核が必要だった。〝私性を放棄せずにいかに自在に書くか〟という問題があったわけだが、その解決の糸口を示唆したのがパウンドの『詩篇』――というより新倉先生の『詩篇』と『ピサ詩篇』だった。パウンドについて書いた田村さんの文章は少ないが彼はパウンディアンの一人である。新倉先生が詩集『エズラ・パウンドを想いだす日』で飯島先生と田村さんを想起したのには本質的理由がある。
イエイツの死を悼んだオーデンの詩に
「死んだ詩人のことばは 生きている者の腸で消化される」
という詩行がある。死語ではなく
詩人の生きたことばこそ生命の糧なのだ
「お前が深く愛するものは残る
その他は滓だ」
そしてすべての人との出会いでも
「あの心のなかに跡を刻んだ
愛情の中身しか問題にならないのだ
-しまいには-
思い出のやどるところに」(詩篇七十六篇)
(『エズラ・パウンドを想いだす日』Ⅳ 最終部)
僕もまた新倉先生訳のパウンドの『詩篇』に影響を受けた一人だ。翻訳は常に更新されてゆくべきものだと思うが、僕にとってパウンドの『詩篇』は新倉先生訳のことである。シェイクスピアが専門であり、ディキンソンの研究者で西脇順三郎の弟子でもある新倉先生の訳以上の質のものは考えられない。また僕は新倉先生と同様に、「お前が深く愛するものは残る/その他は滓だ」という断言を信じている。
新倉先生の詩集『エズラ・パウンドを想いだす日』は、自由詩にとっていかに〝自由〟が大切なのかを教えてくれる。親しい友人が亡くなった時に、その感情の高まりまでを含めて詩で自在に表現できない詩人など詩人ではない。詩の世界が思想的信念を持たない詩人たちの〝死語〟で埋めつくされようとしている時に、それはおかしいのではないかと表現できない詩人など必要ない。『エズラ・パウンドを想いだす日』はパウンドの翻案詩では決してない。戦後を代表する優れた詩人たちを悼むことで、現在の詩への厳しい批判を表現した優れた詩集である。
鶴山裕司
【新倉俊一詩集『エズラ・パウンドを想いだす日』書誌データ】
発行 二〇一四年七月三日
発行者 新倉俊一
制作所 ヨシダデザイン株式会社
私家版
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
