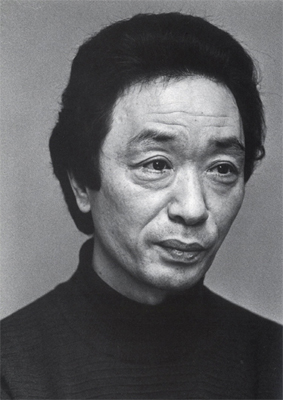
垂直と水平
天地と東西南北からはじめて
行(ゆ)き方(がた)知れずになる
(『ぜんまい』冒頭。『行き方知れず抄』[一九九七年])
世を絶した銀嶺の荘厳に向けてでも
遙かな環礁のエメラルドグリーンの海に向けてでもなく
オットセイよりも臭い息を吐きながら逃げてやる
行き方も知れず逃げてやる
(『雲行き怪しく』終結部。同)
詩集『行き方知れず抄』は、後期・孝輔文学の方向を決定付けた作品集である。ただそれは、『行き方知れずになる』、『オットセイよりも臭い息を吐きながら逃げてやる』とあるように、方向性を定めないという意味での方向性だった。孝輔は破れかぶれの醜態を曝してでも、虚無的絶望から逃れようとあがいている。どんなことをしてでも、八方塞ぎの状態から逃れ出ることに希望を見出している。
思想だけを抽出すれば、孝輔は『漆あるいは水晶狂い』で創作活動を終えていても不思議ではない。実際、大学生の時に初めて『漆』を読んだ時、わたしはこれは一種の翻案思想詩であり、ここで表現されているヨーロッパ的思想を、日本人が生涯に渡って探究することはできないとはっきり思った。しかし孝輔はその後も多作だった。孝輔は必ずしも思想そのものには忠実ではなかったのである。
孝輔は処女詩集『場面』の末尾を、『構えは要らない/言葉をねじ伏せて進むつもりなら/言葉が私をみちびくだろう』(『夜の樹間』)という詩行で終えている。これらの言葉は孝輔本来の資質をよく表している。端的に言えば、言葉への信頼(あるいは過信)が孝輔に詩を書き続けさせたのである。思想的閉塞を、詩の言葉で打破できると信じ得た孝輔の資質が多作を可能にしていると言ってもよい。この言葉への信頼は、孝輔が書いた批評からも読み解くことができる。
批評家として孝輔が高く評価した日本の詩人は、蒲原有明、萩原朔太郎、吉田一穂、瀧口修造などである。孝輔は朔太郎を日本で最初に『詩的幻想の自立化を推し進め』た詩人だと評価しながら、最後まで『おのれの自我意識の統一性』に固執し『近代的自我から、言語自体への主導権の移行』を為し得なかったと批判している。朔太郎の詩は彼個人の自我意識に支えられており、汎用的な詩的言語となっていないという意味である。
これに対して瀧口の詩は、『朔太郎的な近代的自我の崩壊とその正統な超克の上に立って、『言語の自己反応の力』を最大限におしすすめながら、いわばランボー的な意味での『客観詩』として成立している』と最大限の言葉で評価している。正否は別として、孝輔は現代詩を、近代ロマン派的な自我意識が担っていた詩的エネルギーを、そっくり『語に主導権を渡す』(マラルメ)ことで得られる言語作品だと考えていた。
また蒲原有明は孝輔最愛の詩人だが、有明のソネット形式や、四六調と呼ばれる独自の音韻(音楽性)のみを高く評価している。有明は晩年に、彼の世界認識思想とでも言うべき仏教的平安の境地を希求するようになったが、それは一顧だにしていない。孝輔は『晩年の『形而上学』は、ついに彼自身の『有明集』の詩美を超える詩的世界を創出するには至らなかった』(『蒲原有明の〈信仰詩〉の位置』一九八四年)と切り捨てている。
孝輔が日本の詩人ばかりでなく、ヨーロッパ詩の批評でも繰り返し語っているのは、自我意識の超克の上に現れる『語』の世界の可能性である。意味的に分析すれば、孝輔が求めたのは新たな世界原理思想である。しかしそれは、本質的には汎用的な(詩)『語』として獲得されなければならないものだった。不可能性の肯定が『水晶』という『語』に結晶したように、新たな世界原理思想は新たな『語』によって明らかにされねばならないということである。だがそんなことが可能なのだろうか。
色とりどりの夢まぼろしだ
けれどもその色を正確に名付けよ
腐ってゆき 傷んでゆき
痴呆の果てに
ついに無意識の混沌たる根源へと向かうのか
晴々しく禍々しく
陽気ではかない祭りの末に
どのような花の色のうちに散ってゆくのか
散ってゆくのか
名付けよ 今はその色を正確に名付けよ
(『晴々しく禍々しく』部分。『啼鳥四季』[一九九一年])
孝輔は『名付けよ 今はその色を正確に名付けよ』と書いている。それは世界の『根源』を的確に表現する一つの『語』への希求である。またそこに思想的探究がなかったとは言えない。孝輔は詩集『啼鳥四季』の頃から一種の東洋回帰を始め、老荘思想から法華経、謡曲や『今昔物語』に至るまで、ほとんど手当たり次第に東洋古典を引用している。しかし孝輔は結局、自分のオリジナルな言葉としてはもちろん、どんな先行的テキストにも根源的な『語』や思想的帰結を見出し得なかった。

左から北村太郎、飯島耕一、渋沢孝輔氏(一九八四年)
また東洋回帰を始めた孝輔の詩には、植物に関する記述が増えてくる。引用の『晴々しく禍々しく』も、梅や桜、木蓮や椿の花を題材にした作品である。しかし孝輔は植物を描くことで、日本文学ではなじみ深い短歌・俳句的季節の循環性に思想的平安を求めようとしたわけではない。『腐ってゆき 傷んでゆき/痴呆の果てに/ついに無意識の混沌たる根源へと向かうのか』とあるように、それは空虚を埋めてくれるだけの一瞬の徒花(あだばな)である。孝輔が求める思想的『語』は存在しないのである。
未経験の地平で日々に痩せながら
奇態な隠れた分身の
宿業の国に咲く花の行方を尋ねている
(『物みなは歳日と共に』最終部。詩集『冬のカーニバル』[一九九九年])
詩篇『物みなは歳日と共に』は病床で書かれ、孝輔の死後、詩集『冬のカーニバル』に収録されて刊行された。孝輔は病で身体を細らせながら、不死であるはずの精神の肉体でなおも『花の行方を尋ねている』。しかし残酷な言い方かもしれないが、孝輔にもっと時間が残されていたとしても、この『花の行方』は解明できなかったのではないかと思う。それは不可能への希求である。
思索的詩人に見えるが、孝輔は最後まで方法を持たない徒手空拳の詩人だった。自らの感覚と勘に従って作品を書き続けたのである。孝輔は詩人の思想は究極的には詩語として表現されると考えたが、誰もが『そうだ』と諾うような〝詩的言語〟や〝客観詩〟は存在しない。詩語もまたわたしたちが日常使っている言葉で書かれる。なんら特殊なものではない。詩語を日常言語と区分するのは、作品全体が紡ぎ出す関係性である。それは思想を究め、言葉の表現可能性を探究し尽くした果てに生み出されるものである。しかし思想面でも詩の技法面でも、孝輔の探究は中途半端だった。
ただわたしは孝輔の詩業が徒労だったと言いたいわけではない。現代詩人は多かれ少なかれ、若い頃雷に打たれるように西方の詩と思想に出逢い、その可能性を真っ直ぐに東方の言葉で表現しようとした時期があるはずである。現代詩人にランボーと芭蕉のどちらが自分にとってより近しい存在かと聞けば、多くの詩人がランボーと答えるだろう。端的に言えば、孝輔が希求したのは世界原理としてのマラルメ的『一冊の書物』概念である。それを日本語で表現しようと試みた。
簡単に言えば、不可能と知りつつも、その可能性を追い求めることができる時代があったのである。孝輔の時代、西の詩と思想は信じるに足るものだった。また日本語の表現可能性はまだまだ残されていた(少なくともほとんどの詩人がそう考えていた)。たとえ必敗の投機であったとしても、わたしたちは孝輔の詩業を現代詩の貴重な遺産として継承することができる。
眠りは新しい中心を探る
すでに軋みがきていた自堕落な世界の肋骨
告げられて久しい黙示のままに
墜ちるべきところにまで墜ちつくし
あらためて組み直されようとする日月の
平たい夢の彼方へと血がめぐるとき
どんな熱い意志が力を藉して
虚空にひとつの円形競技場を描きだすのか
執拗にからみつき脊髄を
突きあげてくるあまりにも刺々しい思い出の数々
けれども眠りは新しい中心を探る
くるまれるべき始原の肉の予感に震え
いまはまだ蒼白の骨と筋とで おのれの
未知の片割れを抱き寄せようと身構えながら
(『眠りは新しい中心を探る』全。『星夜/施術者たち』[一九八七年])
引用の詩篇『眠りは新しい中心を探る』は、典型的な〝現代詩書法〟で書かれている。基本は〝私〟の内面独白である。またなんらかの欠落(引用詩では『中心』の喪失と回復への希求)を巡って言葉が生み出されている。作品に即して説明すれば、『眠り』→『中心』→『肋骨』→『血がめぐる』→『円形競技場』→『からみつき』→『骨と筋』→『片割れ』といった、喩とイメージの連鎖で作家の内面が描写されている。
今ではあまりにも読み慣れた〝現代詩書法〟になってしまっているが、この書法を確立した一人は孝輔だと思う。孝輔の欠落意識は強靱なものだったからである。欠落は一つの観念である。詩人は失恋から世界原理の欠如までを主題として措定することができる。特定の観念ばかりでない。鮎川信夫や田村隆一らの戦後詩人の詩に表れているように、社会体制(状況)の喪失をも、詩人は一つの観念として措定できる。わたしは孝輔的現代詩書法を美しいと思う。なんらかの至高的観念(それは結局は欠落であるだろう)を直截に探求する点に、日本文学における自由詩の存在意義があるからである。しかしこの書法には限界がある。
多くの詩人は詩を書くに当たって観念的中心を設定する。中心を最初から到達不能な観念(欠落)に設定すれば、作品はある程度量産できる。様々な角度から不可知の観念を叙述すれば良いからである。ただいつまでも欠落に主題を置くことはできない。明確に主題を認識把握しなければ、結局は先には進めないのである。現代詩書法を援用する詩人の詩集が、処女作は斬新だが、二、三冊目はその変奏で、四冊目くらいから単調な繰り返しになってしまう理由がここにある。詩人は空虚のまわりを堂々巡りしながら言語的に衰えていくのである。
状況論やジャーナリスティックな言説として受け取られてしまうことが多いが、わたしは〝現代詩〟の時代は本当に終わったと確信している。西の思想の優位性や、東の言語での無限の表現可能性など、現代詩の時代には存在していたほとんどの要素と状況をわたしたちは既に失っている。一九六〇年代から八〇年代に活躍した詩人たちの作品を正確に批評すれば、それは誰の目にも明らかだと思う。
渋沢孝輔の詩の愛読者には、わたしの批評は乱暴で残酷かもしれない。しかしそうではない。わたしは孝輔詩を愛している。ただその愛は、孝輔の詩を愛誦することにはなく、その可能性と限界を正確に認識把握して引き継ぐことに向けられている。(了)
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




