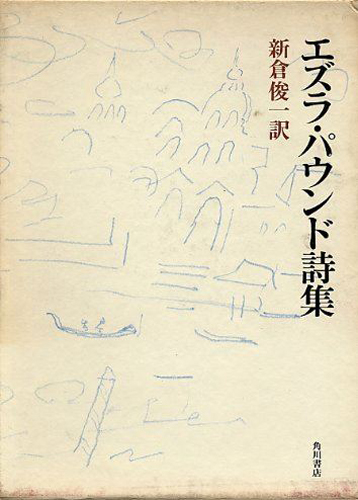
僕はしばらく前から詩は原理的に〝自由詩〟と定義すべきだと書いている。それはじょじょに詩人たちの共感を呼んでいると思う。しかし一部で誤解されているように、僕が主張しているのは詩を「自由詩」と呼ぶのか「現代詩」と呼ぶのかといった呼称の問題ではない。本質的には詩人の認識系の転換の問題である。今現在書かれている詩は〝現代の詩〟だから現代詩なのだといった議論は意味がない。過去はすべて〝今現在(現代)〟の積み重ねだが、これを定義とすると有史以来現代詩になってしまう。また現代は歴史概念でもあるが、文学では現代の起点をどこに置くかは明確に決められない。『新体詩抄』でも「荒地」派でもいいわけで、この思考パターンは何をやっても強弁に終わる。必要とされているのは「自由詩」と「現代詩」の可能な限り厳密な定義である。僕は原理として詩は〝自由詩〟だと認識しなければ、混沌とした現状を抜け出す道筋は見えて来ないと考える。
驚くべきことだが日本において詩の原理的定義は存在しない。正確に言えば最近まで存在しなかった。萩原朔太郎はやはり偉大な詩人で、彼なりに詩について考え抜いた『詩の原理』(昭和十三年[一九三八年])を書いた。朔太郎は「序」で「諸君がもしこの書物を一読すれば、すくなくとも翌日からして、詩の批判を正当にすることができるであろう」と記した。しかし朔太郎は詩を「内容論」と「形式論」に分けて論じ、結局は検討すべき問題を列挙しただけで終わった。『詩の原理』を読んで〝詩とは何かわかった!〟と思う人はいないだろう。むしろ検討すべき問題が増え、読む前より混乱するはずである。しかし朔太郎の『詩の原理』の原題が『自由詩の原理』だったことは留意してよい。〝自由な詩〟であるからこそ、朔太郎は詩を巡る驚くほど広汎な問題を検討できたのである。
歴史的事実として〝現代詩〟という呼称は戦前から存在している。モダニズムは日本やアメリカなどの文化後進国が、フランスを中心とした文化先進国の〝現代=モダン〟に追いつこうとした一連の文学運動である。二十世紀前半の日本の詩人たちが〝モダン(最先端の現代)〟という言葉(概念)に魅せられたのは当然であり、「現代詩」という名称の詩誌も刊行された。しかしもちろん戦前の現代詩と戦後の「現代詩」は質的に異なる。
戦後の現代詩は戦前のプロレタリア社会批判詩を引き継ぐ「列島」派や、思想詩の系譜を継ぐ同人誌「荒地」派の全盛期に、それらへの激しい反発として生み出された。具体的には同人誌「アモルフ」の入澤康夫と岩成達也が現代詩を創出した。彼らはほとんど過度なまでに言葉の意味(思想)伝達性を排除した。その結果とても難解だが、少なくとも当時は誰も読んだことのない純言語構造物的な新たな作品を生み出した。戦後の詩が誇って良い文学的成果である。
このアモルフ的現代詩の成果に、社会批判・思想詩系の詩人はもちろん、抒情詩人やプロレタリア系詩人など、資質は違っても新たな詩の表現を求める意欲的な若い詩人たちのほとんどが飛びついた。当時は〝言葉の関節を外す〟などという言い方もされたが、言葉の意味伝達性をひとまず無視すれば、無際限に新たな表現が可能になると思われたのである。詩の世界ばかりではない。現代詩的言語実験は、同時代の現代短歌や現代俳句にも多大な影響を与えた。
今も昔も俳句、短歌、詩の愛好者の比率はあまり変わっていない。現在では俳句愛好者が少なくとも五百万人、短歌がその五分の一の百万人強、詩の愛好者は恐らく短歌の十分の一の十万人を切るだろう。熱心な詩の読者は一万人いないかもしれない。にも関わらず現代詩が詩の世界のフラグシップとみなされたのは、現代詩が詩の世界全般の現代的表現を牽引する〝前衛〟だったからである。詩のジャンルを問わず、誰もが新たな表現を求めていた時代が確かにあった。
現在では短歌・俳句の世界では、現代短歌・俳句はすでに一定の役割を終えた文学運動だと認識されている。乱暴に言えば現代詩的前衛は、戦後日本の高度経済成長に呼応したかのような向日的で楽天的な言語表現探求運動だった。ただ無際限に新たな表現方法を生み出し続けることはできない。また新しさは時代によってその質を変えてゆく。現代俳句の時代を通過した俳壇は、その反動のように保守化を強めている。歌壇では新たに口語短歌が生まれた。表現技法面でも内容面でもわかりやすさを全面に押し出しながら、短歌の本質を再検討する動きである。これに対して詩の世界はいまだ現代詩に固執し続けている。
その最大の理由はポスト現代詩の姿がいっこうに見えて来ないことにある。また詩の世界全体のフラグシップであった〝現代詩〟という指標を手放せば、詩は短歌・俳句界に比べてとてもマイナーなジャンルになってしまうという詩人たちの恐怖もあるだろう。日本の詩のジャンルの中で、詩を特権的位置に押し上げていた基盤が失われてしまうのだ。しかし現代詩は、杓子定規に言えば思想的意味表現を重視する戦後詩と対立関係にあった。意味伝達性を棄却した現代詩と意味重視の戦後詩の両極が、戦後の詩の黄金時代を築いたのである。ほぼすべての詩人が田村隆一の死去によって戦後詩がひとまずの終焉を迎えたと認識している中で、一方の極である現代詩が生き延びることはあり得ない。
要請14:(詩作品の理解不能性、宣言)
(1) 詩的関係それ自体は理解し得るが、詩(作品)はそれのみでは理解し得ない。
(2) あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必要とする。
要請18:(詩的関係の意義、世界把握と書法)
(1) 詩的関係の意義は、言葉を介して新しい世界把握を(私達に)可能ならしめる点に求められる。
(2) 一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する。
(岩成達也『詩的関係の基礎についての覚え書き』平成八年[一九九六年])
現代詩を創出した「アモルフ」の詩人たちはやはり優秀で、入澤康夫は『詩の構造についての覚え書―ぼくの「詩作品入門」』(昭和四十三年[一九六八年])を書いた。その中で入澤は「詩は表現ではない」という一章を立てた。入澤の意図は「詩は日常言語のように意味を伝達するための手段(道具)ではない」ということにあったのだが、その詩作品での実践はともかく、入澤理論はいまだ不十分だった。詩の成立要件は意味内容なのか形式なのかという朔太郎以来の議論を越えて、初めてそれを原理的に定義したのは「アモルフ」のもう一人の雄、岩成達也だった。
岩成理論は意味内容にも形式(詩型)にも偏らない形式論理学である。詩は行分けでも散文でも小説のような物語でも、俳句や短歌を連ねた形式でもよい。形式的に完全に自由な表現芸術である。内容は詩的関係(いわゆるポエジー)が表現されている必要があるが、これは相対的で曖昧である。一つの意味を伝達しようとする日常言語の秩序を崩せば簡単に詩的関係が生じる。しかし何を詩的関係と感受し認識するのかは人や時代によって異なる。「青い/青い/青い」という言葉の羅列にポエジー(詩的関係)を感じる人もいるし、「あなたを愛しています」を「愛しています/あなたを」と表記すれば詩的関係が生じると感じる人もいる。つまり詩は詩的関係を含むが、詩的関係は厳密に定義できない。従って「詩的関係それ自体は理解し得るが、詩(作品)はそれのみでは理解し得ない」、「あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必要とする」ことになる。「関与者」は作家と読者を含む。作家がこれは詩作品であると宣言し、読者がそこに詩的関係を認めればあらゆる表現は詩作品として認知される。単純だがこれが自由詩の原理的定義である。
では日本文化には短歌と俳句という独自の詩型(定型)が存在するのに、一見、ほとんど無秩序な自由詩がなぜ必要とされるのだろうか。それについて岩成は、「詩的関係の意義は、言葉を介して新しい世界把握を(私達に)可能ならしめる点に求められる」、「一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する」と定義している。自由詩は世界が変容したときに、その変化を真っ先に感受し表現するための前衛言語芸術だということである。そのために形式・内容両面で完全に自由な表現である必要がある。実際、自由詩はそのような前衛芸術として推移してきた。戦前にはサンボリズム、モダニズム、シュルレアリスムといった最新思想を移入するアンテナ芸術だった。戦後も社会思想を鋭敏に表現する戦後詩を生み、その逆に意味や思想の影響を受けない純言語芸術的現代詩を生み出している。世界が変容した時に「新しい世界把握」を体現する「新しい書法」を創出できなければ、自由詩は日本文学におけるアイデンティティを失うだろう。このような自由詩をあくまで現代詩と呼ぶかどうかは好みの問題である。
これはとても書きにくいことだが、〝現代詩〟は詩のジャーナリズムを含む現実制度としても存在している。詩人たちが頭では詩を自由詩と定義した方がスッキリするとわかっていても、現実問題としてそれに強い抵抗を感じる理由はよくわかる。ささやなか告白をすれば、僕はどんな詩人よりも遙かに強烈に現代詩的思考フレームに囚われていた。そうせざるを得なかった。そこから抜け出すためには長い時間がかかり、また自分の退路を断つような乱暴な言説が必要だった。もちろん僕のような抜け出し方はおすすめしない。しかし未来のヴィジョンが見えず、先行作品の成果が参考にならない時には、詩を可能な限り原理的に捉える必要がある。
詩の専門家を自任する作家なら、ティピカルな意味でということになるが、現代詩が過去の戦後詩やモダニズム、シュルレアリスム詩と同質の、ある時代固有の詩の潮流であることがわかるはずである。問題を曖昧にしたままでは先に進めない。自由詩か現代詩かという呼称の問題ではなく、認識系の転換に関わるというのはそういうことだ。また現代詩の可能性は尽きている。新たな詩のヴィジョンを創出しなければその遺産は活かせない。
それから船に降りていき
砕ける波に船をつけて 聖なる海へ乗り出した
(中略)
やがて深い流れの果てのキムメリオスの地に
辿りついた その死者たちの町は
細かいくもの巣のような霧におおわれ
星々が空に満ちるときも 大空から見返すときも
陽の光はついぞ貫くことなく
ただ真暗な夜がそのみじめな人たちの上に広がっていた
(中略)
だが最初にエルベノールが現れた
(中略)
「不運と度を過ぎた飲酒のせいだ わたしはキルケーの館に眠っていたが
油断してながい梯子を踏み誤まり
控え壁のうちに落ち
首の骨を砕いて 魂は冥府に下った
だが王よ 嘆かれ葬られもしなかったわたしをおぼえて
どうかわたしの武具を高く積み 海の辺りに塚をつくりこのように刻んでください
〈不運にして ただ未来に名をもてる者〉
(中略)
つぎにテーバイの人ティレシアースが
黄金の笏をたずさえて現れると わたしを認めて語りかけた
「二度目とは ああ 不幸な星の男よ
なぜ陽の射さぬ死者と喜びなき地を訪れたのか
いざ この溝より退いて わたしに血潮を与え
予言する力を得させよ」
そこでわたしは退いた
やがて血を飲んで力を増し かれはこう語った「オデュッセイウスよ
恨み深いネプトゥースの手で暗い海を渡り
おまえはすべての部下を失って 故郷に帰るだろう」
するとつぎにアンティクレイアが現れた
安らかに眠るがいい ディーヴスよ
ウェルケスの店から一五三八年にホーマーを訳した
アンドレアス・ディーヴスのことだ
それからかれはセイレーンの傍を過ぎ そこから遠ざかって
キルケーのもとへと航海した
(エズラ・パウンド『詩篇』第一篇 新倉俊一訳)
パウンドの『詩篇』第一篇である。パウンドはある文学状況が安定している時代に生まれ合わせた詩人ではない。世界全体に激震が走る二十世紀初頭に本格的に活動を開始した。彼は初期の混沌の時代に新たな文学を創出した「発明者」であり、その手法を的確に組み合わせて作品を量産した「巨匠」でもある。ただパウンドが発明者であり巨匠でもあることに気づいた文学者は、彼の晩年に至るまでほんの少数しかいなかった。
『詩篇』第一篇を読めばわかるように、パウンドは自らを航海者オデュッセイウスになぞらえている。なぜか『オデュッセイア』第十一巻の、「死者たちの町」を訪れる箇所を選んだ。詩篇中にオデュッセイウスの部下で、キルケーの館で酔って不慮の死を遂げたエルベノールが現れる。パウンドはエルベノールの「不運にして ただ未来に名をもてる者」という言葉を、その後『詩篇』中で何度も繰り返すことになる。パウンドはオデュッセイウスと同様に「不幸な星の男」だったかもしれない。故郷アメリカに戻ったのは国家反逆罪の未決囚として精神病院に強制収容されるためだった。「暗い海を渡り」、すべてを失って故郷に帰ったのかもしれない。軟禁状態を解かれた後、パウンドはすぐにイタリアに赴きそこで没した。晩年の『詩篇』第百十五篇でパウンドは、「わたしの故郷では/死者が歩き回り/生きている人間はボール紙でできていた」と書いた。パウンドはダンテ『神曲』になぞらえて『詩篇』を百篇で終わらせるつもりだったが、それは破綻した。
『詩篇』第一篇は予言的だがそれには理由がある。パウンドは新たな文学の発明者だが、それは保守的文学者たちの間に数多くの軋轢を引き起こした。彼は伝統主義者であり、かつ本質的意味での反逆者でもあった。資本主義世界の牙城であるアメリカで、彼の利子嫌いが受け入れられるはずもない。パウンドが『詩篇』を書き始めたのは四十歳頃からである。草稿を読んだW・B・イェイツは、「なにをしようとしているのかわからない」と言った。『詩篇』はムチャクチャな作品である。ほかならぬ『詩篇』を読んでわたしたちは初めてこういう詩の書き方があることを知った。しかしそう簡単に人々に理解されるはずがない。中年を迎えていたパウンドには、『詩篇』と自身の未来が希望に満ちたものでないことは予想がついただろう。だが押し切った。詩人はそれでいい。
「安らかに眠るがいい ディーヴスよ」とあるように、『詩篇』第一篇の第一行目から六十七行目までは、アンドレアス・ディーヴスが一五三八年にホメロスの『オデュッセイア』をラテン語訳したテキストの英語抄訳である。『詩篇』は引用の織物でもある。パウンドの自我意識は強固であり希薄でもあった。パウンドは日本の能や俳句の知識を援用して、極端に自我意識を縮退させることができた。『詩篇』は具体物だけでなく、事件や思想を含む現実事象が縮退した自我意識に雪崩れ込み、そこに彼自身の強い自我意識が岩のように析出する構造を持っている。パウンドの詩法の基本は意識の流れにあったが、他者の意識を自己のものとして語り、過去の事件を今現在のように叙述することができた。このポリフォニックな方法はペルソナと呼ばれる。それは現代でも有効な方法だろう。
現代はもちろん将来的にさらに進行するはずの高度情報化社会フレームにおいて、個の思想は即座に相対化される。また情報は過去から現在に至るまで一瞬でデータベース化され、開かれたものとして共有されるようになる。優れた記憶力が知性の証であった時代は終わり、情報を秘匿し囲い込むことも難しくなる。反動は起こるだろう。しかし過去の文学神話そのままに特権的文学者像を演じ、神から選ばれたかのような霊感に満ちた詩人を演じるのは一時の悪あがきで終わる。
アポリアは文学においてこの社会フレームをどう総体的に捉えるかにある。またこのフレームが何によって統御されているのかを探ることにある。それが「一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する」ということである。神と呼ぼうと思想と呼ぼうと、高度情報化社会フレームには中心が存在しない。しかし世界は大混乱に陥ることなく調和を保っている。この調和総体には必ず求心点がある。それは従来の軸のような中心ではなく、陥没点のような負の焦点だろう。作家の自我意識の質的転換が必要とされ、作品のオリジナリティについても質的転換が必要とされるようになる。ペルソナや引用の織物が鍵になるかもしれない。
鶴山裕司
(了)
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


