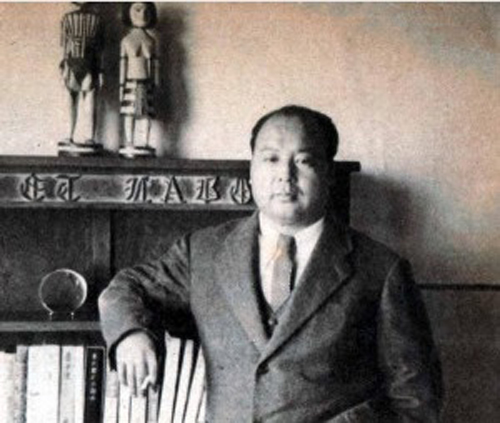
清水宏監督
東京の京橋に国立近代美術館フィルムセンターという施設があり、フィルムアーカイブとして映画の保存のみならず所蔵作品の上映も行っている。そこで現在「生誕110年 映画監督 清水宏」という特集が開催されている。清水宏という名前に誰しもが聞きおぼえがあるとすれば、それは相米慎二と異なり、あまりにもありふれた名前だからであって、相米慎二と同じく世界最高の「子供映画」を撮った監督としではないだろう(1月に『ションベンライダー』、『台風クラブ』、そして『お引越し』の相米慎二特集が行われ、その半年後に清水宏特集が行われている2013年は瞠目すべき年なのだ)。
もちろん、小津安二郎と同い年の清水は子供が主役の映画ばかり撮っていたわけではなく、松竹という大会社で大人が主役のメロドラマなども撮っていた監督である。しかし、ここではあくまで清水作品の子供を中心に書こうと思う。まずは、子供は遊ぶのが仕事という言葉に従い、「長編製作の合間に暇を見て撮影した」という『團栗と椎の実』を取りあげることにする。

『團栗と椎の実』より
この29分の短編の物語は、都会から山奥の田舎に養子としてやってきた子供(秋雄)が、地元の子供たちの遊びについていけず、だからといって家に帰ってくると養父に怒られて無理やり外で遊ばされ、それでも結局は女の子と遊び始める気弱な子を見かねた養父が、木登りを教えるというものである。この映画は、ジャン・ルノワールの『ピクニック』、また同じく子供を主題とするジャック・ロジエの『新学期』といった短編と同様に、全てが瑞々しく、的確で、さらに誰も予想していないほど徹底的に、人物の行動とそれが起こす波紋を描写している点において共通している。ルノワールがブランコの幸福と口づけの残酷さを、『新学期』が少年の蛇を使ったいたずらが巻き起こす混乱を徹底的に描き切ったのと同様に、『團栗と椎の実』では木登りが、その木の高さとともにあますことなく描かれている(後の『蜂の巣の子供たち』における登山シーンへと繋がるものだ)。木はどこまでのどこまでも天にとどくほどに伸びており、秋雄は養父の声に押され、木をどこまでもどこまでも登っていく。あたかも秋雄が登れば木も伸びていくようであり、地面が写されないせいか、観客もカメラが置かれた高さが分からず、ただ相当な高さであることが確信されるばかりで足がすくむ思いをすることになる。なにも木登りが出来るようになったという描写なら、ここまで高く登る必要もないはずだ。田舎の子供として少し成長した姿が示せればよいはずなのだ。したがって、この映画の主題とは子供の成長ではなく、木登りなのである。そもそも木を登る秋雄は、次にどこに手をかけ足を置くのかを考えるのに忙しく、自分の過去と今を対比して「成長したんだなぁ」などと悠長に考える暇など与えられていないのだ。
物語を超えた、このような「やりすぎ」の感覚は、その後の秋雄とガキ大将がけんかをするシーンでさらに顕著なものとなる。橋の上で取っ組み合いのけんかが始まり、地面に押し倒され馬乗りになられたかと思うと、逆転したり再び返されたりとどちらが勝つともいえない接戦となる。そしてついに秋雄が勝ち、降参してもはや元ガキ大将となった少年が泣きだす。しかし、秋雄は再び一発バシンと頭をたたき、さらにもう一発頭をたたく。この最後の二発は誰の目にもやり過ぎに映るだろう。負けた相手を容赦なくたたく秋雄の姿はただの乱暴者のようにも見え、観客を心配させるが、次のシーンではガキ大将となった秋雄が元ガキ大将の少年とともに協力して栗をとるのであって、私たち観客の心配は全くあたらないのである。それに周囲の子供たちはあれほどの「乱暴」を見たのにも関わらず躊躇せず秋雄についていくのであり、彼らの論理ではあれくらいはなんてことないらしいのだ。そして、あの二発無しでも物語は成立しえたのに、それでもなお二発を撮り、編集でも切らなかったこの映画は、あたかも子供が撮った映画のようであり、その意味でも「子供映画」なのである。
そして、この「やりすぎ」という点は、同年に撮られた『簪』にも見られる。この映画は温泉で簪が足に刺さり怪我をした笠智衆と、その落とし主の田中絹代の関係とともに、彼らを含めた旅館の宿泊客のやり取りで物語が成り立っている。中盤で笠智衆が歩く練習として、川面ぎりぎりの高さに渡された細い板の一本橋を、ぎこちなくこけそうになりながらも渡るシーンがある。彼はあと少しのところで転んでしまい、すると田中絹代が彼を助け起こして背におんぶして橋を渡り切るという、素晴らしいシーンである。しかし、このシーンの素晴らしさは女性が男性をおんぶするというアクションの独創性だけにあるのではなく、この一連のアクションを見守る子供が、その様子を岸辺で実況している点にも多くを負っている。オリンピックを実況するような少々「やりすぎ」な実況・応援が、ただ歩くという日常的であるはずのアクションに潜むスリルを最大限に引き出している。しかし、そればかりではない。田中絹代が岸にたどり着くと、同じカットに画面左から按摩が二人これ以上ないという絶妙なタイミングで入ってきて、今しがた二人が渡った橋を渡ろうとする。すると子供は目の見えない按摩が橋を渡るのを、笠智衆と田中絹代の時と同じように実況・応援するのである。つまり、子供は主役と端役の区別もつかず、「やりすぎ」てしまうのだ。むろん、子供にとっては川に渡された一本橋を渡ることがもつスリルに変わりはないのだから、実況・応援しない方が不自然なことなのだ。その結果として、物語の要請に応えるだけなら笠智衆の歩行練習と田中絹代との交流だけを描けばよいはずが、この70分しかない映画は先を急ぐこともなく、端役でしかない按摩を主役の二人と同等のものとして画面に導き入れるのである。さらにここでは、周囲の大人も笠智衆を心配するのと同等に按摩の歩みを気にかけ、「段差がありますよ」と声をかけている。つまり、この映画は70分の中で物語をどう完結させるのか心配するのではなく、画面の隅にいてしかるべき人物を画面の中央に据えて遊んでいるのだ。
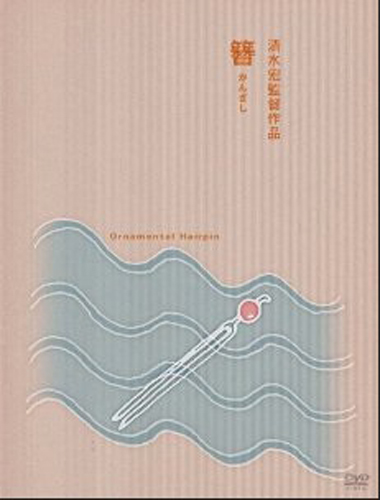
『簪』DVDパッケージ

『簪』より 田中絹代におぶさる笠智衆
「遊んでいる」ということは、これこそこの映画が真剣に果たした「仕事」なのだ。このような、語るべき物語からの「脱線」こそ、『簪』の主題とさえ言える。たとえば、田中絹代は、実は東京で愛人ないし遊女として金銭に不自由のない生活を送っていたことが暗示されており、彼女はそんな生活から逃れるために、温泉宿に滞在し続けるのである。したがって、彼女にとって温泉宿とは遊びの場であり、かつ人生の転機となるべく真剣に過ごされる場所なのだ。さらに東京から彼女を迎えに来た、同じ境遇にあるらしい女性との川辺でのシーンは特筆に値する。田中絹代は自らの東京での贅沢な生活を悔い、今の生活に生きがいを見出したことを彼女に言い終わると、田中絹代は取り込んでいた洗濯物に顔をうずめて泣き始めてしまうのだ。1941年という制作年を考えれば、「ぜいたくは敵だ」の標語が既に存在し、さらに前年には奢侈品等製造販売制限規則が公布されており、このシーンは「銃後の戦い」との関係もあるかもしれない。しかし、例えば晴々とした田中絹代の顔のアップでも撮っておけば、彼女の改心を通じて戦時下の観客に向けてのメッセージとなるかもしれないが、実際には田中絹代は泣きだすのであり、しかもその顔を洗濯物にうずめてしまって一切顔を観客に見せることがない。しかも、前景に泣く田中絹代を配したショットで、遠い背景から白い点が現れ、次第にこちらに近づいてくるに従い子供だと分かるような演出が行われている。このように演出することで、前景にいて物語的にも重要な田中絹代に観客が視線を集中させることを妨げ、前景から背景まで画面全体に観客の視線を浮遊させ、一瞬、物語から映画を脱線させるのである。

『蜂の巣の子供たち』より
そして、このような「浮遊」と「脱線」こそ、『簪』の登場人物が置かれた状況とぴたりと一致しているのだ。若々しい笠智衆がなぜ日中戦争下で温泉地に逗留しているのか、その理由は田中絹代の「お聞きしたの悪かったわね、もうお聞きしませんわ」という言葉通り、明示されることはない。田中絹代もその身の上がはっきりと示されることはなく、二人とも浮遊状態にあるのだ。特に田中絹代は家を失い東京にすら帰れないのである。
「家がないこと」。このテーマを引き継ぎ、清水宏は戦後も子供を演出し作品を作っていくことになる。しかし、その子供は戦前の子供とはやはり異なる位置にたっているだろう。戦争を通じて分かったことは、子供だけではなく、時に大人も派手に「やりすぎ」るということであり、その波紋のなかに実際に残された子供たちとともに、清水は蜂の巣三部作を作ることになるのである。蜂の巣三部作についてはここでは書かないが、是非スクリーンで“目撃”して頂きたい。この空前絶後の三部作を見るためにも、この夏、京橋にひと月くらい逗留して、スクリーン上に視線を泳がせてみるのもよいかもしれない。
玉田健太
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
