
60代の頃の吉岡実
ドジソン家の姉妹ルイザ マーガレット ヘンリエッタ
緑蔭へ走りこむ馬 読書をつづける盛装の三人 見よ寝
巻のなかは巻貝三個
*
C・パーカー牧師の娘メイは椅子の上へ立っている 靴
のまま この狼藉の恍惚 十二歳になったら飛びおりる
*
主席裁判官デンマン卿の娘グレース・デンマン 石の階
段の一番下が彼女の憩いの世界 重い大きな鎚で赤いカ
ニを一撃したら 恋する女の心にちかづく
(『ルイス・キャロルを探す方法』部分 『サフラン摘み』昭和五十一年[一九七六年])
『ルイス・キャロルを探す方法』は、昭和四十七年(一九七二年)に雑誌のキャロル特集のために書き下ろされた作品である。この詩篇について吉岡は「これは私の詩業のなかでも、独自性と新領域をきり拓いたものだった」(『高遠の桜のころ』)と自信に満ちた言葉を書き残している。内容は高橋康也らのキャロル関係の書物からの引用である。
吉岡の詩は再び絵画のような明確なイメージを結び始めている。ただ吉岡のイメージや観念は、もはや彼個人の想像力に限定されることがない。引用により他者=世界が作品に取り込まれている。少女たちは明確な個の輪郭を持ちながら、それぞれに異なる秘めた内面を読者に開示している。自動筆記的に世界を描写するのではなく、単純なら単純、複雑なら複雑のままの世界を直接作品世界に取り入れる方法が、『神秘的な時代の詩』を経て吉岡が見出した新たな詩法だった。
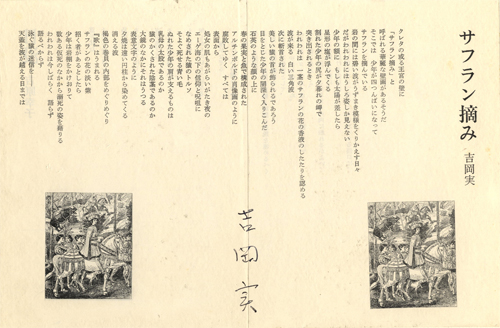
吉岡実サイン入り『現代詩手帖』1973年7月号『サフラン摘み』初出稿切り抜き(著者蔵)
吉岡には昭和三十五年(一九六〇年)にラジオ放送用に書き下ろした長篇詩『波よ永遠に止まれ』がある。中国は楼蘭遺跡の発見で有名なスヴェン・ヘディンの『中央アジア探検記』を下敷きにした作品である。引用の手法はこの作品で初めて試みられた。ヘディンの『探検記』を詩の土台にしたのは、当時は長い作品を書いておらず、かつ短期間での依頼に応えるための苦肉の策だった。また吉岡は『波よ永遠に止まれ』で『探検記』の内容を自由に変え、原書では前編に当たるタクラマカン砂漠横断部分だけを詩の素材にしている。ヘディンが渇死寸前でタクラマカン砂漠を渡りきり、オアシスを発見するまでの部分である。吉岡は未知の表現地平を希求していた当時の心境を、『探検記』に重ね合わせて表現したのである。
『神秘的な時代の詩』の苦しい時期に、吉岡が十数年前に書いた『波よ永遠に止まれ』の詩法をふと思い出した可能性は十分にある。ただ『波よ永遠に止まれ』と『サフラン摘み』の引用の詩法は質的に異なる。吉岡は思いつきではなく、強い確信を持って新たな引用の詩法の可能性を探求し、確立している。
優雅な命のこと切れるような日没の
観念の枠から外れる
関節の地平へ
言語から舞踏へと景色を替え
「赤子の頬にふれる
網の目から
わたしは何を覗けばよいのか
カモイの塵
くびれた茄子の尻
蛸の吸出しが吸い出したもの
それとも抽象された線
愛」
器物へのなかま入り
を了へるために
「わたしは寝床にまんじゅうを引き入れる」
(『聖あんま語彙篇』Ⅰ部分 『サフラン摘み』)
『聖あんま語彙篇』は暗黒舞踏の始祖・土方巽の言葉の引用から構成されている。カッコで括られた部分が土方の言葉である。土方は決して経験を超える動きができない肉体に苛立つかのように、稽古中に数々の奇妙な言葉を発した。またニジンスキーに代表されるヨーロッパのバレー・ダンサーたちが、究極的には神の舌に触れるために人間離れした跳躍を試みたように、土方は日本文化の根底的観念(神々)と親しむために、人間以下の動物や虫に憑依し肉体を変容させることを切望した。それが土方が創始した日本独自の暗黒舞踏の根幹思想である。吉岡には『土方巽頌─〈日記〉と〈引用〉に依る』(昭和六十二年[一九八七年])がある。他者に捧げた吉岡唯一の散文集である。晩年に至るまで土方は吉岡の良き友人であり、詩の発想の源だった。
『聖あんま語彙篇』で吉岡の詩法はその急進性を一気に加速させている。『ルイス・キャロルを探す方法』で吉岡は、引用を自らの言葉に置き直していた。しかし『聖あんま語彙篇』では他者の言葉がそのまま引用されている。詩法が短期間で間接引用から直接引用に変わったのである。それは詩が「観念の枠から外れ」「器物へのなかま入り」をするための方法だった。直截な他者の言葉の引用により、吉岡の詩はその言語的硬質性を増し、より多面的読解が可能な作品になっている。
私はそれを引用する
他人の言葉でも引用されたものは
すでに黄金化す
(『楽園』冒頭 『夏の宴』昭和五十四年[一九七九年])
詩集『夏の宴』冒頭の詩行は、吉岡による新たな詩法の勝利宣言である。吉岡の引用の詩法の特徴はその直接性にあった。創作であろうと批評であろうと、多くの作家は自己の思想や観念を補足的に説明し、その正当性を強化するために他者の言葉を引用する。そのような作家の場合、原則として引用部分を除去しても作品は成立する。引用以外の部分で作家の思想や観念は既に十全に表現されているからである。
しかし吉岡の引用の詩法は異なる。吉岡は他者の言葉をできるだけ生のまま作品に取り込んでいる。自己とは明らかに異なる他者の思想・観念、イメージを丸のまま作品に配置している。それはパッチワークのような引用の織物である。そして吉岡は、これこそが現代を捉えるための決定的詩法だという確信を抱いていた。ほとんどランダムなまでに他者の言葉を取り入れ、取り合わせ、それにより鏡のように世界を表現する作品世界が吉岡が把握した現代的詩法だったのである。
吉岡の引用の詩法は、『静物』から『静かな家』までの自己の言葉で世界を描写する方法や、『神秘的な時代の詩』の現代風俗をなぞる方法とは対局にある。『サフラン摘み』や『夏の宴』では、『静物』から『神秘的な時代の詩』で表現されていたような現代風俗の描写が消えている。むしろ作品は古典的相貌を深め、現代から退行したような印象を与える。しかしそこにこそ吉岡が掴んだ新たな詩法の根幹があった。吉岡はもはや次々に現れては消えてゆく現代風俗や流行思想を追おうとしない。吉岡の興味は現代を含め、日本文化が有する根底的構造を表現することに向けられている。
わたしが心から求めているのは
打ち付けられた夥しい釘と
生皮を張った堅い板
「不滅の傷痕」そのもの
(『不滅の形態』冒頭 『サフラン摘み』)
暁の丘へ
のぼる若い女を見たことがある
二股の美しい尾をかざし
〈還元不能〉な言葉を求めているようだ
(『サイレント・あるいは鮭』部分 『サフラン摘み』)
『サフラン摘み』にはしばしば、曖昧であやふやな言語では表現しにくい、ある決定的で「還元不能」な「傷痕」を求める詩行が表れる。そしてこの拭っても拭っても消えず、それを見るたびに常に鈍い疼きを想起させるような「傷痕」は、もはや人々の耳目を大きく惹き付ける現代的事件や事象に求められることがない。「傷痕」は引用の詩法の構造、あるいは引用の詩法によって作り上げられた作品世界自体が表現するものである。それはジャック・デリダが表現した『シボレート』と同義である。そしてこのような詩の指向に沿うように、吉岡の作家主体の位相が大きく変容している。
あけぼのの横雲の下で
青草はおびただしい蛍を生む
自己か他者
「いずれかが幽霊である」
(『野』部分 『夏の宴』)
『サフラン摘み』の最後に置いた詩篇『悪趣味な内面の秋の旅』の末尾を、吉岡は「「われわれは本当に自己の身体のなかに収まって/いるのだろうか?」/旅する者はわが心に問う」で終えていた。『夏の宴』ではそれが、「自己か他者/「いずれかが幽霊である」」という認識に定着する。吉岡はもはや作家主体の絶対性にこだわっていない。引用の詩法を実践することで、当然のように作家主体の存在格の縮退・希薄化への道を探っている。それは驚くべき出来事である。
一九八〇年代に隆盛を極めたポストモダニズム哲学は、言うまでもなくモダン(この場合は近代)哲学の批判運動だった。デリダに代表されるポストモダニストたちは、近代哲学の基盤であったヨーロッパ的イデア(ギリシャ的イデア、あるいはキリスト教一神論的神概念)を批判・解体(脱構築[デコンストラクション])することで新たな世界認識を得ようとした。このポストモダニズム思想が、八〇年代以降の世界的高度情報化社会の到来に正確に対応しており、人間の力による自然の制御からエコロジズムによる共存、あるいはインターネットによる情報と知の組み替えに至るまで、幅広く現代的事象の基本思想となり得るものだったことは言うまでもない。
吉岡の作家主体の縮退・希薄化指向は、このポストモダニズム哲学の本質に極めて近似している。ヨーロッパ的イデアの脱構築(デコンストラクション)は、当然、神の似姿である人間(作家)主体の存在格の解体にまで至るからである。ドゥルーズ=ガタリの「器官なき身体」を想起すればよい。同じくドゥルーズ=ガタリが示唆したように、無限の織物のようにリゾーム状に絡まりもつれ合う思想・観念・事物の綜合体である世界認識モデルに、もはや神のような中心概念はない。人間はそのような世界を総体として把握するか、基本的には無限に存在するリゾームの突出点の一部を自己の思想として限定把握するほかないのである。吉岡の作家主体の縮退・希薄化は、言うまでもなくこのようなポストモダン的世界モデルを総体把握するためにある。
また日本では高度な知的ゲームでもあるポストモダニズム哲学の脱構築(デコンストラクション)手法ばかりが注目されるが、それは本質的には神に代わる新たな求心点を激しく希求している。それはまだヨーロッパではデリダの「シボレート」といった形で曖昧に示唆されているだけだが、吉岡の引用の詩法と作家主体の縮退・希薄化は、そのような求心点=「傷痕」を直截に指向している。
吉岡は戦後の処女詩集『静物』冒頭の表題作で、「夜の器の硬い面の内で/あざやかさを増してくる/秋のくだもの/りんごや梨やぶどうの類/それぞれは/かさなったままの姿勢で/眠りへ/ひとつの諧調へ/大いなる音楽へと沿うてゆく/めいめいの最も深いところへ至り/核はおもむろに存在する」と書いていた。詩法は変わっても吉岡文学の本質は全く変化していない。現代世界が引用のパッチワークとしてしか表現できないとしても、そのリゾーム状の世界が全体として「ひとつの諧調」を保っている以上、世界内に「核はおもむろに存在する」のである。
女の子が生まれた
(不可解なものは何もない)
地上は常に明るく
キリギリスが三匹死んでいる
母はトウモロコシの種子を播き
父は大木を伐り倒す
燃える夕日のなかで
それはしばしば(絵画)に似ている
しかし(生成変化)をくりかえし
人間は(白骨)と化す
(『春思賦』冒頭 『薬玉』昭和五十八年[一九八三年])
『薬玉』について吉岡は、「私は遅まきながら、『古事記』や柳田国男『遠野物語』や石田英一郎『桃太郎の母』などの「神話」や「民間伝承」に、心惹かれるようになった。私のもっとも新しい詩集『薬玉』は、それらとフレイザー『金枝篇』の結合に依って、成立している」(『白秋をめぐる断章』)と書き残している。また「この詩集は今までの作品とは詩形が異り、ことばの塊をいわば「楽譜」のように散りばめた、いってみれば「言譜」のようなもの」(『くすだま』)だとも書いている。
補足しておけば『薬玉』のタイポグラフィックな詩型は、二〇世紀初頭のアメリカ・モダニズム詩を代表する詩人、W・C・ウィリアムズの長篇詩『パターソン』から発想を得たものである。ウィリアムズは詩行が徐々に下がってゆく段連詩の形で『パターソン』を書いた。吉岡はそれを援用して独自の詩型を編み出している。頭揃えの詩では前後の詩行に意味やイメージがかかってしまうが、詩行を段型に並べることで意味やイメージの連鎖を断ち切り、ブロックごとにより明確な言語的イメージを想起できるようにしたのである。また垂直に下降する詩型はある求心点=核を指向する吉岡の姿勢を表現している。

自宅での吉岡実。壁の絵は片山健作の詩集『サフラン摘み』のカバー画
『サフラン摘み』や『夏の宴』で、吉岡は様々な文学作品から言葉を引用していた。しかし『薬玉』では初めて引用の原典を絞り込んだ。『古事記』や『遠野物語』、『金枝篇』といった、神話と民俗学を巡る他者の言葉が詩集全体に散りばめられているのである。それに伴い『薬玉』の言語表現は、『サフラン摘み』や『夏の宴』とは比較にならないほど一貫しながらも豊饒さを増している。詩では通常使えないような言葉が頻出しているのである。ただ『薬玉』で最も重要なのは作家主体である。『薬玉』では引用原典の言葉が持つ呪力に促されるように、吉岡の作家主体が再び微妙に変化している。
「女の子が生まれた/(不可解なものは何もない)/地上は常に明るく/キリギリスが三匹死んでいる」という『春思賦』の冒頭は、意味的には決して難解ではない。しかしそれは読者の心の中にいわく言い難い不安感をかき立てるだろう。吉岡が描いているのは隅々まで明るく照らされた現世世界である。女の子が生まれ、キリギリスが死に、母は種を撒き父は木を切り倒す、まるで「絵画」のような日常的風景である。具体的な言葉とイメージを用いながらも、現世世界が極度に抽象化されて表現されていると言っても良い。そして人間はそのような「生成変化」を繰り返し「(白骨)と化す」。それは人間の必定であり謎はない。だから読者が不安を感じるのは、詩篇の内容ではなくその書き方に対してである。作家主体の視線が余りにも冷徹なのである。
簡単に言えば吉岡は、神話や民俗学のテクストを引用することで、その作家主体の位置を、人間の生死を支配し、人々の暮らしを残酷なまでの視線で見透かす神に近い位相に変化させている。
『薬玉』には、「起りうることが起るならば/起りうることは起れ/起り得ないことが起りえないならば/起りえないことは起るな」(『巡礼』)、「岩が声を発す/時まで待てよ/それが永遠であれば/永遠に」(『天竺』)、「生きている限り/人等よ/((時空)と(謎)に身をまかせよ)」(『落雁』)といった、有限な肉体を持つ個の認識では表現し難い言葉が頻々と表れる。『薬玉』で吉岡は、ほとんど神に憑依して詩篇を紡ぎ出している。そして『薬玉』でのこのような吉岡の視線は、徐々に一つの焦点へと収斂してゆく。「聖家族」の肖像である。
菊の花薫る垣の内では
祝宴がはじめられているようだ
祖父が鶏の首を断ち
三尺さがって
祖母がねずみを水漬けにする
父はといえば先祖の霊をかかえ
草むす河原へ
声高に問え 母はみずからの意志で
何をかかえているか
みんなは盗み見るんだ
たしかに母は陽を浴びつつ
大睾丸を召しかかえている
万歳三唱
満艦飾の姉は巴旦杏を噛む
その内景はきわめて単純化され
ぴくぴくと
肛門は世界へ開かれている
真鍮の一枚板へ突き当り
死にかかっているのが
優しい兄である
かげろうもゆる春の野末の暗がり
蕨手のように生えてくる
それがわが妹だ
だれだって拍手したくなる
家系の序列ととのえ
二の膳 三の膳もととのう夜
ぼくは家中をよたよたとぶ
大蚊をひそかに好む
青や黄や紅色で分割された
一族の肉体の模型図ができ上る
その至高点は今も金色に輝く
神武帝御影図
嗚呼 薬玉は割られ
神聖農耕器具は塵芥にうずもれて行き・・・・・・
(『薬玉』Ⅰ 『薬玉』昭和五十八年[一九八三年])
引用は表題作の前半だが、そこに表れるのは「祖父」「祖母」「父」「母」「姉」「兄」「妹」による「祝宴」であり、日本的な「一族の肉体の模型図」である。祝宴は祖父が鶏の首を落とし、祖母は鼠を水に漬けて殺し、母は恍惚として大睾丸を抱え、姉は肛門を世界に向けて開いているといった猥雑で滑稽なものである。しかしこの現世的な生と性、生と死に彩られた聖家族の「模型図」は一つの「至高点」へと向けられている。「神武帝御影図」である。古い農耕民族の末裔である聖家族の「神聖農耕器具は塵芥にうずもれて行」くのである。
言うまでもないことだが「神武帝御影図」や「神聖農耕器具」は存在しない。詩篇は一つのフィクションである。しかし吉岡が詩篇で描いたのが、彼が神的存在に憑依して捉えた日本文化の原理的言語像であることは確かである。それは天皇の起源にまで遡っているが、国粋主義とは全く異質の猥雑な日本文化の原像である。そしてこのような詩篇は日常的な思想や観念に立脚する作家主体の位相からは決して生み出せない。単に他者=世界を作品世界に引用するだけでなく、その本質を作家主体が実存的に生きることなくしては表現不可能である。
その意味で吉岡が『薬玉』で切り拓いた言語表現地平は、今でも新しい。そこには特権的で全能な個の作家主体の位相から世界を認識するモダニズムとは対局の方法がある。作家主体の内実をできるだけ空虚に保ち、そこに生(なま)の世界を取り入れ、それを足がかりに一気に世界本質を掴もうと試みる方法である。この意味で吉岡の詩法は、恐らく二十一世紀のポストモダニズム文学の原理的方法論を先取りしている。
「ヘアードライヤーで
早くかわかしなさい」
これがぼくの(作品)の形姿?
(水車の水受板)
水をかぶったり 廻ったり
「兄の寂寞を
妹が慰める」
(ハーベスト・ムーン)
(秋の満月)
「眠れるものなら
とっくに
眠っているよ」
(『寿星(カノプス)』5 『ムーンドロップ』昭和六十三年[一九八八年])
最後の詩集になった『ムーンドロップ』で、吉岡は再び苦悩を深めていた。過渡期の詩集である『神秘的な時代の詩』と同様に、作品には「ぼく」や「わたし」の一人称が頻出し、クエスチョンマークが表れる。「「眠れるものなら/とっくに/眠っているよ」」という詩行に明らかなように、吉岡は眠れない夜を過ごしている。吉岡は自己の作品に懐疑を感じておりその言語的達成に決して満足していない。
『ムーンドロップ』が満足のゆく作品に仕上がらなかった理由の一つは、吉岡がこの詩集で『薬玉』のような魅力的原典を措定できなかったことにある。吉岡は「ぼくの構想する(作品)は/複雑な媒介が必要だ」(『寿星(カノプス)』)と書いている。『ムーンドロップ』には『薬玉』のような「複雑な媒介」が欠けているのである。
ただ吉岡は繰り返しを避け、『ムーンドロップ』ではあえて『薬玉』のような「媒介」を設定しなかったのだとも言える。『ムーンドロップ』には「絵画」という言葉が頻出する。「(すべて[絵画]とは/不透明なるものに/依存した/[透明]なものなのだ)」(『晩鐘』)、「[メティエ]がそのまま/[思想]であるところの/[絵画]」(『銀鮫(キメラ・ファンタスマ)』)と吉岡は書いている。
吉岡は『ムーンドロップ』で『薬玉』の詩法を援用しながらも、必ずしも引用原典の力に頼らない「絵画」のような作品を希求していたのだと言って良い。吉岡に今しばらくの時間が残されていたならば、引用の詩法の勝利宣言を行った『夏の宴』のように、『薬玉』詩法を自在に援用して作品を量産できたかもしれない。ただその可能性は永遠に失われた。わたしたちは吉岡が切り拓いた豊饒な詩の実りの、さらにその先を行かねばならない。(了)
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




