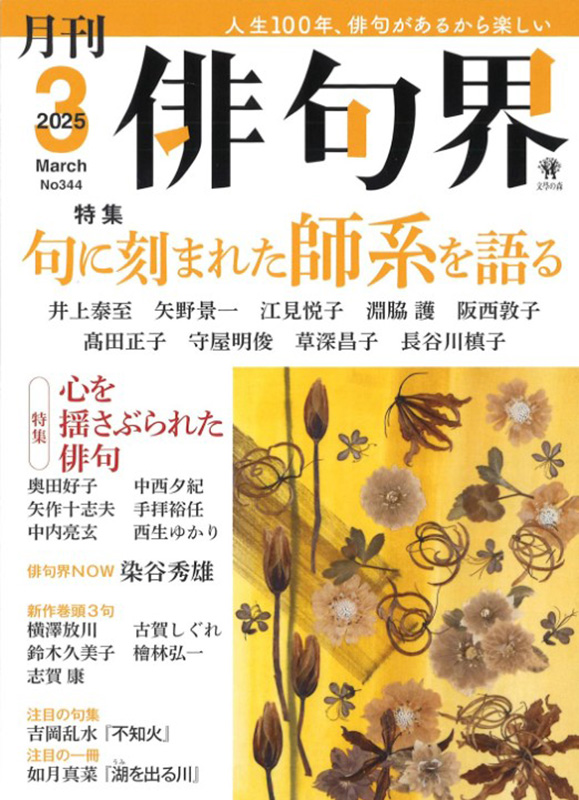
んー、正直言って、句誌時評はなかなか書きにくいな。なんか町内会の回覧板を読んでるみたい。町内の住民にとっては必要な情報なんだろうけど、違う町や村の人にとってはあんまり関係ない。逆に言えば違う町や村に住んでいても、「ん」と立ち止まってしまうような作品や評論が載っているのが理想なわけだ。それを広い広い俳句の世界から吸い上げて拡声器的に外の世界に向けて紹介するのが商業誌のあらまほしき姿、ということになりますな。
しかし広い広い俳句の世界を見渡してもたいした動きがなければ商業誌だって手の打ちようがない。一ヶ月とか二ヶ月前に依頼されて書く10枚前後の評論は埋め草書き飛ばし原稿なわけだから、一年二年とかをかけた腰を据えた仕事がどんどん出てくれば、少しは盛り上げようがある。広い広い俳句の世界が凪いだ海のように平穏無事で、昨日と同じ今日と明日が続いているならどんな商業誌だって山場を作りようがない。
本稿は二〇二四年度に出版された評論・作家論・作家研究・評伝などの著作と、俳誌や紀要などに掲載された論考類を対象とする。
まず「評論展望」の範疇にこだわらず、二〇二四年にいろいろ考えさせられた事柄の中で、主なものに触れておこう。
一つ目は、十数年前から『昭和俳句作品年表』(現代俳句協会)の編集委員の一人として昭和初期から昭和の終焉までの秀句を収集する作業を通して見えてきた俳人の句業の厚みや秀句の新風や燃焼度についての感慨。山口誓子・中村草田男・渡邊白泉・富澤赤黄男らが斬新な新風を確立した戦前。飯田龍太・金子兜太・鈴木六林男・高柳重信らが独自の新風を確立した昭和二、三十年代。この二つの世代の俳人たちの句業はぶ厚く、新風の燃焼度は高い。四十年代を中心に加藤郁乎・阿部完市・河原枇杷男・安井浩司ら「第四世代」(昭和一桁生れ)が燃焼度の高い新風を示したが、世代としての句業のぶ厚さは前の二つの世代より薄いだろう。六十年前後には戦後世代が清新な新風で登場したが、句業の厚みと幅は縮んだように映る。つまり、世代が現代へと下るにつれ句業の厚みが先細っていくというのが率直な感慨だ。安井浩司亡き後、俳人たちの念頭には乗り越えるべき俳人として誰が想定されているのだろうか。
川名大「2024年評論展望 まだ見ぬ俳句/世界俳句の多様性/評伝的作家論」
川名大さんが「2024年評論展望」で、二〇二四年中に発表された評論・作家論・作家研究・評伝などの中からめぼしい作品を批評しておられる。川名さんは腰を据えた仕事をなさる方だが「2024年評論展望」などの小文は、言ってみれば掃除当番のようなもの。誰がやってもいいわけだが川名さんなら安心というところ。公平な方ですからね。
で、川名さんは俳句研究者であり創作者ではない。特定の作家や結社、流派に偏ることを避けて客観的に、特に昭和俳句の歴史や仕事の意義を丹念に資料にあたって発表しておられる。研究者なら当然の姿勢でそれは倫理的立場だとも言える。俳人は優れた俳句を書こうと努力するのはもちろん、俳句の将来に責任を負っている。商業句誌に作品や評論を発表し、結社で俳句初心者を指導しメディアで俳句選者や賞の選考委員を務めるというのはそういうことだ。ただ川名さんの著作を読んで俳人が、それをどのように自己の作品や俳句の未来に活かすのかは作家次第。研究者だから「こっちだよ」とはお書きにならない。
ただそうは言っても川名さんも人間である。「2024年評論展望」の冒頭で、昭和六十年代以降にはめぼしい俳句の成果は現れていない、「世代が現代へと下るにつれ句業の厚みが先細っていくというのが率直な感慨だ」と書いておられる。戦前や昭和二、三十年代の俳人たちの仕事に比べ、「(昭和)四十年代を中心に加藤郁乎・阿部完市・河原枇杷男・安井浩司ら「第四世代」(昭和一桁生れ)が燃焼度の高い新風を示したが、世代としての句業のぶ厚さは前の二つの世代より薄い」と書いておられるが、「安井浩司亡き後、俳人たちの念頭には乗り越えるべき俳人として誰が想定されているのだろうか」とも批評しておられる。川名さん、珍しくちょっとだけ〝振り込み〟ましたね。
俳句界には今だって中堅・長老と呼ばれる俳人がいらっしゃる。俳句商業誌で活躍しておられるのはもちろん、大手新聞の投稿欄選者や、有名俳句賞選考委員などのお歴々だ。そういった先生方の「句業の厚みが先細って」いると言ってしまうと失礼に当たるから誰も言わないわけだが、まあホントのことですね。
文学の世界は年功序列ではない。もちろん小説、短歌、俳句、自由詩などの世界にはいわゆる〝壇〟というものがある。そこで要職を務める人材はいつの時代でも必要だ。しかし優れた作家だから壇の要職についているとは言えない。要するに掃除当番。できれば公平で人間味のある方に要職を務めていただきたいが代わりはいくらでもいる。
創作者は創作を始めた当初、ほとんどの人が優れた作家になりたいと願うものではないかと思う。俳句なら芭蕉、蕪村、子規らに肩を並べるような作家になりたいのではなかろうか。しかしじょじょにモチベーションが落ちてゆく。俳壇で小さな役職を与えられ中くらいの仕事を任され、大結社の要職や大新聞の投稿欄選者に納まればそれでアガリになる。川名さんが書いておられる通り、昭和六十年代以降の俳人の仕事にはほとんど見るべきものがない。もう四十年近い不作だ。どうしてそうなったのかと言えば、要するに志が低い。みっともないほど足掻くことすらしていない。そうでなければこんなていたらくにはなっていない。
安井浩司を「乗り越えるべき俳人として」「想定」している俳人などほとんどいないと思うけど、彼は創作ノートに、
俳句に伝統というものは無い。伝承のみだった。俳句は芭蕉をもって完成され、終熄したのである。従って、厳密には、僕らは俳人でなかったのかもしれない。あるいは俳人の幻影を背っているにすぎないかもしれない。
と書いている。その通りなんだ。俳句を書くなら俳句について原理的に考える必要があるけどそれができていない。安井が書いたように、極論を言えば俳人たちは飽くことなく芭蕉ただ一人の俳句を伝承している。
「俳句は芭蕉をもって完成され、終熄した」というのは事実である。この完成・終熄は実に単純で恐ろしいものだ。ほとんどの俳人が芭蕉全集を通読したことがないだろう。蕪村、子規全集などはさらに縁遠いのではないか。歳時記をこねくりまわしてどう俳句を書こうかと思案している俳人が99パーセントのはずだ。小手先の技術を見よう見まねで真似するだけで、俳句について本腰を入れて勉強する必要がないということである。もっとわかりやすく説明すれば、俳句は芭蕉「古池」一句を知っていれば誰でも書ける。心敬でも宗祇、貞徳宗因西鶴季吟でもいけない。芭蕉「古池」一句で必要十分。決定的なのだ。
単純な話だ。自分の足もとを見て、手の平をじっと見つめればそこに答えは書いてある。現世の俳壇雑事に浮かれるのは大いにけっこう。誰だって身過ぎ世過ぎは必要だ。ただ真摯な俳句作家なら、一人になった時に俳句に絶望しない方がおかしい。俳句は何をやっても変わらない。名句を書くなど奇蹟的なことだ。だが不可能を可能にするためにはまずそんな俳句に絶望する必要がある。まあこんなこと書いても誰も耳を傾けないでしょうけどね。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


