 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
二六、森の女
「文字のなかだけでの殺人。物語のリアルにはふれない、文字の塊のレベルでの殺人ってこと?」
「そう。だから、実際には恭助の死体はない。三四郎が野々宮の家で見たような、『右の肩から乳の下を腰の上までみごとに引きちぎって、斜掛の胴を置き去りにしていった』というような列車事故の損傷もないし、ナイフと包丁で刺された傷もない。ただ、『誰かに背中を刺された。それ自体は大した傷ではなかったのだが、逃げようとして線路に落ちて、轢死した』という文字だけがそこにあることになる」
「いるけどいない、いないけどいる存在だから、殺されているけど命を失ったわけではない、死んでいるけど死体ではないというおかしな状況になってるってこと?」
「うん。でも、文字の上では確かに死んでるわけだけどね」
「変な殺人ね」
「確かに変だけど、でも、それが一番説明としてしっくりくるんだ」
「どうして、しっくりくるわけ」
「物語の構造を考えたらそう思えるんだよね」
「ああ、例の二つの中心ってやつ?」
「そうだ。こうすることで何が変わると思う?」
結局、これが俺が犯人像を絞り込む際の一番大きな手掛かりになった部分なのだ。作品内の構造を最小の一手でゆるがす手段は何かということ。実際には血を流さず、仮想の死、象徴的な死、あるいは偶像破壊的な一手で作品内に一つの革命をもたらす手段。それを突き詰めていくとこの答えしかなかったのである。
「広田ー原口ー野々宮ー美禰子ーよし子ー(与次郎)というラインを、三四郎には見えないところで束ねていた中心が消えるってことかしら」
「そうなるよね。そうするとどうなるかな?」
「物語的には、与次郎を媒介として、三四郎がこれらの登場人物とつながりをもったわけだから」
「そう、今度は三四郎が関係性の中心に居座ることができるようになる」
「関係性が組み直されるわけね」
「しかも、その三四郎の背後には九州というかくれた中心がある」
「東京を代表する恭助によって束ねられていた人間関係が、九州を中心に再編されるってことね」
「それだけじゃないんだ」
「恭助やその友人の金縁眼鏡は法科の出身だっただろ。明治時代において、法科出身者というのは、主として官僚だったわけだよ」
「官僚もしくは実業界よね」
「つまりは、帝国主義化していく日本、広田先生のいうところの憲法が発布された明治二十二年以降の日本を担っている層ってことになるわけだ」
「なるほど、それに対して九州はその逆なわけよね。中心に対する周縁であり、権力者に対する庶民であり、さらにいえば母親とお光さんだから男性に対する女性でもあるわけね」
「そう、アフラ・ベーンの話を思い出すならば、肌の黒い九州人たちは、白人に対する黒人でさえある」
「恭助の死因が轢死じゃなきゃいけなかったのも、それと関係あるのかしら」
「そりゃあそうさ。国家を縦断し、兵士や武器などを輸送して戦争を支えた鉄道は、帝国主義を象徴するものだったわけだろ」
「軍事国家を支えているものだったわけね」
「でも軍国主義は当然ながら、国民の犠牲の上に成り立つものだ。それを象徴するのが、その戦争によって夫を亡くし、社会に居場所を失った戦争未亡人たちの鉄道自殺だった。鉄路に身を横たえて鋼鉄の汽車の轍に身を引きちぎらせる行為は、まさに帝国主義による蹂躙に対する身体を使っての告発だったということになる」
「なるほど、彼女たちが恭助を轢死による死へとおいやったのは、単に轢死した女性への共感と義憤からじゃなかったってことね」
「そうだね。帝国主義に『生身で』蹂躙されることの痛みを、教えるという意図があったことになるわね。何しろ恭助は死ぬけど本当に死体になるわけじゃないから、象徴的に帝国主義体制に対して一つの教訓を与えようという意図があったことになるのかもしれないね」
つまり、恭助を中心とするネットワークと、三四郎を中心とするネットワークというのは、単なる二つの中心ということではなかったということ。作品の根幹的なテーマと密接に絡み合う、地理的、権力的、階級的、性的、さらには人種的な関係性の対比であったということなのだ。三四郎が、三と四との間に分裂していた理由も、この二つのネットワークの狭間で揺れていたという「迷羊」性とつながっていると俺は思う。

でも、それだけじゃない。
「さらにいえば、与次郎はどうだろう」
「撰科生ってことは裕福な家庭の出ではないってことよね。自分の家も借りられずに広田の家に居候するしかないわけだし。学歴的にも、将来的にも高いところは望めない。東京にいながら、その東京の上層には近づけない存在ってことよね。三四郎が体現しているような無自覚な権力に、最初から閉め出されている存在でもあるってこと」
「協力する動機は十分ってことね」
「そう、これはある意味でひとつの革命なわけだよ。そして、与次郎が、その革命の線を引いたということ」
そうなのだ。二つのネットワークの間を自由に行き来できる与次郎だが、彼自身は最初から、恭助ネットワークの一員とみなされてはいない。こちらのネットワークからはあらかじめ締め出されている存在なのである。与次郎が、三四郎に近づいた理由も、三四郎が、もう一つのネットワークを持っていて、それが自分の置かれている社会的境遇と近いものだったというところにあったからという可能性もあるというわけだ。
「すごく見えにくいしわかりにくいけどね」
「反聖文らしいわね、たしかに」
そう、彼らはやはり壊滅してなどいなかったのだ。俺にわざとゴミ箱の中に潜らせて、原文破壊ウイルスの脅威を見せつけてから、このテロに及んだ。つまり、やつらは俺たちに挑戦状をたたきつけたということだ。つまり、戦いの火蓋は、まだ切られたばかりだということ。
そして、ここに至って、俺の脳裏に、もう一枚の絵が浮かび上がってきた。
「こうして、『森の女』という絵画に関しても、図と地の反転がみごとに成し遂げられることになるんだ」
「え? 『森の女』って、二枚あったかしら」
「うん、あるじゃないか、ほら」
俺は、第十一章で、広田が夢の女に向かっていった言葉を引用した。
『「あなたは絵だ」』。
「つまり?」
「表面的には、絵に描かれて『森の女』というタイトルを付けられるのは美彌子だよね」
「ええ」
高満寺がうなずいた。
「でも、それを三四郎は否定するよね。『「森の女という題が悪い」』って」
「そうね。それから『「迷い羊」』ってつぶやくのよね」
「つまり、三四郎の視点からすれば、あの絵のタイトルは『森の女』ではなくて、『迷い羊』だっていうことになる。帝国主義自体の明治の社会で、美彌子は自分が演じた「絵」としての自分を貫き通すことはできず、おそらくは好きでもない男と結婚することで体制のなかにのみ込まれていってしまう。そういう本来の自分から逸れてしまった「迷い羊」となってしまうわけだよね」
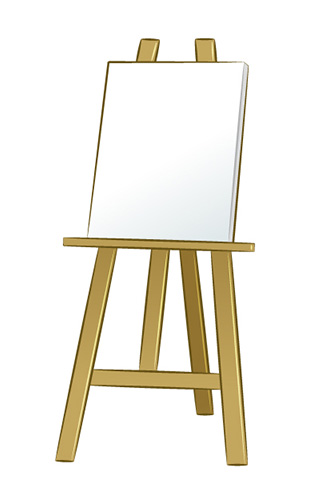
「だから?」
「ここで反聖文は、革命を起こしたわけだ。図と地を反転した。帝国主義の側にいた恭助を、帝国主義そのものを象徴する汽車で殺害することによって、象徴的に自壊させた。作品を裏から支配していた恭助ネットワークを解体し、三四郎を中心としたネットワークに組み直した。そのとき、復活してくるものはなんだろう?」
「東京中心の価値観じゃなく、資本主義的な価値観じゃなく、自己本位の価値観ではない何かかしら?」
「そうだね。そして、マチスモの空気の強い九州は現状では帝国主義的な価値観に呑みこまれているとしても、それ以前にあった牧歌的な方向性の回復への糸口も、その方向からは望み見ることができるかもしれない」
「古い価値の復活ってこと?」
「そう、そしてそれを象徴するのが、明治憲法発布という境目だとしたら?」
「ああそうか。広田の見た夢がここで出てくるわけね」
「そういうこと。広田が見た夢の中の森と、そこにいた少女とは明治憲法発布前の世界、そして帝国主義以前の価値観を象徴しているわけだよね」
「つまり、真の『森の女』、絵としてほんとうに変わらない価値観としての、反帝国主義、非帝国主義的な世界観が、浮かび上がると」
「そういうことにならないだろうか」
そういえば、与次郎がお膳立てした晩餐会の席で、広田は意味深なことを言っていたではないか。野々宮のやっている物理と、文学との違いについての議論の中で、広田は『「ある状況のもとに、ある人間が、どんな所作をしても自然だということになりますね」』と、物理現象と人間行動との違いを指摘していた。つまり、『ある状況の下に置かれた人間は、反対の方向に働きうる能力と権力を有している』ということだと。与次郎しかり、『森の女』しかりというわけである。
もう一枚の『森の女』。ほんとうにそのタイトルにふさわしい絵が、俺たちの目の前に浮かび上がってきた。『「十二、三のきれいな女だ。顔に黒子ほくろがある」』と広田が語った少女の姿が、一枚の絵として浮かび上がってきた。そう、三四郎は、こちらの絵が本物の『森の女』だと知っていたのだ。だから、美彌子の絵のタイトルが間違いだということを指摘しえたというわけだ。
「さらにいうと、あれね」
手弱女が、何かに気づいたようだった。
「九州中心のネットワークに組み直すってことは、お光さんがちゃっかり三四郎を手に入れるってことでもあるわけね」
「そうなんだよ。さらには、もっとひどい可能性もある。たとえば、結婚したばかりでまだ子供もいない恭助が死んだとしたらどうなる?」
「そうなると、里見家がなくなるってこと?」
「すると? どうなる」
「ええっと、ああそうか、美禰子は自分の出自である里見家を失うってことになるわね。里見家が消滅するってことになる」
「そうすると、結局は家同士の結婚として、社会的体面のために里見家のお嬢さんをもらった金縁眼鏡君はどうするだろうか」
「まさか、離縁とか?」
「最悪そうなるだろうし、すくなくとも美禰子に対する態度は冷たくなるだろうね」
「でも、もし離縁されたら三四郎がかけつけるんじゃないのかしら」
「それはないよ。絶対ない」
「どうして?」
「だって、さんざん見たように、三四郎が惚れてるのはそういうヴァルネラブルな生身の女としての美禰子じゃないからだ。本物の美禰子じゃなくて、『団扇をかざして立った』姿勢に象徴される演出された美彌子、絵の女としての美彌子に対してしか三四郎は興味を示さないからね」
「つまり、母親とお光は、三四郎を翻弄した美禰子をそうやって罰するってこと?」
「そう。反聖文的には革命がやりたかったんだろうけど、母親とお光が動いた最大の動機は、結局こう言うところにあったんじゃないかなって思うとちょっと怖いよね。与次郎あたりが、その辺をさかんに焚きつけた可能性はあるよね」
ぴいろりいろりいん、ぴいろりいろりいんと俺の携帯のアラームが鳴った。あと五分でタイムリミットだという警告だった。
「あ、やばい。そろそろ時間よ。入力しなきゃ」
閑話休題。もうだべっている暇も、悩んでいる暇もないってこと。俺たちは、ちょっと顔をみあわせた。高満寺が、顎で俺を促した。「いいから、とっとと吹き込みな」っていう指示だった。
俺は、思い切って爆弾の中心に設置されているマイクのボタンを押した。そして、音声認証がなされたのを確認してから、犯人の名前を吹き込んだ。

「三四郎の母とお光さん」
すると、続けて、「その推理の道筋を簡潔に記述せよ」という機械音での指示が出た。俺は、いま高満寺に話した内容を、要約して語った。「回答を照会中」という音声での解答が出た。
機械音声はそれきり沈黙した。
起爆装置に設置された液晶画面に、「回答を照会中」という表示と、「すべての聖典に聖なる死を!」という反聖文のスローガンが、交代で点滅した。
どきどきした。心臓が破裂しそうだった。もし間違っていたら、『三四郎』が壊滅する。ERRORという表示が現れると同時に起爆が起こり、原典攪乱ウイルスが放出される。眼前で、漱石のテクストが見る間に蚕食され、誤変換され、文脈が、センテンスがばらばらに解体されたあげく、でたらめに接ぎ木されていく。ランダムに成長していく尿素の結晶のようによく知っていたはずのテクストが見知らぬものへと変貌していく。それはたとえば癌化と呼んでもいいのかもしれない。テクストが癌に冒されて、見知らぬものへと変貌していく。それはもはや異化というレベルを超えた、得体の知れない文字の塊でしかない。通常の理性をもってして読み解くことは不可能な、ダダイズムの極地的な破壊をこうむることになる。
しかもその被害は、『三四郎』だけでは収まらないかもしれないのだ。先ほど受けた報告では、あのゴミ箱内では、疫病のように無秩序化現象への感染が続いているという。どうやら、この原典攪乱ウイルスには、綿毛機能が備わっているようなのだ。つまり、タンポポが種を拡散させるのに使うあの綿毛である。ある程度まで原典の攪乱が進むと、ウイルスは原典の文字を飛ばす。それは、電脳空間を移動して、易々と同じハードディスクに収蔵されている他のテクストへと飛び火する。さらには、電子回線という血管系を経由して、他のハードディスクへの侵入まで試みるというのである。どうやら、VRへの侵入者たちは、ただ侵入するだけではなく、このシステムのセキュリティホールも入念に調査していたようであり、それに会わせたウイルスを開発してきたということのようである。われわれのなかには、内通者の存在を疑う者すらあるくらいである。それくらい、このウイルスはみごとにわれわれのシステムを知り尽くしている。反聖文という組織の性格を考えると、確かにどこに賛同者がいてもおかしくはない。だから、これほど厄介な敵はいないといっていい。
だから、俺は目を覆いたかった。
答えを打ち込んで、しばらくウィーンウィーンという照会音が響くのにも耳をふさぎたかった。答えが照会され、そして、ランプが点滅した。
CLEARED
反聖文のスローガンに代わって、そのありがたい文字が液晶画面に浮上した。そして、埋め込まれていた挿入文がかちゃりと原典から外れた。その瞬間の安堵たるや、筆舌に尽くせないものがあった。
「やったわね、このなよなよ野郎!」

ばーんと背中を叩かれて俺は悲鳴を上げた。力の加減を知らないやつめ。背骨が折れるところだったじゃないか。
「くうっ、痛え」(何かの引用)
苦痛にうめきつつも、おれは笑顔だった。よかった、危機は無事に回避することができたのだ。同時に、強烈な眠気に襲われて俺はほほえみながら意識を失った。そういえば、不眠不休で、この長いテキストに入りづめ、体験づめ、考え詰めだったのだ。俺の脳は完全に限界を超えていた。おやすみ、エブリバディ。
(第41回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


