 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
二五、与次郎の義
「いよいよ、図と地を反転して犯人探しの始まりってわけね」
「うん、とはいったものの」
ちょっと困った。どこから出発すべきか、俺は少し悩んだのだ。だが、悩むという現象とはおそらく袖振り合ったことがないのであろう高満寺が勝手に始めてくれた。
「凶器は二つだったわね」
「ああ、なるほど、そこから始める手もあるな」
出たとこ勝負だ! とばかり、俺はこの流れに乗ってみることに決めた。
「二つといっても、全然別の場所から取られてたのよね」
「そうだね」
「最初の凶器は第二章に出てくる野々宮の地下の実験室にあった。そうよね」
「うん」
「で、二つ目は、ずいぶん後の第十章に出てくる広田の新居にあった」
「その通り」
「その二つの場所に共通する登場人物といえば、三四郎しかいないことになるわ」
「そうだね」
「じゃあ、三四郎が犯人ってことになるじゃない」
「でも、そうはいかないんだ」
「どうして?」
「だって、この物語は三四郎の視点で書かれているだろ」
「ええ」
「ところが、この物語を読む限りでは、三四郎が見た野々宮の部屋や広田の部屋には、最初っからナイフや包丁はなかったことになる」
「なるほど、三四郎が訪れる前に盗まれてたってことよね」
「うん、そういうこと。犯人は、三四郎より先回りしていることになる」
「そんなこと可能かしら?」
つまり、書かれていないことについて考えねばならないということなのだ。
「まあ、その問題については、後で俺の考えを言うつもりだよ」
「そう。で、どうなの」
「どうなの、ってなにが」
「だから、目星よ。犯人の目星」
いや、いきなりそこかよ。これから順番を追って推理を展開しようって時なのに。でもどこかの時点ではそれを言わなければならないのは確かだ。ただ、俺のなかにはちょっとした躊躇がある。口ごもってしまう感じが。なぜだろう。なんだかためらわれる感じがどうしてもぬぐえないのだ。
それでも、俺は決意を固めた。
なんにせよ、これは職務なのだ。それに、ちゃんと犯人を挙げないと、大変なことが起きるのだ。
「凶器が二つってことは、おそらく背中の刺し傷も二つだった。俺はそんな風に思ってる」
「どうしてそう思うの」
「たぶん犯人が二人だからだよ」
「なんで」
「二人で共謀することでしか、そして二人で『せーのっ!』って感じで刺すことでしか動く勇気がなかったからともいえるだろうね。しかも、なるほど刺しはしたものの、二人の攻撃はまったく致命傷を与えるにはいたっていない。そこまで本気で殺す気にはなれていないってこと。彼が死んだのは、逃げようとして線路に落ちたからだからね」
「そして、汽車に引き裂かれたのよね」
そういう意味では真犯人は汽車ってことになる。でも、犯人は汽車ですと書いても正解にはならないだろう。
「つまり、何が言いたいわけ?」
「本来は、そういう犯罪とは縁遠い人たちだったってことだよ。やむにやまれぬ衝動に突き動かされてやったんだ」
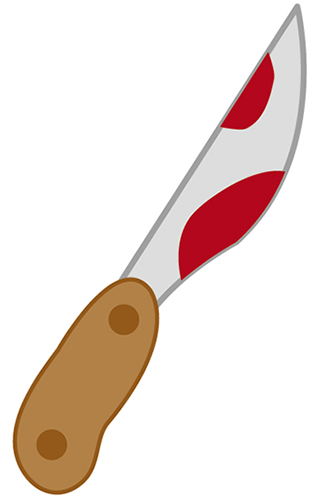
「どういう衝動」
「たぶん、三四郎のため」
「三四郎のためって、三四郎をそんなに思ってる人たちといったら」
「うん、そうだよ、それしかない」
ここまで言えばもう、俺が考えていることは誰にも明らかだろう。通常は察しの悪いことこの上ない、コンニャクなみに打っても響かない高満寺ですら、わかったようだった。
「でも、あの人たちは、物語の表面には姿を現さないじゃないの」
「そうだね」
「つまりあれでしょ、熊本の母親とお光さんだって言いたいんでしょ」
「そうなんだよ。母親は結構存在感があるけど、実際には手紙を送ってきているだけだ。そして、本文中で母親の手紙がそのまま引用されることはない。常に三四郎による要約のかたちで紹介されるだけだ。三四郎というフィルターを通して、翻訳された形でしか、読者たる俺たちには示されない。だから、おそらく開けっぴろげで素朴な文体をもつであろう、母の人格を示す言葉づかいが、作品の表面に剥き出しで現れることはない。その意味で、母親は野々宮や美禰子や広田のような登場人物とは異なって、物語の背景に埋め込まれていることになる」
「つまり、見えないところってことね」
「そう、お光さんもまた三四郎の回想と、手紙の中に登場するだけで、物語の表面に姿を現すことはない」
「母親は手紙以外にも野々宮にひめいちの粕漬けを送ったり、三四郎に金を送ったりしている。お光さんも、羽織を送ってきたりするからそれによって、実在が証明されている。つまり、実在はしているけれど、われわれ読者にはその姿は見えないわけだ」
言いながらも、俺だって確証があるわけじゃない。もし間違っていたら、とんでもないことが起こるのだ。原文攪乱ウイルスが発動して、見る間に『三四郎』の原典は壊滅的な損害を被ることになるだろう。文字と文字がバラバラにカットアップされて再配列され、作品は見るも無残に解体される。乱雑な遺伝子組み替えが行われた後の遺伝子のように、得体の知れない文字の固まりだけが残されることになるだろう。さらには、それが隣接して保管されている他の漱石作品へ、さらにはそれに並列されている明治期の諸作品へ、そしてさらに別の時代の作品へと規範文学を解体していく可能性がある。
しかも、このウイルスは原典一つだけではなく、予備のファイルにも仕掛けられており、予備ファイルでも同時にウイルスが活動を始めることが予測される。そうなると、VR社の存亡そのものが危機に瀕することになる。
VR全盛の今の世の中、いまさら国会図書館に所蔵されているリアルな書物を引っ張り出してきて読もうという人はほとんどいない。そこにはただ文字体験があるだけだからだ。一度VRを体験してしまった人間にとって、その「単なる読書」はあまりにも退屈で、苦痛でしかない。しかし、もしウイルスによってVR配信用の原典が破壊されてしまったら、もう一度その書物を取り寄せてスキャンし直し、原典を再度作り直す必要が出てくる。その手間は確かに大したものではないかもしれない。会社の信用は確かに丸潰れになるだろうが、会社そのものが潰れるほどの損害を受けるとは思えない。
いや、その可能性はないとはいえない。たとえば、われわれが気づかない内に仕掛けられたウイルスが発動した場合だ。われわれが気づいていれば、謎解きのためにアクセスは遮断されるから、一般読者がダイブインする可能性はない。けれども、今回のような宣告なしに、ひそかにどこかの作品にこのウイルスが仕掛けられたとしたらどうだろう。そこに入り込んでいる読者は、崩壊する作品に巻き込まれたらどうなるだろう。以前俺はダストボックスと呼ばれる、泡沫作品の掃き溜めでその現場に直面したことがある。本部からの指示で緊急脱出したからよかったようなものの、もしあのまま作品内に度停まっていたら、壊れていく文字列に巻き込まれて二度と生還できなかったかもしれない。あるいは、解体され無秩序に再配列される文字を読み、そこから派生する得体の知れないイメージや体験をVR体験することで精神を破壊されてしまっていた可能性だってある。そんなことが、今後一般読者を巻き込みでもしたら、VRの評判は一気に下がってしまうだろう。それどころか、訴訟沙汰に発展して、社運が傾くという可能性だってないわけではないのだ。
さらに、問題はそれでは終わらない。ほんとうの問題は、一度このテロが成功してしまったら、次々と同じ手口での犯行が繰り返される可能性が出てくるということにある。たとえばいくつもの規範文学にこの「なぞなぞ付きウイルス起爆装置」が同時多発的に備え付けられたら、大変なことになる。複数の作品となると、今回のようになんとか謎を解こうと取り組んでみることすら難しくなってしまうからだ。さらに進めば、もはやなぞなぞなどなしにいきなりVR空間上に、このウイルスが大量にばらまかれる危険だってあるのだ。
そんな突破口を開かせないためにも、なんとしても俺たちはここで正解を導き出さねばならないのである。俺は責任感で胃が痛くなるのを感じた。
「でも、どうやって九州から東京まで二人が出てこれたわけ? それに、動機だってわからないわ」
「うん、ここはちょっと突飛な話になるから、俺も言うのにちょっと躊躇がある。説明しにくい気がするんだけど、なんとかがんばって説明してみるよ」
「うん、がんばって」
おや、高満寺らしくない、素直な応援ではないか。返す返すも残念でならない。これが、可愛い女子であったら、俺のやる気も倍増なのだが、筋肉むきむきの大女にいわれると、なんだか違和感で眩暈がしそうな気分になる。
「まず、被害者の里見恭助だけど、彼もまたいるけどいない人だよね?」
「そうね。名前が出てくるのもほんの数カ所だけだものね」
「うん。具体的には、原口と広田の会話の中(七)と、与次郎と三四郎の会話の中(八)、三四郎が訪ねる美禰子の家の標札の名前(八)、ちなみにこの標札を見て三四郎は『里見恭助という人はどんな男だろう』って思うんだよね。つまり、三四郎のなかでは徹頭徹尾、名前だけの存在でしかないわけだ。それから、三四郎が里見家にお金を返しに行くときに、もしかしたらこの時間には家にいるかもしれないと敬遠する場面(八)。ここでは、三四郎が恭助に会うことを恐れてる感じが伝わるよね。妹にちょっかい出すなと叱られるのが怖かったのかもしれないよね。それから、原口が独身ものの例としてあげる場面(十)。実は、この五カ所だけなんだよね」
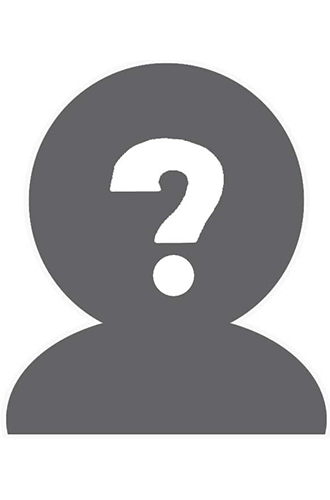
「最初に関係性が説明されるのは、三四郎がよし子から情報を引き出しに野々宮の家を訪れる五章の場面よね」
「うん、そこで広田が野々宮の師であり、野々宮の友人が恭助であり、恭助の兄が広田の友人であったというつながりが明らかになるわけだ。さらには、美禰子自身も英語を習いに広田のところをときどき訪れているということもわかってくる。さらに、原口が広田を訪ねてくる七章では、原口と恭助が一中節を一緒に習っている仲であることがわかる。そして、十二章で美禰子の結婚相手が恭助の友人だちであることがよし子の口から明かされる」
「これだけなのね」
「そう。これだけなんだ。でも、これだけなんだけど、とても重要な役割を果たしている」
「つながっているわけね」
「そう、恭助は野々宮、広田、美禰子、よし子、原口、与次郎、さらには美禰子の婚約者など、重要な登場人物すべてと面識がある。全員とつながりがある重要な存在なんだ。それなのに、三四郎は一度も会ったことがないし、最後まで会うことはない」
「あ、わかったわ」
「なに?」
「存在の仕方が、三四郎のお母さんやお光さんと似てるってことね。お母さんとお光さんも、三四郎に大きな影響を与えるけど、読者には最後まで見えないものね。っていうか、作品の中で、文字として書かれている部分では三四郎にも見えない」
「そうなんだよ。実は、この二つの力が、作品を支える重要な陰のネットワークになっているわけだよ」
先ほど使った表層と深層という表現がここで生きてくることになる。
三四郎の視点で見られた世界が表層の世界であり、その世界を三四郎には見えないレベルで支配するのが深層だという見方である。
「九州と東京にそれぞれ見えない中心があるってことね」
「でも、どうやって九州の二人が、東京に出てきたのかしら。三四郎が帰省した直後に、後を追うようにしてやってきたってことかしら」
さて、ここがなかなか説明しにくいところだ。どういったらいいんだろう。俺は悩んだ。俺なりに。
「たとえばさ」
俺は俺なりに切り出した。
「はあ」
なんとも頼りない反応である。
「俺たちの仕事ってあれだろ、文字の連なりを見据えつつ、それが描き出す世界を体験しもするって感じだよな」
「そうね。ふつうのVR体験者には文字の連なりの方は徐々に意識されなくなっていくわけだけどね」
「つまり、そこには二つの世界があるってことだ。作品が描き出す世界と、文字の塊の世界」
「まあそうなるわね」
「『三四郎』で言えば、三四郎や美禰子や広田先生は、作品が描き出す世界の中で躍動するよね。彼らは身体を帯びた存在として、九州から東京に移動するし、菊人形を見に行ったり、芝居を見に行ったりと忙しい」
「ええ、それが物語の世界だからね」
「でも、三四郎の母親やお光さん、あるいは里見恭助の場合はどうだろう?」
「そうね。少なくとも、物語の世界には顔を出さないわね」
「ってことは、彼らはどっちの世界にいることになるのかな」
「うーん、そうねえ。一応三四郎たちの世界に属しているようにも見えつつ、文字の塊のなかに埋め込まれてもいるような感じかしら」
「そうなんだよ。彼らは、姿を現さない名前=文字だけの存在として登場するから、いるけどいない存在なんだ。同時にいないけどいる存在でもある」
さっきの表層と深層というたとえでいえば、表層にはいないけど深層に潜んでるってこと。深海魚みたいに。そして、表層にいないってことは、イメージを伴わない文字として存在してるっていう感じである。VRで体験される世界が表層、体験化されない文字テキストが深層という対比でどうだろう。
「でも、そんな彼らが物語の求心力となってもいるって、不思議よね」
「肉体を持たない文字としての存在であるから、彼らの自由度は極めて高いといえるんじゃないかな」
「どういうこと?」
「時間にも空間にも縛られないってこと。そして、彼らの関心の中心は物語の完成度にあるっていうこと」
「彼らにも関心っていうか、意識があるってこと?」
「ふつうの人間の意識じゃないよ。物語の構成要素としての使命感っていうか、構造に関する意志っていうか」
「なんか、難しいわね」
そうなのだ、この辺りの事が自分でもなかなかうまく表現できなくて困ってしまう。
「でもまあいいや、とにかく彼らは物語の進行と無関係に移動できるって想定して見ようよ」
「そうすると?」
「汽車にも電車にも乗らずに、三四郎の母とお光さんは文字群の間を移動することができる。その途中で、必要なもの、ここでいえば野々宮の研究室のナイフと、広田の家の台所の包丁だね、それを抜き取っていくことができる。あるいは、汽車に轢かれて自殺した女の足元に『復讐』を約束する花束をおいていくことができるってこと」
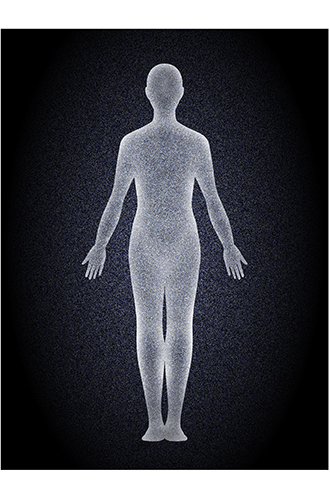
「物語の世界じゃなくて、文字の世界を移動するわけね」
「そう。俺たちが虚構パトロールとしてやっている仕事って、けっこうそういうことだろ。物語外部の存在として、物語の文字列にダイブインして、損傷箇所や、書き換え箇所、余分な付け足しなどをなおしていく。それと同様のことは、物語に姿を現さない文字だけの登場人物にはできるってことだよ」
「じゃあ、これは物語が勝手に動いたってこと?」
「いや、それはない」
いくらなんでも、それはないだろう。俺たちだって、物語の修復のために外から入るわけだから。
「やっぱり、外からの侵入者が、二人をそそのかしたんだろうね。二人にとって一番魅力的な方向に物語を修正する方法をほのめかしたんじゃないかな」
「でも、二人は恭助を知らないんじゃないの?」
そうなのだ。表層の物語を読む限り、九州の二人が、三四郎を取り巻く東京の状況を事細かに知るすべはなさそうなのである。三四郎が書く手紙は、ひどくぶっきらぼうなものでしかないからだ。だから、どこかに仲介者が必要とされることになる。
「そこに登場するのが与次郎なんだよ」
「与次郎?」
「うん、与次郎って実はすごく特別な存在なんだよ。広田先生が、与次郎を田んぼの中を流れる細い水にたとえるだろ? 広田先生を東大教授にしようと奔走したり、文芸協会の講演会のために走り回ったり、東大生のふりをして女をだましたり、いつも動き回ってる。三四郎をいろんな人とつないで行ったのも与次郎だからね。実際、与次郎はいってみれば水銀みたいに流れる物体、身体を持っているようで持っていない存在として描かれてるんだよ」
「身体を持ってない?」
「うん、三四郎は目として描かれることが多いよね。女性を嘗めるようにねちっこく観察するだけじゃない。男性である広田や野々宮や原田も観察している。たとえば、広田は『面長のやせぎすの、どことなく神主じみた男であった。ただ鼻筋がまっすぐに通っているところだけが西洋らしい』などと評されているし、野々宮は『いくぶんか汽車の中で水蜜桃を食った男に似ている』『額の広い目の大きな仏教に縁のある相』と評されているし、原田は『フランス式の髭を生やして、頭を五部刈りにした、脂肪の多い男』と描写されている。ところが、三四郎が一番しょっちゅう会っているはずの与次郎に関しては視覚的な観察がないんだ。容姿だとか、背格好だとか、服装だとかの描写が一切ない。それでいて、活発に会話をし、三四郎をいろんなところへ連れ回す。不思議じゃないかい?」
「そういえば、そうね。読書=体験してるときは適当に姿を思い浮かべて映像化してたけど、根拠はないわよね」
「俺はね、与次郎は存在しないという説をもっているんだ。いや、存在はしているんだけど、他の登場人物とはちょっと違って、やっぱり、三四郎の母やお光さん、あるいは恭助と相通じる文字だけの存在という感じがするんだな。しかも、テクストの中を自由に行き来できる、媒介者みたいな存在じゃないかって思ってる」
「どういうこと?」
「わかりやすくいえば、野々宮は科学という島であり、広田は文学という島であり、原田は美術という島である。さらにいえば三四郎は正科生であり将来の島の卵である。島であるからそれぞれに動かない。これに対し、与次郎はどこにも属してないだろ? 働いていないから企業にも役所にも所属していないし、大学生とはいっても選科生だから正式な大学の所属者ではないし、広田の家に居候していて実家が果たしてほんとうにあるのかどうかも定かではない。さらには、女をたぶらかすために、偽医学生のような偽りの帰属を捏造したりもする。つまり、与次郎はアイデンティティのよりどころとなる場をもっていないんだ。それは、もしかしたらあえて持たないということなのかもしれない。なぜなら、彼はいわゆる道化であり、媒介者、あるいは触媒であるからだ。自分の領分を持たないから、どこへでも行けるが、何者にもなれない。とはいえ、この越境者なくしては、それぞれに動かない島である彼らはつながり得なかった。いるけどいない存在。いないけどいる存在が与次郎。服装も表情も描かれることはない。声としてのみ現れる存在」
「だから、地理的な隔たりを無視してテクストの中を移動して、三四郎の母やお光さんにも会えるし、恭助にも会える、ってこと?」
「そういうわけ。で、この与次郎が外部の力とも共謀したんじゃないかって俺は踏んでるわけだよ。物語をもっとおもしろくするためっていう動機に動かされて、導き手になったんじゃないかってね」
「それが、恭助殺害事件」
「そう。今風のミステリに慣れた読者には違和感のない設定でもあるしね」
「じゃあ、身体をもたない与次郎に例の調子で説得された、同じく身体を持たない二つの名詞である母親とお光が共謀して、同じく身体をもたない恭助という名前を消しに行ったというわけなの」
「そういうことだ。でも、彼女たちは殺意は抱いたが、自分たちで殺したわけじゃないよね。挿入分を読む限りでは、ナイフあるいは包丁による怪我は致命傷にはなっていないから。逃げた恭助が、線路に落ちて列車に轢かれたことになっている」
「つまり、この現場もまたノーウエアであったということだよ。表層の物語世界には場所を持たない、どこでもない場所。それゆえにどこででもありえる場所」
「あ、だから」
「そう、だから恭助の逃げる先に線路が出現し、折よく汽車が通り抜けるなんてことが可能になった」
「つまり、そのシチュエーションを呼び出したのは与次郎だったと」
「そういうわけだよ。おそらく、犯人、そして恭介にとって直接の加害者は汽車でなければならなかったってことなんだと思う」
だから、挿入文でも、どこで殺されたのかという場所の情報は提供されていなかったんじゃないだろうか。それがどこでもない場所であるがゆえに。
「で、恭助の死を見届けて、与次郎はまた平気な顔をして物語の表面に戻り、三四郎たちといっしょに『森の女』の絵を見に行ったというわけだ」
(第40回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


