 学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
恐ろしくて艶めかしく、ちょっとユーモラスな『幸福のゾンビ』(金魚屋刊)の作家による待望の新連載小説!
by 金魚屋編集部
2.三美神
ステージに現れた三人はみな女学生だった。
そのうちの一人は背が高かった。モデルのような体形だが、メリハリのある身体の線はむしろ挑発的な気配を放っていた。歓声が上がった。
「なによその男性の視線を意識した服装は!」
もろに橋田由香、ことフェミニズム・クイーンの逆鱗に触れたようだった。
「名乗りなさい、あなたは誰!」
しかし、当のビッチ風の女子学生はびくともしなかった。
「さあ、みんな教えてあげてわたしは誰?」
「AWA様!」
「桜木泡様!」
「うそ、ナマ泡様、まじでぇ」
「この大学にいるとは聞いてたけど、まさかこんなところにぃ」
黒いウェディングドレスの一人が、橋田由香に駆け寄って耳打ちした。情報を伝達しているようだった。つまりコミュニケーションね。
「ほお、グラビア・アイドルとはな」
軽蔑の目線が送られた。橋田由香が桜木泡を見下そうとした。しかし、桜木泡の方が背が高かったので、見下ろされる構図となってしまった。
「この場がなくなるのは困る。中止はやめて欲しい」
桜木泡は動じていなかった。あの橋田由香の強烈な邪眼を平然と受け止めていた。
「なぜなら、本日わたしたちもまたこの場を占拠するつもりだったからよ」
さすがに、このセリフには橋田由香も驚いたようだった。
「どういうことだ」
「こういうこときゅん!」
「教えてあげるから、そこに膝まづけ!」
さらに二人の派手な装いの女子学生たちが進み出た。
「おおっ」
「なんてことだ」
聴衆がどよめいた。むろんぼくの心もどよめいた。普段テレビやネットのような二次元の世界でしか見ることの出来なかった有名人が三人もステージ上に登場したのだから。
「さあ、教えてみんな、わたしはだあれ?」
かわい子ぶりっ子な感じだが、もう完全に許せちゃうってな感じのきゃわゆさで問いかけるやや背の低い彼女。その彼女とはぁ?
「フクロウちゃん」
「香月梟サマだぁ」
「新曲『斧で割られたパパの頭から爆誕いぇい!』サイコーだったよぉ」
「また名曲がひとつふえたよなあ」
再び黒いウェディングドレス姿の一人が橋田由香に耳打ちした。

「ほほぉ、シンガーソング・コケティッシュ・アイドルというのがお前のキャッチフレーズなのか?」
「そうだよ、それが何か問題きゅん?」
「きゅんて、あんた」
「きゅんはきゅん、きゅんとくるのきゅん、きゅんとくるからきゅん」
橋田由香は眉間を指先で抑えた。軽い頭痛を覚えたようだった。
「ふん、コケテマスアイドルだって」
「コケティッシュだけどきゅん」
「フリフリのドレス着て踊って、オタクどもの好奇の目線を集めるのが嬉しいのか」
「うん、嬉しいきゅん」
あっさり答える梟であった。
「さあ、いよいよ大トリってわけね。そこらに生えそめし朔太郎的細い竹ども、けぶれるごとく見える根を垂れた、あはれふかき竹どもよ。わたしの名を呼び、崇め、そして讃えるがいいぞ」
三人目は、黒いレザースーツに身を包み、片手にしなやかな鞭をもった女王様であった。足下は当然ながら、黒いハイヒール。ヒールも壊れておらずびんびんにとがっている。踏まれたら確実に悶絶する、背中にずどっと突き刺さる、正真正銘の激痛ヒールであった。
「お世話になっております」
辺りじゅうの男性たちがひれ伏した。
「われらがセックスシンボル、石榴さま」
「文芸AVの監督脚本主演をつとめる天川(ル、あまのがわ)石榴さま」
「写真集もDVDも全部持ってまーす」
辺りじゅうから讃美の声があがった。再び身内から耳打ちを受けた橋田由香が怒りも露わに石榴を睨みつけた。
「なんという恥さらし。学生でありながら、性搾取の極北たるAV嬢をつとめるとは」
橋田由香は嘆いたが、その嘆きを、天川は鼻先でせせら笑った。
「AVをジャンルとしてしか見れない視野の狭小さ、恥じるべきね。わたしは、タブーとされている性のジャンルを切り開く冒険者よ。あなたのようなイデオロギーの奴隷には理解できないでしょうけど。わたしはいわばクリエイターにしてアーティストにしてアクトレス。脚本、監督、主演、全部兼ねてるからね。主題歌だって自作自演しているしね。そして、最新作は日本アカデミー賞にもノミネートされたわよ。ハリウッドからもリメイクの依頼来てるんだから」
まったく動じることなく石榴が橋田由香を見返した。
「いったい、どういうことなの?」
当惑した橋田由香が、順に三人を見た。いずれ劣らぬ美貌と美ボディの持ち主たち。
「つまりなに、あなたたちはルッキズムの勝者だから、自分にとって都合のいい現状を追認しようっていうつもりなわけ?」
「バカをいうでないよ」
一笑に付したのは桜木泡だった。
「もちろん、わたしら三人はライバルだけどね、今日この場を占拠しようと思ったのは別の意図があってのことなわけよ」
「ほう、その意図とは?」
「あらゆる制限を取っ払ったところで真の美を競い合おうって魂胆だよ」
「結局美じゃない、なにその制限って」
梟がしゃしゃり出てきた。
「ここはわたしにまかせてきょん」
「うわ、わたし嫌いなのよね、ぶりっ子」
「いいじゃない。これがわたしのスタイルなんだからミョ」
まったく動じない梟ちゃん。
「あのね、まず『ミス』を外すわよきょん。未婚者だけってのをやめるんるん」
「それだけじゃない。いいか、女だけってのもやめるんだ」
割り込んできたのは天川石榴だった。
「諸君、ここにわたしは、いやこのわたしが宣言する。本日これより、この場において、年齢、性別、人種、すべてを問わない美の饗宴(シュンポシオン)が催される、と」
男女の区別も、年齢の区別も、人種の区別もない美の饗宴?
考えたこともない企画だった。
「そ、そんなことが可能なの?」
戸惑う橋田由香。彼女はフェミニズムの理論に従って批判を繰り広げてきたので、そのはしごを外されると拠り所がなくなってしまう感じだった。
「可能じゃないって考えるほうががおかしいだろ?」
「でも、どうやって? 美の審判の基準は何?」
「それは、だいじょうぶ。わたしたちはすでにパリスの存在を知っている」
「パリス?」
「そうよ」
今度は桜木泡。
「この日のために、彼はこの学園に入学し、この時を待ってきたのよ」
「そんな、たった一人の人の価値観で決めるなんて」
「でも、その人が、そういう宿命の元に生まれてるとしたら? それはそうするしかないし、ほかに方法ないでしょ」
「っていうか、そんな宿命なんて」
「あるのよ!」
「あるみゃん!」
「あるのだ!」
三人が唱和した。
「じゃあ、呼びましょうか」
「ええ」
「はい、出ておいで。針素一郎君!」
はあ?
なんで?
どうして?
どういうこと!
ぶったまげた。
わけがわからなかった。了解不能すぎて頭がバグった。
な、な、な、なぜ、ぼくの名前が!
「おい、イチロー呼ばれてるぞ、とっとと出てこいよ」
おい稗田、なんでお前そんなに嬉しそうなんだよ。なんだよ、そのついにその時が来たかぁ的なうれし気な顔は! なんだよその、さあおいで、こっちにおいで的な手招きは! 大事な友達の危機なんだぞ。人目につかないように、ひっそりと、そして記憶に残らない薄味のうどんのように生きてきたこのぼくが、公衆の面前に引きずり出されようとしているんだぞ。これまで、ついぞ大声で呼ばれたことのなかったぼくの名前が、唐突に公衆の面前でまるで公然猥褻行為のごとく読み上げられたんだぞ!

「なんだよお前、あの三美神と知り合いだったわけ?」
照明ブースでいっしょに働いていた友人の城島拓郎までが、そんなことを言い出した。
「まさか」
「だよなあ、針素だもんなぁ。女子に名前覚えられない男子ナンバーワンと言われたお前だもんなあ。まあ、俺もナンバーツーではあるけどさ」
城島はぼくの背中をどんと押した。
「たぶんあれだな、態のいいイジメだな。祭り上げるフリして、お前をさらし者にしてからかうって魂胆だぞ」
「だよね、知らんふりしてようか?」
「そうだな。どうせ、適当に名簿とかでお前の名前見つけただけで、どれがほんとうの針素一郎かなんて、あいつらも知らないだろうから」
「っていうか、この学園のほぼほぼすべての人が知らないと思うよ」
というわけで、ぼくはこの唐突な呼び出しを拒絶することにした。そう、ぼくは目立たない。人に名前も顔も覚えられないというのが特技とさえいえる存在なのだ。あの三人にしても、ぼくのことを知って名前を挙げたとは思えなかった。華やかな舞台で注目を浴びる存在というのは、ぼくが北極なら南極みたいなものだった。つまり、対極という意味だ。接点がなさ過ぎた。ぼくが出て行かなければ、どうせ誰でもいいんだろうから、あきらめて別の人の名前を呼んでくれることだろう。
「早く来なよ」
桜木泡が、呼びかけた。
「イチロー君、来てくれないのきゃん?」
香月梟が、悲しげに問うた。
「来ないなら」
少しいらついた感じで、天川石榴が宣言した。
「こっちから赴こうぞ!」
「だいじょうぶだ。顔を伏せてろ」
城島がぼくの頭をグッと抑えた。驚いたことに、三人はほんとうにステージを降りた。ステージの周りの客たちが二つに割れる。人垣のなかにできた一筋の道。まるでモーセの出エジプトだった。三人はステージからまっすぐ歩き出した。そう、まるでぼくがここにいることを知っているかのごとく、ステージ後方の照明ブースに近づいてくるのだった。
「なんでだ? なんであいつらこっちへ向かってくるんだ」
理解できないという風に、城島があわてる。
やがて、見られないように伏せた頭の上で声がした。
「はあい、イチロー君見っけ!」
「園庭かくれ鬼は終わりみゃん」
「針巣一郎! 観念して出て来いよ」
「えっ?」
思わず反応していた。
「園庭かくれ鬼って・・・?」
そんなはずはないと思った。この言い方はぼくと稗田が通っていた幼稚園での特別な呼び方だったはず。
甲羅から首を出す亀のように、おそるおそる照明ブースから顔をもたげたぼく。
「久しぶりね、イチロー君」
「あっ」
不思議なことだけどすぐにわかった。十数年の時を経て、体形も顔立ちもだいぶ変わっているにもかかわらず、肉声を聞き、肉眼で見たとたん、ぼくには彼女らが誰なのかがすぐにわかったのだ。
「あわちゃん、ふくちゃん、さくちゃん!」
「そうよ、わたしたちよ。イチロー君も変わらないわね。アレイもだけど」
幼少期の思い出がふっと蘇ってきた。
いつもぼくらはいっしょに遊んでいた。園庭かくれ鬼もよくやった。あの頃は良かったな。勉強ができるとか運動ができるとかかわいいとかかっこいいとか男とか女とか、そんなことなんにも考える必要なかった。何の区別もなくぼくたちはともだちだったのだ。そしてひたすら無邪気に戯れていたのだった。
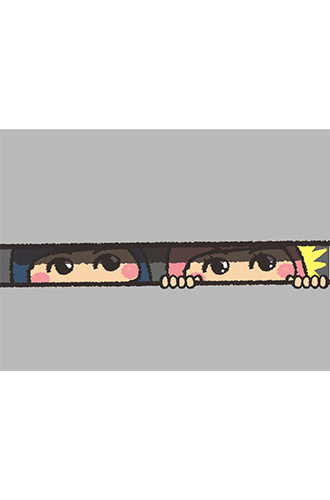
「覚えてるでしょ?」
「なにを?」
「わたしたちがビューチーコンテストオやったこと」
「ビューチーコンテストオ?」
「そうよ、誰が一番ビューチーかってイチロー君に聞いたじゃない」
「そんなことあったっけ?」
まったく覚えがなかった。
「そう、君はあの時も答えなかった。『わかんない』とかって逃げて帰っちゃったもんね」
「そうだったっけ?」
「そうよ、あれ以来わたしたちずっとくすぶったままなのよね。それぞれの道を極めようと努力しながら、わたしたちまだ競ってるのよ。そして、審判役はイチロー、いえ針素君、君じゃないとだめなんだ」
「ええっ、そんなこといわれても」
「はい、問答無用」
あっけに撮られる城島の前で、ぼくは三人の美女たちに引っ張り出され、ステージまで連行された。いや、ぼくからすれば三人の美女じゃない。いつまでたってもこの三人は、ぼくにとってはあわちゃん、ふくちゃん、さくちゃんのままだから。
「さあ、みなさん、この方が審判の針素君ですよ」
と桜木泡。
「それでは、これよりんりん」
これはもちろん、香月梟。
「ビューチーコンテストオを開催する。ミスコンを期待してきた諸君、残念だったな。そして、騒ぎを聞いて駆けつけたやじ馬諸君。貴様らまとめて観客となることを許そう。いいか、言っている意味はわかるね? 帰ることは許さんと言っているのだよ、この私が」
と天川石榴。
かくして、ミスコン会場は占拠され、同じステージを使ってビューチーコンテストオが開催される運びとなった。詳しい趣旨は、あたかも彼女らと確信犯的につながっていたのではないかとすら思える稗田の弁舌でご紹介しましょう。
「ではみなさん、ミスコンに変わりまして、本年はビューチーコンテストオを開催させていただきたく存じます。これは、ミスコンにあったあらゆる制約を取り払ったものであります。性別、年齢、未婚既婚、職業、国籍不問!であります。あらゆる区別も差別もないなかで、いったい誰が究極のビューチーな存在であると言えるのか、その判断基準はどこにもとめればよいのか? 容姿、性格、特技もろもろなんでもありでしょう。そのすべての総合得点として、審判者針素一郎君に判定を仰ぎたいと存じます。
すでに確定している参加者は、提唱者の三名、桜木泡さん、香月梟さん、天川石榴さんでありますが、あまねく全世界に開かれたこの大会でありますから、飛び入り参加、いきなり参加、駆けつけ参加、とまどい参加、ふらふら参加、日和見参加、よそ見参加、気が付いたら参加なんでもオッケーです。我こそはと思われる方がおられましたら、いますぐミスコン開催本部、いや転じましてビューチーコンテストオ開催本部までおいでください。また、オンライン配信で全世界に向けて発信されているこの映像を見て参加を決意された方がおられましたら、まずはメールにて問い合わせをお願いしたく存じます。
さあ、それでは、かつてない試み、すべての要素を含み込んだビューチーの競演、どうぞ皆様のご参加と、そしてご声援をお願いしたく思います」
(第02回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『ビューチーコンテストオ!』は毎月13日にアップされます。
■遠藤徹の本■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


