 妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
by 金魚屋編集部
「この度はご迷惑をおかけして、本当に申し訳ございませんでした」
座っていた問題の撮影者が立ち上がって頭を下げた。パンツ、シャツ、パーカー、バッグ、そして長い髪の毛も含めて全身黒づくめの女性。まだ顔は見えない。
「いや、まあ、頭上げてください。だって別に悪気はないんでしょう?」
マキが険しい表情で俺を覗き込む。甘やかすな、ということだろう。それは分かるが、最初から飛ばすのはちょっと危険だ。相手は決してガードを崩さないだろうし、何かが覆れば一気にこちらが不利になる。
「悪気のアリ、ナシはこっちの取り方次第だけど、とりあえずあなたの事情を聞かせてよ」
トダの声は大きくないが尖っていて、撮影者は更に深く頭を下げる。まあまあ、という感じで視線を合わせたが、小刻みに首を横に振られてしまった。この辺り、長年ひとりで店を守ってきた厳しさがある。一番最後に来たせいか、どうも俺だけテンションが違うようだ。
「私、ニシムラといいます。アルバイトをしながらインフルエンサー……みたいな活動をしています」
ようやく撮影者の顔が見えた。色々と引っ掛かる自己紹介をしたのは全体的に小作りな女性。メガネの太いフレームのせいで顔の印象はぼやけるが、まだ三十歳前だろうか。
「あ、あと京都から来ました」
ほう、という反応がそのまま顔に出るところだった。危ない危ない。言葉に訛りがないので不意打ちに近い。まさかコケモモの使いではないだろうが、ほんの少し印象が変わる。どっちに? 多分良い方に。
「えっと、うちの店の写真を撮っていたということでいいのかな?」
「はい。ちゃんとお声をおかけするべきだったんですが、不快な思いをさせてしまい本当にすみません」
うちの何を撮っていたんですか、とマキが硬い声のまま尋ねる。そういえば永子とリッちゃんの姿が見えない。多分二階だ。
「はい。私、城山先生のことを大変尊敬しておりまして……」
その名前からカメラマンの彼女が浮かぶまで少し時間が必要だった。
「先生が先日、こちらのお店を撮影したと知りまして、それならば実際に見てみたい、そしてご紹介させていただきたいと思いました」
へえ、と思った俺の隣でトダが「無許可で?」と尋ねる。想定外の質問だった。俺からは決して出てこないヤツ。
「いえ、ちゃんと許可はいただくつもりでしたが、お店の前からの光景が素晴らしく、つい撮影の方を優先してしまいました。本当に申し訳ありませんでした」
俺としてはこの辺りで手打ちにしてもいいが、マキとトダは何となく物足りないようにも見える。その気配を感じたのかニシムラさんが動いた。一度立ってから恭しく屈み、足元に置いてあった手提げ袋を「お口にあえば幸いです」とマキに差し出す。「いえ、こんな……」と慌てる姿を見て、今なら手打ちにできると確信した。お気遣いいただいてすみません、と頭を下げるとトダにも伝わったのだろう、声色が明らかに柔らかくなった。

「あの……記憶違いでなければ、まだ掲載される雑誌って発売されてませんよね?」
そうだった。うっかりその事を忘れていた。手打ちにするのは早かったか、と一瞬歯を食いしばったが、ニシムラさんは照れ臭そうに俯き加減で真相を教えてくれた。
「あの、出版社のホームページに少し前から詳しい予告が出ているんです。それを見て、なるべく早く取り上げたくって……」
その後の流れは早かった。トダの仕切りでニシムラさんは撮影を再開し、マキは残りの閉店作業、二階から降りてきたリッちゃんと永子は京都土産の生八つ橋をいただき、俺はただぼんやりと椅子に座ってハイネケンを飲んでいた。
さっきまで両親と会っていたことを思い出し、改めて疲れを噛みしめる。あらかじめ決まっていたスケジュールなら、ここまで疲れないと思い込みたい。こんな俺の姿をトダのリードでニシムラさんが撮っている。わざわざ京都から来てくれたんだしいいか、と放っておいた。
彼女が帰る際、城山さんとの面識の有無を尋ねると、SNS上でのやり取りならあるという。どんな感じか具体的なイメージは浮かばなかったが「そうですか」と頷いてみせる。きっとトダには伝わっているはずだ。
「そうそう、こんなのもあるんですよ」
以前、公園で打ち合わせをした時に撮ってもらった、永子のポラロイド写真をニシムラさんに見せるととても喜んでいた。未発表のレア物といったところか。「ねえ、可愛いでしょう」とだらしない声を出しても以前ほど恥ずかしくないのは、歳を重ねたからだと思う。
時間が経つのが早いのも加齢のせいらしいが、様々な感覚が鈍くなった結果だと思えば別に不思議なことではない。だからあっという間に母親が入院する日になった。さっきから店の隅っこのテーブルで、父親がリッちゃんに数学を教えている。
今日の「授業」のテーマは「二次関数」だと思うが、アイスコーヒーを運んだ際に二人の会話を聞いてもピンとこなかった。父親が何度か口にしていた「ヘンイキ」という言葉は、「変域」と書くのだろうか。分からない。マキにも訊いてみたがやはり分からなかった。両親揃ってこんな調子だから、永子もきっと理系ではないはずだ。
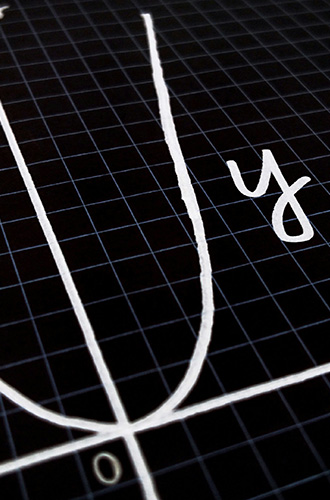
結局母親の入院に関して俺がすることは何もなかった。昨日、母親から電話で直接言われたから間違いない。
「明日のことなんだけどね」
「うん、一応病院には行くつもりだけど……」
「いや、いいわよいいわよ。気持ちだけありがたくいただいておくわ」
聞けば兄貴が病院まで車で送ってくれることになったという。もちろん父親も一緒だ。そうなると別に俺がいても特にやることはない。
「じゃあ入院中、どこかで顔出すよ」
「それもいいから。こういう時くらい、ゆっくりのびのび寝かせてちょうだい」
「いや、でもさ……」
「毎日お父さんには来ていただけるそうですから、本当に大丈夫。あ、そうそう、ワカメとマイタケ、まだもう少しあるから受け取ってね」
まだあるのかよ、と言ってはみたがそれで役に立てるならお安い御用だ。大腸がんを患う母親が手術のために入院する際、電車一本ですぐに行ける病院へ行かないのは正直なところ落ち着かないが、本人から直接拒まれては仕方ない。今、俺にできることは、ワカメとマイタケの追加分の受け入れだけだ。もちろんマキも全面的に協力してくれる。
一昨日もらった分はさっそく鍋料理として美味しくいただいた。カロリーも低いので、お年頃のリッちゃんも気にせず食べられる優れものだ。
「あ、あとお父さんから伝言よ」
「伝言? 何?」
「明日は数学を教えたら帰るって。ちゃんと帰れるから心配ご無用だそうよ」
泊まることをここまで拒否し続けるのは、ある意味しっかりしているのかもしれない。渋々納得した末っ子の様子に思うところがあったのか、電話を切る直前に「あんたは自分の家族、そして店のことを頑張らないと」と母親は言った。正論に言い返すのは一仕事だ。まあねえ、と呟くのが俺には精いっぱいだった。
「なかなかいい眺めだと思わない?」
そろそろ父親の「授業」が終わる頃、マキが俺に言う。制服姿の女の子と勉強を教えるおじいちゃん。たしかに店の雰囲気によく馴染んでいる。老若男女に愛されている店、なんてありきたりなキャッチコピーが浮かんだ。
病院の面会時間から考えると、結構早めに父親は店に到着した。てっきり制限時間いっぱいまで粘ると思っていたので、内心驚きながら「お疲れ様です」と大袈裟に頭を下げた。
「ちょっと予習しておかないとな」
そう言って空いている席に座り、取り出したのは年季の入った数学の参考書。立場が人を作る、というのはこういうことだ。
「黒板いらないの?」
「お客さんがびっくりするだろ」
会話のテンポだって悪くない。まだ本調子ではないにせよ、ずいぶんと持ち直した印象だ。昨日の電話で俺に正論を繰り出したように、病室のベッドに横たわったまま母親が荒療治を施した可能性はある。
その変化にはリッちゃんも気付いたらしく、学校から帰ってきた彼女は父親と二、三言話してから「先生の時はキャラが違うかも」と笑っていた。兄貴にLINEでそのことを伝えると、すぐに「朝から調子良さそうだったぞ」と返ってきた。母親が荒療治を施した場所は家だったかもしれない。そうマキに話すと「それって一昨日なんじゃない?」と推理した。
「ねえ、制服のままなのは私のアイデアよ」
「え?」
「リッちゃん。なんかそっちの方がいいじゃない? 老若男女に愛される店って感じで」
永子は理系科目に弱いだけでなく、キャッチコピーを作ることも苦手かも。もしそうなら俺たちのせいだ。
「まあ、夫婦じゃなきゃ分からないことってあるもんね」
「特に長年やってるとそうだろうな」
「あ、そうだ。今度京都に行ってみない?」
いいねえ、と答えた俺の声は少し上ずっていたと思う。それに気付いていないのか、マキは「いいよね」と声を弾ませた。
「ほら、この間もらった生八つ橋。あれ食べて浮かんだんだよね。京都行きたいって」
やっぱりニシムラさんはコケモモの使いだったのかもしれない。
(第45回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


