 母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。
母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。
by 金魚屋編集部
三十九.
お昼になって身体がバッテリー切れを起こしたらしい。リビングのソファーへ寝そべってウトウトしたまではいいが、烈しい脱力感におそわれ身体にスイッチが入らない。がらんとした広いこの家の中でだんまりを決め込んだ父親の顔を眺めていると、突如「ンゴゴーッ」とまるでダース・ベイダーが装着する黒い人工呼吸器の調子が狂ったときのような音を立てて、いまにも息を吹き返しそうに思えてならない。その顔をただ()呆けたように眺めていた。これから葬儀の段取りをつけなくてはならないというのに、どうしたことだ。つい昨日までは永遠に続くかと思われた日々のルーチンが、突然プッツリと途切れてしまった。これからは食事と薬の用意も洗濯も買い出しもオムツの始末もカテーテルを突っ込んでの吸引も、ヘルパーたちとのたわいのない会話も、そして父親の寝息に昼夜なく聞き耳を立てることも、もうないのだ。
悲しみも喪失感もなかった。これでせいせいしたという解放感もなかった。ただ前後左右も天井も底もしれない冥界のなかへひとり出し抜けに放り込まれたようだった。
雨雲レーダーを見ると、降り出すまでにはなお時間がありそうだった。大船のコーナンまで自転車で買い物がてら、手広から柏尾川沿いの道ではなく、わざわざ回り込んで高谷の交差点から渡内の坂を登ると、三〇二号線を車を追い越しながら下った。下りきった信号の向こうがコーナンだが、右折してS総合病院の前の道を通り過ぎた。季節は三月のはじめ、通りに沿って玉縄桜がそこかしこに開花していた。一年前のことが昨日のようだった。五階のあの病室から桜を眺めては、早く良くなって花見に行こうねと語り合ったものだった。母親が逝く直前のことだ。そのときは桜がこれほどに艶やかな花だとは思いもしなかった。あれから何という一年だったことか。早かったとか長かったとかそんな感慨に耽るどころではなかった。かつての心とこの心と、比べることすらできずにただ途方に暮れていた。
式の段取りは、亡母のときよりも面倒になりそうだった。田舎の小さくない農家の長男、社会的な地位もあった。ほんの数行だが新聞各紙に訃報も載った。すでに問い合わせも入って来ている。でもぼくは、もう決めていた。亡母と同様、自宅でこじんまりと家族葬で済ませようと。親族からすれば立派な葬殮をもって送りたいという気持ちは、土地柄からして分からなくもない。父だって、じぶんの父親つまりぼくの祖父の葬儀では実家の周りを大きな生花スタンドと溢れるほどの参列者で取り囲み、どうだ見ろと言わんばかりに華々しく式をとり仕切ったものだ。けれどここは郷里から遠く離れた鎌倉の地だ。縁の深かったひとたちもみな鬼籍に入るか高齢化している。Z学会のひとたちも呼ばなかった。いっそ藤枝の生家でという声もあったが、本人がわが家でと望んでいたのだ。

介護業界の輩というのは、どうも信用がおけないと前から思っていた。命日となった二月一五日以後、皆で示し合わせたようにぷっつりと連絡が途絶えた。一週間経っても一か月が経っても誰からもお悔やみのことばひとつない。電話もメールも一本たりとも寄こさない。お客が死ぬたびにいちいち弔問なんぞしていられない、それなら横並びでという話かもしれないが、ビジネスライクな関係ならばなおさらだろう。得意客が死んだのだ。それがお悔やみの電話一本寄こさず、金の切れ目が縁の切れ目とばかり、さっさと引き上げてハイ任務完了かい。そう言うお前の方こそ菓子折でも持ってお礼の挨拶に来たらどうだと言うなら、それこそ介護業界ヒエラルキーに淫した者たちの傲慢だろう。
どうにかこうにか式を終え荼毘に付し、最後までつき合ってくれた親族八人とM道路のSさんら二人をタクシーに乗せ鎌倉駅まで懇ろに見送って、遺骨を家に持ち帰り、家の中の配置を父親が退院する前の状態へ戻した。介護用ベッドは葬儀の前に業者が解体して運んで行った。すべてが片づいたところで身体が軟体動物のようにぐにゃりと潰れた。この日も眠れなかった。やはりあのイビキが不協和音のようにひびかないと調子が狂うのか。
眠れない夜をやりすごそうと、久しぶりにウォークマンを取り出した。何かあったらと思うと、気になってイヤホンで耳を塞ぐことができないでいた。それ以前に、ゆっくり音楽を聴こうという心持ちになれなかった。
この夜はセバスチャン・バッハのモテット第一番にはじまって、思いつくままにロ短調ミサ曲の「クレド」と「サンクトゥス」、ヘンデル「アルチーナ」から「Ⅴerdi Prati」、トマス・ビクトリア「聖週間の聖務曲集」の聖土曜日、LectioのⅠとⅢを聴いてから、モーツァルトの弦楽五重奏曲K五一六のアダージョと弦楽三重奏によるディヴェルティメントK五六三の変奏曲をたて続けに聴いた。聴くにつれ、一年のあいだに起きたできごとが音とともに舞い、灯篭流しのように蘇った。走馬灯の音楽。ぼくはモーツァルトをよくそう呼んだ。チロル民謡からとられた変ロ長調の主題をチェロが親しげにかなではじめると、このときも記憶は前へ前へと遡っていった。遡ってはまた遡る。どこまで行くんだろう。いつもとちがっていた。離岸流のように抵抗できない潮の流れに遠い沖まで連れていかれたと思ったら、ふと水中から浮かび上がってきたある光景がぼくを激しく揺さぶった。
昭和五十二年の夏のことだった。
妹の祐子は当時八歳、小学校の二年生だった。どこまでも青空が広がるひどくむし暑い日だった。広島に原爆が投下されたのと同じ日だった。いつものように母の乗る自転車の後ろの荷台にまたがって、鎌倉郵便局と旧・駿河銀行に挟まれた脇道を通り抜けようとしていたときだ。後方から来た白いライトバンが追い抜きざま二人に接触、ママチャリは横転した。妹は倒れた勢いで郵便局の鉄塀へ頭部を烈しく打ちつけた。救急搬送されたが「重篤な脳挫傷です。頭蓋骨の損傷が酷く一部は陥没して出血しています。ウチでは無理ですね」と断られ二つの病院をたらい回しになった末、駿河台のN大学病院まで転送された妹を、両親はICUの外で夜通し待ち続けた。ぼくはひとり家で待機していた。
そのとき目にした真夏の夜の帳の中に、四十年前へワープしたように突然投げ出されたのである。
漆黒の空を真白なちぎれ雲が大あわてで流れ、雲間からは地に降り注ぐ雨滴のような星がのぞいている。蛙たちが四方八方から恋の鳴き声を競っている。むっと匂い立つ草いきれの中、小さな川面からたち昇った数えきれないほどの蛍がいっせいに光で交信している。原っぱのそこかしこに散らばった濡れた星屑のかけらが、そして小川のほとりのいまは亡いあの懐かしいわが家の前景が――ベコベコの青いトタン屋根、そのトタン板を茶色に塗って囲っただけの白壁、その壁からはみ出るほど大きく縁どられたサッシ窓、大谷石のブロックを積み上げた小さな門、芝を敷きつめた中庭、そこで主の帰りを待つ、風に揺れるたびにきゅうきゅうと鳴るピンクのゆりかごブランコが――手に触れんばかりに迫り、ぼくを包み込んだ。それらはたったいまここに生きて呼吸していた。万感の思いに圧し潰されそうになって、ぼくは夢中でイヤホンを外した。音楽って何とおそろしいのだろう。時はあるようにみえて、じつはないのだ。この世界をつかさどっている何かありえない力が、いまを生きているぼくらの中にいつだって脈打っているんだ。

*
お墓をどうしたものか。
父親は曹洞宗だった。亡母はZ学会だった。墓も戒名も位牌もまだ無い。「戒名なんていらないのよ」と母は生前よく言っていた。でも妹がいる。こちらは戒名も位牌もある。眠っている霊園は富士山と駿河湾を眼前に眺める広々と開けた材木座の高台にあった。すぐ上にはかつて石原裕次郎と並ぶ日活の看板スターだった赤木圭一郎の墓碑がある。父の選びそうな立地である。ただ宗派を問わず受け容れてくれる代わりに、どこかの寺社が供養してくれるわけではない。
「あんた。ここでお参りしていればお墓なんて行かなくていいのよ」
和室に鎮座する大人ひとり軽々入れそうな仏壇を指して母は言った。黒檀に鳳凰の木彫細工が施され電動扉には金箔が奢られていた。ずいぶんと寄進したのだろう。
入ってもらうならその霊園しかない。宗派の問題も解決する。けれど家から四キロ先の丘の上までタクシーを呼んで行っても、さらに急な階段を上りつめなくてはならない墓所を、杖が頼りになった晩年の父親は億劫がって足も遠のいた。残ったぼくが歩けるうちはまだいいとして、いずれ遠からず無縁仏になる。
ぼくは日進の忠広叔父さんに相談し、かの地にある曹洞宗の寺を訪った。
「故郷に骨を埋めてやりたいんです。父はそのままお世話になりたいと思いますが、あとの二人はどう処遇してやればいいでしょうか」
事情を聞いた方丈さんはすぐさま言った。
「お母様も妹さんもこの機会にご一緒にされたらどうですか」
気がかりだった母親の信心のことは「もうよろしいのでは。仏さんは自由ですから」方丈さんのこのことばがぼくの背中を押してくれた。父母には戒名を授けてもらい、妹と三位一体の位牌を作る。墓を閉じ、祐子の骨と位牌は父母の骨壺と一緒に日進のお寺へ持参し、揃って永代供養してもらう。鎌倉での半世紀を超える三人の足跡はこれで無くなるが、ぼくが死ねば同じことだ。
*
三月一八日は春の彼岸の入り、妹の祐子の命日だった。雲ひとつなくおだやかで、めったにない日和となった。庭の沈丁花が甘くただよい、零れた椿は足元に紅い絨毯を作り、満開を迎えた白木蓮はいっせいに空と交わっていた。二十一で逝った翌年から数えて二八回目の命日墓参だった。生きていれば四十九歳、妹の生涯を二回り巡ってもお釣りがくる歳月がすでに流れていた。
ほんとうにいいのだろうか。祐子は鎌倉に生まれて死んだ。唯一の故郷をはじめて離れることになる。かつて二階堂の奥所、瑞泉寺の近くにあった生家から、同じ市内の大町へ居を転じたことがあった。現在の笹目に住む前の家、ぼくと妹の実家である。妹は当時九歳、お似合いのニットの帽子を脱ぐと、刈り上げた頭部には大きな手術痕が弧を描いていた。本人からすれば、それは降ってわいたような大事件だった。

――ここ どこのおうち
「この家はね、大町っていうんだ。祐子の家だよ」
――おおまち にかいどうの うちじゃ ない にかいどう いってだめ
毎日のようにそう訊かれることがなくなるまでには、数年かかった。自閉症の子にとって、じぶんの居場所がある日突然失われて、でもあって、けれどやっぱりなくて……それはついさっきまで踏みしめていた地面がいきなり消滅するような、じぶんの理解を越えたできごとだった。
――おうち こわす!
と言い出したのは、越してからまもなくのことだった。
でもいまはもう「仏さんは自由ですから」。十年住んだその家もすでに存在しない。
妹の墓がある材木座の高台まで片道四キロの道を歩いて往復した。墓閉まいを終え、二〇キロを超える骨壺を家まで抱えて運ぶと、父と母の遺骨のあいだに、両親が左右を挟むようにぴったりくっつけて並べた。「お帰り、ゆうちゃん。やっとお父さんとお母さんと一緒になれたんだね。これからはいつも三人一緒だよ。仲良く休んでね」涙がこぼれた。
この家を見守るようにそびえ立つ三本の大躑躅があでやかな紅白の蕾をふくらませつつあった四月の半ば、日進で追善法要、納骨式と永代供養を終えた。往路は鎌倉から四時間かけて、三人の遺骨を担いで運んだ。骨箱一つ二〇キロ超、両手で抱え持つだけでも困難なのに、それが三つである。山道で見かける歩荷さんのような恰好をしたって腰が持たない。けつまづいて万が一壺を割ろうものなら縁起でもない。
あれこれ探し回った末、行き着いたのが灯台下暗し。自転車、それも小径車を持ち運ぶためのやや小ぶりの輪行バッグだった。入れてみるとまるで設えたかのように横一列、ピタリと収まるではないか。とはいえ一つ間違えれば脊椎ヘルニアを抱える身、たちまちゴキゴキっとイカされる。たすき掛けにした横長のバッグの中心を支点に、背から腰へおんぶするようにして数十メートルずつそろそろ進んでは降ろして休み、休んでは進みのくり返し。家から駅へ、駅のホームからホームへ、階段を上っては下り、エレベーターではベビーカーのお母さんの顰蹙を買い、電車の中で幾度も尻もちをつきながらぼくは運んだ。地べたにコテンとひっくり返っては、起き上がり小法師のようにゴロンと立ち上がる。倒れた反動を利用して勢いをつけないと、ふたたび立ち上がるなんてマネはとてもできやしない。コテン、ゴロンのたびにウォォーっと汗まみれになって雄叫びを上げている喪服姿で頭頂の禿げかかったオヤジを、電車の乗客や通行人は目を合わさないよう遠巻きにしていた。
三人の戒名が刻まれた位牌を、代価に持ち帰った。
ヒデトシ一家のツアーはこうして終わった。
時は移り、令和の世を迎えた。世の中は、新型コロナウイルスがもたらした異界の中へ呑み込まれていった。
エピローグ
鎌倉の家を処分することにした。
習志野の自宅と鎌倉をほぼ一週間ごとに往復する、そんな生活が四年ほど続いた。移動に要する時間は二時間ちょっと、電車で一本だから手間はそうでもないが、経済的な負担がじわじわとぼくの首を絞めつけていた。固定資産税や交通費はもちろんのこと、光熱費も使用分だけでなく家ごとに基本料金がかかるから、倍とはいかなくても片方に住むより高くつく。あと一年もしないでぼくの貯金は底をつくところまできていた。どっちかを売ってどっちかに定住するしかない。
考えるまでもなかった。鎌倉の物価は観光地仕様と言っても過言ではない。大船や藤沢まで出れば普通のスーパーマーケットもドラッグストアもファーストフード店もあるのだけど自転車しか足のないぼくには雨天だとお手上げだった。何より手間なのは庭の維持だ。春から秋にかけて、庭木や雑草はあれよという間に伸びてくる。放っておけば虫がつく。真夏の炎天下でも容赦してはくれない。一日剪定したり草むしりをしているうちに熱中症で倒れかけたことも一度や二度ではなかった。けれど庭師を呼ぶ金なんてありはしない。移り住んではや五年、もはや潮時だった。

年末セールのたたき売りよろしく売りに出して、三か月で買い手がついた。両親が買った当時の価格に比べたら税務署も同情するほど足元をみられたが築三十年の中古物件、家ごと売れただけマシだ。
売れるまでの間、すこしずつ遺品の整理をはじめた。残すものと売るものと廃棄するものとを選り分けなくてはならない。残すものと言ったって、習志野の狭いマンションに置けるスペースなんて段ボール数箱分がせいぜいだ。それよりも仏壇である。マンション向けの小さな本棚サイズの仏壇を買い、その中へご本尊と位牌を納めることにした。あとはみな廃棄処分するしかない。とんでもない量だ。断捨離なんてものじゃないな。
前から気になっていることがあった。
隔週ごとにこの家へ来ると、庭の樒に折々の花を添えて活け、仏壇に手を合わせた。仏壇のあるこの和室に以前のとおり布団を敷いて寝ていた。二階には使い古したじぶんのベッドもあったが、なぜかこの部屋でないと落ち着かなかった。寝ていると真夜中にしばしば、ぼくの耳元で何かうなるような音が聴こえる。機械音のようでも、小さな子どもの寝言のようでもあった。目を覚まして肘をつき、よくよく耳をすませているとやはりひとの声だ。声の主は見えない。その声はぼくにしきりに言っていた。――親殺し。それでもぼくは光に吸い寄せられるあの羽虫のようにここへ来ずにはいられなかった。
ある冬晴れの日、ぼくは二階の父の書斎へ入ると、書棚に置かれた三十冊ほどのフォトアルバムをみな引っ張り出して片っ端からめくりはじめた。引っ越しの期日が迫っていた。せめて写真くらいは持っていかなくては。そう思いながらも何となく整理するのを先延ばしにしていた。
アルバムには父と母、妹、祖父母と親類縁者、父の勤めていたM道路の関係者、母と妹の通った幼稚園と小中学校、養護学校のクラスメイト、母のハワイアン仲間、父の趣味だった書道とカメラと俳諧仲間といった大小さまざまな写真が貼られていた。エミ子と亜矢の姿もあった。それらは父の性格を正しく反映して年代順に整然と配置され〝祐子の思ひ出〟〝亜矢の思ひ出〟などと自筆でタイトルが貼られて、各頁には一行ずつボールペンでコメントを書いた自筆の付箋まで貼ってあった。
ところが、それらのなかにぼくの写った写真は――一枚も無かった。ぼくが残しておいたはずの小中高校の卒業アルバムまで見当たらない。やはりそうか。家中の戸棚という戸棚を開け、引出しを引っくり返した。汗が頬を伝った。落ち着くんだ。戸籍謄本はいつぞや相続の関係から取り寄せて見たじゃないか。財布から免許証を引っ張り出した。オレのだ。顔写真も間違いなくオレだ。血迷うんじゃない。
父の書斎に隣接する四畳半ほどの細長いクローゼットの奥に、長さ一メートル、高さと幅四〇センチほどの錆びついた鉄製の衣装箱が中身の入っていないカメラバッグやゴルフセットなどと一緒に置かれてあった。おそるおそる開けてみると、埃とパラゾールの臭いを引き連れ、若いころのものらしい父の古着に埋もれて、一冊の真白いアルバムが出てきた。意図的にそこへ隠し入れられたのは明らかだった。背表紙には黒い太字の油性ペンで〝アツヒトの思ひ出〟とタイトルが書かれてあった。見たことのないアルバムだった。紙質の状態からするとそれほど古いものではない。
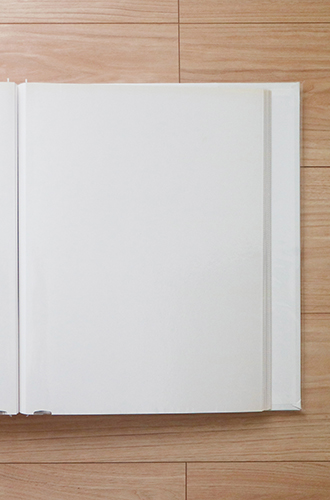
耳を突き破るような心臓の高鳴りを聴きながら、ふるえる手で表紙をめくった。そこに写っていたのは――白紙だった。それぞれの頁には何ひとつ貼られていなかった。貼られた形跡すらなかった。ただ何も書かれていない白い付箋だけがどの頁にも貼られてあった。最後の頁の中央に、ひときわ大きな付箋が貼られていた。剥がすと、そこには紙片と糊と黒い油性ペンの痕跡が鴉の飛来した爪跡のように残っていた。別の紙をいったん貼り付けて何かを認め、また剥がしたのだ。しかし何が書かれてあったかは読み取れなかった。
お前の〝思ひ出〟など何もありはせんってことか。言われるまでもない。実の父親をクソ呼ばわりしロクに面倒も看ず、一度は首に手をかけようとしたオレだ。あげくのはてに、わずか一年足らずで死へ追いやった負債はまだ清算していない。わかってるさ。ただ言っておくが、オレはあんたに負い目はあっても悔いているわけじゃない。同じ状況に置かれたら幾度だって同じことをくり返すだろう。それにしたって、いったい何してたんだ。オレの痕跡を注意深くこの家から取り除けていたのはなぜなんだ。遺品整理をはじめれば、いずれお前はこの白紙のアルバムを見つけ出すだろうってか。わざわざこんな手の込んだ仕掛けをいつやったんだ。本物の病人だった? そういえば家に戻ってきた時、毎晩のように懸垂していたよな。二階への階段を駆けるように上がっていたな。あんたってホントは何者だったんだ。〝アツヒト〟っていうヤツはどこの誰なんだ。いやそれは、むしろあんたの問いだったのか。
頭が弧を描くように旋回しはじめた。それまでぼくを取り巻いていたはずの世界が、ことごとく砂礫のように滑落していった。混濁したぼくの頭は斥力も重力も失った落葉のようにひらひらと舞った。舞いながら窓の外へ出た。ぼくは色のない世界へ没していった。
*
誰もいない波打ち際をどこまでも歩き続けていた。
幾万羽か数えられないほどの椋鳥の群れが音もなくいっせいに舞っては、フッと消える。と思うとまたべつの山の端から突然姿をあらわす。海のかなたからときおりたおやかな陽の光が射し込んできて、そのたびにセピア色というより脱色したようなあの山裾や無秩序に並べられた防波堤の消波ブロックや、足元で刻々とうつろっていく砂の紋様たちが世界を裏返しにしたようにがらりと姿を変える。
ふいに疾風が騒いだ。
仄かな、けれどなじみ深い匂いを引き連れあわただしく通り抜けていった。ああと呻くような声が漏れ出る。
春が来たんだ。いのちあるものもなきものもみな漂れ出る春が。南風は形にならない夥しい記憶の粒子を運んできて、小さくない混乱をぼくの中のいちばん奥まったところに引き起こした。いったいどうしたっていうんだ。ここはどこなんだ。入ってはならない見知らぬ土地へ踏み入ったという越境感覚におそわれぼくは佇んだ。
目の前に見えるのは三浦半島の先端じゃないか。岬の左手前にあるのは逗子マリーナのヨットハーバー、すぐ左はそれへ抜けるトンネルだ。ならばその上に続くのは披露山、そして小坪の丘陵にちがいない。ほら、そこに焼却炉の大きな煙突がのぞいている。そうだ昔から知っているじゃないか。いつも目にしていたはずだ。見慣れた近所の光景だっていうのにどうしたんだ。

ちがう。そうじゃない。以前もこれと同じ光景を目の当たりにしてまったく同じことを考えたんだ。同じ光景だって? ――湯舟に顔まで沈んだままなのは誰。祐子? いやお袋か。あのときもこの何ともいえない感じを忘れないよう記憶に止めておかなくてはと、思わなかったろうか。それともたったいま、そう思っただけなのか。考えようとするほどにそれが粒となり、南風に乗って、コンクリートの土手の片隅にひっそりと群れている色もかたちも名もないあの小さな花たちの中へ溶け入っていく。
頭上に圧力を感じて空を見上げた。
雲がいくつも激しく動いているのだ。
ひとつは見たことのない巨きさで、全体が黒光りしていた。縁の方は銀を溶かしたようで、中心へ向かって異様な速度で渦を巻いていた。雲の中心である渦の芯の部分はあやしいオレンジ色の光を放ちながら、漏斗となってぼくの真上へ低く垂れ込めてきた。釘付けにされてなお凝視していると、漏斗の芯部は渦の中をつき抜けて、はるか星宿の向こうまで透かし視えるほどしずかに澄んでいた。いつか視たおぼえがあるな。にわかにぼくの身体が前後左右へ揺れた。雲のふしぎな演舞にみとれているうちいつの間にか水の中へ入っていたのだ。揺れた拍子に足元の砂が引き波と一緒に崩れ、ぼくも崩れていく。水面は無数の雲母のかけらを散りばめたようにきらきら光っている。光の先端に和賀江島の岩礁がちらと見えたと思ったら、たちまちかき消された。水に浸かりながらも半身を起こし、肘を立ててすっかり両脚を伸ばしたぼくの目の前に広がっていたのは、とほうもなく大きな湯舟だった。――湯舟ってのはこう、とにかくデカくないとな。あれ誰かそんなことを言ってたな。あー何てあったかくて気持ちいいんだ。お袋と祐子が浸かったのはこれだったんだ。ん。まだ三月だというのにお湯みたいにあったかいって? そうさ、これはおかしいぞって思えるんだからオレ、まだ大丈夫だろ。こりゃ愉快だはははは――そうこうする間に波は肩の上まで呑み込んでいく。
そのとき、ぼくの前にいきなり一本の動画が立ち上がるようにして、ある情景が広がった。
二年前の、二月はじめの朝のことだった。
これは二年前に遡った現実の情景なのか、それとも二年間におよぶ長い夢をいまなお見続けているのか、いやそう感じられるつかの間の夢をいま見ているだけなのか。
ぼくにはもうわからない。でも、どれだって同じだ。
*
その前の晩、この家を訪ったぼくは父と母と三人でおでんをつついていた。
具材が足りなくなったので近所の井上蒲鉾店まで、ちょっと奮発したくなって買い足しに行った。それがきっかけになったか、翌朝、寝坊して二階の寝室から降りて来た父が「おい、たまには昼飯食いに行くか。天婦羅でもどうだ」と言い出した。
せっかくだから小町通りの「ひろみ」へ行こう、食ってからお前は津田沼へ帰ればいい。そんな話になって、歩いて向かう途中店に電話したら、混み合っていて早くても一時間以上は待たなくてはならないという。
「そんなに待つんじゃなァ」
「じゃここでいいわよ」
鎌倉駅東口駅ビルの二階にある和食の店へ入ろうと、ヒョコヒョコ階段を上がっていく母。こういうとき、母は決断が早い。
揃って天丼を頼んだ。
三人で外でランチなんて何年ぶりだろう。こうして会うのはもう最後かもしれないな。虫の知らせというわけではない。けれど、そう思ったことをこの後も心に刻んでおこうと、駅の改札をくぐるときに思ったのをはっきりおぼえている。「元気でおやりなさい」という母に続いて「じゃあ、しっかりな」と頷いて手を上げる父。その父が倒れたのはこのときから二週間後だった。
天丼を食べながらふと昔、伊豆の今井浜まで一家四人で旅行へ行った話になった。祐子は当時八歳だから小学校の二年生、交通事故に遭う直前だった。昭和五十二年の梅雨明けまもない七月末のことだ。ぼくは高校に上がっていた。家族旅行に加わるのはこのときが最後だった。

「あのときオレ、浜辺で水中メガネをいじくってたらいきなり割れちゃってさ。左の親指切ってけっこう血が出て大変だったんだよね」
「まあ、あんた覚えていたの、そんなこと」ニコニコと母。
「せっかく来たのに、海へ入れなくなっちゃってさ。ほら、まだここに縫った痕が残ってる」
「シズ子に祐子をみてもらって、お前を病院まで連れて行ったんだ。祐子がとにかく海が大好きでなァ」
「そうそう。浮き輪につかまって、波に向かって嬉しそうに手足をバタバタさせて、――こーゆーふう! って叫んで。
ことばは話せないけど、ちゃんと聞こえたよ。ねえねえ見て見て あたし上手に泳げるでしょ、って」
「あのころがいちばん幸せだったなァ」と父。その横でずっとニコニコしている母。
そのとき、ぼくたちのテーブルをそっと優しく包み込むように、そのひと隅だけ異なる時間が流れたみたいだった。
「オレだって同じだよ、オヤジ」
そう呟いた。
すると、このひとの朽ち果てて折れかかった肉体がぼくの頭上にあらわれ、ベッドに横たわっていたときの姿勢で垂直にするするすると降りてきた。それを両手で抱きとめると、あのはかなげな重みが、あの虚ろな瞳にたたえられた微光のうつろいが被さった。そしてぼくへ向かって笑みを浮かべた――ニコォーッと。
「これでほんとのお別れだね、オヤジ」
遠くからサイレンの音が近づいてくる。気づいたら、砂浜にうつ伏せになったきり動かないじぶんの残骸と、斜め上のほうからそれを見つめるぼくの肉体のない眼差しだけが残っていた。
(第17回 最終回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『春の墓標』は23日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


