 母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。
母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。
by 金魚屋編集部
二十五.
ひどく漏らしていた。
いくら臭っても汚くてもじぶんの手は汚さないと決めたぼくは、ヘルパーに電話して早めに来てもらうことにした。オムツを取り替え、車イスでダイニングまで連れて行ってもらい、食事を摂らせたところでヘルパーは任務完了、お引き取り頂く。一回につき一時間が契約条件なので越えたらタイムオーバー、延長料金を払わなくてはならない。高齢化の進んだこの界隈では、ただでさえ人手不足なヘルパーにはたいてい次のお客が待っている。もうすこしやってよなどとムリなお願いはきかない。
サシで向かい合うのは久々だ。北欧風のテーブルは永年使い込まれたせいであちこち傷がついているが、いい塩梅に黒光りしている。その上でひとり黙々と夕飯を食べている。介護用の宅配弁当は塩分控え目、食べやすいようご飯もおかずも柔らかく仕立ててある。せめて見た目だけでもと家にあった九谷焼の器にそれらをとり分け、レンジで温め直し、さらにコンビニで買い込んだミルクプリンや杏仁豆腐のなかに粉薬を混ぜ、トロ味を付けたコーンスープや味噌汁やお茶と一緒に出す。薬は十種類もの錠剤をすべて挽いて散剤にし、一包化してもらっている。
父親はいくら時間がかかってもいつもじぶんでスプーンを口へ運び、完食するまで手を止めない。ところがこの日はデザートのフルーツゼリーだけ摂ろうとしなかった。はじめて出すメニューではない。好きなリンゴ味だ。薬の混ぜ方が半端で苦かったか。テーブル越しにぼくの方へ手で押し除ける。「薬が入ってるんだ、一口でもいいから食べてよ」そう言ったところで素直に聞いたことは一度もない。亡母といい父親といい、いくら呆けても子の指図なんか誰が受けるかと、端からそんなハラだからこっちもむかっ腹が立つ。何度でも言うが、早く死にたければ服薬を拒否するもよし、摂食拒否もよし。オレは止めないから好きにしてくれ。
テレビのリモコンをしきりに弄ってチャンネルを切り替えていたが、観ることもなくスイッチを切る。沈黙がづり下がってくる天井のように部屋内を潰しにかかる。新聞をめくりはじめるが、眺めているだけで活字を追う様子はない。顎が外れるんじゃないかと思うほどの大あくびをするので「ベッドで横になる?」首を横に振る。ありし日の団欒の記憶にしばし浸ってでもいるのか。あるいはこうして半身だけでも起こしていなくてはと、衰えゆく細胞にいささかなりとも抗おうとしてか。七時、八時、九時……無為に流れゆく時に気が滅入るばかりなのでぼくは席を立ち、洗い物と翌朝の食事の下準備をはじめた。
ところが横目で様子をうかがっていると、例のつなぎ服のファスナーの留め具を覆っている襟元のホックを引きちぎろうとしきりに弄っている。それを外せばファスナーを下ろし、服を脱げるとわかっているのだ。股ぐらから延びているファスナーに添って指をそろそろと上に這わせていく。ほどなくホックへたどり着く。「認知症の方の手付きじゃ、ありませんわね」とヘルパーの長谷さんも感心していた。外されたら一巻の終わりである。「そうしたひとには外せない設計になっていますんで」介護用品店の店長がニヤニヤしながら持ってきた、たかが綿のパジャマ一枚で八千円もする代物である。

テーブルの真向かいに座り直して、ぐっと睨みつけた。ちらっとこちらを見たが反応する気配すらない。そのホックがオレとあんたの命綱なんだぜ。あんたがそいつを外したら、あんたとオレの親子の縁はそこで途切れるんだ……コックリしはじめた。やれやれやっと寝かせられる。ここまで四時間、すでに十時を回っていた。
このときぼくの心の針は大きく振れた。施設へ入れるしかない。このひととはこれ以上心を通い合わせることができない。家族としての情など微塵も感じない。家族っていえば、あんた死んだお袋に一度でも手を合わせたことがあるのか。そりゃショックだったろうよ。オレだって心臓が止まりそうだったよ。死を受け入れられないのはわかる。八十七になる年寄りにはキツいよね。独りベッドの上で昼も夜も何か月も暮らし続けていたらボケちまうのも無理はない。でもな、お袋は六十年ものあいだ、ずっとあんたに仕え続けてきたんだ。あんたが入院してからじぶんが死ぬその日まで毎日あのひとが良くなりますようにって言いながら、そこの仏壇に向かって一所懸命読経を続けていたんだぜ。あんたの時計をいつもじぶんの腕にはめてな。だからわざわざ目の前に大きな遺影と遺骨を置いて、庭の折々の花を活けているってのに、あんたは手を合わせるどころか目を向けようともしない。それで夫かよ。わかってるさ。お袋はじぶんのことをネタにオレがオヤジと諍いを起こすなんぞ望んじゃいない。でもなお袋、あんただって浮かばれないじゃないか。それについこの前なんて、ショートステイ先で何が不満だったかスタッフの女性に手を上げたって? そのくせじぶんより強いか偉いと思ったヤツにはへいこらする。あんたそんな男だったんか。これ以上一緒に暮らしたってお互い不幸なだけだよ。遺影に向き直って頭を下げた。もう限界です。家に連れ帰ってほんの一か月半しか経っていないけれど、このひとの面倒なんてこれ以上オレは看れません。すまんお袋。
その夜は眠りこけた。
*
翌日、午後四時を回ったところだった。陽はたそがれて、部屋の中は早くも薄闇に包まれていた。さっきからベッドの中でしきりにゴソゴソしている。いつもと様子がちがう。枕元に何か落ちていると思って眼をこらすと、入れ歯だった。じぶんで外したのか。下の歯をしきりに弄っている。「どうした。痛いの?」ムニャムニャ喋ろうとしてはいるのだが、歯が無いせいでなおさらことばにならない。具合が悪いと訴えているようだ。「口を開けて見せて」素直に開ける。中を覗きこむと、下の前歯にあたる位置つまり入れ歯がそこへ被さるはずの、もともとの前歯が抜けた穴に食べカスが詰まって痛むらしい。歯ブラシと爪楊枝でそろそろと慎重に取り除けてから、うがい受けに用いているサラダボウルにグチュグチュペーを三回させたが、完全に取り除くことはできない。ちょっと放ったらかし過ぎた。こんなふうにいつも協力してもらえれば、と言うよりじぶんの意思で出来ることは進んでやり、出来ないことは身を任せてくれるなら何の問題もないのだが、その「じぶんの意思で出来ること」と「出来ないこと」の範囲に本人とぼくらとのあいだで、いやそもそも本人の自己認識にズレがあるから、本人にとっては要らぬ節介をするなとなり、ぼくらにとっては任せてくれなきゃ助けようがない、となる。そうこうするうち「出来ないこと」の勢力範囲がじわじわと拡大していく。わかっていても手遅れになる。

その夜の十一時を回っていた。さっきから父親がつなぎ服のホックを外そうとしてずっと弄っている。思わず声を上げた。
「そいつを外したら終わりだぞ。わかってんのか」
おっと無視かよ。そんな言い方でわかるわけがないか。
「お袋、何とかしてくれえ」
声を張り上げたらやっと止めた。がしばらくするとまた弄りはじめる。
「このクソオヤジがちっともオレの言うこと聞いてくれないんだよお袋」
左へ九〇度回転すると、横たわっている父親に向かって、
「何だよ。気の触れた息子に絡まれて困ってるってか」
あんたがそんなふうに狸寝入りしているとき、いつも眉間に皺を寄せているのはオレのせいか。オレはオレで、あんたを父親そっくりの着ぐるみを着たゾンビとしか思えない。どっちがゾンビかって話は横へおいて、この後も夜遅くまでしきりにゴソゴソゴソゴソと動いているので気になってしかたない。午前一時だったか二時だったか記憶もおぼろだが、気づいたらベッドへ寝そべったまま右手を垂直に伸ばし天井を指差している。その指が意味不明な奇妙な動きをくり返している。何か天井に見えるのか。宇宙文字でも描いているのか。それとも直立して前へ直れをしているつもりなのか。天啓でもおとずれたか。眺めているとゆっくり肘を曲げ、降ろしたその手を胸元のホックへあてがうとまたぞろ外そうとする。しつこい奴。
「それを外したら、親子の縁を切るからな」
手を止める。アイツ居おったのか、くらいの反応だろうか。またはじまる。
「親子の縁を切るって言ってんだろがあ。何とか言えよ」
また手を止める。かと思ったらまたホックを弄る。野郎、わかってやってるな。からかってるのか。それとも意地になってるのか。
「福三さんも信乃さんも、このありさまを見て悲しんでいるぞ」
父親の両親つまり、ぼくの祖父母の名を口にすると、挙げた手が止ったまま固まってブルブル震えている。しかし震えているのはぼくの発したことばへの感情的な反応だとは思えない。それにしてはあまりに無機質な動きだった。死者までも総動員して利用するあさましさをふり返るヒマもなくまた記憶が途切れた。
三時半になろうとしていた。窓外からはしきりに秋の虫たちの音が聴こえてくる。まだ大合唱と言うには早いが、耳を澄ませているといつも幽冥の境へ誘われずにおれないのは、なぜだろう。そこへ「グゴォーッ」と不規則かつ不自然な父親の呼吸音が被さり、倍音と非倍音とが入り混じって、奇妙てきれつなハーモニーならぬ不協和音を鳴らしている。ひとが生きるためには、米粒ほどでも希望がなくてはならない。なにもなくたって、芥子粒ほどの未来がなくてはならない。ただただ生き存えているというだけ、そんな状態にひとは耐えられない。眠りはそのためにあるのか。だからこうして眠ってばかりいるのか。この老人にとっては、眠ることが生きるというそのことなのか。
二十六.
にわかに動きが活発になった。ずっとモゾモゾし続けている。服を脱ごうとしている。奴さん、オシッコをしたいのだ。ズボンを脱ごうと手をかけても、かけるべきところがない。股間の周りはファスナーで厳重に閉ざされている。手はそれを川の源流をたどるように腹から胸へそろそろと這っていく。胸元にファスナーの起点はある。ところがそこにあるはずのファスナーの引手の上からホックが被さっていて、そいつを外さないと引手に触れることさえできない。そこまでは解明できた。ならば、とホックを弄り回す。引きちぎろうとする。いくら引っ張っても取れないのでいったんはあきらめるが、またすこし経つと再開する。執拗に弄くり、引っ張る。認知障害と診断されたひとの仕草とはとても思えない手指の動きである。外すことはできないと皆からいわれても安心できない。ホックの中心部にスイートスポットがあり、外すにはそのど真ん中を指先で強く押下すればいい。健常者でもなかなか気づかないだろうそれを、認知症のひとはなおさら、引っ張るばかりで押すという真逆の動作を思いつけない。そんなカラクリだが、ぼくは父親をナメてはいない。いつかは開けるにちがいない。子どもの頃から何をさせても不器用でのろまなぼくとちがって、頭の回転は速いし指遣いもはるかに達者だ。父親は昔、子どものぼくを「ゴジラ」にかこつけて「お前はいつもグズラだなあ」と口癖のように言ったものだ。しかもいったん目的をこうと定めたときの父親は、なし遂げるまでけっして退かない。いつかの階段駆け上がり事件でぼくはその片鱗を見せつけられていた。
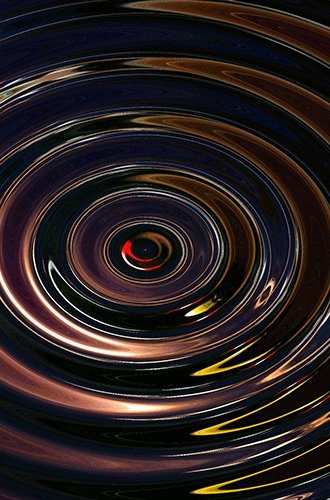
昼夜逆転した眠りを改善しましょう、と医師が睡眠導入剤を処方してくれたが一向に効き目はなかった。デイサービスのスタッフと家族との連絡用ファイルには、たった一行こう記されていた。「お昼はずっと傾眠されていました」寝かせておくのがお前らデイサービスの仕事か。
百均ショップでふとん叩きを買ってきた。
本人を叩いて憂さを晴らそうというのではない。かと言って不自由な相手の身体に直接危害を加えるのはアンフェアだとカッコつけるガラでもない。ただ深夜ゴソゴソ起き出して胸元のホックを外そうとしている父親のベッドを囲っている鉄の柵を、そいつでガンガンと叩いて威嚇してみたくなったのだ。
ぼくは父親の好きだった藤山一郎の「東京ラプソディ」(作詞・門田ゆたか、作曲・古賀政男)の替え歌を唄いながら、
「そーろそろオーレーさァー」ガンガン。
「ぶちキレるー ぶちキレるゥー」ガンガン。
「ぱーらだいすぅー」ガンガン。
「たーのーし この夜ォー」ガンガンガン。
「こーこーは みやこー」ガンガンガン。
「あーあーアはじまったーよ 花のオーヤジ ショー」ガン!
「……」
「わかってんのかテメエ」
「……」
ぼくのやっていることは、どのみち高齢者への虐待でしかないだろう。だがこうしてさんざん罵り虐げたことを、この老人はどこまでおぼえているのだろうか。忘れずにしっかり記憶にとどめてくれ。忘れるくらいなら、オレを憎み呪ってくれ。切にそう願った。そんな父親とぼくの関係を、二人の置かれている状況を正しく語っているのは、この小さなホックひとつだけだった。
ある朝いつものようにヘルパーが父親をベッドから起こし、車イスに乗せようとしたら、じぶんで移ると言ってきかない。いや、口に出して言えないので態度で示すのだが、寝てばかりで筋力のすっかり衰えたいまの父親にそんな力がないことは明らかなので、手助けしようとする。その手を振り払って「こいつめ」と怒る父親。今度はぼくが怒る番である。
「このままじゃあ、ホントに寝たきりになっちゃうだろ。それじゃイカンから助けも呼んで、せっかく来てもらっているのに何だ」
すると意外にも大人しく聞き入れた。車イスに乗せダイニングへ連れて行くと、ご飯とおかずも残さず食べた。はじめてのことだ。何だやれば出来るじゃん。
器質的な損傷はとうぜん影響しているだろう。認知症といってもタイプや進行状況はそれぞれだ。けれどアルツハイマー型ならともかく、認知症などという実体ある病態が脳内のどこかにあるとは思えない。ひとそれぞれの進行に応じて、ボケたフリとまでは言わないが、都合の悪いことは忘れる一方、都合の良いことはしっかりおぼえている。そんな恣意的な面は否めないと思う。じっさい感情と記憶力には、浅からぬ関係があるという有力な学説がある。

「記憶障害のひとは記憶にアクセスする、または入出力にあたる機能すなわち海馬のはたらきが衰えたのであって、記憶それ自体が損なわれたわけではないという意のことをアンリ・ベルクソンはすでに戦前から主張していました。認知症は治るとまでは言わないけど、ボケの対象範囲を動かしたり狭めたりする、あるていどの可塑性は認めていいんじゃないですか。どうボケるかに、そのひとの個性が出るんじゃないですかね」
ある日訪れたいつもの訪問医にそう話したら、相模湾沖の海の底で見たこともない珍魚に出くわしたような目でぼくを見たが、否定はしなかった。
口がきけなかったら、態度で示せばいいのに。オシッコがしたくなったら「オレはトイレへ行きたい」と意志表示すればいいのに。その時点でぼくやヘルパーの負けである。なぜならぼくもヘルパーもそのひとを介護し、生活を支援するためにわざわざ来ているのだから、トイレへ行きたいという本人の意志を無視することも、拒むこともできないからだ。しぐさひとつでいい。意思表明の能力をこの老人はまだ持ち合わせているはずではないか。だったらお前が察してやれよ。トイレに行きたがっているとわかるなら、お前が連れてってやればいいだけじゃないか。ちがうのだ。いまの父親にとっては、ベッドがトイレなのだ。だから起こしてトイレに連れて行こうとしても「何をする」と怒るだけ、ましてオムツをトイレと思って出してくれと頼んだって、聞き入れるわけもない。そりゃ難しいよな、尿瓶だって出来ないのに、オムツの中にしろと言われたらやっぱイヤだよな。そうは思いながら、どうしても通じないからあんたってさァ、畜生にも劣るんだよとついつい口走る。それでもあんた人間かよと罵られたならただひとこと「そうだ」と返せばいいのだ。本人はただ立ちションしようとしているにすぎず、便器がたまたまベッドだというだけのこと。立ちションを常習にしている動物は生物学的な人間の男くらいだ。そこで「そうだ。人間以外の何だというんだ」と返されたらこっちはぐうの音も出ない。なのに無反応だからついぼくはエスカレートする。罵り、貶めるほどに自ら畜生道へ堕ちていくだけだと思いはしても、いやそう思えばこそやめられないのだ。堕ちゆくことの快感をかみしめながら「よォ、今夜も一緒に地獄めぐりといこうぜ、なァオヤジ」真夜中にひとりわめくぼくをよそに、ギシギシギシギシと音を立ててベッドで黙々と懸垂を続ける終始冷静な父親。
(第10回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『春の墓標』は23日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


