 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
二十三、『三四郎』第十三章 ストレイ・シープ
a:事件
原口さんの絵が完成する。丹青会では一室の正面にこの大作を掲げ、その前に長い腰掛けをおく。タイトルは「森の女」である。
登場人物たちのなかで、最初にこの絵を見に訪れるのは美禰子とその夫である。夫は『「この団扇をかざして立った姿勢がいい。さすが専門家は違いますね」』とモデルのポーズを誉めるが、それは美禰子の提案したものであると原口は告げる。それを聞いて、夫は素直に喜ぶ。
「確かにこれは美彌子の決めポーズなんだよね。第二章で、三四郎が初めて美彌子を見る場面にはこう書かれてただろ? 『まぼしいとみえて、団扇うちわを額のところにかざしている』」
「ええ、単なる読書じゃなくって、体験として記憶してるから忘れてないわ。いずれにせよここは二通りに解釈できそうね」
「というと?」
「つまり、妻の提案したポーズがすばらしいということで純粋に喜んでいるとも取れるし、自分の所有物が優秀であることを誇りに思う所有者の感覚とも取れるってことよ。たとえば、自分の所有している馬がレースで一等賞を取って喜ぶオーナーみたいな感覚かしらね」
「なるほどね。まあ両方の感覚が同居してるっていうのが、無難な落としどころかな」
「でもって、問題はこの場面の直後だよね」
そうなのだ。いまなお、時限装置付きの改竄文が挿入されているのはまさにここなのである。長い道のりだったが、われわれはついに、問題の箇所に到達したことになる。挿入された文は、文体的には地の文になじませてある。けれども、内容的には明らかに異様だ。これで物語が終わるという場面だから、余波はあまりない。けれども、この文が挿入されることによって、作品のトーンが大きく変わってしまうのは疑いようのないところである。
「しかも、原文攪乱ウイルスが潜ませてあるから、下手に外そうとすると、本文全体に感染して『三四郎』という作品そのものが支離滅裂になってしまうわ。それどころか、新型の播種爆発型だったりすると、っていうか十中八九間違いなくそうなんだけど、隣接する他の漱石作品、あるいは明治期の作品へと感染が拡大する可能性がある」
「なんとかしなくちゃね。パスワード欄に、正しい犯人の名前と、そう推理した理由を打ちこまないと、時限式だからやはり感染はスタートしちゃうわけだし」
改竄文、あるいは新たに挿入された文は、こんなものだ。
(LOCKED)
「警察が、驚くべき報せを持って、二人を捜し当てたのは、まさにその絵の前においてであった。報せを聞いて夫は驚きの声を発し、美禰子はその場にくずおれた。驚いた原口が問うと、答えられない美禰子の代わりに金縁眼鏡の夫がこう答えた。
「信じられないことが起きた。恭助が」
「恭助? どうしたね。とうとう馬鹿囃子でもやったのか」
原口の口調は、相変わらず暢気である。
「死んだのだそうです」
「死んだだって? この間会ったときはあんなにぴんぴんしてたのに」
信じられないという風に原口は、髭を撫でた。まだからかわれてるのかもしれないとでも思っているかのようだった。
「いえ、警察がいうのだからたしかでしょう。誰かに背中を刺された。それ自体は大した傷ではなかったのだが、逃げようとして線路に落ちて、轢死したのだということでした」
警察に守られるようにして二人が去る後ろ姿を、原口はただ呆然と見送っていた」(LOCKED)
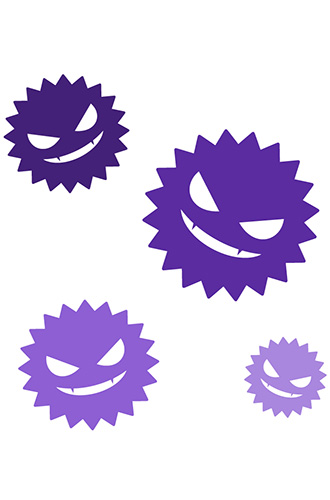
b:森の女/迷羊
そして、開会後の第一土曜日に、残りの登場人物たちがやってくる。つまり広田と野々宮と与次郎と三四郎の四人である。挿入された文は、さっき挙げた箇所だけで、このことを四人が知っているのか知らないのかについての説明などはいっさい加えられていない。しかも、この後は原田も登場しないから、四人が事件について誰かと話すということもない。
「「森の女」を見ながら、広田が『「佐々木に買ってもらうつもりだそうだ」』と与次郎をからかうと、与次郎は『「ぼくより」』と言いかけて三四郎を見る。三四郎をからかおうと思ったんだろうね。でも、三四郎がむずかしい顔をして座っているので、黙ってしまうって展開になる」
「与次郎ですら、軽口がたたけない雰囲気を三四郎は醸し出してたってことよね。この当たり、挿入文と呼応するように読めなくもないわよね」
「広田と野々宮は『技巧の評ばかりする』んだよね。菊人形の時もそうだった。結局二人は、どこまでも批評家であって、自分をさらけ出すことはしないわけだ」
「でも、そんな野々宮だけど、ちょっとだけさらけ出すわよね」
「うん、鉛筆を探して隠袋、つまりポケットを探ったときに、美禰子の結婚披露の招待状が出てくるわけだ。でも、それを野々宮は『引き千切って床の上に捨て』るんだよね」
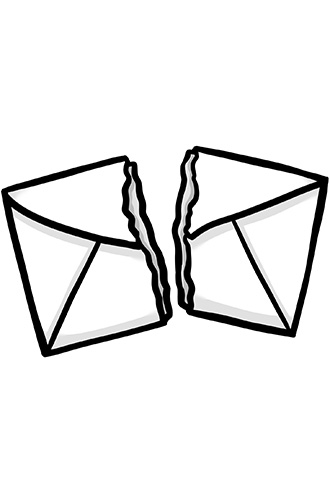
「だめよね、ちゃんとゴミ箱に捨てなくちゃ」
「はは。でも感情をさらけ出すのはその一瞬だけだ。すぐに広田と他の絵を見始めるわけだからね。そうやって、野々宮は自分の本心というものから目を背け続けるわけだよね」
「三四郎は、帰省していた熊本から戻ったときに招待状をみるのよね。とっくに結婚式は終わっているわけだけど」
「ここは不思議といえば不思議だよな。だって、本当に来てほしかったら、熊本の実家の住所を親しい野々宮から聞けたはずだからね。よし子を通して聞くこともできたはずだ。つまり、美禰子は三四郎に来てほしくなかったってことになるよね」
「あくまで三四郎の中で、自分は絵としての虚構の女でありたかったんじゃないかしら。知的で、おしゃれで、生意気で、謎めいた新しい女として三四郎のなかにとどまりたかったんだと思うわ。家制度に翻弄される生身の社会的弱者としての自分を見せることで、その幻想を壊したくなかったんだと思うわ」
「たぶん、そうだろうね。でも、三四郎にはもうわかってるわけだ。だから、与次郎に『「どうだ森の女は」』と問われて『「森の女という題が悪い」』と答える。『森の女』っていうのは、広田先生の夢のなかの少女のように、永遠に絵でありつづけなければならない。現実に翻弄される美禰子はもう森から出てしまっているわけだから、『森の女』と呼ばれる資格はないんだよね」
「広田先生の『森の女』は、広田先生の無意識のなかに絵として残りつづけて、広田先生という存在を深いところから支配しているわけよね」
「それに比べると、美彌子は蛇の抜け殻みたいに、絵だけ残して、現実の肉体は別のところに行ってしまった」
「いやむしろ、この絵の方が本体かもしれないわよ。ワイルドの『ドリアングレイの肖像』みたいに、なりたかった自分を絵に留めたってことかも」
「なるほど、認めたくなかった社会的弱者としての自分は、家制度のなかに取り込まれて、ただの妻という存在になり果ててしまったわけだものね。それも、帝国主義を支える政財界の男の妻に。つまり、帝国主義を影から支える存在になり果ててしまった。そういう意味では、肉体のある自分の方が抜け殻なのかもしれないな」
「だから、三四郎は『ただ、口のなかで迷羊、迷羊と繰り返した』のね。「森の女」でいたかったのに、その理想を貫けず、現実に負けて「生身の女」になってしまった美禰子の弱さをなじったってことかしら」
「同時に、自分のことも指しているのかもしれないよ。誰が迷羊なのかを、三四郎ははっきり口にしていないからね。もしかしたらだけど、故郷に戻ったときに、失恋の痛手もあって、母親の勧めるままにお光さんとの縁談を飲んだ可能性だってあるからね。自分自身もまた、理想と現実の間をさまよって、結局現実に破れた迷羊だという意識もあったのかもしれないな」
「こうしてみると、三四郎にとって、ほとんど描かれない九州、あるいは熊本がすごい求心力をもっていることがわかるわね」
「そうね。その辺にきっと何か鍵があるはずよ」
(第38回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


