 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
二十二、『三四郎』第十二章 ヘリオトロープ
a:暗闇の男
演芸会の二日目、三四郎は与次郎に頼まれて広田を誘いに行く。広田は一緒に出かけはするが、会場に入ることはせず『また暗い方へ向いて行』ってしまう。
「さすが、偉大なる暗闇だ。明るい方にはいかないんだな」
「出世も名声も望まず、結婚も望まず、新しいものを追いかけもしないのよね。そして、自分の悪評が立つことにも怒らない」
「それは、三四郎の根拠のないプライドとは正反対のものなのかもしれないな」
「根拠のある自己滅却みたいなものよね」
「すくなくとも、いわゆる『男性的』な姿勢じゃないのは確かだな。三四郎は、臆病ながらも『男性的』欲望を露わにしているからね。『暗闇』っていうのは、明暗でいうところの暗だから、自分にも人からも見える明るい方へいこうとするのが『男性性』だとしたら、広田にはむしろ『女性的』な側面があるってことかもしれないね」
b:尼寺へ行け
『薀蓄』によれば、文芸協会の演芸会は、実際にはこの物語が書かれる前の年の明治四十年に第二回が催されている。そして、本文に描かれるように、杉谷代水が書いた『大極殿』のような雅劇、『ハムレット』のような洋劇、逍遙の『浦島』のような伝統芸能など和漢洋ががミックスされたものであった。『ハムレット』の上演は、後の新劇の源流となる。また、こうした和洋混交路線は、坪内逍遥の提唱によるものだった。まさに、古き日本と、新しい西洋とが同居していた明治そのものを体現していたともいえる。
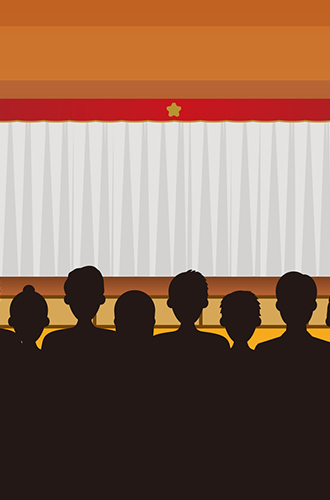
「でも、三四郎には『大極殿』はわからないし、『ハムレット』も集中して見れはしない」
「やっぱり興味があるのは女なのよね。隣の人の噂話で知名の人の名が出るのを幾度か聞くわけだけど、『三四郎はおかげでこれら知名な人の細君を少し覚えた』と、女性ばかり見ている。隣の人も同じで『わざわざ眼鏡をふき直して、なるほどなるほどと言って見ていた』ってあるから、それが男性一般の態度っていいたいのかもしれないけど」
「いずれにせよ、三四郎は男性一般に含まれるわけだ。その後は、美禰子をやっと見つけるけど、その隣に野々宮がおり、よし子がいることにも気がつく。さらにそこに原口が近づいて行って合流するのを見る」
「三四郎は、原口をうらやましく思うのよね『ああいう便利な方法で人のそばへ寄ることができようとは毫も思いつかなかった』って。でも自分もやる勇気は出ないのよね」
「近くへ行く勇気はないので、あるいはないから、三四郎はやがて始まる『ハムレット』を見ながら、美禰子をも見る。『ハムレットに飽きた時は、美禰子の方を見ていた。美禰子が人の影に隠れて見えなくなる時は、ハムレットを見ていた』」
「って、つまりは美禰子を主として見てるってことよね」
幕間に美禰子とよし子が席を立つ。それを見て、三四郎も席を立つ。
「目的は明白だな」
「ええ、美禰子に会いに行こうとしたのよね」
「ところが、そうはいかない」
「『二人は廊下の中ほどで、男と話をしている』そして、『男の横顔を見た時、三四郎はあとへ引き返した』。つまり金縁眼鏡がいたわけね」
「途端に三四郎は逃げ出してしまう」
「ほんと意気地がないわね。現実を受け入れられないのね」
「受け入れるにはつらすぎるんだろうね。下宿に戻って『床の中で、雨の音を聞きながら、尼寺へ行けという一句を柱にして、そのまわりにぐるぐる彽徊』する」
「恨み骨髄ね。俺と結婚しないなら尼寺へ行けってわけね」
「いや、結婚まではまだ考えてないかもしれないね。俺とつきあわないなら尼寺へ行けくらいかな」
「つまり、他の男とつきあうなら尼寺へ行けと」
「ハムレットは結婚したくなかったのだという広田と、劇を見てハムレットは『結婚してもよさそう』だと思う三四郎の対比だね。結婚願望のあるハムレットは欲が深いんだな」
「だから、絶望も深い。で、そのまま熱を出す」
「訪ねてきた与次郎に、『演芸場が暑すぎて、明るすぎて、そうして外へ出ると、急に寒すぎて、暗すぎるからだ。あれはよくない』と風邪を引いた理由を三四郎は説明するよね」
「著名人が集まってまぶしすぎる世界と、何もかも失って絶望した世界の対比かしらね」
「この後のやりとりがおもしろいと俺は思うね」
「どこ」
「『「いけないったって、しかたがないじゃないか」
「しかたがないったって、いけない」』
ってとこ。つまり、与次郎の言葉は、美禰子が金縁眼鏡の男に取られるのはしかたがないという意味と重なり、それでも自分は許せないという三四郎の思いがその返答となっているってことだ」
三四郎は、与次郎に美禰子の結婚のことを聞く。どうも相手は野々宮ではないらしい。与次郎は、『「ばかだなあ、あんな女を思って」』と三四郎を憐れむ。同い年くらいの女にほれてはならない、『二十前後の同じ年の男女を二人並べてみろ。女のほうが万事上手だあね』という。
「で、与次郎が自分の女の話をするのよね」
「ひどい話だよね。文科の撰科生なのに、医科の学生だと偽って女と関係し、縁を切るのに長崎へ黴菌の試験に行くと嘘をつく」
「正体がバレる前にずらかろうとしたわけね」
「で、その女が林檎を持って駅に送りに行ったら与次郎はいない、というわけだ」
「でも、そんなひどい話に三四郎は愉快になるのよね」
「まあ、エピソードそのものはひどいわけだが、当事者の与次郎が自分が困った話としてしか話さないからだろうね。相手に迷惑をかけたことよりも、自分が閉口したことしか眼中にないんだから」
「ある意味女をバカにしてるのよね。そして、そういう自己中心的発想、男性中心主義の発想に根ざす女性に対する蔑視に三四郎はいやされたのよね」
「与次郎が医科生のふりをするというところには、世の女性が結局は男性の権威になびくのだということが、示されている。男性は権威を帯びなければ意味がない存在でもあるわけだ。女性がそのままの生身で存在しているのとは大違いなわけだね」
c:お兄さんのお友だち
続いて、与次郎が『美禰子に関する不思議』を説明する。つまり、よし子と美禰子に同一人物との結婚話があるというのである。その謎を解明するために、与次郎を通して、よし子を三四郎の見舞いに来させるよう手配することになる。三四郎は、『「病気が直っても、寝て待っている」』と答える。
往診に来た医師が、インフルエンザであることを告げる。翌日、寝ているとよし子がやってくる。『ちょっと入るのを躊躇した様子が見える』が、結局入ってくる。
「そりゃあ、未婚の女が、独身男が寝ている部屋に入ろうってんですもの。躊躇するわよ」
「明治時代なら、なおさらだろうね」
「でまあ、入ってきたよし子に、蜜柑をごちそうになった後、美禰子の結婚話を聞くことになるのよね」
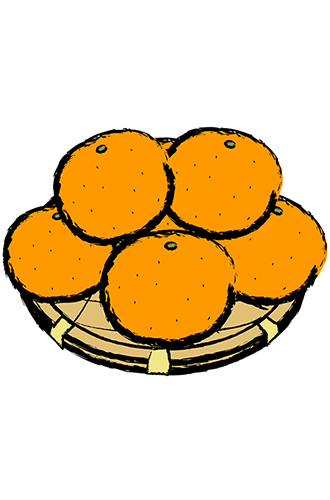
「謎解き的には、よし子の、『「私をもらうと言ったかたなの。ほほほおかしいでしょう。美禰子さんのお兄さんのお友だちよ」』という言葉で、すべてが判明することになるわけだ」
「そうね。嫁には『「行きたい所がありさえすれば行きますわ」』と答えるよし子が、その縁談を断り、とにかく結婚を急ぐその男性が、それじゃあと美禰子に白羽の矢を立てたってわけだ」
「結局、自立している女性はよし子のほうだってわけかしら」
「いや、違うだろうね。家がしっかりしていたから、よし子には選択権があった。兄が結婚して家を失う美禰子には、選択権がなかったということだよ。個人の気質の問題じゃなくって、明治時代の家制度の問題だねこれは」
「ねえねえ」
不意にいらずらっぽい笑みを浮かべて高満寺が、俺に一枚の紙を示した。この体格の人には「おい」とか「おら、そこのオマエ」とか言われた方が落ち着くような気がするのはなぜだろう。
「なにそれ?」
「ええとね、まあ漢字テストかな」
「そんなことしてる場合じゃないだろ、今は」
「まあ、いいから、ちょっと見なさいよ」
最初は、「開巻驚奇 暴夜物語」とある。
「なんだこれ。かいかんきょうき、ぼうやものがたり?」
「わかんないでしょ。これって、『千夜一夜物語』のことなのよね。一八七五年に永峯秀樹って人が翻訳したときのタイトルよ」
「へえ、なんで暴夜なんだろうね」
「知らないわ」
知らないって、自分から問いかけておいてほんと適当な奴だ。。
「じゃあ、次はこれ」
しらっと第二問にうつる高満寺。
「鵞瓈皤児回島記」。
なんじゃこりゃ?
「読み方もわからん。最後はかいとうきかな」
「そう、がりばあかいとうき、って読んでジョナサン・スイフトの『ガリバー旅行記』のこと。一八八〇年に片山平三郎が翻訳したときのタイトル」
「だから、こんなことに何の意味が?」
「わかったわよ、じゃあ最後はこれね」
「甸国皇子 班烈多物語」
「ははあ、わかったぞ」
ようやく高満寺の意図が読めた。
「皇子ってあるから、あれだな。つまり、これはハムレットだ。読み方は全然わかんないけど」
「そういうこと、でんまーくおうじ、はむれっとものがたり、って読むわけよ。一八八五年、坪内逍遥の翻訳で出たみたいよ」
明治時代がまさに漢語の文化であったことがいたく了解された。いま俺たちが、流行語が中国で漢字表記されるのに感じる違和感に近いものが、そこにはあるように思った。
迪斯尼乐园(ディズニーランド)、禾球影城(ユニバーサルスタジオ)、麦当劳(マクドナルド)。
d:ヘリオトロープ
数日後、病気が治った三四郎は、里見家を訪ねる。よし子が出るが、美禰子は教会に行ったと聞かされ、三四郎は教会に向かう。
「ここまで行動があからさまだと、もはや誰の目にも三四郎が美禰子に夢中なことは明白よね」
「三四郎は、漏れ聞こえる賛美歌を聞きながら『美禰子の声もそのうちにある』と思う。外套の襟を立てて待ちながら、『美禰子の好きな雲』を見上げる」
「もう美禰子尽くしね。その雲を見ながら、広田の家を掃除したときに二階から一緒に見た雲を思い出し、田端の小川の縁に座ったことを思い出し、そしてストレイ・シープを思い出す」
「すると、雲が羊のかたちに見えるんだよね。まさに風景そのものまでが、美禰子に染め上げられて見えているっていうわけだ」
「でも、過去を回想するってことは、終わりのサインでもあるわよね」
「うん、実際、三四郎は終わりを覚悟して来ているわけだからね」
「だから、お金を返すのね」
「そうだね。美禰子としては、象徴的なかたちででも作り上げた絵としての自分に恋してくれたひととのつながりを維持したかっただろうけど、虚構の美禰子と現実の美禰子の区別がつかない三四郎には、そういう美禰子の気持ちはまったく見えないからね」
「素直に受け取る美禰子の中で、このとき絵としての自分は死んじゃったわけよね。もう現実世界にいる生身の女、結婚という制度に取り込まれていくただのありふれた女になるしかなくなっちゃうわけよね。そう考えると、この場面は結構切ないわね」
「最後の残り香が、ハンケチに染み込ませた香水の匂いというわけだ。それを、美禰子はわざわざ手を延ばして三四郎にかがせるんだよな。『ハンケチが三四郎の顔の前へ来た。鋭い香がぷんと』する」
「そして、美禰子が『「ヘリオトロープ」』と静かに言うのよね。すると、『三四郎は思わず顔をあとへ引い』てしまう。衝撃的な一撃だったのよね、たぶん。この辺の描写、読むだけだとさらっと過ごしちゃうけど、読書=体験すると、細かい動きが目に見えるし、匂いも伝わってくるから、すごく感動的よね」
「三四郎が彼女のために選んだ香水。決定的な別れの瞬間にそれを自分にかがせる女。そこに三四郎はストレイ・シープを見たわけだね。虚構の絵の女として生きたいという思いを抱えながら、現実には生身の女として実業界の男の妻とならざるを得ない境遇にある女の切ない気持ちに打たれたんじゃないかな」

「最後に美禰子が口にする『「我はわが咎を知る。わが罪は常にわが前にあり」』は、美禰子なりの謝罪の言葉だったのかしらね」
「うん、たぶん。絵としての虚構の自分を見抜けない三四郎を翻弄してしまったことへの謝罪だろうね。でも、それは実のところは、彼女が本当になりたい自分だったわけだろ。そういう女になることを許さず、家に所属する生身の女に還元してしまう世の中への呪詛でもあるように感じられるね」
「こうして、二人の関係は終わっちゃうのよね。そして、そういうとき常にそうであるように、傷心の三四郎を待っていてくれるのは故郷なのよね」
「家に戻ると、母からの手紙が来ていて『「いつ立つ」』?と書かれてるわけだからね。かくして、正月休みの帰省というかたちをとって、傷心の三四郎は母に象徴される故郷に慰撫されに戻るわけだ」
「そこには、お光さんが待ちかまえているわけよね。謎のない、徹頭徹尾生身の女であるお光さんが。彼女は美禰子のように翻弄したり、夢を見させたりはさせてくれない。彼女との暮らしは、ただの現実なのよね。小川家の家長として生きていく道がその先には待っているだけだから」
「そうなると、美禰子も三四郎も、家制度という社会の慣習にとらわれていくことになるわけだよね。でも、それじゃああまりに救いがないから、その辺の三四郎の未来については、はっきりとは書かれていないんだろうね」
というわけで、この章をまとめるとすると、まず文藝公演会が催され、三四郎は美彌子に近づこうとするが、金縁眼鏡の男の存在に気づいて逃げ帰ってしまい、あまつさえ熱を出して寝込んでしまう。与次郎の画策で見舞いに来たよし子から、金縁眼鏡は恭助の友人であること、当初はよし子に来た縁談だったが、よし子が断ったことから、美彌子に結婚の対象が移ったことを知らされる。数日後、教会にいた美彌子に、三四郎は金を返す。お返しに美彌子が三四郎に嗅がせるのは、以前彼が彼女のために選んだ香水ヘリオトロープであった。傷心の三四郎は、正月休み、母にすがるようにして故郷へと戻る。
「この章で三四郎の恋は決定的な終わりを迎えるわけね」
「でも大丈夫。ちゃんと三四郎はそういう時のための安全策を講じてありましたとさ、っていう終わりだよね」
「ちゃんと傷ついたりはしないってわけね」
「常に逃げ場を確保する用心深さってのが、三四郎の特徴でもあるわけだよな。それは、いわゆる彼の度胸のなさと表裏一体なわけだけど」
「そうやって、現実を回避して生きていくわけね」
「ここでは三を熊本、四を東京と考えれば、やっぱりそのどちらにもきちんと足場を置かない中途半端な生き方が、三四郎っていう名前に表れてるって読めるよね」
「いろいな解釈に使えて、意外に便利ね、この名前」
(第37回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


