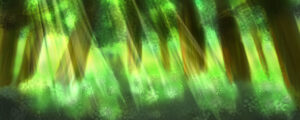 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
二十一 『三四郎』第十一章 夢の女
a:暗い部屋―電気化以前―
「せかせか動きまわる割に、本質的には現実を動かせない男、つまりは与次郎の描写からここは始まるね」
「すごく活動してるのに、すべて空回りしている感じよね」
「文芸協会の演芸会の切符を売りまくる与次郎は、『演芸会をみない者は、まるでばかのような気がする』ほどに、講釈を繰り広げる。景気はよいのだが、その目的が明確に見えないがために『相手はばかのような気がするにもかかわらず、あまり与次郎の感化をこうむらない』とあるものね」
「確かに、広田のいう田圃の間を流れる細い水という表現はあたっているわね。絶えず動いてるけど、浅くて狭いっていうあれ」
「でまあ、その調子の良さに同調して三四郎が『演芸会万歳を唱えた』と思ったら、夕方にはがっくりしてやってくるんだよな」
「でも本題に入る前に、与次郎は、『「この家ではまだ電気を引かないのか』って尋ねるわよね」
「うん、三四郎は『「そのうち電気にするつもりだそうだ」』と答える。ちょっと『蘊蓄』してみたところ、確かに東京では、明治時代に徐々に電気が普及していったようだね。そして大正までには、当時東京市と呼ばれていた場所にあるほぼすべての家庭に電気が引かれることになる」
「でも、明治二十四年には漏電で国会議事堂が焼失したりもしてるじゃない?」
「便利な反面、危険なものでもあったわけだ」
まずは、明治十五年に銀座のアーク灯がともされた。その明るさに人々は感激したという。そのあと、鹿鳴館が電気化され、電気で走る市電の時代となり、東京の町はどんどん電気にしびれていく。
「たぶんあれだね、広田のところは電気灯が点ってて明るいんだろう。でも三四郎のところはまだランプだから暗い。その暗さが、自分の落ち込んでいる気分と一致するような気が与次郎にはしたのかもしれないな」
「さて、そろそろその与次郎さんを落ち込ませた本題にはいりましょうか」
「うん、そうしよう」

b:偽りの記事
『「たいへんな事ができてしまった」』と与次郎が差し出した新聞には、外国文学科に海外留学の経験のある日本人が教授として採用される旨がでている。
「海外留学の経験のある、というところですでに広田ではないことがわかるわけだよね」
「与次郎がさんざん苦労して作った隙間に、別の人がすっぽりはまっちゃったわけね」
この辺、読書=体験者には、与次郎が新聞を畳む音や、読む三四郎の持つ新聞のインクのにおいまでが感じられる。
さらに別の新聞には、広田が教授職を得るために運動をしており、門下生である小川三四郎に零余子という匿名を使って「偉大なる暗闇」という論文を書かせたと出ている。
「三四郎は、意想外のとばっちりを受けるわけね」
「なぜ自分の名前がと問うた三四郎に、与次郎は『「君は本科生でぼくは撰科生だからだろう」』って説明するよね」
「ここには、世間が本科生こそがちゃんとした学生であるという見方をしていたということがよくでているわね」
「実際、撰科生というのは、正式な学生じゃなくって、お金を払っていくつかの講義を聴講しているだけだからね」
「そう、実際与次郎は撰科生なのに、本科生を装って女性をだましたりしていたんだから、ある意味偽学生ってことでもあるわよね」
「迷惑しているのは三四郎なのに、与次郎は『「あの論文は佐々木与次郎以外に書ける者は一人もいないんだからなあ」』と自分こそが迷惑しているというようなことをいう」
「人に迷惑をかけているっていう感覚が麻痺してるっていうか、抜けてる感じよね」
「ただ、広田に迷惑をかけたっていう感覚だけはあるのよね」
「うん、謝らなくちゃならないってしきりにいうよね」
与次郎が帰ったあと、最初三四郎はなかなか寝付けず寝返りばかり打つ。そして『国にいる方が寝やすい心持ちがする』。つまり、東京で次々とやってくる刺激の連鎖、『偽りの記事ー広田先生ー美禰子ー美禰子を迎えに来て連れて行ったりっぱな男』などが三四郎を悩ませる。
「でも夜中からはぐっすり寝たってあるわよね。やっぱり心底悩んでるわけじゃないのよね、三四郎は」
「それに、あれだね。ちょっとつらいことがあるとすぐに故郷がよみがえるんだよね。自分を暖かく包んでくれる、刺激がなくておもしろくはないが安心できる場所。それが母親が象徴する故郷なんだよね。兄が結婚すると帰るところすらなくなる美禰子とは大違いなわけだ」
「基本的にぼんぼんで、のん気なのよね」
「三四郎の気持ちを察したかのごとく、翌朝母親からの手紙が届くよね。大学に行って講義の間に読んでみると、冬休みには戻れと書いてある。お光さんも待っているとあり、彼女が、女学校をやめて家へ帰ったともある」
「これって?」
「つまり花嫁修業に入ったってことじゃないか? 三四郎の帰郷を待って結婚するためだろう。近いうちにお光さんが縫った綿入れが小包で届くともある。いよいよ、本格的にお光さんと母親が共謀して、三四郎を故郷に戻し、結婚させる計画が始動したってことだよね」
「そういえば、大学に行く途中で三四郎は広田を目撃するのよね」
「うん。急ぎ足で歩く学生に紛れて緩慢に歩く彼は、『歩調においてすでに時代錯誤である』と三四郎には見える。そして、そんな広田の存在を象徴するのが、広田が門に入ってすぐ三四郎が見る時計台の時計だよね」
「ええ、この時計は『常に狂っている。もしくは留まっている』ってところね。時代錯誤っていう言葉と、この時計が一致しているわけよね」
「自分のことを第一に置く利己主義ではない広田、帝国主義化する日本に同調しない広田は、まるで古い時代の遺物みたいだっていうことだよね」
c:達観した人
三四郎が読んでいる母からの手紙を、与次郎は美禰子からの手紙と誤解する。三四郎が、母からだと訂正すると、与次郎が『「君、里見のお嬢さんのことを聞いたか」』と聞いてくる。三四郎は、何のことか尋ねようとするが、演芸会の切符をほしがっている学生がいると聞いて与次郎は去ってしまう。
講義が終わった後、三四郎は広田を訪ねるが、広田は仮眠を取っている。三四郎は広田に借りたハイドリオタフヒアを読んで待つ。起きた広田に誘われて三四郎は銭湯に行く。戻って与次郎のことを問うと、広田は『「あれは悪戯をしに世の中へ生まれて来た男だね」』という。新聞記事のことも知っているが、『「お驚きなすったでしょう」』と問う三四郎に、『「まったく驚かないこともない。けれども世の中の事はみんな、あんなものだと思ってるから、若い人ほど正直に驚きはしない」』と答える。『「迷惑でしょう」』と問うても、『「若い人ほど正直に迷惑とは感じない」』という。『「先生のためを思ったからです」』と与次郎を弁護すると、『「存在を無視されているほうが、どのくらい体面を保つにつごうがいいかしれやしない」』と答える。
「達観してるよね。確かに仙人めいているし、偉大なる暗闇と呼ばれるにふさわしい人物だと思うな」
「まるで世俗の野心がないのよね。人に期待もしていないし。ただ淡々とそこにあるって感じよね」
「その理由が、この後で明かされもするわけよね」
「そうだね」
「誹謗中傷といえば、「照魔鏡」を思い出すわね」
「ああ、あいつか」
そう、「照魔鏡」というのは、小説内に不法侵入しては、作者や作品への誹謗中傷を書き加えるという改変を行う面倒な輩である。単独犯であるという噂もあれば、複数名からなる集団だという説もある。
たとえば、田山花袋の『蒲団』で、主人公の作家が弟子であった芳子が寝ていた蒲団や夜着に顔をうずめる場面に、「おいおい、○○美千代の蒲団でほんとにやったんじゃねえの。これ、実録じゃねえの」と書き込みをしたり、谷崎潤一郎の『蓼食ふ虫』には、「奥さんを他人に譲ってんじゃねえよ!from人権狂会」、佐藤春夫の『秋刀魚の歌』には「人の奥さんもらってんじゃねえよ!from人権狂会」と対の書き込みをしたりという具合である。グループ説が出ているのは、この時二つの書き込みがほぼ同一時に行われたことが発端となっている。このように作家の伝記を丹念に掘り起こして、ゴシップネタを見つけては、それを作品内に書き込んでいくという迷惑な奴(ら)なのである。
「元ネタは『文壇照魔鏡』だよね」
「そうね、もしかしたらこのくだりを書いたとき、漱石もこの事件のことを多少は思い出してたかもしれないわよね」
「『三四郎』は明治四一年、『文壇照魔鏡』事件はその七年前の三四年だから、まだ記憶は新しかったはずだもんな」
これは、与謝野晶子の夫で、同じく歌人であった与謝野鉄幹を中傷しまくった作者不詳の書物のタイトルで、しかもそれが正規のルートで出版されもして大スキャンダルとなったのであった。
たとえば、
「鉄幹は妻を売れり
鉄幹は処女を狂せしめたり
鉄幹は強姦を働けり
鉄幹は少女を銃殺せんとせり
鉄幹は強盗放火の大罪を犯せり
鉄幹は金庫のカギを奪へり
鉄幹は喰逃に巧妙なり
鉄幹は詩を売りて詐欺を働けり
鉄幹は教育に藉口して詐欺を働けり
鉄幹は恐喝取材を働けり
鉄幹は明星を舞台として天下の青年を欺罔せり
鉄幹は投機師なり
鉄幹は素封家に哀を乞へり
鉄幹は無効手形を濫用せり
鉄幹は師を売る者なり
鉄幹は友を売る者なり」
といった見出しからもわかるように、彼は不貞者であり、強姦者であり、強盗であり、放火犯であり、詐欺師であり、恐喝者であり・・・とこれでもかとばかり、でっち上げの中傷を展開しまくったのであった。鉄幹の妻、与謝野晶子がこの時詠んだのが、
「幸おはせ羽やはらかき鳩とらへ罪ただしたる高き君たち」という『みだれ髪』に収められた一句である。罪もない弱者を捕まえて断罪する偉そうなあなたたちに、幸せあれ、という皮肉に満ちた一句である。
「いや、明治もなかなか烈しかったわけだ」
「今みたいに、作家のゴシップがほとんど取りざたされない時代とは大違いね」
「この当時は、小説は娯楽の王様だったわけだから、作家は今の芸能人みたいな扱いだったってことだろうね」

与謝野鉄幹は、匿名の作者と思しき人たちを断罪し、告訴したが証拠不十分で敗訴した。つまり、激しく戦った。それに比べると、広田の鷹揚さは、なんとも際立って見える。自分の名誉ということに重きをおかないからこそ可能なスタンスなのだといえるだろう。
d:森の女
恐れ入ったように控えている三四郎に、広田は『「済んだ事は、もうやめよう(中略)それよりもっとおもしろい話をしよう」』といって、さっき昼寝をしているときに見た夢のことを話し始める。
「『ぼくが生涯にたった一ぺん会った女に、突然夢の中で再会したという小説じみたお話』だと広田は言うんだよね」
「『十二、三のきれいな女だ。顔に黒子がある』って広田がいい、十二、三と聞いて三四郎は失望するのよね」
「どう考えても、恋愛対象じゃないからね。それも二十年前に会った女だという」
「森の女なのよね、それが」
「そう、夢の中で広田は大きな森の中を歩いている。『森の下を通って行くと、突然その女に出会った。行き会ったのではない。向こうはじっと立っていた。見ると、昔のとおりの顔をしている。昔のとおりの服装をしている。髪も昔の髪である。黒子もむろんあった。つまり二十年前見た時と少しも変わらない十二、三の女である』っていう感じだよね」
「二人は会話するわよね。『ぼくがその女に、あなたは少しも変わらないというと、その女はぼくに大変年をお取りなすったという。次にぼくが、あなたはどうして、そう変わらずにいるのかと聞くと、この顔の年、この服装の月、この髪の日が一番好きだから、こうしていると言う。それはいつの事かと聞くと、二十年まえ、あなたにお目にかかった時だという。それならぼくはなぜこう年を取ったんだろうと、自分で不思議がると、女が、あなたは、その時よりも、もっと美しいほうへとお移りなさりたがるからだと教えてくれた。その時、ぼくが女に、あなたは絵だと言うと、女がぼくに、あなたは詩だと言った』って」
「つまり、広田も、三四郎と同じかたちの恋をしたってことだね」
「絵としての女に惚れた、女の実在ではなく、一幅の絵として切り取られた女に惚れたってことかしらね」
「森が象徴しているのは、無意識の世界だろうね」
「そうだね。近代化されていく日本の外部というか、そこからの避難所というか、なんかそういう感じがするわね」
「広田がこの少女を実際に見たのは、二十年前の高等学校生の時だった」
「そう、これも意味深よね。それは明治二十二年の憲法発布の年だったとされているわけだから」
「そして、広田が少女を見るのは、その年に国粋主義者に暗殺された、欧化主義者の文部大臣森有礼の葬儀の列の中になのよね」
「つまり、列強に互しうる強国たらんと、西洋に学んだ憲法を強いて、帝国主義化し始める年ってことよね。そして、軍国主義とは違うかたち、つまり文化や教育の西洋化を唱えて、その礎を築いた人の供養の場においてだということになる」
「漱石のイギリス留学だって、大きく見れば帝国主義の一環だったわけだよね。ただ、漱石自身は、そのなかにあっても、むしろ森文部大臣の考える文化的な西欧化にむしろ関心があったってことかな」
「明治二十二年は、広田が『滅びるね』と汽車の中で三四郎に予言したような国へと変質していった年ってわけよね。その年に失われたものを、この少女は象徴しているのかもしれないわ」
「つまり、広田の森の女っていうのは、単なる絵じゃないってことだね。変わっていく日本、その日本に取り込まれて移ろっていく自分、そんな自分を我に返らせてくれる存在ってことになる」

「止まった時計であり、二十年の時を経ても時間がたたない狂った時計でもあるって言うことね。そういう時計を広田は内側に持っているってことだ」
「時代錯誤の存在であり、時間の外にいる仙人のような存在である広田の本質的な部分を、この少女が代表しているわけね」
「そして止まった時間の話には、さらに続きがあるよね」
三四郎が、この夢の少女への思いから先生は独身を続けているのかと問うと、先生はそこまで自分は浪漫的な人間ではないと応じる。ただ、『いろいろ結婚のしにくい事情を持っている者がある』と言い、『たとえば、ここに一人の男がいる』と前置きして話し始める。
それは、母一人子一人で育った男で、しかも母は病気で死に瀕している。その母から、『じつは誰某がお前の本当のおとっさんだ』と、つまり自分は不義の子であったことを知らされるという話である。そういう母を持つと、『その子が結婚に信仰を置かなくなるのはむろんだろう』と広田は言う。
「たとえ話の体裁を取ってるけど、これは広田自身のことって感じがするよね」
「ええ、読書=体験だと、もうそうとしか感じられなかったわ、私の場合は」
「自分は正当な結婚で生まれた子ではないという認識。それは、自分が結婚するということへの確かな障壁になるかもしれないね」
「そして、広田は自分の母もまた憲法発布の年に死んだというわよね」
「そう、森の女であるところの少女は、だから、変わっていく日本の向こうで変わらずにあるものであると同時に、結婚制度の外で自分を生み出した母の記憶ともつながってることになる」
「規範化する力と対極にあるものかしらね、それは」
「うん、憲法発布後失われて行ったアナーキーな力を指し示しているのかもしれないね」
まとめるならば、偽りの記事が発端になる章である。つまり、広田が帝大教授の座を得ようとして、三四郎をそそのかして「大いなる暗闇」の記事を書かせたというデマが新聞に載る。与次郎は慌てるが、広田はさして驚きもしないし、与次郎を責めもしない。そして、三四郎に二十年前に出会った少女に、夢のなかの森で再会したという話をする。次いで、自分が私生児だと知って結婚に信を置かなくなった男の話をする。
「なんていうのか、憲法発布を期として、大きく変わりつつある日本の体制ってのが、背景にあるような感じがするね」
「そうね、さっき話してた『現実』が、否応なく日本を変えつつあるわけよね。でも広田はその少女に、憲法発布前に出会っている。それは『滅びるね』といわれるような日本ではなかった時代を象徴してるのかもしれないわね」
「そういえば、そういう世界がまだ三四郎には残されてるんだよね。『なんだか古ぼけた昔』って三四郎が描写するような世界が」
「そうね。で、そこを代表する母親からは、正月に戻ってこいコールが来てるし、お光さんはとうとう花嫁修業に入ったわけだし」
「三四郎を引き戻そうとする勢力も健在だってことだね」
「ここでも、三と四の間に引き裂かれてるわけよね。東京と九州、つまりは資本主義化及び帝国主義化していく憲法発布以後の明治とそれ以前の牧歌的な時代との間に」
「うーん、戻るかもよ。三四郎。戻っちゃうかも。だって、美彌子さん連れ去られちゃったもんね。馬車に乗った金縁眼鏡の男に」
「戻らないためには、立ち向かわねばならないけど、その勇気も力もないからなあ」
「そうねえ、金縁眼鏡の男が殺されたんなら、話は早いわよね。犯人は三ちゃんか野々ちゃんしか考えられないもんねえ」
「でも、殺されたのはその友人の恭助だった、と」
「ええ、そうね。ということで、この線では答えにたどり着けないと」
「別の線だよね。そう、別の線を引いて見なきゃならない」
(第36回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


