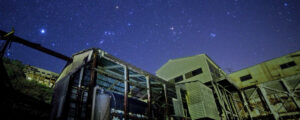 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
10
美雨は、小門付近に停めてあった車に乗りこみ、赤土色の一本道を走っていた。行く手を阻もうとするのは、路面の凹みと強まる横風だ。あっという間に視界が悪くなり、礫が音を立てて攻撃しはじめた。それでも砂嵐は援軍に違いなかった。64を乗せた小型トラックは幌付きだ。突風のなかを全速力で走れるとは思えない。きっと追いつける。立ち往生しているところに衝突しないよう集中力を高めた。
工場までは二十キロほどだと聞いている。教師たちの住まいを過ぎ、丘陵地を横目に不毛地帯を突っ切っていかなければならないということだ。
教師の居住エリアは、砂嵐を真正面から受けていた。窓という窓が錆びた色で染まっている。確認できたのは数秒間だけだった。風が丘陵地の岩肌にぶつかり、跳ね上がる。その直後だけ無残な姿をさらしたのだ。
強風を遮る丘がなくなり、視界は赤茶け、天候が回復する見込みもなかった。深夜のドライブよりも距離感が掴めない。路面の硬さを確かめながら、真っ直ぐ進むことだけに意識を向けた。気を抜けば、砂の小山に乗り上げるか、窪みにはまりこんでしまう。
時間の感覚も鈍くなったときだった。アクセルを踏みこもうとして息が止まった。トラックがすぐそこにいたのだ。工場があると思われるエリアに入る手前だった。そこを境にして風が盛り返している。向こう側はまたしても視界数メートルの世界だ。
急ブレーキをかけた。しかし、アスファルトは砂塗れだ。タイヤの溝から効力を奪っていた。ハンドルを右左に切れば横転する。左に左にと念じながら、ブレーキを細かく踏み続けた。車の重量に手伝ってもらいながらスピードを殺すしかない。

間に合う。いまなら右に切っても大丈夫だ。美雨は衝突寸前のタイミングでトラックをかわした。路肩の小山がクッションになった。
トラックはハザードランプを点けて停まっている。美雨は駆け寄り、幌のジッパーを開けようとした。が、運転席と助手席が同時に開き、銃を手にした男たちが降りてきた。C班の作業助手である。いくらゴム弾でも、この距離で食らえばひとたまりもない。
「工場送りになる生徒との接触は禁じられている」半歩でも動けば撃つという構えだ。
「会えなくても構いません。ここから話ができれば」
幌を開けなくても、声を届けることはできる。会話が成立しなくても、心を伝えられるだろう。しかし、そのすべてが接触行為にあたると一蹴された。
ゴム弾が先か、声が先か。いましかないという思いが背中を押した。
「わたしよ、22よ!」
声を張り上げたときだ。爆発音が轟いた。銃撃ではない。作業助手が身を翻した。金属とガラスが同時に破壊されたような、その音の出所は背後だった。
美雨は路上に転がり、反射的に突っ伏した。見上げた光景に目を疑った。小山に乗り上げた美雨の車にもう一台が突っこんでくる。横転した状態で、運転席のドアが火花を散らしていた。
助手席のドアをこじ開け、出てくる姿があった。金髪と包帯が見えた。87だ。ブレーキを刻まず、横転して減速するほうを選んだという顔だった。唾でも吐くように美雨の足元に一発撃った。ゴム弾が跳ね、砂塵を抉り取る。
「動くな。捕縛する」
培養組は同乗していない。調整するだけの時間がなかったからか。
いくら87といえども、単身で乗りこむのは賭けに近い。事実、彼女の目は虚ろだった。襲撃のダメージから回復していない。だからこそ敢えて横転するほうを選んだ。ほかの手段が思いつかないほど思考力も鈍ったままなのだ。気力で持ち堪えている。
それでも黄が担当させた。87が外組トップの座を奪われた手負いの虎だったからだ。容態と執念を秤にかけ、後者が勝ると期待した。
急げ。87が作業助手に合図した。彼らの仕事に気を配ったという態度ではない。邪魔をするなと睨んでいる。生徒が指示することなど考えられなかった。半年間の学園生活で見たこともない。事実、作業助手がこの場を制圧すれば、副担任への階段を一歩上がることになるのだ。銃を構え直し、出過ぎた真似をするなと一喝すれば済んだことだった。87が抵抗すれば墓穴を掘ることになる。それでも作業助手たちは引き下がった。いそいそと車に乗りこんだ。すでに黄から連絡が入っていたのではないか。87が向かっている。こういった局面になったときは捕縛の邪魔をするなと。黄が敢えて87を担当させたのなら、助手たちは彼女の顔を立てなければならない。トラックが発進しはじめた。
七時。それなりに風は強かったが、嵐というレベルではなくなっている。一本道が徐々にその姿を伸ばしていた。いつの間にか西の彼方には雲が現れ、足取りを速めながら迫りつつあった。水平線の向こうは影のように暗い。雨だ。天気が劇的に変わろうとしていた。
「手は頭のうしろ」
肋骨の辺りを押さえ、87が近づいてくる。額に巻かれた包帯は赤黒く染まっていて衛生的とは言えない状態だ。足元も覚束ない。この距離で彼女が狙いを外すとは思えないが、何かの拍子に立場が逆転してしまうという場面も想像できた。運は美雨に味方していたからだ。こちらが風上だった。
手を挙げ立ち上がろうとする刹那、美雨は一握りの砂を投げつけた。
格闘訓練では一度も勝ったことがない。射撃訓練も然りだ。しかし、87の反応は想像以上に鈍かった。人形を相手にしているかのようだった。
美雨は87の背後を取り、右手をうしろに回した。握力を喪失しかけた手から銃を奪い取るのは、熟れた果実を捥ぎ取るようなものだった。
「64に言っておかなきゃならないの」
手錠を探り、捕縛した。こんな場所に置き去りにするのは気が引けたが、用を済ませればすぐにもどってくるつもりでいた。
美雨の車は生きている。いまならトラックに追いつける。銃も手に入れた。
「おまえが工場に送られることになっても、か」
64への思いを告げ、時間内に学園へもどるつもりでいた。授業に間に合えば、自習に滑りこめば問題はないと思っていた。しかし、87が追ってきた。逃亡したと見なされたからだ。このまま目的を達成できたとしても、両親が責任を取らされる。

幸い無傷の車がある。このまま街へ行き、両親に連絡すべきではないか。そのあとは逃亡生活に入ればいい。1―30のように。19の一件が起こるまで、逃亡の事実は隠されてきたのだ。ハンターも放たなかった。C班のメンツを守るための苦肉の策だった。
美雨は両親を思った。危機が迫っていると告げたところで、彼らは逃げるだろうか。どんなに脅されても毅然としてきた。まして『常言』の創設者でもある。同志たちにどう弁解するというのか。
しかし。
両親は党からの依頼を受けたのだ。クローン計画の一部を担ってきた。信じるべき人物が、最も嫌悪すべき人物と重なり合う。
しかし。
疑い切れないのだ。目に浮かぶ両親の表情がそうさせなかった。慎ましく、潔く、何より信念に忠実だった。彼らがクローン計画に加担したなら、そうしなければならない理由ができたからではないか。信念よりも重大な何かを守るために。従わなければ、何もかも跡形もなく消してやると脅された。『常言』の発行に携わる同志たちの生活か、命か。
いや『常言』の読者ではないだろうか。
計画に加えられることで、両親は相応の傷を負ったはずだ。屈することで読者を守ったとはいえ、その心は想像に余りある。自問を繰り返してきたに違いない。こんなことをして、真に読者のためになるのかと。
逃げろと言われても、了解するとは思えない。今度こそ活動家としての本懐を遂げる。脅しの対象が読者だろうと、屈すれば信念に背くことになる。そんな『常言』に価値はない。読者が求めるはずもなかったのだから。何より美雨の行動を恥じ、斬るだろう。
95の言葉がそこに重なった。あなたは何をしてあげた?
黒雲が陽射しを遮り、湿り気を含んだ大気が風を止めた。辺りを見通せるようになった。
トラックが急停止していたのもわかる。一本道は、五十メートルほど先からなくなっていたのだ。急な落ちこみがある。ここから眺めると景色に断層ができている。
87の顔にも驚きがあった。手錠をかけられたまま「断崖」のほうへ歩み寄っていく。
眼下に工場と思しき建物が見えてきた。真の不毛地帯というのはこのエリアを言うのではないか。辺りには緑に着色されたものが見当たらない。岩石砂漠に支配された世界は無限のように広く、同色だった。そのなかに平屋の建物がぽつねんとあるのだ。存在の仕方があまりに不自然に見えた。じつは砂の下には街が埋もれていて、あの建物だけが呼吸をするために顔を出しているのではないか。

トラックは工場に到着していた。幌が開けられ、ここからでも荷台が空だとわかる。その隣には小型のトレーラーが並べられてあった。食材を届けるためだろうと思ったが、農園からやってくる車とは型もサイズも違う。落ちこぼれた生徒たちは扱いが異なるのか。
「あの車」87が膝をついた。「あのマーク」
トレーラーのことか。シルバーの荷台には血管を模したようなマークが施されてあった。
「隣村によく来てた」
「確かなの」
「間違えようがない。話を聞いた子供たちは隣村へ近づこうとしなかったからな」
言い淀んでいる。
「おまえたちは絶対に遊びに行くな、と。あのクソ親父でさえ心配してた」
「人さらいの連中が乗ってたとか」
「子供を誘拐するんじゃない。若い村人だけを乗せていく」87の唇が震えた。「ダメだと言われると子供は反発したくなる。オレもこっそり行った。隣村には沼があったしな。最高の遊び場だったんだ。そのとき仲良くなった子の兄貴が乗せられていったらしい」
「帰ってこなかった」
「いいや、来たさ。そのあと家が新しくなって、畑も広くなった。井戸も掘ってたな」
「出稼ぎか何かで」
それほどの稼ぎをもたすのなら、普通の若者が毛嫌いする過酷な現場に違いない。
「そいつが沼で水浴びをしていたところを見たんだ。すっかり変わってた」
87が眉間を寄せた。
「友達思いで、楽しいやつだった。それが、なんというか」
表現のしようがないという顔だ。
「話せなくなった。こっちから話しかけても唸るばっかりで」
しかも。
「ガキみたいにはしゃいだかと思えば、いきなり暴力的になる。素っ裸で走り回ったり、沼の水を飲んだりする」
「頭がおかしくなったってこと」
「それしか言いようがないな。帰ってきた連中は、みんなそんな感じだった」
「帰ってこなかった人もいるの」
「そっちのほうが多かったよ。しかも、そいつの家はもっと羽振りがよくなったんだ」
87が首を振った。
「妙なことをされたんだと思う。それと引き換えに、見たこともないようなカネが舞いこんできた。オレはそう思ってる。村の連中もな」
87がこめかみを突いた。
「ここをイジられたんだろ。じゃなきゃ、あんな風にはならないさ。帰ってきたのは、おそらく失敗作なんだよ」
87は「矯正人間」という言葉を用いた。
「先方の望むような人間につくり替えられる。叶えば成功。失敗すれば村へもどされる」
変わり果てた姿を見ている。若者が帰ってこなかった家を知っている。あくまでも想像でしかない、と前置きをしていたが、彼女の目には確信が灯っていた。

「隣村が終われば、ウチの村にも来たはずだ。オレはそのまえに出てきたけどね」
「村から若者を運んできて、ここで『矯正』を? その作業のために生徒たちが働かされているってこと?」
「かもな。それにしても変だ。灯りがついていない」
「まだこんな時間だから」
「あんなに車がいるのに作業はまだ? だいたい窓にはカーテンもない」
違和感は美雨にも伝染していた。
「窓といえば鉄格子がないわね」
「逃走できない特別な方法があるのかもしれない。たとえば薬物」
生徒を薬漬けにしているなら辻褄が合う。作業の抵抗感を薄め、逃走の気概も削げる。しかし、目的はそれだけではないだろうと87が眉間を寄せた。
「各世代の落ちこぼれが集まる。オレたちや下の世代が入れるだけの余地があるかどうか」
「新しい生徒を入れるには、その都度『空き』が必要になる」
「そういうこと。薬漬けにされた生徒なら、すぐ廃人になるだろ」
あとは順送りか。
「諦めろ。今頃は64にも――」
「入ったばかりよ。間に合うかもしれない」
奪った銃を87のこめかみに当てた。
「わたしを捕縛して」
「そのつもりで来たんだぜ。いまさら何を言ってる」
「フリをしてほしい。工場に侵入するの」
「64に会えるかどうかはべつの話だろ」
「わたしを捕縛できれば大きく加点される。あなたにはそれで充分でしょ」
トラックがもどるのを待つつもりだった。しかし、狙い澄ましたように降り出した。ふたりは美雨が乗ってきた車に移動した。87の話では敷地内に入るなと厳命されたという。
しかし。
「やはり灯りがないな」
本降りに変わった。夕暮れのように暗かったが、工場は濡れそぼるだけだ。灯りらしきものを確認できない。87がエンジンをかけた。思うところを確かめたいという顔で車を発進させていた。一本道が黒く染まり、急斜面に雨が流れこんでいく。岩石砂漠にこれほどの雨が降るのかと疑いたくなったが、そもそも、こんな不毛地帯が存在するとは思えなかった。教師たちの住まいを越えたあたりからずっと続いているのだ。地理的に考えれば疑問符がつく。何かしらの開発に失敗した結果がこの状態なのではないか。化学的で、非人道的な実験の類か。その跡地に工場が新設されたのなら、かつての所業と肩を並べる何かがおこなわれていても不思議ではない。87の話が現実味を帯びてくる。近づくと、工場の陰に隠れて見えなかった車が姿を現した。十台以上だ。裏手まで停められているとすればその倍はある。全土から集められた若者を扱う秘所なのもしれない。87の表情が険しくなった。隣村で見かけた光景が頭をよぎっているのだろう。生々しい手術痕。唸り声。帰ってこない子供。悲しむことを忘れたように楽な暮らしに浸かる家族。幸せと地獄。
工場の正面に着いた。87が目を閉じた。聞き耳を立てている。
美雨も感じた。おかしい。工場の外壁はお世辞にも新しいとは言えなかった。それでも、物音ひとつ漏れてこないのだ。
87が工場の横っ腹に向かった。砂が濡れ、足音はしない。ボンネットを打つ雨音だけが響く。窓を覗き、体を起こすまで一分とかからなかった。しかし長い潜水を終えたようにそのまま動けずにいる。額にかかる金髪をかき上げようともしなかった。美雨と目を合わせた。頷きもしなければ、首を傾げることもなかった。これまで見聞きした知識と経験を総動員し、思考回路をフル稼働させているはずだ。それでも理解不能だということか。

美雨も車を降りた。窓辺に近づいたが、作業音は聞こえない。無人だと言われても納得できるような静けさだ。87と同じように窓を覗いた。目にした光景をしばらく理解できなかった。生徒たちは一体どれだけ慎重な作業を求められているのだろうかと思った。節約された電力のなかで相当な過酷さを強いられていると想像していた。どれも違った。工場には何も置かれておらず、誰もいなかった。
それぞれの世代で卒業できるのは十五名だけ。第一世代と第二世代で、合わせて百七十名ほどが送致されたことになる。薬漬けにされ、廃人になった者がいるとしても順送りだったのだ。かなりの生徒が残っている。まして第三世代も送られはじめた。肩をぶつけ合うほど窮屈な作業を強いられているものだと思いこんでいた。
工場は稼働していなかった。みな消えてしまった。工場の入り口を抜ければ揮発してしまうかのように。
87が先に気づいたようだ。類推すれば思い至るという顔だった。
目眩がした。美雨は、自分が想像した惨状を反射的に消そうとしていた。
「たぶん、そうだ」
顔に出ていたのかもしれない。87が頷いた。
「村の若者が集められているのはべつの場所だよ。ここは遠すぎる」
矯正されるのは脱落した生徒たちか。
「何もかも嘘八百だったのさ」
87が掠れた声で自嘲した。
「わたしたちを欺いていたのは、いまにはじまったことではないのよ」
美雨は張から依頼された内容を伝えた。C班が過去の逃走事件を隠し、今回の一件も葬り去ろうとしていた。先導したのはいずれも胡だった。
「卒業できるってことも嘘なんじゃないか」
「それは事実よ。捜査には第一世代の先輩が同伴したの。教師への信頼はどうであれ、あなたはこれまでどおりでいいでしょう」
卒業できれば問題ないのだ。
「工場の件はべつ。明確なことは何ひとつない。生徒が送られたことは事実だし、これだけの車が停められている。人影がないってことは、地下で働かされているのかもね」
想像が的を外し、薬漬けの生徒が働かされている可能性はまだある。
「地下が稼働していることはまず間違いないだろう。でも期待は望み薄だと思うよ。黄は敷地に入ることさえ禁じたんだ。オレたちの姿が生徒に見えてしまうのはよくないと言ってね。あの窓から覗けば、送られた生徒を確認できる物言いだった。事実は違った」
工場はべつの目的で稼働している。おそらく美雨たちの想像どおりに。
「ここはクローンのリサイクル工場ってことか。もしかしたら、そっちが本来の」
87が言葉を切った。美雨も耳をそばだてた。話し声が聞こえた。金属音も重なった。正面だ。作業助手たちが入り口から姿を現した。
美雨は身を屈め、車にもどった。彼らが気づく寸前のことだった。
「連れてきたよ」87が自分に注目させるように両手を挙げた。
「ここには入るなと言われてあっただろうが」
作業助手のひとりが舌打ちする。
「あそこで待ってろってのか。土砂降りだってのに」
87が斜面の上を指す。まるで小川だ。
「担任に報告は」
「いや、これから」
「帰っていい。ただし窓には近づくな」
美雨が手錠で繋がれていることを確認すると、リモコンで正面玄関のロックを解除した。
「おい」
87が声をかけてきた。ここで気づいたことを確認するような短い間があった。
「しっかりやれよ」
美雨は微笑み、一度だけ首を真横に振った。ここへ来ちゃだめよ、と目で伝えた。
1―30はドアノブを握った。この冷たさが、木目調のドアの重さが、かつての「特訓」を思い起こさせる。胡は姿見のまえにいた。椿油を滲みこませた白髪がサイドバックに撫でつけられている。紳士然とした表情に威厳という凄みが加わっていく。言葉を放つ用意は整いつつあった。訓示が刻々と迫っている。

五年前。1―30はC班に選ばれ、トップ争いの常連組だった。しかし、どうしても勝てない相手がいた。幼少期からともに学んできた培養組のひとりだ。特別変異ではないかと噂されるほどで、王校長が特に期待していた天才肌である。
あと一歩届かない。紙一枚の差が縮まらない。死に物狂いで努力する自分に比べ、彼女はいつも涼しい顔をしていた。周りから見ればミクロン単位の差だったのかもしれない。しかし、当時の1―30にとって、それは長城を見上げるほどの落差に感じられた。女王だと認めてしまえば楽になると思いかけたある日、担任の胡に声をかけられた。驚かされた。教師がアドバイスするのはいつも外組で、トップ5入りが当然視されている培養組に寄り添うことはなかったからだ。
上にいる生徒の特徴を解析し、数少ないウィークポイントを見つけ出し、勝負しなければならない場面で的確に突く。いままで自分がやってきたことはそれに尽きた。結果、連敗だった。女王の最右翼と呼ばれた相手はやはり稀有だった。ウィークポイントを自覚し、相手がそこを狙ってくると予測し、返り討ちにするだけの能力にも長けていたのだ。
胡は、培養組に欠けているのは実体験であり、それを超克することが近道だと説いた。「女王」も培養組のひとり。彼女が未経験であり、自分が経験済みなら、能力に厚みが生まれる。成績にも反映するという理屈だった。縋る価値があると感じた。思いつくことはすべてやってきたという自負がそう思わせた。放課後の校長室が訓練場に変わった。ふたりだけのトレーニングが続けられた。「女王」が持っていない感覚を養う。そこから紡ぎ出される心理を会得する。胡のレッスンは、1―30の神経と精神をフル稼働させるためのものだった。秘められた能力を呼び起こし、紙一重の差を突き破るためのカリキュラムだ。胡は1―30を抱いた。じっくり蕩けさせ、白濁した景色のなかへと召喚した。天と地を自由に行き来できるのではないか。そんな錯覚を呼び起こせる経験だった。来る日も来る日も綿密に積み重ねられた。1―30は、そこから発芽する新たな情感に気づかされた。「嬉しい、悔しい」は「好き、嫌い」に変換され、感覚が立体的になっていたのだ。世界は豊潤なのだと噛み締められた瞬間だった。自分がどれだけ無味乾燥した闘争のなかでもがいていたのかを思い知らされた。
胡から特別に寵愛されたい。そう気づかされたのは訓練の最終日だ。いつしか女王への興味が失せていた。気持ちを伝えることには躊躇いがあった。胡は、自分をベストな生徒に仕立てるために尽力してくれたのだから。しかし杞憂だった。様子がおかしいと感じたのだろう。表情を覗かれ、心を読まれた。胡は叱らなかった。それも生き方のひとつだと認め、許してくれたのだ。1―30は胡を悦ばすために生きたいと告げた。
「連絡することをお忘れですか」
櫛を動かす手が止まった。忙しかった。疲れていた。妻の調子が悪くなった。孫と過ごす時間をつくる必要があった。いくらでも言い訳を捻り出せた。が、胡はおぞましい何かと出くわしたように立ち尽くしている。
質問を変える必要があった。あらゆる盾を射抜く鋼鉄の矢だ。
「あなたですね、ここにタレこんだのは」
胡が後じさりした。椅子にぶつかり、腰を下ろす。
「逃げた3―19が新しい愛人」
手が静かに引き出しを探っている。
「わたしが捕まれば五年遅れの工場行きになる。あとは、彼女とよろしくやれる」
取り出したのは、C班で使っている銃よりも小型だった。実弾用だろう。

「教育畑一筋のあなたが上手に扱えて?」
突進しようと踏みこみ、1―30は、コンマ数秒のタイミングで姿勢を落とした。胡に実射訓練の経験はないだろう。虚実を見分ける力に乏しいはずだ。
案の定、という反応だった。最初の挙動に釣られ、慌てて撃ってしまった。1―30が視界から消えたとわかったときにはすべてが終わっていた。
1―30は、校内アナウンス用の機材がある場所まで胡を連れていった。
「すべて話してもらいます」
抵抗する彼の髪を引っ掴み、股間に銃を押し当てた。マイクのスイッチを入れるか、男を捨てるか、ふたつにひとつだと囁いた。
(第10回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


