 自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
by 金魚屋編集部
池上晴之(いけがみ・はるゆき)
一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。
鶴山裕司(つるやま ゆうじ)
一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。
萩野篤人(はぎの あつひと)
一九六一年、埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元IT関係の会社員。十代の頃から文学・哲学・思想に関心を持つ。二〇二三年、相模原障害者殺傷事件をテーマにした評論『アブラハムの末裔』で第一四回金魚屋新人賞を受賞。現在、小説『春の墓標』を文学金魚で連載中。
■吉本隆明の思想基盤■
鶴山 「詩の原理」というタイトルで対談して来ましたが、今回は戦後思想を代表する吉本隆明さんということで、鮎川信夫、田村隆一篇と違って詩の話ばかりにはならないと思います。かと言って『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『心的現象論序説』などについて一冊ずつ議論するわけにもいかない。それをやると数ヶ月かかってしまう。そこで吉本さんには大変申し訳ないんですが、吉本さんの仕事についてザックリ議論したいと思います。また僕と池上さんはどっぷり文学寄りなので、今回は哲学にも詳しい萩野さんに参加していただく鼎談です。萩野さんは小説を書いておられますが、『アブラハムの末裔』という評論もあって哲学だけでなく社会思想についてもお詳しい。ただ萩野さんのバックグラウンドについてはあまり存じ上げない。萩野さんは大学の学部はどちらですか。
萩野 慶應大学の文学部仏文科です。
鶴山 大学で哲学を勉強なさったんですか。
萩野 学部で哲学を学んだわけではないですが、ずっと関心を持って独学でやってきました。
鶴山 どのあたりに興味がおありなんですか。
萩野 西洋哲学ではアリストテレス、中世神学、カント、ウィトゲンシュタイン以降の分析哲学、東洋哲学だと「哲学」の意味合いが違いますけど、仏教思想全般と近代日本の哲学者・西田幾多郎、九鬼周造あたりでしょうか。
鶴山 アリストテレスが好きなんですか。あんな面倒臭い哲学を……尊敬します(笑)。
萩野 アリストテレスの哲学って読み込んでいくと面白いんですよ。一番面白いのは時間論です。未発表ですが今、ひたすら書いている時間論の原稿があるんですけど、その大きなヒントになったのはアリストテレスです。アリストテレスの時間論は全集第4巻『自然学』のほんの数ページしかないんですが、アリストテレスの時間論なしにその後の西洋哲学の時間論は始まらないと言っても過言ではないです。
鶴山 簡単に言うとどういう時間論ですか。
萩野 うーん、有名なゼノンの「飛んでいる矢は止まっている」っていうパラドックスがありますね。あれを批判して、人間の常識的な時間感覚の方が正しいという議論をしているんですけど、ゼノンはゼノンで、わざとありえないパラドックスを主張しているんです。アリストテレスもそれを承知で批判している。その微妙な演出というか絡みが面白い。
鶴山 時間と人間ということですか。
萩野 はい。極論すれば、時間は人間が作り出したものです。事実、時間は実在しないとハッキリ論証した人がいるんですが、『時間の非実在性』という論文を書いたマクタガートという英国の哲学者です。彼の論に基づくと時間は幻に過ぎない。そうは言っても人間には現に生きている時間がありますよね。生きているとは今を生きているということですけど、〝今とはそもそも何なのか〟。これが大問題でして……まあそんなことを自分なりの時間論で考えているんです。
鶴山 萩野さんの時間論の元になっているのはアリストテレスとマクタガートだと。ヘーゲルはどうですか。
萩野 ヘーゲルまでいっちゃうとイマイチ関心が持てないんですよ。非常に精緻で認識論としてはその先へ行けないほどなんだけど。もちろんマルクスでも実存主義でも、ヘーゲルを批判することで一九世紀以降の哲学は発展したわけですが。
鶴山 薄っぺらい知識しかないんですが、大雑把なことを言うとアリストテレスからヘーゲルでいわゆる西洋論理哲学は一応の完成ですよね。吉本さんの著作を読んでいて思うんですが、一番影響を受けた哲学者はヘーゲルじゃないですか。
萩野 そうですね。若き吉本さんがヘーゲルから影響されたことは、その精緻な弁証法と観念論の体系の見晴らしの良さではないかと思っています。ご存じの通り、その後マルクスが史的唯物論、科学論を打ち出して、ヘーゲルの観念論を批判しその限界を示した。でも一方、マルクスのいう「下部構造」、つまり経済とか身体といった物質的なプラットフォームに対する人間の「上部構造」ですね、吉本さんはそれを〝全幻想領域〟と呼んでいますが、それを全体として把握するには、ヘーゲルの体系がまだまだ有効だと吉本さんは考えました。それが後の代表作である『共同幻想論』で〝共同幻想〟〝対幻想〟〝個人幻想〟というキー概念となって実ります。ひと言で言えば、国家と性と個人とを包括的にとらえる〝世界認識の方法〟を学んだということですね。吉本さんが影響を受けた西洋の思想家はヘーゲルの他に三人いまして、まずはマルクス、それにニーチェとフロイトです。
鶴山 そうそう、ユングじゃなくてフロイトなんですよね。今の心理学はほぼユング派になっているわけだけど、吉本さんは比較的論理的なフロイトなんだな。でもニーチェの影響は受けてるのかな。
萩野 初期の吉本さんはニーチェだと思います。中学三年生の時に初めて読んだ吉本さんの初期の評論が『マチウ書試論』で、これには衝撃を受けました。この論は、史的イエスは作り話だと主張して物議をかもしたドイツの哲学者・アルトゥール・ドレフスの『キリスト神話』をベースにしていますが、キリスト教の背理的な部分、つまりユダとか仲間内での裏切りや他派であるユダヤ教への近親憎悪、揺れ動く人間心理の裏の裏まで洞察し矛盾をあらわにするような手法は、ニーチェのアンチ・キリスト論を抜きには可能でなかったと思います。また、フロイトの影響はさっきの〝対幻想〟という概念を考えるうえで見逃せません。人間の心、とりわけ性というものを初めて無意識の構造として立体的にとらえた人がフロイトですから。
鶴山 キリスト教は背理だらけでしょう。ローマがキリスト教を国教に定めた後、四世紀に開かれた第一回ニカイア公会議で父と子と聖霊の三位一体が公式教義になるわけですが、アリウス派はキリストの神性を否定し続けますよね。
萩野 アタナシウス派とかネストリウス派とかいろいろありましたね。
鶴山 ただキリストの神性を否定して父だけになると、これはユダヤ教の唯一神・ヤハウェじゃないかってことになってしまう。またキリスト人気がもの凄かったので、まあ無理くり三位一体の教義を作り出した。吉本さんが『マチウ書試論』を書いた当時、すでに聖書学は進んでいたんでしょうか。
萩野 進んでいました。有名なところでは吉本さんの十歳下に田川建三という人がいて、自分のことを「神を信じないクリスチャン」だと言ってますが、この時期の吉本さんを高く評価しています。後に批判する側に回りますが、交流もあったようです。カトリックだとニカイア公会議以降の矛盾点を自覚した上で新しいカトリックのあり方を考えた吉満義彦という神学者がいまして、この人は遠藤周作に影響を与えています。
鶴山 セム一神教の中で首尾一貫しているのはユダヤ教とイスラーム教ですが、キリスト教は背理があるから神学(思想)が発展したとも言えますね。ユダヤ教やイスラーム教は厳しい戒律宗教でもあります。これは底辺の話ですが、戒律さえ守っていれば自分たちは聖なる民であり、そうでない異教徒には何をしてもいいんだということにもなりかねない。宗教の硬直化・世俗化が起こりやすい面があります。キリスト教は三位一体という曖昧な神性定義をしたから思想が発展していったと言えるかもしれない。
萩野 キリスト教はイスラーム神学の影響をモロに受けています。キリスト教はいったんすたれちゃうんですが、それは中世になってイスラーム勢力がどんどん中東からヨーロッパに侵攻して来たせいでもあります。その時にギリシャ哲学を吸収したイスラーム世界で発達していた神学がヨーロッパに入って来た。
鶴山 ギリシャ語からアラビア語に翻訳されたアリストテレスとプロティノスがさらにラテン語に翻訳されて、アウグスティヌスなどのヨーロッパ初期神学が生まれたんですよね。でもそれはイスラーム教の直接的影響とはまた違うでしょう。
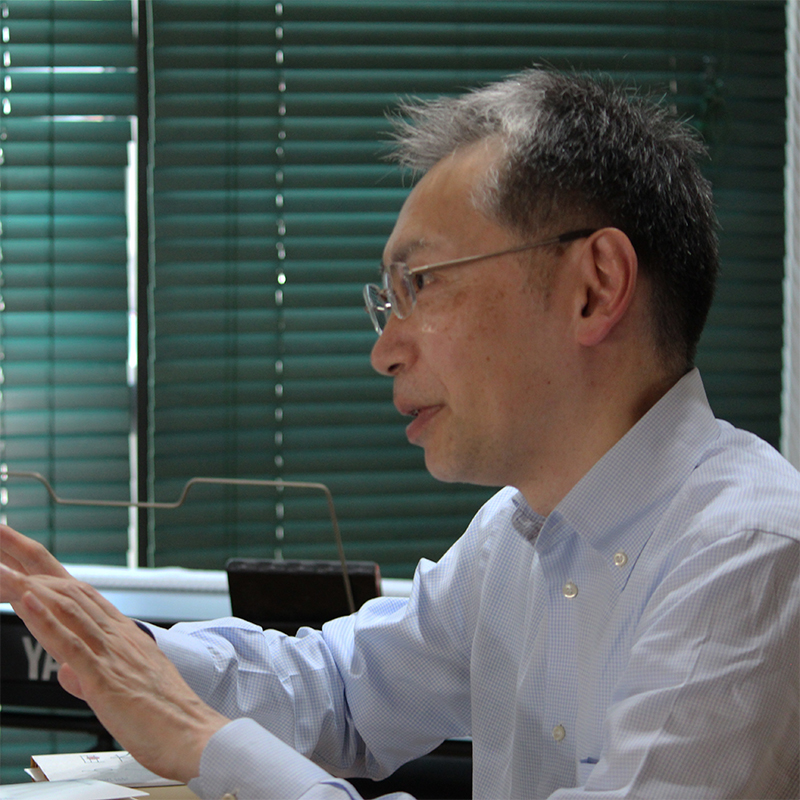
萩野 いや、元々はイスラーム教の影響です。イスラームという厳格な一神教が独自に培ってきた神学の影響があります。例えば、イブン・スィーナーの存在論なんかそうです。
鶴山 ああなるほど。井筒俊彦さんの専門領域だ。
萩野 ユダヤ教は密儀宗教ですから教義を囲い込んで外に出さない。イスラーム教は教義を外に出したから大きく広がり普及した。その神性をめぐる存在論が、後々のハイデッガー以降の存在論にまでつながっています。
鶴山 ハイデッガーの先にまで行くと、グルッと一回りして神秘主義になるんじゃないですか。
萩野 もちろん大元は神秘主義から来るんですが、そこから純粋な論理学と神秘主義が分かれます。
鶴山 ギリシャ哲学の祖はプラトンで神秘主義ですよね。西洋哲学の祖と言ってもいい。プラトンの場合最初にイデアの直観真理が来るわけですが、イデアを神と言うかどうかは別として、イデアの存在について突き詰めて考えてゆくと存在するかしないかの二元論になるんじゃないですか。
萩野 確かに二つの道に分かれます。純粋な無神論と神の実在論。でも存在そのものと神の存在は分けて考えなければならない。
鶴山 そうですね。杓子定規に言うと吉本さんは無神論ですよね。
萩野 もちろんです。ただ、神を信じる者の人間心理にあれだけ通じているところを見ると、根っからの無神論者ではないと感じますね。
鶴山 そうとうヘーゲルを読んでいる。
萩野 読み込んでますねぇ。
鶴山 ヘーゲルの厳密な論理学を前提にすると無神論になるわけだけど、吉本さんの場合、それにプラスして戦後の状況が大きく影響している。それを簡単に無神論と言ってしまうと正確じゃないような気がしますが、徹底した論理的分析重視で直観把握を排除している。
萩野 敗戦の影響は相当大きかったと思います。それまで当然と思っていた信念や世界やものごとの価値が瓦礫と化す経験が敗戦だった。ゼロからの出発を強いられた人たちの一人ですものね。吉本さんが市井の生活人としての「大衆」を思想的拠点にして〝大衆の原像〟ということをいい、誰にもくみせず、どんな党派性にもよらない〝自立〟ということを主張したとき、そこには強い必然性がありました。
鶴山 だから戦後を代表する思想家になったわけですが。詩の話をすると吉本さんは戦後詩人でいい。ですが戦後詩を代表する詩人と言っていいのかどうか、少し迷うところがあります。
池上 そこのところを今日お話ししたかったんです。野村喜和夫さんと城戸朱理さんの『討議戦後詩――詩のルネッサンスへ』では十人の詩人を取り上げて論じているんですが、吉本隆明は入っていません。そもそも、吉本隆明が詩人だという認識がない人も結構いるんじゃないかと思います。
鶴山 吉本さんの詩をどう評価するのかは非常に微妙な問題です。詩は勁草書房版の『吉本隆明全著作集』では三巻分にまとめられています。晶文社版の『吉本隆明全集』は年代順なので分散掲載ですが、初期詩篇は最初の二巻に掲載されている。そのうち公刊されたのは私家版の『固有時との対話』と『転位のための十篇』、それに晩年に角川書店から刊行された『記号の森の伝説歌』だけです。後はすべて『日時計篇』を中心とした未発表詩篇です。ただ数から言えば普通の詩人が一生かかって書く詩の数はじゅうぶん書いている。池上さんは詩は全部読みましたか。
池上 後期の詩は全部は読んでいませんけれど、大学生の頃に勁草書房版の『吉本隆明全著作集』に収載されている詩はひととおり読みました。お二人がおっしゃるように吉本隆明は無神論者かもしれませんが、「『新約聖書』をよんだのは、敗戦直後の混迷した精神状態のさ中であった。その頃は、ちょうど天地がひっくりかえったような精神状態で、すべてを白眼視していた時期であった。(中略)いまおもうと、自分がコッケイでもあり、悲しくもあるが、富士見坂の教会などに行って、牧師の説教をきいたりしたこともあった」(「読書について」『読書の方法――なにを、どう読むか』)と書いています。小林秀雄や江藤淳と比べても、吉本隆明にとって宗教は生涯を貫く本質的なテーマだったと思います。「巡礼歌 La idéalisation」という初期の詩があります。
Ⅰ
梵字廻向の袖は雨臭く
ふたつないさびしい影は
その錫杖の音に連れられて
おゝそれではもう
おれのゐるこの孤点のやうな街を去つて
いまだ雪も溶けない
舟坂峠を越えるのか
おれが街角で貴公の巡礼旅装を見送つて
貴公の後相がまだみえるあひだ
たつたひとりの好意ある道連れなのだが
おれはいつもこんなに暗いし
貴公でさへも峠のサイプレスのあひだで
恋人や妻子を想ふよりは
二三遍の称名をくりかへし
刻み煙草などを喫するだらう
(かまひはしない)
ひとの世はどこもかも訣ればかりだ
そんなことを患うよりは
おれも貴公も
さびしい二月いまはの黄昏を
こゝろのなかでもつことにしよう
Ⅱ
けれど貴公の後相は
たいさう頼りないな
そうして貴公は迷つてゐるな
あまりに空虚なさびしい心に耐えて
念仏など称えて御遍路にあるいたとて
それが何になるのだ
〝もうやめろ――
やめて帰つて恋人や妻子を愛した方がいい〟
おれもむしろ貴公と一緒に
あの舟坂の切通しに立ちたいけれど
あんまりさびしい同志が
一緒になるのはよくないし
それにおれは明日も学校へゆき
悪しみや迷ひがあるとまるで判らない
化学といふのをやらなくてはならない
お互いに漂浪として呑気そうでいながら
どうしてこゝろばかりは
こんなにせはしく熱して辛いのだろう
おれも貴公も
所詮は智度論に説かれてゐる
善悪不行のしがない旅人だけれど
(まあそれはいゝ)
あの吾妻峯が夕映えるころは
醜いものをおさへてゆけよ
昭和二十二年(一九四七年)の詩です。まだ東京工業大学電気化学科の学生時代で、太宰治に会いに行った二十三歲の頃の作品です。「エリアンの手記と詩」(一九四六年)と「日時計篇(上)」(一九五〇年)の間の時期ですね。
鶴山 「智度論」が出て来ますがこれはどういう論ですか。
萩野 『大智度論』といいまして、龍樹(ナーガルジュナ)が書いたとされる大乗仏教の有名な経典です。自分の悟りだけを求める小乗に対して、自分が悟りを得るだけではなく、そこから戻って来て衆生を救済しなければならないと考えるのが大乗の菩薩道です。吉本さんは後年、『最後の親鸞』という代表作の一つを著しますが、この大乗の考え方はその本で展開される思想のコアになります。ちょっと引用しましょうか。「〈知識〉にとって最後の課題は、頂きを極め、その頂きに人々を誘って蒙をひらくことではない。頂きを極め、そこから世界を見おろすことでもない。頂きを極め、そのまま寂かに〈非知〉に向って着地することができればというのが、おおよそ、どんな種類の〈知〉にとっても最後の課題である。」というたいへん有名な文章で、いま読んでもしびれます。この考えはもっと後のハイ・イメージ論まで一貫していると思います。
鶴山 親鸞への親和がすでに表現されているわけだ。「巡礼歌」に関しては相手、他者が見えますね。恐らく実在の他者がモデルにいる。
池上 「善悪不行」という言葉が使われていますしね。この詩は、宮沢賢治に傾倒した米沢高等工業学校の頃を思い出しているわけですが、「貴公」という言葉が何とも言えない雰囲気を醸し出していて、いい詩だなと思います。それと「化学」という、彼にとって実人生の基盤にある世界への直接的な言及があるのも興味深いです。
今回初期のいくつかの著作を読み直してみて感じたのは、吉本隆明は自分の方法をかなり早い時期に確立しているということです。問題認識の枠組みがしっかりできているというか。だから、普通の評論家だと一つか二つの分野しか手がけられないわけですが、吉本隆明はジャンルで言えば詩、文芸批評、言語論、それから平たく言って思想に宗教、あと政治ですか、とにかく多方面にわたって批評活動を展開できたのだと思います。
鶴山 その枠組みっていうのはなんだろう。
池上 一九四九年に書かれた「詩と科学との問題」という文章を読むとよくわかるんですが、カントルの集合論以降の科学的な認識をベースにしたうえで、「僕らに必要なことは表現上のリアリズムとロマンチシズムというような問題を人間の社会意識との関連において思い描くことではなく、言葉の構造の曇りない解析を通して、人間存在の本質に思い到る道を行くことではあるまいか」と言っています。

鶴山 それは詩に表現されていますかね。
池上 あぁ確かに一篇の詩にストレートに表現されているとは言えませんね。ただ村瀬学さんが『吉本隆明 忘れられた「詩的大陸」へ 『日時計篇』の解読』という本で、「日時計篇」に吉本隆明の基本的な思想が表現されていると読み解いていますし、菅野覚明さんは『吉本隆明――詩人の叡智』という著書で『固有時との対話』(一九五二年)を分析して、吉本隆明の「哲学」の基本に「詩」があることを論じています。
一方で、初期の詩を読むと吉本隆明の詩人としての資質がよくわかります。「巡礼歌」は仏教的な関心が表現されている詩ですが、吉本隆明が影響を受けた詩人は宮沢賢治、中原中也、高村光太郎などで、その中でも資質的にいちばん近かったのが立原道造だと思います。『固有時との対話』では、「建築は風が立つたとき揺動するやうに思はれた/その影はいくつも素材に分離しながら濃淡をひいた」というように、「建築」という言葉が印象的に使われています。立原道造の詩には「建築と建築とが さびしい影を曳いてゐる/人どほりのすくない 裏道を」(「晩秋」)という詩行があります。立原は建築家でもあったから「建築」という用語を使ったのかもしれませんが、普通、詩に「建築」という概念的な言葉は使わないと思うんです。「ビル」とか「家」とか、せいぜい「建物」ですよね。吉本隆明の詩は一読すると抒情詩のように思えるんですけれど、よく読むと用語の使い方が非常に独特です。もちろん「荒地」に参加して鮎川信夫や田村隆一の影響を受けて戦後詩の手法を取り入れた詩もありますが、感性的には基本になっているのは近代詩ではないでしょうか。
鶴山 それは「荒地」の詩人すべてに言えることですけどね。「荒地」の詩人たちは戦前に思春期を送っていていわゆる近代詩から多大な影響を受けています。影響と言っても北園克衛や春山行夫、村野四郎らのモダニズム詩の批判的乗り越えも含まれますが、北原白秋や蒲原有明くらいまでは一応抑えている。
吉本さんの初期詩篇はちゃんと読んでいなかったので今回全部読みましたが、正直に言ってつまらなかった。最初期の詩は確かに瑞々しい。「日時計篇」も表題作は「れんげ草が敷き詰められた七月末の野原で ぼくらは日時計を造りあげたものだった」と明るい外界描写から始まるわけですが、すぐに具体物が抽象的になる灰色の内面詩になってしまう。詩の表現が平板。「日時計篇」にまとまっている詩は日記のように書いていたんですよね。
池上 そうですね。芹沢俊介さんによる吉本隆明へのインタビュー(「わたしのものではない〈固有〉の場所に」)によれば、「日時計篇」にまとめられた詩は、一九五〇年から五一年にかけて四七九篇書かれているそうです(「現代詩手帖」二〇〇三年九月号)。吉本隆明自身は、詩で書くものが何もなくなっちゃった、その何も書くことがないという状態の表現だというようなことを言っています。最初期の詩については「自己慰安」、つまり自分を慰めるために書き出したんだと書いていますけれど。さっき引用した「巡礼歌」は「日時計篇(上)」を書き始める以前の詩です。作者の思いが抒情詩として表現されていて、とてもいい作品だと思います。でも「日時計篇」や『固有時との対話』は、まったく異質な作品です。村瀬学さんや菅野覚明さんが「日時計篇」や『固有時との対話』には吉本隆明の思想や哲学があるという、そういう読み方ができてしまうということ自体が、やはり普通の詩じゃないと思うんですよね。
■吉本批評の難解さ■
萩野 基本的にお二人に同感ですが、詩の良し悪しは別として、吉本さんは初期から詩と評論と生活人という三つの柱が三位一体となっている思想家です。この柱は切り離されないままずっと続いていく。それで吉本さんの評論を読んでいると、これって詩じゃないのと思うところがいくつもある。
鶴山 詩と評論と生活が三本柱だというのはその通りですね。特に生活は吉本さんが全共闘世代以降の読者から絶大な支持を得た大きな理由になっている。思想が地に足が着いている。丸山真男なんかをもの凄く批判していますが吉本さんは頭でっかちの抽象論をまったく信じていない。それは個別作家論や状況論ではハッキリ読み取れます。評論初期三部作の『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『心的現象論序説』も地に足が着いている。でも後期になるとぜんぜん理解できない評論が増える。『ハイ・イメージ論』や『心的現象論』本論とかには、読んでもほぼまったく理解できない章があるでしょう。
萩野 そうそう、まったく読み解けないんです。だから、そんな吉本さんの評論は、概念構造だけを取り出して論じてもあまりうまくいかないだろうと思います。吉本さんという思想家がたどってきた文脈そのものに即して読んでいった時に、あっと腑に落ちる瞬間というか、刺さる瞬間がある。そういう特異な文章に接すると、吉本さんってやっぱり詩人なんじゃないかと思ってしまうんです。評論の言葉の表出のあり方が普通の批評家とは違う。
池上 萩野さんの言う詩というのは、具体的にはどういうものを指しているんですか。
萩野 その文脈やその言葉でしか表現できない思想や観念のことです。例えば、『共同幻想論』で出てくる〝逆立〟や〝逆立ち〟だってそうです。〝共同幻想〟と〝個人幻想〟は逆立するって言われても何だかよくわからないでしょう? 『言語にとって美とはなにか』や『心的現象論序説』で語られる〝発生〟にまつわる文章もそうです。〝原生的疎外〟なんて言われると、読んだ時はわかったような気がするんです。ところがそれを、第三者にわかるように説明しろと言われると急にむずかしくなる。それ以外の言葉や用語でパラフレーズできないんです。そのまま受け取り、可能であればそのまま理解するしかない面がある。
鶴山 それは詩の一つのあり方ではあります。詩は直観的断言だからどんなに奇矯な用語を使い、奇妙な文法を使っていたとしてもそこに作家の思想があれば読み解くことができます。ただ萩野さんがおっしゃった〝詩のような評論〟と吉本さんの〝詩〟が直結しているのかというとそれも微妙です。公刊された『固有時との対話』と『転位のための十篇』は言語的起伏があり個々の詩の表現内容も違っていて詩として読める。しかしほとんどの未刊詩は同じような内容をくどいほど書き連ねている。意外と単純な詩です。「自己慰安」のために書いたと言われればそうかなと思いますが。
池上 「自己慰安」のために書いたというのは「日時計篇」よりもっと前の最初期詩篇のことね。

鶴山 うーんそうかな。最初期詩篇には確かに吉本さんの抒情的資質が垣間見えます。その意味で楽しんで書いたんでしょうね。「日時計篇」になると詩の質が変わってきますが最初期よりさらに起伏に乏しい。詩を個々に独立した表現にしようという意識がほとんどないという点で「自己慰安」的な作品に見えます。
おう安らかに眠るひとときを有たせよ
わたしの書物やわたしの仕事にわたしのはりつめた意識が眠り込むときを有たせよ それはひとびとが生存と呼んでゐるところのものだ 何故に? わたしだけが生存をゆるされないのか
わたしだけが未だ書かれない余白を宿運のやうに背負はなければならないのか
何時も重たげに背をまるめて街角を消え去るわたしの後影
また次の一刻わたしは同じ時間のなかを歩むでゐる
わたしには地上におとす影があつたか その影はいつも変わらなかつたか
わたしは知らない 知らない・・・・・・
けれどわたしの影は刻々と変つてゐただらう 移りゆく時が
わたしのうへで刻々と量を変へてゐたのだから
「日時計篇」の〈空洞〉という詩の末尾三連です。「(わたしの)影はいつも変わらなかつたか」以下は反語表現で、「移りゆく時」とともに影は「刻々と変つてゐただらう」と表現されていますが本質的には何も変わらない。萩野さんの「時間論」で論じた方がいいような現存認識かもしれません。
それはともかく吉本さんは「安らかに眠」れない。「わたしだけが生存をゆるされない」。なぜならわたしは「未だ書かれない余白を宿運のやうに背負」っているからです。だからわたしはいつも「同じ時間のなかを歩むでゐる」。しかしそれはまったく特権的意識ではない。他者には出来ない仕事を課された人の特権意識はなくって、その逆に「ひとびとが生存と呼んでゐるところのもの」から放逐されている。社会から疎外された孤独意識が非常に強いわけですがそれを繰り返し表現しています。
なるほど詩が書かれた時期と吉本さんの実人生(年譜)を付き合わせれば、その時々の彼の思考の変化を読み解くことはできます。しかし疎外・孤独意識は一貫している。セレクトすればいい詩もあるんですが、なぜこのような同じ認識を膨大な詩で書かなければならなかったのかは謎ですね。
詩が平板ということを補足すると社会からの疎外・孤独意識がまったく揺るがないということです。鮎川さんの「橋上の人」も孤独なんですが橋の上に立って現世と異界で交流している。田村さんの「おれは垂直的人間」も同様で孤独ですがハッキリ社会と馴れ合うことを拒絶している。それも一つの社会との交流です。しかし吉本さんの疎外・孤独意識は定点的です。内にこもって社会と一切接触しようとせず交流を拒んでいる。そのため痛切なんですが被害者意識のようなものが目立ってしまう。
評論もそうなんですが、吉本さんの批判は切れ味鋭いですが決定的な自己思想を表現するのを嫌う。そこには戦中に尊敬していた思想家や詩人たちが次々国粋主義的思想の波に飲み込まれていった苦い経験があると思います。しかも彼らは戦後にそれを拭ったように忘れて活動を再開した。カッコ良さげな抽象思想を信じないという吉本さんの姿勢は徹底している。またそれは同時代作家だけでなく皇国少年だった自己にも及んでいる。自己もあまり信用していませんね。しかし例外的表現もあります。
ぼくの孤独はほとんど極限に耐えられる
ぼくの肉体はほとんど苛酷に耐えられる
ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる
もたれあうことをきらつた反抗がたふれる
ぼくがたふれたら同胞はぼくの屍体を
湿つた忍従の穴へ埋めるにきまつてゐる
ぼくがたふれたら収奪者は勢ひをもりかへす
だから ちひさなやさしい群よ
みんなひとつひとつの貌よ
さやうなら
戦後詩の文脈での吉本さんの詩の代表作は『転位のための十篇』の「ちひさな群への挨拶」でいいと思います。田村隆一篇で言いましたがこの詩の「ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる」という詩行は田村さんの「おれは垂直的人間」といった決定的断言に影響を受けている。「荒地」派から受けた最大の影響でしょうね。
ただ今回初期詩篇を読んで思ったんですが、吉本詩では「ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる」という詩行の方が例外的です。彼はこんな決定的なことを書く詩人ではない。また以前読んだ時は勇ましい詩だと感じたんですが、初期詩篇から通読していくと「ちひさなやさしい群」=社会と折り合えない悲しみのようなものの方が迫ってくる。吉本さんは多くの理解者・信奉者に囲まれていた人なので不思議ですね。優れた作家は正直だから、もしかすると「ちひさな群への挨拶」のような柄にもない詩を書いてしまったことがその後の詩作上の長い沈黙になったのかもしれません。
池上 先ほど挙げた芹沢俊介さんのインタビューでは吉本隆明は「たしかに『転位のための十篇』では、当時の「荒地」の人たちの詩のレベルに、ある程度は追い着くくらいの表現が自分でも出来たと思いますし、現実の事や物を詩のなかに自分なりの表現として持ち込むことが出来たと思いますけれども、そのあとのレベルを一貫して維持することは自分にはなかなか難しかった。(中略)もっと詩をやればよかったんだと思いますけれども、詩で食べていきたくても自分には出来なかったんだっていうのも理由のひとつになるでしょうか」と言っています。当時というのは『転位のための十篇』が刊行された一九五三年頃です。
ちょっと話は変わりますが、『固有時との対話』や後期の『記号の森の伝説歌』(一九八六年)は元になったたくさんの詩を再構成して詩集にしていますよね。『固有時との対話』は「日時計篇」の再構成だし、『記号の森の伝説歌』は雑誌「野性時代」に一九七五年から八四年まで連載していた六十六篇の連作を再構成している。吉本隆明は詩を自然体で書いていると思うんですが、それを再構成して、いわば不自然にして刊行するのはどういうことなんでしょうかね。再構成して詩としてよくなっているかというと、ぼくにはそうは思えない。詩集を作る時は詩を並べ替えたり取捨選択することはあるでしょうが、全面的に作り変えちゃう、あるいは作り変えられるというのはどういうことなんでしょう。
鶴山 吉本さんは弱音を吐かない、弱みを見せない作家だからね。もんの凄く乱暴なことを言うと文学は弱者の表現という面が確実にある。金も力も持ってる人が文学をやることはあまりないでしょう(笑)。あえて人間の弱い面を表現するのが文学の魅力になったりします。でも吉本さんが公刊した本はだいたい強気。それは詩集でも言えることで彼本来の柔らかい抒情的部分を削ってしまう。
加えて吉本さんの本の出し方は書き捨てに近い。もちろん一作ずつ全精力を注ぎ込んでいる力作なんですが、次の仕事に移ると忘れてしまうようなところがある。初期詩篇も非常に不思議なまとめ方で吉本さんは詩稿ノートをポンと川上春雄さんに渡して編集してもらっている。生きている間に著作集や全集撰が出ているわけですから普通の人なら自分で未定稿や難読文字を校訂すると思いますが一切やってない。『言語にとって美とはなにか』という名著を書いた人ですが言語表現に対する美意識が欠けていると言わざるを得ない面がある。
池上 『記号の森の伝説歌』の元になった詩は、「野性時代」に連載していた時にチラチラ読んでいたんです。写真が一緒に載っていて、レイアウトとしてもすごく新鮮に感じました。同時代の詩としても結構いい連作なんじゃないかなと思っていたんです。それが詩集になったら、まったく印象が変わってしまった。文字にこだわったり、ルビを多用したりしていてなんだか昔の詩集みたいで、通読してガッカリしました。
萩野 吉本さんは評論でもルビやゴシック体を多用しますね。『マス・イメージ論』なんてそうですが、独特な強調の仕方でなぜこんなところを、と思う部分をゴシックにしたりする。でもそれを真似したくなるのが吉本さんの文章(笑)。それと、吉本さんの文章には飛躍があります。『マチウ書試論』ではえんえんと新約聖書「マタイ伝」の批判を書いてきて、最後に有名な「関係の絶対性」という言葉が出て来ます。「律法学者やパリサイ派にたいするマチウの作者の、蛇よ、まむしの血族よ。という憎悪の表現はここからヒントを得たのだが、原始キリスト教の苛烈な攻撃的パトスと、陰惨なまでの心理的憎悪感を、正当化しうるものがあったとしたら、それはただ、関係の絶対性という視点が加担するよりほかに術がないのである」と言って終わります。でも、それまでの文脈を踏まえてもこの「関係の絶対性」の意味がよくわからない。わかるようでわからない。もっと後になって、『最後の親鸞』で「殺害などすまいとおもっても、百人千人を殺すこともありうるはずだ」という親鸞の言葉を引いている箇所で、やっとこういうことかと思った。さっき吉本さんの評論は詩のようだと言いましたが、それは文章の異様な飛躍が大きいということでもあります。
池上 『固有時との対話』と『転位のための十篇』の「固有時」や「転位」は元々科学用語でしょう。もちろん固有の時とか転調の時期とか文学的に読むことはできるんですが、吉本隆明の中では彼独特の科学的意味が付与されているんですよね。「固有時」については先ほどの芹沢俊介さんのインビューの中で、量子物理学の「固有値」から来ているって説明しています。「〈固有時〉は、その人に固有の時間の流れ方という意味でなくて、要するに点々としてしかその人の位置や状態を言えないということです」と語っている。確かにこの説明を読んだら、『固有時との対話』の世界がだいぶわかる気がしたんですが、ぼくはずっと「固有の時間」だと思っていた(笑)。要するに作者の意図は全然伝わって来ない。というか、「点々としてしかその人の位置や状態を言えない」という事態が、「固有時」という普通に意味としては伝わらない事態として表現されちゃっている。これについてはどう理解したらいいんでしょうね。「荒地」派の詩人で吉本隆明のように科学用語を詩に使っている人はいません。
鶴山 それはよくわからない。「荒地」の詩人たちは正統文学青年たちだから、詩では言語的豊かさ、抒情、それと直観的表現の切れ味を重視しました。でも吉本詩にはそのいずれの要素も少ない。科学的用語といえばそうなんですが、じゃあ本家科学と強い関連があるのかというとそうでもない気がします。
池上 最近、講談社文芸文庫で『わたしの本はすぐに終る』という吉本隆明のセレクト詩集が出ました。長女のハルノ宵子さんが「著者に代わって読者に」ということで書いているんですが、「父の詩は分かりづらい。人が理解しようがしまいがおかまいなしに、ことばを事象をゴンゴンと積み上げていく。共有できなければ、叙情でもなく叙事でもない、抽象的な言葉の羅列だ。だが3割程がうまくハマる(私の場合はね)。刺さる人は、全面的にブッ刺さるのだろう。(他の文章と同様)実に不親切なのだ。だから何ひとつ訳分からなくても、決して悲観しないでください」とあります(笑)。
鶴山 その通りですね。さすが長女さんだ。
池上 「人が理解しようがしまいがおかまいなしに、ことばを事象をゴンゴンと積み上げていく」というのは詩だけじゃなくて、評論でも同じですね。
鶴山 詩や小説の解釈が多様になるのはある程度当然ですが、吉本さんの場合評論の解釈も膨らみを持ってしまう。すんごい初歩的イメージなんですが吉本さんは左翼とみなされていた。公安にマークされているというまことしやかな噂もありました。でも共産主義はもちろん暴力革命に対しても否定的です。『カール・マルクス』の著作もありますが貨幣論には一切触れていない。「マルクスの〈自然〉哲学の本質である人間と自然とのあいだの〈疎外〉関係」をヘーゲルを元にえんえんと論じている。吉本さんは生活から乖離した抽象思想を一切認めないんですが論としては分析と批判に留まる。でも読者が吉本さんの評論を読んでその先に左翼といったイメージを作り上げていった。左翼が吉本さんの厳しい知識人批判を拡大解釈していた面がある。
萩野 吉本さんはぜんぜん左翼じゃないですよ。もちろん保守でもない。『マス・イメージ論』以降の吉本さんを、資本主義におもねる主張だと批判して離れていった人もいる。でも、吉本さんはそんなこと承知の上ですから。軸はまったく変わっていない。
池上 鮎川信夫が吉本隆明と付き合いだす前に最初に発した質問は「あなたはコミュニストですか?」だったそうです(笑)。一九六八年に書かれた「「マチウ書試論」まで」という文章に書かれているんですが、鮎川信夫が吉本隆明に初めて会ったのは一九五三年の秋ですから、当時はそういうイメージがあったんでしょうね。
それから、先ほど挙げたハルノ宵子さんの文章は「佃渡しで」というタイトルで、吉本隆明の代表作の一つ「佃渡しで」という詩にまつわるとてもいいエピソードが書かれていますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。その詩の最後の連です。
〈あれが住吉神社だ
佃祭りをやるところだ
あれが小学校 ちいさいだろう〉
これからさきは娘に云えぬ
昔の街はちいさくみえる
掌のひらの感情と頭脳と生命の線のあいだの窪みにはいつて
しまうように
すべての距離がちいさくみえる
すべての思想とおなじように
あの昔遠かつた距離がちぢまつてみえる
わたしが生きてきた道を
娘の手をとり いま氷雨にぬれながら
いつさんに通りすぎる
一九六四年に刊行された『模写と鏡』という評論集に収載された詩なんですよね。吉本隆明自身も思い入れのある詩だったんだろうと思います。吉本隆明の詩の中ではやさしい作品で、抒情性もあり、ハルノ宵子さんも「名詩と言われる」と書いています。ところが、一九七二年の「現代詩手帖」1月臨時増刊の「「荒地」の意図と成果」という座談会では、鮎川信夫の評価がものすごく厳しかった。中桐雅夫が「あれは、いい詩だね」と言ったことに対して、「「転位のための十篇」を書いてからのあとの詩は、(中略)詩が、自分の思想の宣伝みたいになっている。「佃島」はぼくも好きだけどね、何かやっぱり宣伝がかった感じはいなめない」と言って、さらに「「転位」のころは、あの詩の中にすべてが凝縮して、骨みたいに入っていた。だけどその後になるとそうじゃなくて、詩でございますって詩だよ」と、ちょっとびっくりするぐらい手厳しい。実はぼくも最後の三行がちょっとわざとらしい感じがして、あまりよく書けている詩だとは思えないんですけどね……。
鶴山 「荒地」の総帥鮎川さんとしては吉本詩は「ちひさな群への挨拶」の「ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる」であって欲しかったんじゃないですか。でも吉本さん本来の資質は「佃渡しで」の方にある。かつ彼自身がそれを抑圧していった気配があります。
池上 詩の話を続けると、一九八九年に刊行された『言葉からの触手』という断片集があります。『わたしの本はすぐに終わる』では詩に分類されていますが、吉本隆明自身は詩とは言っていない。だけど詩的というしかない不思議なフラグメントから成る作品です。
概念はどんなふうにつくられるものか。その過程が高速度映写され、ゆっくりとスクリーンに投影されたと仮定する。いま「海辺の草花」という「概念」がつくられるとする。それは海辺の岩や砂浜のかげで見かけるたくさんの草花、たとえば、浜かんぞう、せんだい萩、はまゆう、つばな、ふじなでしこ……などの視覚像から共通の芯にあたるものが抽出されてつくられる。共通の芯にあたるものは「概念」にまで抽出されたときには、もう視覚的な像を離脱して、あるレベルで抽象的なものになっている。だがこのものはいったいなにか。(中略)うまく言葉で捉えることができない。また名づけようもない。意味ある抽象体のレベルにあって、起源が具象的な実在の視覚像であるものが「概念」だ、としかいいようがない。(後略)
「7 超概念 視線 像」の冒頭です。『ハイ・イメージ論』で論として書かれていることが、凝縮されて、言ってみれば詩的に表現されています。例えば「海辺の草花」という「概念」は、「浜かんぞう、せんだい萩、はまゆう、つばな、ふじなでしこ」などの「視覚像から共通の芯にあたるものが抽出されてつくられる」と書いています。この「浜かんぞう、せんだい萩、はまゆう、つばな、ふじなでしこ」という例の選び方と言葉の表記の仕方に、吉本隆明の詩的な感性が現れていると言えると思います。『言葉からの触手』が詩なのかどうかは別として、批評と詩の交点で成立している文章ではないでしょうか。
鶴山 晩年に近づくと批評が甘くなっているとも言えますね。優れた作家はそうですが、皆抱えている主題(テーマ)は一つです。吉本さんの場合は評論初期三部作の『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『心的現象論序説』にそれが表現されている。
『言葉からの触手』「7 超概念 視線 像」について言えば『言語にとって美とはなにか』の「たとえば狩猟人が、ある日はじめて海岸に迷いでて、ひろびろとした青い海をみたとする。人間の意識が現実的反射の段階にあったとしたら、海が視覚に反映したときのある叫びを〈う〉なら〈う〉と発するはずだ」という問いかけを繰り返している。それは完全解明不可能な起源を巡る問いかけです。晩年になるとそのアポリアを性急に探求する姿勢が出て来ます。「せんだい萩、はまゆう、つばな、ふじなでしこ」といった例も『初期歌謡論』から来てるんじゃないかな。
これもちょっと乱暴ですが『ハイ・イメージ論』の時代になると吉本隆明版小林秀雄の『考えるヒント』じゃないかって思えてしまうようなところがある。もちろん評論の質はぜんぜん違います。ただ両者とも謎かけのように思考のためのヒントを放り出しているようなところがある。吉本さんの用語は独特で本当に理解するのに苦労しますが、後期になるとそれがどんどんエスカレートして直観理解するしかない。あるいは解釈が多義的にならざるを得ない。
(金魚屋スタジオにて収録 「吉本隆明篇」第01回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。
■萩野篤人さんのコンテンツ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


