 自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
by 金魚屋編集部
池上晴之(いけがみ・はるゆき)
一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚に連載。
鶴山裕司(つるやま ゆうじ)
一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。
萩野篤人(はぎの あつひと)
一九六一年、埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元IT関係の会社員。十代の頃から文学・哲学・思想に関心を持つ。二〇二三年、相模原障害者殺傷事件をテーマにした評論『アブラハムの末裔』で第一四回金魚屋新人賞を受賞。現在、小説『春の墓標』を文学金魚で連載中。
■吉本の批評の方法■
萩野 吉本さんは江藤淳と幾度か対談しているんですが、一九八八年九月に行われた対談がとても面白かった。吉本さん六十三歳の時です(「文学と非文学の倫理」『吉本隆明 江藤淳 全対話』)。ちなみに江藤さんは吉本さんより七歳年下だと言ってますから、当時五十六歳ということになります。その中で吉本さんが「僕は小林秀雄が六十三か四のときにどういう仕事をしていたのかなと考えます」って言ってるんです。意外に思いました。もともと吉本さんは小林秀雄批判から批評家として出発したと言ってもおかしくない人です。だから小林はとっくに乗り越えられた存在なんだろうと思っていました。もちろんこの対談の時も、ああいうふうにはなりたくないぞという意味合いで言ってるんですが、その歳まで意識せずにおれない存在だったのか、って。吉本さんが小林秀雄のどこを批判したかと言いますと、ちょっと図式的ですが、初期のマルクス主義批判を展開した時の小林は評価できる、けれど後の小林は結局何を論じても自意識のドラマを演じてしまう。そこには他者との「関係性」が抜け落ちている、ということです。他者との出会いもまたドラマの世界になってしまう。それは晩年になっていっそう純化され、日本的な花鳥風月の世界とも距離感を失うようになった。一九七九年の『悲劇の解読』の小林秀雄論で吉本さんはそれを批判してこう結んでいます。「肉体のように眼に視え、肉声のように耳に聴くことができる思想と論理だけに席があたえられ、それ以外なものは削りとられる。この観念の肉体は生々しいかもしれないが、蝸牛のように殻の内だけを磨くことになる。だいたい思想や論理が、肉体や肉声のように生々しいだけで済むようなあらゆる抽象と論理と感覚の行手はたかが知れている。小林秀雄が到達した場所はそこであった」。
とは言え同じ六十三歳の時に二人は何を書いているかというと、小林秀雄は『考えるヒント』を連作する中、『本居宣長』の連載を始めています。一方吉本さんは『ハイ・イメージ論』です。しかも『心的現象論』を長期連載しながらです。文体も思想も内容も方法論もまったく違う二人ですがどこか共通するものを感じるんです。まず基軸がブレないという点、次にこれぞ小林秀雄であり吉本隆明であるという、それぞれの批評家としての営みをある意味で深化させるような大作・代表作が書かれている点、いや吉本さんからしたら小林の場合は退化だよって言うかもしれませんが(笑)。でも両方とも大家だ(笑)。そんな大家としての自らのあり方というかな。吉本さんが生きていたら違うぞって言うかもしれないけど、でも小林秀雄に続く批評家は江藤さんより吉本さんだと思うんですよ。
鶴山 吉本さんの批評の方法について整理しておいた方がいいと思うんですが、『共同幻想論』では「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」という三つの概念を元に社会というものの発生を考察した。『言語にとって美とはなにか』は古代から現代に至る文学史ですが軸になっているのは自己表出性と指示表出性という二つの軸です。軸というかXY軸の相関的漸近線だな。社会全体が動揺して人間の自我意識(危機意識)が高まる時期には自己表出性が強くなる。戦後の太宰治の会話体などがその例としてあげられています。社会が平穏で文化が成熟すると指示表出性が強くなる。文学の修辞が発展する時期で『新古今』時代や明治末から大正初期の時代などが例にされています。『心的現象論序説』は本論を含めて難解極まりないですが、空間把握と時間把握を元にいわば人間の脳のニューロンが捉える心的現象全般を解き明かそうとしています。乱暴に言えば吉本さんは批評家として出発する際に三つの原理論を書いてその基盤に据えた。社会原理論、文学原理論、人間心理原理論です。この吉本原理論は直観把握から始まるヴィジョンの論理化ではなく分析的関係性理論です。
わたしたちは、言語が、機能化と能率化の度合をますますふかめてゆく事態を知っている。生産力の高度化と生産関係の複雑化にともなって、言語の指示機能は能率化を強いられ、それ自体が明晰になることを余儀なくされる。これは言語においては語彙の多様化と、個々の語彙の内部での明晰さを強いられることを意味する。概念をあらわす語彙は増える一方であるが、それとともに個々の語彙は、ある概念と一対一で対応する記号化の作用をますます強くされてゆく。
しかし、これが言語の現代性のすべてではない。この語彙の多様化と明晰化とは、言語の内的な構造を分裂させ、一方では、幻想性はますます言語の内部で、この機能化と能率化に疎外された本質を抽出してゆく。はじめは、言語を自己表出と指示表出の構造をもった球面として想定できるとすれば、この言語の現在性は、自己表出と指示表出との分裂した歪みとして想定することができる。
『言語にとって美とはなにか』の一節ですが吉本さんの方法論がよくわかります。言語表現における自己表出性と指示表出性は、時代ごとに、作家の実人生の時々においても不断に蠢き続けている。それを古代から現代まで通史的にテキストを分析してゆくと文学史が出来上がる。もちろん吉本隆明独自の文学史ですがそれは正しい。吉本さんの分析能力は驚異的ですからそれを積み重ねた原理論は自ずと強い説得力を持ちます。ヘーゲル的ですね。
ただ吉本原理論が分析に基づいていることは常に意識した方がいい。吉本さんの分析は少なくとも中期までは緻密かつ正確なのでそれを積み上げてゆくとある結論に達する。分析があれば結論は書かなくてもいいということでもあります。中期までの吉本さんの政治や知識人批判が分析批判に留まっているにも関わらず読者が〝その先のイメージ(観念)〟を生み出してしまう原因がここにあります。
またこんなことを言うと怒られるでしょうが吉本さんの分析論証の積み上げは、乱暴なことを言うと案外常識的です。分析が正確なら当たり前ですがそうなります。つまり優れた文学者や思想家が直観把握したヴィジョンを元に作品を書いたり批評で論理構築していった場合と同じ結論に達する。
『初期歌謡論』は『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『心的現象論序説』に基づく名著ですが、古代母権社会が父権社会に移行してゆく過程での和歌の成熟を論じています。しかしこれは直観ヴィジョンで捉えることもできる。小原眞紀子は『文学とセクシュアリティ―現代によむ『源氏物語』』で男性性と女性性のXY軸からなる「テキスト曲線」で『源氏物語』から江國香織さんらの現代文学まで論じました。これは母系と父系と言い換えることもできる。両者とも原理論ですがそれは分析によっても直観によっても論証できる。これも乱暴かもしれませんが文学者は直観把握から始め批評家は分析から始める傾向がある。吉本さんが文学者資質であったかというと、やはり批評家資質だったと言わざるを得ないんじゃないかな。
萩野 今の鶴山さんのお話に付け加えますと、吉本さんが原理的な著作・思想を生み出すさいの手法でもう一つ特徴的だと思うのは、言語でも心的現象でも社会・国家でもそうですけど、それぞれの分野で〝世界認識の方法〟またはそれに匹敵するような領域を開拓し確立した思想家や学者がいますよね。その著作を批判的・分析的に包み込むことで独自の吉本世界を生み出していく点です。吉本さんが生み落とした数々の独特の概念用語はそのプロセスの産物です。『言語にとって美とはなにか』なら時枝誠記と三浦つとむの言語学から自己表出と指示表出という概念をみちびきましたし、『心的現象論序説』だったらフロイトと、解剖学者でユニークな生命哲学の提唱者だった三木成夫で、原生的疎外とか構造って言ってるのがそうです。構造っていうのはいわゆる構造主義の構造とは意味が違う吉本さん独自の概念です。完全に自分のものにしていない概念や思想はけっして用いない人ですから。『共同幻想論』なら西洋の社会学者や人類学者などを安易に引かず柳田國男というように、相手の選び方が上手いですね。彼らを批判的に乗り越えることで自らの世界認識を確立してきた。柳田國男を吉本さんや小林秀雄を通して読んだという人はけっこう多いと思いますよ。『初期歌謡論』ならもちろん古典そのものが相手ですが、そこにはやはり折口信夫の影を感じます。
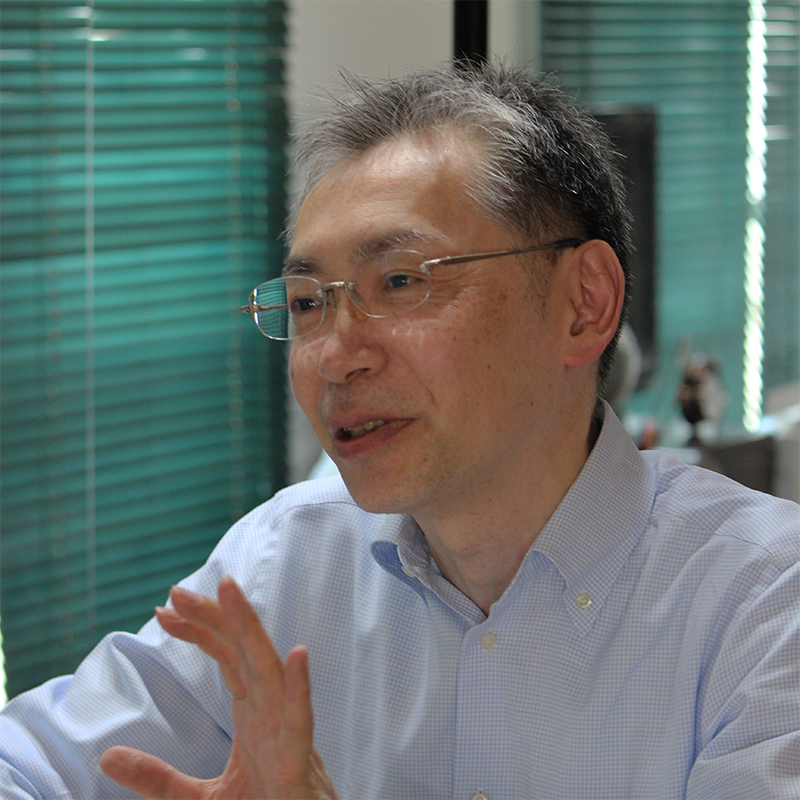
池上 萩野さんがおっしゃった小林秀雄についてですけれど、ぼくは高校二年生の時に吉本隆明の講演を聴いたんです。一九七九年の三月で、無限アカデミーの現代詩講座でした。テーマは「現代詩の思想」だったんですが、話の中で小林秀雄についてはっきり批判したんですよ。それは今でもすごく印象に残っていて、要するに小林秀雄は若い時はフランス文学をやっていたのに、自分の老いを意識した時に、日本的なもの、つまり本居宣長ですよね、日本的な思想を肯定して元の木阿弥に戻ってしまったんだ、それが日本の知識人の典型なんだという批判なんです。若い時にヨーロッパの文学や思想にいかれて、年を取ると日本的な美学や思想にいかれるっていうのは順番が逆じゃないか、って言っていました。ぼくはこれから大学に行ってフランス文学をやろうと思っていましたから、内心、困ったなぁと思ったのと、自分も年を取ると日本回帰しちゃうのかなって心配になりました(笑)。
小林秀雄の『本居宣長』が刊行されたのが一九七七年の秋で、まだその余韻があって、吉本隆明がどういう評価をしているのか、ぼくも興味がありましたが、質疑応答で質問した人がいたんです。そうしたら、もう徹底的な批判でした。小林秀雄は年を取って、社会制度とか政治制度に対する考察がどうでもよくなっちゃって自然思想を受け入れているのに、本居宣長をダシにして後から論理をつくっている、しかもその論理がデタラメで、批評家が言うべきことじゃない、ああはなりたくない、と吉本隆明は言ったんです。小林秀雄は本居宣長の言葉を使って天皇制はいいと言っているのがダメだっていう批判でした。何にも言わなければそれでいいのに、制度について言うのがやりきれない、江藤さんも同じだって言っていました。
鮎川信夫篇の時にも言いましたけど、吉本隆明は講演はすごくわかりやすくておもしろいんです。文章を読むとわけがわらないんですけれど。構文がねじれていて何度読んでも文章の意味が取れないことが多い。やっぱり読む人のことは考えていないですよね(笑)。ハルノ宵子さんが、あれだけ仕事をしたのにノートは一冊もなかったって言っていることからすると、本として出版されているものがノートだったんじゃないかって思うんですよね。『心的現象論・本論』なんて、ノートそのものだと思うなぁ。だから、もしこれから吉本隆明の本を読んでみようと思っている人がいたら、『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』『心的現象論序説』といった原理的な著作は無理して読む必要はないと思います。読んでもまずわからないから(笑)。
吉本隆明の思想の核心を彼の表現を使ってひとことで言えば、「言葉という思想」ということになると思います。わかりやすく言えば「詩とは何か」ということなんです。詩を書いたことがある人なら誰でもすぐわかると思うんですが、詩を書き始める前に「詩とは何か」なんて考えて書き始める人はいないわけです。最初は誰だって何か自分の心の中に言いたいことがあるけれど、それをうまく言えないから詩を書きだすわけですよ。だけど、今度は自分が書いた詩を自分で読んでみると、自分が言いたかったことが必ずしも表現できているわけじゃない。中原中也みたいには書けないんだってことがわかる。友だちに読んでもらっても、「なんかよくわからないね」とか言われてしまう。親しい他人に通じないくらいだから、もちろん社会の中でも自分の表現した言葉は流通しない。じゃあ、そもそも「詩」っていったい何なんだ、「言葉」って何なんだ、「表現」って何なんだということで批評意識が芽生える。だから詩人はたいてい批評や詩論も書くようになるんです。鶴山さんも『自由詩論』を書いていらっしゃいますよね。吉本隆明もここから始まっているんだと思います。
これはぼくの考えに過ぎませんが、三部作も核心にあるのは「言葉という思想」で、吉本隆明の中では「詩とは何か」という問題意識が根底にあって、『言語にとって美とはなにか』は「表現された言葉」つまり「文学」について、『共同幻想論』は「言葉がつくり出す世界」つまり「観念」について、『心的現象論序説』は「言葉を生み出す心」つまり「発生」について、模索しながら考えているんだろうと思うんです。ここのところをよくわかっていないと、『言語にとって美とはなにか』を言語論だと捉えたり、『共同幻想論』を社会思想だと捉えたり、『心的現象論序説』を哲学だと捉えたりしても、吉本隆明が何を本当に問題にしているのかが理解できないんじゃないかと。要するにキモは「言葉」だと思うんです。「言葉」の問題をすっ飛ばしちゃって、文学論とか社会思想とか哲学といった既成概念の枠組みの中で捉えても吉本隆明の「思想」というか、そもそも何でこんなことを論じているのか、その理由がよくわからないんじゃないかという気がするんですけどね……。
というわけで、もちろん三部作は重要なんですけれど、そう言うぼく自身、何度読んでもよく理解できないので(笑)、詩に関心がある人には、むしろ『初期歌謡論』を読むことをおすすめしたいですね。これもノートと言えばノートなんですけれど、文章も原理論のように読みづらくないし、話が具体的だから、読もうと思えば読めると思います。神話の「歌謡」から「和歌」の成立までを論じていて、「日本の詩の原理」を考えるうえでは重要な本だと思います。
鶴山 『初期歌謡論』は学問的に正しいかどうかは藤井貞和さんとかに聞かないとわからないですが、恐るべき本です。『言語にとって美とはなにか』とかもそうですが、まずあんなに本を読めない。吉本さんの読書量は驚異的で、しかも古代から現代に至る本の内容を正確に把握している。
池上 『言語にとって美とはなにか』は原理論ですけれど、それを具体的に展開した文芸批評はあまり書いていないですよね。『初期歌謡論』くらいなのかな……。あと昔から引っ掛かっているんですけれど、『言語にとって美とはなにか』の「美」って何なんですかね。
鶴山 吉本さん独自の美的感覚でしょうね。『言語にとって美とはなにか』は基本自己表出性と指示表出性の関係性理論ですからそのバランスが取れたポイントが美なんじゃないでしょうか。つまり美もまた相対的。それは吉本さんの優れた点であり物足りない点でもある。ただ吉本さん的なやり方で『島尾敏雄論』や『高村光太郎論』、『宮沢賢治論』などでそれを表現しようとしたのではないかと思います。だけど『島尾敏雄論』や『高村光太郎論』の分析は非常に正鵠を得ているんですが、『宮沢賢治論』は的を大きく外している。賢治の本質を射貫いていない。
萩野 そう思います。ただ、吉本さんは宮沢賢治に対する思い入れがずっとあって、うまく距離が取れていないせいで結果的に的を外してしまっているような気がするんです。「江藤さんについて」というインタビューがあるんですが(二〇一一年九月、聞き手は大日方公男、『吉本隆明 江藤淳 全対話』)、そこでこう言っています。「(賢治は)人間や社会や思想を水平的な地政学として考えるより、宗教的というか、垂直的な天上の問題として捉えて、生命というものをそこから眺めてゆくところがある。個々の人間が鎖のように繋がっていて、時間も空間も越えてゆくような思想を賢治は持ちました」。これは賢治というより、自分自身のことを言っていますよ。この見方は『ハイ・イメージ論』にもつながってくるしこの本をはじめ賢治への言及も多い。共感が必ずしも批評に結びついていないという例じゃないでしょうか。漱石なんてどう捉えていたんでしょう。
鶴山 夏目漱石論は書かなかったですが講演があります。しかしこれも外している。吉本さんは江藤淳と同じように漱石小説の三角関係に強くこだわった。それを漱石文学の本質として捉えようとした。でも小説において三角関係は手法であって本質になり得ない。単純に言ってなんらかの三角関係がなければ小説に必須の事件を起こせないからです。小説では恋人や夫婦の一対一の関係でも強い観念軸などが措定されていて広義の三角関係になっています。恋人の死とか理想的対幻想とかね。漱石小説の三角関係を重要と捉えるのはリテラルな吉本さんとしては当然なんですがその限界はすでに江藤淳の漱石論で示されている。大思想家ですが吉本さんは万能でも全能でもない。島尾敏雄や高村光太郎論が優れているのは彼らが戦争の痛みを骨身に染みて感受した作家たちだからです。『ハイ・イメージ論』で舞踏なども論じていますが、それも本質を把握できていないですね。
池上 『ハイ・イメージ論』とか『共同幻想論』とか『心的現象論』といったタイトルの付け方からすれば、『言語にとって美とはなにか』は『言語表出論』とかになっていてもおかしくないと思うんですけれど、そうはなっていない。吉本隆明の本の中でも『言語にとって美とはなにか』っていう書名は例外的だし、文法的にもへんなタイトルですよ。「言語にとっての美」ですからね……。ぼくが昔この書名から連想したのは、服部達の『われらにとって美は存在するか』だったんですよね。吉本隆明は一九五四年に奥野健男と同人誌「現代評論」の創刊に参加して、「反逆の倫理―マチウ書試論」を発表するんですが、服部達もこの「現代評論」の創刊同人でした。吉本隆明より二歳年上ですけれど、翌一九五五年に「われらにとって美は存在するか」を「群像」に連載したり、「メタフィジック批評」というのを提唱したりして批評家として注目され始めた時にプライベートな問題で若くして自殺しちゃうんです。
吉本隆明は服部達を悼む「挽歌 服部達を惜しむ」という詩を書いています。
きみは証せ
或る死が 或る時ちいさな希望
かもしれない理由を
よせあう頬と喰べるパンが
なくなつたのではない
洗つた髪が抜けおちたのでもない
駈けつけた電話口が拒んだのでもない
しずかな しずかな死が希望
かもしれない理由を
きみの失踪は昨日
揺れるこころできめられた きみは
ほんとの虚栄とほんとの絶望のあいだで
ほんとの涙と
うその弔辞を拒んで去つた
肌ざむいきみの衣裳に
夕陽は やさしく消え
背丈よりもひくく眠らせた
きみは
時代が 眠りを拒み 毒死を惜んで
ちいさなノートの余白に
のこした約束をみつけられなかつたか
戦火にさらされ
戦火によつて死にそこなつたものに
無償の死は
いつもあこがれだつた きみは
おぼえているか
かつてわれらの最後のイメージが
硝煙と業火のなかで描かれたことを
きみの
荒涼とした論理には
はにかんだ空白があつた いまそれは
ひとすぢの真昼の夢のように
われらの
たたかうべき果てに合流する
この詩は「近代文学」の一九五六年四月号に発表されました。あまり取り上げられないんですが、とてもいい詩ですし、重要な作品でもあると思います。この一九五六年という年は、吉本隆明がいちばん困窮していた時期で、鮎川信夫が翻訳の下訳を廻してくれたりして凌いでいたんです。ちなみに吉本隆明が下訳をしたと思われるエラリー・クイーンの小説があって、タイトルは忘れちゃったんですが、訳語が「鬼ばばあ」とかね、読めば絶対鮎川信夫訳じゃないってすぐにわかります(笑)。
服部達は三角関係で悩んで自殺したと言われているんですが、吉本隆明自身もこの年は三角関係で「ほとんど進退きわまる」って自分で書いている年です。そんなこともあってか、「きみは/ほんとの虚栄とほんとの絶望のあいだで/ほんとの涙と/うその弔辞を拒んで去つた」と「ほんと」という吉本隆明にとっていちばん大切な言葉を繰り返し使っているくらい、この詩には深い感情が流れています。そして「戦火にさらされ/戦火によつて死にそこなつたものに/無償の死は/いつもあこがれだつた きみは/おぼえているか/かつてわれらの最後のイメージが/硝煙と業火のなかで描かれたことを」という詩行があります。服部達は陸軍の特別操縦見習士官だったんですけれど、吉本隆明にとっては「死にそこなったもの」同士だという意識があったんでしょうね。この詩は吉本隆明が戦後詩人である証しだと思います。
吉本隆明は服部達の遺稿集『われらにとって美は存在するか』の書評では、論としての「われらにとって美は存在するか」を「仮面の論理」だと批判しながらも、「原理的な批評家に親近感を持つ」と書いています。『言語にとって美とはなにか』の中でも、大岡昇平の文体を論じるところでわざわざ服部達の「大岡昇平論」を引用していますし、この詩の「われらの/たたかうべき果てに合流する」という強い表現を読むと、吉本隆明は一九六一年九月の「試行」創刊号から連載を始めた「言語にとって美とはなにか」というタイトルの中に「われらにとって美は存在するか」というタイトルを秘かに込めて、服部達の論理の「空白」、それは戦中派に共通する「倦怠」だと書評で書いているんですけれど、その倦怠を自分自身の論理で乗り越えて行くことを、亡き服部達に「約束」したんじゃないかとぼくは勝手に想像しているんですけどね……。

鶴山 残酷なことを言えば多くの作家が自分のエピゴーネンに対して脇が甘くなる。僕は『言語にとって美とはなにか』というタイトルはしっくり来ますね。言語美は決め打ちできません。相対的にならざるを得ない。美術は「キレイ」を多数決で決めることもできますが言語美は振れ幅が大きい。一九八〇年代か九〇年代に小説の美文を抜粋した本が出たことがあってなんて下らない本だろうと思ったことがありますが、言語美は相対的で「とはなにか」にならざるを得ないんじゃないでしょうか。
余談ですが『言語にとって美とはなにか』は本当に優れた文学ジャンル論で文学史論です。画期的な事柄がいくつも書かれています。例えば演劇について「かれ(俳優)はいまや、演じられる劇のなかにのみ実存しており、そこでかれが発揮するのは、演じられた劇のなかでのみ存在するところの、かれ自身の歴史的累積と現存性との葛藤と矛盾である。このばあい、すでに言語としての劇(戯曲)が、かれを制限し、かれを捕捉するのは、ただ舞台というわくぐみを通じてのみである。その他の点で戯曲がかれを規定する意味は、まったく終わっているのだ」と批評しています。
演劇は俳優で成立するのか戯曲が重要なのかという分析から始めて舞台がそれを成立させているという方向に進んでいくわけですが、ほぼ完璧な演劇定義です。こういう定義は吉本さん以外してない。以前から演劇界最大の賞の岸田戯曲賞が脚本に与えられることにモヤモヤした気持ちを抱いていましたがその理由がわかった。演劇賞はたとえば二〇二四年○月○日に○○劇団が○○で上演した〝舞台〟に与えられるべきものなんじゃないかな。
池上 いやぼくも今回『言語にとって美とはなにか』を読み返して、いちばん感心したのは演劇論の部分です。特にびっくりしたのは文楽(浄瑠璃)と歌舞伎を論じているところです。文楽はなぜ人形が演じなければならないのか、歌舞伎はなぜ人間が演じる劇なのかを、理論的に説明したのは吉本隆明だけだと思います。これは本当にすごい。「浄瑠璃の言語が、自己表出として時代の観念の頂きをはしりつづけたとき、それを演じるのは〈人形〉でなければならなかった。しかし、浄瑠璃の言語が、指示表出を拡大し、構成の展開を複雑にし、語り言語のほうへ下降していったとき、それを演じるものは〈人間〉でなければならなかった」って書いているんですよ。文楽と歌舞伎は共通する演目も多いんですけれど、近松門左衛門なんかは文楽のほうがやっぱりいいんですよね。だけど、「仮名手本忠臣蔵」になると今度は歌舞伎のほうがいいような感じがするんです。吉本隆明の論を読んで、なぜ自分がそう感じるのかが初めてわかって感動してしまいました。浄瑠璃と歌舞伎を論じたところが、間違いなく『言語にとって美とはなにか』のクライマックスだと思います。
でも大学生の時には読んでもまったくわからなかったんですよ。「浄瑠璃」って書いてあっても文楽なんか観たことがないんだから、わかるはずがないですよね。年を取って日本回帰してさんざん文楽とか歌舞伎を観たから、ようやくわかるようになった(笑)。それこそ余談ですけど、二〇二二年に現代芸術家の森村泰昌さんが「人間」をやめて「人形」になるとおっしゃって、自分が文楽人形になって『人間浄瑠璃』を上演したんです。これはすごくおもしろかったですね。人間が人形になっちゃうんだから。自己表出なのか指示表出なのか……さすがに吉本隆明もこの事態は予想していなかったと思いますね(笑)。
『言語にとって美とはなにか』はすぐれた文学史であり表現史でもあるんですけれど、もしこれから読もうと思っている人がいたら、「第Ⅳ章 表現転位論」「第Ⅴ章 構成論」だけ読めばいいと思います。だけ読めばいいっていうのもアレなんですけれど、第Ⅲ章までは総論だから、第Ⅳ章と第Ⅴ章の個別論を先に読んだほうが、絶対わかりやすいと思う。
鶴山 批評家が批評を書く場合、普通は作家やテーマを絞った個別論を書いてから総論に進んでゆく。でも吉本さんは最初に総論を書いています。しかもまず人間存在に関わる社会、文学、心理の総論を書いた。終戦は明治維新に次ぐ日本社会の大変革だったわけで「荒地」の詩人たちはその影響を強く受けました。戦前の思想・表現史全般が白紙還元された時期だった。吉本さんは思想家としてそれを真正面から受けとめその後の戦後文化の軸になるような三本柱を立てた。これはなかなかできないことです。
吉本さんは『言語にとって美とはなにか』で「戦後表出史は、近代文学史のうえではじめて意識の〈時間〉の統覚をうしなう体験をもった。この体験のなかに〈戦後〉という言葉の意味がかくされているように、この体験が二・三年のうちに失われてしまったことのなかに〈戦後〉の意味が隠されている」と書いています。
比喩的に言えば戦後文学の核は戦後の二・三年に凝縮されており、かつそれはあっさり霧散してしまった。しかし戦後文学の核が戦後の二・三年に凝縮されていることを直観把握した作家が戦後を代表する文学者になったと言えます。詩人でいえば飯島耕一や吉岡実、鮎川信夫や田村隆一です。また二・三年に凝縮され霧散してしまった戦後文学の核は非常に捉えにくい。それが多様な作品となって表出されたと言うことができる。
また吉本さんの批評の素晴らしい点は徹底して自分で考えたということです。『初期歌謡論』で「わが国では、文化的な影響をうけるという意味は、取捨選択の問題ではなく、嵐に吹きまくられて正体を見失うということだった」と書いています。古代歌謡に関する一節ですがこれは現代に至るまで当てはまる。実存主義が入ってくると狂ったようにそれに熱狂し、ポストモダニズム、ソシュール言語論などに関しても後先考えずに飛びつく。で、十年二十年経つと拭ったように忘れて「やっぱ花鳥風月だよなぁ」になる(笑)。吉本さんはある批評家を「回らん口でシーニュとか言うな」と揶揄したことがありますが彼は絶対に外来思想に飛びつかない。参考にはしますが自分で考える。これはとても大事なことです。
一方で吉本思想に欠けている部分を言うと「戦後表出史は、近代文学史のうえではじめて意識の〈時間〉の統覚をうしなう体験をもった」に集約されていると思います。時間性について鈍いところがある。時間は同じ速さで流れない。古代で言えば日本に漢字が流入してそれを書き文字として使いこなすまでの時間は恐らく短い。しかし遣唐使が廃止され『古今和歌集』が上梓されて以降の国風文化時代になると時間の流れがゆっくりになる。ずっと飛んで戦後はまた早くなりますね。現代は情報化社会ですが世界中の情報が大量に均一に入ってくるのでグローバリズムと同時にナショナリズムの時代になりつつある。時間の流れは遅くなっていると言えます。変化はゆっくりとしか起こらない。
歴史的に見ると社会・文化はこういった時間の遅速の時期を繰り返している。吉本さんは「二・三年のうちに失われてしまった」戦後の核を明らかにしようとした思想家ですから手法が分析的です。つまり時間軸を棚上げして表現史をフラットに分析していく。正確に表現史を把握できるんですが時間軸の中で何が突出しているのかについては鈍い面がある。

萩野 時間軸を棚上げして、と今おっしゃった点については、そうだろうと思いますね。江藤淳とこの時は一九六五年ですから、四十歳ごろに行った対談で(「文学と思想」『吉本隆明 江藤淳 全対話』)、徳川時代についての話になって、史実というか史料については、ある程度捨象してもいいという発言をしています。例えば「実証性ということはトコトンまでやっていくと、どうしようもなくなっちゃう。どれを選択していいかわからなくなっちゃうし、それから、ああいう史料、文献などというものは、あまり信用できないと僕は思うのです。これは数年前のことでも信用できない。だから、ましてや、ということになって、それは信用できない。最後は自分の選択力と構想力に頼ることになる」と言って、江藤淳や小林秀雄との手法の違いを語るんですけど、吉本さんは時間軸はある程度カッコにくくって、それを飛び越えて上から垂直に射し込む視線で事象を捉えようとする。ものごとの「構造」がスパっと透かし視えさえすればいい。よくもわるくも吉本さんは「今」の思想家なんだと思います。「今」とは時間的な、または時代的な「現在」という意味ではありません。〝永遠の今〟つまり〝永遠の相〟ってことです。吉本さんの原理的思考の中にはそんな眼差しがある。
■文芸批評について■
池上 日本の文芸批評って何なんでしょう。
鶴山 小説批評に関しては感想文です(笑)。たいていの人が小中高で小説を読んで感想文を書かされたわけだけど、それを精緻にしていったのが大方の日本の文芸批評の流れ。この感想文的文芸批評を最初に破ったのが小林秀雄です。決して良き詩の理解者ではなかったけど富永太郎や中原中也との交流から文学を相対化して捉える視点を持っていた。だから音楽論から美術論、思想論、古典論まで書けた。また小林さんは「批評とは竟に己れの夢を懐疑的に語ることではないのか」とも書いた人でいわゆる〝創作批評〟の走りでもあります。
創作批評とは批評の創作化です。乱暴に言えば作品を論じるのではなく作品をダシにして批評家独自の感性や思想を表現する。そのトップランナーが蓮實重彦さんと柄谷行人さん。蓮實さんにも柄谷さんにも漱石論があります。これも乱暴なことを言いますが読んでいるうちはとても刺激的で面白い。で、読み終わって肝心の漱石がどういう作家なのかわかったのかと言うと皆目わからない。蓮實さんと柄谷さんの特権的知性の印象だけが残る。
もちろん柄谷・蓮實さんは創作批評の創始者ですから偉大です。しかしその後のエピゴーネンたちによって文芸批評はどんどん堕落していった。作品をダシに批評家がいわば夢を書いているわけですからまず創作者が批評を読まなくなった。批評家を信用しなくなった。また全盛期の蓮實・柄谷さんほど切れ味のある創作批評家も現れなかった。
蓮實・柄谷さんは今の文学界の現役の大物ですが、物故なさった超大物の吉本さんについて好き勝手言わせていただいているので公平を期しますと、蓮實さんの批評は冗談としては飛びきり面白かった。ケツをまくったことを言うと、東京の育ちのいい坊っちゃんが「文学なんて下々の者が書くもんだぜ」という感じで縦横無尽に名作文学を切り捨てていく批評は痛快だった。世の中に熱中できるものなんてないので退屈しのぎに映画を見て冗談を飛ばしてる感じだった。でもいつの頃からかミイラ取りがミイラになっていった。これは解せない。
柄谷さんの批評は審級が混乱している。「例えば」で他者の評論などを引用するたびに批評の審級が変わる。読者はジェットコースターのように振り回されるわけですが読み終わると何がなんだかわからない。柄谷さんという特権的批評家の印象だけが残る。問題はこの審級の混乱が意図的に為されているということです。「柄谷批評は何度読んでもわからないからスゴイ」と書いていた批評家の文章を読んだことがありますが、そりゃ何をどうやってもわかんないということです。なぜわからないのかを考えれば柄谷マジックの種は意外と簡単に解けます。
萩野 確かに柄谷さんの本は読み物として面白い。むしろわかりやすいくらいです。柄谷さんは鼻が利くし勉強家だから、ポストモダンをはじめ最新流行の思想にいち早く目を付けて自分の文脈に取り入れるのが上手かった。『隠喩としての建築』とか『内省と遡行』あたりまではそれでも面白く読ませるっていう、ただそれだけでも柄谷さんにしかできない芸だから、批評文としてはそれでよかったと思うんです。だけどその後の例えば〝NAM〟(『原理』)とか何だったんだ、ってことですよ。グローバル資本主義の問題や限界はわかります。でもそれに対して柄谷さんは、コミュニズムの残り香というか、幻想を振りまいただけじゃないですか。その総括はなされたのか。読んで虚しさが残ります。
柄谷さんの思想的「転回」と言われる『探究Ⅱ』の冒頭はこう始まっています。「私は十代に哲学的な書物を読みはじめたころから、いつもそこに「この私」が抜けていると感じてきた。哲学的言説においては、きまって「私」一般を論じている。それを主観といっても実存といっても人間存在といっても同じことだ。それらは万人にあてはまるものにすぎない。(中略)私は自分がいかにありふれているかを知っている。それにもかかわらず「この私」は他の誰でもないと感じている。肝心なのは、「この私」の「この」の方であって、私という意識のことではない」。
ここまで読むと、おっ柄谷さんわかってるな、と思う。ところが柄谷さんはこの後、こう書くんです。「私が「この犬」というとき、それは犬という類(一般)のなかの特殊を意味しているのではない。たとえば、「太郎」と呼ばれるこの犬の「この」性は、その外見や性質となんら関係がない。たんに「この犬」なのだ」と。こう語ってしまったとたん、柄谷さんのいう「この」性とは、たかだか「かけがえのなさ」という以上の意味はなく、「万人にあてはまるものにすぎない」話になってしまう。「この」性ってほんとは存在論の一筋縄ではいかない問題なんです。だからキルケゴールの「単独性」に直結する。なのに、ソール・クリプキの固有名の議論に引っ張られて問題を掘り下げきれずに最後まで展開してしまった。批評家としてはともかく、哲学者としてはどうなのって思います。
池上 ぼくは「哲学」的な著作は読んでいないのでコメントできないんですけれど、文芸評論家としての柄谷行人さんはすぐれた著作を書かれていると思います。NAMの後、二〇〇二年に出た『日本精神分析』はすごくおもしろかった。「文学金魚」に連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」でも触れたんですけれど、芥川龍之介の「神神の微笑」を使って論じた漢字と仮名の話は、見事に「日本」の本質を突いていました。柄谷さんも「あとがき」で「私は根っからの批評家なのか、と思った次第である」と書いています。この批評家というのは文芸評論家という意味です。
ぼくらが若い頃は、小林秀雄や中村光夫や本多秋五も現役で、吉本隆明、江藤淳のほかにも秋山駿とか磯田光一とかすごくたくさん文芸評論家がいましたよね。いま批評はどういう状況になっているんでしょう。
鶴山 現状分析になってしまうけど批評は低調、もしくは本質的に存在しなくなっているんじゃないかな。日本文学は短歌、俳句、自由詩、小説と官庁縦割りのようにジャンルごとに孤立していますが底辺では繋がっています。他産業に比べると文学は小規模産業だけど、その中では小説が大企業で短歌、俳句、自由詩は中小企業です。でも中小企業で起こっていることはそのうち必ず大企業でも起こる。詩というマイナージャンルの方が直截に今の状況を反映するからです。
詩の世界の批評は大方は誉め合いになっています。君の作品はいい、君のもいい、でも(本当は)僕の、私の作品が一番いいだろといった大昔の学生創作批評みたいなことをやっている。戦後文学の時代まで文学はズバッと本音で批評できる場で言いたいことをハッキリ言えるジャンルでした。吉本さんや鮎川さんの批評はまあ厳しかった。でも今はかつての文学批評の熾烈さを、留保はありますがYouTubeが担っている感じです。これは小説でも起こる、あるいは起こっている。ある意味文芸批評家は労力を割いて小説(家)の本質を抉り出す努力をやめてしまった。批評家仲間から誉められるのを目標に批評を書いているようなところがある。自己中の時代だね。でもこれはある程度仕方がない。戦後文学が霧散して現代をどう捉えて批評していいのか誰もが模索中なんだから。今、文学の世界でストレートに「ホントのことじゃん」ということを言うとみんな引きますね。敬遠される。
池上 「ほんとうの考え」は吉本隆明がいちばんこだわった表現ですね。色紙にサインを求められると、「ほんとうの考えと/嘘の考えを分けることができたら/その実験の方法さえ決まれば」と書いたそうです。
鶴山 吉本さんは社会事象に関して相手の嘘や偽善を見抜く異様なほどの鋭い感覚を持っていた。コミュニズムから反核署名運動に至るまでね。
萩野 一九五〇年代末に始まる花田清輝との論争も吉本さんのそんな資質がよく出ていましたね。戦争責任論や芸術の大衆化論が主な論点でしたが、転向問題の本質は転向の有無よりも、庶民にどこまで寄りそえたか、それをどこまで自らに問えたかというプロセスにあるんだ、というのが吉本さん。これに対して、花田の自由奔放、ちょっと茶化すような批判的応答が薄っぺらいレトリックと感じられた吉本さんは、かつて戦時中は東方会にいた花田のことを「転向ファシスト」と非難した(「転向ファシストの詭弁」『吉本隆明全集5』)。十代のころから「ほんとうの考え」を希求してきた吉本さんから見ればもっともなんです。ただ、よく読むと論点があまり噛み合っていない。芸術の大衆化論なんて、どっちがどっちの立場を否定し肯定しているか微妙で、勝ったも負けたもないと思うんですけど、吉本さんの攻撃の激しさに花田さんが論争の土俵から降りたことになっている。評価はいまも定まっていません。
鶴山 ただ吉本さんの「ほんとうの考え」はただ一つの直観的真理ではありません。真理は社会情勢などに応じて変わるものであり相対的だというのが吉本さんの一貫した考えです。
池上 吉本隆明が色紙に書いた言葉は、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の「けれどももしおまへがほんたうに勉強して実験でちゃんとほんたうの考えとうその考えと分けてしまへばその実験の方法さへきまればもう信仰も化学と同じやうになる」をアレンジしたものなんだそうです。糸井重里さんとの対談で、「うその考えと分けてしまへば」を「嘘の考えを分けることができたら」に変えて、その後に「、」を打つんだと言っています。色紙には「、」は書かれていないんですけれど、そこで区切るんだってことでしょうね。それで「その実験の方法さえ決まれば」というところで止めて、その先は書かないんだ、と言っています。「ほんとうの考えと/嘘の考えを分けることができたら/その実験の方法さえ決まれば」となるわけです。これはちょっとおもしろいですよね。さっき鶴山さんがおっしゃった「分析があれば結論は書かなくてもいい」ということに繋がりますね。
鶴山 その通りだと思います。ただ創作者はせっかちなのよ。吉本さんのように分析によって真理に近づくのではなく直観で捉えたい。『宮沢賢治』論で吉本さんは「喩法・段階・原型」や「擬音論・造語論」など分析によって賢治文学の本質に迫ろうとしました。彼の考えでは分析方法さえ正しければ本質は自ずと明らかになるはずだから。最初の賢治全集を編纂した入沢康夫さんや天沢退二郎さんも彼らの賢治論で同じような分析方法を採っています。なるほどテキストを比較検討した分析自体は正しい。でも相対化するとズレが生じてしまう。
賢治という作家を相対化して眺めると彼は満三十七歲で亡くなっています。実働二十年弱ですが異様なほどの量の原稿を書き残しました。またその原稿内容が特異です。ジョバンニとかグスコーブドリとかクラムボンとか欧米でありそうなんだけど実は存在しない名前が頻出する。擬音も賢治以外の作家には絶対にない特殊なものです。語源を調べてもわからないんだ。どっかから引っ張ってきた言葉ではないということです。
膨大な量の原稿やその明瞭な視覚性・音韻(音楽)性を考えると、これは突飛に思われるかもしれませんが詩や物語が見えていた、聞こえていた作家だとしか思えないところがある。賢治が熱狂的を通り超した狂信的法華経信者だったのはよく知られています。法華経は光と音の経典です。夏目漱石や正岡子規を始めとして日本の文学者は思想の中心に無を据えたいわば禅系の作家が多い。しかし賢治は広義の密教系です。
賢治のような密教系の鬼っ子作家はときおり現れる。唐十郎などもそうです。つまり吉本さんの分析的方法は万能だとは言えない。吉本さんが色紙に好んで書いた言葉は賢治の方法論ではなくその倫理表白だと思います。今に至るまで説得力ある形で賢治文学の全貌を解明した評論は存在しないわけだけど、賢治の場合は分析ではなく直観把握から入れば案外簡単なんじゃないかと思います。
池上 そういう意味では吉本隆明がすぐれた文芸批評を書いているかどうかは微妙ですよね。『悲劇の解読』は重厚で本格的な作家論なんですけれど、読んでいてあまりおもしろくない。本人も文庫版のあとがきで「論考が、いかにもやせて骨ばった印象を与える」ことが不本意だ、って書いています。
鶴山 戦後文学批評は『高村光太郎』論と『島尾敏雄』論でじゅうぶんじゃないんですか。『高村光太郎』論は戦争責任論ではない。「高村ほど、全身をこめて戦争に突入した文学者はいなかった」と戦前・戦中・戦後の高村を一貫した知性だと評価しています。島尾さんは小説家だからちょっと厄介。吉本さんは島尾さんと対談もしています。小説中の島尾さんと妻ミホさんを始めとする女性関係を対幻想などで詳細に分析しているんですが、島尾さんに直接尋ねると「あれは女について書きたかっただけだから」といった答えが返ってくる。詩人で批評家気質の人が小説家を理解するのはなかなか難しい。
ただ吉本さんが初期に島尾敏雄にこだわって書き下ろしの作家論を書いた理由はよくわかります。島尾さんはよく知られているように奄美大島に赴任していた特攻隊の生き残りです。それも特攻隊長だった。部下を統率してお国のために死なせなければならない重い任務を負っていた。
でも奄美の特攻隊には海軍予備学校あがりの島尾より古株の下士官がたくさんいた。島尾隊長は事あるごとに下士官から皮肉られ軽んじられる。文学青年が付け焼き刃で兵隊になったのだから当然ですね。島尾は下士官に劣等感を感じながらそれでも自分の職務を果たそうとします。しかし敗戦によって奇妙なねじれが生じる。島尾さんは本当に一人っきりで放り出される。
こんなとき先任下士官のひとりが「私」のところにやってくる。かれは十年軍隊でたたきあげてやっと上等兵曹になった人間である。かれはその意味で鍛えぬかれた軍人だが、論理や知識なしに、肉体で転換する術をしっている大衆のひとりである。かれは未熟な指揮者である「私」をたえずおびやかしつづけていた成熟した軍隊専任者である。しかし、転換に論理はいらない。
「いえ、それはわたしだって隊長のあとにつづいて立派に突撃するつもりでした。でも何だかこんなふうになるのじゃないかと思っていました。わたしは本当は軍人などに向きません。これからわたしは家に帰ったら百姓をやりながら好きな発明の研究に没頭したいと思っています」
吉本隆明『島尾敏雄論』
根っからの軍人だと思っていた下士官の言葉が、どれほど島尾さんに衝撃を与えたのか言うまでもありませんね。吉本さんは「ここで「私」は職業軍人ともちがい、軍隊生活に長年たたきあげられた下士官ともちがった、自分の発想の位相をかいまみる。「私」は敗戦の報とともに、(中略)職業軍人とも、下士官に象徴された甲らのはえた生活者ともちがった難関につきあたる。それはただ「私」が知識をもつものであり〈考えること〉をしている習性をもっているためにだけ、おとづれたものである」と書いています。吉本さんが初期に「大衆」にこだわった理由でもありますね。
最近中国などとの関係が悪化するのに呼応するように、太平洋戦争の戦死者を美化する風潮がじょじょに蔓延し始めています。戦死者には敬意を表しますが、戦争が異常事態であり特攻もまた異常な行為であり、それを免れればもうどうしようもなくすぐに根強い日常が、生活が戻ってくるのを忘れてはなりません。その意味で僕は今ウクライナやパレスチナで書かれている反戦詩をあまり評価しません。戦時中の詩は反戦詩でもプロパガンダになるに決まっている。日本の戦後詩が優れているのは戦〝後〟に訪れる本当に恐ろしい人間の性を経験しているからです。
吉本さんは島尾さんが陥った苦しみを「敗戦を、軍隊の敗戦から、日常生活にあるだろう敗戦へと復帰させることさえできそうにない。敗戦を〈生〉の方へ歩みだすには、未知で未経験の、これからの〈生〉を孤独にとおりぬけなければならない。ある意味で、これは特攻隊の心理状態のまま〈死〉に突っ込んでゆくよりはるかに面倒で困難なことである」と書いています。見事な戦後思想の分析です。
吉本さんは戦争に取られませんでしたが島尾さんと同じ精神の傷を負っていた。「荒地」の詩人たちもそうでした。田村隆一の「おれは垂直的人間」は八〇年代まで続いた戦後詩に決定的影響を与えましたが、この一行に敗戦時に〝水平的人間〟たちと別れた彼らの精神の孤独が表現されています。垂直的人間たちは何事もなかったように日常の生活に戻れなかった。その意味では吉本さんも当然垂直的人間です。
池上 はい。それから、小林秀雄は同時代の日本の現代詩については何も書いていませんよね。柄谷行人さんは鮎川信夫の『歴史におけるイロニー』については書いていますけれど、現代詩については書いていないと思います。蓮實重彦さんも佐々木幹郎さんと対談はしていますけれど、日本の現代詩については書いていないと思います。江藤淳も書いていないですよね。そんな中で吉本隆明は詩人だから当然ですけれど、日本の現代詩をずいぶん取り上げて論じています。
鶴山 詩人が一番読んだのは『戦後詩史論』でしょうね。でもこれは詩史論としては失敗作なんだな。もうちょっと正確に言うと、吉本さんの思想家としての歩みに即せば『マス・イメージ論』『ハイ・イメージ論』に繋がる重要な著作です。でも『戦後詩史論』自体は決して出来のいい批評ではない。
池上 不思議ですよね。確かに『戦後詩史論』は出来がよくない。一九七八年に大和書房から初版が出て、ぼくもずいぶん期待して読んだんですけれど、あまり力が入った著作には思えなかったですね。二〇〇五年に思潮社から新版が出た際のあとがきの冒頭に「この本の中味はほとんど覚えていなかった」と書いてあって、ガクッときました(笑)。
鶴山 『戦後詩史論』の冒頭に戦前詩の総括があって、それはプロレタリア詩とモダニズム詩です。鮎川さんもそうなんですが吉本さんは戦前のプロレタリア詩とモダニズム詩を現代詩として捉えている。この現代詩が敗戦を経て生活に根ざした思想詩になり、高度経済成長期から一九八〇年代にかけて吉本さんが「修辞的な現在」と呼んだ衰弱期に入ってゆく。それが『戦後詩史論』のおおまかな流れです。
つまり吉本さんは入沢康夫・岩成達也の「現代詩」をまったく視野に入れていない。『戦後詩史論』でも一切言及していません。これは公平で網羅的な分析を良しとする吉本さんとしては異例です。戦前の現代詩(プロレタリア詩とモダニズム詩)が思想的戦後詩となり当初の思想を維持できなくなった時点で空虚な修辞に傾いてゆくという理解なんですが、これは実はプロレタリア詩系の思想表現詩の流れを総括した詩史論に過ぎません。
現在では戦前現代詩(プロレタリア詩とモダニズム詩)は近代詩として総括され、戦後は個の思想中心の戦後詩と思想を排したほぼ純粋言語構築物の現代詩の二つの流れがあるという認識が一般的です。戦後詩と現代詩では世界認識方法が違う。でも両者は表裏一体で戦後世界を表現している。『戦後詩史論』にいわゆる現代詩として短歌、俳句、小説にまで多大な影響を与えた詩の修辞的実験の評価がゴッソリ欠けているのは致命的です。
池上 ぼくが高校生の時に聴いた講演では、入沢康夫の「泡尻鷗斎といふ男」を取り上げて、入沢さんの詩は的確に深読みしなければならない、入沢さんという人は重要な詩人の象徴だ、と評価していましたけれど、確かに文章では書いていないですよね。吉本隆明は「荒地」の同人だったのにモダニズム詩からの影響がほとんどないんです。だから本音を言えば吉本隆明にとっての詩は立原道造や中原中也であって、現代詩はあまり好みじゃなかったんだろうと思います。
鶴山 普通詩人はいわゆるモダン、現代を表現している新しい修辞に飛びつく。でも吉本さんにはそれがない。また新しさは常に相対的です。時代が変わると新しさが変わる。北園克衛のコンクリートポエムが新しかった時代もあるし吉岡実『薬玉』の擬古典詩が新しく見えた時代もある。吉本さんは『初期歌謡論』でそういった新しさの相対性についてさんざん論じているんですけどね。
池上 ぼくは高校生の頃は詩を書いていたから、『戦後詩史論』の「修辞的な現在」が実作の参考になるんじゃないかと思って読んだんですけれど、ぜんぜん参考にならなかった(笑)。後に『マス・イメージ論』や『ハイ・イメージ論』を読んで、「修辞的な現在」を論じる視点がようやく理解できたんです。だから鶴山さんのおっしゃるとおり、『マス・イメージ論』『ハイ・イメージ論』に繋がる論ではあるんですけどね。
鶴山 ただ個人的には『戦後詩史論』は思い入れ深い本でしてね。僕は『戦後詩史論』を読んで現代詩への視点が欠けていることに猛反発して二回くらい自分で戦後詩史論を書いたんですが途中でやめてしまった。書く際に戦後の詩だけじゃ吉本さんと同じになってしまうと思って『新体詩抄』『海潮音』から蒲原有明、北原白秋くらいまでおさらいしたんですが、それをやるうちに戦後の詩を論じるだけでは意味がないと気づいたんです。
自由詩が発生したのは明治維新以降ですが、乱暴に言うと漢詩が滅びて自由詩になった。江戸時代まで最新思想の流入口は中国でそれは漢詩・漢文として入って来ていましたから。それが明治維新以降に日本の文化規範が欧米に変わると自由詩が新たな文化の受け入れ窓口になった。実際自由詩はずっと日本文学における前衛でアンテナ文学でした。またお手本となる欧米詩をどう日本文化に移入するのかは試行錯誤の連続だった。小説の言文一致体と同じように思想・修辞両面での移入が求められた。
自由詩の最初の本格的接続窓口になったのは短歌です。与謝野鉄幹・晶子の「明星」でそこから北原白秋や木下杢太郎が現れた。ただ文語詩は自由詩最初の修辞的完成形ですが白秋や三木露風の象徴詩を読めばわかりますが思想面は恐ろしく貧弱だった。この思想・修辞両面を合体させて日本自由詩のアイデンティティを確立したのが朔太郎です。『月に吠える』は大正六年(一九一七年)刊で、小説の言文一致体は明治四十年代には確立されていましたから自由詩は小説に十年近く遅れてアイデンティティを得た。そのくらい日本自由詩を確立するのは難しかった。小説で坪内逍遙・二葉亭四迷が言文一致体の修辞を模索して漱石の出現によって修辞と思想が合致したのとほぼ同じことが起こっています。
そんなことを考えていると詩史論を書くのがイヤになった。いまだに書いてない(笑)。現代文学の母胎になった近代文学は明治の四十年間くらいの混乱の坩堝から生まれています。詩と小説に分けて日本の近・現代文学を考えたのでは相対的認識が得られないわけで、子規や漱石、鷗外といった俳句・短歌・小説の確立者の仕事を検討する方が面白くなってしまった。
僕は再三文学をジャンル別に捉えてはいけない、綜合的に認識把握しなければいけないと言っていますが、それをやると漢詩と自由詩が断絶しながら地続きだということがわかる。漱石の漢詩は極めて自由詩的です。また俳句が本質的には世界で例を見ない非―自我意識文学だということがわかりますし、すべての日本文学の母体である短歌が明治維新期にいかにフレキシブルに作用したのかがわかります。自由詩が原理的に一切制約のない自由な表現だという理由も腑に落ちます。でもこういったことは僕以外の人は言っていない。文学を綜合的に捉えた上での認識です。
池上 ぼくは鶴山さんの「自由詩は原理的に一切制約のない自由な表現だ」という主張は卓見だと思っています。これはあまり説得力がないんですけれど、ぼくの「ザ・バンド論」も自分では「自由詩」として書いているんですよね……ただ自分が好きな「ザ・バンド」を「口実」つまりプレテクストにしたために意味内容が勝っちゃって、当初の目論見を逸脱しかかって結果的に音楽評論に近づいちゃっているんですけれど(笑)。
ところで、萩原朔太郎は昭和三年(一九二八年)に『詩の原理』という有名な詩論を出版していますよね。この詩論は最近ではあまり触れられませんが、『言語にとって美とはなにか』に先行する重要な著作ですね。吉本隆明も高く評価しています。
鶴山 詩の世界で本格的原理論を書いたのは朔太郎と岩成達也の『詩的関係の基礎についての覚書』だけなんだ。原理論を書いた作家は偉大です。朔太郎は『詩の原理』の序文でこの本を読めば詩とは何かが完全に分かると書いていますがぜんぜんわかりませんよね(笑)。でも詩で検討すべき要素を全部列挙した。また『詩の原理』は初稿では「自由詩の原理」だった。自由詩の中に戦後詩や現代詩、近代詩という文学潮流が含まれる。現在書かれている詩だから現代詩だと言う人がいますがそれは詭弁に過ぎない。現代詩のかつての栄光にすがっているだけだな。
岩成さんの『詩的関係の基礎についての覚書』は昭和六十一年(一九八六年)刊ですが朔太郎『詩の原理』から約六十年かけて詩人はようやく自由詩についてほぼ完璧な定義に達した。岩成さんは詩は形式・内容両面で完全に自由であり作家がこれは詩であると宣言し読者がそれを肯った時点で詩は成立すると定義しました。あっけないほど単純ですがこれ以上の自由詩の定義はありません。また「新たな世界認識には新たな詩の書法が対応する」とも書いた。自由詩がアンテナ文学であることを言明している。
(金魚屋スタジオにて収録 「吉本隆明篇」第02回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。
■萩野篤人さんのコンテンツ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


