 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
9
城壁の灯りが見えてとき、肩の力が半分だけ抜けた。間もなく農園から食材が届く。ドライバーは小門用のキーを持っている。開けたタイミングを見計らい、校内へ入りこむ算段だ。こんな事態になったのはほかでもない。共同住宅でトラブルが発生したからだ。なんとも間抜けな話だった。
結局、1―30は姿を見せなかった。しかし、美雨が「そろそろ時間だ」と合図しても、1―41が部屋から下りてこなかったのだ。日が替わるまえに校内に入らないとカードキーの認証が替わってしまう。二時間前には辞去しなければならないと決めてあった。
二時間というのは、深夜のドライブを考慮してのことだ。危険を冒せばもっと早く着けることは確かだった。結局もう三十分だけ待つことにした。それでも1―30は現れず、1―41も合図に応じない。焦った美雨は再び五階まで向かった。
ぎりぎりの段階を迎えつつあった。城壁の外で立ち尽くす姿がはっきり見えてきた。除けておいたはずのビスケットの缶に足を取られ、転びそうになりながらドアノブに手をかけたときだ。1―41が、どうしたの、という顔で部屋から出てきた。時間がないと急かせても、のんびりしたものだった。部屋のなかを調べているうちに「お団子」が乱れてしまったのだろう。髪の毛は解かれていた。それをまとめ直す様にも焦りは感じられない。キーの認証が、と告げても焦点が合わない返答をする。挙句の果てには、どうせ間に合わないのなら腹ごしらえをしていこうと言いはじめた。開いた口が塞がらなかった。キーのことだとあらためて告げると、今度は首が折れるのではないかと思うほど頷いてみせた。しかも、日が替わるまでに到着できない責任から逃れるためか、必死に話題を逸らそうとする。1―30が起こした事件について、しつこく見解を訊くのだ。
美雨には返す気力が残っていなかった。小門を開けるなら、農園のドライバーを利用すればいい。そのひと言にやられてしまった。
食事を終えると、車のカギを渡された。使用不能になったコピーキーも押しつけられた。胃が膨れたあとは瞼が重くなるといわんばかりに、1―41は寝息を立ててしまったのである。美雨の了承を取りつけることもなく。
十八歳の誕生日を迎えてすぐ、美雨は車の免許を取得できた。高校三年の夏だった。通っていた高校の規則が緩く、両親にも理解があったおかげだ。彼らを乗せてドライブしたこともある。が、あれほどの暗がりを走った経験はない。共同住宅を出てから憶えているのは、氷を握ったように手が震えたことと、やけに疲れた顔をして眠っている1―41を睨んだことだけだった。
四時半。トラックが来た。シルバーの荷台には何も記されておらず、鈍い光沢を放っている。水平線の向こうから夜が溶け出し、今日がはじまることを宣誓していた。ドライバーは、美雨たちと目を合わせても表情を変えなかった。禁じられているのだろう。
小門がガタガタと音を立てて開きはじめた。奥の光景にドライバーも驚きを隠さなかった。美雨は1―41と顔を見合わせた。校庭が真っ青だったからだ。
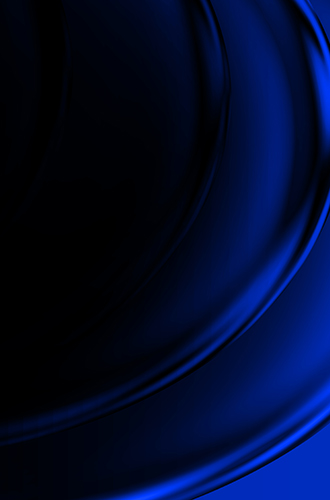
逃亡者が出たのだ。しかし警告音は消えている。すでに捕縛されたということだ。
エンジン音が聞こえた。農園のトラックよりも小型の響きだ。学園が所有している一台で、工場へ送られるさいに使われる。荷台には食材でなく生徒が積みこまれるのだ。
医務室の周りに人だかりがあった。教師たちも集まっている。
看護師が担架で運ばれてきた。血塗れで、酸素マスクを装着され、一見しただけでは誰かわからなかった。が、細すぎる顎に見覚えがある。同性愛疑惑を持たれていた女性だ。
張が歩み寄ってきた。「――64の仕業だ」
看護師を襲い、カードキーを奪って逃げようとしたらしい。しかし、日が替われば認証できなくなる。専用の機材に通して更新する必要があった。64は知らなかったのだ。キーを翳しているうちに警告音が鳴り、C班の生徒が現れた。さっきのトラックには64が乗せられていたということだ。
「カードキーのことはともかく、逃亡すれば」
「無論、おまえたちに追われることになる。いまのあいつが逃げ切れるとはとても思えない。本人もそれを自覚していたと思うんだが」
それでも逃げようとした。何があった。教師たちが、それぞれの推測を口にしていた。しかし、無理矢理に起こされた恨み節のようにも聞こえる。そのうちに踵を返しはじめた。まだこんな時間なのだ。職員室には仮眠スペースもある。
教師の輪に加わっていた張がもどってきた。彼らの目を気にしながら、捜査結果を尋ねた。美雨はガセネタではないという印象を伝えた。「張りこみを続ける必要があるかと」
1―30の部屋に漂っていたのは困窮のにおいではない。磨き上げられた節度だ。しかも、あの部屋のまえにだけ荷物が置かれていなかった。異質の住民だった。
やや遅れて1―41が歩み寄ってきた。ほかの教師たちに見られると、張の思惑が勘繰られる。
「今夜も行けるな」
美雨は即答できなかった。心はすでに医務室にあった。
「おまえにできることはない。諦めろ」
張の言うとおりだ。美雨が動いたところで64の工場送りが覆ることはない。しかし、だからといって頭のなかから消し去れなかった。後悔があった。一度も見舞えず、この日を迎えてしまった。分身のように慕ってくれた唯一の生徒だったのに。
張からの依頼を拒まなかったのは、64を元通りにできる可能性があると思ったからだ。胡の方針をリセットし、王時代に再転換する。親と連絡を取り合えるようにする。そうすべきことだと信じた。しかし、彼女は事件を起こしてしまった。リセット云々では解決できない。ただ、そこまで彼女を追いこんだ理由があるはずだ。工場で働くという結果は変わらなくても、やるべきことは残っている。できないことがわかったからこそ、いまできることが見えてきた。
「今夜も張りこんでみます。ですから」
張から許可を得て医務室に入った。64のベッドだけカーテンが引かれていないという。どこが惨劇の現場なのかは一見してわかった。窓ガラスには針金が仕込まれているが、そこに看護師の顔面を打ちつけたのだ。罅の中心が赤黒い。

64はここでクラスメイトの遺体を発見した。眠っているあいだに、隣のベッドで首を吊っていた。その光景が忘れられず、なんとしても脱出したいと思い、強行したということか。考えられなくはない。が、彼女にはそれ以上に強い動機があった。家族に会いたいという思いだ。願いが叶うなら捕まっても構わないと覚悟を決めたのだろう。
どうしていまになって逃亡を図ったのか。医師たちは様々に施してくれたはず。だからこそ、授業に復帰できなくても、自殺に追いこまれなかった。亡くなった生徒は医師に黙って服用を止めていた。マットレスの下に薬が隠され、ゆうにひと月分はあったという。
美雨は何を探しているのか自覚できないまま、貪るように視線を動かした。どうしていまになって。その問いに感応する何かが、無作為に放つ投網にかかるのを待ちながら。
視界の端に違和感を覚えた。異状というほどのことではないが、通常ならば考えられない光景ではないか。控室のドアが少しだけ開いている。看護師は夜勤中だった。いつもどおりに巡回に出て、生徒の様子を確かめた。刹那、虚を衝かれて襲われた。そこまでは容易に想像できる。教師たちも同じ結論に結びつけていた。しかし、ドアの件に触れた者はいなかった。大した問題ではないと見過ごしたのか。
事件が発覚し、教師たちが控室に出入りしたのかもしれない。看護師の行動を確認すべく、日誌を検めようとして。それならば問題視されなくても頷ける。しかし、張は否定した。医務室に入ったのは遺体を搬送した職員だけだという。事件を受けて医師と看護師は呼び出され、まだ到着していなかった。
控室には誰も入っていない。つまり、夜勤の看護師は施錠していなかったのだ。
失念していたということか。64がそれに気づいていたとしたら。
美雨は控室に入った。医務室より広く、奥には執務室が設けられている。手前のスペースは看護師たちの待機場所で、それぞれにデスクが与えられていた。美雨の目は給湯器の周辺に向けられた。電話が置かれてある。迷わずリダイヤルを押すと、眠気と苛立ちを隠さしない女の声が返ってきた。美雨たちは声もそっくりだ。骨格が同じなのだから当然だった。差があるとすれば、性格が現れる言い回しだけだ。相手の女は、またかけてきたと勘違いしたのだろう。受話器が割れるのではないかと思うほどの罵声を浴びせた。
「張さんのお宅では」美雨は間違い電話を装った。
似た声をした別人だと気づいたのだろう。やれやれという言い草だった。
〈違う。孫だ!〉
64は実家にかけた。ここに通信手段があると知り、狙っていたとしか考えられない。看護師がカギをかけ忘れたことに気づき、襲撃を思い立った。いましかない、と。
1―41が首を傾げた。「逃亡するつもりなら、どうして実家に電話しようと」
外に出れば電話は見つかる。敢えてここからかける必要はない。確かにそうだ。まして彼女は極度のホームシックに罹っていた。脱出したら、真っ先に実家へ向かったはずだ。この電話を使う意図がわからない。

あの女は「母親」だろう。話しぶりから判断すれば、64からの連絡を嬉しく思っていなかったようだ。もちろん、かかってくると予想もしていなかっただろうが。
おそらく言い合いになり、一方的に切られてしまった。64は思いの丈を伝えられなかった。あるいは誤解を与えたと感じた。そこで計画を切り替えた。顔を合わせなければ伝わらない心があると思い立った。逃亡すれば両親が責任を負わされるというのに。電話だけなら彼女が工場送りにされて終わるのに。それでも敢えて逃げようとした。会わなければ、という一心がすべてを狂わせたのか。
「それにしても不用心ね」と1―41がドアノブを検めた。「でも、おかげで思いがけない『仕事』が回ってきた。願ってもないことだわ。自分たちの足元で起こった事件だもの」
「担当は95だ。また引き離したってことだな」
張の視線の先には87が眠るベッドがある。歯軋りが聞こえてきそうだ。
「ツイてるやつは、どこまでもツイてるもんさ」
あの時間帯に警報が鳴れば、情報はC班担任の黄へ送られる。彼女は自薦者のなかから最適者を選び、寮長へ連絡する。しかし、今回の捕縛劇では一連の流れが機能していなかった。警報が鳴るや、95は寮長のもとを訪れ、自分に任せてほしいと直訴したのだ。黄から連絡が来るよりも早かったという。
「その場で即決されたってことですか」
「あんな時間の仕事だからな。手間を省こうと思ったらしい」
87は手負いだ。差を広げられるとすればいましかない。そう確信し、95は嘆願した。早期解決を望む寮長にとって、彼女の申し出は渡りに船だった。
「培養組からも文句は出なかったようだ。大した問題にはならないだろ」
95が捕縛に成功しても、ベスト5のメンバーに入れ替えはないのだ。まして早朝の捕り物に加われば睡眠時間を確保できず、疲労を回復できない。健やかさを維持するほうが明日に繋がるという判断なのだろう。彼女たちの日常を知っていれば、なるほどと思える。
五時を回った。張の話では95はカフェテリアにいるらしい。87との一騎打ちにピリオドを打つきっかけになる。そんな話でもしているのだろうか。
美雨は地階へ下りた。ここに来れば、朝、昼、夕方の三度の食事を摂れる。休み時間も自由に使用でき、飲み物も含めてメニューは豊富だ。非常事態が起こったということもあり、今朝はいつも以上に混雑していた。黄が95の奮闘を称え、周もご満悦だ。
捕縛は用具室の開錠前におこなわれた。ゴム弾はもちろん警棒さえ使えない状態だった。格闘術を駆使して無力化しなければならなかったのだ。95は格闘訓練で苦戦してきた。周が手を焼いたひとりだ。ここ一番という場面で力を発揮したということになる。だからこそ喜びもひとしおなのだ。出来過ぎた活躍ではないか、という疑いは無視されている。
培養組の活躍は当然視された。外組が成果を上げたときは、教師にも刺激になるのだろう。班の区別なく集まり、闊達な意見交換が続いている。
美雨は教師の視線を薙ぎ払う思いで近づいた。場に相応しくない目つきだと感じたのだろう。周が腰を上げた。要件は何か、と肩を怒らせている。
美雨は取り合わなかった。
「あの看護師に頼んでいたんじゃないの?」
95の目のまえに出た。
「巡回のとき、カギをかけ忘れたフリをするようにって」
ついうっかりする。施錠し忘れる。何度か繰り返せば、64は嫌でも意識するようになる。彼女が夜勤になればチャンスだと思わせる、撒き餌だったのではないか。

彼女にまつわる噂を信じて近づいた。気があるように見せかけ、頼みごとをねじこんだ。
「64が極度のホームシックだったことは誰でも知ってる」
弱った心を利用すれば、難なくポイントを稼げる。まして87が負傷した直後なのだ。
「巡回中に看護師が医務室から出ていく。トイレに行く、気分転換をする、物音がしたから確認しようする。理由はなんだって構わない。とにかく出ていく。その隙に64が控室に入り、通話しようとする」
それを見届けたうえで、看護師が警報を鳴らせばいい。
「まさか襲いかかるとは思わなかった」
64の心は想像以上に病んでいたのだ。決断した者の狂暴さを甘く見た結果だった。
「87ならまだしも、あなたにとやかく言われる筋合いはない」
どう足掻いてもライバルになり得ない。疑念を持つ権利も資格もないと一蹴した。
「成績が伸びないからって、逆恨みはしないでもらいたいわ」
重圧に耐え切れず、美雨の目のまえで失禁した。同じ人物かと思うほどの変わりようだ。いまなら、あの事実をなかったことにできるとでも言わんばかりだった。
「64はあなたを慕っていたものね。でも、あなたは何をしてあげた? 言いがかりをつけるために、あの子を利用するつもり?」
95が何かを認めるはずもない。このまま歩めば、間違いなく卒業資格を得られる。
優秀者を贔屓するのは学校関係者の生態だ。美雨に心を動かされた教師は皆無だった。
打ちひしがれたのは持論が通らなかったからではない。
あなたは何をしてあげた――。
95に言いがかりをつけるため、64と親しかったフリをした。彼女がここにもどってこないから、反論できないから、逆恨みをぶつけるために利用した。そう指摘されても美雨は何も返せない。64の心に応えてこなかったのだから。
64は何を求めていたのか。それは、かつての分身が求めていたことでもあるはずだった。あのとき学校へ行かないほうがいいと言えばよかった。それで悲劇は避けられた。64が予行練習に参加すると言い出したとき、街へ出ないほうがいいと指摘すればよかった。それだけで彼女の心は壊れずに済んだ。美雨の警告なら聴き入れたに違いない。
あのときと同じだ。伝えなかった。何もしなかった。日本に留学できれば、忌まわしい記憶から遠ざかるとさえ思っていた。解決していない過去は、表に現れ出るタイミングを見計らっているのだ。日本行きが絶望的になったことをあらためて自覚させるかのように、先送りしてきた宿題に向かえと命じているかのように、64の事件が起こってしまった。
何もしなかったからこそ、自分を慕う者の人生を狂わせた。何もしないことの罪深さを誰よりも深く学んでいたはずなのに。
五時五十分。工場は稼働前だろう。美雨は、職員室の出入り口近くにある小箱に近づいた。認証を更新するための機材だ。張のコピーキーを差し入れ、完了を告げる点灯を確認した。車のキーがポケットに入っていることも確かめた。そこでようやく気がついた。1―41の姿がなかった。彼女は教師たちのまえに顔を出せない。カフェテリアに入ろうとしなかったのは理解できる。が、美雨がもどるのを待っていなかった。張と一緒にいるのかもしれない。今夜も1―30の部屋に行く。それまでは彼が保護してくれるはずだ。
急げ。両足に命じた。授業開始まで三時間を切っていた。
不届き者が現れたという一報でたたき起こされた教師たちと一緒に、黄は、二杯目のコーヒーに口をつけていた。ようやくカフェインの恵みを感じたはじめた頃、95が一礼して出ていった。あれほど得意げな顔を見せたことはなかった。87を抜いたときも喜んでいたが、敵失には違いなかった。今度こそ自力で掴み取ったという実感があるのだ。22の指摘が完全に的外れだったとは言えないが、救急病院に搬送される途中で看護師が息を引き取った。95の策謀を実証する術がないのなら、目のまえの事実をそのまま受け入れるほうが建設的だ。

95は運がよかった。しかし、いつも女神が微笑んでくれるとは限らない。ここには運を差配できる者、すなわち教師がいるからだ。運自体がそれを認めているかのような事態が起こっていた。一足先にカフェテリアを出た教師から情報が入ったのだ。確認してみると、西口の連絡通路に設置されている監視カメラが22を捉えていた。カードキーを使用し、小門から抜け出したのだろう。オリジナルかコピーかは不明だが、登録者名まで写し取らなければ使用不能だ。ディスプレイに表示されたのは張だった。
「呼び出しますか」周が訊いた。何事かと引っ付いてきたのだ。
授業がはじまり、生徒が揃ったところで事実を突きつければいい。キーを貸したにせよ、盗まれたにせよ、張のメンツは丸潰れだ。平素から気に入らない男だった。胡の方針に異を唱えていることは嫌でも耳に入った。それでも専門科目の教師として引き抜かれ、C班の生徒を一定レベルまで育てた立役者のひとりだ。胡による方針転換がおこなわれたものの、C班が別格の存在だという認識と指導方法は堅持された。代わりの人材を充てることはできても、首を挿げ替えるだけではレベルの低下を招く。C班のメンツが立たなくなる。胡はC班の担任から出世した男だ。彼のメンツにも直結する問題なのだ。
腫れ物であり、臓器のひとつでもある。そんな男を切るにはどうすればいいか。胡の心情を忖度する日々が続いた。いい方法を模索してきた。そこへ思わぬ失態が飛びこんできたというわけだ。これほど鮮やかなオウンゴールはなかった。周も納得した顔だ。
誰をハンターに選ぶか。黄は自薦者のリストを頭のなかで捲った。閃きがあった。
「95が看護師をたぶらかしていたのなら、フェアじゃないと思わない?」
「ですが、アンフェアだという証拠もありませんし」
「あの看護師の噂はあなたも知ってたでしょう」
「まあ、それなりには」
「当然、ほかの生徒も知っていた。だとしたら、95に加点することを納得しない生徒も多い。彼女の計画を証明できないなら、ポイントを加えるしかない。でも、このままスムーズに与えてしまっても示しがつかないわ。士気が下がるようなことがあってはならないのよ。特に、わたしたちC班の生徒はね」
「何か策が」
「今回のことを一番アンフェアだと感じている生徒に行ってもらいましょう」
運を差配できる。自在にタクトを振れるのだ。だから教師は面白い。
以前は、生徒の特性を見極め、最大限に伸ばすためのサポート役に徹しなければならなかった。生徒のなかから天才的な力を持った者が現れ出ることを期待して。自分たちは原石を目のまえにしている。彼女たちが輝けるかどうかは、教師が的確に磨けるかどうかにかかっている。王は、教師には天才創出の使命があるのだと力説してきた。

胡がC班の担任を務めていたとき、子飼いとして可愛がっていたのが黄だった。胡と同じく三大都市の地方政府を回り、中央教育委員会と丁々発止のやり取りを経験した上での採用である。先輩である胡の働きかけがあったからこそ抜擢された。その恩義も手伝って、初代校長だった王の方針には早くから疑問を持った。
王は研究者だ。クローン計画の中核にいて、比類なき学び舎の建設を党に打診した。旧体制下で草案が揉まれ、棄却と提出を繰り返しながらようやく認められた経緯がある。
研究者が考えていることはワンパターンだ。有能な者を自分の手で造形することである。オリジナルを超えることはもちろん、この国が誇る一握りの天才にも引けを取らないような人材を輩出することだ。だからこそ教育の質に拘った。しかし体制が入れ替われば状況も一変する。この国の性だ。権力争いが落ち着く先は、旧体制下での方針の見直しである。国家百年の大計を転換させるような真似はしないものの、旧体制指導部の面々を葬り去るため、汚職での逮捕を皮切りにあらゆる手を尽くしていく。王の異動もその大きな流れのひとつだ。失脚扱いではなかったが、学園の運営には手を出せないようなポジションに異動させられた。畑違いの解放軍だ。兵士を強化するための遺伝子治療チームで生き長らえている。ただ、胡や黄にその情報が届くまでにはかなりの尾ひれがつく。都合よく歪められてきたはずだ。ふたりは、軍と距離のある教育畑を歩んでいたのだから。
正確な内容は把握できないということになる。しかし、確実に言えることは、現指導部は超がつくほど現実主義だという点だ。世界的にも数名しかいない天才児をデザインしようとしても、結果が保障されているわけではない。予算はともかく、膨大な時間を費やしていながらギャンブルが過ぎるという判断が下された。
有能な人材なら国内外に数多いる。いまの教育システムを維持できれば、いずれ世界中で、我が国出身の秀才たちが支配的な役割を果たすことになるのだ。すでにその兆しがある。ありとあらゆるフィールドで勇躍しはじめていた。ならばクローン計画の最終目的をシフトすべきだというのが現体制の基本方針であり、胡はもちろん、黄も賛同してきた。クローンが人類に尽くす役割は完全に修正されたということだ。
旧体制下でも進められてきた事業がある。当時は付属的な側面を持っているに過ぎなかったが、現体制では主幹事業だ。学園から二十キロほど離れた工場で遂行中である。
黄は医務室へ向かった。壊された窓ガラスは修復され、清掃も終えられていた。カーテンを開けると、87が上半身を起こし、噴火寸前の火山を思わせる目で見詰めてきた。頭に、首に、肩に、血の滲んだ包帯を巻いたままだ。昨夜、取り換えるはずだったのだろう。そのタイミングで看護師が襲われたのかもしれない。医師たちの到着は遅れていた。この一件を事故として処理するための報告書の作成に忙しいのだ。
黄は黙って見詰め返した。95が看護師の性癖に目をつけ、ここに足を運んでいたことは知っていたはずだ。企てに気づいていたとしても、87には何もできなかった。全身に散らばる痛みや目眩と戦うだけで精一杯だった。そんな自分に、彼女はいま猛烈に腹が立っているはずだ。滲む鮮血は、抑え切れないマグマそのものに見えた。
「22が逃げたわ」
95は見事に計画を成功させた。ただし、相手は医務室組だった。難敵とは言い難い。22を捕縛できるなら、当然、得られるポイント数はもっと高い。
「行けるかしら」
87は頷くより先にベッドから降りていた。痛みに顔を顰めたが、それを恥じるかのように体を動かしはじめた。

「あなたのパートナーはまだ決めてないの」
「要らない。培養組は信用できないからな」
パートナーに足を引っ張られ、この様なのだ。組ませたとしても独自に動くだろう。培養組は、95を単独で行かせても問題視しなかった。より下位の生徒に仕事を任せたところで異論が出るとは思えない。
「学園の車を盗んでる。位置情報は把握済みよ」
北上していた。
「工場へ向かっているのかもしれない。64が運ばれたからね」
「奪還するつもりか」
「どうかしら。そんなことをしても無意味だけど」
自分を犠牲にして助け出す。64にそれだけの価値があるとは思えなかった。しかし、方角的に工場しか考えられない。
「工場に近づくようなら、敷地に入れるまえに捕らえるのよ。あそこで働いている生徒たちを動揺させたくない。君たちが活躍する姿は目に毒だわ」
黄は成功を確信した。87が虎と重なって見えた。
六時十五分。捕り物の影響で、教師の出勤時間は大幅に早まった。それでも職員室に揃ったのは定時だ。自分が生徒だった時代と変わりない。ならば彼らの規範も然りだろう。
22は今夜も共同住宅を張りこみに行くはずだ。しかし、1―30が現れることはない。彼女と同じ顔をした骸を見つけることになるだけだ。
五年前、1―41と初仕事に向かった。現場に到着し、ターゲットを捕獲する方法を協議し、それから十分も経たないうちに計画を実行した。彼女は培養組を唸らせるほどの才を持っていたが、味方を疑える目までは備えていなかった。培養組が反乱を起こすはずがないという先入観に負けたのだ。
一階の奥が校長室。1―30は入室を知らせる表示を指でなぞった。教師が揃ったという報せを受けると、校長は、威厳を噛み締めるようにゆっくりと職員室へ向かう。訓示を述べるためだ。
言葉の効果を上げるため、教師たちよりも早くここに入り、出勤途中で乱れた様子はないか姿見で確かめる。言葉の効果が、何よりも見た目に左右されることを知悉していたからだ。校長らしく身なりを整えれば、あとは話し方を少し工夫するだけでいい。いくらでも説得力は増し、教師たちの表情に畏れを見出せる。その瞬間が堪らないのだという。
腕枕をしながら、胡は、そんな自慢話を披露したものだった。あのときは統べる者の威厳に満ちていた。慈愛を疑うこともなかった。それなのに。
(第09回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


