 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十三、『三四郎』第三章 肌の白い女、よし子(中編)
d:轢死事件
明けて日曜日に、昨日の用がなんだったのか気になった三四郎は、大久保にある野々宮の家を訪ねる。結局昨日の用というのは大したことではなかったことが判明する。三四郎の母が、息子が世話になるからと「ひめいち」という名の赤い魚の粕漬けなどを野々宮に送った。そのお礼を言おうとしただけだったというのである。ちなみに、VRには広告付きの安価なバージョンもあって、それを使っていると作品内に登場する衣服や食品や調度品を、商品として販売するバナー広告や、作品内に出てくる場所への旅行プランの提示などもなされる仕組みになっている。大概の人はこの廉価版を使っているから、その広告収入はVR社にとって重要な財源のひとつとなっている。
俺たちが使っているのは、広告のないプロ仕様のものだが、「ひめいち」を「蘊蓄」で調べたところ、けっこううまそうな赤い魚だったので、逆に広告付きのバージョンで干物でも注文したいような気分にさせられた。「商品検索モード」を起動して、注文してもいいような気になった。
ヒメイチは、四国や九州で秋に食される、スズキ目ヒメジ科に分類される海水魚であるとのことだった。くせのない味で、焼いたり、干物にしたりして食べることが多いようだ。このように、VRで読書=体験すると、食欲もけっこう刺激されたりする。
「そこに電報が来るわけよね」
それは、大学病院、つまり東大の校内にある病院にいる野々宮の妹からの電報である。この物語は、とにかく本郷文化圏を中心に描かれているってことがここでもわかる。電報の内容は、すぐ来て欲しいというものである。

妹のいたずらでしょうと行く気を見せない野々宮に、もし悪いといけないからと行くようにと勧めるのは三四郎である。このあたりはドライな野々宮と、田舎のウエットな人間関係のなかで育ってきた三四郎との対比がおもしろい場面だ。それで、行くことになった野々宮に『下女が非常に臆病で、近所がことのほかぶっそう』だから、泊まって欲しいと頼まれる。泊まることになった三四郎は、さっきのひめいちのついた晩飯を食うことになった。結果的に、俺たちもひめいちの食感と味覚を、三四郎といっしょにバーチャルに体験することができた。なるほど、赤い色が目に鮮やかで、淡白かつ上品な味わいでございました。バーチャルだけど。
「晩飯後一人になった三四郎は、妄想し始めるのよね」
「そう、三四郎はけっこう妄想する。ここでは、顔も知らない野々宮の妹を、勝手に危篤にする。そして、その妹を、この間池のほとりで出会った女に置き換える。さらには、看病している野々宮を自分に置き換えてしまう」
「でも、電車の音で我に返るのよね」
「うん、家のある土手の下を線路が通っていて、電車がごうと通ると座敷が震えるんだね。我に返った三四郎は、その家がかなり古いことに気がつく。最先端の学者なのに、こんな寂れた郊外の古い建物に住んでいる野々宮の厳しい経済状態に思いを馳せる」
「学問を追求することと、現実世界で栄耀栄華を極めることとはつながっていないってことが、ここで示されるわけだ」
「経済の厳しさという現実を、家の振動で体感したとき、遠いところで誰かが『「ああああ、もう少しの間だ」』という声を三四郎は聞くのよね。それは三四郎には『すべてに捨てられた人の、すべてから返事を予期しない、真実の独白と聞こえ』るんだけど、そこへまた再び電車が近づいて家が震える。そして、この二つのことがむすびついたとき、三四郎はなにが起こったのかに気づいて『ぎくんと飛びあが』るのよね」
三四郎はあわてて線路のところへ降りていき、半町、つまり五〇メートルほどいったところで、女の轢死体を見ることになる。『汽車は右の肩から乳の下を腰の上までみごとに引きちぎって、斜掛の胴を置き去りにしていったのである。顔は無傷である。若い女だ。誰が添えたのか、その足元に花束があった。金盞花を束にしたものを白爪草で編んだ花輪で巻いたものである』とある。言葉で読むとさほどでもないが、読書=体験者である俺たちは、けっこうどぎついものを見せられて目を背けたくなった。漱石の作品で、こんな場面に遭遇するとは予期していなかっただけに、衝撃は大きかった。殺人事件ではなく、自殺ではあるが、この描写はなかなか凄絶である。殺人事件の捜査中であるだけに、死体との遭遇に、どきどきしてしまった。死者が若い女であるだけになおさらだった。
「三四郎もけっこう衝撃を受けるわよね」
「そりゃ、当然だけどさ」
VRだけに文字だけの体験じゃすまないわけだ。肉体をもった女の死体を現実に目撃したとしたらちょっとしたホラーだよね。それがまあ、三四郎が体験したことでもあるわけだけど。
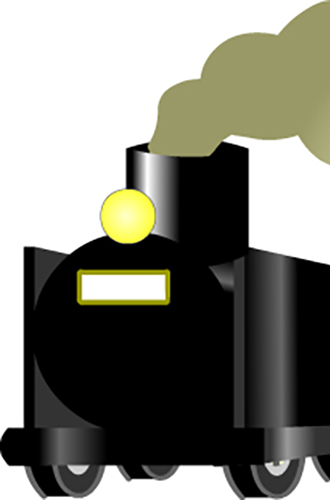
「帰ろうにも、最初は足がすくんでほとんど動けないし、座敷に戻っても動悸がひどいのよね。さっきの女の顔が思い浮かんでくるし、「ああああ・・・・」と言った力のない声がそれにつながるし。そして、『人生という丈夫そうな命の根が、知らぬ間に、ゆるんで、いつでも暗闇へ浮き出してゆきそうに思われる』という心境に至るのよね」
「現実、とくに生身をさらけ出して生きている女たちが直面している現実にひどく揺さぶられるわけだ」
「さっきから、生身の女って表現をよく使うわね。どういう意味なの」
「そうだなあ。たとえば、こういう説明ができるかもしれない。明治時代ってのはまだ男社会だろ。外で働くのは男と相場が決まっていた。つまり、社会のなかに自分の位置をもっているのは男だけだったわけだ。逆にいえば、男は社会のシステムに組み込まれて、生身の存在というよりは、役割とかステータスといった機能や象徴として存在していたといえる。
女たちも、そういう男たちに守られている内はいい。男に所属するものとして、社会に〈家〉という場所を与えられるから。だけど、ひとたびその男に離縁されたり、男が失職したり、男が戦死したりしたらどうだろう。
明治時代の〈家〉は、男のものだから、男がいなくなったら崩壊する。すると、そもそも社会の内部に位置づけられていない女たちには、居場所がなくなってしまう。かくして、どこにも身の置き場のない生身の女が出現するというわけだよ」
「社会性を奪われた女っていうことかしら」
「そうだね、己が肉体以外によりどころをもたない存在っていう感じかな」
うまく説明できたかどうか自信はなかった。でもなんとか高満寺にも伝わったようだったのでほっとした。まあ、高満寺の場合は、生身の女として最強だから、社会が崩壊してもなんの苦労もないだろうが。いや、むしろそうなった時の方が輝くタイプだともいえる。
「そういえば、三四郎が上京の途中で出会った女も、夫の生死が不明で、仕送りが途絶えたために故郷に帰る途中だったわよね。だから、彼女も生身の女ね」
「そうだね。この時代には、いわゆる戦争未亡人の問題ってのがあって、経済的支柱であった夫を戦争で失って寄る辺をなくした女性が多かったんだ。そういう女性の鉄道自殺が増えているご時世でもあった。だから、野々宮の家の近くで轢死した女も、そういう一人だという可能性も考えられる。なにしろ、三四郎が、野々宮の経済状況について思いを巡らしていた時に事件が起こったわけだから、相関関係はありそうだよな」
「西欧列強に肩を並べる文明国の象徴であり、国土をつないでその輪郭をくっきりさせ、国家の効率性を高めるものが鉄道であったわけよね」
「そうだね」
「だけれど、その重量感溢れる鉄の塊は、同時に多くの物を踏みつけにし、破壊するものでもあることがわかるわね。テクノロジーが諸刃の剣であることが、ここには示されていると思うわ。だって、人間の力で、人間の体をそんな風にまっぷたつにするなんて考えられないもの。このわたしにだってできないくらいだからさ。でも鉄道にはそれができるってわけよ」
さて、こうした現実の厳しさを目の当たりにした三四郎は、どう反応しただろうか。社会の歪みに気づき、それを正すべく立ち上がった・・・りはしないのである。
「でも、三四郎は都合よく身をかわす人間だよね。一瞬、愕然とするものの、すぐに、『あぶないあぶない、気をつけないとあぶない』といった水蜜桃の男のことを想いだす。そして、こう考える。『あぶないあぶないと言いうるほどに、、自分はあぶなくない地位に立っていれば、あんな男にもなれるだろう』。つまり、水蜜桃の男のように世の中を傍観している『批評家』は、現実そのものとは交わらないから、つねに安全でいられると気づく。そして、穴倉で光線の圧力の実験に専心している野々宮もまた、その同類であると気づく。当時男の職業のひとつであった学問が、現実と遊離したものであることが、ここに暗示されているともいえるよね」
「でまあ、三四郎はそんな浮世離れした学問にもちょっとは魅力を感じるけれど、現実、つまり女によって劇烈に体現されている現実に、学問よりも強く引かれているという、分裂状態にあるわけよね」
e:金盞花と白爪草
それから、間もなく俺たちはとんでもないことに気が付いた。さっき、引用した女の轢死体の描写の後半、つまり花束について書いてある部分『誰が添えたのか、その足元に花束があった。金盞花を束にしたものを白爪草で編んだ花輪で巻いたものである』が、後から書き足されたものだということが判明したのだ。
「どういうことかしら、これ?」
「まあ、ひとつのヒントと受け取るべきなんだろうね」
「ヒントって?」
そんな風に問われたって、俺にだってすぐにわかるわけではない。無残な女の死体と、そこに手向けられた鎮魂の花束という対照は、実際、読み=体験してみたとき、とてもインパクトがあったのは確かだ。
「少なくとも、鎮魂の意があるのは確かよね」
「そうだな、つまり犯人は、こうした時代や社会の犠牲者である女に共感的な人物だと考えられるってことだよな」
「そうね。これが犯人、あるいはその関係者が置いたものだったとしたらそうなるわね」
「えっと、ちょっと待ってよ、いま『薀蓄』してみるから」
俺は、急いで金盞花と白爪草について調べてみた。いろいろ細かい記述があったが、俺がはっとしたのは、花言葉についての部分だった。

「ああ、そうか!」
「え、なに? なによ」
「うん、金盞花の花言葉は、『別離の悲しみ』とか『寂しさ』とか『失望』だってさ」
「なるほど。まさに、彼女の境遇よね。で、白爪草のは? 白爪草って、つまりあれでしょ、クローバーでしょ」
俺は思わず、高満寺の顔をまじまじと見てしまった。胸の内のざわつきのせいだった。
「『復讐』、だってさ」
「うわっ」
「つまり、あれだな。共感と共闘。そんな意識が感じられるよな。名もなく、はかなく社会の犠牲となって消えていく声もない人々、あるいは女性たち。そんな人たちの側に立って、なんらかの復讐を企図する勢力。そんなのが犯人像として浮かび上がってくるような気がするな」
「ナイス、プロファイリング!」
どんっ、と背中を叩かれて、俺はぐべっと呻いた。俺だって体を鍛えて、いつかこいつに白爪草だ! と胸のうちではかなく叫んだ。
妹は無事だったという野々宮からの電報で三四郎は安心して眠るが、悪夢を見る。それは、轢死した女は野々宮と関係があり、それを知っているから野々宮は帰ってこない。電報も自分を安心させるためで、轢死事件と同じ時刻に妹も死んでしまった。そしてその妹とは、自分が池のほとりであった女のことであった、というものである。
「この夢は、学問の世界に逃げている野々宮が、現実の女性を傷つけている、つまり精神的に殺しているということに無意識下で、三四郎が気づいていたことを示しているね」
「そうね、池のほとりで三四郎が会った女を、現実世界を忌避する野々宮が苦しめているという事実を遠回しに表現しているわけよね」
「実際戻ってきた野々宮は、轢死事件のことを『「それは珍しい。めったに会えないことだ。僕も家におればよかった。死骸はもう片づけたろうな。行っても見られないだろうな」』などと無責任に、興味本位で語る。批評家の水蜜桃の男がそうであるように、光線の圧力を試験する客観的視点で人の死まで見ているのだと、三四郎は思う」
「さらに、妹のことでも、野々宮は冷たいことを言うわよね。三四郎は、『わざわざ電報を掛けてまで会いたがる妹なら、日曜の一晩や二晩をつぶしたって惜しくはないはずである。そういう人に会って過ごす時間が、本当の時間で、穴倉で光線の試験をして暮らす月日はむしろ人生に遠い閑生涯というべきものである』と感じるわよね。でも、対する野々宮は、異状がないのに、退屈紛れに兄を釣り寄せた妹はばかだというでしょ。それも、『本当にばかだとおもっているらしい』っていうんだから重症よね。研究上のものの見方が、実生活におけるものの見方まで支配しちゃっているわけよね」
「現実にはいないんだね、水蜜桃も、穴倉も」
「三四郎はその点、軸足はまだ現実の方にあるってわけよね」
(第17回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
【新刊】
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■






