 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第九幕(下編)
「ポリグラフで陽性と出たって。でも、検査にかかること自体に動転して、自責の念を抱く人だっている。血圧も上がるし、手に汗もかくのよ」
すべての質問に、いいえ、で答えなさい。
妻の姉と、リビングで抱き合いましたか。
いいえ。
握った手に汗をかいていた。
今ならわたしも間違いなく陽性だ。
「供述調書にサインしたら、終わりよ。拒み通せるといいんだけど」
もし彼が、殺人未遂を認めさせられたら?
同時に、わたしとのことを洗いざらい話したら?
自白の強要、すべて嘘だと、夾子と弁護士は主張するだろう。が、結局どうなるのか、想像もつかない。
「さっき、院長先生がみえたでしょ」
手紙をサイドテーブルに置き、上の空の表情で妹は言った。
「肝臓の数値が、なかなか改善しないよね」
できれば御出発を延ばして、もう数日、経過を見ましょう、と院長も言った。「しかし、たいしたことはないですから。心配いりませんよ」
しかし、それも主治医の夾子から聞かされるまま、仕方なく挨拶に来ただけの様子だった。
「実際、それどころじゃないみたいだった。やっぱり何か、あんたたちを切り捨てようとしてる気がする」
わかった、と白衣の夾子は疲れた声で囁き返す。
「弁護士の先生も、医療ミスの可能性を調べるって。もう手詰まりというか、何でもいいから突破口があれば、って」
あんた、痩せたんじゃない、とわたしは言った。
「食事は摂れてるの? このケーキだって、一口しか」
ダイエットに苦労してたのが嘘みたい、と面窶れした妹は苦笑した。
「患者さんに心配されちゃ、面目ないけど。眠れないほうがこたえてるかも。死刑の夢を見るのよ」
死刑。
あの長い睫の下の、欲望に満ちた瞳が。
と、そのとき夾子は突然、ベッドに泣き崩れた。
「老人ばかりじゃないだろう、未遂を含めて一五人はやってる、って。起訴に持ち込めるのは五人程度だけど、死刑にはそれで十分だって。検事がそう言うんだって」
緊張の糸が切れたかのようだった。なだめようにも言葉が浮かばない。
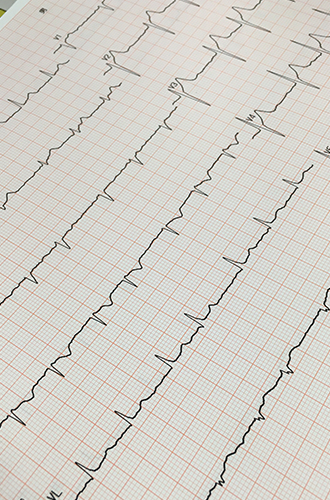
「ほら、誰か来たら、」
「姉さんはもう、ホノルルへ発って」
夾子の声はとめどなく掛け布団に籠もり、吸い込まれてゆく。
「これ以上、巻き込まれないで。向うでゆっくり暮らして。そのぶん、わたしたちも安心できる」
「三方栓っていうのは、それのこと?」
二日ぶりに、小久保ナースが担当に回ってきた。
「ええ。三方活栓と言います」と、相変わらず屈託なく答える。
前々日、吉田というナースは、ごく単純な質問にも、警戒心が露わな目で見た。昨日の担当だった川本ナースに至っては、生返事をしたきり、耳に入らない振りをして出ていった。
「筋弛緩剤は、そこから入れるの?」
さすがの小久保ナースも、その問いには眉を寄せた。
「普通はヘパフラなどの側注に使います。ヘパリンといった血液凝固阻止剤を入れるんです。テレビで言われているような、マスキュラックスやサクシンといった筋弛緩剤を入れるのはめったにないと思いますけど。必要があれば、麻酔医がやります」
患者の問いかけには応じる。たとえ特殊な状況での、特殊な不安を和らげるためとしても、と、そんな覚悟を決めた物言いだった。
「どんな場合に必要になるのかしら」
「そうですねえ、」
考え込むが、言い渋っているふうではなかった。
「夜間、人工呼吸器を付けた患者さんに対しては、あり得ます。でも実際に見たことはありません」
「すると注射を間違えるみたいに、別の患者さんに入れるはずのマスキュラックスをついうっかり、という事故は考えられないわけね?」
今度ばかりは相当に困惑した視線で、小久保ナースはわたしを見た。
「つまり、点滴から筋弛緩剤が入れられたことが確かなら、わざとやった以外にはないと」
「真田くんは、そんなことはしないと思います」
「どうして、」
小久保ナースの若さに一瞬、嫉妬を意識した。
「あなたはそう思うの? あの人のこと、よく知ってるの?」
「ここへ移ってきたとき、とても親切に仕事を教えてくれました」
そう。そんなこともあろう。
密やかなシンパは、常に存在する。
「夾子が言うには、吉田ナースって、彼にちょっかいを出してたんですって」
小久保ナースは躊躇したが、ドアの方を窺い、早口で囁いた。
「そうです。わたしがここへ来た時分から」
「川本さんは。警察にあれこれ言った一人なんじゃないかしら」
患者の質問というより、もはや尋問に近い。
小久保ナースは首を横に振った。
「一人ずつ事情聴取を受けましたが、何を言ったかまではわかりません。だけど確か、川本さんのところには、刑事が何度も来ていました」
「なぜ彼が疑われたんだと思う?」
彼女はしばらく黙って宙を見つめていた。

「仕事熱心すぎたのが、仇になったんじゃないでしょうか」
「いい看護師なのね」
「はい。後片づけや申し送りにも手を抜かないので、当直明けでも残ってることが多かったんです。患者さんが急変したとき、彼がいて助かったと皆、以前からよく言ってました」
「でも、そういうときに動くのは一人じゃないでしょ?」
「もちろん、急変を見つけるのは真田くんとは限らなかったし、手の空いている者が数名は駆けつけます。夜間でもドクターを呼びますし」
「それでも急変は、彼がいるときばかり起こった」
さあ、どうだか、とナースは首を傾げた。
「記録がそうなっているなら、そうかもしれません。だけど、どの症状をもって急変と呼ぶかによっても違うし。特に高齢者の場合、わかりにくいことがあります。几帳面に対応して記録を付けるほど、いわゆる急変が多いことになるので」
小久保ナース自身、自分の説明に苛立っている様子だった。
記録というのは、それほど曖昧なものか。
急変という、いかにも切羽詰まった言葉ひとつ取っても、その定義を使い分ければ、筋書きは都合よく紡げる。
「薬剤の在庫が足りないと報告したのは、彼だって聞いたけど」
「そうでした。オペ室の薬品冷蔵庫をチェックして、サクシンの二〇ミリグラムの箱がなくなっている、と」
「それもまた自作自演だ、と言われてるわけよね?」
「オペ室の掃除とか、ワックス掛けとか、准看がやらざるを得ないんです。率先して雑用をして、不備を見つけて、そんな目に遭うなんて」
彼女も准看なのだろう。若いナースは視線を落とした。
「廃棄物ケースというのは、何なの?」
彼が窃盗容疑で逮捕されたとき、病院に入り込んでいた私服刑事が金属のケースを押収した。裏口の扉の陰にあったもので、廃棄された点滴のボトルが入っていたという。それに筋弛緩剤を直接混入したと疑われ、警察の動きを察知した彼が、慌てて隠したと見られている。
その蓋から彼の指紋が出たというのが、今のところの唯一の物証らしかった。
「オペ室で使うものです。真田さんか誰か、廃棄場に持っていこうとしたけれど、何かの拍子に置き忘れたんじゃないでしょうか」
置き忘れ。
そうだ。隠し場所としては、あまりに中途半端だ。
何のことはない。ただの点滴の空き瓶を、あまりに忙しく、手一杯で置き忘れたとみる方が、ずっとあり得る。
オペ室から裏口の扉。廃棄場へ。
今からベッドを出て、それらの場所を見に行くと言ったら、彼女は案内してくれるだろうか。
「学会で発表するような、実験的な先端医療はどうなってるの? その患者さんはまだいるのかしら」
「さあ。以前はやっていたようですけど」
見た覚えもない、というように、小久保ナースは首を振る。
「だから筋弛緩剤がなくなってるって、真田さんの報告を聞いて、その治療でも再開したかな、と思ったんです」
「もともとの在庫記録の間違いでなければね」
その通りです、と珍しく皮肉な笑みを浮かべた。
「あのね。明日にでも、隣りの老健施設を見学できるかしら。見に行くようにって、三和子さんに言われたんだけど」
「院長代理の許可があるのでしたら」
小久保ナースは普段の表情に戻った。
「夾子先生にもいちおう確認します。検査の数値によっては、もう少し安静が必要かもしれません」

(第19回 第九幕 下編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■





