 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十二、『三四郎』第二章 『三四郎』第二章 森の女(後編)
c:穴蔵の男
小説を体験している俺たちは、動き出した三四郎とともに再び屋外、つまり東京の街に出る。といっても、三四郎は東京帝国大学のすぐ近くに下宿しており、訪ねる先はその理科大、つまり理系学部の方だから、本郷文化圏の外に出るわけではない。俺たちは、三四郎といっしょに歩いていく。「地図」モードで確認したが、帝国大学の敷地は皇居に次いで大きいように思われた。やがて高等学校の横を通って、弥生町の門から入っていく。
当たり前のことだけれど、当時の道はアスファルト舗装ではない。だから、往来に積もった埃に下駄の跡や、靴の底や、草鞋の裏が残っている。車の輪と自転車のあとも無数に残っている。この辺りの描写はじつにみごとで、体験のしがいがある。
休暇中にも関わらず、野々宮宗八は研究室にこもって実験中である。ちなみに、三四郎が野々宮に会いに来たのは、母親の手紙で『勝田の政さんの従弟に当る人』が理科大学にいるから会いに行くようと促されたからである。ここでも三四郎が、物語の主要登場人物と接触するきっかけを作るのは母親なのである。つまり、東京での最初の交友関係の背景には、故郷の地縁関係があったことになる。三四郎の東京は、いつだって故郷とひとつながりだということだ。
『和土の廊下を下へ降りた。世界が急に暗くなる』とあることから、野々宮の部屋は地下室であることがわかる。『穴蔵だから比較的涼しい』とも続くしね。つまり、野々宮は、激しく動いている東京の現場にはおらず、その地下に潜んでいる存在とされているわけだ。俺たちも三四郎といっしょに、昼なお暗涼しい地下室へと入っていく。汽車で会った桃食う男が山という異界に暮らす仙人であるとすれば、野々宮は地底人なのである。どちらも地上、すなわちこの現実世界にはいないということになる。
「二人が似ていることは三四郎が『いくぶんか汽車の中で水蜜桃を食った男に似ている』と言ってるから間違いないわね」
俺と、高満寺は、それぞれに、『額の広い目の大きな仏教に縁のある相』をしており、しみのある背広を平気で身に付け、背がすこぶる高くてやせている野々宮を目の前に出現させた。同時に、部屋の真ん中の大きな樫のテーブルの上にある様々な物も見た。『なんだかこみいった、太い針金だらけの器械』、水の入った大きな鉢、やすりと襟飾りなどである。そして、部屋の隅にある三尺ぐらいの花崗石の台の上に乗せられた、『福神漬の缶ほどな複雑な器械』なども見た。その器械には二つの穴があいていて、そこが蟒蛇の目玉のように光っているのも見た。
「光線の圧力の試験をしているっていうけど、なんだか手作り感溢れる装置ばっかりよね。冷暖房も整ってなくて、冬なんか冷たくてやりきれないって言ってるし、ほんとに地味感が溢れてるわね。女子があこがれる世界じゃないのは明らか。これじゃリケジョなんて増えようがないわ」

「それでも野々宮は、実に楽しげだよね。『正月ごろからとりかかったが、装置がなかなかめんどうなのでまだ思うような結果が出てきません』だなんて、もう九ヶ月も経ってるのに、なんの目処もついてなくて、それでも全然平気という感じだからね。そもそも三四郎が尋ねていったのは夕方なわけだから、朝からずっとそのなんの目処もついていない研究に、淡々と取り組んでいたってことになる。そして実験は夜に本番を迎え、『交通その他の活動が鈍くなるころに』望遠鏡の穴から、あの目玉のようなものを覗いて光線の圧力を試験するのだという」
勧められて望遠鏡を覗いた三四郎は、さっきの『福神漬の缶ほどな複雑な器械』の光を放射する二つの穴を見る。すると、輪郭のぼんやりした明るいなかに物差しの度盛りがあって、その数字が動く。三四郎はそのことに驚いて、望遠鏡から目を放してしまう。
「驚きのあまり度盛りの意味を聞く気にもならないってあるけど、どういう心境なのかしら」
「あれだろうね。あまりにも世の中の動きと異質の光景なもんで、三四郎はいわばバクっちゃったわけだね。拡張主義や国家主義とも、明治の栄光とも、田舎の母の見ている世界とも、いずれともまったく異なる世界、つまり科学の世界に触れたわけだから」
三四郎の戸惑いは、読者=体験者たる俺にもよく伝わった。なにしろ、いまのところ三四郎が落ち着ける場所はどこにもないのだ。激動する東京にはついていけず、思想界とは縁がなく、母のいる故郷は離れてきた。そして、やっと見つけた同郷の士は、得体の知れない科学の世界に暮らしている。そして、そのいずれの世界にも自分が親和性を感じることができるものがない。
「だから、森に入っていくのね」
そう、穴倉を辞した三四郎は、いまではこの小説のせいで三四郎池と呼ばれるようになった池へと向かう。その池を取り囲む森のなかへと入っていくのである。
d:森へ
あたかも現実世界から逃避するかのように。実際そこは、現実世界とは隔絶した場所のように感じられる。『非常にしずかである。電車の音もしない』。そして、赤門の前を通るはずだった電車を、大学が抗議して小石川の方へと迂回させたという事件を思い出し、『電車さえ通さないという大学はよほど社会と離れている』と考える。東京という激動する現実を代表する電車を、本郷文化圏は寄せ付けないのである。ちょうど穴倉にこもっている野々宮のように。
「三四郎は、この静けさの中で、野々宮のことを理解したように感じるわよね。質素な身なりをして、穴倉の中で、欣然とたゆまずに研究に専念する野々宮のことを『生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない』と思い、そんな『生きた世の中と関係のない生涯』も悪くないかも知れないと思うのよね。でも、すぐに寂しさや寂寞感を感じてしまう。『現実世界はどうも自分に必要らしい』と思うわけよね」
「でも同時に『現実世界はあぶなくて近寄れない気』もしてしまう。現実世界には、あの汽車の女みたいのがいるからね。それも怖い。だから、どっちつかずの居場所のない感じにさいなまれるわけだ」
「で、そんなときはお母さん!」
またマザコン三四郎の登場というわけだ。
「まったくそうだよね、その逃げ場のない状態から逃げるために、『三四郎は早く下宿に帰って母に手紙をかいてやろうと』思うわけだから」

「でも、そこに現実世界が違うかたちで近づいてくるのよね。母のことを思ったときに、別の女がふいとたち現れるわけだから」
この場面転換はとてもみごとだ。読む=体験してみるとよくわかる。さらりと書いてあるのだが、母に心を向けようとした三四郎の視界に、そんな気持ちを一発で吹き飛ばす別の存在が取って代わる瞬間である。このみごとな転換も、ただ読んでいるのでは伝わりにくい。VRで体験してこそよく感得できるのである。
e:団扇をかざす女
『ふと目を上げ』た三四郎は、左手の丘の上にいる二人の女に気づく。ひとりは『きれいな色彩』の着物を着た女であり、『まぼしいとみえて、団扇うちわを額のところにかざしている』。もうひとりは白衣の看護婦である。
やがておもむろに丘から降りてくる二人の姿を三四郎は例によって注視している。二人は分水嶺にさしかかる。つまり、坂を下りきったところにある石橋を渡らなればさっき後にしてきた野々宮がいる理科大学の方へと通じている。つまり、二人は去ってしまうことになる。逆に、石橋を渡れば自分の方に来る。
結果的に、二人は石橋を渡る。つまり、野々宮ではなく三四郎の方へと歩み寄って来る。このことが、三四郎自身も気づかぬ自らの内面に小さな勝利の喜びを与えたことが、読書=体験してみるとわかる。無意味だけれど有意味な、ささやかだけど大切な、野々宮への象徴的勝利だからである。
女はいまは団扇の代わりに『左の手に白い小さな花をもって、それをかぎながら』来る。三四郎から一間、つまり一・八メートルほどのところで立ち止まって頭上の大きな木のことを、同行の看護婦に尋ねる。看護婦が『「これは椎」』と教えると、女は『「そう。実はなっていないの」』といいながら、ちらりと三四郎を見る。
「この会話の意味はちょっと不明ね」
そういうときは、はい「薀蓄」!
「なるほど。当時椎の実っていうのは、煎って食べるおやつだったみたいだよ。駄菓子屋には普通に椎の実がするめやら、ラムネやらと並んで売られてたわけだ。つまり、せっかくの椎の木だけど、残念ながら実はなってないのね、って感じじゃないかな」
「でも、そういいながら、なんでちらっと三四郎を見たのかしら?」
「他愛もない会話をわざとして、気を引いてる感じがするよね。っていうか、この女に関しては、何もかもが芝居がかってる。田舎者の三四郎は女の一連の行動の意味をはかりかねるけれど、女が自分をちらりと見た時の黒目の動きに衝撃を受ける。『その時色彩の感じはことごとく消えて、なんともいえぬある物に出会った。そのある物は汽車の女に「あなたは度胸のないかたですね」と言われた時の感じとどこか似通っている』とあって、三四郎は恐怖すら感じる。異性という実在する外部、それも自分を誘っているのかそうではないのか判然としない、了解不能の意味深な素振りを見せる美しい異性に、三四郎は翻弄され始めたわけだ」
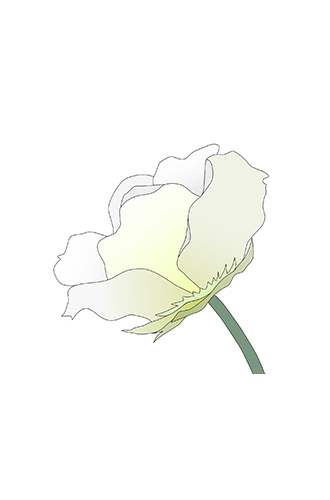
「確かに、翻弄されるわよね、あっちへこっちへと」
というより、「読書」ではなく「読書=体験」してみることで初めてわかるんだけど、この物語の中で三四郎が興味を示す対象は女性に限定されている。文学でも、科学でも、芸術でもなく、世の中の変化でもなく、とにかく三四郎はただただ女性に近づくことだけを考えているように感じ取れるのだ。
「この女のそぶりが芝居だってことがわかるのは、三四郎の前にわざとらしく落としていった白い花が証しだててくれているよね。だって、三四郎はその花を拾ってにおいをかいでみるわけだけど、『べつだんなんのにおいもなかった』んだから。つまり、女が花に白い花をあててにおいをかいでいたというのは、まったくのポーズだったということがここでわかるわけだ」
f:リボン
この次の転換もうまい。三四郎は女が落としていった花を池に投げる。池に花が浮く。それと同時に、さっき二人の女がわたってきた石橋のところに野々宮が現れて三四郎の名を呼ぶ。
つまり、白い花と野々宮とがつながっていることが、ここでもそれとなく暗示されているわけだ。実際、三四郎は野々宮のポケットからはみ出た封筒の上の文字が女の手跡だと気づく。そして、後になってその手跡が、さきほどの女のものだと知ることになる。
装置が狂ったから今宵の実験はやめたという野々宮に誘われて、三四郎は散歩する。野々宮はさっきの女の足取りを逆にたどるようにして丘の上へ上がる。そこからの景色を見ながら、建築の知識を開陳し、三四郎が読んでいないラスキンの話をして文科の知識も三四郎以上にあることを示し、雲が雪の粉にすぎないという科学的世界観を披瀝し、さらには画家の知人のあることも口にする。あらゆる意味において三四郎より抜きんでている存在であることがここでさらりと示される。
「同時に野々宮は自分の穴倉生活を全肯定してみせるわよね」
「そうだね、騒々しい都心にありながら、この池のあたりが静かなことを述べ、学問はこういうところでやらねばならないという。そして、大学の外で電車などが激しく動いている以上に、世界に互した研究をしている自分のような人間の頭の中は、それ以上に激しく動いているというんだからね。つまり、さりげなく自分の超俗的なエリート性を誇っているわけで、『「ぼくは車掌に教わらないと、一人で乗換えが自由にできない」』と一見欠点と見えることを、逆に頭の中が活発なエリートであるため、世俗には疎いのだという自慢のように言ってのける」
「ところが、そんな野々宮が予想外の行動に出るのよね」
「そう、散歩の途中でいきなり西洋小間物屋に入る。そして、蝉の羽根のようなリボンを買うんだ」
「女の影がちらつくわけよね」
野々宮とリボンほど、隔たって感じられるものはない。この二つを結びつけるものがあるとすれば、女しかないということになる。
「でも、三四郎はまだそこまで想像が及ばない。逆に自分も買って故郷のお光さんに鮎のお礼に送ろうかと考える」
「でも、けっきょく買わないのよね」
「そう、『鮎のお礼と思わずに、きっとなんだかんだと手前がっての理屈をつけるに違いない』って思ってやめてしまう。東京の女、未知の外部としての女の世界を前にした三四郎は、お光なんかに縛られたくないと思っているわけだ。プレゼントなんか送って、変に期待されたら東京での自由を失うってね」
「故郷のお光は安全稗として確保しておいて、自分は東京でいいことしちゃうぞっていう、スケベ根性丸だしの、虫のいい期待よね」

「そう。でも、三四郎はまだ大人じゃないからね。二十三歳だけど。すべては意識的というより無意識的な反応だから、三四郎を責めることはできないように思うね。地方エリートが、全国区のエリートとなるべく東京に出てきた。当然親もお光さんも、地元の人々も輝かしい未来を当然視して疑わない。そういう環境が培った特権意識が、三四郎をそういう人間にしちゃってるわけだからね」
「それって、日露戦争に勝って思い上がって自分を見失ってる当時の日本の心理的状況と、ほんとうにパラレルよね。そうすると、三四郎にとっての女にあたるのが、帝国主義の征服欲を駆り立ててやまない異国の領土にあたるのかもしれないわね」
「まあ、でもそこまで飛躍するのはどうかなとも思うけどね」
g:石膏の化け物
三四郎は、野々宮に西洋料理をごちそうになって別れる。帰りに下駄屋に入るが、『真っ白に塗り立てた娘が、石膏の化物のようにすわっていたので急にいやになって』やめてしまう。それから、三四郎が考えるのは先ほどの池の女の肌の色についてである。『薄く餅をこがしたような狐色』で『肌理が非常に細か』な女の色を、三四郎は『どうしてもあれでなくってはだめだ』と断定する。
「これって、白い肌に拒否反応を示したってことよね」
「そうだろうね。汽車の女に対しても肌が黒いことで興味をもったわけだから、狐色という白ではない有色、それも九州的な黒さをやや緩和した色に共感を感じたということなんだろうね」
「有色人種同士の間での共感っていうことね」
そう、あくまで三四郎は、肌の黒い有色人種なのである。
第二章を整理すると、激動する東京で生活を始めた三四郎が、地下室にこもってそのような外界の変動とはまったく無縁に科学の実験に没頭する野々宮と知己を結ぶ。その後、森のなかで団扇をかざしていた若い女性、つまり森の女に魅了される。彼女もまた狐色の肌をした「異性の味方」と三四郎には感じられる。
実はここで、見えない三角関係がすでに編まれていることに気づかれただろうか。ほのめかしを通して、三四郎と野々宮と池の女との間に、微妙な恋情の駆け引きがここに開始されたのである。
「まだ、犯人探しには早いね」
「ええ、でもちょっと気になったことはあるわ」
「なに」
「消されてる単語が一つあったのよ」
「そうなのか?」
「ええ、ここよ見て」
高満寺は、持参した文庫本のページを開いて見せてくれた。テロリストが原典も、その予備も改竄してロックしてしまったので、比較のためには紙媒体の書籍を使うしかないという状況になっているからである。
「あ、ほんとだ」
俺たちは、野々宮の部屋からある物が紛失していたことに気がついた。
「しかも、これってあきらかに凶器たりうるものだよね」
「ええ、看過できない問題だわ」
そうなのだ、野々宮の部屋にあるとして列挙されていた物のなかから、ひそかにナイフが一本抜き取られていたのである。元々は『やすりとナイフと襟飾りなど』となっている部分が、『やすりと襟かざりなど』とさらりと短縮されていたため、読者=体験者たる俺たちも、ナイフのない情景しか体験できなかった。これが意味するところはまだ定かではないが、いずれにせよ、明らかに凶器とおぼしき物が消失したのは間違いないことだ。
「あ、あったわ」
いつの間にか、高満寺は「商品カタログモード」を呼び出して何やら調べていたようだった。
「ほら、椎の実を炒ったやつとか、椎の実クッキーとか、意外とあるわね。ちょっとどんな味か試してみようかな」
お取り寄せボタンをぽちっとする指のでかさに、ひそかに引く俺であった。それにしても、『あれは椎』『そう、実はなってないのね』っていう若い女同士のやりとり、なんだか印象に残る台詞である。
(第15回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










