 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十三、『三四郎』第三章 肌の白い女、よし子(上編)
a:始まらない新学期
かくして、小さな手がかりのようなものを得た俺たちは、勇んで第三章の捜索を開始した。
第三章でようやく、大学の新学期が始まる。けれども、きまじめな三四郎が授業開始日に大学に行っても教師はおろか、他の学生もまるでいない。
昨今は文科省の締め付けが厳しくなって、大学教員もきっちり初日から授業をせねばならず、さらには休講したらその回数だけ補講もしなければならないところも多い。けれども、まだこの時代は牧歌的だったわけで、初日から講義をするような教師はどこにもいなかったというわけだ。
勇んで大学に出かけたものの空振りに終わってしまった三四郎は、この前出会った池の女がいはしまいかとまた森のなかの池に行く。そして例の椎の木のところから丘の上を見上げるが、当然のことながら誰もいない。そこに午砲(どん)が鳴ってびっくりした三四郎は下宿へ帰る。その威嚇的な音は、読者=体験者たる俺たちにも当然聞こえたわけで、俺たちもいっしょになってもびっくりした。この辺もVRならではのダイナミズムだ。俺たちが知っているのはせいぜい、NHKの「正午です」というお知らせくらいのものだから、大砲の音にはさすがにびびった。
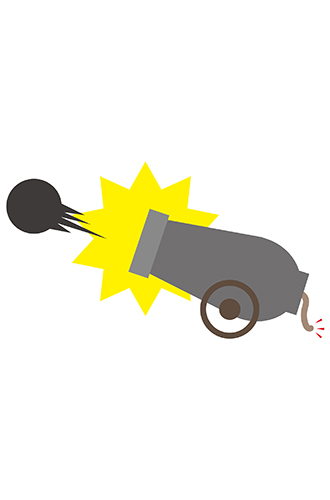
「午砲って、明治時代に始まったのかしら?」
「そうだね。「蘊蓄」で見てみたけど、一八七一年(明治四年)に午砲の制が出されて、大砲や空砲を撃って正午を知らせるということが始まったようだね。海軍や陸軍がこの業務を担っていたらしいよ。昭和になってサイレンに変わるまで、ずっと続いたみたいだ。太平洋戦争の開始とともにサイレンは空襲警報用として使われることになって、正午を知らせる役目は終わったらしい」
「でも、三四郎の驚きようからすると、熊本にはなかったのかもね」
「いや、熊本城でやってたみたいだけど、たぶん距離の問題だろうね。東京では、皇居の旧本丸跡庭園に午砲台があったらしいから、三四郎のいた東京大学まではほんの三、四キロだ。だから、かなり大きい音で聞こえたんだろうね」
「当時はまだ車もほとんど走ってないし、騒音も少なかっただろうから、そうとうよく響いたのねきっと」
b:ポンチ絵の男=与次郎
翌日も三四郎は大学に行って、立派な校舎の並びを見て感心し『「学問の府はこうなくってはならない。こういう構えがあればこそ研究もできる。えらいものだ』と自分が大学者になったような錯覚を起こす。けれども、その期待に肩すかしをくらわすかのように、やはり教室には誰もいない。結局授業が始まるのは、十日ほどたってようやくのことである。
ところが授業が始まり、西洋人の教師が流暢な英語で講義をする。とはいえ、その中身はanswerの語源だとか、スコットが通った小学校の名前だとかどうでもいいような知識ばかりである。逆に哲学の講義の方は難しくてわからない。つまり、三四郎はうまく授業になじめないのである。
そんなとき、熱心に筆記を続けていると思った隣の男が、実は教師のポンチ絵を描いていることに三四郎は気づく。その男が、講義後『「大学の講義はつまらんなあ」』と言ってくるが、三四郎には自分が受けている講義がつまるのかつまらないのかすら判断できない。
「まったく評価の基準を自分の内側に持っていないのよね、三四郎は」
「そうだね。女性には興味を示すけれど、学問にはどうにもなじめない感じがあるようだ」
ポンチ絵を描いていた男に淀見軒という店でカレーライスを食わされる。ちなみに、カレーライスは、当時東京や大阪などの大都市で普及しつつあった、新しい味だったようである。当然、九州出身の三四郎は、初めて食した可能性が高い。
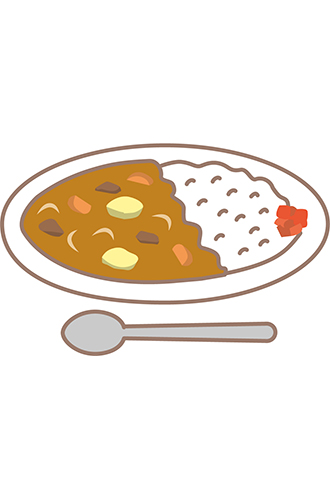
「カレーといえば、わたしが思い出すのは」
ふいに高満寺が脱線の気配を見せた。
「え、なに、脱線すんの?」
この時間のないときにと思ったが、高満寺は食い物の話になると、自分を制御できないようだった。
「ほら、だいぶ後、つまり昭和の話になるけど織田作之助の『夫婦善哉』に出て来るじゃない。あの場面、けっこう好きなのよね」
「そうだっけ? カレーなんか出てきたっけ?」
「ほら、ここよ。すでにVRで呼び出しをかけていた高満寺がその部分を引っ張り出してきた」
いうまでもなかろうけれど、『夫婦善哉』は、安化粧屋のぼんぼんで浪費家の柳吉と駆け落ちした芸者の蝶子が、ダメ夫のせいで苦労しつづける話である。今風にいえば、柳吉は典型的なダメンズであり、蝶子は貢ぐ女ということになる。柳吉は、親に勘当され、前妻との間にできた娘にも会わせてもらえず、ふさいだ揚句、蝶子の貯金通帳を勝手におろして豪遊し、酔っぱらって戻ってくる。腹を立てた蝶子は、『「おばはん、何すんねん、無茶しな」』とほざく柳吉の頭を叩いて家を出る。高満寺が引っ張ってきたのは、それに続く場面だった。
「『二日酔いで頭があばれとると、蒲団にくるまってうんうん唸っている柳吉の顔をピシャリと撲って、何となく外へ出た。千日前の愛進館で京山小円の浪花節を聴いたが、一人では面白いとも思えず、出ると、この二三日飯も咽喉へ通らなかったこととて急に空腹を感じ、楽天地横の自由軒で玉子入りのライスカレーを食べた。「自由軒ここのラ、ラ、ライスカレーはご飯にあんじょうま、ま、ま、まむしてあるよって、うまい」とかつて柳吉が言った言葉を想い出しながら、カレーのあとのコーヒーを飲んでいると、いきなり甘い気持が胸に湧わいた。こっそり帰ってみると、柳吉はいびきをかいていた。だし抜けに、荒々あらあらしく揺すぶって、柳吉が眠い眼をあけると、「阿呆あほんだら」そして唇をとがらして柳吉の顔へもって行った』。ね、いいでしょ」
「うん、いいけどあれだね、この時のキスはカレー味だね」
「コーヒーでだいぶ抑制されてるはずだけどね」
c:図書館―アフラ・ベーン―
閑話休題。こんなことしてる場合じゃないんだった。カレー味のキスは忘れて本筋に戻ろう。
三四郎にカレーライスを食わせた男は、佐々木与次郎といって、専門学校を卒業して今年選科に入った。広田という高等学校の先生の家に寄宿している。
「でも、不思議なのはあれだね、汽車であった水蜜桃を食った男、つまり後の広田や、野々宮については容姿の描写があるのに、与次郎に関してはないんだ。だから、読者=体験者たる俺たちは、勝手な像をそれぞれに作り上げるしかない」
「三四郎にとっては、この男こそが、ある種の道化的な導き手になるのにね」
どういうことなのだろう。この後盛んに活躍し、三四郎とも大いに会話を交わすこの男に、漱石はなぜ容姿風貌の描写を行わなかったのだろうか。正規の学生ではなく、選科生という中途半端な地位にあるこの男に、漱石はあまり重要性を認めたくなかったということなのかもしれない。まあ、この点も読み進めるにつれてわかってくるのかもしれないと、俺はとりあえず鷹をくくることにした。
週に四十時間も講義を受けて、それに圧迫感を感じて、楽しくなくなっていた三四郎は、『「まずい飯を一日に十編食ったらものたりるようになるか考えて見ろ」』と与次郎にどやされる。
「ここなんだけど、そもそも選科生である与次郎には、そんなにたくさん授業を取る権利すらないことに、この時三四郎はまだ気づいていないと思うな」
「三四郎は本科生で、与次郎は選科生。すでに格差があるんだけど、逆に偉そうなのは東京出身の与次郎のほうよね」
三四郎は、まず『「電車に乗るがいい」』というアドバイスを受ける。『「生きてる頭を、死んだ講義で封じ込めちゃ、助からない」』からという理由からである。与次郎は、三四郎を電車で、新橋に連れて行き、日本橋で飯を食い、本場で寄席を見せる。
そして、『「ありがとう、大いにもの足りた」』と感謝する三四郎に、『「これからさきは図書館でなくっちゃものたりない」』とアドバイスする。それを受けて三四郎は、講義を半分に減らして図書館に通うようになる。

「万事がこんな風なんだよな。三四郎は与次郎から東京での暮らし方を学ぶわけだよね。いわば、与次郎は三四郎のなかのかたちにならない思いをすくい取って、それにかたちを与えてくれる存在だともいえる。『与える』から与次郎なのかもしれないね」
「三四郎には、図書館はまさに知の宝庫、真の学問の場として感得されるのよね。本こそが、真の学びをもたらすものだっていう予感がそこにはあるわよね」
「予感だけだけどね。だって、三四郎には何を読めばよいかわからないんだから。本を抱えて出て行く人、本を広げて調べている人を見て三四郎は『うらやましく』なって、『読んでみたい』とは思うんだけど『何を読むかにいたっては、べつにはっきりした考えがない』わけだ。『何かあの奥にはたくさんありそうに思う』んだけど、箱入りの札目録をめくってみると、『いくらめくってもあとから新しい本の名が出てくる』だけで、三四郎に手がかりをあたえてくれるものはない。本の側が、池の女のように、ちらりと目配せしてくれるようなことは起こらないわけだ」
「翌日には実際に借りてみるのよね。でも思った本じゃなくてすぐ返してしまう。それから毎日八、九冊ずつ借りるわけだけど、『どんな本を借りても、きっとだれか一度は目を通しているという事実』に三四郎は驚く。無名そうな作家アフラ・ベーンの小説を試みに借りてみるわけだけど、『そこにもやはり鉛筆で丁寧にしるしがつけてあった』のを見て、『これはとうていやりきれない』と思ってしまう」
「ある種の敗北感だよね。ちなみに、このアフラ・ベーンは、後でけっこう重要な意味を担ってくることになるから要注意だ。何でもないように書いておいて、後でそこに大きい意味を付すってのも漱石のうまいところだと思うな」
「こんなところ、読むだけだと簡単に流しちゃうものね。読書=体験だと、実際にアフラ・ベーンの書物をめくった感覚が残るから、簡単には忘れないけどね」
本の世界には、自分のための未開拓の領域がもはや残されていないと悟った三四郎に俺たちが同一化していると、窓の外を通る楽隊の音が聞こえてくる。外界からの誘いであると、読書=体験者にはしかとわかる。ある種の敗北感を抱いたままの三四郎とともに俺たちは散歩に出る。そして青木堂に入る。
「そこで、汽車のなかで水蜜桃を食った男が、茶を飲みながらたばこを吹かしているのを見るのよね。服装は野々宮君と同じく立派なものではない。三四郎はあの人物だと気づいて注視するけれど、向こうはまったく気づかない。それで、結局三四郎は声をかけそびれて、葡萄酒を飲み干すと図書館へと戻っていく」
「水蜜桃の男が三四郎の背中を押してくれた感じよね。その日は二時間も読書に集中でき『例になくおもしろい勉強ができた』わけだから。そのとき、借りた本の見返しにはへーゲルを讃える鉛筆書きの言葉が踊っているわけだけど、それが水蜜桃の男の姿と重なるような気もするわ」
「そうだね、その落書きはへーゲルについて、『彼の講義は真を説くの講義にあらず、真を体せる人の講義なり』と讃え、『道のための講義』であると述べる。さらには、彼の講義を聞きに集まった学生たちについて『彼らはへーゲルを聞いて、彼らの未来を決定しえたり。自己の運命を改造し得たり』と続ける。それに対して、試験のために、『のっぺらぼうに講義を聞いて、のっぺらぼうに卒業し去る』日本の学生はタイプライターにすぎないと述べている。あたかも、真を体せる人は大学の教室ではなく、青木堂にいて煙草をふかしているのだと三四郎に教えようとしているかのようだよね」
「でも、三四郎にはそこまでの気づきはない。ただ『黙然として考え込』むことしかできないのよね。その言葉の指し示す方向が見えないわけよね」
「そこにまた彼の導き手たる与次郎が現れるわけだ」
「野々宮宗八さんが君を捜していたと言われて三四郎はさがしにいく。けれども結局見つからない。それから、与次郎が、野々宮さんは、与次郎の寄寓先である広田先生の弟子であることを告げるのよね。こうして、登場人物がつながり始めるわけね」
(第16回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■






