 妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
by 金魚屋編集部
実家の近くに来ても、気持ちはなかなか鎮まらなかった。大人げないとは思ったが仕方ない。悪いのはあの醜いインチキ女だ。マキはヨガ教室を出てから二度謝った。この苛立ちはちゃんと伝わっている。そして、それ以上謝れば更に俺が不機嫌になることも分かっている。
喫茶店のドアには「四時から貸切です」と母親の字で貼ってあった。途中で店を閉めるのは一緒に食事をしたがっている合図だ。中に入ると客も母親もいない。マキと挨拶を交わした後、「母さんなら買い出しに行ったよ」と父親が小声で教えてくれた。
マキは店の中を見回している。光を浴びたシルエット。こうして改めて遠目で見ると驚くほど妊婦然としている。コーヒーカップを棚にしまっている父親に、店を閉めさせて悪かったと伝えると、興味なさそうに「気にするな」と目で応えた。
「あらあらマキさん久し振り、もうすっかり妊婦さんねえ、まだお腹空いてないかしら」
両手に買い物袋を提げた母親が帰ってきた。一気に騒がしくなる。有線のクラシックが聴こえないほどだ。マキが甘納豆を渡すと一オクターブ高い声でお礼を言っていた。俺が子どもの頃はこんな声ではなかった気がする。「あなたのお母様」というグレースの声を思い出した。何が俺をあんなに不快にさせたのだろうか。きっとうまく言葉にはならない。
まだ時計は三時前だったが母親が促して店を閉めた。四人で店の二階に上がる。お土産の甘納豆をさっそく食べながら、母親は色々とアドバイスを始めた。マキは時折メモを取りながら一所懸命に聞いている。俺と父親で話すことは特にない。
「おい、ビール買いに行くか」
その声に従い二人で外に出た。懐かしい街並み、と呼ぶには変わりすぎた風景を父親と歩く。この辺りをのんびり散歩するなんて何年振りだろう。

近くのコンビニでもビールは売っているが、昔からある酒屋へ足を伸ばした。何を喋るでもなく屋根付きの商店街を歩く。米屋、畳屋、花屋、本屋。昔ながらの店も数軒残っていたが、閉まっている店の方が格段に多い。周りと不釣り合いな小洒落たカフェも二軒あったが客の姿はなかった。多少賑わっているのはチェーン店の牛丼屋くらいだ。二年前、駅の近くに大きなファッションビルが建った。こういう場所で、個人商店が生き長らえていくのは難しいのかもしれない。
ビルが完成した頃、「あんなの営業妨害じゃないの」と母親はよくぼやいていた。建物の中には所謂シアトル系コーヒーショップが入っている。影響がないと納得するまではずいぶん文句を聞かされた。客層が違うだろ、と笑って取り合わなかったが、今なら母親の気持ちも分かる。あの店を継ぐことが、俺の中で現実味を持ち始めている何よりの証拠だ。
酒屋でビールを買った後、レジで父親と話していた店のおばさんが、俺の方に「あら立派になって」と声をかけてきた。父親が以前やっていた塾の生徒さんの家らしい。「どうも」と頭を下げながら、中学生のように恥ずかしかった。
帰りの道すがら父親が煙草をくわえた。家に帰ったら吸えないだろうと俺にも一本勧める。マキに気を遣ってくれたのが嬉しくて、ポケットの中には自分の煙草が入っていたがありがたく頂戴した。小さな児童公園のベンチに座る。商店街同様、ここにも人の姿はない。銘柄は昔からハイライト。いつもメンソールの俺には少々重いが、まずくはなかった。煙草を吸っている間も、特に話すことはない。

帰ると、母親とマキが並んで台所で料理を作り始めていた。自然、男二人はリビングで相撲中継を見ながらビールとなる。やはり話すことはない。時折マキがおつまみ代わりの料理や新しいビールを持ってくる。段々と皿の数が増えて食べきれるかどうか心配になっていると、母親が電話で寿司を注文している声が聞こえた。それはさすがにトゥーマッチだ。慌てて止めに行こうとすると父親に制された。ああなったら止まらんだろ、と苦笑している。それもそうかと、上げかけた腰を元に戻した。
結局実家を出たのは九時過ぎ。やはり食べきれなかった寿司をパックに詰めて持たされた。帰り際になって母親が俺を呼んで耳打ちをする。
「まだあちらの家に行ってないらしいじゃない。来週にでも絶対に顔を出しに行きなさいよ。向こうのお母さんだってマキさんのことを心配してるんだからね」
まあな、と言葉を濁すと「恥かかせないでよ」と強い口調で詰め寄られた。まあそういうことだよな、と了承する。三年が過ぎても、いや過ぎたからこそ、結婚は当事者だけの話ではないらしい。
寿司以外にも色々と手渡され、結構な大荷物になってしまった。持ちきれない分は今度来た時に持って帰ると言ったが、「早く冷蔵庫に入れないと」と母親は譲らない。これ以上は言い合っても無駄だ。だから全部持ち帰った。中には貰い物の缶詰など余計な物も入っていたが、もちろん文句なんて言わない。帰りの電車の中、マキは機嫌が良かった。
「お義母さんってあんなに優しかったっけ」
優先席に座り、ぽつりと呟きながら眠りに入る。前はあまり優しくなかったのかな、と考えながらマキのつむじを眺めていた。電車はそこそこの混み具合、これくらいお腹が大きければ優先席に座っていても違和感はない。降りる一つ前の駅で起こすと、ふいに喫茶店の名前の由来を尋ねられた。俺もよく知らない、というかシンプルな名前すぎて由来なんてなさそうだと勝手に思っている。
店の名前は「ピース」、平和のことかどうかも分からない。
妊娠七ヶ月目(二十四週〇日~二十七週六日目)
梅雨が長引いていた。マキはまた一段とお腹が大きくなり、身体を動かすだけでも苦しそうな瞬間がある。もともと華奢だからより一層苦しそうに見えるのかもしれない。
俺がグレースと会ったあの日以来、マキはあまりお腹の子に話しかけなくなった。多分そういう姿を見せないように努めているのだろう。パン屋の仕事もそろそろ辞めていい時期だが、出来る限り仕事は続けたいと言う。何より気分転換になるからいいらしい。気分転換、という言葉が引っ掛かる。お腹の子どもに話しかけたりすることに、マキ自身も息苦しさを感じているのだろうか。
気分転換? と訊き返すと「だって家に一人でいたって特にやることもないしさ」と答える。お腹の子に喋りかけていても、一人でいることに変わりはないのだろうか。お腹の子がいるじゃないか、と言おうとしたが嫌味に聞こえそうだからやめた。
いつも通りに「夜想」で飲んで帰ってきた夜、シャワーを浴びてベッドに入ったらマキの手が股間に伸びてきて形を確認するように握られた。まだ酔いが残っていた俺は間抜けな声を出して、そのままマキに身を任せていた。暗闇の中、二人とも何も喋らない。
そういえば長い間マキとしていない。そのせいか、みっともないくらい直ぐに反応してしまった。指の腹が形をなぞる度に薄膜の快楽が折り重なっていく。この薄膜をどこまで破らず重ねられるかは、気持ちよさの度合いと比例している。
マキの身体が下に移動して形を確認しはじめた。俺も身体を上に移動させる。さもないと、マキがベッドからはみ出してしまう。その体勢は妊婦にとってはかなり辛いだろう。
トランクスを脱いだ俺の脚をマキはぐっと開いた。目が少し慣れてきたので、両脚の間から顔を見ようと顎を引いたら気持ち悪くなった。少し飲みすぎたようだ。四つん這いになったマキの気配と唾液の音に溶けてしまえば楽になる。よし、楽になろう。腰を突き出すと呻き声がして、更に強く吸い込まれた。腕を伸ばせば髪の毛に触れられる。細かい部分に舌が届く度、俺も呻いてしまう。その呻き声を頼りにマキの舌先は先へ先へと進んでいく。先へ先へ先へ先へ。弾けそうになり堪える。堪えながらふと思った。
――俺ばっかりじゃ悪いかな。
そう思う。ただもう七ヶ月だしな……。そうとも思う。マキの身体を考えて、というのは本当だ。ただそれ以上に、お腹の大きいマキに欲情できるかどうかが不安だった。
そんなことを考えていると、どうしても集中力が途切れてくる。分かっているがこればかりはどうしようもない。想像力を総動員しても無理だ。いやらしいことを考えようとすればするほど裏目に出るし、妙なタイミングで一気に身体へと還元される。
そう、萎えてしまった。元に戻ってしまった。無理になってしまった。
マキが口を離して指先で何かを試すようにゆっくりとリズムを刻む。一分ほど続けたがもうダメだった。目が慣れた粒子の粗い闇の中、マキが静かに動いて元の位置に戻る。俺も戻った。また沈黙。時計の針の音。外を走る車の音。何だか判らないジーという機械の音。手を握ろうと思った。強く手を握ればそれで上手くまとまるような気さえした。
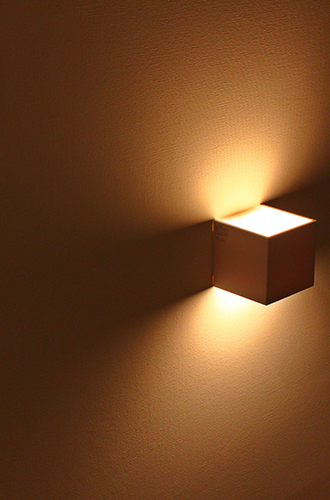
マキの手は少し汗ばんでいて握っても反応がない。粒子の粗い闇の中で俺は不安になって頬にキスをした。少しでもいいから何かの反応が欲しくてキスをしたが反応はなかった。怒っているわけでも泣いているわけでもなく、ただ反応がないだけの人は重い。その重さに耐え切れず遂に話しかけてしまった。
「どうした?」
その問い掛けにも反応はない。十数えても反応がなかったら話しかけよう。そう決めて七まで数えた時、マキがこっちを向いた。再び「どうした?」と尋ねる。一方的に握っていた手に微かな反応があった。そして「大丈夫なの?」とマキの声。「しなくて大丈夫?」。そう言われてやっと意味が掴めた。
「ああ」
「本当に?」
「ああ」
「でも」
「大丈夫」
「うん」
言葉は便利だ。十秒もしないうちに意志の疎通が出来てしまう。よかった、と言ってマキは体勢を戻した。よかった、と俺も思った。これで本当に安心してくれたのだろうか。隣から聞こえ始めた寝息をどこかで俺は疑っていた。
横浜にあるマキの実家へ行こうと日取りも決めていたが、急遽中止になってしまった。叔父が事故で入院をしたとのことで、わざわざマキの父親から謝罪の電話までもらった。話すのは久しぶりだ。緊張しながら対応していると、「どっちが謝ってるか分かんないじゃない」とマキに笑われた。
その代わり、ではないがマキの姉の子ども、姪っ子のリッちゃんが週末に山梨から遊びに来ることになった。電車で二時間もかからないので、年に二、三度は泊りがけで遊びに来る。最後に会ったのは正月の時期だっただろうか。
「もう中学生になるのか、リッちゃん」
「まだ五年生よ」
会って一年も経たない姪っ子の年齢を覚えていないなんて、もうオッサンだな。
「あれ、そうだったっけか」
「あの子、大人っぽいからね。背も私やお姉ちゃんより大きいんじゃないかしら」
体格だけではない。リッちゃんは全体的に大人びた雰囲気の女の子だ。ませているとか、背伸びをしているという感じではなく、どちらかというと、そんな大人びた自分を目立たせないよう気をつけている印象がある。
「で、何しに来るんだ?」
「別に目的なんかないんじゃないの」
半年振りに会うリッちゃんは、また背が高くなったみたいだった。派手な色使いの服ではなく、シンプルなジーンズに無地のシャツという恰好がなお大人びた印象にしているのかもしれない。端正な顔はマキの姉似だろうか。眉毛がやけに綺麗に整えられていて、最近の小学生はそんなこともするのかなと驚いた。
それともうひとつ、気付いた、というか気になったことがある。土曜日の午前中、たしかに俺は半分寝ぼけていたが、以前よりリッちゃんが明るくなっていると感じたのは勘違いではないだろう。ニコニコと笑いながら、大きくなったマキのお腹に耳をあてているリッちゃんは、寝ぼけた俺が見てもやはり以前とはかなり印象が違う。さばけた、という言い方が一番正確かもしれない。
「え? 今お腹蹴ったの? 違う? 違う?」
そうやってはしゃいでいる姿は、子どもらしくて無邪気、というよりも、何だか大人としての処世術を身につけたように見えなくもない。
「リッちゃん、また背が伸びたんじゃないか?」
歯ブラシを片手に訊くと、大袈裟に表情を曇らせる。「もう背が伸びるのイヤなんだって」とマキが笑うと、「女子で百六十になってるの私だけなんだもん」と言い添えた。その仕草は五年生らしいものだったが、素直に受け取りづらい感じもどこかある。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






