 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第七幕(後編)
月子の家へ出かける。
文彦がそう言い出したとき、それもまた夢の中の馬鹿げた言葉のように聞こえた。
晴れた日の夕方だった。
窓から覗くと、家の周辺は見たところ以前と変わらなかった。
コートを着て、文彦と外に出た。
近所の人影は疎らで、取材のクルーも特に見あたらない。
冷たい外気に触れると、二足歩行する人間のあり方をどうにか思い出した。タクシーを拾い、都内の月子宅へ向かった。
この医院を訪れるのは二年半ぶりくらいか。
白い建物の表玄関脇の看板を見ると、月子と広司に加え、長女の玲が大学病院勤務の合間に診療する三人体制となっていた。
四階の自宅に上がり、診察が終わる夕方まで待った。応接間の窓際に所狭しと置かれた観葉植物、家政婦の手で夕飯が用意された食堂を、文彦は鋭い目つきで眺めていた。
階下の診察室から先に上がってきたのは、義兄の広司だった。
「やあ、ご無沙汰だね」
薄い白髪頭を陽気に振り、忙しげに白衣を脱ぐ。
「これから大森の医師会で講演を聞かなくちゃ。最近の患者の耳学問は最新医学を捉えてるからね、まったく」
背広を取り、そそくさと出ていった義兄に、文彦は憮然としていた。この家や義兄の、やたらと尋常な雰囲気が気に入らないに違いあるまい。が、わたしはむしろほっとした。
「いらっしゃい。二人で珍しいこと」
応接間に入ってきた姉はにこやかだが、やや緊張した表情が見て取れた。
ハンガーに白衣を掛けると、前もって用意させてあったらしい紅茶の盆を運んでくる。

「悪いわね、姉さん。先に夕飯を済ませてきてよ」
そんなまっとうな言葉を口にすると、何やら日常の感覚が戻ってくる。
いいの、と月子は首を振った。「いろいろと大変そうね」
月子からは、これまで二度ほど電話をもらったが、ただ事態の推移を見守るという態度を崩そうとしない。
「そういえば一昨日、好女子からも連絡があったわ」
好女子からも、とは何だ。文彦はそう言いたそうだった。
「夾子さんの出ているテレビは、ご覧になりましたか」と、その代わりに言い出した。
「あれが妹と知れたら、さぞお困りになるでしょう」
「ま、妹とわかれば」と答えた姉はしかし、顔色ひとつ変えない。確かに夾子は旧姓を使っているものの、この医院とすぐ結びつけられはすまい。
「好女子のところは、だいぶ苦慮してるようだけど。田舎町だと何でも知れ渡ってしまうからね」
「こちらだって時間の問題でしょう」
文彦は皮肉っぽく言い放った。
「そしたら、あれは生さぬ仲で、って眉をしかめるつもりよ」
姉は肩をすくめた。「他人以上に付き合いがないんだと、勝手に思ってくれるもの」
「なるほど、腹違いも使いようだな」
苛立った文彦から、姉は黙って目を逸らした。
「こっちは腹違いを理由にか、姪を虐待したと疑われる始末ですがね。ともあれ私どもの陥っている面倒には、民事と刑事の二種類があって」
「刑事って」
突然、姉はソファで身じろぎした。
「まさか逮捕されるって、本当なの? 週刊誌には抗議したって、夾子は言ってたのに」
「もちろん、そんなことはさせませんよ」文彦は声を上げた。
「神経症の子供の言い分なんかで、公判維持できるもんか」
「でも、もし。万が一にも、」月子は肩を落とし、掌で顔を覆った。
この姉の狼狽ぶりに、文彦も心を動かされた様子だった。
「弁護士が言うには、美希が本当に男の子を突き落としたなら、それを家内が指示したといった刑事上の事実がなくとも、民事の上で、美希に対する管理責任を負うそうです」
月子は頭を振り、話を聞こうと努力していた。
「その場合は家内と夾子、美希の両親の連帯債務だけれど、この三者、たまたま姉妹関係にある。ならば熊本の実家の土地建物を処分して損害賠償に充て、なお払いきれない分を三分割しては、と」
話が事務的になるにつれ、姉の表情は冷めるように落ち着いてきた。
「七年経つと失踪宣告が下りるので、お義母さんがこのまま出てこなければ、あと三年あまりで相続開始します。いずれ、そのくらいの時期まで民事裁判や話し合いが続く可能性もある」
「つまり、わたしが相続放棄すればいいというわけね?」
月子は言った。「もちろん、あなたが助かるなら構わないわ。あれが実家だなんて思ってないもの」
ありがとう、と文彦は頭を下げた。
「でもまた、どうしてこんなことに」と、姉は再び弱々しく呻いた。
「好女子の娘だの、夾子の彼だの、どうだっていい。でも、あなたまで」
「まあ、こうなったら、お義母さんが出てこないように祈る気分です。申し訳ないが」と、文彦は苦々しげに呟いた。
「出てこないわ」月子は不意に顔を上げた。
「出てくるもんですか。あの女が」
文彦の驚いた眼差しに、姉は我に返り、硬い笑みを浮かべた。

「何度も言うけど、わたしはあの家を捨ててきたのよ。ほら、食べる物だって差別されて」
そのとき、食堂との仕切りのアコーディオンカーテンが開き、玲が入ってきた。
「楡木子叔母ちゃん、お久しぶり」
玲は大学病院の夜勤明けで、早く帰れたのだと言う。
続いて次女の郁が、ジーパン姿でやってきた。
「ママ、相続放棄って、前もってはできないのよ」
夕飯を済ませてから聞き耳を立てていたのだろう。私大の法科三年に在籍する郁の生意気な物言いに、文彦はすぐさま色をなした。
「知ってるさ。今が今、放棄させに来たんじゃないよ」
「あんたたち、向うへ行ってなさい」と月子が促した。
「いや、構わない」
夫は教師然とソファを指した。「そこへ坐りなさい。ママの財産は、君たちにも関係するんだから」
郁はただ考えもなく、学んだ知識を口にしてみただけに違いない。
お調子者の妹が慌てるのを尻目に、玲はワンレングスの髪とワンピースの裾をひらめかせ、無表情でソファに掛けた。そのクールさは月子譲りだが、夫の目にはさぞ挑戦的に映ろう。
「もう承知だろうが、叔父さんと叔母さんは厄介ごとに巻き込まれている。無論、自分たちだけのせいなら、頼み事などしやしない。だけどこれは、君たちの親戚でもある美希や夾子さんから起こったことだ」
玲の隣りに渋々腰掛けた郁は、何度もかくかく頷いている。
「早く解決しなければ、この医院にも影響が出るだろう。もちろん相続放棄してもらうと決まったわけではないさ。そのときになって、もしここが困っていれば頼まない」
たとえば、と文彦は、ゼミの学生を虐めるように睨めつけた。
「君たちのお父さんも、医療ミスで訴えられて損害賠償を請求されたとか。あるいは、ここの家族の誰かが交通事故を起こしたとか。郁ちゃん、君が男に騙されて巨額の借金を背負ったとか」
「もう、いいじゃないの」
郁がかわいそうになり、わたしは口を挟んだ。
歳の離れた優秀な姉がいるというだけでも、彼女には何やら同情心が湧く。ロースクールを諦めた郁は、マスコミを志望したい、と電話してきたことがあった。が、この事態ではわたしのささやかな人脈が役立つどころか、汚点にもなりかねない。
「そりゃ誰だって、何が起きるかわからないわ」
ふいに玲が言い出した。「だけど、起こるべくして起こることもあるでしょ?」
夫は眼鏡越しに覗くように姪を見た。
「相続放棄のことは関知しない。ママが生きているかぎり、相続するのはママであって、わたしたちじゃないもの。法律はよく知らないけど、常識からしてそうでしょ、郁」
二十七歳の研修医の姉に、郁はしょぼくれたまま頷く。
「楡木子叔母ちゃんは、災難だったと思う。でも美希ちゃんがトラブルを起こすってのは、ずっと想定の範囲内だったもの」
そうだよ、と郁もぶつぶつ言いはじめる。「昔、遊びに来たときだって、意味のない嘘ばっかりついてさ」
「もともと手に負えない小児が成長するにつれ、身の丈に合った大きなトラブルを起こし、他人を巻き込む。要はそういうことでしょう?」
玲の言葉に、文彦はしばらく考え込んでいたが、「それ、二人とも、もしかして裁判で証言してもらえるかな」と言った。
「構いませんけど。たぶん必要ないんじゃないですか」
大学病院の勤務を終え、口紅を落とした玲は、漂白されたような疲れた表情だった。
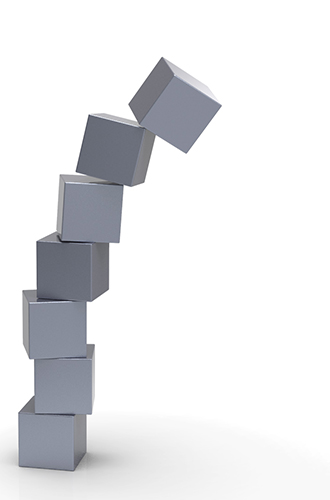
「どっちみち、そう嘘を吐き続けられるわけないし」
「そうだよ。あの子やなんかに、みんなして振り回されることないよ」
郁が口を尖らせた。「阿呆らしくってさ。テレビに出てる夾子叔母ちゃんの格好も、中年女っぽくて最悪じゃん」
若作りだと、もっと最悪なのよ、とは言いそびれた。
「だいたい、こんなことになる前に、さっさと逃げればいいのに」と、玲は深い息を吐く。
「ほんと。若い男にしがみつくなんて、物欲しそうで、みっともなくてさ。血が繋がってるって思うと、吐き気くるって感じ」
尻馬に乗る郁を、玲はおろか月子すら、たしなめる素振りもない。
見かねたわたしは「あんたたち、小さい頃は仲良しだったじゃないの」と言った。
「仲良しってゆーかー」郁は肩をすくめる。「受験生の友にさせられただけ。だって三〇歳にもなって問題集なんか解いてんだもん」
「子供は馬鹿にしないって、安心してたんでしょ」
玲の口調も、大学生の妹に劣らず軽蔑の色を帯びている。
「中学生だったあたしに、フランス文学を専攻しろって言うのよ。少女趣味ったらないの」
「ふん。お姉ちゃんが自分より先に医学部に入ったらって、怖れてたんだよ。今はテレビなんかで、お利口ぶっちゃってるけど」
こんな雑言を聞き流している月子に、わたしは憤っていた。
優秀な姉が、娘たちをしつける素質をこれほど欠いていたとは。
「ブスと馬鹿こそ医者になれ、ってか。なりふり構わず、親戚中に頭下げてたくせに」
「そうだ」と、突然、夫が頷いた。
「親の臑を長々かじってたくせに。何が厚生省の医療行政の不備だ、偉そうに」
「医療行政ねえ」と玲が失笑した。
はん、と郁はさらに調子づく。
「国公立以外ダメって、お祖父ちゃんの主義だったのに。もし長生きしてたら、いまだに浪人だよ」
「今さら、色気づきやがって」と、文彦は罵った。「男と乳繰り合うのに邪魔になって、ガキを押しつけてきたんだ」
「欲求不満の中年女だもん。ホストにでも入れあげてくれれば、まだ周りに迷惑かけないのに」
「あのね、」
妙に意気投合したこの三人に、わたしは割って入るのがやっとだった。
「美希を学校に行けるまでにしたのは、夾子なのよ。頭がいいより面倒見がいい方が、医者には向いてるでしょ?」
「違うわよ、叔母ちゃん」玲が可笑しそうに掌を振った。
「面倒見がいいのはナース向き。医者に必要なのは、逃げ足が早いこと」
なるほど。さっきの、あなた方のお父さんみたいにね、とは月子の手前、さすがに言えない。
「とにかく、」大御所然と、月子が口を開いた。
「取り越し苦労はやめておきましょう。いずれ状況は変わるかもしれないし」
帰りは電車で。
それがどうにか生活感覚が戻った、わたしの判断だった。
JR大森駅までのタクシーの中で、文彦はやや緊張が解け、同時に気も抜けたようだった。

「月子さんは無関心な鉄仮面と思っていたが、あんなに動揺するとは。やはり君に対しては、多少の情はあるとみえるな」
「あれで昔は結構、世話好きだったのよ。下の妹たちのことは、振り捨てると決めてしまったみたい」
「食い物の恨みは怖ろしい、か」と、文彦は笑う。
「そんなんじゃないわ」
食べる物だって差別された。
娘たちの態度も、そんな月子の言葉を真に受けてのものなのか。
確かに好女子が生まれてから、お腹が弱いという口実で、彼女だけ特別の皿を誂えられていた。が、長男の赤ん坊が亡くなった後も、姉が実家へ戻らなかったのは、少なくとも食べ物のせいではない。
新婚の婿養子夫婦にと、母が用意したのは、物置にあった中古の家財道具だった。
金がないという理由だったが、その頃、県立高校に落ち、私立の寄宿舎に入った好女子には新品の家具を買い与えていた。父はあえてそれに反対もしなかった。
もう腹はわかったけん、と月子はあのとき言った。
新しい家具が欲しいわけではなかった、と思う。差別されていると感じないよう、子供の頃から努めてきたのは、わたしも同じだ。それを無にされた。そんな気持ちだったろう。
だが、わたしも歳を取るにつれ、母の立場もわかってきた。
腹を痛めて産んだ子の不出来は、誰のせいにもできない。腹違いの上の子の出来がよければなおのこと、比較される不憫も母親である自分のせいだ。それを金の力で、少しでも庇ってやれるなら。
「ま、いいさ。助かった」
車から大森駅に降り立つと、文彦は言った。
「相続で揉めるのは損得より、子供時代への執着心からだそうだ。我々の今の状況からすると、月子さんの冷淡はむしろありがたい」
(第13回 第七幕 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








