 妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
by 金魚屋編集部
次の日からマキが何となく変わってきたような気がした。どこがどう、という訳ではない。ようやく俺がマキのことを「妊婦」だと認めただけかもしれない。これから煙草を吸う時はベランダで吸うとマキに伝えた。あんまり気にしないでよね、と言われたが「お腹の子のためじゃないか」とたしなめると「あ、そうか」と笑っていた。
実を言うと、煙草を吸いにベランダへ出るのは俺自身にとって好都合だった。今までだとマキが家にいる時は我慢したり、吸っても半分で消したりしていたがそれでは落ち着かない。ベランダ喫煙宣言をした翌日、エアコンの室外機の上に灰皿を置き、椅子も近所のホームセンターで用意した。折り畳みチェア、二千円。何だかずいぶん楽しんでるみたいじゃないの、とからかわれたが特別否定はしなかった。
五階のベランダから眺める景色は特別綺麗というわけではないが、特に夜、ぼんやり眺めていると妙な心地の良さはある。煙草の煙がゆっくりと空気に溶けていき、町のざわめきが明瞭に感じられる。瞑想と名付けては大袈裟だが、喫煙の効果も含めてベランダにいる時間は明らかに気持ちが落ち着いた。あとはジャズが聴けたら最高なんだけどな、と真剣に考えてしまうほどだ。呆れるマキの顔が浮かぶ。ベランダは秘密基地じゃないのよ、と呆れている妊娠中の女房の顔。
数日前、連絡がつかなかった元「余り者」のひとりから遅い返事が来た。イノウエだ。遅すぎるだろ、とぼやくと「お前みたいに暇じゃないんだ」と間髪入れず返された。近くに来ているから食事でも、という誘いを断る理由はない。外回りの帰りだというイノウエとは半年振りで、少し老けたなとからかうと「お互い様だろ」と笑っていた。妊娠のことを告げると、イノウエも付き合っている彼女と来春結婚の予定だという。
「なるほどな、それでずいぶん遅くなったけど連絡をくれたわけだ」
「それは俺のセリフだよ。あんな時間に暇なのは失業保険を貰ってる奴だけだ」
「しかも二回目な」
乾杯してから軽く互いに近況報告。吉報を抱えた同士、何となくスタートからテンションが高い。ただでさえ酔うのが早いイノウエは、一時間も経たないうちに顔が赤くなってしまった。いい具合に酒が回り始め、少しずつ口が軽くなっていく。気をつけろよ、と俺は密かに自分を制した。コケモモの話はしない。そう家を出る前、鏡の前で言い聞かせたのに、ふとした瞬間イノウエにならいいかと気が弛んでいる。
「余り者」だった連中は、俺たちが大学卒業後に別れたことを承知している。ただ、その理由まで知っている奴はいないはずだ。コケモモは誰かに相談するようなタイプではないし、卒業以来、誰とも連絡を取り合っていない気がする。あいつはそういう極端なヤツだ。毎月二十六日、俺に送ってくるメールも「連絡」とは呼べないだろう。
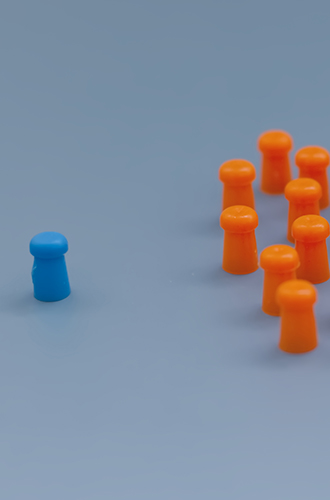
コケモモの話題を喉の奥に留めつつベランダの話を切り出すと、「尻に敷かれてるんじゃないか」とイノウエは肩を揺らしながら笑った。ただ、そのベランダが妙に落ち着くことを打ち明けると表情が微かに硬くなる。どうした? と訊きたい俺を片手で制し「これから結婚する俺が言うこっちゃないがな」とトーンを落とした声で話し始めた。
「それはさ、きっとどっかでカミさんのことを避けたいと思ってるんだよ。いや、それが悪いってわけじゃないんだぜ。多分だけど、妊娠前のカミさんと、妊娠後のカミさんって別人みたいなもんなんだろ?」
俺はよっぽどセックスをしている時に、髪を乱暴に掴んだりタオルで目隠しをしたり、という行為が出来なくなったことを打ち明けようかと思った。
「分かってるだろうけど、ベランダで煙草を吸うのが安らぐっていうのは不健康だぞ。どうせ安らぐんだったらさ、もっと健康的な方法にしろよ」
そう熱弁を続けるイノウエに、じゃあどうしろっていうんだと尋ねると、難しい顔のまま小指を立てた。元「余り者」の二人は数秒間の沈黙の後、目を見合わせて吹きだした。
別れ際、デパート勤務のイノウエは「ベビー用品はうちの売り場が関東一だぞ」と叫びながらタクシーに乗り込んだ。いい酒だったな、と足取り軽く帰宅するとマキが電話をしている。また電話相談だ。どうやら相手は山梨の義姉らしい。ケンコウホケンとかシュッサンイクジイチジキンなんて単語が聞こえてくる。メモを取りながら電話をしている後ろ姿を見ていると、マキとの距離がどんどん開いていく気がした。
イノウエの「不健康だぞ」という言葉を思い出しながらベランダへ向かう。室外機の上には灰皿と共に煙草とライターも置くようにしている。不健康か、と呟きながら煙草に火を点けた。毎日の生活は変わらないし、もちろんマキと喧嘩をするようなこともない。他愛もない会話で微笑んだり、理由のはっきりしない感謝の念に包まれたりもする。だけど、なのだ。だけど、それなのに、何処かが軋んでいる気配ははっきりと感じる。軋ませているのは俺か、マキか、それともお腹の子か――。
帰って来る時は気にならなかったが、時折冷たい風が吹きつけてくる。酔い醒ましにしては強すぎる冷気の中、窓越しに見えるマキの後ろ姿にふっと煙を吹きかける。と、その時コケモモの顔が一瞬浮かんだ。あの似ている女優ではなく、ちゃんと本人の顔だったような気がする。不思議なのはようやく元恋人の顔が浮かんだのに、ちっとも生々しくなかったことだ。
ネットで面白そうなバイトの募集を見つけた。西新宿にあるジャズ専門のレコード店のスタッフ募集。住所を確認するとマンションの一室、時給は千百円、時間は午後二時から七時。失業保険を貰っていても、週に二十時間未満なら働けるし、何となく俺向きの条件に思える。

もちろんネットから申し込むことも出来たけど、雰囲気が知りたかったので直接電話をしてみた。話をしてくれたのは、声から察するに初老の男性。では明日面接なんてどうでしょう、と尋ねられた。こういう話は早い方がいい。「よろしくお願いします」と電話を切った後、もう何か一仕事終えたような気持ちで煙草を吸う。最近、マキのいない昼間でもベランダで吸う癖がついてきた。
遠くに見える桜が散り始めている。ジャズは好きなだけで詳しくないけど大丈夫かな、ただ時給千百円だから倍率は低そうだ、そういえば東京の最低賃金っていくらなんだろう――。無防備で楽観的なことばかり考えつつ、深く煙を吸い込む。
明日もし採用されたら、マキにはどのタイミングに、どんな感じで伝えよう。あいつはそろそろパン屋の仕事を、アルバイト扱いに切り替えるつもりらしい。もったいない、という言葉を慌てて呑み込んだのは正解か、それとも……。
冷静に考えれば、こんな世の中だから産休や育休を取っても問題はないはずだ。ただ、そんな世間一般の話と、あいつの想いは別モノ。妊娠とは関係なくそろそろ転職を考えていたとか、出産したら専業主婦になるつもりとか、何かしら考えているはずだから、やはり呑み込んでよかったのだと思う。まあいいや、当面の家賃や生活費くらいは貯金でどうにかなる。
ちょうどいい風が吹きつけてきた。聞こえてくるのは部屋の中のテレビの音や、下のベランダで布団を叩く音。穏やかな春の午後ってヤツだ。この間、俺はここでコケモモの顔を正確に思い出した。そしてそれは、ちっとも生々しくなかった。何ていうか、ある時期を一緒に過ごした女という感慨がまるでなかった。どうしてだろう?
数年前に俺たちは、色々な方法と色々な場所で互いを貪った。例えばそういう記憶が生々しさに直結してもいいはずなのに、どうしてだろう?
一時間にも満たない起承転結、それが幾つか積み重なった起承転結、そして付き合ってから別れるまでの大きな起承転結。コケモモと過ごした多くの起承転結の中で、俺の感情は様々に、時には散り散りに変化し続けたはずなのに、どうしてだろう?
異常なのかな、と暗い気持ちになる。ヒトの忘却能力に値が付けられるなら、俺は余裕でトップランカーかもしれない。気付けば、指に挟んだ煙草はくすぶっていた。新しく火を点け、コケモモにまつわる生々しさを見つけてやろうと椅子にどっかりと腰を降ろす。でもそんな気負いは要らなかった。あいつと俺の間に今も生々しさが残っているとすれば、それはひとつしかない。薄々分かってはいたくせに、向き合うことを拒んでいたあの一件。六年前の十一月二十六日の話だ。コケモモは俺にこう言った。
「赤ちゃん出来たって言われた」
この間のマキと同じく、味噌汁の具を告げるように素っ気ない口調だった。でも似ているのは口調だけで、それを告げる気持ちはまったく違ったはずだ。マキは出産を反対される可能性など考えもしなかっただろう。でもコケモモは違う。俺の反応次第で状況は百八十度変わってしまう。
場所はコケモモの部屋だった。昼飯を食べていたから、間違いなく土曜日だ。もう二人とも学生ではなかった。妊娠を告げられた俺は動揺した。妊娠は結婚を意味していて、俺にその意志は皆無で、でもそれは胸を張ってあいつに言えることではなく、結果沈黙するしかなかった。動揺を気取られないように、俺は黙んまりを決め込んだ。卑怯者だ。
「可愛い女の子だったらいいんだけどね」
普段どおりの頭が悪そうな喋り方。試されている、と俺は身を固くして頭上の嵐が通り過ぎるのを待った。当然沈黙していたし俯いていた。
「……ほんじゃ、別れよう」
嵐は通り過ぎるどころか、一瞬にして消え失せた。慌てた卑怯者はようやく口を開く。
「いや、あの……」
「心配御無用。さ、帰って」
卑怯者といるぐらいなら孤独と静寂を選ぶ。コケモモのそんな姿に俺は気圧され、おろおろとその場を立ち去るしかなかった。あれが最後だ。あの日以来一度も会っていない。
あいつから短いメールが届いたのは一ヶ月後だった。
調子はどう? /さびしい毎日を送っているかい/こっちは新しい毎日をエンジョイしてるよ/じゃあね/分かってるだろうけど、返事なんか出すなよ
別れた日から、ちょうど一ヶ月経っていた。本当は返信したかったけれど、中絶した女にかける言葉を俺は持っていなかった。あれ以降、一ヶ月毎に他愛もないメールが送られてくる。未だに俺は一度も返信していない。
思い出したくないことを思い出したせいで疲れた。まだ立ち上がりたくない。この二千円の椅子に座っていたい。ただ脳味噌は持ち主の意向に反して活発に動き続けている。俺は脱力した身体を持て余しつつ、あの日の感覚と今現在の感覚が勝手に溶け合っていくのを受け入れるしかない。
「中絶したことある女なんて珍しくないだろ?」
当時、酒の勢いに任せて何度かそんな質問をした覚えがある。相手は男ばかりだったので、芯まで酔っていたわけではない。欲しい答えが決まっていたから相手を選んでいた。卑怯者だ。当然すぐにコケモモを連想するであろう、元「余り者」の連中にはしたことがない。

「そうだねえ、実際はかなりの数がいるんじゃないの?」
そういう都合のいい答えしか聞きたくなかった。「どんなに小さくても命は命」とか、「本質的に人殺しと同じ」とか、そんな稔りのない正論に用はなかった。そんな言葉でよかったら俺でも言える。計画性も避妊具も想像力も持っていない俺でも言えるんだ。馬鹿野郎。
「まだ産まれてもいない命って、そんなに大切なのかよ」
さすがにそこまでは言えなかった。好んで軽蔑される趣味はない。ただ、ことあるごとに胸の中で繰り返していた。この世に産まれてきて、人口としてカウントされて、初めて「命」扱いするんじゃないのか。ずっとそう思っていた。
しでかしたコトに対する後悔や、コケモモに対する罪悪感はあったが、その何十倍、何百倍の苛立ちを抱えていた。本当にどうしようもない。
そして今、似たような苛立ちが発生している。
表面上は平穏に見える生活を、どこかで軋ませる原因があるとすれば、やはりそれはお腹の子なのではないか。マキが妊娠さえしなければ、俺たちは「友達みたい」な夫婦のままいられたのではないか。
――まだ産まれてもいない命って、そんなに大切なのかよ。
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






