 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第三幕(前編)
三週間。
それが美希を預かると、約束させられた期間だった。
平日の夜と休日、妹の婚約者が頻繁にやってきて、美希の面倒を見る。
夾子はなるべく顔を出さない。彼と美希の、二人の距離が保たれ、うまく縮まるよう、わたしが見守る役回りだ。
二人の距離。
その言葉を聞いた瞬間、わたしは彼と自分のことかと錯覚した。
いったい、あれは何だったのか。
あの骨っぽい手を、わたしは払いのけなかった。
彼の指はわたしの指に絡み、手の甲を裏返させ、掌が吸いついた。互いの指は指の間の奥まで深く入り込んだ。捻れつつ結ばれた肉体そのもののように。
あのとき確かに、わたしたちの手は一種の共犯を為していた。
だが、もしかしたら。
わたしはあのファミレスでまんまとはめられ、美希を引き受けさせられたのではないか。
馬鹿馬鹿しい。
そんなわけはなかった。
そう確信させたのは、だが理屈でなく、わたしを見つめていた彼のあの潤んだ眼差しだった。
朝、七時半。
こんな時刻に起き出すのは、数ヶ月ぶりだ。
「じゃ、楡木子姉さん。悪いけど」
出勤の途中、美希の手を引いて立ち寄った夾子は、髪をきりりとアップに引っ詰めていた。
「忠くんは夜勤が明けてから、午後三時過ぎに来るって」
慌ただしくも屈託がない妹に、およそ話し込む余地などなかった。
話し込む。
そもそも、わたしはあのファミレスでのことを話すつもりがあるのか。
小走りに玄関から出る夾子を見送り、話しても信じはすまい、と自分に言い聞かせた。
いずれにせよ、簡単に婚約を破棄するとは考えられない。結婚を諦めさせようと、言いがかりをつけたとでも思われかねなかった。
そういう生き物だ。恋する女とは。
恋する女。
ふいに頬が熱くなる。
あの手の動きに、わたしは応えたのだ。
妹の知らない婚約者の一面を、その場で暴露することもできたのに。
忠くん、と、所有物を舐めまわすような夾子の声が耳に残る。
わたしはといえば、あのファミレスで、甘ったれの末妹を説教すべく待ち構えていたはずだった。さぞ幼稚だろう初対面の男に、お子さまランチはいかがと、嫌味をかまそうとすらしていたのだ。

「伯母ちゃん、顔が紅いね」と、美希が言った。
オレンジジュースを与えてから、ただの一度もこちらに目を向けないと思っていたのに。
「あんた今日、学校はどうするの?」
そう問うたとたん、美希はダイニングテーブルにコップを倒した。
わたしは一言も発さず、雑巾を手渡した。
以前に見かけたときと比べ、たいして成長したように見えない。十一歳だが身長で十歳ぐらい、雰囲気的にはもっと幼い。だが好女子に似ず目が大きく、顔立ちはまあまあ可愛らしかった。おかっぱ頭は、いつも夾子がカットしているという。
「行きたくないなら、別にいいのよ」
登校は無理強いしないように、としつこく注意されていた。それと、感情的に怒らないように。
とはいえ、ベビーシッターになるのは御免だ。年齢相応の対応をさせてもらうと、言い渡してある。
「夾子叔母ちゃんは、今夜から難しい患者さんが入るんで、病院に泊まり込みよ」
待っても無駄だ、と暗に言い含める。
美希は目を硬くつむり、いやいやをしながらテーブルにジュースを擦りつけるように雑巾を動かす。その幼児的な身振りは、まるで三歳児だ。
壁の時計を見た。八時十分。
もし登校しないなら、彼が来るまでこの子と二人、まだ七時間もある。
彼が来る。
赤面せず、落ち着いていられるだろうか。
あらかじめ姿を思い出してみた。潤んだ眼差し。少年じみた声に、匂うがごとき繊細な表情。そして、あんな真似を仕掛ける神経。
それにしても夾子も迂闊にすぎる。彼はわたしのファンだなどと取り持って、あの真剣な眼差しにまるで気づかないとは。
人のよい妹が、それだけ夢中、ということか。
自分には彼の本性を掴む義務がある、とわたしは考えはじめていた。無論、そんな使命感はただの隠れ蓑だったが、少なくとも部分的には筋が通っているように思えた。
「しゃぶい」
おかっぱ頭を正面に向けたまま、美希は腕を抱えていた。
十一月初旬にしては、底冷えする朝だった。が、ピンクのセーターに格子縞のジャンパースカートを着込んでいるし、ダイニングには暖房が入っている。ここの住み心地を試すかのように、美希の言動はいちいち要求がましい。
「寒いなら、上着を出しなさい」
動こうともせず、震えてみせるばかりの美希にじれて、わたしは立ち上がった。初日は仕方あるまい。夾子が置いていったキャスター付きバッグを開け、駱駝色のニットジャケットを放ってやった。

「あなたの部屋は、あそこよ」と廊下の奥を指さす。
わざとなのか、ジャケットをもたもた裏返しに着ている美希を放置し、わたしは階下へ降りた。
「荷物を運んで片づけて。それと夕方から英語劇教室だから、邪魔しないでちょうだい」
インターホンが鳴ったのは、三時半過ぎだった。わたしはリビングで椅子を並べ替え、教室の準備をしていた。
玄関に彼が立っていた。
先日のデニムのジャケットに、カッターシャツ、ジーンズ。一瞬、目の前の姿が信じられなかった。
「いらっしゃい。美希ちゃんがお待ちかねよ」
そう言うと、彼はすねたように目を逸らし、黙って会釈した。
やはりそんなものか。
わたしは落胆した。
気まぐれは若さの特権とやら、と怒りすら覚えた。「ご苦労様」と、彼の背に向かい、出入りの業者に対するように言った。
気に入りのクリーム色のアンゴラのセーターに、すらりと見えるチュールのスカートを着込み、わたしの方こそ、ご苦労様だ。
と、すれ違いざま彼は振り返った。目が真っ赤だった。
そのときになって、わたしは自分の嘘に気づいた。
彼を待っていたのは美希ではない。大人の特権のようなつまらぬ挨拶をした、わたしではないか。
同時に、夜勤明け、という夾子の言葉を思い出した。徹夜の後も、この時間まで働かされていたのだ。
看護師とはそういう仕事だ。
アンゴラのセーターにチュールのスカートで、わたしは立ちつくした。
年甲斐もない。そのくせ恥もなく、世ずれた物言いをした。
思わず視線が泳いだ。
美希が階段に坐り込んでいるのが目に入った。
これ見よがしに裏返しに着ていた駱駝色のジャケットはどこへやら、可愛らしいレースのカーディガンを羽織っている。
勇気を奮い、わたしは再び彼の背に声をかけた。
「教室が終わるまで、美希の荷物の片づけを手伝って」
片づけといっても、もうすることはない。美希の部屋のベッドで、すぐ彼を休ませてやりたいだけだった。
その意図が伝わったかどうかわからないが、彼は痛々しく充血した目で見返し、疲れた笑みを浮かべた。
教室に一番乗りでやってくるのは、たいがい中学三年生の敏彦だ。詰め襟に輝く私立進学校のバッジは、この辺りでは垂涎の的だった。
続いて公立小四年の由梨、女子大付属小五の沙也香が入ってきた。
リビングが賑わってくると、吹き抜けの天井が劇場に、階段の上がバルコニーのセットに見えはじめる。さらに子らが集まり、収拾がつかなくなると、活気ある舞台のあるべき姿が彷彿とするような瞬間もある。
そんなとき、わたしの中では、これが本業でないことは吹き飛んでいる。独りで悩み、脚本を書きあぐねる時間がもっと増えることを、本当に心から望んでいるのだろうか、とも思う。
ぎりぎりの時刻になり、アーネストこと陽平が入ってきた。横浜駅にほど近いキリスト教系私立小の六年生だ。今日は全部で七人らしい。
と、二階から彼の声がした。
「美希ちゃんは、そこで見ていたいそうですが」
カーディガンを着た美希が階段に坐り込んでいる。モデルのように足を揃えて流し、おかっぱ頭で小首を傾げた様子に、つい吹き出しそうになった。
「上の方にいるなら、いいわよ」
登校拒否児でも、子供たちの賑わいはやはり気になるのか。
由梨は美希と同じ学校のはずだが、美希は登校しても保健室にいるし、学年も違う。他の三人のうち四年生の一人は国立大付属、低学年の二人は公立だが、美希の小学校とは離れた学区域だった。
鞄から台本を出し、生真面目な視線で読み返している中三の敏彦を、美希はじっと見下ろしていた。

「はい、静かに。立ち位置について」
真田は二階のダイニングで椅子に掛け、吹き抜けの手摺りに肘を突き、階段の美希を見守っている。
部屋の隅に寄せたテーブルにカセットを置くと、わたしはやや教師然と背筋を伸ばし、台詞合わせを始めた。
「I want to come home」
エレナ役の沙也香は、いわゆる成りきりタイプだ。
長い髪を縦ロールに巻き、大人びた仕草で絶世の美女役にはまっている。が、その甲斐あって発音の上達も著しい。
「なぜ、あなたはわたしをさらってきたの」
そう日本語で促すと、沙也香はすぐさま情感込めて英訳してみせる。
「じゃ次、ハリス。あなたがわたしについてきたのだ」
照れ屋できかん気の陽平は、余分な手振りをくっつけ、わざとひどい声を出す。
てめえが勝手にくっついて来たんじゃねえかよ、とがなり立てているようにしか聞こえないが、放っておくしかない。
「キューピッドの魔法が解けたか、エレナ。愛する故郷とこの夫の顔を思い出したか」
と、長台詞の冒頭だけ示せば、メネラ王役の敏彦は淀みなく進める。もう台本を完全に暗記しているのだろう。この敏彦の落ち着きを羨み、いまだ声変わりしない陽平は親爺じみた濁声を上げるのだ。
「思い出したか、思い出したか」
小三以下の子供たちが声を揃えてリピートする。
そこへ被さるように、「恋は一時の気の迷い。だがそれはいわば神の御意、わたしの罪ではない」
沙也香は気取ってはいるものの、歌うごとき発音で読み上げる。
わたしの罪ではない。
突然、わたしは彼の視線を意識した。
立ち位置を変えながら、さりげなく上方を窺う。
うたた寝でもしているかと思いきや、彼はわたしを見つめていた。物狂おしく訴える眼差しは、疲労で血走っているのとは違う。
その瞬間、あの掌の感触が蘇った。指の間から全身に電気が放たれる。
「You goddesses what do you do. She should be mine」
てめえ、女神たちよお、どうしてくれる、俺の女じゃねえのかよ。
興奮した陽平は、そんな語調でわめくと、テーブルの物差しを取って振り回した。いつものことだった。
止めなければ。だが二階を意識して、わたしの動きは一瞬、遅れた。
と、そのとき何か飛んできて、陽平の顔に当たった。
「なんだ、この野郎、」
陽平は日本語で怒鳴った。
「ごめんなしゃーい」
幼児の甘え声で、階段の美希が応えた。絨毯の床に消しゴムの欠片が転がっている。
「陽平くん、ほら続けて。ならば国へ帰れ、争いの種となったおまえは殺されるだろう」
陽平の台詞を茶化すように、美希が片言めいたリピートで遮った。
Be killed、Be killed。
「うるせえ、馬鹿」
陽平が割れ鐘のようにがなり、階段に物差しを投げつけた。
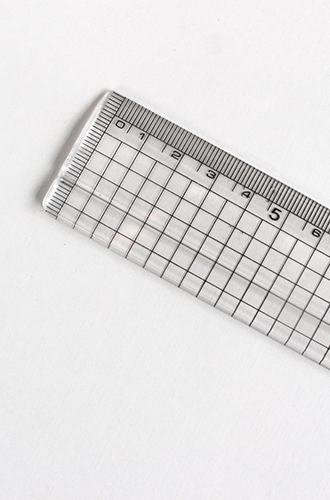
「美希ちゃん」
わたしは跳ね返った物差しを拾い上げた。
「邪魔をするなら、部屋へ行きなさい」
「はーい」と美希は返事した。よろけながら立ち上がった様子は、おむつでお尻の膨らんだ赤ん坊に似ていた。
真田が近づいて手を掴もうとしたとき、美希はいきなり回れ右をして階段を駆け下りた。
その素早さには、唖然とするしかなかった。
リビングを中央突破した美希は、陽平のズボンにむしゃぶりついた。
陽平は慌ててパンツを引き上げた。が、遅かった。
「なにあれ、ちっちゃーい」
優雅さをかなぐり捨て、嬌声を上げた沙也香に、陽平が泣きながら襲いかかっていった。
「きゃあ、先生」
「やめなさい、陽平くん。みんな止めて」
その陽平の足首に、美希が犬のように噛みついた。
陽平はめちゃくちゃに美希を蹴飛ばした。頭が床にごんごんと音を立てて打ちつけられ、美希はようやく陽平から手を離した。
陽平は腕を振り回し、隅に寄せたテーブルの上のものを全部払い落とすと、うおーっと叫び声を上げて外へ飛び出していった。
(第05回 第三幕 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








