 女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
やがて舞台からテレビへと活躍の場を移す彼女の七転び、否、八起きを辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑が Write Up。今を喘ぐ若者は勿論、昭和→ 平成→ 令和 を生き抜く「元」若者にも捧げる青春譚。
by 文学金魚編集部
四季をやめたい、という決心は確かにある。それは間違いない。決して一時の気の迷いなどではなく、その証拠にこうして東京へ帰ってきても、変わることなく胸の奥に置かれていた。
理由だってちゃんとある。とにかく今回の旅公演で疲れてしまった。あれさえなければ、やめるなんてこれっぽっちも思わなかっただろう。それほど辛い経験だった。あの人たちと一緒に芝居はできないし、やりたくない。しかもそんな思いまでしたのに、最終日に先生がつけた点数は六十点。情けないやら馬鹿馬鹿しいやら、涙も出ないとは本当、こういうことだ。
ただ、やめたいという決心は揺るがないけれど、不安がないわけではない。この重大な決意を、ちゃんと先生に伝えられるだろうか? 私はまだまだこれからだ。何も成し遂げていない新人が、それも大きなチャンスをもらっているにもかかわらず、自分からやめたいなんて何様だろう。きっと怒られるに違いない。本当にちゃんと伝えられるかな、私。
こんな風にグルグルと悩んでも、最後はまあ大丈夫かなと思える。だって、あんなに頑張っても六十点しか取れない役者は、きっと用無し・役無しだ。先生も「そうか、仕方ないな」と案外あっさり認めてくれるかもしれない。それはそれで有難いけど、意外と寂しくなったりして――。
こんな風に自分と向き合っている時、人は大切なことを見落としがちになる。御多分に洩れず、おチビちゃんも浅利先生のハード・スケジュールをすっかり忘れていた。携帯電話がないこの時代、忙しい人を捕まえるのは困難を極める作業だ。気付けば東京に帰ってきて二、三日が過ぎているのに、先生と言葉を交わすチャンスが一度もない。
しかも、あろうことか自分の予定も抜け落ちていた。アヤメさんと暮らしていたあの初台のマンション、元々浅利先生が住んでいて「管理人として」家賃も安くしてもらっていたあの部屋を、これからは劇団が利用するからと出なければいけなかったのだ。もちろん昨日今日に突然言われたわけではない……と思う。その証拠にアヤメさんはもう準備を終えていた。こんな大事な話を忘れてしまうくらい疲れていたのか、と改めておチビちゃんは落ち込み、我が身を憐れんだ。
幸い持ち物は少なかったし、家具などもそのままにしておけたので、引越し自体はちっとも面倒ではなかったけど、さすがに新しい部屋を整える気力はない。そして気付けば、明日は久々に稽古場へ行く日だ。ほぼ何もない部屋の真ん中で、おチビちゃんはとりあえず床の上に身体を横たえた。とりあえず今日は寝ちゃいましょう。明日、先生には会えるのかしら――。
翌日、朝から気はずしりと重かった。先生がいれば自分の決意を告げなければいけないし、いなければその決意をまた胸の奥にしまい直して、あの何もない1DKの新しい部屋まで持ち帰らなければならない。

そう、今まで大なり小なり「抜擢」されることが多かったおチビちゃんには、悩みを打ち明けられる人がいなかった。こういう時に必要なのは、家族や先輩、後輩ではない。その人たちも無論大切な存在だけど、少しだけ違う。同じ経験を積み重ねてきた仲間――同期だからこそ、分かち合える何かがあるはずだ。でもおチビちゃんの場合、抜擢され続けた結果、なかなかそういう相手には恵まれず、そればかりか同期の行動を上の人たちに密告していたのではないかというスパイ疑惑をかけられたことさえあった。
はーあ、と肩が揺れるくらいのため息を隠しもせずに稽古場へ入る。特に懐かしさはない。それよりも浅利先生はいるのかしらと社長室に直行しようとしたその時、廊下の人だかりが目に入った。遠慮がちな声も飛び交っている。
「え? 嘘?」
「あ、すごいよ、あの子、入ってる!」
「どこ? どこ?」
何だろう、と息を潜めて近づいてみる。先生に決意を伝えるまでは、誰とも喋りたくなかった。壁に大きく貼り出されていたのは、二ヶ月後から始まる舞台、『むかしむかしゾウがきた』の配役だ。携帯電話がないこの時代、重要事項は自分の足で見に行かなければならない。なんだ、とおチビちゃんは肩透かしを食らった気分を味わう。六十点女優には関係ないわね、と通り過ぎようとした瞬間、人の頭に隠れていた文字がちらりと見えた。ん? 思わず声が出た。立ち止まって爪先立ちになる。そこには確かに自分の名前があった。しかも、順番から察するに主役。
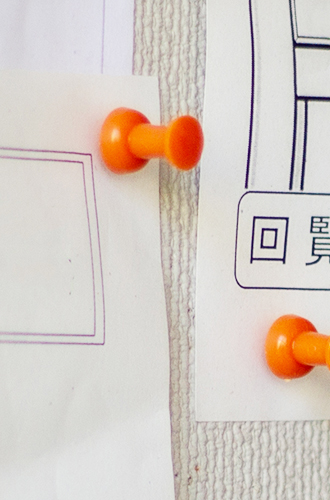
「ちょっと!」
そう口走って社長室へ直行する。小走りではなく、しっかりと走った。ノックはしたけれど、返事は待たない。ドアを開ける。果たして先生は――いた。
「おお、おはよう」
のんびりした声だ。張り詰めていた気持ちが、今にもひゅるひゅると抜けそうになってしまう。だから「おはようございます」とわざと硬めの声を出した。
「大変だっただろう? ゆっくり休めたかな?」
「いや、はい、えっと……」どうにも調子が狂う。「ちょっとは休めました」
「そうか。よかった。で、どうした?」
「はい、あの、休むには休めたんですけど、その、これからのことを……」
「あ、廊下のアレ、見たかい?」
「あ、はい。えっと、そのこともなんですけど……」
ダメだ。全然話ができない。しっかり順序立てて話さないと、訳が分からなくなっちゃう。
「あの……私、疲れてしまいました」
「うん」先生は柔らかい笑顔を崩さない。「何となくね、見てれば分かる」
「……それで、お願いがあるんですが……」
「うん、分かった」
「?」
「あと二、三日、休んでなさい。いいか? 右ノ者、自宅静養ヲ命ジル。な?」
「いや、それだと……」
「大丈夫、大丈夫。変な心配するな。みんなには俺から言っておくから」
まるで外国人と喋っているみたいだと思った。面白いほど話が噛み合わない。いや、外国人の方がもう少し話を汲み取ってくれそうだ。
「先生、あの、発表になっていた……」
「ああ、あれな。今度初めてやるんだけど、本当にいい話なんだ。大事な役だから、ちゃんと休んで疲れを取るように」
「……」
「初回の顔合わせ、日程書いてあっただろ? とりあえずあそこまでは休んで大丈夫だから。台本、無理がない程度でいいから、目は通しておいてほしい」
その後、何を話したかは覚えていない。気付いたら、新しい部屋の床の上で寝転がっていた。よく前の家に間違えて帰らなかったな、と我ながら感心する。
結局、引き受けたみたいになってしまった。何が悪かったんだろう? 私の伝え方かな、と思わなくもない。こんなことなら、あの旅公演でのひどい有様、先輩たちの悪行を全部ぶちまけてやるんだった――。
いや、それでもダメだったかもしれない。先生のことだ。その場でみんなを緊急招集して、私に頭を下げさせて、「こうして謝っているんだから、な?」と微笑んで、すぐに丸く収めてしまうかもしれない。
あーあ、という大きなため息の代わりにお腹が鳴った。身体は厄介だ。ヨイショ、と起き上がってゆらゆらと近所のスーパーを目指す。何でもいいからすぐに食べられるものを買ってこよう。そんな気はないけれど、自炊するにしてもこの部屋には包丁も鍋もない。それ以前に食器もない。
財布ひとつ持ってマンションを出ると、そこは三月の夕暮れ。もう一枚着てくればよかったと思うくらい肌寒かった。
知らないうちに眠りに落ちていたらしい。読まないつもりだったけど、やっぱり台本には目を通してしまった。まあ仕方ないか、と昼過ぎに目を覚ましたおチビちゃんは、昨晩買ってきた甘いだけの菓子パンを口に放り込んだ。
どんなに疲れていても、台本があれば読みたくなる。きっと職業病だ。やれやれと頭を軽く振って起き上がったのは派手に散乱したティッシュペーパーの上。床がほとんど見えないくらい覆い尽くされている。
部屋中大変な有様だが、別に驚くことはない。全部、自分の仕業だ。本当は皿を派手に割るつもりだった。何枚も何枚も割れば、少しは気持ちが晴れるだろうと思ったから。これまで一所懸命働いたので、割る為に皿を買うくらいの贅沢はできる。だけど後片付けの大変さを考えた末に予定変更。ティッシュペーパーを箱から滅茶苦茶に引っ張り出して撒き散らすことにした。本当に気が晴れたかどうかは分からない。だからまた後で、きっと同じことを繰り返すはず。おチビちゃんは足元のティッシュを摘み上げ、菓子パンでべとついた指先を乱暴に拭った。
それから数日、着替えもしなかったし、もちろん化粧もしなかった。誰と話すこともない時間を、初回の顔合わせの前日まで過ごすうち、心の中には今まで抱えたことのない気持ちが生まれていた。いや、元々あった「劇団をやめる決意」がスクスクと成長したのかもしれない。
どうにか言葉にするならば自暴自棄、もしくはヤケのやんぱち。好き勝手にやろう、それでやめさせられるならラッキーじゃん。そんなささくれ立った気持ちのまま、おチビちゃんは初回の顔合わせへ乗り込むことにした。
約二ヶ月後の昭和五十五年六月二日から同年十月十六日まで、四ヶ月半に渡って全国で公演される「ニッセイ名作劇場」の『むかしむかしゾウがきた』は、児童文学作家・長崎源之助原作の物語で今回が初演となる。招待学校数は約千三百校、招待児童数は約十七万人を予定している大きな舞台だ。
昔々、遠い国からやってきたゾウの九郎衛門と人間の交流を描いた物語で、おチビちゃんが演じる女の子「おミヨ」は、確かに先生が言っていたとおり、後半に重要な役割を担うメインキャスト。これも傍から見れば大きな「抜擢」に違いない。改めて考えるまでもなく、そこで自暴自棄になることの意味は限りなく重い。
いよいよスタッフ、演者が全員集まる重々しい雰囲気の中、初回の顔合わせが始まった。
いつもの稽古場にパイプ椅子の輪が幾重にも重なっている。その中心にいるのはもちろん浅利先生。さっき入口で会った時に、「おお、ゆっくりできたか?」と声をかけてくれた。先生はまだ、私の心の中の自暴自棄に気付いていない。
簡単な挨拶や話が終わり、いよいよ本読みがスタートした。今回、出番は後半に集中しているので、最初の台詞までに少し間がある。他の演者の声を聞きながら準備をしているうち、おチビちゃんは自分の中の違和感に気が付いた。

――どうしてみんな、こんなに不自然な声の出し方をしているんだろう?
まず大人の役の声が高すぎる。大人より子どもの声が高いのは分かってるはずなのに、なぜだろう? この調子だと「おミヨ」はもっと高い声じゃなきゃいけないじゃない。……まあ、もうやめるつもりだから別にいいんだけどさ。
最初の台詞は、おミヨがゾウに初めて会う場面。役者の意地で母親役より高い声を出してみせる――つもりだった。そう、気持ちは前向きだった。でも、やはり身体は厄介だ。自然と喉が締まってしまい、思う通りに声が出ない。想定外の事態だ。それでも頑張ると今度は涙声になってしまう!
いくら自暴自棄になっているとはいえ、さすがにおチビちゃんも焦った。通常、劇団四季において台詞への過度な感情移入は、「パセティック」と呼ばれ禁忌とされている。パセティック(pathetic)、は直訳すれば「哀れを誘うさま」だ。周りにいる誰ひとり何も言わなかったが、その空気は明らかに異様だった。
「あいつ、何やってんだ?」
「おいおい、あんなんじゃ絶対降ろされるぞ」
「こんなのボスが許すはずないだろう」
そんなムードが溢れる中、何とかおチビちゃんは泣きながら最後まで読み終えた。この部屋の誰もが、絶対に先生が途中で止めると思っていたはずだ。
「よし。少し休もうか」
静かな戸惑いが広がる中、一旦休憩に入る。人数分のクエスチョンマークが漂う稽古場を、おチビちゃんは足早に出ようとした。とにかく一度、ここを離れなくちゃ。でもその瞬間、背中越しに先生から声がかかった。
「ちょっと。社長室に来るように」
(第23回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『もうすぐ幕が開く』は毎月20日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






