 女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
やがて舞台からテレビへと活躍の場を移す彼女の七転び、否、八起きを辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑が Write Up。今を喘ぐ若者は勿論、昭和→ 平成→ 令和 を生き抜く「元」若者にも捧げる青春譚。
by 文学金魚編集部
その後、おチビちゃんが稽古の流れを止めることはなかった。何かが呑み込めたのかもしれないが、自分ではよく分からない。分かっていることは、ただひとつ。今、私はとても素晴らしいレッスンを受けている――! これは間違いないと思う。
日々、豊かな経験を持つ先輩たちと一緒に稽古をしていると、たとえ直接的なアドバイスがなかったとしても多くを学び取れる。充実した時間の中、ピックアップされたメンバーによる山荘での稽古は案外早く終わってしまった。
東京に帰ってからは、キャストが顔を揃えての「全体稽古」となるが、もうあの時のように先生から何度もダメを出されることはなかった。
劇中、おチビちゃん演じる見習い看護師、ケイ・サドラーとのシーンが多いのは雑役夫のジョン。そしてこの役を演じるのは年齢が近い、といってもそろそろ三十歳になる川原洋一郎さん。数年前にNHKの人気子ども番組『おかあさんといっしょ』で、「たいそうのおにいさん」をやっていた先輩だ。リードをしてくれる役ということもあり、もしかしたら彼の方が注意される回数は多かったかもしれない。
今回、浅利先生が演出面でこだわったのは「リアル」ということ。見せかけの芝居や、芝居めいた演技を削げば削ぐほど、劇としての面白さが出てくるという考えがあった。
「雰囲気で芝居をするな」
「どこかで見たような芝居をするな」
実際におチビちゃんもそういう教えを受けてきたし、もっと直接的な言葉を投げられたこともある。
「やるな」
きっと字をあてはめるなら「演るな」だと思う。そう、とってつけたような芝居ではつまらない。セリフだって、しっかり自分の身体を通さないとダメ。
そういう意味で今回の稽古は、ミュージカルよりストレート・プレイをやってみたいおチビちゃんの中に響いていた。
「そうそう、こういうことが知りたかったのよ」
こんな風に喉の奥で呟き、密かに頷く瞬間が何度もある。そしてある日、遂におチビちゃんは「この感覚、あれに似てるんだ」と思い当たった。
頭の中に浮かぶのは、高校三年の時に見学させてもらった「無名塾」のレッスン。自分の固定概念や価値観を揺さぶる、本当に凄い経験だった。あの時宮崎恭子さんから教わったのは「大切なのは容姿やテクニックではなく気持ち」ということ。それが今、また新たに自分の内側を揺さぶっている。
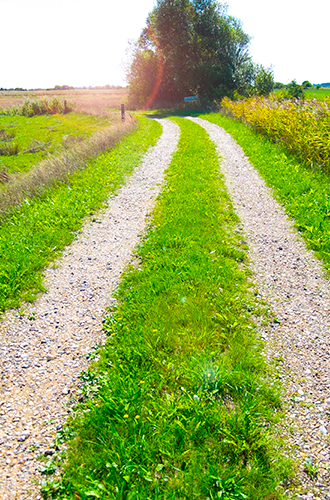
ふと想像してみた。もしあの日、宮崎さんが「あなたにはね、四季がいいと思う」と言ってくれなかったら、私は今頃どこにいたんだろう?
どこか他の劇団に入って、日々頑張っていたのかな?
それともまったく違う仕事をしていたのかしら?
当然考えてみても答えは出ない。ただ、こんなに充実した時間を過ごしてはいないだろうな、と自然に思えた。
通常、一緒に稽古をしている先輩からアドバイスを受けることは滅多にない。おチビちゃんが何度もダメを出された山荘での稽古の際、日下武史さんたちから色々と教えてもらえたのは珍しいことで、いかに自分が追い詰められていたかよく分かる。
ただあの時、何とか修正して乗り切ったおチビちゃんを「律儀なだけよ!」と評した影万理江さんは、時折「今のところ、よかったわよ」とか「さっきの場面なんだけどさ……」と声をかけてくれる。本当にありがたい。
劇団の看板女優として活躍しながら、映画やテレビの世界でもそのコケティッシュな魅力で人気を博していた影さんは、どことなくとっつきづらい大先輩。好き嫌いがはっきりしていて、群れたがらない孤高の人。いつでもどこでも女優然とした方だ。スタイリッシュな着こなしで好きな色はブルーとピンク。そんな影さんからは洋服をいただくことも多い。
話をするようになったのは一年ちょっと前。劇作家・山崎正和による、戦前の共産党員が主人公の戯曲『地底の鳥』のダメ取りを任されたのがきっかけだったと思う。彼女くらいしか女性のキャストがいないこともあり、ちょくちょく話しかけてくれたのだ。あの時、おチビちゃんは「すずめ」と呼ばれていた。その前にダメ取りをしていた、フランスの劇作家、シャン・アヌイの作品『ひばり』をもじって「すずめ」。
「すずめ、ちょっとコーヒー入れてくれない?」
そんな風に稽古の合間に頼まれることが多かった。そして読書家の影さんは本の話が大好き。
「すずめ、今どんな本読んでるの?」
「え、本ですか? いや、あの……」実はおチビちゃん、あまり本を読まない。
「何?」
「……すみません。何も読んでおりません」
「あら、ダメじゃないの。しょうがない。じゃあ今度持ってきてあげるからね」
そうやって本を貸してくれることもある。推理小説に始まり、ジャンルは多種多様。もちろんお借りしたからには心して拝読する。感想を聞かれるから、という事情もあるが、普段なら読まないような作品に触れるのはとても刺激的だ。

『この生命誰のもの』で彼女が演じるのは、女医のクレア・スコット博士。劇中に日下武史さん扮する主役の患者、ケン・ハリソンから「見事なバストをしていらっしゃる」とからかわれるシーンがあり、それがちょっとした話題にもなっていた。
ちなみに影さんは、浅利先生の元奥様でもある。離婚した後も一緒に働く気持ちは想像もつかないけれど、もう少し大人になったら分かるようになるのだろうか。でもその件に関しては、まだ付け足すことがある。浅利先生にとって影さんとの結婚は二回目。つまり当時バツイチだった訳だが、最初に別れた奥様はこれまた大先輩の藤野節子さんだ。
研究生時代に授業を受けていたおチビちゃんからすれば、藤野「さん」ではなく藤野「先生」。初めての大舞台だった『ふたりのロッテ』で共演もしている。歩いて行けるほど家が近所なので、稽古が早めに終わった時は藤野先生からパチンコに誘われ、そのままお宅にお邪魔することもある。
おチビちゃんが半分ほどの年齢ということもあり、その可愛がり方は我が子に接する時のようだ。そういえば「ベイビー」と呼ばれる時もある。影さんがお姉さんで、藤野先生はお母さん……なんて言っては失礼かもしれない。だって二人は七歳しか違わないんだから。
今回藤野先生が演じるのは、病棟婦長のシスター・アンダーソン。人の面倒をよく見たり、きちっとしているところが自分に似ているとインタビューで答えていた。先ほど話に出てきた「すずめ」……ではなく『ひばり』では、主役のジャンヌ・ダルクを演じて「文化庁芸術祭賞第33回優秀賞」と「紀伊國屋演劇賞 第13回個人賞」を受賞している。本当に凄い。藤野先生は劇団四季の看板女優というだけではなく、創設者の一人でもある。
不思議だなあ、とおチビちゃんは思う。浅利先生、そして二人の元奥様から様々なことを教わりながら、日々女優として成長していくなんて予想もしなかった。特に感じるのは、たまに藤野先生、影さんと三人で喫茶店に入ったり、ランチを食べたりしている時。二人きりでいる時とはまた違う雰囲気の中、「すずめ」でもあり「ベイビー」でもある新人女優は、不思議さと贅沢さを密かに噛み締めている。
稽古が進むにつれおチビちゃんは、自分が演じる見習い看護師の役割が、物語全体にどんな影響を及ぼすかが見えるようになってきた。
四肢の機能を失った主人公にとって、まだ未熟で若い彼女は「生きること」の象徴だ。観る側からすればその対比に感情を揺さぶられるし、彼女が自分の生命力に無自覚であればあるほど、その対比はより鮮やかになっていく。もちろん「芝居めいた演技」では「無自覚」を伝えられないので悩む。壁にぶつかる。考える。自分の役だけを仕上げてもうまくはいかない。だから難しい。
また、「尊厳死」というテーマゆえ、全体の雰囲気はシリアスになりがちだが、未熟で若い彼女が登場するシーンには緊張をほぐす和やかさも求められる。やはり難しい。
主人公役の日下さんは、「こういう芝居は絶対にアンサンブル・プレー(=群集劇、群像劇)でないとダメ」と語っている。誰かひとりが輝くようではいけない、と。
その言葉の意味は分かっている、はずだ。でも、だからうまくいくという訳ではないし、うまくやろうと意識し過ぎてもいけない。「やるな」という聞き慣れた浅利先生の声が身体の内側から聞こえてくる。
不安と期待が入り混じる中、とうとう昭和五十四年十二月五日・水曜日、東京・池袋のサンシャイン劇場にて舞台の初日がやってきた。
ただ、人生は難しい。なかなか物事は思い通りに運ばないものだ。本来なら全力を尽くせるよう、心穏やかにコンディションを整えているはずの本番前、おチビちゃんはメイクは途中、髪は結いかけ、しかもまだ私服のまま劇場内の喫茶店にいた。目の前には両親とおばあちゃん、そして妹のミナミと――浅利先生! こんな状況でどう振る舞えばいいのよ、と言いたくもなるが家族を呼んだのは自分だから仕方がない。

実は今回の公演、初演ということや、「尊厳死」というテーマの重さからなかなかチケットの売れ行きが伸び悩んでいた。四季の大ファンならいざ知らず、多くのお客さんは内容や評価が分からないのにチケットを買いはしない。そんな背景もあり、おチビちゃんも家族を呼んだのだが、まさか本番前に一緒に喫茶店で過ごすとは思いもしなかった。
「どうした、緊張してるのか?」
浅利先生から声をかけられても、「ええ、まあ」としか言葉が出てこない。いつもとは違う姿を家族に見せているという恥ずかしさもあるし、先生への申し訳なさもある。実は浅利先生、初日があまり好きではないのだ。もちろん挨拶などがあるから劇場には来るけれど、本番直前にどこかへ行ってしまったりする。聞けば観客の反応が怖いらしい。
「パパさん、心配いりません。大丈夫ですよ。ちゃんと頑張ってましたから。なあ?」
なあ、と言われても困る。答えようがないし、なにしろ照れ臭いから、口の中で小さく「はい」と呟いた。きっと今、私の顔は真っ赤だろう。
結局そんな感じで落ち着かないまま本番になってしまった。しかも初っ端から、山荘の稽古で浅利先生から何度もダメを出された問題のシーン。見せかけの芝居や、芝居めいた演技をうまく削げたかどうかは分からない。それが自分で分かってしまううちは、まだまだなのかもしれないし、今の時点で分からないのは致命的なことかもしれない。ただ余計なことを考えずにやれたと思う。これは確かだ。
その結果、受けた。ドッと笑いが起こった。第一幕のことだ。素直に嬉しかった。ちゃんと緊張をほぐせたという達成感もあるし、単純に「受けた」という気持ち良さもある。でもやはり芝居は奥が深い。第二幕に入る前、浅利先生からダメを出された。いや、ダメというほどではなかったかもしれない。
「おい、ちょっと」
「はい」
「まあ、受けてたけど、あれだぞ。な?」
言葉だけでは伝わらないが、先生の表情を見れば言いたいことは分かる。とにかく「気を引き締めろ」ということだ。正直なところ「お客さんが楽しんでくれたんだから……」と言いたい気持ちもあった。でも、そこは気持ちを切り替えなければいけない。はい、と答えた後おチビちゃんは、二、三度軽く頭を振って邪念を追い払った。
それが功を奏したのか評判は上々だった。
「良かったじゃない」
初日が終わった後に開かれたパーティー、「打ち上げ」ならぬ「打ち入り」でそう声をかけてくれたのは誰だっただろう。まさか浅利先生ではないだろうし、観劇した後そのまま出席していた自分の家族でもないと思う。まあ、そのことを覚えていないくらい力を出し切れたのだと考えれば、少しは安心できる。
でも気は抜けない。なぜなら明日は二日目。演劇の世界では、緊張感溢れる初日が終わり、ホッとした心の緩みから二日目は芝居が崩れると言われている。いわゆる「二日落ち」。そしてそんな日に限って、いや、そんな日だからこそ評論家や新聞記者の連中が観に来ているという。
もちろん、おチビちゃんにとって評論の対象となる芝居に出るのは初めて。変に緊張することはなく、「ああ大人向けの作品なんだなあ」と改めて実感出来た。その心持ちがよかったのか、複数の新聞に掲載された論評はおおむね好意的な内容だった。名指しで「好演している」と評されて、嬉しくない女優はいないはずだ。
ただ某新聞社だけは少々手厳しく、おチビちゃんを「子どもっぽすぎる」と評していた。その新聞を持ってきたのは浅利先生。ある日、楽屋に入って来るなりゴロンと大の字に寝転んだ。
「なんだか変な文章書いてるヤツがいるんだよ。本当、何も分かっちゃいない」
どうしたんですか、と訊く間もなくその「子どもっぽすぎる」という論評を読んでくれた。たしかに悔しいような気もするが、「まったくどこ見てるんだよなあ」と寝そべったまま呟く先生の姿を見ていると、どこか愉快な気持ちも混ざってくる。何も言わないおチビちゃんが物足りなかったのか、先生はまた「どこ見てるんだよなあ」と繰り返した。
(第18回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『もうすぐ幕が開く』は毎月20日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






