 ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
by 小原眞紀子
7(前編)
二百万円の包みを畳の上に置いたとき、舅と姑の顔色は一瞬、青ざめたように見えた。
「瑠璃さんの知り合いだったんかね」
「はい。大学の後輩で青山での講義を聴きに来ていて、精神的に不安定になったとか。警察に告げても構わない、と言っています」
「構わないっちゃ、どういうことだ」
舅は落ち着かなげに訊いた。姑は封筒を見つめて、じっと考え込んでいる。
さあ、と瑠璃は言葉を濁した。「反省しているのだろうと」
「自分にも何か言い分がある、ってことじゃないんか。出るとこ出ても、いいってことは」
「瑠璃さんの知り合いかね。亮介の、じゃなくて」
姑が唐突に口を挟んだ。瑠璃はそのときやっと、舅姑の心配のありかを悟った。
違います、と瑠璃はきっぱり言った。「亮介さんとは一面識もありません」
「だったら、なんでここに。関係なかろうが」舅は初めて語気を荒げた。
「ええ。青山にあるお家にパーティルームを作ろうと計画していて、それがうまくいかないようです。予算のことやなんかで、ご主人とも揉めているらしくて」
瑠璃は嘘を言った。防犯ビデオに映っていたのが女だったので、亮介のトラブルではないかと、舅姑はずっと気に病んでいたのだろう。良心の呵責は感じたが、鮎瀬という昔の同級生との仲を誤解されたのだ、とは言えなかった。
「予算で揉めてるって? それでこんな余計な出費をするって、わからんな」
舅は首を傾げ、どうにも腑に落ちない様子だった。
「当てつけだろ」と、姑が言った。「欲しいもんがあるのに、思うとおり金を出してくれん亭主への。騒ぎになれば、結局こうやって弁償しなきゃならん、て」
「子供っぽいこっちゃな」と舅が呆れて呟いた。「今日びの若い奥さんってのは」
内容は違うものの、栞が子供っぽいというのは瑠璃も同感だった。
「瑠璃さんも華やかにやってるように見えるんだろうし」
姑の方は納得した様子だった。「逆恨みされたんだろ。仕方ないね。人前に出て仕事をしていれば、付き物だね」
「そうだな。ご主人とうまくいってないとすると、うちの店を襲うというのも」と、舅も頷く。
「あたしらや亮介に、瑠璃さんが叱られよう。そう仕向けたいと、思ったんだろ」
だから瑠璃を責めまい、と言いたげな姑の優しさに、瑠璃は居たたまれなかった。
「警察には、どうします?」
「わしらのお客さんだった、って言っておこう」

舅は封筒を手に取り、帯封のついた札束を確認しつつ、「いや、お客さんの家族かね。なん、贋物つかまされたと勘違いして揉めたけど、毀した分はこうしてお買い上げいただいた、とでも」
そんな騒ぎの噂は店の評判にも響く。傍目にはわかりにくい骨董取引のことだ。解決した、と言えば、警察も事情聴取ぐらいで矛を収めるだろう。
警察。警察は厄介事を増やすだけだ。とりわけ何とも説明に窮する出来事に関しては。
それとも。瑠璃は考えた。
警察ならわかるだろうか。病院でもはっきりしない、ここ二日ばかりの瑠璃の体調不良、あのときの記憶が欠落している原因が。
意識が戻ったのは、タクシーに乗ったときだった。窓越しに瓜崎が立っているのが見えた。あまりの気分の悪さに、挨拶もおぼつかない。タクシーが発車すると、胸がむかついた。いったいなぜだ。瑠璃は、店で口にしたものを思い出そうとした。
「お客さん、大丈夫ですか」
返事の代わりに目を開いた。そんな声をかけられるのは心外だった。酔っぱらってなどいない。後部座席を汚す心配など無用だ、と毅然とした態度で示したつもりだった。
実際、飲んでいないのだ。最初のビール。ワイングラスに二杯ばかり。決して酒に強くはないが、あのぐらいで酔っぱらったことなどない。
妙なことに視野が縁の方から少しずつ狭く、暗くなっていった。きーん、とも、しーん、ともつかない耳鳴りがして、頭頂から下へ血の気が引いてゆく。やはりアルコールの作用か。が、そんな感覚は初めてだった。
ダッシュボードの時計を見た。十一時八分。洗面所に立ったのが確か十時半で、足元がふらついてなどいなかった。鏡の中の顔だって普通で、口紅を直しただけだ。席に戻ったところまで覚えている。瓜崎はカードで勘定を済ませていた。
そこから突然、記憶が途切れていた。倒れたのだろうか。だが記憶がないのは約三十分。店を出て、タクシーに乗せられるまで、そんなに時間がかかるとは思えない。その間、自分はどこで何をしていたか、あるいは何をされていたのか。

そもそも瓜崎はなぜ、あの店に連れていったのか。
タクシーの中で、瑠璃は正気を保つために考えていた。洒落たレストランなどではなく、わがままの言える勝手知ったる店。その選択を気が利いている、とすら思ったのだが、前もって予約した席に近づき、準備されたグラスに何か塗ることだってできたろう。
馬鹿な、と瑠璃は思った。妄想だ。
だが、いつの間にかバッグから携帯電話を出し、握りしめていた。
自分も心臓マヒで死ぬのだろうか。そうなったら瓜崎だって、ただでは済まない。今回は大勢が集まるパーティではなかった。瑠璃と食事していたのは、瓜崎ただ一人なのだ。
さっきの窓ガラス越しの瓜崎の表情。運転手にタクシー券を渡し、座席に押し込んだ瑠璃を一瞥した。掘った穴に何か捨てるような冷たい眼差し。思い過ごしか。それとも洗面所に立つ前に、瑠璃が言ったことのせいだろうか。
仕方がない。ああ言わずにはいられなかった。最初から、それを問いただすために来たのでもあった。
「黒岸くんは、よく君のことを言っていたよ。自分のことを比目子って言い出したのは、君だって」
「あたしが?」
「そう」
瑠璃には、そんな覚えはなかった。姫子という可愛らしい名が、皆で集まるときのリストなどに、比目子、と書かれるようになったのは、いつの間にかだった。それが本名だと思っている者もいた。
「あたしじゃないわ。姫子は嫌がってたの?」
ものすごく、と瓜崎は答えた。「恨んでいた。君のことを」
まさか、と瑠璃は呟いた。
「だから銀座で偶然、再会したっていうのもね。彼女、君に会いに行ったんじゃないかな。君、日本に戻ったのは最近なんだろ」
「最近ってほどでもないけど」瑠璃は思わず、考え込んでいた。
銀座の展示会の予定はネットで広報されるから、あの辺りに瑠璃がいることは予想がつかないことはない。
「何か嫌なこと、言われなかったかい? 黒岸くんが、君に嫌がらせしに行ったんだとしたら」
「ないわよ。そんなこと」
瓜崎は顔を覗き込み、はねつけるように瑠璃は言った。
姫子がしたことといえば、展示会に同級生を呼び、直後の同窓会に瑠璃が出席せざるを得なくしたことだ。それが嫌がらせと言えるなら、何よりも最大の迷惑は、ホールで姫子が死んだことだった。
「そうか」瓜崎は肩の力を抜き、背もたれに寄りかかった。
「もし君が黒岸くんから何かされたなら、高梨が言うのとも整合すると思ったんだけどね」
罠だ、と瑠璃は思った。保護者めいた教師面。しかも高梨まで利用して。
昔から、こんな男だったではないか。何も変わってない。それを年月とともにすっかり忘れ、仲よく温い雰囲気に浸っていたとは。
「二十年間、あたしを恨んでいたっていうのは、姫子なの? あなたじゃなくて?」
自分は猿なみに愚かしい、と瑠璃は自ら恥じた。こんな猿と差し向かいで食事しているなんて。
瓜崎は眉を上げ、心外そうに瑠璃を見た。
「僕が? どうして」
瑠璃は肩をすくめた。「あたしがあなたを振ったから」と、あけすけに言ってやる。米国風といえば言えたが、むしろ猿に対する、わかりやすい対処だ。
「へえ」瓜崎もまた大仰な声を上げる。米国風のジョークのやりとり。その目の奥には、嫌悪と敵意が閃いている。
「振られたんだっけ? それは残念だ、もう望みはないかな」
瓜崎は笑っていた。が、いきなり手を伸ばしてきて、瑠璃はテーブル越しに身を引いた。何か取ろうとしたのか、瓜崎の手は宙で一瞬迷い、戻って自身のグラスを握った。瑠璃の言葉を押し込めようとしたかのようにも見えた。
「ない、って言ったはずよ」
「そのときに?」
瓜崎は目を見開くと、心底驚いてみせる。
なんて厚かましい、と瑠璃は思ったものの、何か引っかかった。
「そうよ。映画に誘おうと思ったって言ってたわね。だけど、わたしが鮎瀬くんと先に行ったんじゃないかって」
鮎瀬という名を聞いても、瓜崎の表情に変化はなかった。二、三日前の計算間違いでも指摘されたかのように首を傾げている。
「よく覚えてないけど。僕は別に君を恨んでなんかいない。だってさ、僕は今、そんな立場じゃないだろ」
瑠璃はつい吹き出した。「どんな立場?」
瓜崎は黙ったまま、微かに頭を振る。地位も名誉も、妻も子もいる。答えるまでもないらしい。
「自分に満足してるのね」

そうだった。瓜崎は昔から、いつも自分に満足していた。それは非難できない。そう、瓜崎は正しいのだ。いつだって瓜崎だけが正しい。
「見たい映画があれば、誰か誘うぐらい、まあ普通にするだろうね」
些細な他人事のように、彼は呟く。
すり替えだ。普通どころか、当時の彼にとっての最重要事で、こっちは騒ぎに巻き込まれたのだ。少なくとも瓜崎は、あの映画が見たかったのではないはずだった。
「君はほら、落第するんじゃないかって、自分でも気を揉んでたろ。当時、女の子で留年なんて、洒落にならなかったし」
落第、という言葉を、瓜崎は必要以上に強調した。
「コンピューター演習と、化学実験は、ね」
一語ずつ区切りながら、瑠璃は応えた。「苦手だったって、覚えていてくれたのね。何かと心配してもらったわね」
両手を顔の前で組み、瓜崎は何度かゆっくりと、また例の保護者めいた頷き方をする。
「で、今は? 姫子とあたしの仲違いを心配してくれてたの?」
「いや。高梨がさ、あんまり君のことを」
「あなた、駅のホームで抱きついてきたわよね」
瑠璃は遮って言った。「あのときは、わたしが飛び込み自殺でもすると心配したわけ? 発情期のオスのカエルがメスに飛びつくみたいだったけど」
顔の前で手を組んだまま、瓜崎は頷くのをやめ、テーブルの一点を見つめている。
「白昼堂々の性犯罪ってやつよね。皆には黙っててあげたけど」
瑠璃はにっこりした。ほぼ営業用と決めている微笑みだ。我ながら、何という下品な物言いか。アルコールの力まで借りて。
「やあ、参るね」
瓜崎は掌で首筋を伸ばすようにし、息を吐いた。
呆れ果てたように、余裕を失うまいと苦笑いを浮かべる。その態度の方が、瑠璃の言葉よりよほど下劣に思えた。
「うん。君なら黒岸くんともやりあえるな。彼女もほんと、気は強かったからね」
「姫子から、わたしへの恨み言を聞いたってのは、いつなの?」
腸が煮えくり返りそうになりつつ、瑠璃は言ってやった。
「かなり親しかったみたいね。ベッドの中? 史朗って男の子、あなたの子だって噂よ。わたしの評判なんか、心配してる暇があるのかしら」
だいたい学生時代、瑠璃を売春婦呼ばわりしたのは、こいつではないか。今さら保護者面して、何の気遣いだ。
「君。ちょっと飲み過ぎじゃないか」
自分を保つためか、周囲に聞かせるためか、瓜崎はよく通る声で言った。
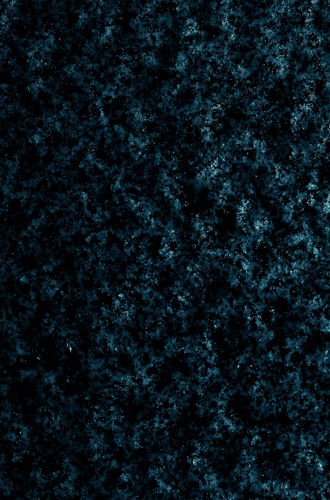
瑠璃は腹を立てるのをやめ、処置なし、という漫画めいた仕草で掌を上に、肩をすくめた。
瓜崎は、もはや酔った女を相手にしてない、という素振りをしたがっていた。だが動揺は隠しきれない。
「ねえ。本当にあなたの子なの? 史朗くんってさ」
周囲のテーブルから、数人の視線を感じた。
「一つ訊こうか。今日、君はどうして来たんだ?」
「来い、って言うからよ」
「そうじゃないだろ」
瓜崎は、初めて露骨な苛立ちをみせた。
「僕は、久しぶりに話したかった、と言っただけだ。社交辞令だよ。大人なんだから、わかるだろ。ただ強いて言うなら、高梨が言っていたのが気になってた。それだって僕にはどうでもいいことだが、君にとってはどうかと思ってね」
苦し紛れであっても、君のため、を崩さない。が、瑠璃の痛いところを突きはした。
「で、君は? そんなことを言うために、わざわざ来たのか? そんなくだらない、あり得ない噂なんか、僕に聞かせるために」
「鮎瀬くんと、何を話したの?」
瑠璃はそう訊いていた。「上高地のホテルで。彼、本当はいったい、何を話しに来たの?」
酒を飲むほどに青ざめるのか。瓜崎の、眉を上げて惚けた顔は、あるいは照明の加減でなのか生白くみえた。

(第13回 第07章 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『本格的な女たち』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■





