 人と人は、文化と文化は、言語と言語は交わり合いながら、新しいうねりを作り出してゆく。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもある、ラモーナ・ツァラヌさんによる連載短編小説!
人と人は、文化と文化は、言語と言語は交わり合いながら、新しいうねりを作り出してゆく。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもある、ラモーナ・ツァラヌさんによる連載短編小説!
by 文学金魚
シーラの家に新原から花が届き始めた。小さな鉢に植えられたカンパニュラの花に付いていたカードに、「昨日はありがとう」という新原のメッセージが添えてあった。会ってたわいもない話をしただけなのに、なにを感謝されているのかわからなかったが、プレゼントのお礼を言うためにシーラは新原に電話した。
翌日も「この花、かわいいでしょう」というカード付きの鉢が届いた。壁掛けのプランターにぴったりのニチニチソウだった。その翌日も「温室にアジサイあったかな? 見つけたのでお送りします」とまた花が届いた。切り花もあったが、ほぼ毎日新原からお花が届くようになった。

思いがけない展開だった。もちろんシーラは新原の好意に気づいていた。花のお礼を言うために電話やメールをしているうちに、気がつくと彼と毎日話していた。シーラと新原は恋人同士になった。仕事で忙しい彼を気づかって連絡しないでいると、決まって彼の方から連絡があった。
ただ親しくなるにつれ、新原とぶつかることも多くなった。地球の自然を復旧してから火星への旅の研究をいくらでもやればいいじゃないとシーラは言い、新原は自分の仕事は宇宙船を作ることで、火星植民化プロジェクトの原因を取り除くことではないと主張した。
言い争っても二人の話は噛み合わなかった。激しく口論した翌日、今日はさすがにお花は届かないだろうとシーラは思った。ちょっと寂しく、自分の毒舌が恨めしかった。しかし新原はちゃんと花を届けてくれた。ただしパッケージから出すと鉢植えのサボテンだった。メッセージカードは添えられていなかったが、もちろん新原の意図はわかった。
「わたしって、棘があるってこと?」
電話でそう言うと、「そうだね」と新原は笑った。
「でもサボテンって、針があって尖ってるけど、どんなに厳しい環境でも生きられるだろ。しかも花はめちゃくちゃきれいなんだ。だから僕はサボテン、好きだよ」
「サボテン好きの彼で、わたし、ラッキーってことかしら」シーラも笑った。
サボテンは環境に強い植物なので、シーラはいつも見える自分の部屋の窓際に置いて育てることにした。

火星移住プロジェクトに対する不満を、新原にぶつけても仕方がないことはわかっていた。シーラは時々、どうしようもない鬱屈を彼にぶつけたくなるのだった。新原は我慢強かった。言い争いになっても、結局はシーラを受け入れてくれた。
ただ新原は根っからの研究者だった。環境問題の解決は自分の仕事ではないと言ったが、シーラの常日頃の言葉を聞き流していたわけではなかった。
「シーラ、頼みがあるんだけど」
「なに?」
いつもと違う電話の声の調子に、シーラは驚いて答えた。
「知り合いの研究者の力を借りて、黒川先生のアシスタントを見つけることができたんだ。黒川美佐子、黒川先生の奥さんだった人だね。でも連絡してみたら、僕とは話したくないんだって。科学者とは話したくないらしいんだ。だからちょっと力を貸してくれないかな」
「わたしなら、話してくれるのかしら」
「もしかしたら、話してくれるかもしれない。僕は、黒川先生の研究について知りたいんだ」
「黒川先生が信頼していたアシスタントで、その上奥さんでしょ。ちゃんとした理由がないと、研究の詳細は教えてくれないと思うわ。まず、あなたが黒川先生の研究を知りたい理由を教えて」
「決まってるだろ。先生の研究成果をもとに自然環境を復旧させられるなら、それを検討しようと思っている」
「ええっ、そうなの? でも何をやるにしても、お金と政府の支援が必要よ。黒川夫人を期待させておいて、何もできなかったら、彼女に申し訳ないわ。また辛い思いをさせるだけになっちゃう」
「だけど何かアクションを起こす前に、黒川先生の研究が、使えるかどうか確認しなくちゃならないだろ。まずはそこからなんだ。研究の詳細がわからないとどうしようもない。だからシーラに協力してほしいんだ。彼女を説得してもらえないかな」
「わかったわ。ちょっと時間をちょうだい。なにかいい方法を考えるから」
新原には前向きな返事をして電話を切ったが、シーラにとっておきの秘策があるわけではなかった。黒川裕先生は生涯をかけた研究が科学の世界で批判され、失意のうちに亡くなった。同じ科学者だが新原は、黒川先生の研究と対立する火星移住のための研究を行っていた。そんな新原に、黒川夫人は研究の詳細を教えてくれるだろうか。しかも黒川先生が亡くなってから、七年も経っていた。
シーラは心細くなった。科学者には会いたくないと言っている黒川夫人を、どうやって説得したらいいのだろう・・・。
壁に貼った空の写真を見つめながらシーラは考えた。「そうだ空だ、この空を送ろう」シーラはそう呟くと、パソコンを開いた。じっくり言葉を選びながら、黒川夫人宛の長い手紙を書いた。地球を青い星に戻せる希望を与えてくれた黒川先生の研究を、是非一度見せていただきたい。そう書き綴った。文字だけでは足りないと思ったので、自分の空の写真のコレクションから、一枚選んで手紙に同封して黒川夫人に送った。
一週間たっても黒川夫人からは返信がなかった。シーラはまた手紙を書いた。内容は最初の手紙と大同小異だったが、違う写真を同封することにした。半透明の葉っぱの間から木漏れ日が差している写真だった。この世界に生まれてくる子どもたちに木漏れ日とは何かを知ってほしい、木漏れ日の思い出を持ってほしい、そのためには自然環境をもとの姿に戻さなければならないので、黒川先生の研究を見せていただきたいと書き添えた。
やはり黒川夫人からの返信はなかった。「ダメなのかな」シーラは弱気になった。しかしあきらめきれなかった。新原は優秀な科学者だった。黒川先生の研究が再検討されるチャンスがあるのに、その実態を知ることができないのは理不尽だと思った。
シーラはもう一度だけ手紙を書いてみることにした。今回は一番大切にしているウスユキソウの写真を同封することにした。ウスユキソウは、三十年前に絶滅してしまった花だった。暑さに弱い花で、高山でも気温四〇℃以上が観測されるようになった時期に、あっさり絶滅してしまった。シーラにとってウスユキソウは、その後次々と絶滅したすべての花を象徴する存在だった。黒川先生の研究を知った時、シーラはウスユキソウのような花を取り戻すことができるかもしれないと希望を持った。そんな思いを込めて、黒川夫人宛に三通目の手紙を送った。

半ばあきらめかけていたシーラの元に、黒川夫人から手紙が届いた。手紙と一緒にウスユキソウの写真も入っていた。写真の日付を見ると、なんと去年の写真だった。
「ウスユキソウをこの間見かけました。高山の岩の間に元気に生えていました。登山がいやでなければ、一度一緒に探しに行きませんか? 都合がよろしければ、今度の土曜日においでください。お友達もご一緒にどうぞ。お昼ごろお待ちしております」
手紙にはそう書いてあった。黒川夫人が返信を書いてくれたことに驚き喜んだが、それと同じくらい、ウスユキソウがまだ絶滅していないことが嬉しかった。すぐに新原に黒川夫人の手紙の内容を伝えると、「ありがとう。よかった、行くよ、土曜日の午前中、予定が入ってるけど、そんなのキャンセルして行く」と弾んだ声で言った。
土曜日、シーラは新原と一緒に黒川夫人の家に向かった。黒川邸は首都圏から北の方、車で二時間くらいで行ける小さな街の郊外にあった。新原は自動運転に設定して、ずっと液晶画面に映し出されるニュースを見ていた。黒川美佐子に会うことになって緊張しているせいか、いつもより口数が少なかった。
シーラはしばらく窓の外を眺めていた。街を出ると視界が開け、空が人工雲に覆われているのがよく見えた。閉じこめられているようで息が詰まりそうだった。昔は森や田んぼがあった地域も、今は何も生えていない荒れ地が続いていた。郊外には古びた空き家が多く、ほとんどだれも住んでいなかった。人々は都会か、まだ少しだけ緑が残っている山のほうに暮らしていた。
外の景色を見るのが嫌になり、シーラは黒川夫人が送ってくれたウスユキソウの写真を眺めた。どこかにこの花がまだ咲いていると思うだけで、わずかだが希望が湧いてくるようだった。
黒川邸に着いたのは正午だった。山に囲まれた小さな街のはずれにある二階建ての家は、外見はごく普通の家だった。ベルを鳴らすと中で犬の吠える声が聞こえた。
「あら、いらっしゃい」
ドアを開けて老婦人が暖かい笑顔で迎えてくれた。黒川夫人だった。
「こんにちは。お邪魔します」
二人が言うのと同時に家の中から犬が飛び出て、彼らの足の間を走り回った。
「ポリー、おとなしくしてね」黒川夫人は犬を叱り、「ポリーは来客に喜んでいるんです。どうぞ中へお入りください」と二人を招き入れた。
家の中は焼きたてのお菓子のいい匂いに包まれていた。明るく暖かい家だった。リビングルームの絨毯のあちこちに、ぬいぐるみや小さな三輪車が転がっていた。

「昨日まで孫たちが遊びに来ていて、まだ片付けていないんです。どうぞソファにおかけください」
「お孫さんがいらっしゃるのですね」新原が言った。
「息子の子どもたちは山のほうに住んでいるんですけど、たまに遊びに来てくれます」
シーラと新原は目を合わせた。世間と絶縁した気難しい女性だと思っていたが、実際にお会いした黒川夫人は生き生きとして明るい人だった。黒川夫人がお茶を出してくれると、二人は名刺を差し出して自己紹介した。
「宇宙船開発プロジェクトの方と環境活動家の方ですね。二人はどこで出会ったの?」
黒川夫人は交互にシーラと新原を見た。その目には、ごく普通の女性が見せるような好奇心が浮かんでいた。普段なら構えてしまうことも多いのだが、シーラはよりリラックスすることができた。少しユーモアを交えながら、二人がどうやって出会い、なぜ黒川夫人に会いたいと思うようになったのかをかいつまんで話した。
「シーラさんは、講演でよく黒川の研究に言及されているそうですね。黒川も喜んでいると思います。でもあれは未完成の研究ですよ。実験を続けなければ、ただの理論に過ぎませんからね」
「研究資料を見せていただけませんか。正直に言うと、資料を見たからといって、すぐに何かできるわけではありません。だけど地球の自然を失いたくない人間の一人として、少しでも自然環境を復旧できる可能性があるのなら、その方法を検討したいのです」
新原の言葉を聞いてシーラは驚いた。シーラが思っていたよりずっと、彼は環境問題に興味を持っているようだった。
「どうぞこちらへ」
夫人は立ち上がると、二人を家の奥にある黒川先生の書斎に案内した。壁の三面は本棚で、資料や本で埋まっていた。ワークデスクの上に、今では旧型になってしまったパソコンが載っていた。ただ部屋はきちんと整理されていて、黒川先生が今にも仕事をしに来るような雰囲気だった。黒川夫人はデスクの引き出しから厚いファイルを取り出すと、パソコンを立ち上げた。
「理論のレジュメは資料にまとめてあります。実験結果などはパソコンのデータを見てください。膨大な量だと思いますが、黒川はデータ管理にはうるさい人でしたから、きちんと分類されていると思いますよ」
「先生は、いつ頃この研究を始めたんですか?」新原はファイルのページをめくった。
「二十年ぐらい前になりますかね。人工雲が使われ始めてからすぐです。あの人は、人工雲がどうしても嫌でしてね。空を人工雲で覆うより、もっといい方法があるはずだとずっと言っていました」
「黒川研究室の、研究員の方たちのことなんですが」新原がためらいがちに聞いた。
「調べさせてもらったんですが、今でも研究者として活動しておられる方が三人いらっしゃいます。アメリカ、ロシア、中国でバラバラに研究活動をしておられるようです。少し気になったのは、なぜ彼らが黒川先生の研究を続けなかったのか、ということなんです。まだ全部拝見したわけではないですが、理論としてはとても面白い。有望だと思います。実験を続ける価値があったと思うんです」
「それは、難しい質問ですね」黒川夫人が複雑な表情を浮かべた。
「大規模プロジェクトはとんでもないお金がかかるでしょう。必ずしも理論的な正しさが優先されるわけではないのです。産業界との癒着に近いような関係や、政府とのコネクションといった、政治力がものをいうことも多いのです。黒川の研究は政府から否定されていましたから、彼も研究員たちも、突然資金が断たれて研究を続けられなくなることだってあり得ると、どこかで覚悟していたと思いますよ。こんなこと、新原さんはご存じだとは思いますが」
「いや僕は・・・」と新原は口ごもった。新原はずっと国家研究機関で仕事をしてきたので、個人資金提供者を募って研究を続けなければならない研究者たちの苦労を知らなかった。
「あ、どうぞゆっくりデータをご覧ください。わたしは隣の部屋にいますから」
シーラは新原と並んでファイルに目を通した。専門用語だらけだったが、シーラにも内容はなんとか理解できた。ただ最も重要な実験データはパソコンに保存されていた。新原はグラフや方程式のファイルを次々に開いていった。最初はシーラに内容を説明してくれたが、じょじょに言葉が少なくなっていった。新原がものすごく集中し始めたのがわかった。

シーラはそっと黒川先生の書斎を抜け出すと、隣の部屋に行った。黒川夫人はソファにゆったり座って本を読んでいた。シーラを見ると「あら、もう終わったの?」と聞いた。
「いえ、わたしには専門的過ぎるので、彼にまかせることにしました」
「そうよね」ふわりと黒川夫人が微笑んだ。
「あの、ウスユキソウの写真、ありがとうございます」
「ああ、そうだったわね。あなたもウスユキソウ、お好きなのね。本当に咲いてるのよ。よかったら、一緒に見に行きませんか? ちょっと前までポリーを連れて登山してたんだけど、年なんだから、一人で行くのはやめてって子どもに言われてしまって。一緒に行く仲間を探してるんですよ」
「ぜひ連れて行ってください!」
「四季が狂ってしまったから、開花時期を予想するのが難しいけど、去年見つけたのは三月でした。山頂まで行かないと見られないかもしれないけど、大丈夫かしら?」
「大丈夫です。あ、その時までに少し身体を鍛えておきますね。新原もいっしょにいいですか?」
「もちろんよ」
黒川夫人は、手紙に同封したのとは別のウスユキソウの写真を見せてくれた。可憐な花だった。人工雲に覆われた空の下でも、山登りが大変でも、この目でウスユキソウの花を見たいと思った。
もう夕方だった。シーラが黒川先生の書斎に戻ると、新原は真剣な表情でパソコンの画面を見つめたままだった。キーボードの音だけが、カチャカチャと響いた。
「ねぇ、もうおいとましないと」
「あ、うん、そうだね」
そう言ったが新原は画面から目を離さなかった。次々にファイルを開き、閉じた。シーラがもう一度声をかけるタイミングを見計らっていると、「じゃ、帰ろうか」とようやく腰を上げた。黒川夫人にお礼を言い、紙のバインダー資料だけお借りして外に出ると、すっかり夜になっていた。
自動運転にできるのに、新原は自分で車を運転した。「黒川先生の研究のこと、何かわかった?」とシーラが聞いても、「ああ、これからもっと調べるよ。デジタルデータも、夫人からお借りしなくちゃ」と言うだけだった。
ちらりと新原の横顔を見たが、考えごとに集中している時の表情だった。シーラはそっとしておくことにした。彼の集中力の高さはもう知っていた。話さないのは、話す内容がまとまっていないからだった。シーラは新原が自分から話し出すのを待つことにした。
突然だった。
シーラはテレビで新原が宇宙船開発プロジェクトマネージャーを辞任したというニュースを見て、仰天した。人類の存亡を賭けたプロジェクトなので、どの局もトップニュースで扱っていた。すぐに電話をかけたが新原は出ない。テレビのニュース番組が終わると、シーラはネットで情報を集めた。新原は個人研究に力を注ぐために、宇宙船開発プロジェクトの総合監修をサブリーダーの篠山龍に任せたのだった。すでにネットにアップされていた記者会見の動画もチェックした。新原から電話がかかってきた時には、もう夜になっていた。
「なんでこんなに大事なこと、教えてくれないのよ」
「ごめんごめん、いろんなことが、急に決まっちゃったんだ。辞任も今のタイミングじゃなきゃ、ダメだったんだよ」
「なんで急に辞めたの?」
「黒川先生の研究のためさ。先生の研究には、なんの欠陥もないよ。少なくとも僕が調べた限りじゃね」
「じゃあなんで・・・」
「政治的圧力だよ。黒川先生の研究より、宇宙船開発の方が儲かるんだね。だから欠陥とも言えないような不備をあげつらわれて、先生の研究は中止になっちゃったんだ」
「そんなこと、あるの?」
「あるんだよ。しかも、黒川先生の研究を中止に追い込んだのは、僕の上司さ」
「まさか!」
「いや、本当だ。裏も取った。僕は人類に残った唯一の希望は火星移住だと信じて、十年間も宇宙船開発に全力を注いで来たわけだ。まったくバカだよな。でもそんなことはどうでもいい。僕は黒川先生の研究を続けようと思う。先生の弟子たちにも連絡して、いくつかの条件が揃えば協力してくれるという約束ももらった。仲のいい研究者たちも何人かサポートしてくれるし、美佐子さんに全データを利用する許可ももらった。後はスポンサーを見つけて実行に移すだけだね」
「すごい」と呟いたが、「でも本当に、そんなこと、できるの?」という言葉は飲み込んだ。
「シーラにも力を貸してほしい。スポンサー集めのためにも、世間に向けて研究の意義を発信しなきゃならない。シーラは黒川先生の研究について詳しいだろ。広報やプレスリリースの作成を頼みたいんだけど」弾んだ声で新原は続けた。
「もちろん手伝うわ、全力で」
「ありがとう。まだバタバタしてるけど、今の仕事の引き継ぎが終わったら、すぐに連絡するよ」
電話を切ってもシーラの心臓は高鳴ったままだった。しかしシーラが一縷の望みをかけた黒川先生の研究は正しく、それを新原が実現しようとしているのだった。
窓の外は夕暮れで、空から人工雲が一つ一つ降りて来るのが見えた。下降中に羽をたたんでどんどん小さくなる人工雲は、粒の大きい不気味な雨滴のように見えた。人工雲のない空に、星が輝きはじめた。新原たちの研究がうまくいけば、空は二度と人工雲に覆われることはない。
シーラは窓際に置いた小さなサボテンを見た。新原はシーラのことを、サボテンのように棘があるとからかったが、本当に棘があり、社会と闘ってきれいな花を咲かせられるのは、新原ではないかとシーラは思った。
新原の行動力はシーラの予想をはるかに超えていた。
二ヶ月も経たないうちに、記者会見で「HOPE」プロジェクトのチームメンバーを発表した。カリフォルニア大学のキャサリン・ウォーウィック氏、モスクワ大学のイリア・アレクセイエヴィッチ氏、そして上海国家工学院の楊宇晶氏という、旧黒川研究室のメンバーたちが集まった。総合アドバイザーは黒川夫人で研究者の黒川美佐子が就任した。広報はもちろん環境活動家のシーラ・ブライトンが務めることになった。新原の宇宙船開発プロジェクト時代の同僚五人も参加することになった。
それと同時に新原は世界を駆け回り、黒川理論とその現実的効果をスポンサーの前でプレゼンし続けた。研究に最も興味を示し、巨額の資金を提供してくれたのは、持続可能技術の開発を支援していたヨーロッパの個人基金だった。
実験は順調に進んでいった。後は小さな問題を解決し、理論を実践応用するだけだった。政府を含め社会から驚きの声があがったが、新原は落ち着いたものだった。「これからだよ」と言っていた。量子を使って一時期的に地球の放射が宇宙に抜けるための穴を大気圏に開ける。うまく行けば地球の温度が正常化し、人工雲を飛ばす必要がなくなるわけだが、「HOPE」プロジェクトを実施するには特許登録や国連の許可など、様々な手続きが必要だった。新原は開発をメンバーに任せて、法的な手続きに専念するようになった。
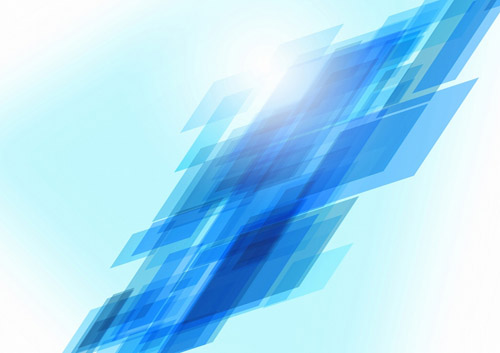
黒川裕の研究は正しかったと世間で認められた時、七年前になぜ否定されたのかを調査し始めたジャーナリストがいた。大きなスキャンダルが起こった。黒川の研究データの改ざんが明らかになり、政府側で火星植民化プロジェクトを推進していた議員が逮捕された。新原の元上司で恩師でもある研究者にも捜査の手が伸びた。「今さらこんなことを蒸し返しても」と新原は不機嫌だったが、裁判所にも出廷して証言しなければならなくなった。シーラが心配したのは多忙を極める新原の身体だった。
新原は昼中は研究所での会議、「HOPE」の特許登録の手続き、記者会見、政府や国連との交渉、そして数ヶ月にわたって続く裁判への出席があり、あちこちへ走り回っていた。夜は研究所に戻り、研究の進捗を確認してスポンサーへの報告書を作っていた。「そんなんじゃ、身体がもたないよ」とシーラが言っても、「だいじょうぶだから」と言うばかりだった。
研究所やホテルに泊まることも多かったが、新原は週に一、二回はシーラの家に泊まり来た。晩ご飯を食べるとすぐにソファで眠ってしまうことが多かったが、それでも二人きりの時間を過ごせるのがシーラは嬉しかった。
「あともう少しで人工雲が要らなくなります。想像してみてください。もう少しで青空と太陽の光が見られるんです。毎日が太陽祭ですよ!」
テレビの中で新原が嬉しそうに笑っていた。対談番組で、これも「HOPE」プロジェクトのリーダーである新原の、大事な仕事だった。ただシーラは新原の目の下のクマがひどい上に、睡眠不足で目が変に光っているのが気になった。しかし健康のことを言っても、新原が聞いてくれないのはわかっていた。
「すごい順調だよね。恐いくらい」
「こんなものなんだよ」
シーラは新原の声の調子にハッとした。悟りきったような声だった。「こんなものって?」と聞き返した。
「そうそうあることじゃないけど、皆がこうじゃなきゃならないっていう方向が、必ずしも正しくないってこと、よくあるだろ。いわゆる既成概念に凝り固まっていると、それしか見えなくなるんだね」
「人工雲や火星移住計画が、既成概念ってことね」
「うん。でもあれだって、一つの解決方法には違いないんだ。現に僕は、十年間も宇宙船の開発をしてたんだからね」シーラを見て、新原は薄く笑った。

「まだ宇宙船開発に、未練があるの?」
「技術者としては興味があるね。でもそんなことじゃなく、もっと基本的なことだよ。皆が決定打だって思うようなことは、疑ってみた方がいいんだ。本当の決定打は、最初の衝撃の次かその次に来ることが多いから。それを忘れてたよ。黒川先生の研究が決定打になったのは・・・」
話しながら新原は眠ってしまった。シーラは彼の上に毛布をかけた。
「HOPE」プロジェクトはもう走り始めていた。既成概念化し始めていると言ってもよかった。だからもう、新原はこんなに頑張る必要がないのだった。彼が抜けても、このプロジェクトは進んでゆくだろう。
しかしシーラには彼の不安がよくわかった。新原は宇宙船開発に全力を注ぎ込んだ人だった。より画期的で根本的な解決方法があるとわかると、迷いもなくそれを探求した。だけどもし間違っていたら・・・。彼は最後までプロジェクトの成果を見届けたいのだった。
「だいじょうぶよ、だいじょうぶだから」
シーラは新原の寝顔に呟いた。
「もしもし。新原のリストフォンからかけています。わたしは田中です。シーラさん、夜分にすみませんが、すぐ研究所に来てください。新原が倒れました」
「すぐ行きます」
シーラはベッドから飛び起きた。
電話して状況を確かめる余裕はなかった。マニュアルで車を飛ばした。研究所に着くと、赤色灯を回転させた救急車が停まっていて、中で新原が応急処置を受けていた。
「ああシーラさん」
黒川夫人が駆け寄ってきた。研究所の顔として、彼女も夜遅くまで働いていた。
シーラは黒川夫人と並んで救急隊員がせわしなく動き回るのを見ていた。新原は横たわったままピクリとも動かず、心臓マッサージを受けていた。顔には酸素マスクがつけられていた。
「心肺停止」
「搬送しましょう」
救急隊員の声が聞こえた。救急車に乗り込もうとしたシーラの腕を黒川夫人がギュッとつかんだ。
「ダメ、応急処置しながら搬送するはずだから、わたしたちは車で行きましょう。わたしが運転するわ」
新原は病院で、一度も意識を回復することなく亡くなった。急性心不全だった。シーラは実感がなかった。病院にぞくぞくと研究所の同僚たちが集まってきた。皆泣いていた。シーラにお悔やみの言葉をかける人もいた。
「ええ、うん、ありがとう」
そのくらいしか言葉は出なかった。対面した新原の顔は安らかだった。葬儀の間もずっと新原の遺体に付き添っていたが、ほとんど涙は出なかった。ただ、なにかとてつもなく不思議で理不尽なことが起こってしまったと感じていた。
シーラはそのまま「HOPE」プロジェクトの広報の仕事を辞めて、家にこもった。最初の頃は寝たっきりで過ごした。たまに正体不明の何かを探しながら家をさまよったあと、温室にたどり着いていた。緑を目にすると、少し落ち着くのだった。ただ、温室には新原にもらった数々の花のがあった。それらを目にすると、涙を流していた。
しばらく温室の植物に手入れをしなかったから、草木は生い茂って互いの空間に枝を伸ばしていた。新原が届けてくれたニチニチソウの細い茎を支えにしてツタが伸びはじめたのに気づいたとき、シーラは久しぶりにガーデニング道具を手にとった。それ以来、ひたすら温室の植物の世話をして過ごした。

新原を失くしてからのシーラの様子を見て、研究室のみんなは彼女が鬱病だと初めて分かった。慰めに行っても会ってくれないので、みんなが心配していたが、元気を取り戻すまでほっておくしかなかった。週に一度、様子を見に訪ねて来てくれる黒川夫人にだけシーラは毎回会っていた。夫人はだいたいたわいもない世間話をして帰って行った。夫を失くしていた黒川夫人とは、その喪失について一度も話さなかったが、シーラは彼女に見習って、心にぽかんと空いた穴を抱えながら生きるすべを探していた。
「HOPE」プロジェクトは順調に進んでいた。新原がいなくても、シーラがいなくなっても、もはやびくともしないほど支持され期待されるプロジェクトになっていた。テレビニュースや新聞で、少しずつ大気の状態が改善され、人工雲を飛ばす回数も減っていることをシーラは知っていた。
「窓の外を見て」
ある朝訪ねて来た黒川夫人が言った。
いつも閉じていた青いカーテンを開くと、地上に瑠璃色の空が満遍なく広がっているのが見えた。太陽は空高くまぶしく輝いていた。そして遠くの地平線の上に、ふわふわで、真っ白なまだら雲が浮かんでいた。人工雲は飛んでいなかった。もうすぐ黒川先生、夫人、新原、シーラが望んだ世界が再生されるのだった。
「もうすぐよ。もうすぐわたしたちの地球が元通りになるの」
黒川夫人は窓の外を見ながら、「もうすぐだけど、この環境を守らなきゃ」と言った。
「環境を、守る?」シーラは聞き返した。
「そう。一度、わたしたちのせいで地球環境がメチャクチャになってしまったのよ。今回はなんとか取り戻せそうだけど、また同じことが起こる可能性は、いつだってあるわ」
シーラは黙った。不安を抱えながら、希望に向かって突っ走っていた新原の姿が頭に浮かんだ。彼のような人の勇気と努力のおかげでやっとの思いで自然環境が復旧し、また青空が見れるようになった。人間の都合で環境が悪化する可能性がまだあると考えると、シーラは血が騒ぐの感じた。
「わたし、研究所、退職しちゃったんですけど、戻ることって、できますか?」と小さい声で聞いた。
「もちろんよ。新原さんとシーラさんは、黒川の研究を復活して実現させた、最大の功労者よ。すぐにでも戻れるわ。まだまだ忙しいのよ。手伝ってちょうだい」
「はい、復帰させてください」
「じゃ、明日からよ」真顔で言ってから、「嘘よ、都合のいい日を教えて」と黒川夫人は笑った。
「いえ、明日から出ます」
シーラはきっぱりと答えた。
新原を失った悲しみは消えそうになかった。しかし新原といっしょに行動していた時から、シーラは彼と同じような不安と希望を抱えていた。希望が叶えば不安は消えると思っていたが、そうではないのだった。希望はいつも不安とともにあった。疲れているが、充実した表情で笑う新原の顔が頭に浮かんだ。シーラは果てしなく広がる青い空を再び見上げた。不安を抱えながら、希望に向かって生きていこうと思った。

(後編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋の本 ■



