 女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
やがて舞台からテレビへと活躍の場を移す彼女の七転び、否、八起きを辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑が Write Up。今を喘ぐ若者は勿論、昭和→ 平成→ 令和 を生き抜く「元」若者にも捧げる青春譚。
by 文学金魚編集部
この年、おチビちゃんを待ち構えていた大波は、初めての大舞台「ニッセイ名作劇場」の『ふたりのロッテ』。別々に暮らす双子、ロッテとルイーゼが出会い、互いに入れ替わり家に戻って……、というドイツの児童文学で、おチビちゃんが演じるのはルイーゼの友人・シュテッフィー。
全国の小学六年生をミュージカルへ無料で招待する、という「ニッセイ名作劇場」のコンセプトのもと、研究生二年目のおチビちゃんは地方公演を体験した。公演回数は八十回以上、招待した児童の数は十三万人という正真正銘の大舞台だ。
子どもたちは授業の一環として観劇するので、普段の舞台とは色々と勝手が違う。朝、昼、の一日二公演。夜ホテルへ帰って、翌朝ホテルから出かける毎日。とにかく朝は慌ただしい。
八時半には会場に入らなければならないので、あまりゆっくり寝てはいられないし、起きたら起きたで朝食も食べたい。一番楽なのはホテルの朝食だけど、おチビちゃんは近くの喫茶店でモーニングを頼むことが多かった。何といってもホテルの朝食は少々お高い。劇団が出してくれるのは現地までの交通費と宿泊費だけ。あとは全部自腹なので、当然みんな節約をすることになる。会場へ向かう時も、何人か一緒にワリカンでタクシー。
会場に着いたら、本番開演まであと二時間。その間にストレッチや発声練習などのウォーミング・アップを済まし、衣装を纏ってメイクを施し、マイクチェックをしなければいけない。ちなみにメイク用具も自腹。巡業全体のキャプテンはいるので、集合時間などの大枠は決めてもらえるが、基本的に自分のことは自分でやる。
やる、といっても普段の授業でたっぷり時間をかけてメイクを習ったわけではないので、先輩の見よう見まねで覚えるしかない。もっと言えば、自分の演技を見てもらうこと自体が初めてだ。毎年文化祭で発表ができる演劇の専門学校や大学の演劇学科とは違い、四季は研究生だけで公演をするようなことは一度もない。つまり研究生たちはおチビちゃんのように役がつかない限り、人前で演技をする機会が巡ってこないのだ。
子どもたちに夢を与えるお芝居だからこそ、演技をする側は準備の段階から真剣勝負。時折衝突することもある。日々の稽古や授業では習わなかったことを求められる瞬間もある。その刺激がおチビちゃんにはとても心地いい。自分の未熟さに腹を立てもするが、そんな暇があったら先輩たちに尋ねた方が早い。十時半の公演の次には、十三時半からの公演が控えている。とにかく時間がない。やっぱり体力勝負なのね、とおチビちゃんは納得していた。
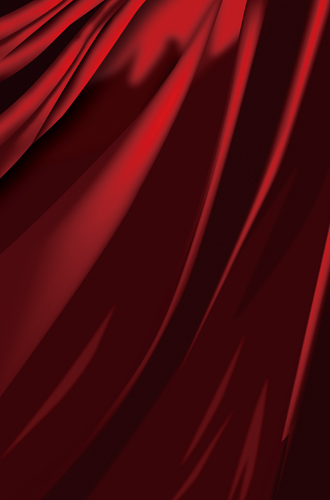
公演がない日も一日たっぷり休めるとは限らない。名古屋、神戸、福岡、大阪、と移動もしなければいけないし、公演とはまた別にイベントもある。地方でのパーティーや「ファンの集い」も経験したし、初めて色紙にサインも書いた。
トントン拍子、と言われれば「そうなのかなあ」と思う。役がついた同期の数は自分も入れて三人だけ。他の二人は喜んでいたし、周りからはよく羨ましがられた。
「やったじゃない。大抜擢だよ、大抜擢」
「こんなに早く全国を回れるなんて、本当にすごい。いいなあ」
そうかもしれないな、とおチビちゃんは思う。もっと喜んでいいのかもしれない。でも「何が?」というのが本当の気持ちだ。大抜擢の何がそんなに嬉しいんだろう?
もちろん舞台の上で演技をするのは大好きだ。目の前にはたくさんの観客がいて、自分のことを真剣な眼差しで観てくれる。そんなに長い時間でなくても「生きてるなあ」と実感できる。
特に子供たちの反応はダイレクトに伝わりやすい。中でも大阪や神戸は一段と激しい。パンフレットをメガホンのように丸めて叩くこともある。歓声も飛んでくる。客席の間を歩く時、衣装を引っ張られたりもする。本当に楽しい。
でも、だからこそ、にもかかわらず、それゆえに――怖かった。
怖いからゆっくりと考えてみる。頭の中をじっくりと整理してみる。
私はまだ未熟だから色々と出来ないのは仕方ない。
下手なことは辛くないし、特に挫折感もない。
でも私は役につくことができた。
つけてくれた浅利先生の目に狂いはない。
だから、きっと、大丈夫――。
そんな風にひとつひとつ確認しないと、不安な気持ちが噴き出しそうになる。
どの役に対しても役者は二人つくので、公演期間の半分は東京に戻る。そして同期や一年下の後輩と一緒に稽古をしたり、浅利先生に呼ばれてダメ取りをしたり、といつもと変わらない下積みの日々を過ごす。でもおチビちゃんは別に慌てたりしない。
初めて舞台に立ったことではっきりと分かった。私は今、焦って役につきたいわけではない。もっとたくさん芝居の勉強をしたいんだ!
「うるさいなあ。さっきから何べん同じこと言えば気が済むんだよ?」
その言葉にハッとする。不安な気持ちを思わず声に出していた。いつもこんな感じだ。結局自分ばっかり喋ってる。
「だからいつも俺が言ってるだろう? とにかくいろんな芝居を見なきゃダメだって」
うん、と答えながらちらりと盗み見る。ベッドに寝転がって本を読んでいる横顔。本当に綺麗なあごのライン。そして彫りの深い顔に高い鼻。あのヒゲがなければダビデ像そっくりなのよね――。
「ったく、君はいつも俺の話を聞いているようでいて、実際は右から左に流しちまってるんだろ?」
目を閉じて聞いていた。ちょっと口は悪いけど、声の響きがいい。ただ低いだけとは違う、魅力的な声。その素敵な声の主は返事を期待していないらしく、再び本を読み始めた。

ついさっき、おチビちゃんは稽古場からまっすぐ帰って来た。帰り際、同期生と後輩から食事に誘われたけど、「高校の時の友達が遊びに来るんだよねえ」と残念そうな表情のまま嘘をついた。あれくらいの演技ならいつでもできる。今日は土曜。彼が来る日だ。でも明日にはいなくなる。次に会えるのは一週間後の土曜日。
おチビちゃんの視線に気付いた彼がこっちを向いた。「お腹空いたんだろ?」とヒゲを触りながら訊いてくる。そう、彼はこの下宿を紹介してくれたダビデさん。週末だけ部屋を使っている。六畳間の洋室はベッドがあるせいで結構狭い。位置的にはおチビちゃんの部屋の隣。
「ううん、大丈夫。お腹減ってない」
実はまだ体重が増えたまま。夜に食べていいことはない。本当かなあ、とダビデさんはからかうように呟いた。
ここ最近、週末はこんな風に彼の部屋で過ごしている。理由なんてひとつしかない。好きになっちゃったからだ。どこを? と訊かれると困る。ここがこうだから、とは言いづらい。でも、あごの形は好きだ。とても綺麗。いつから意識し始めたかは、何となく思い当たる。やはり、駅まで車に乗って迎えに来てくれたあの夜のような気がする。あの時助手席から彼の横顔を見ているうち、何かに気付いてしまった。
七歳年上の建築家。大学の建築学部で教授の助手をしている。お父様の元教え子で、普段は神奈川の実家の近くに住んでいて、海外へよく旅行に行っていて……。不思議だ。知っていることを並べていくと、本当は何も知らないような気持ちになる。
もちろん、自分の気持ちを伝えてはいない。もしダビデさんにその気がなかったら大変だ。これから気まずくて仕方がない。もう二度とこんな風に過ごせなくなっちゃう。だから、今はこのままでいい。恩師の娘だからなのか、妹みたいだからなのか、理由は分からないけどとりあえず部屋に入れてくれるということは、そこそこいい線いってるはず……でしょう?
「おい、もうこんな時間だぞ。そろそろ部屋に戻れよ。明日寝坊するぞ」
明日は日曜だから休みなのよ、という言葉を呑み込んだのは、子どもっぽいヤツだと思われたくなかったから。分かった、と立ち上がって「おやすみなさい」と部屋を出る。おやすみ、と彼は言ってくれなかった。代わりに聞こえたのは洗面器の音。週末、「目黒エンペラー」は盛況だ。
役者にとって日々の鍛錬と同じくらい大切なことは公演のチケット売り。これには新人もベテランも関係ない。劇団四季は班体制を組み、週に一度は夕方から会議、月に一度は全員参加の総会を行い、班ごとのチケットの売り上げをグラフで示していた。稽古場にはチケット売り専用の電話機もあった。
もちろん何かを「買ってもらう」という行為は難しい。中でも公演のチケットは大変だ。だから「その時だけ連絡をしてもダメ。ちゃんと誠意を見せないと」と諸先輩方は教えてくれる。
おチビちゃんの所属は浜畑班。当時、舞台だけでなくテレビでも活躍していた浜畑賢吉さんの班だった。チケットに関してはお父様の教え子や関係者に協力をお願いしていたけれど、やはり公演の度に売り続けるのは難しい。ただそれも諸先輩方に言わせれば「チケット売りは、一生やり続けること」。たしかに最高の舞台を作り上げても、お客様に観てもらわなければ意味がない。
そんなある日、おチビちゃんは下宿先の近所にある寮の前にいた。しばらく迷っていたが、意を決してインターフォンを押してみる。別に行き当たりばったりではない。夜でも煌々と電気を点けているこの建物の正体がずっと気になっていた。「ドレメ女学院」と掲げているから女子寮だとは思うが今一ピンとこない。だったら直接訊いてみよう、もしかしたらチケットを何枚か買ってくれるかもしれないし……。しばらく待たされた後、「はい」と聞こえたのは意外にも男性の声だった。警備員さんかしら?
「こんばんは。こちらってどんな建物なんでしょうか?」
そんな突然の質問にも彼は丁寧に答えてくれた。「ドレメ」は「ドレスメーカー」の略称、つまり洋裁学校らしい。なるほど、それで「ドレメ女学院」なのね、と納得したおチビちゃんはもう一歩踏み込んでみる。
「あの、私、四季という劇団の者なんですけど……」
「はい」
「えっと、今度創立二十五周年記念で『桜の園』の公演があります。チェーホフの名作です。場所は日生劇場です」
「……」
「それで、もしよろしかったらチケットを買って頂けませんか?」

しばらくの沈黙。ダメだったかな、と思ったその瞬間「少々お待ち下さいね」と返事があった。その場でまた待つこと数分、返ってきた答えは「では、後で院長に話しておきます」と少々そっけなかった。
ちょっぴり不安だったけれど、後日再び電話をかけてみると、何とチケットを買ってくれるという。しかも六十枚という団体券! 舞台用衣装の勉強になるのか、それともおチビちゃんの無鉄砲、もとい情熱の為せる技なのか、とにかくたくさん買ってもらえた。嬉しい、というより驚いた。
それは劇団の人たちも同様で、次の総会ではなんと売り上げ成績トップ。浅利先生に名前を呼ばれて褒めてもらえたし、「キップ売りの少女」というあだ名まで頂いた。さすがに恥ずかしかったけれど、「虚弱体質」に比べれば全然マシ。おチビちゃんはそう思っていた。
ちなみに「ドレメ女学院」は「杉野服飾大学短期大学部」として、今でも同じ場所に複数の校舎を持っているし、あの「目黒エンペラー」もお城の形のまま営業を続けている。
気付けばそろそろ二年目も終わりかけていた。「ふたりのロッテ」で巡業を経験したおチビちゃんは、ほっと一息ついている自分に気付く。去年はこんな瞬間、なかったような気がする。のべ十万人以上の子どもたちの前でお芝居をした経験が、ほんの少しだけ自信と余裕をもたらしてくれたみたいだ。
「何かね、焦らなくなったんだよね。自分のペースでいいっていうか……」
この前の土曜日、ダビデさんにそう伝えると「身の丈が分かったんだろ?」と言われた。本当にあの人は口が悪い。でもまあ、そういうことかもしれない。
ほぼ毎日のように浅利先生の隣でダメ取りをしていると、「良い」と「悪い」の違いが何となく分かってくる。動き、間、発声、表情。どのポイントにも必ず「良い」と「悪い」はあって、それは時と場合によって逆転もする。
「浅利先生、昨日はあれでオーケーだったのに、今日はダメなんだ」
そんなことはよくある。理屈はまだ分からない。でもそういうものなんだな、と納得はできる。まだ二年目の自分にとっては、きっとそれが大事なことなんだろう。
時折後輩から演技について質問をされることもある。自分で言うのも何だけど、面倒見はいい方だと思う。教えられることは全部教えているし、背丈のせいか変な威圧感もないみたいだ。
威圧感、といえば思い当たることがもうひとつ。近頃、浅利先生から前のような威圧感を感じなくなってきた。もちろん、怖い。それは間違いない。でも、顔も見れずに俯いてビクビクしているような感じとも違う。ちゃんと表情を見て、目を見て、接することが出来る。大袈裟だなあ、という感じでダビデさんは笑うけれど、先生と実際に会ったことがある人は分かると思う。先生は身体が大きいだけではない。まとっている空気が特殊だ。
あの佐藤栄作首相のブレーンを務めていたというし、今でもよく政治家の先生たちと会っているらしい。そういえば、この間の都知事選でも石原慎太郎候補の参謀を引き受けていたそうだ。何ていうか、まるで政治家みたい。多分、普通の演出家は、あまりそういうことをしないような気がする。でも、自分の隣に座り稽古にダメを出す姿はやっぱり演出家だ。よく分からない。どんなに頑張っても、先生の全体像を掴むのは不可能だろう。
先日、同期だけで二泊三日の合宿を行った時のことを思い出すと、更に混乱してしまう。芝居の基礎を習得する、かなり濃い内容の三日間だった。場所は劇団四季が持っている長野・信濃大町の山荘。その合宿中、おチビちゃんは一対一で先生と話をする機会があった。夜だった。小さなテーブルを挟んで向かい合う。リラックスしているのは一目で分かる。少しお酒も飲んでいた。
他愛もない話を何度かやり取りした後、先生は突然話を切り替える。少しだけ、声が柔らかくなった。
「昔な、戦争の頃の話だよ。疎開、分かるよな? そ・か・い」
「はい」先生は昭和八年生まれだ。「疎開、分かります」
「ずいぶんと田舎なところだった。戦争やってるのが嘘かと思うくらい、のんびりしていた」
長い間があった。視線を逸らすのも、じっと見つめ続けるのも変だから、目のやり場に困ってしまう。
「外でな、寝そべってたんだ。ゴロンと空を見上げてさ。そしたら牛がいてさ、何してたと思う?」
「あ、えっと……」
「尻尾でさ、たかってくるハエを追っ払ってたんだよ」我慢できない、といった感じで微笑む。「右、左、右、左ってプランプランさせてたんだ」
想像すると確かにのんびりした感じがする。そのまま告げると「だろ?」と大きく頷いた。

「でさ、イタズラのつもりで小さな石を投げてたんだよ、牛の尻に向かってさ。そしたらどうなったと思う?」
「?」
「スポッと入っちゃったんだよ」
「スポッと?」
「うん、尻の穴にな。石がスポッと」
「え!」
「そしたら怒ったみたいで、こっちに向かってきちゃってさ。ほら、牛はデカいだろ? 怖くて怖くて、もうあの時は必死に逃げたもんだ」
あの話をしている時の先生は、演出家の顔でも政治家の顔でもなかった。牛に石を投げる少年の顔をしていた。どれが本当の、ではなく、どれも本当の先生だと思う。やっぱりあの人の全体像は掴めなさそうだ。
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『そろそろ幕が開く』は毎月20日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■



