 ささやかな日常の一瞬を切り取り、永遠の、懐かしくも切ない言語的ヴィジョン(風景)に変えてしまう、『佐藤くん、大好き』で鮮烈なデビューを果たした原里実さんによる連作短編小説!
ささやかな日常の一瞬を切り取り、永遠の、懐かしくも切ない言語的ヴィジョン(風景)に変えてしまう、『佐藤くん、大好き』で鮮烈なデビューを果たした原里実さんによる連作短編小説!
by 文学金魚
三度目の週末は、庭ですごした。たくさんの肉と野菜を買ってきて、バーベキューをした。
わたしは楽しくなって、歌を歌った。歌を歌うと、鳥たちがやって来た。わたしはうれしくて、もっと歌った。博士は楽しそうにその様子をながめながら、また少し、悲しい顔をした。
「どうしたの?」
わたしはたずねた。
「なんでもないよ」
と博士は答えた。
「嘘よ」
と、わたしは言った。
「博士、ときどき悲しい顔をしてる」
博士はわたしの頬に触れながら、
「ごめんね」
と言った。
「どうして謝るの?」
「きみじゃない人のことを思い出しているんだ」
何かがはじけたように、わたしの頭は真っ白になった。
「わたしじゃない人のこと?」
「いや、きみじゃない、というわけではないのかもしれない。ぼくにはもうわからない」
博士はそう言って頭を抱えた。こんなふうに動揺をあらわにしている博士は初めて見た。博士はわたしの前で、いつも穏やかに笑っていた。
「きみが生まれる前、きみのからだのなかには別のプログラムが入っていたんだ」
博士は苦しそうにそう話した。
「でも、重大な不具合が見つかってしまってね。リセットせざるを得なくなった。そうして生まれたのがきみさ」
わたしは自分の手のひらを見つめた。それは間違いなく、わたしの意思で動いていた。これが、ほかの意思で動いていたことがあったのだ。
「もしかして、博士。その人と、このあいだの丘や海に行ったことがあったのね?」
博士はわたしの目をじっと見て、
「メイはやっぱり、頭がいいね」
と言った。わたしは博士の肩に手を伸ばして、さすってみた。強ばっていたからだから、徐々に力が抜けていった。
わたしは、頼りない博士を抱きしめた。そして背中をさすりつづけた。博士はわたしの胸に顔をうずめた。わたしは悲しいような、さびしいような気持ちになった。
目の前でビスケットをかじっている男を、わたしはまじまじと見つめた。こんなに博士とそっくりなのに、こんなにもはっきりと博士ではない。わたしにはそのことが不思議でたまらなかった。
「兄貴はおれのことが嫌いなんだよ」
博士の弟は言った。
「そうなの?」
「うん。でももう慣れてるんだ。昔からそうだったからね」
「でもそんなの、なんだか悲しいわ」
「仕方ないさ。だって昔から、兄貴の好きな女の子は、みんなおれのこと好きになっちゃうんだもの」
仕方ない、と言った博士の弟は、実際にさばけた顔をしていた。でもほんとうのところはどう思っているのかしら、と、わたしは内心で首をかしげた。

「それに同じ顔のやつがいたら、意識しない方がおかしいよ」
「じゃ、あなたはどうなの? 同じ顔した博士のこと、どう思っているの?」
わたしはたずねた。
男は少しだけ考えるそぶりを見せて、
「どうだろうね」
と言った。
「もうずっと前からだから、わからないな」
男はそう言って、紅茶をすすった。
「ねえ、ところであなた」
わたしは気になることが次々に出てきて、重ねてたずねた。
「どうしてそんなに博士にそっくりなの?」
男はきょとんとしたあとに、吹き出した。それから真面目な顔になって、
「おれはね、博士の双子の弟なのさ」
と教えてくれた。
「今日、誰か来たの?」
お風呂の掃除をしているわたしのところへやって来て、博士はたずねた。
「そんなことないと思うけど」
わたしは浴槽をこする手を止めて答えた。
「でも、ほら。ビスケットが増えてるよ」
博士は赤いビスケットの箱を、両手に持っていた。
わたしはそれを見て考えた。そう言われると、誰か来たような気がした。そしてその誰かが、ビスケットを置いていったのだ。
博士は思い出そうとしているわたしの顔を、じっと見ていた。
「いや、いいんだ。来てないんなら」
やがてそう言うと、博士はぷいといなくなった。
わたしはひとりでしばらく、ビスケットについて考えていた。けれどあまりに深くビスケットについて考えるうちに、なぜビスケットについて考えているのだったかを忘れてしまった。

博士の弟は、わたしにひまわりを差し出して見せた。
「どうしたの?」
わたしがあっけにとられてたずねると、
「持ってきたんだ」
博士の弟は言いながら、どんどん家のなかに上がりこんできた。
「なぜ?」
わたしは追いかけながらたずねた。博士の弟は、ソファに腰かけた。わたしは、ソファの反対側の端に腰を下ろした。
「おれは、花を売っているんだよ」
「花を?」
「ああ、そうさ」
「博士の仕事と、ずいぶん違うのね」
「そうだね」
博士の弟は腕を組んで外を見た。
「どんな花を売ってるの?」
「なんでもあるよ。一度来るといい。広くて、色鮮やかで、青くさい匂いがして、きっとびっくりするよ」
わたしは花屋について想像した。頭のなかからいろいろな花屋を呼び出してみた。どれも色鮮やかで、たしかに青くさそうだったけれど、男が言っている場所はもっとすごい気がした。行ってみたいと思った。
「おれはね、その日のその人の気分にぴったりの花を選ぶのが得意なんだ。だいたいね、どんなのが欲しいんですかって聞いても、人はあんまり上手に答えられないものなんだよ。その日の気分はピンクなのに、青が好き、とかぜんぜん違うことを答えてしまったりね。でも、おれにはどうしてか、その日のその人にいちばん必要な花がわかるんだ」
おもしろいことを言う人だ、と思いながら、わたしは手のなかのひまわりの花を見た。
「じゃあ、今日はこの花が、わたしにいちばん必要な花なの?」
「さあ、どうだろうね」
となぜだか男は言った。わたしはひまわりを差しておく花器を出してこようと、立ち上がり、食器棚の横の戸棚を開けた。そこには、赤い箱に入ったビスケットがあった。
「あ」
わたしはそれを見て、ぴんときた。
「これ、あなたの好きなビスケットじゃない?」
そいつは少し驚いたような顔で、
「そうだよ」と答えた。「よくわかったね」
自分でも不思議だった。なぜわかったのだろう。
「変ね。わたし、あなたがどこの誰かも知らないのに」
男は乾いた笑い声をあげて、
「変だなあ」
と言った。
わたしのすぐうしろに立って、博士が「ただいま」と言うので、わたしは飛び上がるほど驚いた。
「びっくりしたわ」
博士が帰ってきたことに気がつかないなんて、いままでなかったことだった。
わたしは慌てて立ち上がり、コロッケを揚げるための油の鍋に火をつけた。
「大丈夫?」
棒のように立ったまま、博士はわたしを見ていた。
「ええ、ついぼんやりして。ごめんなさい」
わたしは火をつけたばかりの鍋の油の表面を見つめた。温まるまでの時間が手持ちぶさただった。何かこの時間を使ってできることはなかっただろうか? そうだ、キャベツ。キャベツの千切りは、もうつくったのだったか。頭のなかがまとまらない。
「何を考えていたの?」
博士はたずねた。わたしは頭に真っ先に思い浮かんだことを答えた。
「キャベツ」
「え?」
「じゃなくて」
博士は静かにわたしのそばへやって来て、コンロの火を消した。
「大丈夫だよ、メイ」
博士はそう言って、わたしの背中に手をやった。わたしはそのぬくもりに神経を集中させた。ほかのことを考えずにすませたかった。けれど、それはとても難しいことだった。
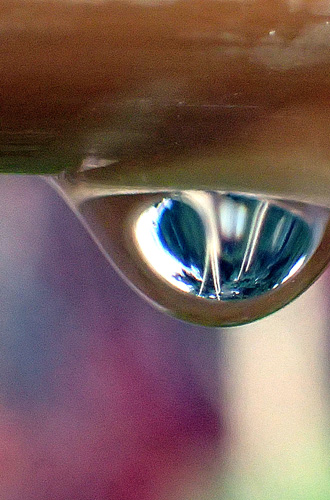
「ひまわり」
「え?」
「見て、そのひまわり」
わたしはテーブルの上に置かれた、しおれたひまわりを見た。博士もわたしと同じように、そのひまわりを見た。
「しおれてるでしょう。どうして捨てないのか、変に思わなかった?」
ああ、と博士は言った。
「そういえば、そうだね。気がつかなかった」
おかしいと思った。あんなに堂々と、何日もテーブルの上に置かれていて、気がつかないわけがないのに。
「捨てようと思ったの。でもなんだか捨てるのが怖くて」
「怖い? なぜ?」
「わたし、あの花がいったいどこからやって来たのか、思い出せないの」
博士はそれを聞いて、しばらくだまっていた。しばらくして、わたしの背中にそっと触れながら、
「大丈夫だよ」
と博士は言った。
「思い出せなくても」
わたしは首を横に振って、博士の顔を見た。
「博士」
博士はとても不安そうな顔で、わたしを見ていた。博士を不安な気持ちにさせていることに対して、申し訳ない、悲しい気持ちがわいてきた。それでも、このことをわたしの胸のなかだけにしまっておくことはもう難しかった。
「わたし、ほかにも、思い出せないことがあるの」
「何を?」
「わからない」
博士は眉根を寄せた。不思議がるのも、無理もない。わたしだって、自分の不安がなんなのか、自分でもはっきりとはわかっていないのだ。
「わたし、思い出せないの、何かを。それが何かは、わからないんだけど、何かを思い出せないってことだけが、確かにわかるの。どうしても思い出せなくて、記憶のなかで、それがあるべきはずの場所だけがぽっかり空いていて、何かそれがとても大切なことなんじゃないかと思ったら、とても怖いの。怖くて、不安になるとますます、きっとそれがとても大切なことだったんだ、という気持ちになってくるの。だからひまわりを捨てるのが怖いの」
博士はしばらく動かなかった。わたしの言っていることがわからないのだと思った。そうではないかもしれない、とわかったのは、博士が、
「ごめんね」
と言ったからだった。

「なぜ、博士が謝るの?」
「ぼくは知っているからさ。きみの消えた記憶の正体を」
わたしは、わたしの消えた記憶の正体が、何か博士に関係のあることだったのかもしれないと思って、笑顔になりかけた。でも、それは違うとすぐにわかった。博士はとても悲しい顔をしていた。
「きみの消えた記憶の正体は、ぼくの弟だよ」
思ってもみないことで、わたしは自分の耳を疑った。会ったことはおろか、存在さえ知らなかった博士の弟が、どうしてわたしの記憶のなかになんかありうるだろう?
「博士の弟?」
「ああ。ぼくには双子の弟がいるんだ」
博士とそっくりの双子の弟を、わたしは想像しようとしてみた。でも、うまくできなかった。わたしにとって博士はたったひとりの、見た目も中身も合わせて、博士という固有の存在だった。
「でも、博士の弟とわたしの記憶に、いったいなんの関係が? わたし、その人に会ったこともないのに」
「会ったことがあるんだよ」
博士は言った。
「メイは何度も、ぼくの弟に会ってるんだよ。そのひまわりも、弟が持ってきたものさ」
そう言われると、ひまわりは確かに誰かからもらったものかもしれないという気持ちになった。でもそれが誰だったのかは、やはりわからなかった。
「そんなのおかしいわ」
わたしは言った。
「だってわたし、博士の弟のことなんか、ちっとも記憶にないもの」
「記憶にないからって、なかったこととは限らないだろう」
博士は言った。
「きみの脳みそは、ぼくの弟のことを覚えられないんだよ。そうなるように、ぼくがきみをつくったんだ」
わたしは首をかしげた。
「どうして博士に、そんなことをする必要があるの?」
ぼくはね、と博士は言って、一度長く息をついた。
「ぼくはずっと、弟のことが怖かったんだ」
「怖い? なぜ?」
「優秀だったからさ」
博士は答えた。
「ぼくたち兄弟の父も、研究をしていてね。ぼくも同じようになりたくて、小さなころから必死でがんばっていたんだ。おかげで成績は、弟よりもよかった」
「じゃあ、よかったじゃない」
博士はゆっくりと、首を横にふった。
「弟はね、ちっとも努力しているように見えなかったのさ。ぼくが一生懸命問題集を解いているあいだに、弟は本を読んでいた。あいつはなんでも好きだったな。推理ものも、翻訳のSFも、恋愛ものも、科学の本や図鑑だって、なんでも読んでたよ。次のテストには、そこに書いてあることなんかひとつも出ないのに。なのにどうしてか、弟は出来がよかったんだ。テストの順位はいつも、学年で一位のぼくより、ほんの少しだけ下だった」
博士は静かに語りつづけた。
「ぼくより上をいってくれれば、遥かによかったよ。そうすればぼくは、弟がいつ本気を出すのか、ぼくが追い抜かれるのはいつかと怯えつづけずにすんだだろう。ぼくはいつも弟にいらだっていた。あいつが本気を出せば、ぼくよりも優れた能力を簡単に発揮するに違いないのに。あいつがちゃんとやらないことに、ぼくはむかついていたんだ」
いつも穏やかだった博士の殻にヒビが入って、ぽろぽろと剥がれ落ちていった。
「大学を卒業したあと、あいつは花屋で働きはじめたよ。ぼくや父とはぜんぜん違う道を行くことにしたんだな。これでぼくはもう弟のことを考えずにすむはずだった。でもぼくはやはり怖かった。いま思えば、くだらない自尊心を満たすために、あいつにきみを会わせたのが間違いだったんだ。あいつはきみに興味を持って、繰り返し会いに来た。そのうちに、きみもあいつに興味を持つようになったんだ。いつものパターンと同じだ。ぼくの大切な人は、なぜかいつも弟を好きになる。なぜなんだ」
博士はそう言って、悲しそうにわたしをにらんだ。
「いや、きみを責めるのは間違いだね。悪いのはきみじゃない。あの女は、ぼくが自分の手で消してしまったんだ」
博士はそっと、わたしの頭に手をやった。そして撫でた。
「ごめんね、メイ」

博士はわたしの頭を撫でつづけた。わたしは博士を見つめた。博士が誰に話しているのか、わたしにはわからなかったけれど、わたしにとって博士は博士だった。
「いいのよ」
わたしは言った。
「博士が笑顔でいてくれることが、わたしの幸せなのよ」
なぜこんな悲しい話になってしまったのだったか、とわたしは考えた。原因はテーブルの上のひまわりだった。わたしはそれを手にとった。
「これがいったいどこからやって来たのかは知らないけど」
わたしはそれをごみ箱に放り投げた。
「いらないわ。わたしには博士がいるもの」
博士は鳩が豆でっぽうを食らったような顔でわたしを見た。そしてしばらくすると、にっこりと微笑んだ。
(後編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『原里実連作短編小説』は毎月11日にアップされます。
■ 原里実さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■



