 〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!
〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!
by 青山YURI子
近代的なホテルで目覚め、もう一度シャワーを浴び―近代的なシャワーが嬉しくて―、朝9時にはチェックアウトした。今日はどんな冒険が待っているのだろう。昨晩、チェックインをしたときにも見かけた女とすれ違った。アンヘラが2、3言交わしていて、確かミレーナと言った。彼女は緑色のワンピースを着ている。挨拶の微笑みをアンヘラがして、僕もそれを追うように目線を合わせた。彼女は、ためらいなく僕たちの視線を拾うと微笑んで、彼女から僕の方へ視線をずらした。正直、彼女は魅力的な女だった。
 とりあえず市内観光をすることにした。アメリカ、アフリカ、カスティーリャの広大な大地、肥沃な土地、荒地、サバンナ、海、モンゴル由来だと思われる草原を経て、自然から一度離れ、都市に留まりたい気分になっていた。市内観光ができることが嬉しかった。見るべき建物がたくさんあるような。どこかのカフェで腰を下ろすのもいい。一日中、僕には骨抜きになって届く言葉の外観を眺めるだけでも楽しい。アンヘラと絆を深めるための会話を何かひねり出してもいい。遠くの街でしかできない会話がある。4棟の〝紐〟ビルが若干の景観を壊していたが、草原の間にオアシスのように現れたこの街は、バロック建築も多くお洒落な都市だった。しかし、僕たちの問題は、何一つ深い話を互いに持ち合わせていないことにあった。今、僕らにそのようなものがあったとしても、過去は取るに足らないもので、新しく目にする、耳にする、一つ一つのことに、まっさらな自分をぶつけたい気分だった。過去と未来からだんだんと距離を狭めていって、より正確で微細な現在のポイントに爪先立っていたかった。お互いのことを考えていても、一つ、一つ、また一つ発見していく互いの特徴を発見し、摘みあげていく喜びを純粋
とりあえず市内観光をすることにした。アメリカ、アフリカ、カスティーリャの広大な大地、肥沃な土地、荒地、サバンナ、海、モンゴル由来だと思われる草原を経て、自然から一度離れ、都市に留まりたい気分になっていた。市内観光ができることが嬉しかった。見るべき建物がたくさんあるような。どこかのカフェで腰を下ろすのもいい。一日中、僕には骨抜きになって届く言葉の外観を眺めるだけでも楽しい。アンヘラと絆を深めるための会話を何かひねり出してもいい。遠くの街でしかできない会話がある。4棟の〝紐〟ビルが若干の景観を壊していたが、草原の間にオアシスのように現れたこの街は、バロック建築も多くお洒落な都市だった。しかし、僕たちの問題は、何一つ深い話を互いに持ち合わせていないことにあった。今、僕らにそのようなものがあったとしても、過去は取るに足らないもので、新しく目にする、耳にする、一つ一つのことに、まっさらな自分をぶつけたい気分だった。過去と未来からだんだんと距離を狭めていって、より正確で微細な現在のポイントに爪先立っていたかった。お互いのことを考えていても、一つ、一つ、また一つ発見していく互いの特徴を発見し、摘みあげていく喜びを純粋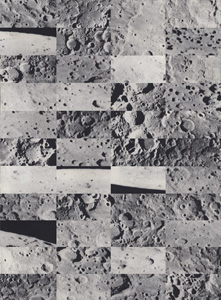 に楽しんだ。そうして胸いっぱいに大きな花束が用意され、腕いっぱいの彼女を所有した気になるのが楽しかった。過去の出来事を引き出すより、新しい一風、一風を、正確に固有の味のまま感じていたかった。だからお互いを眺めていても、ただ一緒にいられるのが純粋に心地よく、同じ空気を感じていることに喜びを感じ、手の平を合わせていることだけがお互いのすることだった。ただ次々と来る丘を登っては降りるように、嬉しさを感じれば彼女を抱き、彼女も僕の首に手をかける。お互いの名前を呼び合い、犬猫のようにキャツキャツと歓び合った。
に楽しんだ。そうして胸いっぱいに大きな花束が用意され、腕いっぱいの彼女を所有した気になるのが楽しかった。過去の出来事を引き出すより、新しい一風、一風を、正確に固有の味のまま感じていたかった。だからお互いを眺めていても、ただ一緒にいられるのが純粋に心地よく、同じ空気を感じていることに喜びを感じ、手の平を合わせていることだけがお互いのすることだった。ただ次々と来る丘を登っては降りるように、嬉しさを感じれば彼女を抱き、彼女も僕の首に手をかける。お互いの名前を呼び合い、犬猫のようにキャツキャツと歓び合った。
僕たちは大きな荷物をホテルに預け、僕はリュックを、彼女は斜め掛けのクラシックな小さなポシェット(ザラで30ユーロだったらしい!)を持ち、近くの公園に向かった。オレンジジュースが似合う朝の空気の中、つい昨日、モンゴルの高原を渡ってきたとは思えない、湧き立つ豊かな緑を目にした。1日目のコテージ周りの緑はこんなに深かっただろうか。彼女の肩に掛かったポシェットが、長く垂れ下がったベルトの皮の紐が白くささくれ立っているのをささやかに僕に気づかせながら、彼女が歩くたびに宙に浮いて、パンパンと太ももを叩く赤が森林のアクセントになっていた。僕の太陽はこの中に入っているのだなあとポシェットを見ながら思った。僕は、こういうことを数え上げることが仕事だった。特に、彼女の深い内面を知ろうなんて思わなかった。彼女の特徴の一つ一つを、細かく細かく、そしてそれが終わるとさらに細かく発見しようとした。新しく刷新された一日と彼女の相性が生み出す効果を認めたり。彼女をより細かく、ある時は僕の感情のフィルターを通して、または彼女の気分のフィルターを通して、ある時はズームを引いて全体像を掴み、焦点をぼかして雰囲気を味わい、さまざまな彼女を見出しては喜びに浸った。彼女もだいたい同じ感じだと思った。
 公園のテラスで昼食を取ると、ミレーナを見つけた。彼女は、ハイキングコースと書かれた小道を入っていった。僕たちもこの町の、明るい色の葉のついた木々の間をもう少し散策したい気分だったので、ハイキングコースを行くことにした。道は斜面になっており、そのまま下がっていけば、どう考えても街に着く。『空港なんてどこにでもありますよ!』確かにどこにでもあるし、ホテルなんてどう行っても辿りつける。なんといっても、こんなに目立つ紐ホテルなのだから。街につけば、方角なんていくらでも調整できる。この街には韓国族の最新のテクノロジーで建てられた四つの紐のようなビルに囲われてこの丘があり、アヤソフィア風を装った都市景観デザインだった。丘の周りの街は繋がっているし、バスの機能を果たす大型馬車も走っている。公園は丘の上にあった。公園までは〝ホテル前〟停留所から黄色いトラムで登ってきた。ちょっとリスボン風だけれど、2の国にはポルトガルは関わってない。
公園のテラスで昼食を取ると、ミレーナを見つけた。彼女は、ハイキングコースと書かれた小道を入っていった。僕たちもこの町の、明るい色の葉のついた木々の間をもう少し散策したい気分だったので、ハイキングコースを行くことにした。道は斜面になっており、そのまま下がっていけば、どう考えても街に着く。『空港なんてどこにでもありますよ!』確かにどこにでもあるし、ホテルなんてどう行っても辿りつける。なんといっても、こんなに目立つ紐ホテルなのだから。街につけば、方角なんていくらでも調整できる。この街には韓国族の最新のテクノロジーで建てられた四つの紐のようなビルに囲われてこの丘があり、アヤソフィア風を装った都市景観デザインだった。丘の周りの街は繋がっているし、バスの機能を果たす大型馬車も走っている。公園は丘の上にあった。公園までは〝ホテル前〟停留所から黄色いトラムで登ってきた。ちょっとリスボン風だけれど、2の国にはポルトガルは関わってない。
丘を降りていく。両脇には流れるように緑が横たわる。首の後ろの毛を二つに分け、すべて前面に持ってきた、長い女の髪のようだった。なんだか丘の土も、肌のように柔らかかった。密接して木々が生えており、枝も一本一本が長く、葉も点描画のように隙なく枝に沿って乗っていたため、本当に緑の髪の毛に思えた。重力によって坂の下の方へとなびいている。道は、二車両分ほどの幅があった。といっても、この国には車が存在しないので、少なくとも今まで目にしていないので、通るのは馬か馬車だろう。しかし蛍光塗料で引かれた仕切り線はない。両脇には土の色の違う、歩道がある。よく交通整備がなされた街で、上る人、下る人用に道は別れていた。だから左の、下る人のための歩道を僕らは行っていた。赤茶色にコルク材の敷き詰められた道路だ。どうりで柔らかいわけだ。たまにリスや小鳥が僕らの見えないうちにくるりと円を描いたり、瞬きをし合ったり、僕たちの目には映らない微細なものをついばんでいる様子が感じられた。太陽の光は、薄く、空全体に塗られたように広がっていた。ホットミルクの薄膜のように、簡単に指先で摘めるような気がする。後ろにも空の層が、何億万枚もミルフィーユみたく重なっている。僕たちは、空気を少しずつ、少しずつ押し、体を食い込ませていきながら、前へと進んでいる。2、3時間歩いて、だんだん周りに人気がなくなってきたのが感じられた。さっき、後ろにいたのはミレーナではなかったか。だんだん記憶も曖昧になってきていた。ミレーナを思い出し、近くに感じるのは、僕の気持ちが彼女の方へ寄っているからか。それとも、彼女の冷たく、賢く、人を引き付ける締まりの良さ、冷却して欲しいと思う何かを冷却してくれる準備の整った感じのある、あの彼女の足跡を、僕は聞いているのだろうか。細身の彼女が、タンクトップに短いホットパンツを履き、下を向き、僕たちを気にしない体で伏せ目がちに歩を下ろしていく。僕は単調な動きを続け、意識を空気の中に紛らわせて溶かせている時、温かいアンヘラの腰に手を回していたが、彼女は大きな肉の塊のように単調に揺れて、機械的に運ばれていくようだった。余計な動きなく、障害があれば避け、リズムを踏んでおりていく。1、2、3、1、2、3ではなく1、2、3、4、5、6、7の繰り返し。もしかしたら可能性の村の教授の歓迎の7回のリズムを思い出しているのかもしれない。徐々に、日が陰ってくるのを感じる。道が木陰になったり、日向になったり、僕たちは前方を見て歩いているけれど、太陽が何度も昇っては沈んでいるように感じる。
Image © Luis Dourado
(第16回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『コラージュの国』は毎月15日にアップされます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
