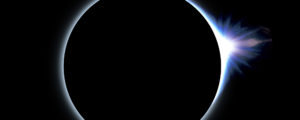 世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
by 寅間心閑
五、彼はきっとブラック
ドアを開けるとそこには警察官が二人。何度も乱暴にドアを叩いている人たちがいる、と近隣の住民から通報があったらしい。部屋を覗き込むようにして「御主人、その時は外出してました?」と尋ねられ、「はい、お騒がせしてすみませんでした」と安太は頭を下げた。前に付き合っていた女の子のことでちょっと、と頭を掻くと「なるほどね」という感じで場が和み、ほどなく警察官は帰ったという。まあ、確かに嘘は言ってない。
ちゃんと事情を説明した方が良かったんじゃないの、と非難めいた口調の俺に、「『御主人』ってさ、『オジサン』って言われてるのと変わらないよね」と壁にもたれて呟く安太。随分疲れている。結婚してたんだろ、とからかいたかったが止めた。憔悴、ってこういう状態なんだろう。ぐちょぐちょやった後、似たような感じにはなるが、ここまで顔色は悪くならない。
結局、あの後電話は切れるし、何度かけ直しても繋がらないからタクシーで様子を見に来ちまった。
「でも何か起きてからじゃ遅いだろ?」
「うん、まあ……」
「そいつら、多分また来るぞ」
「うん、まあ……」
時間は午前二時、草木も眠る丑三つ時。明日はバイト、オープンからクローズまでフルだ。もう今日はここに泊まろう。枕を引き寄せると「明日早いの?」と訊かれたので、それには答えずナオから聞いた「ランブル」の話を伝えた。
「色々ありがとう。でも、ちょっと今日は疲れた」
神妙な顔のまま立ち上がり、安太は電気を消す。女がいないのにこの部屋に泊まるのは初めてかもしれない。ヤケクソで誰か呼んでもよかったが、こんな時間じゃ難しい。それにバイアグラのジェネリックも家に忘れて来た。ずいぶん慌ててたんだな、俺。
「明日早いの?」
目が慣れてきた闇の中、さっき無視した質問を投げ返してみた。ちっとも眠くならない。また連中が来て、そのドアが乱暴に叩かれるんじゃないか。そんな不安がある。もう一度尋ねてみたが、安太の返事はなかった。聞こえて来るのは寝息だけ。やっぱり神経太いんだな。
目が覚めると午前九時。「食べる?」とコンビニのサンドイッチを投げてよこされた。シャキシャキレタスサンド。今しがた行ってきたらしいが、まったく気付かなかった。俺も案外図太いのかもしれない。

レタスをシャキシャキ食べながら、改めて半半グレについて安太が知っていることを確認してみる。なぜか熱心に調べてくれているナオに伝えられることは――、結局ひとつもなかった。耳が餃子みたいな首謀者、モエカちゃんの彼氏の名前すら安太は知らなかった。
「被害者っていうのは何も知らないのかもしれないなぁ」
そんな戯れ言が言えるなら大丈夫だ。少し早いが仕事に行こう。安太の目を盗み、隅に寄せられたキャンバスを確認する。何も描かれていないことに、俺は何故かホッとした。
あれから三日間、安太から連絡はなかった。
暴行、拉致監禁、そして最悪のケース。色々よぎったが実際に連絡をしなかったのは、不安は不安のままにしておきたかったからだ。それを言葉にしたり、行動に移したりすることで、不安は必ず現実のものになる。我ながらよく分からない理屈だが、子どもの頃からずっと信じている。
小学三年になると夏休みや冬休みになる度、爺さんが住んでいた広島へ三歳下の妹と二人だけで行かされた。新幹線はもちろん、普通の電車にさえ乗り慣れていなかったから、とても緊張したことを覚えている。でも俺は決して不安を言葉にはしなかった。妹の手を握り締めながら我慢していた。大丈夫かなあ、と口にしたら大丈夫ではなくなってしまうと思い込んでいたからだ。
さあ、考えたって仕方がない。俺は安太じゃないんだ。パーッと遊んで忘れちまおう。LINEとメールで誘いをかける。ちょっと前に同じことをした。あれはバーバラと会った日の帰り、たしかゴールデンウィークの最終日だった。結果は完敗。さあ、今日はどうだろう。
もちろん御新規さんがベストだが、正直少々面倒くさい。安太と二人の場合とは勝手が違う。女に声をかけさせる才能、俺は持っていない。それに今は午後三時、外はまだ明るいじゃないか。果報を寝て待つ時間くらいはある。
すぐ出られるように着替え、再放送の刑事ドラマを眺めながら、返信が来るのを待っている。先週、バイト先の「フォー・シーズン」から二割引で買ったサマー・ジャケット。短大一年の安藤さんも「似合ってますよ」と言ってくれた。下ろすなら今日、と羽織ってみる。うん、悪くない。ただ、今のところ来るのはNG報告のみ。来るだけマシか、と思い直して冷蔵庫からビールを出し、カンカン響く世田谷線の踏切の音を聞いている。

俺も安太も風俗を使わないのは、女が何も纏っていないからだ。脱がす為の服を脱がしてもつまらない。まあ、俺は安太ほど意志が強くないので、実はさっきからチラチラと頭をよぎっている。
三ヶ月前、大久保の居酒屋で連絡先を交換したミンちゃんは、鶯谷の韓国デリヘル勤務。日本語がうまい二十代半ばの綺麗な子だったが、職業を聞いた途端、明らかに安太のテンションが落ちた。なので結局何もナシ。本当に変なところ、ストイックだ。
俺は違う。プライベートで知り合った子をデリヘルで指名するのは、意外とやらしいんじゃないかなんて思っていた。いや、今もそう思っている。あれ以来連絡は取っていないが、確か店の名前をスマホにメモしたはずだ。でも源氏名を知らない。本名で指名なんて出来るのかな、と思っていると電話がかかって来た。LINEでもメールでもなく電話。画面に表示された名前を見る。
――柴田知子
大学の同級生、シバトモだ。アナウンサー顔の帰国子女。意外といえば意外。最後に会ったのは二年前、同級生の結婚式だった。二次会、三次会とずっと一緒に飲んでいた。相当酒は強いと思う。もし今日はNGだとしても、わざわざ連絡をくれたのは嬉しい。
「もしもし」返事がない。「もしもし?」
「おう、久しぶりだな」
「?」
間違いなく男の声がする。しかも「久しぶり」って……。これ、誰だ?
「俺、俺、カタヤマ。久しぶりだな」
カタヤマ、カタヤマ、カタヤマ。思い出せない。ただ、シバトモの電話からかけているなら、きっと大学関係のはずだ。
「びっくりしたか? まあ、でも驚いたのはこっちもだから、これでチャラな。それともお前、誰かから聞いたの? あ、ちょっと待って」
分かった。中国語の授業で二年間一緒だった、ガリガリで背の高い静岡出身の片山だ。でも「聞いたの?」って何を? いや、その前にシバトモ本人は?
「もしもーし、久しぶり。っていうか、突然どうしたのよ。もし都合が良ければ軽く食事でも、なんて。でもさ、何週間か前にも同じような連絡くれたじゃん? 多分誰かと間違ってんだろうなあ、とは思ってたんだけど」
これがシバトモの声だ。別にあの日も今日も間違っちゃいないが、そういう事にしておこうかな。それにしても彼女、こんなにマシンガントークだったっけ。
「でも本当にグッドタイミングだよ。こっちから連絡しなきゃ、って思ってたところだったんだ」
「え?」
「じつはね、私と片山、今度結婚するのよ。まだ細かい日取りは決まってないんだけど、年内には式挙げる予定で……」
何がグッドタイミングだ。そっと悪態をつきながら、二本目の缶ビールを取り出した。もう少し飲まないと、適当な相槌だって打つ気になれない。結婚するのよ、か。本当、心の底からどうでもいい話だ。途中であと二名、去年結婚したという同級生の名前が出たが、顔も浮かばなかった。結局、再び片山に替わってもらい「おめでとう」と告げてようやく電話を切る。少なくとも四、五回は「式には出てくれよな」と言われたはずだ。通話時間十五分三十二秒。どっと疲れた。

そうか、もうそろそろ三十歳だもんな。知り合いの結婚話に出くわしても不思議なことはない。よいしょ、とサマージャケットを脱いで顔を洗う。別に今日下ろさなくてもいい。そもそもこれ古着だし、「下ろす」とは言わないんじゃないか。
何となく、今日はもう誰からも連絡が来ないような気がする。もちろん寂しい予想だが、もし連絡があったとしても、鬱陶しいだけかもしれない。それくらい今の電話で疲れてしまった。
だから声に出してみる。
「今日はもう、連絡来ないだろうな」
言葉にしたからもう大丈夫。多分、現実になるはずだ。
腹が減って目が覚めた。テレビの光だけでは暗くて何も見えない。窓の外はもう夜だ。スマホを確認したが、何一つ履歴は残っていない。シバトモ以降、本当に誰からも来なかったらしい。眠ったら腹が減って起きた。それだけだ。馬鹿馬鹿しい。
せめて飯くらいは外に出ようと、さっき脱いだサマージャケットをまた羽織る。寝る前は気にならなかった踏切の音が、今はこんなにもうるさい。逃げるように家を出て、ダラダラ歩きながら何となく下北方面へ。途中、我慢できずにコンビニでおにぎりを二つ買った。昆布といくら。羽根木公園入口の階段に腰掛けて食べながら、「マスカレード」に顔を出そうと思った。昔の同級生の結婚話ではなく、三十歳の「今」の話をしたかった。それが可能なのは、安太とナオしかいない。
「はい、『マスカレード』です」
「もしもしナオ? 俺」
「お、グッドタイミング。これから来る?」
今度は本当にグッドタイミングなんだろうな、と疑ったのも束の間、今から例の「おしぼり屋」が来るという。これは本物だ。あと二十分で行くよ、と言いながら立ち上がって歩き出す。公園の中を突っ切る方が早いはずだ。小走りに近道を選びながら、頭の片隅で考える。俺は何の為に急いでるんだろう?
安太のため、ではないと思う。もちろん半半グレの連中から危害を加えられることなく、この瞬間も無事でいてほしいと願ってはいるが、それとこれとは多分違う話だ。当然ナオのためでもない。
来年三十歳になる身としては恥ずかしいが、単純に楽しいからこうして「マスカレード」に向かっているだけだ。不謹慎だが仕方ない。もしかしたら良い情報を入手して、安太の身の安全に貢献出来るかもしれないじゃないか……なんてぬるい言い訳も必要ない。
神妙な顔を作ろうともせず、俺は夜の街を急ぐ。同期の結婚式? そんなつまらないもの、出席なんかするもんか。だったら粗悪な風俗に引っ掛かって病気を移された方がまだマシだ。
ちょうど二十分で「マスカレード」に到着。先客は一人、カウンターの一番奥に座っている彼が「おしぼり屋」に違いない。細身のジーンズにピチピチの無地白Tシャツ。シンプルだからこそ着こなしづらい格好だ。いや、分かっている。彼が誇示したいのは服ではなく肉体だろう。
太過ぎない首や腕、厚過ぎない胸板、所謂「痩せマッチョ」タイプ。俺と目が合うと椅子を降りて「よろしく」と一礼、そして近寄ってきてガッチリ握手。ちょっと苦手なノリだ。わざわざ距離を取るのもおかしいので、流れに任せて彼の隣に席を取る。
そんな彼、おしぼり屋の右田ケン氏は俺と同じ歳。ナオ曰く、高校と大学、そしてOB絡みのパーティーで「絶対に何度か」顔を合わせているらしい。もちろん互いに覚えてはいなかった。
右田氏は中学受験で大学の附属校に入り、遊びながら大学を出た俺の「同類」……ではない。彼の母校は六大学。俺なんかとはまるでレベルが違う。正直なところ、「おしぼり屋」という職業がピンと来ない。
「別におしぼりオンリーって訳じゃないんですけどね。あ、何飲みますか?」
彼と同じくブラッディ・マリーをナオに頼む。ここで酒を飲むのは久しぶりだ。毎度ありでーす、とおどけたナオは「ケン坊、前置きはいいからさ、ちゃちゃっとね」と右田氏に話を急かす。
「はいはい。そうですねえ、おしぼり以外の商売道具は足拭きマットとか絵、絵画かなあ。あ、あとは観葉植物。これでさすがにピンと来ませんか?」
いつの間にかクイズになっていた。しかも難問だ。観葉植物にいたっては、頭にイメージ画像すら浮かばない。ナオに救いを求めるが、カウンターの中で微笑みながらブラッディ・マリーを作るだけ。ちょっと浮かばなくて……すいません、と答えると「そりゃあそうですよねえ」と何故か楽しそうな右田氏。笑う度に胸や腕の筋肉が動く。左の袖に透けているのは刺青だろう。その柄までは分からない。

「昔風にいうなら、みかじめ料です。そこで営業するなら納めてほしい、と。その代わりトラブルがあったら処理させてもらいます、っていう関係性。何となく察しは……」
ヤクザですね、とはさすがに言えないので、ちゃんと目を見て「はい、分かりました」と微笑んでみせる。どうして申し分のないキャリアを持ちながら、という質問はまだするべきではない。
所謂暴力団対策法以降、警察や世論がうるさく、大っぴらにみかじめ料を要求しづらい。なので、おしぼりや観葉植物といった「隠れ蓑」をリースして、店から金を巻き上げているらしい。頭いいな、というのが正直な感想だったが、もちろん顔には出さない。
「まあ御存知でしょうけど、このやり方もずいぶん古くなっちゃって、今ではかなりレアなんですよ。だって暴力団対策法って、俺らが高校の時ですよ?」
右田氏はタバスコをたっぷり入れたブラッディ・マリーを一気に飲み干すと、今回の件に関しての説明を始めた。つまりはこうだ。
以前、オムライスが有名だったカフェバーの頃は、おしぼりを毎月納入出来ていた。ところがオーナーが替わり、「ランブル」になった途端、おしぼりの納入を拒否してきた。そうは言っても恐ろしいヤクザでいらっしゃるんですから、という俺の表情を読み取った右田氏は大袈裟に頷く。
「でも、あまり強硬にやってもねえ。あの店自体そんなにデカい店じゃないし、無理矢理絞めて大騒ぎになるのは困っちゃうんですよねえ」
結局、「ランブル」の処遇は上の判断で「保留」扱いになった。それが半年前。
「そしたら、今回の話でしょ? この街でボッタクリとはねえ。いったい何考えてんのかなあ。ねえ?」
一貫して右田氏は喜怒哀楽が分かりづらい。いや、立場だって分かりづらい。そもそも彼はヤクザなのか? それとも半グレなのか? まあ、どっちにしても俺ごときに分かることはひとつ。安太を脅かす餃子耳の男より、この右田氏の方がブラックだということだ。
「そういえばさ、そっちは何か分かったことあるの?」
ふと会話が途切れた時にナオから訊かれた。確かに今まで何の報告もしていない。ナオが知っているのは、俺が経験したボッタクリ未遂の一件だけだ。
出来れば安太の名前は出したくなかったが仕方ない。これまでの一部始終をほぼ全部話した。餃子耳の男が子分を引き連れて現れたコンビニ襲来の件、三日前の家の近所で御挨拶の件、そして突然の警察官訪問の件――。時折ナオは心配そうな表情でこっちを見ていたが、右田氏はずっとニヤニヤしながら俺の話を聞いていた。思わず言葉に熱が入る。
「でも結局、彼自身は何も知らないんですよ。その餃子耳の男の名前だって分からないんです」
多分すぐに分かるよ、という右田氏の言葉に飛びつけなかったのは、彼がグレーよりも濃いブラックだからだ。どういう人物なのか、ナオからちゃんと聞いておくべきだったな、と思う間もなく「どうします?」と畳み掛けてくる。
「そいつの名前くらいすぐに分かると思うけど、どうします? ちょっと調べてみましょうか?」
本当なら断りたかった。この手の人物に借りを作ってはいけない。どうして安太の為に俺がここまで、とも思った。でも、もう引き返せないことは右田氏の表情を見れば分かる。今更「撤退」や「保留」は選べない。彼はきっとブラックだ。
「あ、申し訳ないです。どうか、宜しくお願いします」
俺はペコペコしながら自然と敬語を使っていた。
(第05回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『助平ども』は毎月07日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
