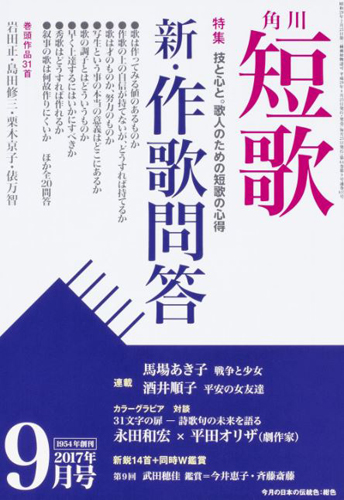
今号の特集は「技と心と。歌人のための短歌の心得 新・作歌問答」です。窪田空穂の『作歌問答』(大正四年[一九一五年])をベースに歌人の心得を今一度確認してみようという特集です。『作歌問答』は読者歌人から寄せられた質問に空穂が答えた本です。特集では当時の読者の問いと空穂の回答を抄出掲載しさらにその意義を現代歌人が解説しています。
質問 歌は才のものか、努力のものか
読者
回答 歌は詩才でも努力でもありません、人間である人のものです。人間であって、自身の思ふ事を言ひ現してみようといふ、自身に対しての愛着を持つてゐる人の専有すべきものです。詩才、努力――さうしたものもあつても差閂はありませんが、無かつたからつてかまひません。
窪田空穂
現代歌人の解説 この一見単純な質問の背後には、かなり複雑な問題が控えているようだ。(中略)世の中には明らかに才能を感じさせる人もいる。ただ、才能がすべてではないし、へたをすると才能が邪魔をすることもないではない。歌会などで高点を得る、小洒落て小綺麗な、小才の利いた歌などはその典型で、読者の受けを計算し、それに対応できるのは才能だが、そんな歌は本物ではない。おそらく空穂はそう言いたかったのだろうし、私もそう思う。
自分が歌を愛していること、そして作歌に喜びを感じていること、この必要にして十分な条件に満足できていれば、克服できる疑問なのだ。
桑原正紀
空穂の回答も桑原さんの解説も真っ当なものだと思います。ただお二人の先人の言葉が腑に落ちるまでには長い時間と短歌が置かれた厳しい現実の認識が必要でしょうね。そのあたりのことをちゃんと説明するのはなかなか「複雑な問題」です。五十代後半くらいになった歌人はお二人の言葉の真意が理解できるでしょうが若いうちは難しいと思います。
短歌は自己表現の道具でもあります。歌人に強い自我意識つまり社会的栄達意欲があるのは当然です。実際空穂や桑原さんはいわば歌壇で功成り名を遂げた集団に属しているわけで本気度が違うとはいえ年を重ねても万年投稿歌人や結社の一員に過ぎない歌人とは一線を画します。そんな歌壇VIPたちが「歌は詩才でも努力でもありません」と言ってもなかなか納得できないと思います。周囲から頭一つでも二つでも抜け出したいと願うのは創作者の常でありそのためには才能が必要で目立つ歌を作るのが当然と考えるでしょうね。
端的に言えば空穂や桑原さんの言葉には社会的つまりは日本文学で短歌が置かれた現実への断念があります。はっきり言えば短歌である限り流行小説家のような有名人にはなれない。あるいは短歌でポピュラリティを求めても一過性の新し味や流行で終わる。そんなことをしていたのではいつか短歌から離れ歌を止めてしまうだろうということでもあります。短歌に限りませんが経済的社会的見返りがあまり望めない詩の世界では詩を本当に愛しているかどうかが創作を続ける原動力になります。それを考えれば多少の才能よりも「自分が歌を愛していること、そして作歌に喜びを感じていること」の方が重要です。
もちろんこういった認識を現実との戦いに敗れ疲れ切った年寄りの戯言と受け取ることはできます。若い歌人がそう考え従来とは違う方法で世の中に出ていこうとするのはとてもいいことです。作風も変わる面があります。ただ道筋を間違えると悲惨なことになります。詩という日本文学のマイナージャンルの現実の壁を越えて社会的・経済的栄達を求める詩人は昔からいました。詩史を細かく検証すれば大正時代くらいからいた。何か新しことを成し遂げようとするなら足下の陥穽にも十分気を配らなければなりません。
今年は俵万智『サラダ記念日』刊行三十年ということで、リバイバルブーム的な俵万智の刊行ラッシュとなっている。その一環として出た『文藝別冊総特集 俵万智 史上最強の三十一文字』(河出書房新社)の表紙は、二〇一七年現在の俵万智が『サラダ記念日』の表紙と同じポーズで「セルフカバー」をしているポートレートだ。
表紙に人物モデルを起用した歌集というのは意外と少ない。河出書房新社の「同時代の女性歌集」シリーズには著者本人のポートレートが使われているが、ほぼそれくらいだと言っていいだろう。(後略)
(山田航 歌壇時評「現代文学地図の中の短歌」)
山田航さんは将来を期待されている若手歌人です。ただ歌壇時評「現代文学地図の中の短歌」を読んでいるとジャーナリズムに毒されているのが手に取るようにわかります。俵万智さんのベストセラー歌集『サラダ記念日』を刊行したのは河出書房新社でこの版元が中心になって「『サラダ記念日』刊行三十年」といった出版や特集を組むのは当然です。これは文学的評価ではなく主に経済的目的です。また山田さんは表紙にポートレートを使った歌集や出版物について延々と書いておられますがこういったジャーナリズム小僧的な目配りは作家には基本的に不要です。本の装丁が文学を変えることはありません。考えるべきことはほかにある。
山田さんはまた同じく河出書房新社が刊行している小説文芸誌「文藝」の特集「現代文学地図2000→2020」についても書いておられます。引用はしませんが山田さんの論旨は短歌を小説を含めた現代文学と同じ質の文学として盛り上げようということにあると思います。しかし難しい。大昔に荒川洋治という現代詩人が「詩で芥川賞を獲る」と言ったことがありますが詩人らしい勘違いです。そもそも芥川賞は獲るものではなく貰うものです。文藝春秋社文學界が中心になって候補を選び選考委員の責任でその中から芥川賞が授与される。当然文芸五誌つまり文學界・新潮・群像・すばる・文藝に社会的・経済的に寄与した小説家にしか基本的に賞は授与されません。小説の世界の賞は社会・経済原則と密接にリンクしており歌壇の賞の方がまだそういった軛がないと言えるくらいです。
何を言いたいかというと特集「現代文学地図2000→2020」は文藝の小説文壇での自己差別化と生き残りを賭けた特集でありそこで引かれた「現代文学地図」という見取り図が小説文壇一般に影響を与えるものではないということです。また河出書房新社は小説出版社としては弱い立場にありそれこそ『サラダ記念日』のような小説外の文学に目配りをすることで独自性をアピールしてきました。しかしだからといって河出書房新社が本気で詩書出版に乗り出すことはない。詩を取り上げてもそれは常に小説の刺身のつまだということです。それを認識しておかないとジャーナリズムの都合に踊らされることになります。
山田さんはまた「文芸誌とそれによって成立する文壇的な空間には現代の言葉のリアルが欠けていて、興味を持てない。それよりも「個人」や「自意識」を解放してくれるネット空間にこそ言葉のリアルはあふれている」と書いておられますがうーんどうかな。ちょっと度を超したジャーナリズムへの目配りを書いておいて「興味を持てない」はないんじゃないか。角川短歌であれ文藝であれ原稿依頼があり歌壇や文壇で目立つことができるなら「文壇的な空間」を簡単に〝大政翼賛〟する姿勢が透けて見えます。信用できないな。自分はネット世代を代表しているというアピールにしか見えず文章に一本筋が通っていない。
七十代以上のネット・フォビア世代には有効でも五十代くらいはもちろん十代二十代の世代にも「「個人」や「自意識」を解放してくれるネット空間にこそ言葉のリアルはあふれている」という言葉は響かないと思います。食傷しています。それに続く新たな認識も決定的作品も現れない。短歌で文壇はもちろん社会一般でも認められたいという欲望を抱くのはいいことですがそれにはまず短歌を社会全体から見回して相対化する必要があります。短歌インサイダーでいたのでは必ず思考が内向きになります。つまり短歌外の文学ジャーナリズムの動きに翻弄されながら結局は短歌事大主義に陥ってしまう。〝短歌である限りここまで〟という断念と絶望を抱え脱落しがちな結社員を励ましながら短歌に邁進する結社主宰の方が社会的栄達の邪念からは解き放たれていて自由かもしれないですよ。
人の手が光をつくるさまを見つ薩摩切子という名の光
うつぶせに鍼刺されればにぎやかに我の背中に集う人々
足三里に灸すえられてわたくしの奥の細道どこまで行こう
みちのくの母の命のよみがえりスミレの花のような毒舌
青ざめて胃の腑おさえる男の子 心豊かに今日は傷つけ
大中小の黄身並びおり命とは順番ありて生まれ出るもの
火をおこし肉を焼くこと人類の一員として君たちを見る
二度寝して見る夢甘し冷蔵庫のマンゴー今日は食べてしまおう
水辺には子どもらのの声泡立ちて虹のシャボンが次々と発つ
さんしょの実摘みつづけたる七月の午後の指先ひりひりと辛い
迷いつつ「いいね」押すのをやめておく君の週末遠い八月
まぶたふと閉じるがごとし時がきて自動で消える廊下の灯り
(俵万智「どこまで行こう」より)
今号には俵万智さんが「どこまで行こう」連作を掲載しておられます。口語短歌と言えないことはないのですが内容的には口語か文語かに執着しておられない作品です。俵さんは言うまでもなく口語短歌を一般に知らしめた歌人ですがその後の歩みは自由です。旧世代と新興口語短歌世代のせめぎ合いにもまったくと言っていいほど興味を示さず淡々と歌を詠んでおられる。
なぜ俵万智さんという歌壇内ではそれほど強い影響力を持たない歌人が一般社会で最も有名なのかを考えてみるのは意味のあることだと思います。しかし一方で〝世の中そんなもんだ〟といった達観も必要でしょうね。誰もが驚き舞い上がってしまうような賞賛の嵐に包まれても歌人がやるべきなのは淡々と歌を詠むことです。短歌に限らず文学表現のゴールが社会的栄達にはないのは確かなことです。
高嶋秋穂
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■











