 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
第05回 (二)象の頭
「それでは、今度はその象は、自分の頭をのこぎりで引くことができるでしょうか?」
「むーん」
って、月かよ。ふたたび真剣に考え込む種山。だから、もうっ。
ややあって、顔をあげる種山。
「いくつか方法はあるとは思いますが、この状況では難しいですね」
「でしょ」
でしょ、でしょ。早くそれを言いなさいよ、まったく。
「覚悟はいいですか、先生。この事件は、ここからもっと猟奇的な様相を呈するんです」
「ほう、猟奇的」
再び種山の顔に光がさした。
「なんと、被害者は首を切断されて持ち去られ、代わりに象の頭がそこに据え付けてあったのです」
「おお! それはまさに」
と、種山は荒い息遣いで口走った。
「ガネーシャじゃないですか」
ガネーシャっていうのは、聞いたことがある。確かインドの象の顔をした神様だ。

「いいですか、先生」
まったく落ちつけよ、と胸の内で毒づくわたし。
「問題はここです。象には共犯者あるいは象使い的な仲間がいた。あるいは犯人自身が象使いであったという可能性もあります。いずれにせよ、象に被害者を踏み殺させた後、その共犯者あるいは象使いは、被害者の首を落とし、さらにはあろうことか象の首まで落とした」
「そして、被害者の首と、象の体を持ち去ったというわけですか」
「そうなりますね」
「密室の中から?」
「ええ」
「少なくとも四トンはある象の体と、血まみれの人間の頭を抱えて出て行ったと」
「そうなりますね。状況からすれば」
「どんだけ怪力なんでしょうか、その犯人は。それとも、共犯者は複数名いたということでしょうか」
「さあ、どうでしょう」
「それも、壁抜け能力をもった数名の共犯者ということですよね」
「さあ、どうでしょう」
なにもかもがありえなかった。だからこそわたしはこんなところまでやってきたのではないか。何もわかりませんねえ。それにしてもすごい事件です。難解で、想像力を刺激する事件ですねえ、なんて感想を聞きに来たわけじゃないのだ。
「で、どうでしょうね、先生」
こうなったら、どうでしょう攻撃だ。
「どうでしょう、とおっしゃられますと?」
「ですから、犯人とか犯行方法とかお分かりになりませんか?」
「いや、いろいろ絵は思い浮かんでいるんですけど、ここでひとつ質問いいでしょうか?」
「はい、どうぞ」
種山君。とはさすがに言えなかった。
「つまり、残されてたのは首がない死体だったってことですよね」
「ええ、まあ、象の首はついてはいましたけど」
「とすると、どうして被害者が先ほどおっしゃっていた、ええと誰でしたっけ」
「橘滋郎、四十歳ですか」
「ええ、そうです。その会社経営橘滋郎、四十歳だってわかったんでしょう?」
「そこなんですが」
そこを、わたしに言わせようっていうのかい、おじさん。困り果てた乙女なわたしは、姉からのアドバイスを思い出した。
「そこんとこはね、上野公園で犬を連れてるあの銅像を出せばいいわ」
そんな風に姉に告げられたのだ。
「間違いなくそれで先生には通じるから」
太鼓版まで押してくれた。だから、わたしはそのまんま投げてみることにした。
「実は、西郷隆盛だったんです」
「えっ」
怪訝な顔。なんだ、だめじゃんこの人。お姉ちゃん、だめだよ、通じなかったよ。と胸の内で叫んでいたところ。
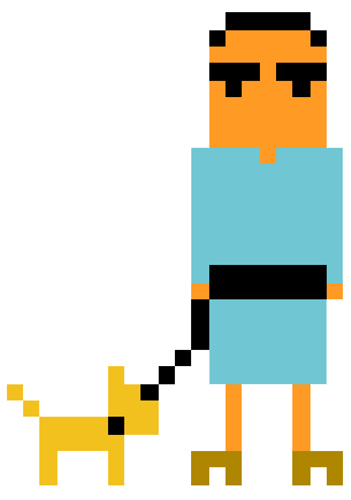
「フィラリアですか?」
いきなりそう問われたので逆にわたしが、
「えっ」
と当惑させられる羽目に陥った。
「『膝栗毛』に出てくる、泊めざるは宿を疝気と知られたり、・・・ってやつでしょ?」
えっ、えっ? さらに面食らうわたし。アッパーどころか、カウンターくらった感じでよろめいてしまう。
「つまり、こういうことですね。被害者には西南戦争で命を落とした西郷隆盛と同じく首がなかった。そして、西郷隆盛がその人だと知れたのは、バンクロフト糸状虫によるむくみが足と足の間に垂れ下がるものを膨らませていたからだ。確か、人の頭位に膨らんでいたとか。それと同じ状況があったと、そうおっしゃるわけですね」
「そうなんです」
やっと話がつながった。
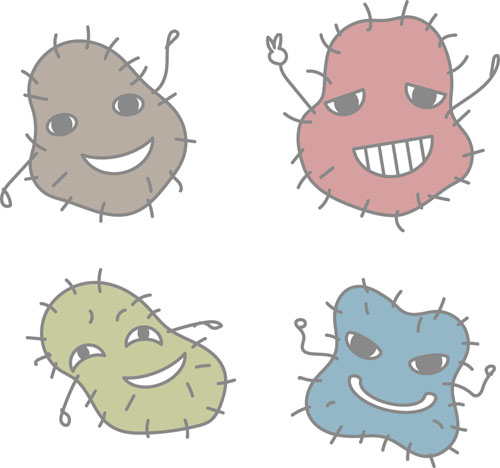
「被害者が、二年前に、おそらくは人目をはばかってでしょうけど、小田原の病院まで赴いて治療を受けていたことがわかったんです」
検死の際に股間を覗きこんだ小田原の医師は(っていうかこの人わざわざそんなものを見るために東京まで出てきたわけよね。そう考えるとなんかかわいそうになっちゃうんだけど)多少回復の傾向はみられるけれども、自分の患者に間違いなかろうって答えたらしい。「なんせ、いまどきこんな病気にかかる患者はめったにいないからね」とおっしゃっていたとか。
「ふーん。なかなかのタブローですね」
満足そうにうなずく種山。あたかも最上級のチーズケーキと、馥郁たる香りのハーブティーを口にしたときのような満足度を感じさせる顔つきだった。
「タブローって、絵のことですか」
「ええそうです。国芳風にいえば、猫尽くしならぬ、象尽くしですね」
「象尽くし」
「ええ、だってそうでしょう? 象の足跡、象の首、そして象皮病ときているわけですから」
「象皮病?」
「ええ、そうです。フィラリア由来のむくみを生じる病のことを、俗に象皮病と呼ぶんですよ。皮膚が象の皮膚のようにごわごわになるからです」
「それにしても、どうして絵なんです」
イメージという意味だろうか? 変わった表現を使う人だと思った。
「だって、こういう事件の場合やっぱり重要なのは推理でしょ。それは論理の世界なんじゃないですか? 絵っていうのはむしろ、感覚的というか、直感的というか」
「実はわたしはちょっとばかり、絵の解読の訓練を受けたことがありましてね」
「へえ、絵の解読ですか」
変ってますねえ、と言いかけてやめた。

「ドイツのヴァールブルグ研究所というところだったんですがね。若いころに少しばかりお世話になっていたことがあるんですよ。それで、まあなんというか、論理よりは直感、演繹や帰納よりは連想や類比を重んじる方法論を学びましてね。わたしなりに発展させたそれをわたしは結合術なんて呼んでるんですけどね」
「じゃああれですか」
わたしは問う。
「先生は、理詰めで考えられるタイプではないんですね」
「だって、しんどいじゃないですか、それって」
なんでもないことのように、言ってのける種山。
「それに、生真面目な感じで面白くないし、なにより」
「なにより、・・・なんです?」
わたしはさらに問う。
「驚きがない」
なるほど、そこへ落としたか。自分の博物館につなげたわけだ。とはいえ先生、残念ながらここ博物館じゃないからね。どうみてもただのラブホだから。
「とにかく」
そうとにかく、手ぶらでは帰れないのだ。このわたしは。
「直感でも、連想でも、類比でもいいから、なにか思いついたことを教えてくださいよ」
(第07回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



