 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
第05回 (二)象の頭
「ではいよいよ、犯行現場の様子をお伝えします」
「はい」
はい、じゃないよ。待ってましたでしょ、そこは!
「被害者は腹部に烈しい打撲傷がありました。内臓破裂および、肋骨の一部が折れており、背骨にもひびが入っていました。頭部にも打撲の跡がありましたが、こちらは致死的なものではなかったようです。死亡推定時刻は夜の十時から翌日の午前一時の間とされています。状況からみて、かなりの重量のものにぶつかった、あるいは押しつぶされたのであろうと考えられています。」
「なるほど。重いものね。で、可能性としては」
「ええ」
思わず唾を飲み込んでしまう。あまりにシュールなので、さすがのわたしも口にするのが一瞬憚られたのだ。
「実は、部屋中に象の足跡が残されていたんです。かなり暴れたようで、足跡はとても乱れており、数も多かった。事件の前の晩は激しい雨が降っていましたので、おそらくその象は雨のなかを歩いて来たのではと推測されています。なぜなら、泥水がくっきりと部屋中に足跡を刻んでいたからです。そして、被害者の腹部にも、同じ跡が」
「ほおっ」
「足跡と、被害状況から考えて、少なくとも体重四トンから五トン、体長二・五メートルから三メートルはある成獣のインドゾウであると考えられるのだそうです」

この辺りは姉から聞いたのを、わたしがメモったものに基づいての報告である。その辺の法医学的な資料はさすがに見せてもらえなかったけど。
「とすると、東京郊外の山道を、真夜中にどこぞの動物園から逃げ出した象がのっしのっしと昇ってきたというわけですね」
「ええ、まあ。でも、調べてみたところ、どこの動物園からも象が逃げたという形跡はなかったんですよ」
上野動物園、多摩動物園、井之頭動物園に「お宅の動物園から、昨夜象が逃げませんでしたか」なんて問い合わせてる刑事の姿をイメージするとちょっと笑える。
楽しそうに聞いていた種山が、ふと真顔になって聞いてきた。
「でも、おかしいですね。その部屋の天井までの高さは?」
「およそ二・二メートルだそうです」
「ふうん。ってことは、少し背の低い象だったのかな」
「でも、窮屈ですよね。ぎりぎりの高さですから」
「狭いゾウ!」、ってか?
「では、部屋の入口の扉の大きさは? あるいは大きなテラスの窓でもありましたか?」
「いいえ、確かに山荘の一階には高さ二メートル以上の、大きな窓が入ったテラスがありました。でも、問題の部屋は二階の書斎だったんです」
「ええっ、じゃあ象さんは階段を上ってきたってわけですか」
「状況からすると、そうなるんですけど」
でも、階段にも廊下にも象の足跡は見られなかったのだと、わたしは説明した。
「現場の部屋には、窓はありました。南向きと東向きにそれぞれつけられた窓で、いずれも縦七十センチ、横九十センチのすべり出し窓でした」
そう、おかしいのだ。明らかに。
「扉は高さ一メートル七十で、幅が八十センチ」
「幅が八十センチ? ずいぶん、小さめな扉ですね」
「ええ。この山荘は、元の持ち主の方の体形に合わせて作られたものだったそうで、全体にかなり小ぶりな作りになっていたようです」
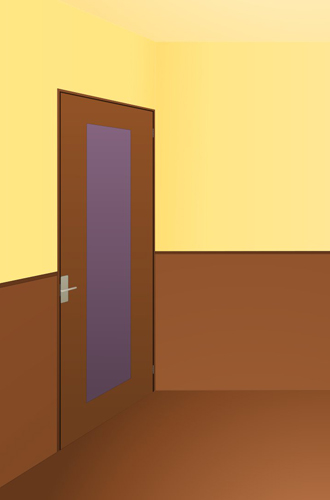
部屋自体も、縦横一メートル八十の正方形で、仕事机を置けば、他に何も入らないような小さな部屋だったとわたしは報告した。でも、調べによると、被害者はむしろこの書斎の狭さが気に入ってこの山荘を購入したのだということだ。
いわゆる、居心地のいい隅っこってやつだろうか。トイレに籠る感覚だったのかもしれない。
「ほかに、開口部のようなものはなかったの」
「実はあるには、ありました」
「ほおっ」
「その扉の上に曇りガラスがはいった縦三十センチメートル、横二メートル強の欄間がついていました。そして、その曇りガラスには何かで叩き割られたらしく、およそ子供の握りこぶしくらいの小さな穴が開けられていたのです」
「ふうん」
それを聞いてはっと目をあげる種山。
「そこだけ密室ではないわけですね。密室には小さな穴が開いていたというわけですね」
「ええ、でも、象は通れませんよ。だって、体長二メートル以上は絶対あったわけですから。それに、体の幅だって八十センチってことはあり得ないから、ドアからも入りようがなかったはずなんです」
見れば種山は微笑んでいた。明らかに楽しんでいるのだ。頭蓋骨の中で脳細胞がわくわくぷちぷち飛び跳ねている音が聞こえてきそうな感じだった。
「ということはあれですね」
「は?」
「自然発生説的なあれってことになりますね」
「自然発生説?」
「ええ、パスツールが十九世紀に病原菌を発見するまで信じられていたあれです」
「で、なんですか?」
「だから、あれですよ。病原菌は無から発生するという考え方です。あのアリストテレスだって、ハチやホタルが草の露から生まれてくるとか、タコやエビが海の泥から生まれてくるなんて信じてたんですよ。十七世紀ごろでもネズミやらカエルやらが何もないところから発生したって主張する科学者がいたくらいです。日本でも言うでしょ、ウジが湧くとか。ああいうのも、自然発生説的な世界観なんですよ。つまりまあ、そういうあれです」
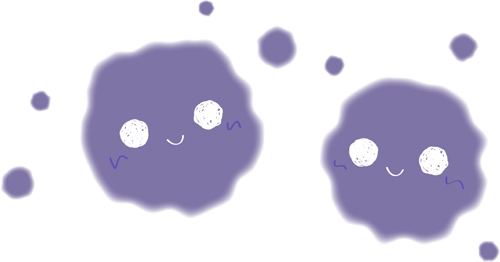
ようやく理解した。
「つまり、殺人現場の密室の中で象が自然発生したと、そうおっしゃるわけですね」
「ええ。だって、どう考えたってその部屋に象は外からは入れない。それに、家の外にも足跡はなく、階段にも足跡がない。部屋の中にだけそれがごまんとあるってわけでしょ?」
やっぱだめだよお姉ちゃん、この人。頭おかしいって。
「おや」
わたしの顔を見て、種山が微笑んだ。
「いまあなた、わたしのことを頭がおかしな人だって思ったでしょ」
「ええ」
ぶっきらぼうなわたし。
「でも、どうでしょう。少なくとも、この状況だけを聞かされたら、そう考えるしかないんじゃないですか?」
「だから、そうとしか見えないこの状況を先生の頭脳によって解きほぐしてもらうためにですね」
「あなたはきたわけですね」
うんうん、うなずいている。ああ疲れるわ、この人、ほんと。
「ええそうです。それに、謎はそれだけじゃないんですよ。共犯者がいたと考えられるんです」
「共犯者? もしかして、そいつも象ですか」
「いいえ、たぶん人間です」
ああ、と種山の顔に失意の色が浮かんだのをわたしは見逃さなかった。どんだけファンタジーに浸りたがってるんだろ、この人ときたら。

「でも、どうして共犯者がいると? そしてそれが人間だとわかるんです」
「ちょっとお聞きしますが先生」
「ええ、どうぞ」
「象にのこぎりは引けるでしょうか?」
「ううん」
いきなり真面目に考え込む種山。おいおい、そういう種類の問いじゃないんだってば。ややあって、種山は考えをまとめるように、
「よほど訓練すれば、なんとかならなくはないでしょうけど」
と答えた。さらになにか言いたげなのを遮って、
「じゃあ、仮にそれができたとしましょう」
とにかく話を進めることにした。
(第06回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



