 久しぶりの故郷。思い出したくない過去。でも親族との縁は切れない。生まれ育った家と土地の記憶も消えない。そして生まれてくる子供と左腕に鮮やかな龍の入れ墨を入れた旦那。それはわたしにとって、牢のようなものなのか、それとも・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑による連載小説第3弾!。
久しぶりの故郷。思い出したくない過去。でも親族との縁は切れない。生まれ育った家と土地の記憶も消えない。そして生まれてくる子供と左腕に鮮やかな龍の入れ墨を入れた旦那。それはわたしにとって、牢のようなものなのか、それとも・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑による連載小説第3弾!。
by 寅間心閑
二 (前半)
私は佐賀にあるじいちゃんの家で育った。
最初に母親が消えたのは二歳の時。父親についてはほとんど知らない。小学生の頃、私が産まれた時の苗字は「井上」だったと知らされた。こっそり「イノウエミワコ」と口に出してみた記憶がある。自分の中に自分の知らない部分があるような、とても変な感じがした。物心がついてから私の苗字はずっと「田辺」で、去年結婚をして「宮野」になった。ミヤノミワコ、という響きにはいまだに慣れない。
消えた一年後、つまり私が三歳の頃、赤ちゃんの佳奈美を連れて母親が帰ってきた記憶は微かに残っている。帰ってきたのは二人だけで、父親にあたる人はいなかった。その人は「井上」とは違うと思うが真相は分からない。当然あの子も知らないはずだ。
そこから六年間だけ、私たち姉妹は一緒に暮らした。じいちゃん・ばあちゃん・母親との五人での暮らしはとても楽しかった。段々と成長する赤ちゃんの佳奈美は可愛かったし、じいちゃんは荷台付きの軽トラックで何処へでも連れて行ってくれた。
私のお気に入りの場所は、駅名にもなっている広大な松原を抜けた先の海岸で、特に冬の夕方に行くのが好きだった。人気のない白い浜辺を走り回り、時折振り向けば、車から降りて煙草を吸っているじいちゃん。家に帰れば母親とばあちゃんと可愛い妹。そのことを確認する度、大きな安心感に包まれた。

しかし、母親はまた私の前から消えてしまう。小学校三年の冬、二学期の終業式の日、通知表を持って学校から帰るといなくなっていた。しかも、春から小学生になる佳奈美を連れて。
私は悲しくて、冬休みの間中ずっと閉じこもっていた。じいちゃんの釣り道具や、ばあちゃんの着物を置くための狭い部屋。エアコンもストーブもないので、ダウンジャケットにマフラー姿で本を読んでいた。もちろんテレビなんてない。
毎年、大晦日と三箇日は賑やかだ。太ちゃんの家族や泰邦おじさん夫婦が訪ねてきて一緒に年を越す。ただ、あの年はいつもと違った。お正月らしくない大人たちの深刻めいた話し合いが繰り返され、私は寒い部屋でひとり、取り分けられたおせちを食べていた。
悲しいだけではない。恥ずかしかったから私は一度も顔を出さなかった。母親に置いていかれるのは、とても惨めだ。鍵のない部屋だったが、ばあちゃんが食事を運んでくる以外誰も入ってこなかった。寒くなかね、と訊かれたって答えない。トイレもわざわざ庭に出て、物置の隣にある簡易型を使っていた。
三学期が始まっても、四年生になっても、母親と佳奈美は帰って来なかった。夏休みに入ってから、太ちゃんの家で暮らすことになったので、友達や先生に別れを告げられないまま転校をした。
太ちゃんの家は電車で十分弱だが県境を跨ぐ。佐賀県ではなく福岡県。それもまた心細かった。必死に頼めば太ちゃんの家から元の学校に通えたかもしれない。そもそも転校などせず、太ちゃんの家にも行かず、これまでのようにじいちゃんの家で暮らせたかもしれない。
でも、ひとり置いてきぼりにされた私にそんな力は残っていなかった。ただ言われるがまま引っ越しの準備に取り掛かり、荷台付きの軽トラックで太ちゃんの家へと送られた。この車に乗るのも最後なのかな、とぼんやり考えていた私に、「美和子のためやけん」とじいちゃんは繰り返した。

「あの家におるよりよかろうもん。心配せんでよか。全部、美和子のためやけんね」
今ならば納得できる。親のいない小学生は祖父母と暮らすより、同じ年齢の従兄妹の家に預けた方が何かと都合がいいだろう。でも当時の私に大人の理屈は通じない。ふてくされる余裕もなく、ただただ諦めきっていた。あの頃からずっと、もちろん今だって私はどこか脱力している。
太ちゃんの家は庭がある一軒家で、二階に専用の部屋を用意してくれた。ドアには「みわこ」というコルクのプレート。自分だけのスペースを持つのは初めてで、とてもワクワクした。「初めて」はそれだけではない。太ちゃんのお母さんは夕食の買い物を手伝わせてくれた。
私は前から、それこそ自分の母親と暮らしていた頃から、彼女のことが好きだった。テニスを習っているからか、とても若々しかったし、女優のように派手な目鼻立ちにも少なからず憧れていた。買い物に行くのはほぼ毎日。学校から帰って少しすると、「そろそろ行くよ」と部屋まで呼びに来てくれる。
「男の子とスーパーに行ってもつまらんたい。だけん美和子、買い物には付き合ってもらうけんね」
道すがら献立をどうするか話し合ったり、店内でああでもないこうでもないと言いながら品物を選ぶのは楽しかった。帰ってからは食事の支度のお手伝い。これも楽しい。私の母親は家事をしない人だった。
太ちゃん一家は以前と変わらず接してくれたので、私は明るく振る舞えた。自分が明るくしていることが、迷惑をかけない一番の方法。それくらいは分かっていた。けれど、置いてきぼりにされた悲しみはどうにもならない。母親のことを考えない日はなかった。なぜ私は置いていかれたんだろう、きっと私より佳奈美の方が好きなんだな、と奥底の方で嘆き続けていた。
嘆きは液化する。気を抜くと目から溢れてしまうので、危なくなると自転車をこぎ、あの大好きだった海岸を目指した。片道一時間もかかったが仕方ない。太ちゃんの家に迷惑はかけられない。自転車から降り、松原の中をしばらく歩くと海が見えてくる。白い浜辺をギザギザに歩きながら深呼吸を何度も繰り返す。何度も何度も繰り返すうち、嘆きは蒸発して空気に紛れていく。もちろん、効き目は長く続かない。一時しのぎの拙い対処法だ。
母親のことを毎日毎日考えてはいたが、会いたいとは思わないようにしていた。特に中学生になってからは、佳奈美を選んだ人になんか会っても仕方がない、と自分に言い聞かせた。悲しい負け惜しみだが、そうでもしなければ私はおかしくなっていただろう。
太ちゃんの家に引っ越した後も、大晦日と三箇日はじいちゃんの家で過ごした。当然、母親も佳奈美もいない。会っても仕方ないと思っているのに、どこか期待している自分が腹立たしい。置いてきぼりにされて以来、年末年始がとても憂鬱だった。
太ちゃんのお母さんから「佳奈美に会いたかね?」と尋ねられたのは中学二年の春休み、一緒に昼食の支度をしていた時だった。突然の質問に驚きながら、「カナミ」という響きを耳にするのは久しぶりだなと考えていた。
「実はさ、昨日佳奈美から電話があったったい。姉ちゃんと会いたか、って」
私も会いたか、と即答したが、お母さんは会いに来てくれないんだ、と気持ちの奥で落ち込んだ。数日後、佳奈美と待ち合わせる場所が唐津だと告げられ、更に悲しくなった。じいちゃんの家から唐津まではバスで二、三十分。そんな近くに住んでいるのに、どうしてお母さんは会いに来てくれないのか!
当日、ハンバーガー屋で五年ぶりに私たち姉妹は向き合った。あの子は小学校五年。入学前の印象しかないので、内心初めて会うみたいだと緊張していた。どう呼んだらいいかと迷ったが、勇気を出して「佳奈美さあ」と話しかけると嬉しそうに微笑んでくれた。

「姉ちゃん、って呼んでもよか?」
そう尋ねた佳奈美が本当に可愛くて、一緒に住んでいた頃の気持ちや、私たちは姉妹なんだという感覚をすぐ取り戻せた。好きなテレビ番組やマンガの話など、とりとめもなくおしゃべりは続いたが、住んでいる家についてはお互い一切尋ねなかったし、話さなかった。
ただバッグに付けていたキーホルダーについて、「お父さんが買ってきたと」と言っていたので、佳奈美の住む家には「お父さん」がいることを知った。もしかしたら、苗字も「田辺」ではなかったのかもしれない。あの日、私たち姉妹は「姉ちゃん」「佳奈美」と呼び合うだけだった。それは今現在にも繋がる話で、私は佳奈美のフルネームを知らない。
斎場からホテルへ帰る途中、近くのコンビニで買ったのはサンドイッチとコーンサラダとカップヌードル。妊娠してから、やはり食べる量が増えている。何となく十キロ以上は体重が増えると思っていたが、せいぜい六、七キロと医師には言われた。太りすぎも良くないらしい。
九月下旬の空は少しずつ暮れ始めていて、ホテルの部屋の窓には難しい顔でサンドイッチを食べる私がうっすら映っている。さっきから考えているのは苗字のことだ。
私の目の前で記帳をし、お香典を出す佳奈美。ちゃんと袱紗に包まれていたことが意外で目に焼き付いている。けれど香典袋に記されていた苗字は思い出せない。その代わり、くせの強い佳奈美の字が浮かんできた。下手ではないが、右側に四十五度傾いたような字――。
久しぶりに唐津のハンバーガー屋で会ったあの日、先に帰ると言ったのは佳奈美だった。私がまだ持っていなかった携帯電話で時間を確認し、「バスの時間があるけん、あとちょっとで帰らんと」と寂しそうは顔をする。そこで初めて、住んでいる場所が唐津ではないと知った。
「またすぐに会えようもん」
「うん……。あ、姉ちゃん」
「ん?」
「今から走れる?」
「え?」
「帰る前に一緒にプリクラば撮りたかあ」
私たちはきゃっきゃと笑いながら、近くのショッピングセンターまで走った。撮影した画像に「うちら仲良し姉妹やけん!」と、くせの強い字で書いてくれたのは佳奈美。それからまた私たちは走り、時間ぎりぎりでバスセンターに着いた。伊万里行きに乗るという。
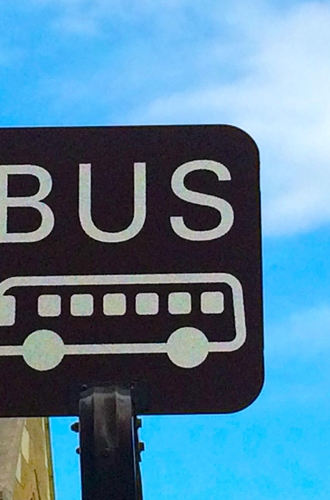
「伊万里に住んどうと?」
「うん」
「……ねえ」
「ん?」
「……いや、よか。佳奈美、また遊ぼうね」
「もっちろん」
あの時、本当は母親のことを聞きたかった。何を聞きたかったは分からない。多分、何でも聞きたかったのだと思う。でもそれを口に出すと、佳奈美とも会えなくなりそうで言葉を呑みこんだ。もう置いてきぼりにされるのは、絶対に嫌だった。
佳奈美が伊万里に住んでいることが分かり、私はずいぶんと安心できた。ひとつは「母親の居場所が分かった」という素朴な安心で、もうひとつは「唐津よりも遠い伊万里だから、母親と会えないのも仕方ない」という無理やりの安心。
それ以降、私たち姉妹は月一度のペースで会うようになり、太ちゃんのお母さんは、その度に千円札を二枚持たせてくれた。
「こんなによかよ」
「佳奈美の分も、あんたが払わんば。お姉ちゃんやもんね」
「……」
「あの子、家の人には内緒かもしれんやろ。だけん、ね?」
私はそんな心遣いが本当に嬉しかった。帰宅して残ったお金を返そうとすると、毎月ちゃんとお小遣いは貰っているのに「へそくりたい」と笑い、決して受け取ろうとしなかった。
実は私たち姉妹が唐津で遊んでいたのは最初の頃だけで、いつからかバスに乗ってあの大好きな場所、広大な松原やその先にある海岸へ行くようになっていた。最初はまるで宝物を分けるような気持ちで佳奈美を連れて行き、無邪気にはしゃぐその姿を見て喜んでいた。
海岸沿いに伸びる松原は全長約五キロ。百万本のクロマツ林は、江戸時代に防風林として植えられたものだ。海風によって幹や枝が傾くので、まっすぐ伸びている松は珍しい。小学生の時、夏休みの自由研究でずいぶんと詳しく調べた。たしか、あのノートは佳奈美にあげたはずだ。
その中で遊んでいる時は何とも思わない。景色が変わらないせいか、五キロという松原の長さを意識はしない。ただ、浜辺に出ればその広大さはすぐ確認できる。延々と続く緑に圧倒され、私も佳奈美も何度ため息をついただろう。
だからさっき、斎場を出る際にあの子は「姉ちゃん、みんなで集まるまでさ、あの松原に行ってみらん?」と提案してきたのだ。急な話に一瞬戸惑うと、明日の飛行機の時刻を訊かれた。まだチケットの手配をしていないと伝えると、「じゃあ、明日の午前中ならよかろ?」と強引に決められてしまった。
「姉ちゃん、ホテルってすぐそこ?」
「うん」
「知っとったら私もそこにしたっちゃけどね」
「え? あんたもホテルなの?」
「あ、太ちゃんから聞いとらんと? 私、今大阪に住んどうとよ」
予想外な話に思わず「へ?」と間抜けな声が出た。てっきりまだ伊万里にいると思い込んでいた。
「その仕草、昔から変わらんちゃねえ」
「ん?」
「驚いたとき、へ、って言うとたい」
私の真似をして、佳奈美が笑う。斎場を出た気軽さからか、その態度はとても自然で、思いがけず声を出して笑ってしまった。明るくなった気分のせいで、「じゃあ松原は明日やけん、今日はみんなと会う前、唐津に行ってみらん?」という誘いにも、素直に頷けた。
(第03回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『松の牢』は毎月07日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
