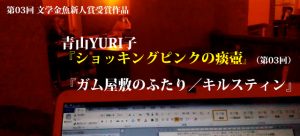 ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。
ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。
第三回文学金魚奨励賞受賞作家・青山YURI子による14のfragments実験小説!。
by 青山YURI子

ガム屋敷のふたり
1.
達哉は理沙子の完全なる冒険家であり、マエストロだった。トーンの落ちた髪色には気品が漂い、二分の一の確立で見え隠れする白髪は、よく見ると銀色に鈍く光っている。彼の髪は、これまでの彼の匂いとは離れて、柑橘の匂いがする。彼の体や、服や、指の第一関節の山からは紙の匂いが、一斉に理沙子の方へと駆け出して下りてくるのに、その不思議がまた奇跡めいて星を散らし、理沙子の心と鼻孔を同時にくすぐる。残り二分の一の毛は渦を描き、ヴァンゴッホの夜のように青黒く、遠くから見ても一本一本のタッチがしっかりと目に入る。艶があり、よくうねっている。
疲労感を嗅ぎとればそれを何よりの好物とする理沙子は、巷でも一番お洒落な店で手に入れたストローを取り出し、それをシーシャのように時間をかけて手に取ると、鼻の裏で味わいながら丁寧に吸った。彼を柔らかくする。つまり抱擁する。爪を立てて胸を掻きむしる。彼の胸の毛の一巻き、一巻きは、指輪のように彼女の指にぴったりとくる。腕を往復させる、彼を溶解させる。胸元に垂れる彼の頭は、優しく、柔らかく、胸の間に埋もれてゆく……彼の頭が見えなくなった!二人の間には快感が納豆の糸めいて宙に浮き、漂い、ほんの少しの空気にも押されて行ったり、来たりする。
そのうち快感の糸は太くなっていき、体内のメロディを引っ掛けて出てくる。二人はその音符を読み取りながら、歌をうたう。
2.
https://www.youtube.com/watch?v=xlVtwF-DrNE
https://www.youtube.com/watch?v=fs5sxTIyn0s
ヴァネッサパラディの曲がかかったクロエの香水のCMを〝ガジェーガのたこ〟をつまみながら見ていた。――ウィーンでキスして。ハーレムでもいい、それともシエナ。愛してるといって、人生は素晴らしいものだと、この世界は狂ってるって!――
 彼は〝テストの先生〟(テストを作って学校に持ってくる先生)なのに英語が上手で、世界中の映画に精通していた。その中でもラテンの国の映画が彼のお気に入りだった。(英語とは関係ないけれど)彼の気取ったアウディの中で、日の暮れ時、コンビニの駐車場に車を止め、高まった恋愛感情の中、素直に主人公2人に感情移入をするという過ちを犯し、若いヴァネッサパラディの出て来る「白い婚礼」に二つの影、二人の姿を重ねて甘い時間を過ごした。彼の手は、思っていたよりも肉厚でぶよぶよしているな、と理沙子は思った。彼女の手は、女の子の割には肉厚でぷにぷにしているな、と彼も思った。それでいて、線が通っている。ストローが通っている感覚がある。こんな手は初めてだ、とも彼は思った。(この年で新しい女の子の手を知って、嬉しかった。こんな手を知らずに、墓場まで行くところだった…!)理沙子にとっては初めての、-少なくとも本当に好きになった初めての-彼でも、彼に取っては何人目かの、本当に気持ちを込めて好きになった相手だった。映画の中で、抱擁している所を同僚に見つかる場面では、「山崎先生に見つかったらどうする?」、「牧野亮子先生は引いて誰にも言えなさそうじゃない?」と、あらゆる先生の名前を出して楽しんだ。「こんな風にキスしたら?」映画を見ながら言った。「山崎先生の前で!」「ゆでた先生の前で、」「まじで?」うぁは。笑い合う。理沙子は鼻で、次に口で、照れているのに口を固く閉
彼は〝テストの先生〟(テストを作って学校に持ってくる先生)なのに英語が上手で、世界中の映画に精通していた。その中でもラテンの国の映画が彼のお気に入りだった。(英語とは関係ないけれど)彼の気取ったアウディの中で、日の暮れ時、コンビニの駐車場に車を止め、高まった恋愛感情の中、素直に主人公2人に感情移入をするという過ちを犯し、若いヴァネッサパラディの出て来る「白い婚礼」に二つの影、二人の姿を重ねて甘い時間を過ごした。彼の手は、思っていたよりも肉厚でぶよぶよしているな、と理沙子は思った。彼女の手は、女の子の割には肉厚でぷにぷにしているな、と彼も思った。それでいて、線が通っている。ストローが通っている感覚がある。こんな手は初めてだ、とも彼は思った。(この年で新しい女の子の手を知って、嬉しかった。こんな手を知らずに、墓場まで行くところだった…!)理沙子にとっては初めての、-少なくとも本当に好きになった初めての-彼でも、彼に取っては何人目かの、本当に気持ちを込めて好きになった相手だった。映画の中で、抱擁している所を同僚に見つかる場面では、「山崎先生に見つかったらどうする?」、「牧野亮子先生は引いて誰にも言えなさそうじゃない?」と、あらゆる先生の名前を出して楽しんだ。「こんな風にキスしたら?」映画を見ながら言った。「山崎先生の前で!」「ゆでた先生の前で、」「まじで?」うぁは。笑い合う。理沙子は鼻で、次に口で、照れているのに口を固く閉![]() じて。彼はニッコリと。「こんな風に」コンナフウニとヴァネッサの囁きを理沙子は真似をした。「マドモワゼルグウィサコ、僕は今から君にキスを届ける」流暢なフランス語でテスト職人は言った。Riをギと発音した。彼は、自分の感情を見つめるように、理沙子を見つめている。自分を、彼の一部、彼の感情の一部に思っているように彼女には感じられた。
じて。彼はニッコリと。「こんな風に」コンナフウニとヴァネッサの囁きを理沙子は真似をした。「マドモワゼルグウィサコ、僕は今から君にキスを届ける」流暢なフランス語でテスト職人は言った。Riをギと発音した。彼は、自分の感情を見つめるように、理沙子を見つめている。自分を、彼の一部、彼の感情の一部に思っているように彼女には感じられた。
「ほら、おんなじ、何かを期待して。子供みたいにはにかんで、身に余るご褒美をもらう時のように」と、校舎の階段の下で、隠れているヴァネッサに視線を当てながら、彼が言う。パラディは教師を指で呼び、彼は小走りで彼女に駆け寄る。その間に彼女が見せる笑顔。
 やっと、〝こんな風〟に唇を重ねる。理沙子の唇は殆ど「無」といっていい程に薄く、暗闇の中で彼はそれを見つけるのに苦労する。暗闇の中で、彼はただ色を意識していた。
やっと、〝こんな風〟に唇を重ねる。理沙子の唇は殆ど「無」といっていい程に薄く、暗闇の中で彼はそれを見つけるのに苦労する。暗闇の中で、彼はただ色を意識していた。![]() 紫を意識すると、簡単に唇まで辿り着くことが出来た。それは彼の考える彼女の色だった。彼女の小さな唇は、むかし、むかし-彼はそう信じている-、彼がイタリア人であった時の記憶にまで辿りつく、ボタンの様なものだった。青の洞窟の中で、若い女と年を重ねた男は光に身を任せる。
紫を意識すると、簡単に唇まで辿り着くことが出来た。それは彼の考える彼女の色だった。彼女の小さな唇は、むかし、むかし-彼はそう信じている-、彼がイタリア人であった時の記憶にまで辿りつく、ボタンの様なものだった。青の洞窟の中で、若い女と年を重ねた男は光に身を任せる。
3.
彼には妻が2人居たが、次々と早くに亡くしていて、最後の妻と住んでいた家を当時のまま空き家にして保っていた。新築だった家も、10年経った今は近寄りがたいほどにツタが絡み付いていて、猫の恰好の爪磨ぎ場所になっている。さらにツタの隙から見える壁には、まだらに、色褪せたたくさんのガムが付いている。ツタの上からも付着している箇所もあった。ツタを壁に上から抑えて張り付けるのに失敗して、ガムが横に延びて、両端が遊んでいるものもある。いくつものガムで、抑えることに成功した箇所もあった。弦に沿って何個も重ねられ、塗るように、貼ってあるものもあった。まるでそこだけ白い蔦だった。葉の、葉脈と葉脈と葉脈と輪郭のトキトキの間に作られたひし形を埋めるよう、貼られているものもあった。それはまだ新しいものであるはずだった。これほど多くのガムは、これだけ多くのガムが貼られているのに誘われた輩がまた多く、自然と延びる植物のように動物の自然を発揮し、付けられていったものに違いない。壁へ斜めに降り注いだ雨が、漫画の中で描かれるもののように小さな楕円を先に付けていて、スタンプを押すように、壁一面に一斉に残した様だった。正確には突き出たテント屋根を持つ玄関を正面から見て右隣りの壁、そして玄関からポーチをくぐって小さな柵の扉を出てから道路沿いにある壁。主にこの二枚だった。そしてこの壁はどんな景色を正面に構えているか。壁の真正面、この家の外にはブルーの畑が広がっている。それも、世にも美しい、ラピスラズリの石(フェルメールが顔料に使っていた)の様に奇跡を体現させたらしい色合いをしている草だ。育ててはいないが、そういう種をどこからか買ってきて、一面に生やしていた。この達哉とはそういう男なのだ。壁の話に戻ると、人目に付かないだけあって、やはり一枚目の壁、畑とは別に、親しみ深い雑草が生えたまま、手入れのされていない庭の奥の人目に付かない一枚が、子供たちと変人にとってのよりガムを付けやすい場所であった。朝と昼は、猫にとっての爪とぎ場、学校から人が帰ってくると、不良少年たちの恰好の暇つぶし場になっていた。そして夜中には、彼らも眠りに付き、ある一組の男女の姿があった。
 「ガム屋敷」と呼ばれている青い草原の前に建てられた家には、扉にも、いつ付けられたのかわからないガムが言い訳のようにペタペタと貼り付いている。洋式の金の取っ手は下げられ、扉は開く。
「ガム屋敷」と呼ばれている青い草原の前に建てられた家には、扉にも、いつ付けられたのかわからないガムが言い訳のようにペタペタと貼り付いている。洋式の金の取っ手は下げられ、扉は開く。
4.
ここでは理沙子の提案で、近隣の住人が想像するように、二人は幽霊のようにこの家で楽しもうとした。「ガム屋敷」の幽霊となろうとしたのだ。ふらりと入って、ふらりと出て行くのが彼らのスタイルだった。夜、暗い家では電気を付けることは少なかった。彼はポータブルのテレビを持っていて、それを一緒に見る事はあったけど、画面の青白い光を受けて、二人は揃いの幽霊のような顔を恋人同士で楽しんだ。彼は腕を延ばしてウィスキーの瓶を掴んで口に運んでいった。水たまりのように、寝転んだ口の中にそれを平たく溜めて、理沙子はその中に舌を入れて細く硬く尖らせた舌の先で、それを掬って味わった。ウィスキーは唾液と混ざり合い、彼の体温で熱くなっていた。水が落ちないように、彼の口の中の壁を慎重に伝って外に出た。彼の口の中はいつも熱かった。理沙子は、身体ごと、彼の口の中に入ってしまいたいと願った。
 それなのに大きな笑い声を出す。カラカラと、乾いた笑い声を彼は出した。時には本物の幽霊と、一緒に遊んだりもした。冗談で古今東西の古くから伝わる幽霊を呼び出すおまじないを、世界まじない全集を参考にしてロシアの方から一つずつ試していった所、7、8つ目の、東欧のおまじないによって、とっても愉快な赤毛の女の子が来た。その子は数百年前のスタイルをしていても、とっても楽しくて、美しくて、こうして飛行機のない時代には叶わなかった、夢の様な日本旅行が、二人が呼び出したおかげで簡単に実現されることになってめちゃくちゃ喜んでいた。理沙子たちもおまじないが成功して、その子は日本に飛んで来ることが出来て、興奮していたので皆でベッドに入ることにした。名前をバルバラと言った。彼女の名前を、二人とも気に入っていた。貴族の子だった。海の底、オクトパスのガーデンで死んでしまったの、と嬉しそうに語った、変な幽霊。だからそういう曲を、と達哉は彼のポータブル音楽プレーヤーで選んでかけた。20世紀の音楽だよ、と。ビートルズのオクトパスのガーデン。すると彼女は、わたし、この人たちに会ったことがある、と言う。「わたしが、この人たちのモデルになったのよ、歌のね。わたしは、天国で両親にしたより詳しく、どうやって自分の息がなくなっていったのかを彼らに伝えたわ。わたしはオクトパスのガーデンを散歩していたのよ。全然、こわくなかった。彼らは真面目に聞いてくれたわ、そしてすぐ歌にしたの。この愉快な歌で、私は救われた気がしたわ。だって私の知っている人はみんな、わたしがどんなに苦しかったのだろう、ってこわくて悲しい話にしてしまったから。わたしはただ、散歩をしていただけなのよ」タコの吸盤のような足の付いたステレオを、木のフローリングの床に立てて、ポータブルプレイヤーに繋げて、音を大きくした。それから、皆でタコの足のように絡まり合った。唾を墨のように吐いて、お互いの体を汚しあった。彼女は、バルバラは、全く汚れなかった。手触りでしか彼女の体を理沙子は感じてないけど、彼女の肌は、もちろん冷たかったけれども、肌触りよく、柔らかいのにサラサラとして、水をはじく加工でもしてあるみたいだった。幽霊を交えての3Pは刺激的だった。途中で、携帯で明かりを付けて、フランスや西インド諸島の文学を参考にしながらやった。彼女の姿は、全く見えなかった。ゴーストって、目で見えないものだが手で触れられるものなのだ、とその時初めて理沙子は学んだ。彼と一緒に学んだ。そのことは彼も初めてだった。マットレスを直に床に敷いていたが、あんまり絡まって一つの生き物のように転げまわったから近くの壁に立てかけてあった黒板を何度も倒してしまった。その度、近所の家では、やっぱりあの「ガムの家」では幽霊が…今度、もしもまたあの男を見る事があったら、やっぱり伝えなきゃ…それにしても、あの男は今何をしているのだろう、奥さんの亡くなった、あの気の毒な男は…。と、考えていたことだろう。その初めの推測、「ガムの家」では幽霊が…。は、もはや現在進行形で、噂ではなくなりつつあった。
それなのに大きな笑い声を出す。カラカラと、乾いた笑い声を彼は出した。時には本物の幽霊と、一緒に遊んだりもした。冗談で古今東西の古くから伝わる幽霊を呼び出すおまじないを、世界まじない全集を参考にしてロシアの方から一つずつ試していった所、7、8つ目の、東欧のおまじないによって、とっても愉快な赤毛の女の子が来た。その子は数百年前のスタイルをしていても、とっても楽しくて、美しくて、こうして飛行機のない時代には叶わなかった、夢の様な日本旅行が、二人が呼び出したおかげで簡単に実現されることになってめちゃくちゃ喜んでいた。理沙子たちもおまじないが成功して、その子は日本に飛んで来ることが出来て、興奮していたので皆でベッドに入ることにした。名前をバルバラと言った。彼女の名前を、二人とも気に入っていた。貴族の子だった。海の底、オクトパスのガーデンで死んでしまったの、と嬉しそうに語った、変な幽霊。だからそういう曲を、と達哉は彼のポータブル音楽プレーヤーで選んでかけた。20世紀の音楽だよ、と。ビートルズのオクトパスのガーデン。すると彼女は、わたし、この人たちに会ったことがある、と言う。「わたしが、この人たちのモデルになったのよ、歌のね。わたしは、天国で両親にしたより詳しく、どうやって自分の息がなくなっていったのかを彼らに伝えたわ。わたしはオクトパスのガーデンを散歩していたのよ。全然、こわくなかった。彼らは真面目に聞いてくれたわ、そしてすぐ歌にしたの。この愉快な歌で、私は救われた気がしたわ。だって私の知っている人はみんな、わたしがどんなに苦しかったのだろう、ってこわくて悲しい話にしてしまったから。わたしはただ、散歩をしていただけなのよ」タコの吸盤のような足の付いたステレオを、木のフローリングの床に立てて、ポータブルプレイヤーに繋げて、音を大きくした。それから、皆でタコの足のように絡まり合った。唾を墨のように吐いて、お互いの体を汚しあった。彼女は、バルバラは、全く汚れなかった。手触りでしか彼女の体を理沙子は感じてないけど、彼女の肌は、もちろん冷たかったけれども、肌触りよく、柔らかいのにサラサラとして、水をはじく加工でもしてあるみたいだった。幽霊を交えての3Pは刺激的だった。途中で、携帯で明かりを付けて、フランスや西インド諸島の文学を参考にしながらやった。彼女の姿は、全く見えなかった。ゴーストって、目で見えないものだが手で触れられるものなのだ、とその時初めて理沙子は学んだ。彼と一緒に学んだ。そのことは彼も初めてだった。マットレスを直に床に敷いていたが、あんまり絡まって一つの生き物のように転げまわったから近くの壁に立てかけてあった黒板を何度も倒してしまった。その度、近所の家では、やっぱりあの「ガムの家」では幽霊が…今度、もしもまたあの男を見る事があったら、やっぱり伝えなきゃ…それにしても、あの男は今何をしているのだろう、奥さんの亡くなった、あの気の毒な男は…。と、考えていたことだろう。その初めの推測、「ガムの家」では幽霊が…。は、もはや現在進行形で、噂ではなくなりつつあった。
 この家は彼の好きな時に入り、帰る、たっぷりと管理を怠った、隠れ家的なアトリエとして使っていた。妻が死んだあと、すぐに彼はこの家を出た。10年前のことだ。管理を怠っていたのは、近所の人に、帰ってきている、となるべく思われたくないというのもあった。妻の死の後の生活をあれこれ勘ぐられるのは、面倒だった。時々帰っている風にして、誰かの意識に、そういえば、あの妻の亡くなったあの人は・・・などと浮かび上がって登場したくなかった。新しい人が見つかったのかしら・・・とでも思われたのなら、自分も死んで幽霊になってしまいたいほど恥ずかしい。同時にとっても不快な気持ちになる。
この家は彼の好きな時に入り、帰る、たっぷりと管理を怠った、隠れ家的なアトリエとして使っていた。妻が死んだあと、すぐに彼はこの家を出た。10年前のことだ。管理を怠っていたのは、近所の人に、帰ってきている、となるべく思われたくないというのもあった。妻の死の後の生活をあれこれ勘ぐられるのは、面倒だった。時々帰っている風にして、誰かの意識に、そういえば、あの妻の亡くなったあの人は・・・などと浮かび上がって登場したくなかった。新しい人が見つかったのかしら・・・とでも思われたのなら、自分も死んで幽霊になってしまいたいほど恥ずかしい。同時にとっても不快な気持ちになる。
でも一番の、帰ってきている風をしない家の体裁の理由は、移住空間とは別の、異空間をここに作っておきたかったからだ。持ち主である自分でさえも、侵入者のように、入る度に少しドキドキして、抜き足、差し足で敷居をまたぐ場所が欲しかった。妻が死んでから数年はこの場所を放っておきながらも、家全体を亡き妻への祭壇だと捉えていた。とっても神聖な気持ちでこの場所に夜、瞑想をするため、こっそりと入りに来ていた。そんな時代もあったが、時が経ち、今は理沙子との愛の巣である。

5.
そんなことを、達哉は感慨深い気持ちで振り返っていた。
「イタリアジン?」「シ、イタリアノ」フェリーニの81/2をスクリーンに流しながら、彼はイタリア人、理沙子は日本人のままだった。「モルボーノ」ふふ、「美味しい?もう一度言って!」「モルボーノ」にっこり。良かった、彼、嬉しそう、と彼が口角を上げる度、理沙子は思う。そうするとやっと、その日の幸福感が理沙子にまで届く。彼は日本語を理解するイタリア人で、理沙子の質問に、イタリア語で返していく。「シ、モルボーノ!」「アンティパースティ」
「ねえ結局、イタリア人なの、フランス人なの、ポルトガル人なの、日本人なの?」
彼は映画を見るたび、その国の人物になりきってしまうのだ。
どこを見ても彼がいる。後で映画を見返すと、イタリア人にもフランス人にもポルトガル人にも、スロベニア人にもスペイン人にもなった彼がいる。彼のリズムとメロディーを刻む人間がこんなにたくさん名作の中に隠れていると、もしも大人になった時、もしも離れることがあった時、困ることになると思う。だから二度と見返さない、マイナーなやつが見たいのに、彼は理沙子を抱きしめて離さない。彼女に教えたいものがたくさん、たくさん溢れ出すのだ。その日初めて、ちょっとだけ、家中のガムで、マットレスに貼り付けにされている気分を彼女は味わった。
でも、二人で跳ぶたびガムは踊って、伸びて、ガムの方が意思を持つように、二人をこれ以上ないほどよく巻いた。二人の体温でガムは溶け、床に転がり落ちればべったりと付着する。そんな瞬間、理沙子は嬉しかった。ガム屋敷に根を張った気分になるのだ。なのに、「ガムの味が完全になくなるまで」達哉は言った。
キルスティン
 キルスティンを初めて、部屋の中に認めた時、銀色の服装を身に纏っていた彼女は、一筆で書ける、銀色の魚のようだった。僕はそれを、片方の指だけで掬って、こちらへ引き寄せることが出来そうな気がした。するり、するりと辺りを移動していく。一人だけ重力を間違えて、体を横に向けていた。彼女にとっての上、とは、あのベルリンの白くむず痒い空の光が入り込む、北の窓の方角なのである。銀色の筆跡。銀怪魚。彼女の腹の下には、今到着した人々がぎこちなく動いている。各、各自のリュックサック、小型のスーツケースを、移動させたり、ベッドの上へ開けて整理をしたりしていた。少し慌ただしい、午後7時だった。空はまだ明るかった。夏が近づいていた。
キルスティンを初めて、部屋の中に認めた時、銀色の服装を身に纏っていた彼女は、一筆で書ける、銀色の魚のようだった。僕はそれを、片方の指だけで掬って、こちらへ引き寄せることが出来そうな気がした。するり、するりと辺りを移動していく。一人だけ重力を間違えて、体を横に向けていた。彼女にとっての上、とは、あのベルリンの白くむず痒い空の光が入り込む、北の窓の方角なのである。銀色の筆跡。銀怪魚。彼女の腹の下には、今到着した人々がぎこちなく動いている。各、各自のリュックサック、小型のスーツケースを、移動させたり、ベッドの上へ開けて整理をしたりしていた。少し慌ただしい、午後7時だった。空はまだ明るかった。夏が近づいていた。
僕はその夏を楽しみにしていた。湖に、泳ぎに行く計画を立てていた。もうすでに、5月の空気に、ベルリンの夏、らしきものを発見したような気になっていた。引っ越してくる前に住んでいた、フリードリヒスハインの、フリードリヒ通り、シモンダッハ通りには4月から緑の木々が目立っていた。他に色が少ないために、あってもそのトーンの淡いゆえに、木々の緑色が目立っていたのかもしれなかった。僕は、初めての土地で、初めての夏に、気持ち良さでうちのめされそうだった。昨日も、前のルームメイトに聞いた、ドイツの湖での夏、森林の中で行われる大規模なダンスパーティ、別荘地でのビアガーデンを、インターネットでググりながら、詳細を目に通し、魅せられていた。黄色い光に囲まれて、落ち着いたネイビーブルーのシャツを来た僕の周りには、黄緑色の光しか、存在していないような気がしていた。僕は、どこにでも、この黄緑色の層をまとって、心地よく街を歩き、人々と会話をしていた。それも、ほとんどが初めて出会う、知らない人々。いつも、初めての会話は、決まり事を述べるだけなのに、新鮮で、気持ちが良かった。自分がどこの出身なのか、何をしているのか、名前、簡単な言葉を交わしている間にも、お互いの、心地良さを大きな爆弾のように交わし合う。共有する。それまで、一人で感じていた気持ちの落ち着く、柔らかく希望の入った光の印象が、初めて現実を帯び、今度は手に取るように感じられることが出来た。それは、感動的だった。どんな会話でも良かった。床に艶のある黒い木の張られている、日本でいう、コンビニ。いくつかの、スーパーで買うよりも少し高い品物を手に取って、お店の人に渡すとき、知らないドイツの中年の男の、どこから来たのだろう、という好奇心と、ウェルカムの籠もった、コーテシーたっぷりの、月の光を放つ、三日月の形をした目。引き締まった笑顔。僕がダンケシュー、と言うと、「どこから来たの」とそれまでひかかっていた、表情に小出しにしていた思いをやっと、口にする。静かに吐かれた「どこから来たの」に、初め、ヨーロッパで生まれた日本人、と言おうとした。その設定の方が、いつも自分には都合が良かったから。でも、その気持ちいい感じに下がった目尻に、僕は正直に、「アジア」と、少しぶっきらぼうに、でも丁寧に、答えてしまった。「アジアのどこ?」僕は、逃げ去るように、「日本」と答えて、手を振り、「今日も気持ちをいい日を!」と言い、店を出ようとした。彼も、「おぉ!日本か。遠い国だね。グーデンターク」と言う。笑顔と笑顔が、かっちりと合った。気持ちのいい空気。こうして、気持ちの良さを交換して、また外に出る。木が茂っている。ボリュームもある。外に出された簡易折りたたみの長椅子に、もうたくさんの人がかけている。前の方から、双子用ベビーカーを押してくるカップルもいる。皆、外の空気を気持ちよく感じている。目がサングラスで隠されているけど分かる。僕は、一人でタバコを吸いながら、携帯電話の画面を見つめているきれいな子を順番に見つめていく。あんな子もいいな、この子も。きれいな子でなくてもいい。雰囲気に、甘えた感じのない子、社会に媚びた感じのない子、さっぱりとした子に目がいってしまう。あの、男もいいな、と思う。彫刻家らしい人、何かの職人かもしれない、も全身に、汚れたつなぎを着、冷静で頭の良い目つきをして、外を眺めている。男に生まれてきたのが残念だ。この世界には、男も女も、たくさんの素晴らしい人間がいる。たくさんの、素敵な、魅力的な人間がいる。僕は男だから、残念だけど、女の子しか愛せないせいで、ー一度確かめようと思って、ポーランド人の友達に誘われ、すごく魅力のある男の人と同じベッドに入ってみたけど、だめだったーその半数しか、身も心も魅せられ、内でつながり、大好きでいる資格を与えられていない。僕は、少しがっかりした気分になってきた。そのがっかりした気分、少し人目から隠れたくなる気分を持って、角のタイ料理屋さんに入って、サーモン丼を頼んだ。でも、料理屋のぶっきらぼうな女と、二言、三言、言葉をかわしているとその気分は少し収まった。外を見る。この場所を愛している人たちが通っていく。フリードリヒスハインには、フリードリヒスハインらしい人が住んでいる。
 初めの日、彼女を認めたのは、たった3秒ほどだった。それに、左目のみで。僕の部屋はルームA、キッチンの隣だ。キッチンの反対には廊下があって、突き当たり、ルームBは、この時、ドアが開いていた。ロッカーが3、4つ立っているのが見えた。そしてロッカーの前で身を屈め、何かを取り出している、一人の女を僕の左目は認めたのだ。「ほら、例えばこういう人」と胸の中で言葉を発してしまったことを覚えている。僕が思う品のない言葉で言うならば、「品のある」、一種「優雅」な、生活に追われた感じのない、慌てた様子のない空気も感じられる。静物画に一度潜って上がってきたような静謐さを身につけ、髪はショートカットで金髪かブルネットだったけど、どちらにしても主張をしていない髪色だった。灰色の、薄いカーディガン、中に着た灰色のタンクトップ、濃い、発色のよくない紺色の、ヒップを隠すために薄く肌を透かす黒い色のタイツの上に重ねているスカート。スカートと呼べるほど、しっかりとした生地で作られた、一つの品物ではなかった。ただお尻を隠すためだけに、タイツの上に重ねられる、タイトな布だ。よく5ユーロぐらいで、見せブラジャーや、靴下、下着、水着やサンダルと一緒に売られているのを見たことがある。でも、この時ばかりは、この服は彼女のために作られた、と思うほどに、彼女の体型にも、雰囲気にも、よく合っていた。それが、一つの、重要なアイテムであることを彼女は証明していた。そこから延びる足も、腕と合わせて、4本同じ細さであると思えるほどだ。ゴムのように、人間の息吹のかかっていないものに思えた。彼女は、誰かに作られたものではないのか、という疑念が頭をよぎった。天の創造者ではない、もっと欲を持った身近な誰かに…。例えば僕だったら、僕にその力があれば、例えばこんな女の子を、作るかもしれない。それほどに、僕の心にしっくりとくる、ある印象をこの女の人は持っていた。
初めの日、彼女を認めたのは、たった3秒ほどだった。それに、左目のみで。僕の部屋はルームA、キッチンの隣だ。キッチンの反対には廊下があって、突き当たり、ルームBは、この時、ドアが開いていた。ロッカーが3、4つ立っているのが見えた。そしてロッカーの前で身を屈め、何かを取り出している、一人の女を僕の左目は認めたのだ。「ほら、例えばこういう人」と胸の中で言葉を発してしまったことを覚えている。僕が思う品のない言葉で言うならば、「品のある」、一種「優雅」な、生活に追われた感じのない、慌てた様子のない空気も感じられる。静物画に一度潜って上がってきたような静謐さを身につけ、髪はショートカットで金髪かブルネットだったけど、どちらにしても主張をしていない髪色だった。灰色の、薄いカーディガン、中に着た灰色のタンクトップ、濃い、発色のよくない紺色の、ヒップを隠すために薄く肌を透かす黒い色のタイツの上に重ねているスカート。スカートと呼べるほど、しっかりとした生地で作られた、一つの品物ではなかった。ただお尻を隠すためだけに、タイツの上に重ねられる、タイトな布だ。よく5ユーロぐらいで、見せブラジャーや、靴下、下着、水着やサンダルと一緒に売られているのを見たことがある。でも、この時ばかりは、この服は彼女のために作られた、と思うほどに、彼女の体型にも、雰囲気にも、よく合っていた。それが、一つの、重要なアイテムであることを彼女は証明していた。そこから延びる足も、腕と合わせて、4本同じ細さであると思えるほどだ。ゴムのように、人間の息吹のかかっていないものに思えた。彼女は、誰かに作られたものではないのか、という疑念が頭をよぎった。天の創造者ではない、もっと欲を持った身近な誰かに…。例えば僕だったら、僕にその力があれば、例えばこんな女の子を、作るかもしれない。それほどに、僕の心にしっくりとくる、ある印象をこの女の人は持っていた。
午後2時、キッチンの壁際に置かれた二人用のイケアのテーブルには、壊れた湯沸かし器があった。まだ仕事に行くには時間があった。僕はテーブルの上の光を追いかけていた。白テーブルなのに、上から長方形、それが変わって菱形、最期には紐のように細くなった光が白を抜き、泳いでいる。まるで、テーブルの内側で泳いでいるようだった。上から手を当てる。かざす。それを捕まえようとした。光は僕の手の甲を思い切りよく伝っていって、分からぬようそっと下りていく。こんどはちょうど縁ぎりぎりにまで来て、テーブルと壁との隙を下に落ちていった。と思えば、僕のジーンズの縫い目をなぞっている。きれいに角ができたリボンの切れ端のような光を、叩くように払った。目を上げると、いつ入ってきたのか、窓縁に座ったキルスティンが、こちらを向いて悪戯そうに微笑んで、片開き窓に手をかけていた。

(第03回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ショッキングピンクの時代の痰壷』は毎月12日にアップされます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
