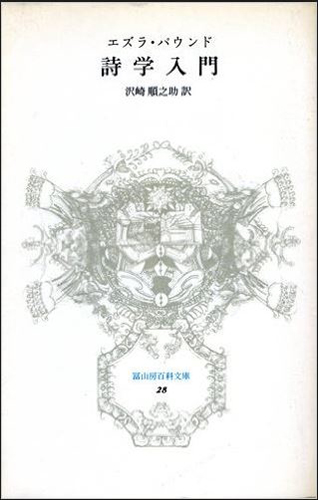
エズラ・パウンドに『詩学入門』(沢崎順之介訳)という詩の入門書がある。沢崎先生には申し訳ないのだが、”ABC of Reading” という原題のままの方がパウンドの意図が伝わるように思う。〝(詩の)読み方のABC〟というタイトルには、同時代に行われていた詩の読解法への苛立ちが反映されている。〝詩の読解法のABCを教えてやる〟という高飛車で傲慢とも言える批判意識があるわけで、攻撃的な入門書である。
実際極めて乱暴な入門書なのだ。筋は通っているが、書き飛ばしたという感じがひしひしと伝わってくる。孔子の正名論を理想に掲げながら、利子(資本主義的利潤追求)を排撃し、過去から現代社会に至るまでの人間の善行と愚行をあらいざらい詩で表現しようとした『詩篇』とほぼ同じ方法で書かれている。
だから〝入門(ABC)〟というタイトルにも関わらず、詩の初心者は置き去りにされてしまうだろう。パウンドは詩は厳格な言語技術で表現されなければならず、現代的表現は過去の詩の的確な理解に基づかねばならないという確信を持っていた。たとえば「へぼ詩人の大多数は、詩は一つの技術であるという意見に憤激していた。詩を書くのに分析などはせずにすべきだと考えていた。依然として、詩は「迸り出る」ものと期待されていた。(中略)よくあるごまかしの手はここから始まる。最上の作品はおそらく迸り出るものである。しかしそれは、表現手段を扱う能力が「第二の天性」と化したそのあとでそうなるのだ」と書いている。
パウンドが批判しているのは一九一四年のロンドン詩壇の状況だが、現代日本も同じようなものだ。詩人らしい風体をして、詩の原理も技術も歴史も考えず、見よう見まねで詩のような詩を書くのが詩人だと思い込んでいる作家が大勢いる。詩の世界など世界中どこでも、いつの時代でもそんなものだと言えばそのとおりである。しかしほんとうに知識と経験を積んだプロがいなければ(育てなければ)詩のジャンルは立ちゆかなくなる。文学に限らずどの世界でも同じことである。優れた詩作品は茫漠とした詩的雰囲気からは生まれない。
”ABC of Reading” では、パウンドが詩の必須要件だと考えた「言語技術」と「詩史的パースペクティブ」が、ある〝高み〟として乱暴に投げ出されている。そこに至るための中間の道筋は詳述されていない。高みは示してやるから、詩を本気で志す者は自分で登頂ルートを探して登ってこいといった質の入門書なのだ。要するにうんとハードルが高い。同時代人から煙たがられるわけである。
文学における「純粋要素」を探しはじめると、やがて、文学は以下に列挙するような種類の人間によって創られてきたことに気づくだろう。
1 発明者。新しい手法を発見した人。あるいはすくなくとも現存する作品が、知られているかぎりでその手法の最初の例となっている、その作者。
2 巨匠。そのような手法を数多く組み合わせ、発明者と同じくらいに、あるいは発明者よりも巧みに、手法を使いこなした人。
3 希釈者(鶴山註-希釈は水で薄めること)。上記の二種類の作家のあとに現れて、かれらに匹敵するだけの仕事ができなかった人。
4 とりたてて目ざましい特質のないすぐれた作家。どこかある国の文学全体が正しく整然と機能しているとか、文学のある特定の分野が「健康」であるとかの時代に運よく生まれ合わせた人。たとえば、ダンテの時代にソネットを書いた人、シェイクスピアの時代あるいはその後の数十年に短い抒情詩を書いた人、フランスでフロベールに手本を示してもらったあとに長篇、短篇小説を書いた人。
5 美文家。すなわち、実際なにも発明したわけではなく、ある特定の分野だけを専門とし、「偉大な人物」つまり人生とか時代の完全な表現を試みようとした作家、とはみなされなかった人。
6 熱狂の創始者。
(エズラ・パウンド『詩学入門』沢崎順之介訳)
パウンドが書いている文学の「純粋要素」は、日本では純文学に相当すると言っていいだろう。パウンド流の二項対立を援用すれば、純文学と大衆文学の境界は曖昧だといった議論は無駄である。明治時代から近過去までの新聞や文芸誌を読めば一目瞭然だが、今では誰も名前を覚えていないような大衆作家は掃いて捨てるほどいる。わたしたちが〝文学の根幹〟とみなしているのは純文学作家の作品である。
1から6までの分類でパウンドが示しているのは文学史的パースペクティブでもある。新たな文学は「発明者」によってその基礎が形作られ、それを巧みに援用した「巨匠」たちによって黄金期が出現する。しかしその時代が過ぎるとじょじょに衰退が訪れる。発明者と巨匠の業績をなぞる「希釈者」と、「とりたてて目ざましい特質のないすぐれた作家」の時代になるのだ。「美文家」や「熱狂の創始者」はいつの時代にもいる。内容のない美文を書くことに終始し、無理くりにでもジャーナリスティックな話題を作りあげ、それに乗っかって世の中を渡ってゆこうとする文学者たちのことである。
前に書いたことがあるが、面白いことに夏目漱石がパウンドとほぼ同じことを言っている。漱石は初期の短編『野分』(明治四十年[一九〇七年])で文学のサイクルを「初期」、「中期」、「後期」に分類した。初期は次世代の「子の為に存在する」時期でパウンドの「発明者」の時代である。中期は「われ其物を樹立せんが為に存在する」時期であり、「巨匠」の時代に当たる。後期について漱石は「(中期の)父母のために存在する」時期だと書いている。発明者と巨匠の仕事をなぞる「希釈者」の時代である。初期は新たな文学の創生期、中期は全盛期、後期は衰退期に相当する。
漱石はまた「明治は四十年立った。まづ初期と見て差支えなからう」と書いた。漱石が文学史のサイクルを四十年単位で考えていたとすれば、初期は明治元年(一八六八年)から明治四十年(一九〇七年)、中期は明治四十一年(一九〇八年)から昭和二十二年(一九四七年)、後期は昭和二十三年(一九四八年)から昭和六十二年(一九八七年)となり、昭和六十三年(一九八八年)から二〇二七年までが再び初期ということになる。つまり漱石文学史観に従えば、わたしたちはこれから黄金期を迎えるだろう、新たな文学潮流を用意するための初期を生きていることになる。
ただ漱石は初期について、「初期は尤も不秩序の時代である。偶然の跋扈する時代である。僥倖の勢を得る時代である。初期の時代に於て名を揚げたるもの、家を起こしたるもの、財を積みたるもの、事業をなしたるものは必ずしも自己の力量に由って成功したとは云はれぬ」とも書いている。漱石は坪内逍遙・二葉亭四迷の言文一致体小説の成果や、明治の文語体小説を書いた幸田露伴や樋口一葉、あるいは同時代に大衆小説作家として最も成功した尾崎紅葉らの仕事を見切っていたのだと言ってよい。実際、日本の近代文学は漱石から始まる。『吾輩は猫である』の初出は明治三十八年(一九〇五年)のことだ。
パウンドや漱石を予言者と呼ぶつもりはないが、彼らの文学史観はおおむね正しいと思う。パウンドは中世ダンテ以降のヨーロッパ詩の的確な知識を持っており、漱石の『文学論』(明治四十年[一九〇七年])はほぼ一世紀にわたる英米文学の詩と小説を概観した驚異的評論である。その期間が四十年なのか三十年なのか、あるいは五十年なのかは別として、文学の歴史はパウンド・漱石が指摘したような発明者(初期)、巨匠(中期)、希釈者(後期)の時代を追って推移するだろう。
わたしたちが生きる現代が、ある文学潮流の全盛期(中期)でないのは明らかである。発明者や巨匠たちの仕事を水で薄めてなぞる希釈者の時代でもない。規範とすべき文学パラダイムが存在しないからである。もしかすると新たな文学潮流が作られ始めているのかもしれないが、現実には「偶然の跋扈する時代」で「僥倖の勢を得る時代」である。現代でも各文学ジャンルにスター作家たちはいる。しかしその本質的評価は留保され続けている。過去の延長上で現代作家の評価が定まる時代ではなく、未来の文学動向によって現代作家に本質評価が下されるだろうという気配が漂っている。漱石は「明治の四十年を長いと云ふものは明治の中に齷齪しているものの云ふ事である。後世から見ればずつと縮まって仕舞ふ」とも書いた。時代状況は必ず変わる。現状がいつまでも続くと思うのは甘い。
とりあえず漱石文学史観に従うと、僕はある文学潮流が衰退する「後期」末の一九八〇年代中頃に本格的に文学に取り組み始めた。そしてすぐに混乱の「初期」時代に突入したわけである。第二次世界大戦が起こったために、戦後文学は自由な表現と新たな情報に飢えた人々の欲求に支えられて空前の活況を呈した。しかし大局的に見れば、それは徐々に衰退に向かっていたと言える。現代文学は漱石や森鷗外、正岡子規はもちろん、谷崎潤一郎や川端康成、志賀直哉といった、戦前にその文学的骨格を作り上げていた作家らの仕事を基盤としている。三島由紀夫らは戦後のスター作家だが、決定的に新しい何かを生み出したわけではない。パウンド的に言えば「希釈者」の位置付けになる。それは自由詩の世界も同じである。
自由詩の骨格は戦前にすでに出揃っている。口語自由詩が萩原朔太郎『月に吠える』(大正六年[一九一七年])によって確立されたのはもちろん、戦後に詳細に検討されることになるサンボリズム、モダニズム、シュルレアリスムといった思想潮流、あるいは散文詩から定型詩、タイポグラフィに至る詩の技法も一通り戦前に試みられた。もちろん戦後には大別すれば「戦後詩」と「現代詩」という二つの大きな文学潮流が生まれた。しかしそれも急速に発明期から全盛期、そして衰退期への道筋を辿った。
こんなことを書くと多くの詩人たちの反発を買うだろうが、僕は一九七〇年代以降の自由詩を評価しない。戦後詩は鮎川信夫、田村隆一のモダニズム系の思想詩がベースになっているが、七〇年代以降はそれをなぞっている。現代詩も同じである。現代詩は一九五〇年代末から六〇年代にかけて、基本的には入澤康夫と岩成達也の二人の詩人によって確立された。日常言語の意味性をほぼ完全に排除した、純粋言語芸術に近い表現を為し得たのはこの二人だけである。たいていの詩人は戦後詩的な思想と現代詩的な技法を援用しながら、実体としては日々の散発的思想や感情を表現している。吉本隆明の言う「修辞的現在」である。
戦前の朔太郎から戦後の戦後詩、現代詩の代表的作家の作品を読み進め、一九八〇年代、九〇年代、二〇〇〇年紀の詩人たちの作品を読んでいって、これはとてもマズイことになっていると思わない詩人がいるとは僕には考えられない。自由詩は一九八〇年代中頃を最後の一つの小さな山として、以降はひたすら衰退の道を辿っている。戦前の三種の神器だったサンボリズム・モダニズム・シュルレアリスム、あるいは戦後の戦後詩や現代詩をなぞる力すら失われている。もちろん新たな文学潮流が生まれていれば話は別である。しかしそれは今のところ影も形も見えない。
こういった分析を書くと、当然だが「ならばどうすればいいのか。もし有効な処方箋があるなら教えてほしい」ということになるだろう。しかしわたしたちは何が次の時代の文学の基層的思想になるのか、技法になるのかわからない時代に生きている。恐らく同時代に為された数々の試行の中から次世代の文学パラダイムが生まれるだろう。そのようなパラダイムが見えてきて初めて、今を表現し認識するためにはほとんど役に立たないとみなされ始めている過去の文学と未来の文学がつながるのである。ただ突然優れた文学者が現れ、人々の度肝を抜くような作品集を出版して新たな文学時代が幕を開けるといった期待は幻想である。近代以降、そのような出来事は起こっていない。
夏目漱石や森鴎外、正岡子規らの全集を通読すればすぐにわかるが、当たり前だが彼らはわたしたちと同じ普通の人々である。彼らになぜ〝文豪〟という称号が与えられたのかといえば、文学についてとことん考え抜いたからである。作品はその顔だが、彼らの思考のほんの一部でしかない。また彼らの文学の評価は時間をかけて形成された。多角的に批判検討された後に優れているという評価を得たわけだ。
乱暴な言い方をすれば、たまさかの偶然で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」と同レベルの作品を書く俳人はいるだろう。しかしそれでは文学史に残らない。残ったとしても微細な影響を与えるに留まる。近代以降の作家は作品を含めその全思考が問われる。文学史を過去に遡るほど、今に伝わるのは作品だけになってゆく。しかし芭蕉も紫式部も在原業平も、過去文学の的確な知識とそれに基づく現状認識、そして現代の最先端に立つ自己から伸びる未来の文学へのパースペクティブを持っていた。
文学の歴史は古く、文学がその基盤とする言葉の歴史はさらに古い。それは太古から現代まで連綿とつながっている。文学の世界では奇抜な題材や表現を使った作品で読者の耳目を集めても、過去文学の理解と未来のパースペクティブを持っていなければ一時のあだ花で終わる。現代的題材も新たな言語技法も相対的なものであり、時代が変わればすぐに古びてしまうからだ。文学の最も〝純粋〟な部分を表現している古典作品は題材や言語技法の奇抜さで評価されているわけではない。文学では常に原理(原点)を見据えながら現在の表現を模索してゆく必要がある。
鶴山裕司
(後編に続く)
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


