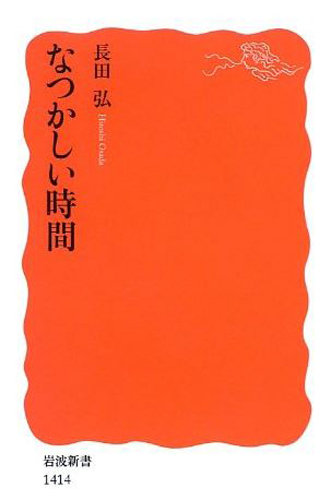
20世紀から21世紀にかけて失われゆくもの、失ってはならないものを語るというものだが、それは結果であり、ときどきのエッセイを集めたものだ。ただ全体には確かに一貫した危機感が流れている。詩人はずっとそのような危惧を抱きながら過ごしてきたのか。
その危惧とは一口に言えば、書物が消えゆくことに尽きるだろう。それは商売柄というものではもちろんなくて、書物によって培われ、世代から世代へ手渡されてきた人間の精神が変容してしまうことに対するものだ。その意味で、詩人の危惧にはスケールがある。
スケールがあるからこそ、詩人はどこかで確信もしている。結局は変わらないものがあるはずだし、それこそが核になってゆくものだと。その確信におそらく理由はない。ただ「なつかしさ」の肌感覚がある。このような「なつかしい時間」がなくて、人間の生が存在し得るはずがない、という確信。それはこれからの人たちにとっては、単に頑迷な思い込みに過ぎないだろうか。
「なつかしさ」が人の生にとって、いつでも変わらない本質であるとしても、それが書物の必然に繋がるというのはなぜか。また、そこから「なつかしさ」とは何であるのかがひもとけるということはないか。何ごとか「なつかしむ」とは、書物に対する理由のないこだわり同様に、他者には理解し得ない頑迷な思い込みそのものだ、と一般に言えるのか。
つまりは何ごとか「なつかしむ」人への共感も距離感も、「書物」という形態へのこだわりを持つ人へのそれと同程度だ、ということだろうか。書物でなくては、という文言に対し、その通りだ、と思う部分と、そうでもないんじゃないか、と思う部分とが同居する我々である。
子供時代などの微細な記憶を語られると、それを共有しない我々は退屈する場合がある。しかし誰もがそういう過去の記憶を抱えている、という点については、我が身を振り返るまでもなく共感する。我々は、他者の関知し得ない線形の時の流れを生きているのだ、という了解。その了解が交錯する瞬間、人と人は孤独なままで互いの存在を理解する。
書物の領域を侵食しつつある新しいメディアやツールは、線形の生を自在に編集し得るのが特徴である。かつてのテレビが、個々の線形の生を束ねたまま時間を大量に浪費させ、大量の擬似的な共感をもたらしたのと対照的に、個は個として、しかし経験は分断され、必ずしも線形を為さない。
書物という形態は、線形の生と相似を為す。そこに身を委ねることは、他者の線形の生をなぞり、共感することでもある。詩人の17年に渡る断続的な思索や感慨に寄り添う時間を持つことは、その17年の上澄みを追体験することでもある。主体的に選択されたその受動が擬似的な時の流れを作り出し、我々はそこに「なつかしさ」をおぼえるのだ。
金井純
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


