Interview:馬場あき子インタビュー(1/2)

馬場あき子:昭和3年(1928年)東京都生まれ。日本女子高等学院(現・昭和女子大学)卒。少女時代から短歌に興味を持ち、歌誌「まひる野」に参加して窪田章一郞に師事。昭和五十二年(一九七七年)歌誌「かりん」を創刊し主宰をつとめる。昭和三十年(一九五五年)に処女歌集『早笛』を刊行以来、平成二十五年(2013年)刊の『あかゑあをゑ』に至るまで二十四冊の歌集を刊行。『式子内親王』、『鬼の研究』、『修羅と艶 能の深層美』など日本の古典文学や能に関する著作も多い。第十三歌集『阿古父』で第四十五回読売文学賞、第十五歌集『飛種』で第八回斎藤茂吉短歌文学賞、第十九歌集『世紀』で第二十五回現代短歌大賞受賞など受賞多数。
馬場あき子氏の基盤には日本の古典文学――特に少女期から習っていた能がある。能論については『修羅と艶』、『花と余情』、『風姿花伝』などの著作があり、古典文学論には『式子内親王』、『和泉式部』、『世捨て奇譚』などの著作がある。また民俗学を取り入れた『鬼の研究』でも名高い。今回は古典文学を能楽などを通して生きた芸術として捉えることができる馬場氏に、日本文化の底流を為す知や感性について語っていただいた。なおインタビューには文学金魚で演劇批評を連載中のラモーナ・ツァラヌ氏に加わっていただいた。
文学金魚編集部
■能について■
金魚屋 文学金魚のような小さなプレスにお付き合いいただきありがとうございます。
馬場 文学金魚なんて、ちょっと面白いと思いましてね。なんでも面白いところに行っちゃうんです。好奇心のかたまりですから(笑)。
金魚屋 馬場さんに是非インタビューさせていただきたいと思ったのは、「角川短歌」誌に掲載されていた「馬場あき子自伝」を読んだからなんです。あれは面白かった。穂村弘さんが聞き手のインタビューでしたが、馬場さんが穂村さんに、口語短歌を始めとする短歌の現状をリサーチしておられる連載でもありました(笑)。
馬場 いろいろ情報を仕入れなくっちゃね(笑)。わたしは本当に頭が悪くて愚かだったんです。面白いくらい愚かだったの。そこから雑学だけで生きてきたようなところがあります。でもそれがいいところでもあるんですよ(笑)。
金魚屋 雑学だけであれだけの作品と批評は書けませんよ(笑)。わたしたちは一九八〇年代に学生だったんですが、大学に入って通過儀礼のように読まなくてはならない本の中に馬場さんの『鬼の研究』がありました。今回、インタビューさせていただくに当たって『鬼の研究』も再読したんですが、ほぼ日本文化(精神史)の始まりから説き起こしておられますね。鬼にも変遷があって、基本的に中世で鬼と呼ばれる一つの形・概念になる。それは初めて馬場さんが明らかにされたんじゃないでしょうか。
馬場 そうかもしれません。民俗学者などが書いている鬼はありましたが、それは民俗学にのっとって鬼を分類したものです。わたしの鬼はそれとは違って、生きた人間としての鬼を書いているんです。それが江戸、近世になると幽霊になってゆく。幽霊もすごく面白いんですが、現代はどうなんでしょうね。鬼も幽霊も存在感がなくなってしまって、ゆるキャラのようです(笑)。
金魚屋 馬場さんは『鬼の研究』や『世捨て奇譚』で、成仏や悟りはないんだと書いておられます。もしそういったものがあるとすれば、現世の汚濁にまみれた迷妄の果てに、ふっと突き抜けた一瞬がそれだろうと論じておられる。現代はそれに近いんじゃないでしょうか。
馬場 わたしは能をやっているでしょう。能の舞台に出られるのは妄執を持った者だけなんです。この世に妄執を持った者だけが、永遠に生きられるといったところがあります。能はそういう面白い舞台なんですが、だからこそ能にはワキ僧という名役者がいるんです。坊さんさえいれば、あらゆる鬼や幽霊などが出て来てもだいじょうぶな舞台なんです。世阿弥がワキ僧を発見したことは、能という芸術を大成させるための最大のポイントだったと思います。中世という時代を考えてみると、坊さんこそがオールマイティの存在だったわけです。宗教者で最高の知識人ですからね。坊さんの前に出れば、懺悔ですからいかなることを喋ってもだいじょうぶです。そういうことはほとんど誰も言っていないですね。

ラモーナ 馬場さんは能楽論の中で、能役者は鬼族の末裔だという意味のことを書いておられます。それは当時の芸能者の立場を表しているのでしょうか。
馬場 河原者は風俗的な「傾きもの」の拠点だったけど、能もその他の芸能者も、日本のその始まりまで遡れば同じですよね。
世阿弥らの芸能者の系譜を遡っていくと、王朝時代に大江匡房という人が『傀儡子記』や『洛陽田楽記』、『遊女記』などを書いています。それらを読むと、川の側に住んだ人、山の中に住んだ人は田んぼを持たなかった。当時は田んぼを持たなければ税金を納めなくていいんです。税金はお米で納めたわけですから。この田んぼを耕さず、税金を納めていない人たちの中から遊芸人が生まれてきた。みんなに芸を見せてお鳥目をもらって物を買ったりしていた。彼らが実際に何を食べていたのかというと、たとえば吉田兼好の『徒然草』の中に、栗しか食べない娘を持った親の嘆きの話しがでてきます。栗しか食べないという記述は、他にもいろんなものを食べてはいたんでしょうが、いろいろな木の実や栗が主食だったんじゃないか。そういう生活をしていた山の民と川辺の民、それから朝鮮半島や大陸から日本にやってきた人たちが、芸能とか染め物とか、様々な技を日本人に教えたんだと思います。ただそういう人たちの集団は、田んぼを耕して税金を払っていた人たちとは違うんです。人外と呼ばれていた。
ラモーナ 世阿弥が活躍した時代は、とても大変な世の中だったと思います。でも世阿弥たちが作り上げた芸術は非常に高度なものになりました。それはどういった情熱に支えられていたとお考えですか。
馬場 世に出たい思いです。それを助けたのが二条良基のような知識人の貴族です。彼らは異様なものを愛した。良基は南北朝時代の人で関白、太政大臣にまで上り詰めました。でももう政権を、権力を握っていないわけです。都のお公家さんたちは傀儡に過ぎなかった。われわれも多分そうだと思いますが、そういう立場の者は異様なものを愛するようになるんです。世の中心から外れてしまった者の目には、異様になったものは素晴らしく魅力的に映りますし、またそういった世の規範を外れるような力が欲しいわけです。わたしが『鬼の研究』を書いた時もそうでした。
それに平安時代まではろくな芸能がなかった。もちろん平安朝以前には田植えの労働を励ます唄や踊りとか、神社のお祭りの時の踊りや、曲芸、手品など様々な芸能がありました。それらが描かれた画を見ると火を吹く男とか綱渡りをする芸人、刀を手玉にとって芸をする人なんかが描いてあります。そういった芸が朝鮮半島経由で日本に伝わっていたんです。そのような芸能集団と遊女集団が、じょじょにいっしょになってゆきます。男の人が斡旋して遊女たちがお客をとり、その時になんらかの歌や芸能が披露される世界ができてくる。どこの国にも同じようなプロセスがあると思いますね。ルーマニアにもあるでしょう。
ラモーナ そうですね。状況は違いますが、結果的には同じようなことが起こっています。
金魚屋 ロマ族はルーマニア人なんですか。
ラモーナ ルーマニアに住んでいるロマ族はルーマニア人ですが、民族的には違います。言葉もロマ族独自のものです。
金魚屋 ロマ族の音楽はすごいですが、ヨーロッパでのイメージはあまり良くないようです。一種の被差別民族と言っていいんでしょうね。

馬場 世阿弥たちの時代に、被差別的であった人たちが芸術家になってゆく。そこが面白いのね。彼らは勉強したわけですが、彼らに学問を与えたのは貴族です。多分、いっぺん聞いたことは忘れないような頭のいい人たちだったんでしょうね。『万葉集』を与えればすぐに覚えちゃう。良基が連歌を始めれば、すぐに連歌もできるようになっちゃう。良基の前で歌を書き写したりできないから、本を借りてくる。それを一夜で読んで覚えちゃうっていうところがあった人たちだと思います。また知的な能力ばかりでなく、身体的能力も優れていた。身体的な芸も一夜で覚えてできちゃうわけです。
江戸時代には、役者と音楽家が一晩で作り上げた作品がありますね。たとえば『越後獅子』などは出し物が少し窮屈になった時に、いろんな民謡なんかを繋ぎ合わせて一晩で作っちゃった。芸能者はそういった能力を持っていた人たちなんです。雑学に長けている人たちが学問に触れると、すぐそれは身体に入ってきます。ですから良基が持っていた学問的なものが、全部身体に入ってしまうと、上流階級、つまり知識に裏付けられた芸能を見たい人たちのために、素晴らしい文言で能を作るようになったんです。
ただそういう芸能は、やはり一人の天才を必要としているでしょうね。一人の天才が一つの芸能を生み出す。そういう人がどこの国にもいるんですね。『平家物語』は琵琶法師が伝えたわけだけど、ああいった文章を作ることができた琵琶法師がいたわけです。なんなんでしょうね、ああいう能力は。今の学校教育とはまったく違って、生まれた時から貧しくて、ひっぱたかれたり食べるものも食べられなかったりした中で、身体を切るようにして覚えた芸です。すごいと思います。
後白河法皇編纂の『梁塵秘抄』と『口伝集』がありますね。特に『口伝集』はものすごく面白い。あれは塙保己一が『群書類従』に収録したことで知られていましたが、明治になって佐佐木信綱さんたちが新たに発見した巻も含めて公刊された。わたしは昭和四十年代になってから読んだわけですが、塙保己一のような盲目の人が、よくまああんな膨大な叢書をまとめあげられたものだと思います。ああいう人がいるんですよ。世阿弥もいっぺん聞いたら忘れないっていう人ですよね。やっぱり恐ろしい鬼ですよ(笑)。
■記憶の伝達について■
金魚屋 馬場さんは武家・貴族が頂点を為す封建社会では、〝才〟がなくては生きていけない人々がいたという意味のことを書いていらっしゃいます。貴顕も努力したでしょうが、基本は世襲ですから世を渡っていくための才などいらない。才を必要としていたのは庶民ですね。
馬場 能に『善知鳥』という曲があります。善知鳥を殺して生計を立てていた猟師が亡霊となって、殺生に終始した前世を嘆くという内容です。あの中で亡霊の猟師が、書がうまかったら、絵が描けたら、琴が弾けたら、歌が上手かったら、こんな殺生をしないで済んだのにと嘆くんです。芸があれば、身分を越えて貴族たちと付き合うことができたのにと嘆く。庶民はそういう憧れを持っていたけど、たいていの場合、猟師は猟師の一生を過ごさなければならなかった。そこから逃れられなかった。鳥や魚を殺せば仏様の殺生の罪に当たるわけだけど、そうせざるを得ない人々がいて、それが彼らの仕事だったんです。あの箇所を読むといつも胸に沁みます。
金魚屋 歌人としても批評家としても馬場さんが面白のは、日本文化の原理から出発されているところです。『鬼の研究』を例にすると、鬼は中国伝来の文字で概念であり、最初は死者とその招魂の意味でした。それが奈良時代になると不特定多数による反体制的意志に変わり、平安時代には怨霊化してゆきます。それは古代的な精神文化の変遷ですが、馬場さんはそれが中世・室町時代の初期になって、世阿弥によって一つの様式にまで高められる、古代的な精神文化が能に集約されるという意味のことを書いておられます。今さらこんなことを言ってもしょうがないですが、それは大変な卓見だと思います(笑)。
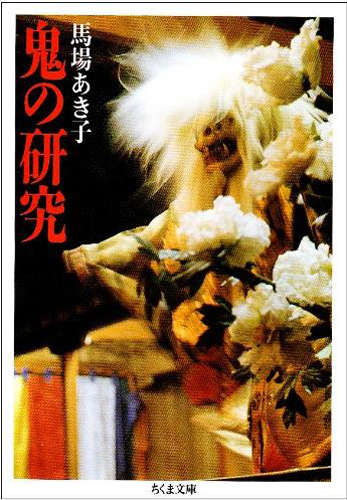
馬場あき子著『鬼の研究』(ちくま文庫版)
初版は昭和四十六年(一九七一年)刊
馬場 だから能が江戸時代の侍の基礎教養になったんです。謡を習えば粗々ですが、なんとなく日本の文学と歴史がわかるんです。今なら中学卒業レベルの教養に値したんじゃないですか(笑)。
金魚屋 まったくそうですね。武士は無駄なことが嫌いですから(笑)。
ラモーナ 能には記憶の伝達という機能もありますね。
馬場 人間の記憶、歴史ね。人間は忘れっぽいですが、どんどん忘れていく過去を、お坊さんの前で告白することによって赤裸々に再現できるんです。題材は古代から『鉢木』のような現在のものまで、能によって過去の記憶を伝達することができた。能の後は歌舞伎などが、能とはまた違う伝統を形作ってゆきました。ただ歌舞伎は時代とか時間を無視することによって、奇想天外なドラマを生んでいきますから、能のような歴史ではないです。もう一つの情念の伝統ですね。庶民の情念が歌舞伎に集約されていった。政治家や学者は情念なんてくだらないものだと思いがちなんですが、庶民が一番鬱々と抱え込んでいるのは情念ですからね。それが歌舞伎に至る芸能で表現されているんです。じゃあ現代の情念って何かというと、なかなか伝わらないというか、表現しにくいですけどね。
小嵐九八郎さんという小説家で歌人がいます。彼は『日本赤軍!世界を疾走した群像』というインタビュー集をまとめています。ご自身は赤軍派じゃないんですよ。早稲田大学の社青同解放派で活動していて、投獄されてしばらく牢屋にいました。我々もそうですが、あの時代が終わったあと、みんな違う道を歩き始めたんです。でも小嵐さんはあの時代に固執して、インタビューによる赤軍派主要メンバーの銘々伝をまとめているんです。そこのところがなかなか見上げたものだと思います。彼はそういう形で自己の情念を通した。それから福島泰樹という歌人がいましてね。彼も短歌絶叫という形で自分の情念を一生通そうとしている人です。だから一九六〇年から七〇年代にかけての人たちには情念があった。
■成仏について■
金魚屋 福島さんは、失礼ですが若い頃はなんだこのオジサンと思っていましたけど、あそこまで一貫しているとこれはやはりすごいやと思いますね(笑)。情念にもつながりますが、観世銕之丞さんにインタビューさせていただいた時に、能では成仏なんてどうでもいいんだ、その前段をどう作るのかが大事なんだということをおっしゃっていました。僕らはヨーロッパ的な物語構成に慣れていますからテキストとして能を読んだ時に、やはり成仏をクライマックスとして捉えてしまうところがあります。でもそうじゃないんだという銕之丞さんのお話しはとても刺激的でした。
馬場 当然です。誰も成仏なんかしてないですよ(笑)。
金魚屋 平安時代は貴顕から庶民に至るまで、成仏できるかどうかが最大関心事だったわけですよね。それが室町時代になると、お約束事としての成仏は残りましたが、実際はぜんぜん成仏しない、できない亡霊たちが現れてくるのはなぜなんでしょう。
馬場 室町時代は、地獄がどんどん近づいてきたような世の中です。現実そのものが地獄なんです。狂言を見れば一番よくわかるんですが、狂言は地獄をおちょくっています。地獄なんてくだらないもので、もっとくだらないのが成仏です。地獄がどんどん現実世界に近づいてきて、観念としての地獄や浄土(成仏)なんかくだらなくてしょうがなくなった時代なんです。世阿弥の時代には、自分たちが住んでいる世の中の方がよっぽど地獄だよという意識があったんでしょうね。さきほどお話しに出たように、能は記憶のものがたりや、歴史の伝達芸術ですから成仏はいらないんです。でも成仏しないと幕が下りない(笑)。正確に言うと能は幕がないですから、成仏して舞台から去っていく以外にどんな終わり方があるのかなと思います。こういう人生を送りました、はい、それで終わりというわけにはいかない(笑)。

ラモーナ 世阿弥の能は、成仏できなかった人たちが能の中で成仏するという構成になっています。それは仮の成仏ということでしょうか。
馬場 『清経』は、平清経が柳浦に入水した史実を元にしています。でも清経がほんとうに成仏したのかどうかは誰にもわからない。それを成仏したということにしてあげると、確かに救いがありますよね。また世阿弥がなぜ『平家物語』にある通りに能を作りなさいと言ったのかというと、現実の世界がひどすぎたんです。現実は殺伐とした『太平記』の世界です。『太平記』の時代の理想が『平家物語』だった。世阿弥の時代は裏切り、詐欺、騙しが朝飯前でした。昨日和睦して今日攻めて、今日攻めて明日降伏するということが平然と行われていた。誰を、何を信じていいかわからない時代だったんです。そんな世の中で世阿弥が求めた倫理が美だったと思います。『太平記』には美がないんです。人間的な倫理や美を求めるとすれば、『平家物語』になる。能はそういう意味で一つの教訓です。目の前にいる侍たちに、人はこうやって生き、こうやって死ぬものだということを教えているんです。
金魚屋 それはすごくよくわかります。『太平記』よりも『平家物語』の方が圧倒的に面白いんですが、それは『平家物語』が美しいからでもあるんですね。
馬場 『太平記』は講談にはなるけど、琵琶には乗らない。美しくないんです。語調が良くて美しいのは、日野俊基卿が東下りをする「落花の雪に踏み迷う、片野の春の桜狩り」の箇所くらいですね。
金魚屋 『太平記』はどう読んでいいのかわからないところがありましたが、現実そのものと考えれば、読み方のとっかかりになりそうです。
馬場 『太平記』は欲望の渦巻く坩堝で殺伐とした世界です。でも『平家物語』は室町初期の武士にとってだけでなく、当然公家の理想でもありました。現実の兵たちを見て、イヤだなと思う気持ちが強かったでしょうからね。『平家物語』に描かれたような死に方が本物だという思いがあったんじゃないでしょうか。いかに死んだかは、いかに生きたかなんですから。もちろんそういった考えが、『平家物語』の時代の人にあったかどうかはわかりませんよ。でも世阿弥にはそういう理想があった。あの人は哲学者であり芸術家なんです。『風姿花伝』は世界で最初の能芸論ですが、それをもっと日本人は誇りにしていいと思います。世界から能が注目されると、日本人もようやく能の素晴らしさに気付くというのが今までのパターンですから(笑)。

馬場あき子著『古典を読む 風姿花伝』(岩波現代文庫版)
初版は昭和五十九年(一九八四年)刊
金魚屋 能はもちろん短歌や俳句にもそういうところがありますが、世界の共通言語で語りにくい、説明しにくいところがありますね。西洋的な論理的言語に乗りにくい。
馬場 当たり前の中に、なにか非凡なものを見つけなければならないんです。
金魚屋 能の成立には禅が影響しているんじゃないでしょうか。平安仏教は密教的ですが、鎌倉になると禅宗が盛んになるでしょう。
馬場 大きいでしょうね。能ができたのは禅の全盛時代ですから。
金魚屋 室町時代の絵画は墨一色の水墨画になるわけですが、どこかで能とつながっているんじゃないでしょうか。
馬場 そうですね。殊に禅竹の作にはそうしたところがあると思います。能が一番大事にしたのは三番目物です。しかもその中に、本三番目物と言われる曲がある。それは三番目物の中でほんの少数です。本三番目物の条件は何かというと、一人の僧の前に一人の美しい女が出てきて恋の過去を語る。そして回想の序の舞を舞う。それは太鼓の音が入らない静かな序の舞なんです。その中に女の一生の思いがこもっていることを表現する舞です。そこには坊さんが必要なんですね。
坊さんはわれわれにとってはたいていの場合単なる坊主ですが、中世の観客は仏に近い偉いお方がお出ましになったと思った。浄土であっても禅僧であっても、坊さんは偉いお方に違いなかった。そして僧の登場によって舞台の雰囲気が無常と化すんです。そこに無常の世界とは正反対の妖艶な美女が出て来る。舞台の上で艶と無常がぶつかるわけです。そして舞台で艶と無常が対話をするところにたまらない魅力が生じる。
現代はそこにあったそういった両極が、わかりにくくなっていますね。坊さんは世を捨て世を超えている存在ですが、艶な女は生の一点に執着している存在です。本来なら交わらないはずなのに、僧は女の言葉を最後まで聞きます。女の言葉はしばしば僧の夢になってゆく。生も死もなく、現世は空無だと思っている僧の脳裏に、女の艶な夢が近づいてくるんです。そのような艶と無常が交差する舞台に、殺伐とした世の中を生きる観客たちが酔ったんだろうと思います。「そうだ、恋というはるかなものへの憧憬がこの世にあったんだ」とね。美しい序の舞を、半分眠るようにして見ながらそう思うのは、やっぱり詩の世界なんです。わたしたちの、日本の詩の世界かもしれません。そういった実に微妙な詩の世界が、これからも生き続けてゆくかどうかはわかりませんが。
■短歌の現状について■
金魚屋 現代の大きな変化は一九九〇年代から始まったと思います。いわゆるインターネット時代、高度情報化時代ですね。それから約二十年ほど経ったわけです。ただ馬場さんはよくおわかりだと思いますが、日本の長い長い文化伝統が、たかだか二十年程度で決定的に変化してしまうとは到底思えません。
馬場 短歌の世界でも、若い人たちの歌がいろいろな形ではやっています。彼らは彼らで短歌の型というものに抵抗しているんです。なんとかこの型を崩さなければいけないと試みています。「人間性がなさすぎる」と言うと、「それって昭和の人間性でしょ。そんなものは問題にしてないよ」っていう答えが返ってきます。そういった状況の中で、どんどん歌い方が変わってきています。生の全体ではなく、断片的な部分に注目して、面白いものももちろん出ています。それから日本語の助詞と助動詞が使えなくなっています。短いフレーズをぽんぽんと重ねてブロックにするのが若い人たちの短歌です。でも助詞と助動詞が消えると日本語には余情がなくなってしまうんです。そういった中でなにが評価されるかというと、アイディア勝負ですね。誰が面白い言葉と言葉を繋ぎ合わせたか、組み合わせたかが評価される。それはそれで面白いんですが、抒情がなくなっちゃうわね。でも短歌は本来抒情詩として出発したものです。それが現代になって滅びるかというと、わたしは滅びないと思います。
若い歌人が四十歳になれば、人生とはなんだろうと考え始める。五十歳になれば老いも迫ってくる。歌人一人一人の人生の歴史が積み上がれば、型を含めた短歌文学の伝統を、彼らもまた認めてゆくだろうと思います。だから若い歌人たちにそんなに失望はしていないです。ただ彼らは「昭和の人間は滅びた」とか言いますから、「そうかい滅びたんだねぇ、わたしは」と言ってるだけですね(笑)。でも人間の生はいつか終わりますが、短歌は滅びないものです。

金魚屋 短歌の世界にはそれほど詳しくないのですが、日本社会が大きく変化するときには、それと連動して文化も変わるだろうという予感はあります。特に詩の世界が世の中の変化にビビッドに反応しやすい。日本の詩には短歌、俳句、自由詩の三つのジャンルがあるわけですが、その中で明らかに大きく変化しようとしているのが短歌で、その代表が口語短歌です。日本の一番古い文学ジャンルが現代に呼応して動揺し、変化しているのはとても面白いと思います。
馬場 口語短歌は面白いですよ。わたしも使っていますからね。口語は実感があってとてもいいです。ただ文語と口語の両方を使わなくちゃならないのね。締めるところは文語の方が締まるんです。
金魚屋 馬場さんは、口語短歌でスタートして歌集をまとめた歌人が、それ以降に文語体を中心とした短歌の王道に戻ることができるとお考えですか。
馬場 難しいと思います。一度口語の毒を舐めちゃったらこれはおいしいですよ(笑)。でも慣れ親しんだお米の、文語の味も、これはこれで絶品なんです。だからいっしょにやったらいいんです。わたしは古典をやっているからよくわかるんですが、『万葉集』だって口語と文語の歌があります。「東歌」なんて、ところどころに文語が入るだけで地は口語、しかも方言ですからね。平安時代だって一般大衆は口語で歌ってたんです。作品がほとんど残っていないだけでね。
金魚屋 馬場さんは短歌結社「かりん」を主宰しておられるわけですが、「かりん」では口語短歌はオッケーなんですか。
馬場 もちろんみんなやっています。それにうちは短歌観にテーゼがあって、強く結束したという意味での結社ではないです。精神的に緩く結ばれたグループです。
金魚屋 巨大グループだと思いますが(笑)。
馬場 わたしのような古いものも抱えながら、若い人たちがわいわいやっていますよ。時々コラッて言うだけです(笑)。うちは本当に自由勝手です。
金魚屋 「かばん」はどうですか。
馬場 「かばん」は今誰が中心になってやってるんだろう。穂村弘や東直子がいっしょうけんめいやってた頃は記憶してるけど、彼らも今は会費くらいしか払ってないんじゃないかな。「かばん」は自由に見えて、てんでんばらばらです。「かばん」ではお互いがライバルでしょう。誰もが新しいことをやって注目されなければならないと考えているから、精神的にはちょっと苦しいところがあるかもしれません。

馬場あき子主宰歌誌「かりん」平成二十七年(二〇一五年)一月号
創刊は昭和五十二年(一九七七年)
金魚屋 短歌、俳句の世界では、精神的な支柱があった方がいいかもしれませんね。金魚屋ではオープニングイベントで「安井浩司俳句と墨書展」を開催しました。その時初めて現実の俳句の世界に触れたんですが、俳壇はものすごく息苦しいですね(笑)。
馬場 俳句の世界の結社がいわゆる結社なんですよ(笑)。「かりん」の歌会を見に来てくださればわかりますが、わたしなんて隅っこでちっちゃくなっています。若い人たちの天下です(笑)。
金魚屋 物知らずなお話しで恥ずかしいですが、俳壇の人たちと接触してみて、「海程」の金子兜太さんが前衛俳人だと初めて知りました。前衛というと高柳重信系のイメージが強かったものですから。俳壇の中心は明治以降ずっと「ホトトギス」系で、「ホトトギス」を中心に考えれば、前衛俳句として許容できる限界が金子さんの「海程」だということなのかもしれませんが。
馬場 高柳さんが「船焼き捨てし/船長は//泳ぐかな」を発表した頃に、金子さんが「湾曲し火傷し爆心地のマラソン」を書いたわけでしょう。重信の抽象的な前衛に対して金子さんは社会詠の旗を立てたわけです。
金魚屋 馬場さんも初期は政治的なことを含め、社会詠をやっておられましたね。生活の機微まで手に取るように伝わってくる歌でした。
馬場 わたしは初期はダメですよ(笑)。わたしは生活短歌から入ったんです。昭和三十一年(一九五六年)に塚本邦雄・大岡信の「前衛短歌論争」がありました。あの論争の、特に塚本の論に大衝撃を受けて目覚めていったんです。大岡さんは詩人ですが、お父さんの博さんはわたしと同じ窪田空穂系の歌人で、ごく普通の生活詠を作っておられた方なんです。人間発見みたいなね。ですからあの論争では塚本の方が急進的で、大岡さんはちょっと引いた立場だったと思います。
金魚屋 俳句は五七五で短歌は五七五七七で、短歌の方が七七長い。だから初心者には俳句より短歌の方が難しそうに見える。実際、俳句人口の方が短歌よりも多いですよね。でも俳句のように形式にがんじがらめになっている表現より、短歌の方が形式的に緩いですからある意味で作りやすいようにも感じるんですが。
馬場 わたしは俳句より短歌の方が作るのが簡単だと思います。でも俳句より七七長いですから、短歌文学では自分を裸でさらけ出さなければならない部分があります。七七にそれが出るんです。それがイヤな人たちが俳句をやるんでしょうね(笑)。またちゃんと自分をさらけださないと、短歌はぐうたらな表現になってしまう。だからわたしたちは下手な俳句を見ると、七七を付けてやろうかと思います。その逆に、俳人は下手な歌を見ると七七を取ってやろうかと思うみたいですね(笑)。よく野澤節子という俳人と、そんなことを言って論争しましたよ。わたしが「こんなの七七付くよ」と言うと、野澤さんが「あなた、この歌は七七取れるわよ」と言った感じでね(笑)。
金魚屋 正岡子規が短歌革新を始めた時に、高浜虚子、河東碧梧桐以下の俳人に短歌を作らせてみて激怒した文章が残っています。俳人の短歌は五七五に七七足しただけだと(笑)。

馬場 オールマイティの七七というのは確かにあります。たとえば「根岸の里のわび住まい」とかね。これはオールマイティで、どんな五七五でもそれでまとめることができる。ただそういったオールマイティが見え隠れするのは手なれたプロの歌人にいますよね。素人の歌は情念だけで、終わりまで自分のことを言いたがっているけれど、でも内容は通り一辺倒になりがちだわねぇ。こんなことみんな歌ってるんだからやめなさいって言いたくなるようなおじいちゃんおばあちゃんの孫の歌なんて、山ほどあるわけです(笑)。だけど百万の大衆が孫の歌を作りたいって言ったら、それはそれでしょうがないんです。それによって短歌が次世代に渡っていくわけですから。それは新作能も同じです。こんな新作能を作らないで古典的ないい能だけ舞ってたらいいじゃないと言うけれども、折りに合った新作能がいっぱい出ることによって、伝統の能のよさもわかり守られていくんです。時の花って仕方ないんです。時の濁流も仕方ない。時の花と濁流に揉まれながら、次の世代に芸術を伝えていくほかないんです。
■新作能について■
金魚屋 新作能はよくご覧になりますか。
馬場 自分でも作っていますよ(笑)。
ラモーナ 来日前で見ることはできなかったですが、馬場さんが二〇一一年に国立能楽堂で上演された『影媛』についてはいろんな人から話を聞いています。さきほど能には記憶の伝達機能があるというお話しが出ましたが、新作能はどのくらいまでの過去を題材にすることができるんでしょうか。
馬場 どこまでも遡ることができると思います。かぐや姫だろうと海彦・山彦の神話世界だろうと、材料としてはなんでも持ってこられる。どんな古い物語だろうと、人間の本質は変わらない。人間が起こすドラマであれば新作能に作ることができます。だから山のように素材はあるんですが、能は短歌と違って口語だけでは絶対に作ることができないんです。わたしも口語で能を作ったことがあるんですが、これじゃあダメだと言われてしまった。なぜかと言うと、能にはお囃子が付いているんです。言葉がお囃子にも合っていなければならない。世阿弥が『三道』という本の中で、初めにワキが出てきたら何句まで道行を謡いなさいと書いているけど、その形式でお囃子ができあがってしまっている。短くても長くても都合が悪い。きちんと作ろうとすれば、能の様式に合わせてその通り作らなきゃならない。お囃子方だけじゃなくて、クセも上ゲ端が一回か二回なきゃいけないとか決まっていますから、そんなに斬新なことができないんです。わたしも何度かわがままな試みをしてみたんですが、みんな直されちゃいました(笑)。そういう決まり事を全部取り外して、能舞という、舞だけの部分を作るならある程度は斬新なこともできると思いますけどね。

馬場あき子作・梅若玄祥演出・村上湛補綴 新作能『影媛』ポスター
平成二十三年(二〇一一年)七月二十九日~三十日 国立能楽堂にて上演
ラモーナ 新作能の題材は、十九世紀とか二十世紀の、近い過去でもいいんでしょうか。
馬場 いいですよ。ちょっと前の過去を題材にした新作能でずっと上演され続けている作品に、高村光太郎の『智恵子抄』があります。観世銕之丞さんの銕仙会が、節付けから型付けまで全部持っている能ですから、他流ではなかなか上演できませんけどね。初演の時は防空頭巾をかぶった智恵子とかが出てきました。今はその中の舞の部分だけを、「智恵子抄」として演じたりしています。
ラモーナ 新作能は、能という芸術に新しい息吹を与えることができるんでしょうか。
馬場 できません。たとえば新作能で、梅若玄祥さんが演じた『紅天女』があります。あれは美内すずえさんの少女マンガ『ガラスの仮面』を題材にした新作能です。そうするとキャピキャピした女の子たちがいっぱい来てくれるわけです。やってる内容は『羽衣』とそんなに変わらないんですけどね(笑)。でもそれによって能という芸能に触れてもらえるわけで、それはとても大事なことです。それでいいんじゃないでしょうか。
ラモーナ 新作能の他に、現代能というカテゴリーもあります。能の要素を取り入れた現代演劇です。錬肉工房さんとかですが。
馬場 ああ錬肉工房ね。銕之丞さんとか金春流の櫻間金記さんとかが時々出ていますね。現代能の『ベルナルダ・アルバの家』とかやっていましたね。
ラモーナ 新作能と現代能の共存についてはどう思われますか。
馬場 いいんじゃないですか。ただ能の世界の人たちは、現代能を能だとは思っていないでしょうね。能を見る人たちの、五分の一くらいが現代能を見てるんじゃないかしら。後のお客さんは、ちょっと革命的な演劇だということで現代能を見ていると思います。鍊肉工房は岡本章さん主宰ですよね。昭和三十年代に前衛演劇が全盛だった頃から活動しておられます。わたしも昔、芝居をちょっとやったことがあるんです。竹内健という寺山修司の友達だった演劇人がいましてね、農協ホールがまだあった頃に、一回だけわたしの原作、竹内さんの脚色で『般若由来記』という劇を上演したことがあります。
■岸上大作と寺山修司について■
金魚屋 馬場さんは岸上大作さんと交流がありましたね。
馬場 あの子がね、(わたしはあの子って呼べる歳だったんですが、)あの子が高校生の頃から遊びに来ていたんです。だけど岸上みたいな時代を象徴するような青年が死ぬと、わーっとわたしのモノですって言い出す人がいるじゃない。だから岸上については、そういう人に任せることにしています(笑)。
金魚屋 あまりいいことではないですが、文学の世界には時々そういう人がいますね。死人に口なしですから(笑)。岸上さんは寺山修司と衝突することがあったようですが、馬場さんは寺山さんとは交流がありましたか。
馬場 割と仲が良かったです。
金魚屋 やっぱり(笑)。金魚屋は時々寺山さんの追っかけじゃないかと思うことがあります。俳人の安井浩司さんは、寺山さんが青森高校時代に出していた俳句同人誌『牧羊神』の同人ですし、脚本家の山田太一さんは早稲田大学時代の友達です。寺山さんは荒木経惟さんに弟子入りしてカメラを習っていますし、イラストレーターの宇野亞喜良さんは寺山さんの舞台芸術をかなり手がけています。また詩人の谷川俊太郎さんは阿佐ヶ谷の河北病院で寺山さんの臨終を看取った。どなたにインタビューしても寺山さんがいる(笑)。
馬場 寺山と付き合っていた頃は、わたしは三十代だったから、中年のオバサンだったんです。寺山は中年のオバサンを大事にしてましたね。舞台のチケットを買ってもらわなきゃならないから(笑)。あまり言っていないけど、当時の女流歌人の多くが寺山さんの舞台のチケットを売ってあげたんじゃないかしら。わたしは寺山さんとはよくシンポジウムなんかでいっしょになることもあって、夜、電車がなくなって男女混みで宿屋で一部屋借りて、寺山さんが「寝ちゃダメだぞ。ここにいないヤツの悪口言おうぜ」と言うもんだから、朝まで人の悪口を言いながら起きていたことがあります(笑)。寺山さんは女の人を文学的にはあんまり信頼してなかった。頼みにならなかったのでしょうね。支援者としては大切だった。

金魚屋 寺山さんは背が高くて大柄だったわりには、ひ弱だったでしょう。
馬場 病弱だし気が弱いしずるいし(笑)。でもそれじゃなきゃ生きられないしね。
ラモーナ 馬場さんは「逆光のロマン」という記事で、馬場さんの出版記念会に来た寺山さんが、「僕と馬場さんの歌はイトコだからな」と言ったと書いておられますね。
馬場 そこが寺山さんのやさしいところです。短歌という様式を使うかぎり、どっちみちいとこくらいの関係はあるでしょう。
金魚屋 どういう意味ですか。
馬場 短歌を作るというなつかしみはあるけど、方向がちがうということですよ。
金魚屋 安井浩司さんはかなり寺山さんを批判しています。東京の大学に同時に進学していますから、例の「短歌研究」新人賞の時に、寺山さんが既存俳句に七七を足すのを見ていたようなんです(笑)。
馬場 あの頃の寺山はひどかったわねぇ(笑)。
金魚屋 でも安井さんを除いて、どなたに聞いても「寺山ね、まあいいじゃない」となる(笑)。
馬場 あの人は、どこか悪口を言えない人なのよ。でも昭和三十年代の寺山は貧乏で身体が悪くてね。われわれは青年歌人会議とか東京歌人集会とかをやっていたんですが、寺山は集まりに来ると「一番安いのはなにかなぁ」と言って、メニューで一番安いオレンジジュースを頼むんです。わたしたちはカレーライスを食べたりしてたから、かわいそうで気の毒で、カレーライスのお金を出そうかと思ったけど、それはみんながいるからできなくてね。でもある時大阪でシンポジウムがあって、寺山といっしょにご飯を食べに行ったら、「馬場さん、いいとこで食べようぜ」って言うの。いいレストランに入ったら「一番高いもの食べようぜ」って言ったんです。へーと思いましたよ(笑)。それで寺山は食べながら、蟹の殻なんかをぺっぺと床に捨てるんです。「あなたそんなことしちゃダメよ」ってわたしが言うと、「俺がここに汚らしく散らすから、あのオバサンたちは首にならないで済むんだよ」って青森弁で言うわけ。掃除するオバサンたちのことを考えてそうしてるんだって言うの。高級レストランに来たら散らかさなきゃならないってのが、寺山流だったようです(笑)。
金魚屋 やっぱり寺山さんは偏在してるなぁ(笑)。
馬場 寺山は自分を世の中に押し出すために、たくさんの人と付き合っていたのね。それに芝居の打ち上げでは親しい人たちがみんな残るでしょう。そうやってお酒飲んだりしてると、自然にみんなと友達になるものね。

馬場あき子監修 『現代短歌の鑑賞辞典』
東京堂出版 平成十八年(二〇〇六年)刊
金魚屋 寺山さんの短歌はどう思われますか。
馬場 面白いです。『空には本』がいいですが、『田園に死す』もまあいいですよね。架空の事柄を短歌で歌いながら、実感があって本当のように見えてしまうところが面白いんです。
金魚屋 寺山さんは希代の嘘つきですからね(笑)。子供の頃貧乏だったとかいじめられっ子だったとか書いていますが、小学校の入学式でみんな下駄や草履のところを、彼だけ革靴だったそうですから。学校でも人気者だったようです(笑)。
馬場 そのへんはみんな嘘(笑)。ほんとにあんなに架空の自分の伝記を作っちゃった人はいないですよね。でも寺山さんのお母さんは、彼の劇の中で挽肉器にかけられても、修ちゃんのやることならって全部許してくれたんですね。
金魚屋 馬場さんは、寺山さんの本業はなんだったとお考えですか。ご本人は「職業寺山修司」とかうそぶいていましたが(笑)。
馬場 そこなのよ。寺山は芝居をやったかもしれない、競馬評論を書いたかもしれない、でも彼は歌人だから名前が残ったんだという見解がありますね。でもわたしは寺山の本業は芝居だったと思います。
金魚屋 そうですよね。アングラ演劇は、どこか懐かしくていかがわしい雰囲気を漂わせていましたが、それが寺山さんによく合っていました。
馬場 寺山はやっぱり芝居ですよ。だって寺山の歌は、今になるともう古いですもの。『田園に死す』なんかもリアリティゼロでしょう。それなのに高度経済成長期のノリノリの気分に『田園に死す』がぴったり合っていたわけです。蜷川幸雄演出の『田園に死す』の舞台も素晴らしかったなぁ。あれはもう一回見たいんだけど見られないわねぇ。舞台は消えちゃうからね。
金魚屋 土方巽さんもそうですが、寺山さんも東北らしい表現者でしたね。
馬場 わたしは土方さんもよく知ってるのよ(笑)。アスベスト館によく舞踏を見に行ったもの。それに土方の最初の奥さんは同僚で友達だったんです。元藤燁子さんの前の、最初の奥さん米山さんね。アスベスト館によく通ったのは昭和三十六、七年頃で、詩人たちがアスベスト館に詰めかけていましたよ。詩人たちが多くて、女で歌人なんてわたし一人しかいなかったから、もう誰が誰だかよくわかりませんでしたけどね(笑)。
ラモーナ 鈴木忠志さんの『リア王』もご覧になっていますね。
馬場 鈴木さんの『リア王』はお能的でした。利賀村の、自分の足下もよく見えないような漆黒の闇の中で見る『リア王』はすごく面白かった。古い農家の梁に、豪華絢爛たる着物を背表に着た俳優の姿が浮かぶんです。不気味なような妖しいような印象の舞台でした。
(2015/10/09 後編に続く)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■馬場あき子さんの本■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


