Interview:三浦雅士インタビュー(2/2)
三浦雅士:昭和二十一年(一九四六年)青森県弘前市生まれ。思想家、文芸批評家、舞踊研究家、編集者。四十四年(六九年)に青土社創業と同時に入社。四十七年(七二年)より「ユリイカ」編集長、五十年(七五年)より「現代思想」編集長を歴任。五十七年(八二年)に退職後、本格的文筆活動を始める。『メランコリーの水脈』でサントリー学芸賞、『身体の零度』で読売文学賞受賞。現代文学と思想のみならず、お能、日本舞踊、バレエなどの舞台芸術にも精通している。
■舞台芸術について■
金魚屋 思想であれなんであれ、最後は納得できるかどうかということだと思うんですね。腑に落ちるという言い方がありますが、肉体的なレベルで納得できなければ思想は意味がないと思います。
三浦 それは本当にとても大事ですね。身体的な芸術の話をすると、お能の系譜で一番重要なのは地唄舞だと思うんだな。地唄舞にお能の最良のエッセンスが残っている。当代の井上八千代が本当に素晴らしいレベルになっているんです。先代八千代の長刀八島がYouTubeにアップされていて、それは本当にすごいんだけど、当代は先代に接近しています。それは背中を見ていればわかる。
日本舞踊の動きは全部当て振りなんです。「わたしはあなたのことが好き」でも、「雨が降ってきましたね」でもいいんだけど、その動きはすべて物真似なんです。だけど物真似だけやっていたのではダメと考えた舞踊家がいた。歌舞伎役者ですが、六代目の尾上菊五郎がそうでした。彼は舞踊には軸が必要だと考えたのですが、その軸を、歌舞伎じゃなくてお能に見つけた。そしてお能からさらに地唄舞に踊りのエッセンスを見出していった。地唄舞では山村流と井上流の二つの流派が重要でした。六代目菊五郎は歌舞伎界の大スターだから、地唄舞の方でも愛想良く対応して、彼はその芸を吸収していったんです。だから六代目菊五郎は、お能を経由した地唄舞の動きをはっきり持っていました。
日本舞踊の動きの要は下半身にあります。移動するにしても、腰から上はぜんぜん動かない。ツーッと平行移動してゆく。この動きを完璧にマスターすると、身体が動いているんじゃなくて、背景が動いているように見える。電車に乗っていると、自分が動いているのか風景が動いているのかわからなくなるような瞬間があるでしょう。それと同じです。この動きはモダンダンスなどでも同じ効果を生みます。特に群舞で腰から上を動かさないで身体を上げたり下げたりすると、背景が上がったり下がったりするように見える。実際に舞台でそれをやると、見ている方は魔法を見ているような感じになります。それをモダンダンスでやったのは、僕が見た範囲では山海塾ですね。山海塾がどういった経緯でそれを取り入れたのかはわかりませんが、動きの効果を十分計算した背景を作っていましたから、意図的なんでしょうね。井上八千代は先代も当代もそういう動きができるわけですが、インドネシアの昔の舞踊の映像を見ても、その動き方は同じです。

現代のポップスターで言うと、マイケル・ジャクソンがそういう動きをしています。彼のムーン・ウォークのポイントは足じゃないんだ。腰が動かない。マイケルの動きはロボットみたいだというけど、井上八千代だってそうです。マイケルはマルセル・マルソーと親しかったでしょう。マルソーの動きもまったく同じです。マイケルやマルソーほどではないけど、ジーン・ケリーやフレッド・アステアの動きも似ています。タップダンスしていても上半身はブレない。バレエなどでも基本は同じです。
なぜ世界中がマイケル・ジャクソンに熱狂したかというと、歌も素晴らしいけど、彼が天才的な舞踊家だったからです。歌以上に彼の身体が観客を魅了した。なぜ彼の身体が観客を魅了したのか、それを考える研究家は今のところいませんね。メルロ・ポンティが生きていればやったかもしれない。彼は諸感覚の秩序ということを考えた哲学者です。見ているだけなのに、なぜ人間は触覚を感じるんだろうといった研究です。
六代目菊五郎は芸が上がってゆかなければ日本舞踊は終わってしまうと考えた人だけど、そのポイントになったのが、井上八千代的な動きだったんです。彼女が橋掛かりから登場してくると、橋掛かりのセットそのものが動いているように見える。そこまでに行くにはすごい修練が必要です。井上流では「おいどを落とす」とかいう言葉があって、上半身を動かさずにスーッと腰を落としてまた上げてゆく。これが完璧にできるかどうかが芸の要なんです。だけどこの動きは元々お能が持っていたものなんだな。井上流はお能から来ていますからね。
こういう一流の舞踊の共通点は、違う文化の舞踊家たちが努力して獲得していったものだけど、次にそれはなぜだろう、なぜそうなったのか考えなくちゃならない。動物にはできなくて、人間だけなぜそんな動きができるのか、その理由を考えなくちゃならないんです。
若い舞踊家で言うと、野村萬斎は今の狂言界のスターですね。萬斎さんの背中を見ていると、まだ舞踊の最高の形を習得していない。まあ現代人は体型も違うからね。ただ萬斎さんは、彼なりに現代風の狂言を作ろうとしている。それが彼の偉いところです。萬斎さんは河合祥一郎さんといっしょにシェイクスピア劇などをやっていますね。池澤夏樹さんの小説を元にした新作狂言も上演した。そういうのを見ていても、萬斎さんは新しい狂言、新しい身体の動きを作り出そうとしている。立派です。だけど背中から匂ってくるものはあまり感じないな。
この背中でわかるお能や日本舞踊が持ってる動きがどこから発生したかと言うと、剣道からだと思います。同じ根から出ている。バレエの場合はフェンシングですね。さきほど井上八千代の長刀八島の話をしましたが、彼女はダテに長刀を持って踊っているわけではない。上半身と下半身を切り離して動いて長刀を振り回すわけだけど、それは生きるか死ぬかの時に重要な動きだったんです。また田んぼの中での動きでもあります。田んぼの中では飛んだり跳ねたりできません。足を取られて転んでしまう。その所作もお能や日本舞踊の基礎になっている。あるいは畳の上で立ったり座ったりする時の動きですね。
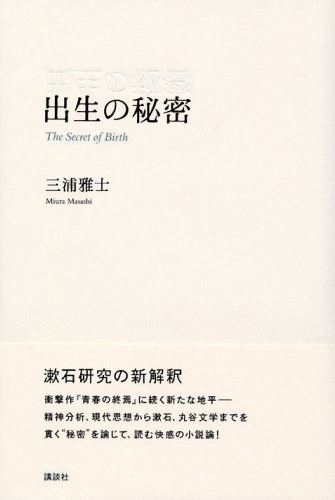
『出生の秘密』
講談社 2005年8月11日
バレエの場合は人間が馬に乗るようになってからの身体の動き、馬上でどのくらい自在に動けるのか、そのエッセンスがバレエの動きになっています。だけど今僕が言ったような形で舞踊を考えている人はいないんだな。オーストラリアに行ってバレエの起源の話をしたら、みんな唖然としちゃってね。「遊牧民、ノマドって、野蛮人じゃないですか」と言った人がいた(笑)。バレエをやっている人は文明人で、馬に乗って羊なんかを追いかけている人は野蛮人だという固定概念があるんだな。でも身体的所作はそういうものじゃない。水田耕作では飛んだり跳ねたりは御法度だけど、馬に乗るのは椅子に座っているようなものでしょう。馬の上でぐるっと回ったり、逆立ちできるような芸当ができて初めて馬と一体化できる。
お能や日本舞踊の動きは東南アジアの稲作文化が持っている舞踊にも共通していますね。バレエの動きはヨーロッパなどで共通です。それは一万年前から続いていて、じょじょに完成されていった舞踊、人間の身体の動きなんです。一万年以前になると、狩猟採集の時代になっちゃうからね。それを考えると、人間の身体の動きは古いものでもあり、どんどん変わってゆくものでもある。ここ何十年かを見ても、日本人の身体は変わったでしょう。みんなが胴長で足が短いより、足が長い方がカッコイイと思うと、じょじょにそうなってゆく(笑)。これは日本だけじゃなく外国でも同じでしょうね。だから伝統というものは、マイナスに作用することもたくさんある。室町時代と江戸時代、江戸と現代の日本人の身体は、ぜんぜん違うと考えた方がいいわけですから。まったく同じふうに繰り返すことはできない。
ただ腰と膝の動きが、世界中見廻しても舞踊の完成した芸の形であるのは確かです。六代目菊五郎はそれに気づいたんだけど、受け継ぐ者はいなかった。なぜかと言うと、芸事は秘伝化されちゃうんです。秘伝として継承されるうちに当初の目的、本質を見失ってしまう。秘伝は先生を権威化するものであって、必ずしも芸の継承ではない。

また身体が動いたときに背景が動いているように見える舞踊は、見ることの本質を教えてくれます。アルベルト・ジャコメッティという美術家がいますね。彫刻家として有名だけど、デッサンも重要です。リルケは『ロダン』という本を書いた後、『マルテの手記』の中で、「僕はパリという街に物を見ることを学ぶためにやってきた」と書いた。それはどういうことなのかを宇佐見英治さんと話したことがあるんです。宇佐見さんは矢内原伊作さんにジャコメッティを紹介され人で、ジャコメッティとも親しかった。そしたら宇佐見さんはジャコメッティのデッサンを見せて、ジャコメッティのデッサンは遠近法を使ってないけど凹凸が見える、鼻とかを見ればわかるけど、前に出てきているように見えるという話をしてくれた。
遠近法は消失点を決めて人や物を描く技法です。確かにリアルに見える。だけど中国の絵画では遠近法を使わずに、雲や空なんかをぼやかして奥行きを表現します。それと同じことをジャコメッティは彫刻で表現したかった。一人だけの人間が歩いてきても遠近を伴って見える。それはなぜなのか。一人っきりの人間の形だけでそれを表現しようとした。
このジャコメッティの意図が一番よくわかるのはデッサンですね。原理はとても簡単で、人間の目は二つあるということに尽きる。ジャコメッティのデッサンは基本的に全部シンメトリーで、かつ描線がブレている。飛び出す絵本と同じですね。飛び出す絵本のなかでも赤と青とか単純な色で構成されているものがわかりやすいんだけど、右目と左目では見たときに違うように見える。普通の画家は右目左目で見たものを一つの描線として描くわけだけど、ジャコメッティはそれは嘘じゃないかと考えた。それぞれの目で見た線をいっしょに描こうとしたんです。右目左目の見え方を重ね合わせれば二重の線に見える。右目と左目の体験を同じ画面の中で表現するのは、すごい発見ですね。この描き方だと平面的な絵でも遠近感が得られる。地唄舞の原理と同じです。平行移動するだけなのに背景が動く。立体的になるからです。
今思い出したけど、地唄舞の動きに注目した舞踊家に坂東玉三郎がいます。彼は世紀の大舞踊家です。昔と今では年齢も違うし、彼を取り巻く環境も変わってきたので難しいところがあるけど、彼の踊りは素晴らしかった。玉三郎さんは今は鼓童なんかといっしょにやっているけど、あれは一種の断念ですね。太鼓は心臓の音で、人を鼓舞するものです。地唄舞など芸の生地を見せるような踊りの名手には必要ない。お能でもそうでしょう。笛のピーッという音は、この世からあの世に移行する際の音で、そこから起こる様々な事を演じている時に、鼓などの太鼓の音が入る。それはともかくとして、六代目菊五郎を継ぐのは玉三郎さんだけだろうと僕は思っていました。いまもそうです。
珠取海女という舞踊があります。日本の伝統芸能は、お能があって地唄舞があって歌舞伎舞踊があるという三段階になっているんだけど、お能がコアで、地唄舞はそれをコンパクトにして、座敷でも見られるようにしたものです。そのさらに一般化が歌舞伎になります。玉三郎さんはお能と地唄舞を研究し尽くしている。珠取海女では海女が海に潜って貴重な真珠を取るんですが、蛸なんかが邪魔をして取らせないようにする。海女は真珠を愛する人に渡したいんだけど、真珠を取ると自分のおっぱいの中に隠す。そしてコンコンと合図して、綱を引っ張って海面に上げてもらう。その時の玉三郎さんの動きは彼の身体が動いているようには見えなかったな。何かの力で上に引っ張られているように見えた。あれは驚いた。
玉三郎さんとは実際にお話したことがあるけど、ものすごく芸について研究しておられる。小道具で手拭いを使う時に、五分くらい絞った手拭いを布団の下に敷いて一晩寝ると、ちょうといい湿り気になって使いやすいとかおっしゃっていました。小道具にまで細心の注意を払っている。それは舞台を見ていてもわかります。また彼のすごいところは、自分のやっていることを言葉で表現できるまで意識的に探求していることです。六代目菊五郎はそこまでやってなかった。玉三郎さんからは、たくさんのことを教えてもらいました。

『身体の零度』(講談社選書メチエ)
講談社 1994年11月/2日
バレエの世界では、ヴラジーミル・マラーホフが玉三郎さんと同じくらい舞踊について考えていた。ジゼルというバレエがありますね。アルブレヒトという青年が登場しますが、彼は都のプレイボーイで、田舎者の女の子をひっかけて泣かせていました。だけど遊ばれただけだとわかった女の子が発狂して死んじゃったものだから、アルブレヒトは後悔して夜中にその子のお墓に行く。そうするとお墓にはゾンビみたいな、だけど綺麗な幽霊がいっぱいいて、彼を取り殺そうとする。ジゼルはアルブレヒトに騙された女の子で、自分も幽霊になりかけているんだけど、この人は助けてあげてって幽霊たちに懇願します。幽霊たち(ウィリ)は男に騙されて死んだ子たちばっかりですから、そんなことできない、絶対殺してやると迫る。騙した男の代表としてアルブレヒトを殺そうとするんですね。ジゼルはアルブレヒトといっしょに踊り始めますが、なぜかというと、踊っている間は殺されないからです。でもアルブレヒトは人間だから、いつまでも踊っていられない。倒れちゃう。それをジゼルが起きなさい、起きなさいと促す。
このシーンで、たいていのダンサーは、よっこらしょという感じで起きるんだけど、マラーホフはスッと胸から起き上がった。目に見えない糸で、スッと持ち上げられたように見た。それはマラーホフ独自に作り上げた型です。マラーホフはあの動きだけのために背中の筋肉を鍛えているんでしょうね。手を使わずに起き上がると、それだけで異常なことが起こったんだと観客に伝わる。玉三郎さんの、目に見えない糸で身体が持ち上げられるような踊りと同じです。二人ともその効果をわかってやっている。こういう動きの積み重ねが、最良の舞踊芸術を生むんです。でも秘伝にしちゃダメなんだな。ダンサーの全盛期は短いといえば短いから、時代時代で最良の舞踊ができるダンサーに学んでいった方がいい。
舞台芸術を含めて視覚の研究はとても大事です。視覚の研究を最初に行ったのはレオナルド・ダ・ヴィンチでしょう。だからダ・ヴィンチからジャコメッティまでの美術の流れは視覚の研究としても捉えられる。人間はどのように人や物を見ているのか、見てきたのかということのプロセスとして美術史を見ることができる。
■アングラ演劇について■
ラモーナ これはぜひお聞きしておきたいのですが、アングラ演劇は日本の演劇にとってなんだったのでしょうか。アングラ演劇は海外では非常に注目されていますが、日本ではそれほどではありません。さきほどアナーキズムの話が出ましたが、アングラ演劇は日本の演劇におけるアナーキズムのようなものだったのでしょうか。
三浦 アングラ演劇で一番重要なことは、演劇の舞台空間に歌と踊りを取り入れたことです。この重要性をみんなちゃんと論じていません。演劇を文学にしちゃったんだな。学者を始めとして、演劇は文学だと思っているでしょう。築地小劇場がそうだった。築地小劇場は左翼的な運動とタイアップしていましたね。そんな文学的演劇に対して、そうじゃない、演劇の最も底の所にあるのは観客を驚ろかすことである、という原点を示したのがアングラ演劇です。
お能のピーッという笛の音が観客をあの世に誘うように、アングラ演劇は観客を非日常的な違う空間に連れ込んでゆきます。連れ込んで観客を覚醒させる。ビックリして世界を違った目で見ると言ってもいい。覚醒のきっかけを与えるのが演劇の根本的な役割なんです。これは舞踊でも美術、演劇、文学でも本当はいっしょです。異空間を体験すれば、今自分がここにいるということに人間は疑いを抱きます。それが重要なんだな。でも二十世紀の演劇は戯曲をスタティックな文学にしちゃった。これはヨーロッパもそうだと思います。ヨーロッパの方がよけいそうかもしれない。文字で書かれた戯曲至上主義だね。だけど演劇にとっては戯曲は部分に過ぎない。消え去ってしまう歌と踊りが前面に出て、重要な役割を果たすということを復活させたのがアングラ演劇です。
もう一つ重要なのは、観客を驚ろかせることで、人間存在に垂直に迫ってゆかなければならないということです。そのためにアングラ演劇は、人間の身体がそれ自体で〝ある次元〟を持って存在しているということを強烈に主張した。歌と踊りが垂直的な人間存在を意識させる重要な要素となったと言ってもいい。それがわかると言語もまた身体性を持っているとわかる。言葉は伝えた瞬間に消えてしまうものですが、「冷たくなったね」「暖かくなったね」という言葉自体がある肉体性を持っていて、「暖かい」という言葉は「暖かい」んだと感受するようになる。微妙だけどこの次元は日常言語とは違う。こういう日常とは違う演劇空間をアングラ演劇は提示した。

アングラ演劇、暗黒舞踏など、アンダーグラウンドの日本の演劇が脚光を浴びたのは、寺山修司の天井桟敷からです。寺山はうさんくさいから学問領域から閉め出してしまおうという動きが一般的なんだけど、とんでもない。寺山は一九六九年にヨーロッパで公演しました。アムステルダムを中心に上演した。アムステルダムのインテリたちは熱狂しましたね。それは寺山が公演する十年前に、モーリス・ベジャールがブリュッセルで『春の祭典』を上演していることとも関係がある。ベジャールの『春の祭典』は、二十世紀舞踊史にとって決定的です。それまでの優れたバレエは演技だった。ダンサーが、どこまでジゼルやアルブレヒトになって演技しているのかが評価されていた。でもベジャールは、ダンサーの肉体そのものを活かした。ベジャールは、『春の祭典』でセックスをそのまま舞台に乗っけちゃったでしょう。もちろん卑猥なものじゃありません。非常に洗練されている。だからこそ根源的にエロチックでもあった。人間の身体の持っている美しさを、セックスというシンボリックな行為で表現したわけです。人間の身体のレベルは、性のレベルと密接に関わっていることを明らかにしたんですね。その後に寺山がヨーロッパに行って上演した。
寺山はベジャールの延長上にありながらベジャールとは逆に、人間の身体が持っている俗っぽさ、生々しさを表現したわけです。この六九年の天井桟敷の公演はヨーロッパでは非常に評判になったけど、日本の文化界、演劇界はぜんぜん反応しなかった。寺山演劇は日本では危険視されてあんなの見世物にすぎない、ニセモノだよと言われていたからね。でもこの後、大野一雄や山海塾がヨーロッパに行って公演を成功させたわけでしょう。ベジャールから寺山演劇へという衝撃が残っていたから、彼らはヨーロッパで受け入れられたんです。ヨーロッパでは、ベジャールから始まった身体の革新運動の中に寺山が位置づけられたんだね。それは人間の身体自体の現出が決定的に新しいんだということを、ヨーロッパの観客が理解した瞬間でもあります。この流れにピタッと乗っかったのがピナ・バウシュです。
日本のアングラ演劇で言うと、寺山のやった身体の現出を、もっと身近な物語として演劇化したのが唐十郎です。唐さんは幼年時代の記憶を戯曲のメインにしました。『下谷万年町物語』なんかで、風呂屋の脇の電信柱の影に身を潜めて大人たちの行動をひっそりと覗き見している少年の姿なんかを描いた。彼はそれまでの戯曲の素材を変えました。寺山の後に、そういうことがものすごくやりやすくなったとも言える。唐の幼年時代の記憶を、高校時代のそれに当てはめたのが野田秀樹でしょうね。彼らは演劇の素材はどこにでも潜んでいることを発見して観客に伝えたんです。ただ寺山が田舎の何気ない出来事を演劇の素材として取り上げたのがすべての始まりでしょうね。ベジャールの舞踊に影響を受け、引き継いだ日本の演劇人は鈴木忠志だと思いますが、彼はヨーロッパよりアメリカで受け入れられた。アメリカではインドネシアのガムランとかがすでに受け入れられていて、鈴木さんの演劇は親しみやすかったからね。
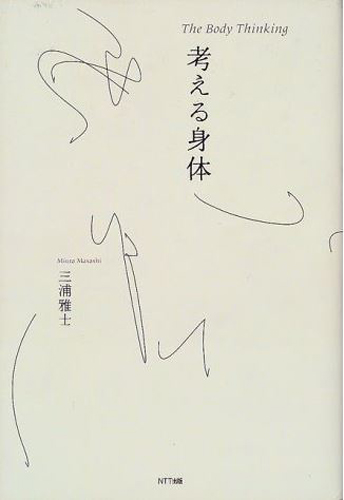
『考える身体』
NTT出版 1999年12月1日
重要なのはベジャールと寺山とピナ・バウシュが登場して、ヨーロッパの舞踊と演劇に決定的な影響を与えたという流れです。それはオランダのアムステルダムとベルギーのブリュッセル、それにドイツのヴッパタール中心に起こった。ヴッパタールにピナ・バウシュのダンス劇団があったからね。またベジャール、寺山、ピナ・バウシュに共通しているのは、幼児体験を創作の源にしているということです。突き詰めると、お母さんとの初源的な幼児体験が創作の基盤になっている。それは断片的だからストーリーにはならない。だけど身体を垂直的に現前させる力です。エピソードは断片的だけど、それを繋ぐ際に群舞や歌を差し挟んで活用してゆく。エピソードを繋ぐ鎖を作ってゆくんだな。
特にピナ・バウシュはそうで、エピソードの繋がりは第一覚醒、第二覚醒といったもので、じょじょに観客の心を揺り動かし底の方を掘り起こしてゆくわけだけど、ピナの群舞は優しさと悲しさを同時に感じさせる踊りです。バックで流す音楽に、戦前の歌謡曲とかジプシー歌謡とかを使ったりしてね。同じようなことをベジャールもやっているけど、最初はクラシック音楽を使っていました。最後はクイーンとかのロック音楽も使ったけど、クイーンの中でもお母さーんと叫んでいるような曲を使った。ベジャールのくるみ割り人形は自分と母親との関係だけを描いた作品です。その中にキリスト教の聖母像を織り込んでゆく。その背後に古代的なものを見たんだね。劇場に入ったときと出てゆくときでは、観客が変わっていなければならない。彼らの舞台はそういった観客の覚醒を促すために根源的な力を活用しています。
こういった二十世紀の前衛舞踊、あるいはアングラ演劇の意味は、日本ではほとんど論じられていないですね。なぜかというと、日本国内で閉じちゃってるから。ヨーロッパも含めて日本のアングラ演劇が世界的な影響力を持つ芸術だったと再定義すれば、今の舞台芸術の流れは変わるかもしれない。僕がこうやってしゃべったことで、変化が起こるといいんだけど(笑)。
ラモーナ 日本に来て、アングラ演劇はすごいんだと言ったりしたんですが、周りの人は、なんでそんなに騒いでいるの? という感じなんです(笑)。

三浦 安保闘争の一九七〇年くらいまでは、東大や早稲田のインテリたちも、アングラ演劇のすごさ、素晴らしさに気づいていました。だけど大学の先生に収まっちゃうと、教条主義的になってアングラをオミットしちゃったところがある(笑)。
寺山が先鞭をつけて、大野一雄や山海塾が活躍した時代までは、日本の演劇や舞踏の軸足がヨーロッパにあった。今もあるつもりかもしれないけど、そういう時代は終わりつつあります。ただそういうインターナショナルな感覚を忘れてしまっているのが、今の日本の舞台芸術の大きな問題点ですね。日本で上演して国内で有名になることばかりに興味がいっている。複眼で世界規模で舞台芸術を捉えなきゃダメです。インターナショナルな視点で見れば、まったく違う光景が見えてきます。
ベジャール、寺山、ピナ・バウシュが二十世紀の舞台芸術で、世界的に見て最も重要な流れだと言ったのは僕だけなんです。だからこれも怪しいかもしれない(笑)。日本人はもちろんヨーロッパ人もそんなことは言ってない。誰もそう考えてくれない。だけどこの認識に従って日本やヨーロッパの新聞雑誌の記事を並べて見るだけで、違う光景が見えてくるはずなんです。やらなきゃならないことがいっぱいあるんだけど、僕はもう七十二歳だからさ。ラモーナさんたちが頑張って、そういう二十世紀舞台芸術の本当に大事なポイントを明らかにしてください(笑)。
ラモーナ いまおっしゃったことは、もうどこかで書いておられるんですか?
三浦 まだ書いてません。どっかで書いた方がいいね。だけど僕からアイデアをもらって書いてもいいんだよ。僕がしゃべったことで、本当にそうだなぁと思ったら、自分の考えとしてそれを展開させて書いていい。そこに所有権はないと僕は思ってます。初めの方で話した知的所有権と同じですね。知は権利として囲い込んじゃダメなんだ。僕の考えに立脚して、それを敷衍して新しい考えを獲得していけばいいんです。僕の考えなんて小さなものだけど、それをきっかけにして新しい見方が出てきたら素晴らしい。

『青春の終焉』
講談社 2001年9月27日
金魚屋 お許しが出たので、このインタビューにインスパイアされた方は、どんどん新しい演劇論、舞台論を書いてください(笑)。ただ一方で、まともな物書きさんなら、出典は忘れずに明記していただきたい。これは「©三浦雅士」だと(笑)。文学金魚はネット文芸誌ですから、ネット時代の知は開かれてあるべきだという考えに共感しますが、他者の認識をそのまま自分のものにしてしまうのはやはり剽窃です。これからも知を囲い込みたがる人は絶えないでしょうが、出典を明記した上で自己の考え方を展開すれば問題は起こりにくくなります。一定の倫理規定は必要ですね。今日は長時間ありがとうございました。(了)
(2018/12/21)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋の本 ■











