Interview:馬場あき子インタビュー(2/2)

馬場あき子:昭和3年(1928年)東京都生まれ。日本女子高等学院(現・昭和女子大学)卒。少女時代から短歌に興味を持ち、歌誌「まひる野」に参加して窪田章一郞に師事。昭和五十二年(一九七七年)歌誌「かりん」を創刊し主宰をつとめる。昭和三十年(一九五五年)に処女歌集『早笛』を刊行以来、平成二十五年(2013年)刊の『あかゑあをゑ』に至るまで二十四冊の歌集を刊行。『式子内親王』、『鬼の研究』、『修羅と艶 能の深層美』など日本の古典文学や能に関する著作も多い。第十三歌集『阿古父』で第四十五回読売文学賞、第十五歌集『飛種』で第八回斎藤茂吉短歌文学賞、第十九歌集『世紀』で第二十五回現代短歌大賞受賞など受賞多数。
馬場あき子氏の基盤には日本の古典文学――特に少女期から習っていた能がある。能論については『修羅と艶』、『花と余情』、『風姿花伝』などの著作があり、古典文学論には『式子内親王』、『和泉式部』、『世捨て奇譚』などの著作がある。また民俗学を取り入れた『鬼の研究』でも名高い。今回は古典文学を能楽などを通して生きた芸術として捉えることができる馬場氏に、日本文化の底流を為す知や感性について語っていただいた。なおインタビューには文学金魚で演劇批評を連載中のラモーナ・ツァラヌ氏に加わっていただいた。
文学金魚編集部
■日本文化と能について■
ラモーナ 日本の舞台芸術には様々な様式、形式がありますが、その中で能はどのような位置にあるとお考えですか。
馬場 現代劇と比較しても能は前衛的だと思います。だって虚心坦懐に聞けば、謡だって犬の鳴き声だか鹿の鳴き声だかわかんないような発声でしょう。かけ声だって「イヤーッ」とか大声を出すわけですが、吠えているような声です。能はかなり野獣的ですよ。フォービズムですね(笑)。
金魚屋 能は本当に芸だと思います。あまり見ていないんですが、若手が登場した後に、いわゆる真打ちが登場する舞台がありますよね。そうするとミュージシャンたちも全員入れ替わる。真打ちになると、鼓を持った能面のような顔をしたおじいさんが舞台に現れて、試しに鼓をポンと打つ。素人ながら、さっきとぜんぜん違う音じゃないかと思いますもの(笑)。
馬場 鼓なら鼓で、打たせてみると名人は音が違うんです。もうお亡くなりになりましたが、第二十二代金春惣右衛門という太鼓方がいらっしゃいました。あの人が太鼓を打つと、同じ楽器でこんな音がするのかと驚きましたもの。やっぱり能は変な芸能ですよ(笑)。
金魚屋 日本人に生まれて、日本人になって行く人とそうではない人がいます。それは人それぞれの選択ですから、自分はアメリカ人だと思って死んでもいいんですが、日本人になろうとすると、どうしてもどこかの時点で能が目に入ってくる。ただどうも能はよくわからない。成仏したってことになってるけど、とてもそうは思えない。何度見ても腑に落ちない棘みたいなところがあります。
馬場 棘だっていうのはいいですね。なかなか抜けないんですよ。小林秀雄が『当麻』というエセーを書いています。ネコがほっかむりしたようなシテが出てきて何か言っているけど、よくわかんない、わかんないまま劇場の外に出てきて星空を見て、忘れがたいと思ったという内容です(笑)。
金魚屋 永遠に繰り返されているフィルムを見ているようなんですが、飽きないんです。
馬場 だからそれが短歌と俳句の様式なのよ。お能はもちろんだけど、短歌も俳句もあの様式によって過去と未来につながっているんです。そういう意味では現代詩はフォルムを自分で作らなきゃならないから、なかなか辛いわね。でも谷川俊太郎さんの『わらべうた』なんかはすごいです。すごい感性よね。『わらべうた』を読んだ時はどきどきするほど驚いちゃってね。

金魚屋 自由詩はなんでもありで、短歌は形式はありますがけっこう緩いですね。でも俳句はものすごく形式にうるさい。高柳重信の前衛俳句運動が終わると、今度は重信の多行俳句形式を新たな型として継承しようとする作家たちが現れてくる。有季定型でも無季無韻でも多行形式でも、ある型を継承しているという点では同じですね。
馬場 だから困るのよ。誰々の固有の型は継承しちゃいけないの。塚本邦雄の「玲瓏」なんかもそうですが、そこで型を継承したら滅びちゃう。誰も相手にしなくなります。
金魚屋 「かりん」では型の継承ということはおっしゃらないんですか。
馬場 一切言いません。わたし自身がはみ出していますから。年中字余りの歌を作って若い者から文句を言われています(笑)。
■馬場氏の初期短歌について■
金魚屋 馬場さんの短歌はかなり変遷してますね。
馬場 最初は素人みたいな歌から始めましたからね。どんな生活してどんな物を食べてるかまでわかっちゃう(笑)。
金魚屋 誰に恋してるかもわかります(笑)。馬場さんの初期短歌は魅力があります。初期は過ぎていますが、「ほのぐらき胸腔ともるまで呼べばわれらの戦後も雨降る動画」などはなんとも言えない余韻があります。
馬場 えーっ。忘れていました。わたしは自分の初期短歌を読むと、涙がにじむことがあります。学校の先生をしていた時代でしょう。歌で詠んだ生徒たちの顔が出てきちゃうのよ。その連中がもう七十七歳で、もう最後のクラス会だからってこの間呼ばれて行ったんです。そしたらよぼよぼのおじいさんになっててね(笑)。「なにやってんだ」って怒りましたよ。あの頃はみんなバカ呼ばわりで、男言葉を使わなければクラスを統一できなかったんです。
金魚屋 一九四〇年代から六〇年代にかけては、ずいぶん政治的運動にも関わられましたね。
馬場 それはみんなそうでしたよ。戦争が終わって、東大の山上会議所あたりで年中講演会や政治集会をやっていて、誰でも聞きに行けるからしょっちゅう行ってたんです。それでちょっとばかり政治思想に染まって、エンゲルスの『空想より科学へ』なんかを読んだりしていました。あの頃はそういうのを読んでいなかったら、男の子とつきあえなかったんです。タバコを吸って足が組めて――あの頃までの女性は足を組むっていう習慣がなかったんです――ちょっとばかり酒が飲めて、『空想より科学へ』を語れないと男の子と友達になれなかった(笑)。そういう政治集会で、大学ごとに自治会を作れって言われて、わたしの通っていた大学でも作りました。それで自治会代表で集会に行くと、男の子たちがずらっと並んでいてドキドキしたっていう時代があったんです(笑)。
金魚屋 馬場さんはドンピシャの戦中世代ですね。
馬場 わたしは今で言う、中学校の四年生までしか勉強してないんです。その後は学徒動員令が下されて、女子学生も身の回りの物を何種類か持って「中島飛行機」の女子寮に入れられたんです。そこでわたしは旋盤を回していました。日本の古典文学は好きだったので、それまでに『平家物語』くらいまでは読んでいました。でも女子寮にいた友達で長唄とかが上手な子がいましてね。この子は十三、四歳で名取でした。昼休みなんかに、その子の口三味線で『藤娘』、『娘道成寺』、『越後獅子』などを四、五曲習いました。それは今も断片的に覚えています。これは戦後になってからですが、ロシアなどの影響で各国の民族音楽を見直そうというブームがあったでしょう。その時にわたしが勤めていた区立中学の音楽の先生が、ピアノで『越後獅子』を弾いて生徒に教えていたんです。その時の感動ったらなかったですね。自分が口三味線で習った『越後獅子』を、今、中学の生徒たちがピアノの伴奏で歌っている。これは素晴らしいと思いました。
■写実について■
金魚屋 馬場さんの初期短歌には生活の色が濃いですが、それは当時は一般的だったんでしょうか。
馬場 当たり前でした。「アララギ」全盛時代ですからね。わたしが師事した窪田空穂は「アララギ」じゃなくて人間探求派ですが、当時は〝写実〟が日本全土を覆っていたんです。歌人たちも戦地に派遣された時代です。歌人は戦地に行って、それを写実で詠んでこなければならなかった。歌人に限らず絵描きも詩人も全部写実で報告する時代でした。写実以外になかった時代に歌を始めているので写実になったんです。それに当時は軍国主義全盛期ですから、『万葉集』の「撃ちてし止まむ」とか防人の歌とか、そういうのばかり習った。またその前にわたしは、お母さんがいなかったから女系家族のおばさんたちに育てられたんですが、小学校六年生の頃には『百人一首』をほとんど丸暗記していました。『万葉集』と『新古今集』と、当時の写実短歌がごちゃまぜに身体の中のリズムに入っていた。その上女学校の四年生の時からほとんど授業がない。なにをしたらいいんだろうって考えた時に、ノートに歌を書く以外なかった。そうやっていくつも歌ができあがりました。
金魚屋 昭和四十四年(一九六九年)の『式子内親王』から古典文学関係の評論を量産されるわけですが、あれは当時の馬場さんの短歌を読んでいた人たちにとっては驚きだったんじゃないですか。
馬場 『式子内親王』や『鬼の研究』は、微妙に六〇年安保の影響を受けています。六十年の十二月に岸上が自殺したんですが、わたしはちょうど、職場の組合の婦人部長だったんです。毎日動員がかかって、学校を留守にして国会前に行っていました。樺美智子さんが亡くなった時も国会前にいました。婦人部長だったから動員で行っていたに過ぎないんですが、それもまあ運命ですね。当時は公立校に十年勤めたら、どこかに転任しなければならない規則がありましてね。転職しようと思った時に、わが身の上を初めて知ったんです。どこの学校に面接に行って採ってくれない。それまで中学の先生だったんですが、これはダメだから試験を受けて高校の先生になろうと思ったんです。それでも面接でオッケーを出してくれた校長が、翌日必ず「採れないことになりました」っていう電話をかけてくる。なぜだろうと思っていたら、ある人が「お前の履歴書には赤が付いている」と教えてくれたんです。つまり履歴書の欄外に「婦人活動家」っていう朱書が付いちゃっていたんです。だからどこも採ってくれない。それでわたしのハートに火が付いて、よし、ぜったいに高校の先生になってやると思って努力しました。
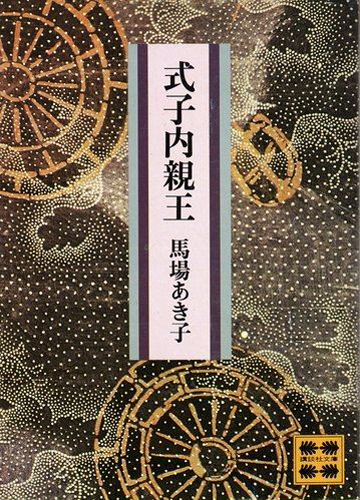
馬場あき子著『式子内親王』(講談社文庫版)
初版は昭和四十四年(一九六九年)刊
金魚屋 それは何年頃の話しですか。
馬場 昭和三十七年(一九六二年)です。六〇年安保が三十五年でしょう。三十九年(六四年)がオリンピックですから、オリンピック前まではそういう統制が厳しかったです。
金魚屋 馬場さんは六〇年代安保世代で、人によって様々な考え方はありますが、六〇年代安保も七〇年代安保も大局的に言えば挫折で終わったと思います。でも六〇年代安保を戦った世代は、七〇年代安保世代に比べてなにか前向きですね。あんまり挫折したという感じがしません。
馬場 六〇年安保の挫折感が『鬼の研究』になったというところはあります。でもそうね、六〇年代安保世代は挫折しても立ち直っている人が多い。
金魚屋 馬場さんの短歌はずいぶん変遷していますが、さきほどおっしゃった写実は初期からあまり変わっていないんじゃないでしょうか。

馬場 純粋抽象はやはり力にならない。ある具体がなければならないです。また優れた芸術は大衆性も持っていなければならない。世阿弥の言葉に「上花に上りても山を崩し、中上に上りても山を崩し、又、下三位に下り、塵にも交はりし」とありますが、上から下まで備えていなければ本当の芸術だとは言えません。藤原定家などは達磨歌と揶揄されたけど、やがてすべての人が彼の歌を知るようになった。最初は達磨歌と言われても、その面白さをみんなに広めて愛唱されるようにしてゆかなければならないんです。
それがある程度できているのは現代では塚本邦雄ですよ。時代を象徴する作品を、ある具象をもって作っていった。塚本は古典を取り入れた時期があって、「春の夜の夢ばかりなる枕頭にあっあかねさす召集令状」という歌があります。これは今の時代にぴったりの歌です。これも塚本ですが「突風に生卵割れ、かつてかく撃ちぬかれたる兵士の眼」という歌がある。生卵が割れたのと銃弾で兵士の眼が打ち抜かれた光景を重ねているわけですが、こういった具体的イメージは古びない。そういった生きている具象、映像力が歌には必要ですね。
■教師時代について■
金魚屋 馬場さんが就職で苦労して努力されたということと『鬼の研究』の執筆は、肉体感覚でつながっているようですね。
馬場 あの時は恨みなんです。わたしを入れなかったもの、肯定しなかったものに対して仕返ししなければならない気持ちがあった(笑)。『式子内親王』にもそれがある。あの時はずいぶん調べました。以仁王の姫宮を八条院暲子内親王が猶子として、その当時の最高の財産を相続したということは、わたしはものすごく嬉しかった。あれは八条女院の情念なんです。以仁王をそんなふうに扱うなら、わたしが持っている天皇家を越える財産を、みんなこの姫宮に付託するぞってことですね。そういうのを読むと嬉しくなります。
金魚屋 漠然と馬場さんはどこかの大学で研究しておられたんだろうと思っていたんですが、年譜を読むと中学高校の先生をなさりながら歌を詠み批評を書いておられた。それは驚異です。相当忙しかったでしょう。短歌はともかく、馬場さんの古典関係の著作は時間がなければ書けないと思うんですが。
馬場 昔の教師は時間的にはすごくいい仕事だったんですよ。わたしがなぜ定時制高校に行ったかというと、勉強できるからなんです。でもあの頃はものすごいハードスケジュールだったわね。身体が強かったので、朝八時に起きて団地の若い奥様たちに仕舞と謡を教えていました。十時から『源氏物語』を読む会を持っていて、午後一時からは自分の稽古に行っていました。学校が始まるのが五時で四時半までに行けばよかったんです。それで九時に授業が終わって、家に帰って一杯飲んで寝ちゃうという生活でした(笑)。
金魚屋 古典関係の本はいつ読んでいたんですか。
馬場 電車の中よ。遠距離通勤してたから。
金魚屋 読んだ内容を覚えていたんですか。
馬場 あの頃の頭はよかったわね(笑)。いっぺん読んだら忘れませんでした。好きなところだということがあるんでしょうが、頭の中に引き出しがいっぱいありました。引き出しを開ければ何が出てくるかがわかっていたわけ。あれは『今昔物語』だぞ、あれは『古今著聞集』、あれは『徒然草』という具合に頭の中に入っていました。今はなんにも出てきませんけどね(笑)。右大臣九条兼実の日記『玉葉』なんかは漢字ばっかりの分厚い本なんだけど、それを神田の古本屋で買って、電車の中で読んでいましたからね。付箋なんてないから、ちり紙をちぎって挟んでね(笑)。それを翌日ノートにまとめるという日々でした。でもそうじゃない日はぽかっと空いているのよ。だから一週間あれば三、四十枚は書けちゃったです。
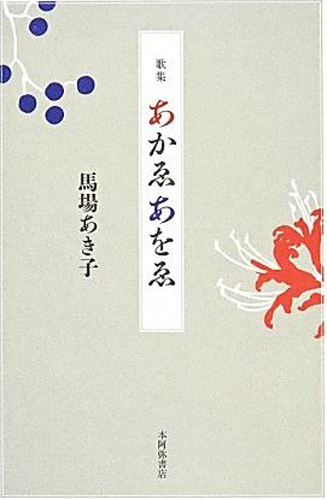
馬場あき子第二十四歌集(最新歌集)『あかゑあをゑ』
かりん叢書 本阿弥書店 平成二十五年(二〇一三年)刊
金魚屋 それはすごいな。『式子内親王』は学者の著作です。書くためにずっと準備しておられたんですか。
馬場 なにもしてないです。『式子内親王』は基礎資料だけで書いたんだけど、楽しかったですよ。わたしは大学の卒論が、『新古今集』の中の宜秋門院丹後だったんです。『新古今集』では丹後の側に式子内親王があるから、資料をいっしょに集めていた。卒論を二十年も寝かせていたんだけど、その内容や集めた資料が『式子内親王』を書く時に役に立ちました。資料を集めるのも写実ですからね。資料というか現実がなければ書けません。そこに空想と自分の情念が投入されるんです。
■口語短歌について■
金魚屋 そういう意味では口語短歌は数を書けないんじゃないですか。
馬場 いや、あれは易しいです。今、歌をたくさんつくろうと思ったら、口語が入った方が書きやすいですね。だって日頃しゃべっている口語で書くわけでしょう。象徴的な歌を作っているわけじゃないから。
金魚屋 穂村弘さんの短歌は比較的読んでいるんですが、彼は口語短歌の作家の中でやっぱりうまいですね。口語短歌は一首で完結していなくて流れる感じの作品が多いですが、穂村さんは一首で完結している。
馬場 いい歌はそうです。また穂村さんは口語短歌だけど、出発点が空想的な非現実ですからね。「サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい」とかね。でも彼は歌いたいことがあって歌っている。夜中に広島の爆心地でシャボンを使っているといった作品があるでしょう。どうやったら一番怖さが伝わるかを考えているんです。彼は恐がりなのよ。感覚的にも皮膚的にもね。そういった人間の一番弱い感覚で歌を作れるのね。
金魚屋 馬場さんは穂村さんと仲良しですね(笑)。
馬場 頭がいいしね。好きな歌人の一人よ。彼に質問されるのが、わたしは一番いいんです。「馬場あき子自伝」のインタビューでも要所をおさえてくれるの。こう言えば、この人はこう言うだろうってわかってる。碁石の棋譜みたいなものね。
金魚屋 さすがに口語短歌を代表するだけのことはあります。ただ口語短歌の人たちが、このまま突き進んで行くのかどうかはとても興味があります。
馬場 わたしは穂村さんに、一千首くらい選んでアンソロジーを出しなさいって言ってるんだけど、まだ出ないわね。ちょっと前に聞いた話しでは、四千首くらいまでワープロで打ったってことだったけど、それを千首に絞るのは大変ね。でも穂村さんは、彼のいい歌をセレクトして出した方が、絶対に特になると思いますよ。
金魚屋 いいことだと思います。ただ物書きは本を出したら出したで、出した本に囚われるというか復讐されるでしょう。今は口語短歌全盛時代と言っていいでしょうが、短歌界がこのまま進んで行くとは到底思えないんですが。
馬場 穂村さんたちの世代はこのまま行くんじゃないですか。
金魚屋 穂村さんは俵万智さん以降の世代として、口語短歌で突っ走るかもしれません。でも必ず世代交代が起こります。ここ二十年くらいで変わった状況が、今後二十年続くとはちょっと思えない。

馬場 穂村さんのところであの世代は終わりかもしれませんね。その後の世代が出てきていますが、それは十年続いたらいい方ですよ。あんな歌で続くとは思えない。まず読者がつかない。わたしは去年、歌は上手いかもしれないし感覚もいいかもしれないけど、もっと人間を差し出しなさいって言ったんです。そしたら「人間を差し出す」っていう言葉に対していっぱい批判が来ちゃったの。今度、ある雑誌の新年号で、「人間を差し出す」ってことをテーマにして、若い人たちと討論しなくちゃならないんですよ。秘策を練っているところなんです(笑)。
金魚屋 文学の世界では、初めて何かをやった人は残ります。馬場さんの世代がそうです。古典から前衛に至るレンジの現代短歌を作りましたし、俵万智さんや穂村さんの世代は口語短歌を作った。でもそれをなぞると堕落すると思います。短歌、俳句の世界はまだまだ元気ですが、自由詩の世界は戦後詩と現代詩、それに昔ながらの抒情詩をなぞって見る影もなく衰退してしまった。わたしたちは一九八〇年代に学生時代を送ったんですが、当時は現代詩の全盛期でした。でも今はほとんど現代詩は読まれていないと思います。
馬場 そうねぇ、衰退してますねぇ。昭和三十年代の現代詩は、誰もよくわからないのに崇めていましたよ(笑)。
金魚屋 だけど現代詩のウリだった前衛性がなくなってしまったわけですから(笑)。
馬場 わたしは何回か詩の賞の選考委員をやったことがあるんです。その時も混乱して評価できなかったです。ものすごく困っちゃいましたね。ある文学賞で辻井喬さんとご一緒したんですが、辻井さんが「ほんとうにこれでいいんだろうか。馬場さん、どう思う」っておっしゃるのよ(笑)。蜂飼耳さんくらいまではわかりましたけど、あとはもうわかんないなぁ(笑)。
金魚屋 こういう状況になると、やっぱり形式がある短歌、俳句は強いですね。
馬場 短歌俳句の形式を大衆が利用している限り、あのジャンルは生きていくわけよね。
■短歌創作について■
金魚屋 日本人の定義は簡単に俳句が詠めることかもしれません(笑)。へたくそな句なら誰でも詠めてしまう。短歌俳句は日本語と日本人の生理にぴったりくっついている芸術ですから。
馬場 日本人は簡単に短歌俳句が詠めると言うと、外国に行った時にものすごく不思議がられることがありますね。日本人って型が好きなのよ。能にしろ歌舞伎、日本舞踊にしろ、型ができあがっています。外国ではある型は時代が生んだものだから、時代が変わると古い型は消えちゃって違う型が現れてくる。でも日本人は型を踏襲するんですね。外国では歌舞伎と能と、どっちが人気があるんですか。
ラモーナ 観劇は別ですけど、能の様式に憧れて能を習う人が多いです。
馬場 能は短歌俳句と同じなんだ。歌舞伎を習う人はいないもんね。
金魚屋 歌舞伎の方が新作は作りやすいかもしれませんが、勧善懲悪や人情といったストーリーも含めてがんじがらめの形式で、素人が真似ても面白くないかもしれません。能は完成されているようで未完成でしょう。
馬場 お茶と同じなのよ。お茶は完成を嫌うでしょう。わざとどっかに隙を作っておくのがお茶です。そういった未完成が面白いのよ。未完成こそ完成だっていうようなことを、岡倉天心が言ってるものね。天心の『茶の本』は絶品に面白い。ときどき読み返しますよ。

馬場あき子著『能・よみがえる情念-能を読む-』
ひのき能楽ライブラリー 檜書店 平成二十二年(二〇一〇年)刊
金魚屋 岡倉天心は化け物っぽい人ですねぇ。
馬場 近代にはそういう人がいたのよ。戦後にはいなくなっちゃった。だから民主主義ってなんだろうって思うことがあります。平等でみんなそこそこ豊かにはなったけど、天心のような化け物的な力を持った、人を心服させるような人は出なくなっちゃいましたね。
金魚屋 能と同じで短歌も完成しないような感じがします。短歌は俳句よりも明らかにゆるい形式です。短歌はみなさんすーっとお詠みになるでしょう。これ本当に短歌なのと思って指を折って数えてみるんですが、ちゃんと五七五七七になっている(笑)。もちろん作っておられる方は、指折って言葉を数えたりしないでしょうけど。
馬場 数えないです(笑)。確かに短歌を作るときには、降ってくるような感覚があります。でもいつ降ってくるかわかんない。もちろんそうじゃない作り方をする人もいますよ。写実というより写生派の歌人たちは、短歌を作ろうと思ったら松の前に立って、松の歌を詠めてしまうことがあるかもしれない。だけどわれわれは、やっぱり降ってこないとダメなんです。どうやったら降ってくるのかというと、ちっとも歌ができない時は、駄作をいくつも並べていくうちに、ふっといい作品ができることがある。十五、六首くらいまでは出ますね。でもそのくらいの数で止まっちゃうわね(笑)。
金魚屋 それはよくわかります。僭越ですが、馬場さんの歌集を読んでいてもある瞬間からぱっと良くなることがあります。均等に良い歌がならんでいるわけではない。でもいい歌を詠むためには前段が必要なんですね。
馬場 助走部分がたくさんないと飛躍できない。
金魚屋 馬場さんはだいたい二年に一度のペースで歌集を出しておられますね。
馬場 そうです。また来年出すんです。それでもう最後の歌集じゃないかと思うんですけどね。
金魚屋 それはないというかあり得ないと思いますよ(笑)。
馬場 今の時期はくたびれちゃってね。もうすぐお正月だから歌の注文が来るでしょうけど、歌ができなくて困ってるところなんですよ(笑)。
金魚屋 だいたい歌集一冊で五百首くらいでしょうか。
馬場 四百二、三十首で一冊です。そう言えば文学金魚を見たら、インタビューでいろんな図版を掲載しているので昔の雑誌を持ってきました。「律」という短歌誌の第三号で、昭和三十八年(一九六三年)の発行です。塚本邦雄がシェイクスピアの『ハムレット』を構成・演出していてそれが収録されています。わたしたちはこの戯曲を上演するために集められたんです。この頃わたしは初めて塚本さんに認められました。塚本版『ハムレット』は芝居にしないで声優だけで読んで上演したこともあります。わたしの短歌も掲載されていますがこの時は謡曲調を入れてみたんです。わたしは前衛短歌グループには、すごく遅く登場したんですよ。「律」に書いている前衛短歌の人たちとはよく遊んでいたんだけど、歌がやっぱりダメだったんです。写実的な歌は前衛時代には認められなかった。だからそこから脱皮するための苦悩がありましたね。写実的な歌で、前衛とどう対峙してゆくのかをわたしなりに考えました。わたしは『式子内親王』や『鬼の研究』を書くことによって古典と出会ったんです。それでよし、歌に古典を取り入れようと思った。だから前衛に対して古典をぶつけていったんです。それで前衛短歌の人たちにも認められるようになった。

歌誌『短歌と歌論 律』No.3 ’63秋
「律」第三号 発行人・深作光貞 編集人・中井英夫
昭和三十八年(一九六三年)九月十日印刷発行
金魚屋 『鬼の研究』は相当力が入っていますね。文章の圧が高いです。
馬場 そりゃそうですよ(笑)。あの疎外の時期に一矢報いたかったのですから。あの時は手が間に合わないくらい早書きしていました。書きたいことが多くて手が震えるんです。原稿用紙の一マスの中に、二字入れちゃうような書き方でしたね。その後の『発心往生論』なんかを書くときは、もっとゆったりした書き方になっていますけどね。
金魚屋 『鬼の研究』や『発心往生論』は古典文学論で、能楽論はまた別にお書きになっていますが、初期の古典文学論を読んで能のこともよく理解できました。
馬場 わたしの原点には能があったんです。劇としての能はもちろんですが、わたしは文学としての能を非常に大きな課題にしていました。『修羅と艶』という本を書いて、あれは今の時代に合わないから再版できないんだけど、それは文学として、あるいは芸術としての能を追及した一冊です。さっき言った三番目能とか、なぜ修羅能なのかを考えた本です。
金魚屋 ダンテの『神曲』でも「地獄篇」と「煉獄篇」の方が、「天国篇」より面白いですからね。馬場さんは『世捨て奇譚』などで、悟っている人なんていないんだ、浄土なんてないんだという意味のことを書いておられますが、少なくとも文学のテーマはそこにあるかもしれない。浄土は平穏無事で変化がなくて、芸術的には死の世界かもしれません(笑)。
馬場 いろいろな仏教説話をよんでゆくと、悟っていると思われている人が死ぬときに心乱れる哀れさというものはありますね。
■日本文化の本質について■
金魚屋 銕之丞さんもおっしゃっていましたが、能自体がそういった、往生しているようなしてないような作りになっているでしょう。
馬場 幕がないから往生しないと終われないわけですが、そうでなければ『道成寺』みたいに鐘の中に飛び込み、あとは日高川に走っていって飛び込む。本三番目の『半蔀』なんかは成仏してないわね。夕顔の霊が現れて、僧侶に光源氏との恋の物語を語るだけ語って、朝になったら帰っていくだけですから。溶明するか溶暗するかどっちかです。『半蔀』は、朝が来て亡霊が明るい光の中に消えてゆく。『鵺』みたいな能は、亡霊が暗い中に消えてゆくわけです。それ以外は成仏するしかない。でも本当に成仏した霊がまた出てくるのはおかしいでしょう(笑)。だからなるべく成仏しない方がいいのよ。本当の妖怪物は成仏していないからまた出られるんです。「闇に紛れて失せにけり」ですからね。また出られるような終わり方をしている曲が妖怪物には多いです。能の曲で成仏してるのは半分くらいじゃないかしら。
金魚屋 成仏は他者指向ということでしょうか。他者(観客や読者)が成仏したと思うから成仏や浄土は存在すると。『源氏物語』で六条御息所が生き霊となって夕顔を取り殺したのかそうじゃないのかが昔から議論されていますが、みんなが六条御息所の仕業だと思っているから、本人もそんな気がしてきたというふうに読めないこともありません。成仏とか浄土も、他者かがそれはあると思っているから存在しているということじゃないでしょうか。
馬場 『葵上』では変な成仏のし方だけど、六条御息所は一応成仏したことになっている。でも『野宮』では六条御息所は成仏していないです。鳥居を出たり入ったりして「火宅」と言って終わっちゃうんですから。最後は火宅に戻っていくんです。

金魚屋 銕之丞さんは『定家』で式子内親王は、定家の霊が乗り移った定家葛に縛られて嬉しいと感じているのでなければ、舞うことができないとおっしゃっていました(笑)。
馬場 観る人と舞う人の意識がぜんぜん違う能ってあるんです。人間のリアルな肉体感がわからないと、演じきれない曲があるんですね。式子内親王は定家葛に縛られて辛いなと思って柱を回るのか、ああまたわたしはあの人の腕で抱きしめられているんだわ、これが運命よねと思って回るのかでは演技が違ってきます。
金魚屋 式子内親王は、一応、嫌がっていることになっていますよね(笑)。
馬場 そう、だからまた出て来られるんです(笑)。
ラモーナ 馬場さんは実際に能を舞っておられますが、能を舞うことで能に対する考え方が変わったりするんでしょうか。
馬場 能楽師が舞うのとわたしたちが舞うのでは、意識が違うと思います。わたしたちは下手にしか舞えない。なぜかと言うと、『葵上』なんかを舞うと、舞に情念がかぶさっちゃうんです。六条御息所の苦悩をよく知っていますからね。でも能楽師は複雑な芸統や自意識や、苦しみは深いでしょうね。
ラモーナ 昭和二十年(一九四五年)に川瀬一馬によって『頭註世阿弥二十三部集』が刊行されましたが、馬場さんはそのあたりのことを覚えていらっしゃいますか。
馬場 昭和二十年当時は学生だったから、『世阿弥二十三部集』が出た時の能楽界の熱狂のようなものはわかりません。ただ『世阿弥二十三部集』は一生懸命読んで勉強しました。わたしは昭和二十四、五年頃に神田の古本屋で買ったんです。大学で能楽を研究していれば別だけど、わたしはもう社会人で学者たちとの接点はなかったから、一人で読んで研究していたんです。
ラモーナ 馬場さんは世阿弥の能に対する情熱を、とてもよく読み解いておられますが、世阿弥はどういう心づもりで能楽論を書いたとお考えですか。

馬場あき子全集『第一巻 歌集一』
三一書房 平成七年(一九九五年)から平成十年(一九九八年)までに本篇十二冊、別巻一冊を刊行
馬場 『風姿花伝』の「第一 年々稽古条々」は、お父さんの観阿弥から教えられたことを筆録しています。「第三 問答条々」や「第四 神儀に云ふ」になると、世阿弥自身がこれは書き残しておかなければならないと考えたことが書かれています。特に「神儀」は世阿弥がとても大切にしていた考えだと思います。能は河原者が作った芸能ではなく、アメノウズメ以来の伝統を継ぐ、神に仕える者たちが作り上げた芸能なんだということを説こうとしている。そこには貴族や武士といった、当時の能の庇護者に対するアピールがこめられていたのではないかと思います。われわれは単なる芸人ではない、神に仕える芸人だということですね。だからなぜ申楽かというと、「上宮太子・末代のため、神楽なりしを神といふ文字の偏を除けて、旁を残したまふ。これ非暦の申なるがゆゑに、申楽と名附く」と言っています。自分たち芸能者のかさ上げを書いた箇所で、世阿弥はあの箇所を読んで欲しかったんじゃないかと思います。
「奥義に云はく」以降は芸術論です。日本人は逆説の芸術論が好きですね。強い能を舞う時は優しい心を持たなければならない、優美に舞う時は強い芯が必要だとかね。常にどこかで逆のものを求めているんです。そういった日本文化の本質のようなものが、たくさん『風姿花伝』には表現されていると思います。その後の『花鏡』とかになってくると、『風姿花伝』とはまた違う世阿弥の老境がにじんできます。わたしはどこかで書きましたが、世阿弥という人は気の毒な人で、文筆が立った人なんだけど、書けば書くほど逆境に陥ってゆく。なぜでしょうね。でも逆境に陥るからこそ、書いて残さなきゃと思うのであれだけの著作を書いたんでしょうね。足利義満が死んでからいっぱい伝書を書いたんですが、その書いた伝書が全部自分の逆境につながっていった。最後には佐渡に流されてしまいました。だから世阿弥の伝書には危機感があります。世阿弥の伝書は直系には伝わらなくて、今の観世流の音阿弥家に伝わるんです。佐渡に流される時に伝書を含めていろんなものを没収されてしまいましたからね。
世阿弥の生涯もそうですけど、能は逆説の芸術という面が色濃いです。わたしは笛を習ったんですが、あれは音が出ないように作ってあるんですよ(笑)。出ない音を出すところに能管の面白さがある。能管は篠笛なんかとぜんぜん違うんです。太鼓は炭火で乾かさないと音が出ないとかね(笑)。それに楽器も陰陽になっています。小鼓や笛が陰で太鼓が陽でしょう。そういうところにも日本の芸能の宗教性が表現されていると思います。
金魚屋 土方巽は「肉体は経験を超えない」――つまり肉体は覚えている動きしかできないと言って自分では踊らなくなりましたが、最晩年に『東北歌舞伎』を演出しました。フィルムでしか見たことがないんですが、様式的には能に非常に近いと思いました。あれだけの前衛舞踏家が最晩年に能に近づくのは、まさに逆説かもしれません。

馬場 金剛流の金剛巌さんが、「動かぬことを能と言う」とおっしゃっていますからね。能も最後は動かない醍醐味に達するのでしょう。なんでしょうね、このへんてこな芸術は。ヨーロッパなどでは動かなければ表現にならないはずなんですけどね(笑)。でもそれは日本の芸能全般に共通しているかもしれません。たとえばお茶でお薄をたてますが、その作法はみんな同じです。誰がたてても同じことをやっている。でも何十人もの人たちが宗匠のお手前を注視するわけでしょう。何を見ているのか。これが日本芸道の神髄なの。質を見ているんですよ。芸じゃなくてその人の到達した人間の質ですよね。質を見ているんです。お茶杓の扱いにその人の全人間的な質がこもっているんです。質の美と厳しさを通して、その人の人格を見ているんです。能の仕舞も同じです。型は決まっているわけだけど、舞う人の格調や気韻を、人間を見ているんです。型を通して現れる、その人間の質が美しいか美しくないかを見ているんです。日本の芸術は質を見る芸術なんです。短歌の場合は声です。その歌を声を出して詠んだ時の言葉の響きに人間の質が出ますね。否応なく出る。
金魚屋 今のお話しで、短歌の本質的な何かがわかったような気がします。馬場さんのお話しはとても面白くて刺激的です。機会があれば、本当に是非またお話しをおうかがいしたいと思います。今日は長時間ありがとうございました。
(2015/10/09 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■馬場あき子さんの本■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


