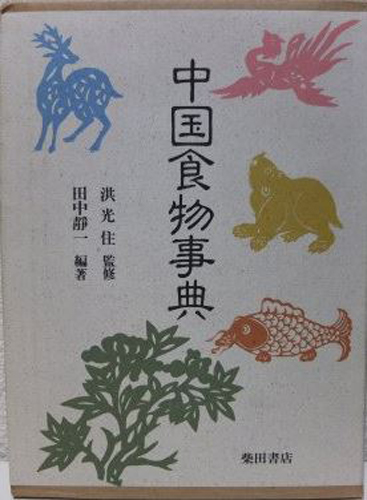
事典の快楽というものは確かにある。それはこの時代にも厳然として残っている、と確認できる。私たちは無限に広がる知識を求めているが、それは可能性として残されているものであってもよい。急を要する情報でない限り、知識の一部は余白として残されていてよいのだ。
その余白とは、今はここまでという断念でもある。それは私たちにちょっとした安堵をもたらす。限りない検索ワード、限りない更新を追いかけてどこまでも広く知識と情報を求め、それが世界を覆い尽くしたとしても、決してすべてではない。すべてではないことに焦燥を感じ続けるのは辛いものだ。余白という断念は断念でありながら、どこかですべてを包含する。
書物のネットに対する優位性は、すなわち余白にあると言えるのかもしれない。あるいは書かれてないことへのスタンスと言うべきか。私たちは書物のページをめくるひと時、しばしの安堵を得ることができる。今はここまで。いいではないか。少なくとも明日、更新されていることはないのだ。そして今日のこのひと時こそ永遠に通じることを皆知っている。
『中国食物事典』は幸福な書物である。そこにあるのは世界のすべてではない。百科事典のようにネットと張り合うことも、それに見劣りすることもない。中国であり、その食物のすべてを網羅しようと試みるそれはしかし世界に匹敵する重みを持ち、むしろ世界そのものよりも魅力のある輪郭を有する。
飛行機以外は何でも食べようとすると言われる中国人だ。確かにそこには、ほとんどすべてがある。地図があり、コイ科やハタ科の魚たち、虫草や髪に似た海藻といった奇妙なもの、羽根をむしられるのを待つ鳥たちが同じ向きに並んでいる。これ以上、何が必要だというのだろう。私たちは飢えることはないだろう。その安堵を世界が与えてくれるのならば。
ここに存在するものたちは、そして例外なく奇妙だ。奇妙さこそが豊かさだ、と主張している。それらを食することで、私たちはその奇妙さを包含するだろう。同時にその奇妙さは私たちを包み込むだろう。私たちもそれらと違わず奇妙であるに相違ないし、奇妙であっていいのだ。
名付けようもなく奇妙なものとして私たちはあるのだが、名付けられることによってこの世界に存在することを認められているのだ、ということが事典のページをめくるごとに確かめられる。事典とは存在するものの集積であると同時に、それらを名付ける装置でもある。
その名を知り、認識することはある意味で食べてしまうことにも似ているかもしれない。世界にひしめく奇妙なものたちの名を書き尽くし、読み尽くすこと。それは世界を食べ尽くし、我がものとし、一体化することでもあるだろう。その奇妙さと豊かさをすべて自分の血肉とすることができるなら、私たちは他に何を望むだろう。至福の象徴としての事典の他に。
金井純
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


